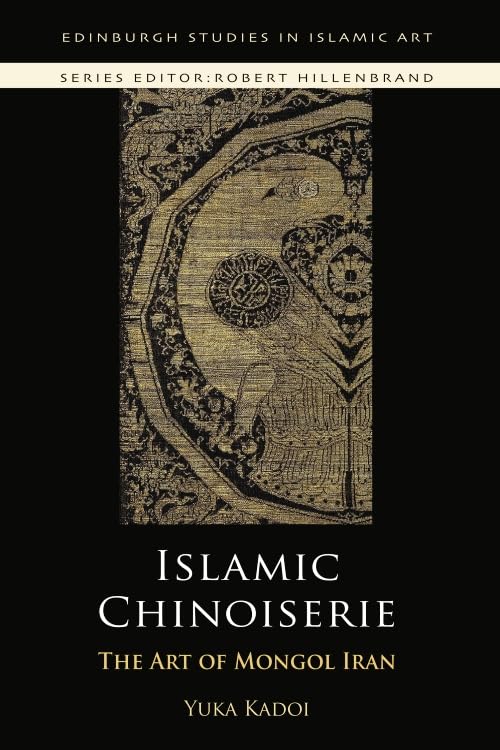- 著者
- Yoshifumi ENDO Toshikazu SAKAI Sho FUKUI Ai HORI Ryosuke ECHIGO Satoru MATSUNAGA Tsuyoshi KADOSAWA
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.2, pp.218-222, 2022 (Released:2022-02-10)
- 参考文献数
- 11
A 10-year-old spayed female Golden Retriever was referred for hindlimb lameness. A firm mass was palpated over the right caudal pelvis. Computed tomography revealed an osteolytic bone region and an associated periosteal reaction in the ischium, including the acetabulum. The histological diagnosis was sarcoma of unknown origin. A mid-to-caudal partial hemipelvectomy was performed to remove the mass. Femoral head and neck osteotomy was performed to allow hindlimb preservation. Following surgery, the dog regained satisfactory hindlimb use over time and was alive for 821 days with no recurrence or metastatic disease. This report indicates that mid-to-caudal partial hemipelvectomy with femoral head and neck osteotomy is technically feasible and allows for tumor control with preservation of the hindlimb and its function.
2 0 0 0 IR バニヤンと戦いのイメージ
- 著者
- 串田 修 新保 みさ 鈴木 志保子 中村 丁次 斎藤 トシ子
- 出版者
- 公益社団法人 日本栄養士会
- 雑誌
- 日本栄養士会雑誌 (ISSN:00136492)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.10, pp.581-588, 2021 (Released:2021-10-02)
- 参考文献数
- 33
本横断研究では、全国の管理栄養士と栄養士を対象に、基本属性、就業状況と職務満足度を把握し、両者の関連を検討することを目的とした。2018年11月にインターネット調査を実施し、就業資格を必要とする15,133人を解析対象者とした。基本属性では、性別・年齢・最終学歴・勤務地域・日本栄養士会の入会有無・研修会の参加回数を、就業状況では、所有資格・就業有無・就業資格・資格手当・優遇措置・雇用形態・実勤務先・勤務年数・年収を尋ねた。職務満足度は、5項目の尺度で評価した。尺度の得点を合計した結果、職務に満足している者は73.9%であった。職務満足度の高さには、年齢の高さ、大学等の卒業、勤務地域、日本栄養士会の入会、研修会の参加、管理栄養士の資格所有、昇給制度等の優遇措置、勤務年数や年収の多さ、勤務先が関係していた(全てp <0.05)。標本の代表性に課題があり、属性を限定した無作為抽出による追試も必要である。
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経レストラン (ISSN:09147845)
- 巻号頁・発行日
- no.472, pp.63-66, 2013-09
●佐賀県伊万里市大坪町甲1384-2 TEL0955-23-0667●月商2500万円●店舗面積/360坪(1188m2)●席数/300席●1日の平均来店客数/平日275人、土日600人●客単価/2000円●原価率/32%●営業時間/11:00〜23:30、第1・3水休●1日当たりのスタッフ数/20人●開店/1969年1月●経営…
2 0 0 0 OA アメリカの婦人解放運動
- 著者
- 松村 尚子
- 出版者
- 大谷学会
- 雑誌
- 大谷学報 = THE OTANI GAKUHO (ISSN:02876027)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.41-55, 1973-08
2 0 0 0 OA 脳梗塞により変形視をきたした2症例
- 著者
- 天野 総 桂 永行 山形 宗久
- 出版者
- 紀要編集小委員会
- 雑誌
- 八戸赤十字病院紀要 = Acta Medica HACHINOHE Institutio Hospitalis Crucis Ruberae (ISSN:09198121)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.17-22, 2015-03-25
- 著者
- 野村 恭彦
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.121-130, 2004-01-15
本論文では,新たなグループウェア設計の指針となる,ストラテジック・ナレッジ・パターン(SKP)を示す.SKPは,日米のナレッジ・マネジメント(KM)に成功している企業11社の半年にわたっての定性・定量調査を通じて構築された,企業の差別化戦略の3つのパターンである.これまでのグループウェア研究では,協業の目的を持ったグループの知識共有の支援には一定の成果をあげてきたが,KMの成功と失敗の分かれ目である,いかに組織の構成員に知識共有の動機付けを行うかという課題に関しては,十分な議論がなされてこなかった.本論文ではまず,KMに成功している企業は,部門を越えた知識共有が特別な取り組みではなく,「当たり前」の企業文化となっていること,その秘訣は,知識経営の「目的」,焦点を当てるべき重要な「知識」,各個人・組織の仕事の背景である「コンテクスト」の3つの可視化にあることを示す.続いて,本調査を通して発見された3つのSKP,ビジョン主導型KM,プロ型KM,創発型KMを示し,各SKPを実現するためのグループウェア設計指針について議論する.最後に,SKPに基づきグループウェア設計を行うことにより,グループウェアの提供価値を,ミクロなグループ活動支援から,経営戦略に基づく組織全体の知識創造活動支援へと,高めることが可能になることを示す.
- 著者
- 麻 子軒
- 出版者
- 計量国語学会
- 雑誌
- 計量国語学 (ISSN:04534611)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.103-116, 2019
役割語をテレビゲームという新しい言語資料を用いて,計量的アプローチで分類・抽出した.『ドラゴンクエスト3』のキャラクターの発話における代名詞や助詞などの特徴量をクラスター分析と特化係数で解析した結果,①格助詞「が/を」,副助詞「は」があまり用いられない「異人ことば」,②代名詞「あたし」,助動詞「ちゃう」,副助詞「ったら/なんて」,接続助詞「けれど」,終助詞「かしら/もの/わ/の/ね」,感動詞「きゃー/まあ/あら」が多用された「女ことば」,③特徴語が観察されない「中立ことば」,④代名詞「そなた/わし」,助動詞「じゃ/とる/である/まい」,副助詞「なぞ」,終助詞「のう/ぞい/ぞ」,感動詞「やれやれ」が多く見られる「老人ことば」,⑤代名詞「おめえ/オレ/あんた」,助動詞「やがる/ちまう/てやる」,副助詞「なんか」,終助詞「ぜ/い/さ」,感動詞「へい/おい」が特徴的な「男ことば」,⑥代名詞「ボク」,終助詞「よう/さ/や/なあ」,準体助詞「ん」,感動詞「わーい/ねえ」が多用された「少年ことば」の6つの分類を得た上,従来では注目されていない副助詞と接続助詞も役割語的要素である可能性を示した.
2 0 0 0 OA 多種還元物質含有輸入ハンドクリームの血糖自己測定値への影響
- 著者
- 藤崎 夏子 尾辻 真由美 簑部 町子 肥後 あかね 後藤 隆彦 赤尾 綾子 三反 陽子 中村 由美子 田上 さとみ 中重 敬子 小木曽 和磨 郡山 暢之
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.9, pp.666-669, 2013-09-30 (Released:2013-10-30)
- 参考文献数
- 5
糖尿病治療において,簡易血糖測定器での自己測定による血糖値のモニタリングは有意義である.様々な要因で測定値が影響を受けることが知られているが,外用品を原因とする報告は認められない.我々は,高濃度のアスコルビン酸と各種還元物質を含有した輸入ハンドクリームによって,血糖値が偽低値を示した2型糖尿病の症例を経験し,健常成人10名での血糖値への影響と簡易血糖測定器における比色法と酵素電極法との間での差異について検討した.血糖値は,クリーム塗布前に比して塗布後に,比色法で有意な低値(p=0.005),酵素電極法で有意な高値(p=0.005)が確認された.流水洗浄で塗布前と有意差の無いレベルに回復したが,アルコール綿での拭き取りでは不充分であった.血糖自己測定においては,還元物質を含有する外用品使用の有無についての問診や,それらの影響に関する知識と流水での手洗いの重要性の啓蒙が必要である.
2 0 0 0 IR 小学校特別活動における討議デモクラシーの実践事例─脱学校化からの合意形成─
- 著者
- 田端 健人 守谷 繁
- 出版者
- 宮城教育大学
- 雑誌
- 宮城教育大学紀要 = Bulletin of Miyagi University of Education
- 巻号頁・発行日
- no.54, pp.367-384, 2020-01-30
本稿は、小学校特別活動での話し合い活動を、新学習指導要領の「合意形成」「意思決定」の視点から構想し実施した研究実践の報告です。構想にあたっては、「討議デモクラシー」ならびに「子どもの哲学ハワイ/ みやぎ」の理論と実践を参照し、小学₆年生の学級での児童による民主的討議による合意形成を目指しました。第₁章では、実践者守谷の問題意識として、「学校的なもの」による児童の抑圧の実態とその解放(脱学校化)という課題を記し、第₂章では、話し合いの議題として学級の多くの児童が「朝遊び」を提案したことを述べ、この議題が前記の実態と課題に沿うことを示しました。第₃章では、実践者守谷の問題意識に対し、合意形成や意思決定の話し合い活動をどのように理解し実践するかについて、研究者田端が討議デモクラシーの理論と実践を参照し応答を試みました。こうした事前の検討を経て、どのような特別活動の話し合いがなされたかを、第₄章に記しています。話し合いは₃時間構成で実施されましたが、議論が白熱した第₁時の詳細な記録を掲載しました。話し合いでは、「朝遊びは『本当に』絆を深めることになっているか」の問いをきっかけに、児童たちは本音を語り始め、「絆を深めるどころか逆に学級内のスクールカーストを助長している」という痛烈な批判まで噴出しました。第₅章では守谷の総括、第₆章では田端の総括を記しています。児童たちの批判意識に一定の限界はあったものの、わたしたちが予想した以上に児童は、自分たちの現状を見つめ直し、批判的・創造的・ケア的思考で話し合いを展開し、自分たちの学校生活をより良いものにする意義深い討議になったと総括しました。わたしたちはこの実践の理念と方法を、「討議教育(デリバレイティブ・エドゥケーション)」として提案します。
- 出版者
- 日経BP社 ; 1992-
- 雑誌
- 日経情報ストラテジー = Nikkei information strategy (ISSN:09175342)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.60-63, 2016-03
「書き込み内容に対してすぐ意思決定する」という社内SNSの活用方法を、恩田部長は業務改善プロジェクトなど、日々手掛けるすべての仕事に適用している。その結果、営業サポート部やプロジェクトの定例会議をゼロにできた。 恩田部長によると「社内SNS上で部…
- 著者
- 野村 恭彦
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.10, pp.500-506, 2004-10-01 (Released:2017-05-25)
ナレッジ・マネジメントは,組織内の知識を共有・活用するレベルから,企業の競争力の源泉として明確に位置づけられるようになってきた。その好例は,プロフェッショナル・サービス・ファームの情報サービス部門で,ライブラリアンの未来の姿をそこに見ることができる。一方で,暗黙知の重要性認識はますます高まっており,図書館の果たす「暗黙知共有の場]としての役割について考えたい。そして最後に,知的競争力やイノベーション能力を可視化するアプローチを示し,知識企業として,組織の持つイノベーション能力に焦点を当て,企業価値の極大化を実現する経営アプローチについて考える。
2 0 0 0 IR <研究ノート>精神障害者支援の「場と空間の活用」に関する考察:文献からの検討
- 著者
- 小田 敏雄
- 出版者
- 田園調布学園大学
- 雑誌
- 田園調布学園大学紀要 = Bulletin of Den-en Chofu Univerisy (ISSN:18828205)
- 巻号頁・発行日
- no.14, pp.63-78, 2020-03
本研究は,精神障害者の意思表出と自己決定支援のための「場と空間の活用」の可能性を実証研究で探ることを目的にした研究のための文献からの検討である。そのため「場」,「空間」が,対人支援など人にかかわる分野でどのように活かされ,意義があるか文献から検討した。文献検索にはCiNiiを活用し該当した31 件の論文と著者検索から9 本の論文を選定した。社会福祉,高齢者福祉,社会教育,精神医療,建築,学校教育の分野から検討し,人がかかわりあう「場」の持つ力と構成する成員の意欲を創出することが確認できた。そして,精神障害の特性を踏まえ検討していった。そのなかで「基地として,隠れていられる場」「抱える環境」が明示され,続いて,当事者であり支援者でもあるパトリシアディーガンが述べている,リカバリーを育むリハビリテーションの要点である①柔軟性②多様性③当事者の存在と希望は伝染する④共に弱さに向き合い成長しようとする支援者の姿勢が,関連しあっていた。今後,前述の二点と合わせ,六つの視点をもち精神障害者の意思表明,自己決定支援のための「場と空間の活用」を実証していくのが課題である。
2 0 0 0 OA 海外におけるナレッジマネジメントの実践(<特集>「ナレッジマネジメントとその支援技術」)
- 著者
- 加藤 鴻介 武田 浩一 野村 恭彦 平川 秀樹 野々村 克彦
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.21-32, 2001-01-01 (Released:2020-09-29)
- 著者
- 宮本 道人 青山 一真
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会
- 雑誌
- 日本バーチャルリアリティ学会誌 (ISSN:13426680)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.32-33, 2021
2 0 0 0 IR 女将の誕生 : 新聞・雑誌記事にみる旅館の女性像
- 著者
- 後藤 知美 GOTO Tomomi
- 出版者
- 現代民俗学会
- 雑誌
- 現代民俗学研究 (ISSN:18839134)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.39-56, 2016
This study discusses the image of okami who (i) has a backbone to manage inns by themselves, (ii) feasts guests with warm hospitality, and (iii) has a good grounding in Japanese traditional culture, especially about causes and processes of its establishment, based on newspapers and magazines. In the fields of conventional folklore, women tended to be discussed in relation to home and local community.\nHowever, this study newly set the above-mentioned issues in the view of the women image in the society. It was found that the image of "okami" was shaped as a result of various situations that Japanese inns faced in each period, and finally was used as a strategy to survive intense competition in the field of inn business. The media played a crucial role not only for shaping the image of "okami" but for actual lives of okami themselves.
- 著者
- 川久保 槙人 菊地 昌弥 北林 真帆 久野 竜之介 松山 玲美
- 出版者
- 東京農業大学農業経済学会
- 雑誌
- 農村研究 = Journal of rural community studies (ISSN:03888533)
- 巻号頁・発行日
- no.130, pp.25-37, 2020-03
本研究は,農林水産物・食品の輸出において特に苦戦している重点品目の「コメ・コメ加工品」のうち,主要品目となっている日本酒を対象に,第2位の輸出先国・地域である韓国向けの輸出拡大に寄与する清酒製造企業の企業行動を初めて具体的に解明した。課題の解明にあたり,本研究では市場構造と企業行動の枠組みからケーススタディを行なった。統計資料の分析の結果,対象とした韓国市場では低価格戦略が機能する構造にあった。ゆえに,本稿では規模の経済性の観点に主に焦点を当て,企業行動に関する調査および考察を行なった。その結果,規模の不経済を回避するための方策と原料費を低位に安定させるための企業行動(方策)を講じており,これらは低価格化や値下げ等の低価格戦略を成立させるための要素となっていた。なお,本研究は国・地域別の輸出戦略を検討する際に不可欠な市場構造の分析に関する新たな視座を提示した点にも意義を有している。
- 著者
- Yuka Kadoi
- 出版者
- Edinburgh University Press
- 巻号頁・発行日
- 2009
2 0 0 0 OA 多層円筒形圧力容器構造規格について
- 著者
- 小谷 敏雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本高圧力技術協会
- 雑誌
- 高圧力 (ISSN:21851662)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.6, pp.869-872, 1966-11-25 (Released:2010-08-05)