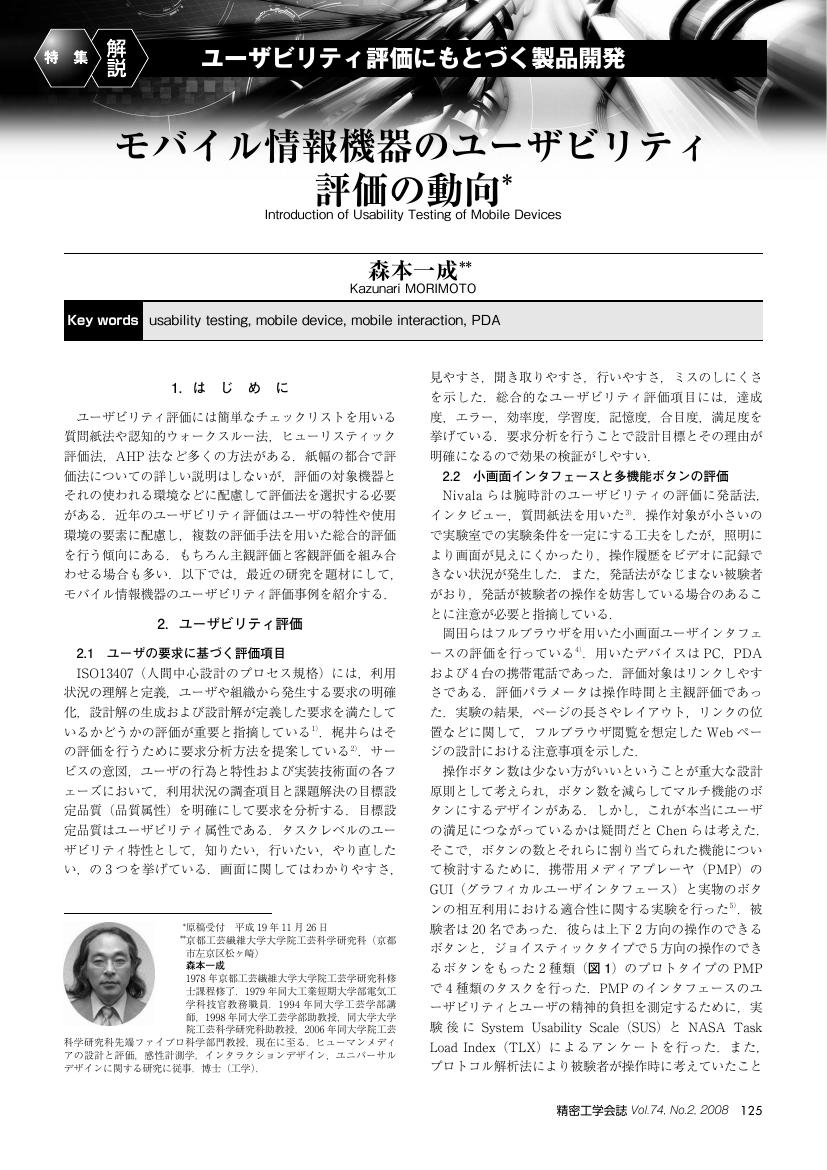1 0 0 0 OA ナビゲーションシステムにおける熟考性と即応性を兼ね備えたルート探索手法
- 著者
- 安場 直史 長岡 諒 矢野 純史 香川 浩司 森田 哲郎 沼尾 正行 栗原 聡
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第22回全国大会(2008)
- 巻号頁・発行日
- pp.16, 2008 (Released:2009-07-31)
ナビゲーションシステムのルート探索手法において、熟考型探索は最適だが計算時間が長く、即応型は計算時間は短いが解が最適でない。短時間先の渋滞予測情報が提供される環境で、相反するこれらの探索を適宜使い分けることでより精度の高いルート探索を実現した。
1 0 0 0 OA 地球生命はいつ誕生したのか?世界最古の生命の痕跡
- 著者
- 上野 雄一郎
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.120, no.5, pp.877-885, 2011-10-25 (Released:2012-01-17)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 1 1
地球上にいつ生命が誕生したのだろうか? この疑問に答えるために,世界最古の地層を探し,その痕跡を突き止める努力がなされてきた。西グリーンランドイスア地域には38-37億年前の太平洋型造山帯が見られるが,そのなかの付加体を構成する海溝堆積物中に石墨が産する。この石墨の炭素同位体組成は起源推定に有用であるのだが,この堆積岩はのちに300-600℃程度の広域的な変成作用を被っているため同位体組成は改変されている。そこで変成作用による影響を考慮すると,もとの炭素同位体組成は-25から-30‰程度であったと予測される。これらの同位体的特徴は,地球誕生後8億年時点ですでに生物は地球に出現していたことを示す。
1 0 0 0 OA 深部マントルへの新しい扉
- 著者
- 山本 伸次 徐 向珍 〓 〓〓
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.121, no.1, pp.161-167, 2012-02-25 (Released:2012-03-05)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 1
ルオブサオフィオライトに産するポディフォームクロミタイトからは,これまで数多くの“異常な”鉱物が見いだされている。それらは,マイクロダイヤモンドを含む種々の超高圧鉱物や,金属相などの還元的鉱物,そしてクロマイト中におけるディオプサイドやコーズ石などの異常な珪酸塩離溶相などである。これらの鉱物学的証拠は,本ポディフォームクロミタイト岩体が超深部マントル(おそらく380km以深)由来であることを強く示唆する。したがって,ルオブサオフィオライトにおけるポディフォームクロミタイトは,これまで手の届かなかった深部マントルに関する重要な知見をもたらすであろう。
- 著者
- マーガレット ウッド
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.121, no.1, pp.168-180, 2012-02-25 (Released:2012-03-05)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 3 6
基質に混在した岩塊を含む「メランジュ」を,グリーンリー(1919)が世界ではじめてアングルシーで記載した。それ以来,この地はメランジュの模式地となった。アングルシー島の大部分およびスリン半島西部は先カンブリア紀後期からカンブリア紀のモナ複合岩体から構成され,欧州に産する低変成度付加型造山帯の最良の例を提示している。これらの岩石は,現在の太平洋西部のプレート沈み込み帯上の前弧域に比較される場で付加した構造的な地質体であり,ゆえに海洋プレート層序をもつことを特徴とする。本稿は,モナ複合岩体およびそのメランジュの形成史に関する解釈が,過去200年間にどのように変化したのかについて記述する。さらに同メランジュがもつ多様性,また古期生命との関連についても議論する。
1 0 0 0 OA 3,4-Dihydroxycinnamic Acid Attenuates the Fatigue and Improves Exercise Tolerance in Rats
- 著者
- Rômulo D. NOVAES Reggiani V. GONÇALVES Maria do Carmo G. PELUZIO Antônio J. NATALI Izabel R. S. C. MALDONADO
- 出版者
- (社)日本農芸化学会
- 雑誌
- Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry (ISSN:09168451)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.5, pp.1025-1027, 2012-05-23 (Released:2012-05-23)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 4 3
3,4-Dihydroxycinnamic acid (3,4-DA) is a natural compound with high antioxidant potential found in various foods. This study found that animals administered with 3,4-DA had higher exercise tolerance, reduced blood lactate, and markers of hepatic oxidation. Blood glucose and antioxidant enzymes were not affected by this treatment. 3,4-DA may have applicability in reducing the fatigue associated with exercise.
1 0 0 0 OA 旋削用自動プログラミングシステムSTORK2の開発
- 著者
- 城 道介 前田 純一郎 武田 健二 吉川 弘之 佐田 登志夫
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密機械 (ISSN:03743543)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.444, pp.38-46, 1972-01-05 (Released:2009-06-30)
A method of processing geometrical patterns is proposed, which facilitates the develop-ment of automatic manufacturing system. The patterns described in a conventional form such as drawings of machine parts, are transformed into some process-oriented form, where the pattern is segmented into elements, codes of which carry all necessary information together with the connecting relationship among these elements. This method is applied to construct a fully automatic programming system for NC-lathe, where the necessary input data is only the shape of part and blank, and every necessary information is available as output of the system. This is called STORK 2 SYSTEM. Some practical applications of this system to turning processes proved its remarkable advantages such as the simplest input form, small core size and short computing time.
1 0 0 0 OA 「第二回表面科学若手研究会」報告
- 著者
- 南谷 英美 武安 光太郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本表面科学会
- 雑誌
- 表面科学 (ISSN:03885321)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.249-249, 2012-04-10 (Released:2012-04-22)
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 OA Predictors of Sickness Absence in Patients with a New Episode of Low Back Pain in Primary Care
- 著者
- Markus MELLOH Achim ELFERING Cornelia ROLLI SALATHÉ Anja KÄSER Thomas BARZ Christoph RÖDER Jean-Claude THEIS
- 出版者
- 独立行政法人 労働安全衛生総合研究所
- 雑誌
- Industrial Health (ISSN:00198366)
- 巻号頁・発行日
- pp.MS1335, (Released:2012-05-30)
- 被引用文献数
- 9 19
This study examines predictors of sickness absence in patients presenting to a health practitioner with acute/subacute low back pain (LBP). Aims of this study were to identify baseline-variables that detect patients with a new LBP episode at risk of sickness absence and to identify prognostic models for sickness absence at different time points after initial presentation. Prospective cohort study investigating 310 patients presenting to a health practitioner with a new episode of LBP at baseline, three-, six-, twelve-week and six-month follow-up, addressing work-related, psychological and biomedical factors. Multivariate logistic regression analysis was performed to identify baseline-predictors of sickness absence at different time points. Prognostic models comprised ‘job control’, ‘depression’ and ‘functional limitation’ as predictive baseline-factors of sickness absence at three and six-week follow-up with ‘job control’ being the best single predictor (OR 0.47; 95%CI 0.26–0.87). The six-week model explained 47% of variance of sickness absence at six-week follow-up (p<0.001). The prediction of sickness absence beyond six-weeks is limited, and health practitioners should re-assess patients at six weeks, especially if they have previously been identified as at risk of sickness absence. This would allow timely intervention with measures designed to reduce the likelihood of prolonged sickness absence.
1 0 0 0 OA PWMインバータによる連続フラッシュ制御法
- 著者
- 佐藤 之彦 石田 宗秋
- 出版者
- 一般社団法人 溶接学会
- 雑誌
- 溶接学会論文集 (ISSN:02884771)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.424-429, 2004 (Released:2005-08-01)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1 1
In previous study, flashing phenomena in square wave alternating current have been discussed for flashing control. The results give a suggestion that PWM inverter has possibility to control flashing phenomena in half a cycle. In this study, flashing phenomena control strategy for flash welding is discussed by use of PWM inverter power supply. The results are summarized as follows : 1 PWM inverter enables to control flashing phenomena in half a cycle. 2 PWM inverter control for continuous flashing is proposed.
1 0 0 0 OA クリーンルーム
- 著者
- 出口 稔芙
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密機械 (ISSN:03743543)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.88-92, 1985-01-05 (Released:2009-06-30)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA モバイル情報機器のユーザビリティ評価の動向
- 著者
- 森本 一成
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.2, pp.125-127, 2008-02-05 (Released:2010-07-21)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA ICRP第4専門委員会ポルト会議報告
- 著者
- 甲斐 倫明
- 出版者
- 日本保健物理学会
- 雑誌
- 保健物理 (ISSN:03676110)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.90-92, 2010 (Released:2011-02-04)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 OA 野兎より感染したと思われるPasteurella症の1例
- 著者
- 都田 梅司 谷川 久一 奥田 邦雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.6, pp.547-550, 1971-06-10 (Released:2008-06-12)
- 参考文献数
- 10
47才の男性.狩猟にて捕獲した野兎を生食し, 2日後に発熱,頚部リンパ節の腫大を来たし,野兎病の疑いで入院.理学的所見では,両側頚部リンパ節腫大,口蓋扁桃軽度腫大を認め,他に著変なく,検査で白血球増多を認めた他は著変がなかつた.リンパ節の組織所見は好中球の浸潤強く,小膿瘍形成を示した.血清凝集反応で, Francisella turalensis陰性, Brucella陰性,Pasteurella multocida陽性で,凝集価は経日的に上昇した.また患者の長男も同様に生肉を食したが,臨床症状の発現はなく,血清凝集反応のみが陽性で,不顕性感染と思われる. a. b. penicillin投与により約1週間で発熱下降,約2日でリンパ節は縮小し,白血球増多も消失した.ヒトにおけるPasteurella multocida感染の報告は外国では今日まで138例あるが,本邦では最初と考えられる.
1 0 0 0 OA 民族楽器の大量生産
- 著者
- 柚木 かおり
- 出版者
- The Society for Research in Asiatic Music (Toyo Ongaku Gakkai, TOG)
- 雑誌
- 東洋音楽研究 (ISSN:00393851)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.71, pp.65-83, 2006-08-31 (Released:2010-09-14)
- 参考文献数
- 34
バラライカは三角形の胴に三本の弦をはった有棹撥弦楽器で、ロシアの民族楽器として広く知られている。この楽器には、音楽事典などに見られるような、板を張り合わせて作った粗末な自作楽器あるいは職人が製作した楽器であるというイメージが先行しがちだが、数量から言えば、工場で大量生産されたものが圧倒的に多い。本稿は、民族楽器の大量生産が文化政策の一環として行われた経緯と理念を一九二〇~三〇年代の五ヵ年計画との関連において分析し、楽器大量生産の後世への影響を考察するものである。ソ連は、「資本主義諸国に追いつき、追い越せ」をスローガンに様々な政策を打ち出した。五ヵ年計画はもともと工業部門の発展を目的とした国家規模の計画であるが、そのうち第二次五ヵ年計画 (一九三三~三八) には特に芸術部門の組織化が含まれた。その計画書の冒頭には「安価で良質な楽器の普及が、社会の文化水準の高さを示す」と述べられており、実にその理念にしたがって民族楽器の国を挙げての大量生産が行われるようになった。世界初の社会主義国ソ連では、文化は国によって計画、運営、管理されるものであり、その意味で「国営文化」だった。工場製の楽器の生産と流通によって、より多くの人々が楽器を手にすることができるようになり、その楽器とともに、政策施行者側が推奨した「文化的な」音楽文化も組織的に普及することになった。しかし楽器の普及は、他方で、「非文化的である」として当局が排除しようとした農民の伝統的な器楽曲や世俗的なレパートリーを根絶するばかりか、政策被施行者側の工夫により、逆に生き残らせるという結果をもたらした。それらは、政策施行者側の推進した工場製楽器によって現在も鳴り響いている。
1 0 0 0 OA 史料からみた西日本の気象災害
- 著者
- 日下部 正雄
- 出版者
- 日本農業気象学会
- 雑誌
- 農業気象 (ISSN:00218588)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.34-37, 1960-06-30 (Released:2010-02-25)
- 参考文献数
- 3
著者は主として西日本災異誌によつて梅雨によつて起つたと推定される災害について調査した。まず梅雨による災害が全災害のうちでどのような位置を占めるかをみると, 古代においては干ばつが首位を占め梅雨についての記録が比較的少なかつたが, 14世紀ごろから次第に重要性を増し, 17世紀ごろになると梅雨は台風についで注目すべき位置を占めるようになつている。またこのころになると単なる長雨による災害ではなく, 梅雨末期の大雨が大きな役割を演ずることを, 洪水の旬別ひん度や, 川潮の旬別ひん度などから明らかにした。また山潮が風化花崗岩土地帯に多いことを示した。
1 0 0 0 OA 納豆製造工程における糖成分の動向
- 著者
- 菅野 彰重 高松 晴樹 高野 伸子 秋本 隆司
- 出版者
- Japanese Society for Food Science and Technology
- 雑誌
- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.105-110, 1982-02-15 (Released:2010-01-20)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1 9
納豆製造工程におけるオリゴ糖の変化をガスクロマトグラフィーにより分析した。同時に粘性多糖レバンと大豆多糖のうち,溶液中では納豆菌のアミラーゼによって容易に分解されるデンプンについても検討した。その結果,浸漬,蒸煮によって,大豆オリゴ糖の一部が失なわれ,デンプンも減少した。発酵においては,発芽後6時間でシュクロースは約1/7に,ラフィノース,スタキオースは約1/3に減少し,早期にオリゴ糖は分解されることが示された。この時大豆オリゴ糖の部分分解によって生じると考えられる,メリビオース,マンニノトリオース,グルコース,フルクトースが遊離し,メリビオース,マンニノトリオースの分解は緩慢であったが,グルコースとフルクトースは速やかに減少した。レバンは大豆オリゴの分解に伴って増加し,デンプンは発酵中にまったく減少しなかった。
1 0 0 0 OA 変化の作用因 印刷とインターネット
- 著者
- 大谷 卓史
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.4, pp.288-291, 2012-07-01 (Released:2012-07-01)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 植物にみられる起電性イオン・ポンプ
- 著者
- 岡本 尚
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.113-124, 1975-05-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 1 1
The conception of "electrogenic ion pump", actively separating charges across cell membranes, has been recently developed as a concequence of the recognition of the more intimate relationship between the mechanism generating resting membrane potential and the energy metabolism of the cell than formerly supposed. Existence of the resting potential larger than the equilibrium potential of any major permeable ion across cell membrance supports the above view and is regarded as a safety criterion for electrogenic activity. Another criterion, rapidity of the depolarization caused by the application of inhibitory reagents or conditions for energy metabolism, is examined critically taking several experimental results for instances. The investigations towards the energy sources for electrogenic activity and several hypothetical models for electrogenic ion pump are also reviewed. The ion which is transported across membrane by the electhogenic mechanism seems to be H+ in most plant cells, though in some cases Cl- is a possible candidate. The role of H+ in plant cells as a substitute of Na+ in the case of animal cells is reviewed with special reference to the "co-transport" of organic molecules and also from the view point of origin and evolution of the membrane transport systems.
1 0 0 0 OA 継時的比較の個人差──継時的比較志向性尺度の作成と検討──
- 著者
- 並川 努
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.6, pp.593-601, 2011 (Released:2011-08-10)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 3
This study developed the Temporal Comparison Orientation Scale and investigated its reliability and validity. Study 1 (N=481) examined the factor structure and correlations with other related scales (self-consciousness scale; revaluation tendency scale; self-esteem scale; depression scale; social comparison orientation scale). The results suggested that the Temporal Comparison Orientation Scale had good reliability and validity. Study 2 examined the relationship between temporal comparison orientation and affect generated by temporal comparisons. The results showed that individuals high in temporal comparison orientation experienced more negative affect after upward and downward comparisons than individuals low in temporal comparison orientation. The possible uses and limitations of the scale were discussed.
- 著者
- Hideo TAKEUCHI
- 出版者
- (社)日本分析化学会
- 雑誌
- Analytical Sciences (ISSN:09106340)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.11, pp.1077-1077, 2011-11-10 (Released:2011-11-10)
- 参考文献数
- 59
- 被引用文献数
- 14 55
UV Raman spectroscopy is a powerful tool for investigating the structures and interactions of the aromatic side chains of Phe, Tyr, Trp, and His in proteins. This is because Raman bands of aromatic ring vibrations are selectively enhanced with UV excitation, and intensities and wavenumbers of Raman bands sensitively reflect structures and interactions. Interpretation of protein Raman spectra is greatly assisted by using empirical correlations between spectra and structure. Many Raman bands of aromatic side chains have been proposed to be useful as markers of structures and interactions on the basis of empirical correlations. This article reviews the usefulness and limitations of the Raman markers for protonation/deprotonation, conformation, metal coordination, environmental polarity, hydrogen bonding, hydrophobic interaction, and cation-π interaction of the aromatic side chains. The utility of Raman markers is demonstrated through an application to the structural analysis of a membrane-bound proton channel protein.