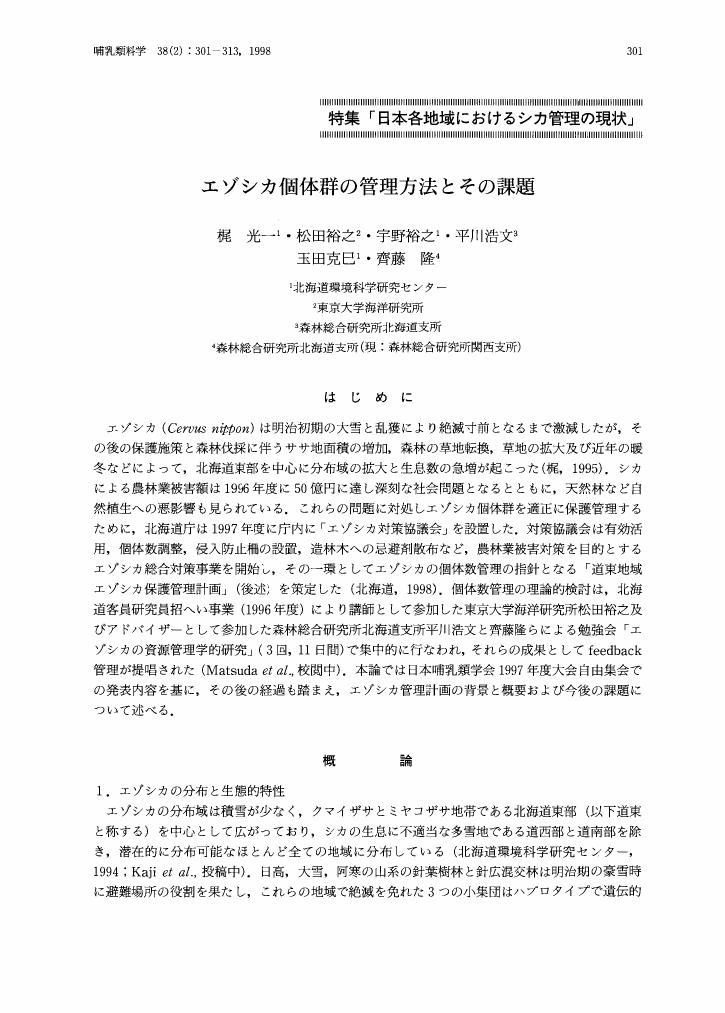- 著者
- Xiaoyan Sun Xiaobing Fu Weidong Han Yali Zhao Huiling Liu Zhiyong Sheng
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.7, pp.1037-1045, 2011-07-01 (Released:2011-07-01)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 18 28
Reprogramming differentiated cells toward stem cells may have long-term applications in stem-cell research and regenerative medicine. Here we report on the dedifferentiation of human epidermal keratinocytes into their precursor cells in vitro with basic fibroblast growth factor (bFGF) but not external gene intervention. After incubation of human terminally differentiating keratinocytes, some of the surviving keratinocytes reverted from a differentiated to a dedifferentiated state, as evidenced by re-expression of biological markers of native keratinocyte stem cells (nKSCs), including β1-integrin, CK19 and CK14. Moreover, these dedifferentiation-derived KSCs (dKSCs) showed an ability for high colony formation correlated with cell cycle analysis showing a marked accumulation in S phases, acquired a similar regional distribution of both α6-integrin and CD71 expression at the ultrastructural level, and had a increased proliferative capacity by releasing telomerase from nucleolar sites to nucleoplasmic distribution. However, on comparing dKSCs with nKSCs, 2 points seem noteworthy: (1) the proportion of transit amplifying cells in dKSCs treated with bFGF is much higher than that in nKSCs and (2) regional differences exist in the subcellular localization of telomerase in nKSCs and dKSCs. Most nKSCs showed a prominent nucleolar concentration of human telomerase reverse transcriptase expression, whereas most dKSCs showed a more diffuse intranuclear distribution of telomerase or even signal depletion at nucleoli relative to the general nucleoplasm. These results indicate that bFGF could induce the terminally differentiating epidermal keratinocytes to convert into their precursor cells, which offers a new approach for generating residual healthy stem cells for wound repair and regeneration.
1 0 0 0 OA 多能性幹細胞から誘導した樹状細胞によるがん免疫療法
- 著者
- 福島 聡 尹 浩信 西村 泰治 千住 覚
- 出版者
- 日本臨床免疫学会
- 雑誌
- 日本臨床免疫学会会誌 (ISSN:09114300)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.113-120, 2011 (Released:2011-06-30)
- 参考文献数
- 14
iPS細胞作製法の開発により,任意個体の体細胞から多能性幹細胞を作製することが可能となった.iPS細胞は各種の再生医療のための細胞ソースとしてのみならず,細胞治療に用いる樹状細胞(DC)を作製するための材料としても有用であると考えられる.多能性幹細胞は,無限増殖能を有し,遺伝子導入も容易であり,より強力な効果を有するDCを無限にin vitroで作成し治療に用いることができるようになる可能性を秘めている.これまでに行われてきた多能性幹細胞由来DCを用いたがん免疫療法の研究を概説し,今後の展望を述べる.
1 0 0 0 OA 潰瘍性大腸炎を合併したHIV感染症の1例
- 著者
- 河口 貴昭 酒匂 美奈子 吉村 直樹 高添 正和 柳 富子
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, no.4, pp.536-541, 2009 (Released:2009-04-06)
- 参考文献数
- 10
42歳男性,HIV感染進行期に全大腸炎型の潰瘍性大腸炎を発症した.緩解導入療法が奏効したが,HIV感染は進行したため,多剤併用療法(HAART)を行った.HIVウイルス量は激減しCD4リンパ球数は回復,さらに潰瘍性大腸炎は無治療で緩解を維持した.潰瘍性大腸炎を合併したHIV感染の報告は本邦初であるが,HIV感染進行期の免疫異常と炎症性腸疾患発症との関連が示唆される興味深い症例である.
- 著者
- 石田 英之
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.123, no.5, pp.329-334, 2004 (Released:2004-04-27)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 3 5
細胞死にはネクローシスとアポトーシスがあり,両者ともミトコンドリアによってその運命が制御されている.とくにミトコンドリアPermeability Transition Pore(PTP)の開口は,チトクロムCの遊離を起こしてアポトーシスを誘導することはよく知られている.また,ミトコンドリアPTP開口阻害薬であるシクロスポリンA(CsA)が虚血再灌流障害によるネクローシスを抑制するとの報告もある.このように,ミトコンドリアPTPは,細胞の生死を調節する重要な因子であるが,その詳細は充分解明されていない.ここでは,ミトコンドリアPTPに関する最新の研究方法と心筋細胞死におけるミトコンドリアPTPの役割に関する検討を例にして,実験法を紹介する.
1 0 0 0 OA 可微分写像の特異ファイバーのトポロジー
- 著者
- 佐伯 修
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.46-67, 2008 (Released:2011-07-01)
- 参考文献数
- 56
1 0 0 0 OA リスク態度と注意
- 著者
- 藤井 聡 竹村 和久
- 出版者
- 日本行動計量学会
- 雑誌
- 行動計量学 (ISSN:03855481)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.9-17, 2001 (Released:2009-04-07)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 11 23 4
Identical decision problems in form may yield different decisions, depending on the subjective decision framing as a function of how the situation is described. This is called the framing effect. The Contingent Focus Model (Takemura, 1994) can theoretically explain why the framing effect emerges. The model hypothesizes that a risk attitude depends on how to focus on the possible outcome (focusing hypothesis), and how to focus on them is, in turn, contingent on situations of decision making (contingent focus hypothesis). To test this hypothesis, we conducted 2 experiments which manipulated the relative size of letters of outcomes to the other letters (n=180, respectively). The results indicated that the subjects were more risk-taking when possible outcomes were emphasizing than those when probabilities were emphasizing. The psychometric analysis using the model indicated that the size of effect of emphasizing conditions on decision making is not different from that of positive/negative frame conditions.
1 0 0 0 OA 電子書籍の衝撃
- 著者
- 三浦 勲
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.4, pp.224-227, 2011 (Released:2011-07-01)
1 0 0 0 OA 東シベリアの石油資源ポテンシャル
- 著者
- 中島 敬史
- 出版者
- 石油技術協会
- 雑誌
- 石油技術協会誌 (ISSN:03709868)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.2, pp.132-141, 2005 (Released:2007-06-01)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
A future pipeline project that will transport crude oils from East Siberian fields to Nakhodka, shipping port along the coast of the Japan Sea, is under discussion and gradually revealing its main framework. One of the major concerns is if significant potential of petroleum is expected in the East Siberian region. In this paper, the total of the original oil resources in the region is estimated ranging from 18.9BBO (billion barrel of crude oil) to 67.2BBO.The Siberian platform is consisted of largely uplifted Archean crystalline basement and the overlaid sediments consisted of the Proterozoic and the Lowest Paleozoic formations. Most of the known oil reserves (85%) in the East Siberian region concentrate on the crest of the highest basement uplift on the two arch structures ; Baykit and Nepa-Botuoba. Petroleum source rocks are not concluded yet. Although the Riphean is expected to contain source rocks, it is entirely absent on the most prolific Nepa-Botuoba Arch area. Moreover, most fields have extremely high helium content (ranging 0.2-0.6 percent) with hydrocarbon gases. Based on several unique characteristics of oil and gas fields on the Nepa-Botuoba Arch, the author proposes in this paper that the theory of abiogenic origin can not be ignored ; hydrocarbons associated with helium gases may have migrated upward through the fractures from the depth of the earth.Upon completion of the pipeline linking the supply area (East Siberia) to the market in the Pacific region, oil exploration activities will be accelerated in the East Siberian region. Subsequently, the additional oils derived from the new discoveries in the East Siberian region will fulfill the new pipeline.
1 0 0 0 OA 4-1.立体映像技術の研究動向
- 著者
- 岡野 文男
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.5, pp.612-613, 2007-05-01 (Released:2009-10-27)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 2 1
1 0 0 0 OA 諸外国を参考とした番号制度モデル比較論と社会情報学の役割
- 著者
- 榎並 利博
- 出版者
- 日本社会情報学会
- 雑誌
- 日本社会情報学会全国大会研究発表論文集 日本社会情報学会 第25回全国大会
- 巻号頁・発行日
- pp.291-296, 2010 (Released:2011-03-26)
Now Japan is discussing about National ID, and will have to make a decision about what type of National ID model Japan should adopt. We can find 3 types of National ID model, separate-model, flat-model, and sectoral-model. This paper shows that the discussion will be led to the wrong way, because that doesn't have the view point of Social Informatics. This paper says that on the basis of Social Informatics, Japan should adopt a flat-model on National ID and establish an independent organization which would protect Japanese people from encroachment thorough flat-model.
1 0 0 0 OA Inverse Monte Carlo法による光線力学療法前後の腫瘍組織の光学特性の算出
- 著者
- 本多 典広 寺田 隆哉 南條 卓也 石井 克典 粟津 邦男
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本レーザー医学会
- 雑誌
- 日本レーザー医学会誌 (ISSN:02886200)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.115-121, 2010-07-30 (Released:2010-11-14)
- 参考文献数
- 21
光線力学療法(PDT)の治療計画において,生体組織内の光の侵達度や照射線量分布を定量的に把握することは,治療成績を向上させるために重要である.生体組織内の光の侵達度は,生体組織の光学特性である吸収係数 [mm-1],換算散乱係数 [mm-1]等により理解できる.一般的に,レーザー照射により生体組織の光学特性は変化する.そこで,我々は,PDT前後の腫瘍組織の光学特性を算出することを目的として基礎的検討を行った.Talaporfin Sodiumを用いたPDTをマウス皮下腫瘍モデルに対して行い,双積分球光学系とInverse Monte Carlo法を用いて波長350~1000nmにおける腫瘍組織の光学特性を算出した.PDT実施7日後,Talaporfin Sodiumの吸収極大波長664nmにおいて,換算散乱係数はPDT前に比べて0.64mm-1から1.24mm-1に増加し,結果,腫瘍組織への光の侵達度はPDT前に比べおよそ44%減少することが見積もられた.以上より,追加のレーザー照射によるPDTの際,PDT後の光の侵達度の減少を考慮し,レーザー照射条件を調整することが必要であることが示唆された.
1 0 0 0 OA 海面養殖種苗導入のリスク管理—タイリクスズキ
- 著者
- 谷口 順彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.6, pp.1125-1128, 2007 (Released:2007-11-26)
- 参考文献数
- 6
- 著者
- 常田 邦彦
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.45-48, 1995 (Released:2008-07-30)
1 0 0 0 OA 「日本各地域におけるシカ管理の現状」,エゾシカ個体群の管理方法とその課題
1 0 0 0 OA 洞爺湖中島のエゾシカの個体群動態と管理
- 著者
- 梶 光一
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.2_25-28, 1986 (Released:2008-10-01)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA エゾシカ個体群の個体数管理とモニタリング
1 0 0 0 OA 兵庫県におけるヌートリアの農業被害と対策の現状
- 著者
- 江草 佐和子 坂田 宏志
- 出版者
- 日本陸水学会
- 雑誌
- 陸水学雑誌 (ISSN:00215104)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.3, pp.273-276, 2009 (Released:2011-02-16)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 3 2
ヌートリアは,毛皮用の家畜として日本に導入された。本稿では,兵庫県における急激な分布と被害の拡大の過程について報告する。アンケート調査の結果,2007年には,兵庫県内の4195集落のうち2349 集落でヌートリアの目撃あるいは被害が確認されていることがわかった。有害捕獲等による捕獲数は,1007頭であった。捕獲努力量は,より深刻な農業被害をもたらすアライグマと比べると少なかった。
1 0 0 0 OA 紀伊半島の降雨量分布に対する地形の効果について
- 著者
- 斉藤 和雄 Lecong Thanh 武田 喬男
- 出版者
- 気象庁気象研究所
- 雑誌
- Papers in Meteorology and Geophysics (ISSN:0031126X)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.65-90, 1994 (Released:2006-10-20)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 7 7
紀伊半島、尾鷲付近での降雨の集中に対する地形効果をみるため、3次元山岳地形を越える流れの場を非静水圧ドライモデルを用いて調べ、観測された降雨量分布との比較を行った。 北東~南西方向に長軸を持つ楕円で単純化した地形に対する数値実験では、南東の一般風が弱い場合、山岳風上側下層の上昇流域は、斜面上と海上に2つのピークが見られた。海上のピークは、ブロッキングによる2次的な上昇流で、山岳前面最下層の逆風を伴っていた。それぞれのピークは一般風が小さいほど風上側に生ずるが、一般風が強く (あるいは安定度が小さく) ブロッキングが生じない場合は、海上の2次的な上昇流は見られない。紀伊半島地形の特徴的な湾曲は、南東風時のブロッキングの効果を高める働きを持つ。 1985年の紀伊半島での降水事例を解析し、尾鷲では潮岬に比べ雨量が多い事と大雨は東南東~南の下層風向時に生じている事を確かめた。紀伊半島の現実地形を用いた数値実験では、東~南のいずれの風向時にも尾鷲付近と紀伊半島南部に下層の上昇流域が見られ、榊原・武田 (1973) で示された紀伊半島の年平均降水量分布の極大地点と良い一致が見られた。ブロッキングにともなう海上の2次的な上昇流は南西~西の風向時には生じなかった。 大雨時に観測された一般場を用いた数値実験でも同様な傾向が見られ、シミュレーションで得られた下層の上昇流域は観測された降水分布に概ね良く対応していた。また、いくつかのケースでは、尾鷲の北東で観測された地上の降水域に対応する場所に山岳波による風下側中層の上昇流域がシミュレートされた。 実験結果は、実際の降雨分布と一般風の大きさの関係-弱風時の海岸域と強風時の内陸域-に対応している。また、弱風時にしばしば見られる紀伊半島風上側海上での対流性降雨バンドの発達に、紀伊半島の地形のブロッキングによる下層の水平収束が影響している事を示唆している。