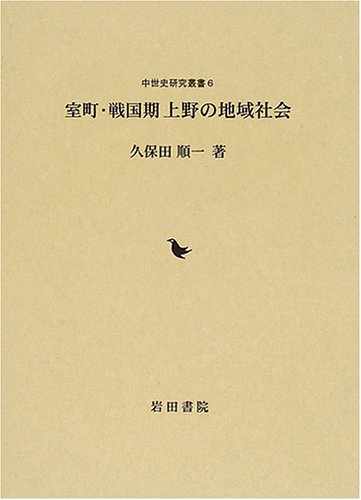1 0 0 0 OA 同時代仏師との比較による快慶作品の特徴について―様式と法量からみる―
- 著者
- 久保 文乃 村上 征勝
- 雑誌
- 研究報告人文科学とコンピュータ(CH)
- 巻号頁・発行日
- vol.2011-CH-90, no.1, pp.1-6, 2011-05-14
本研究は,鎌倉時代の仏師快慶を中心に,快慶とほぼ同時代を生きた仏師 3 人との造像における作風の特徴を数量的に比較する事を目的としたものである.分析作品を坐像のみに絞り,法量を用いて主成分分析を試みた.その結果,快慶が中央部へまとまったのに対し,運慶が全体に散らばり,院派・円派の京都仏師たちの作品は左上部へ附置された.この結果は従来の様式研究で指摘された作風の特徴と矛盾してはおらず、法量の数量分析でも仏師の作風の特徴が見出されうることが明らかとなった.
1 0 0 0 OA 宇宙実験室から宇宙工場へ(宇宙化学を支える化学)(<特集>宇宙と化学)
- 著者
- 久保園 晃
- 出版者
- 社団法人日本化学会
- 雑誌
- 化学教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.6, pp.496-498, 1984-12-20
1 0 0 0 OA 消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティ実践ガイド
- 著者
- 赤松 泰次 石原 立 佐藤 公 尾家 重治 大久保 憲 伏見 了 佐藤 絹子 田村 君英 藤田 賢一
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.89-107, 2014 (Released:2014-02-22)
- 参考文献数
- 79
1 0 0 0 室町・戦国期上野の地域社会
- 著者
- 久保出 将司
- 出版者
- 公益社団法人日本数学教育学会
- 雑誌
- 日本数学教育学会誌. 臨時増刊, 総会特集号
- 巻号頁・発行日
- vol.92, 2010-08-01
- 著者
- 出村 光一 久保 縁
- 出版者
- Japanese Dermatological Association
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, 1961
1951年にWilkinsonは,chronic vesicular impetigo of the trunkという表題で,高令の婦人にみられた2症例を報告している.即ち躯幹,大関節屈側面に膿,水疱性の皮疹が群生し,次第に遠心性に拡大して連圏状,或いは不規則地図状になり,皮疹はやがて結痂を形成する.病変はその辺縁部に於て殊に著明である.自覚症状は特記すべきものではなく,全身状態も良好である.組織学的所見としては,角層下に水疱形成があつて,その中に多核白血球を入れる.真皮に軽度の炎症々状をみるが,その他に特記すべき所見は無い.水疱内容の培養を行つて,その1例にStaph. aureusを証明している.治療としてはD.D.S.或いはsulfapyridineが効果的であつたが,再発の傾向があつた.この報告に対してSneddonは,彼が矢張り全く同様の症例を1947年の国際医学会の席上に供覧したが,同席せる皮膚科医諸氏,何れもその診断を附するのに困難を覚えたことであつた,と追加発言した.その後1956年にSneddon and Wilkinsonは,この様な症例を6例集めて観察し,これ等は,在来の分類では,その位置付けが困難である,一つの独立疾患に属するものと見做さるべきであるとなし,そのclinical entityに対してsubcorneal pustular dermatosis(S.P.D.)なる名称を用いて詳細に報告した.かくして独立疾患としての本症の輪廓が次第に明かになるや,その後は相次いで類似症例の報告がみられ,現在に至る迄に欧米では27例,本邦では我々の症例の他に去る1959年9月の東京地方会に於て,横浜警友病院から1例の供覧患者が報告されている.我々の症例も1959年10月の第23回東日本連合地方会,並びに第155回日本皮膚科泌尿器科学会新潟地方会に於いて報告されたものである.
- 著者
- 林 浩康 山本 恒雄 大久保 牧子
- 出版者
- 恩賜財団母子愛育会日本子ども家庭総合研究所
- 雑誌
- 日本子ども家庭総合研究所紀要 (ISSN:13442716)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, pp.133-161, 2013
1 0 0 0 OA 映画からの俳優の演技の測定とCGによる再演
- 著者
- 八木下 勝利 古山 隆志 大久保 直人 山中 一 山本 正信
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告グラフィクスとCAD(CG)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.112(1998-CG-093), pp.13-18, 1998-12-10
本論文では,動画像から人間の動作を解析し,それをアニメーションとして再構築する手法を示す.人間の動作の解析には時空間勾配法による手法を用いる.これにより普通の映画やビデオ映像などからでも対象の運動を測定できる,解析の精度向上のためにいくつかの拘束条件を利用している.解析された動作はデータベース化しておき,アニメーション作成時にはそのデータベースを利用してキャラクタの運動を再生する.データベースに無い動作を人間らしさや個性などが保存しながら生成する方法についても検討する.本手法を用いて複数の映画から解析した俳優の動作を一つのCGアニメーションとして再構成したので紹介する.
1 0 0 0 IR 所得税率のインフレ効果--ヒックス的アプロ-チ
- 著者
- 久保田 義弘
- 出版者
- 北海道大学經濟學部 = HOKKAIDO UNIVERSITY SAPPORO,JAPAN
- 雑誌
- 経済学研究 (ISSN:04516265)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.p515-533, 1982-08
- 著者
- 久保田 喜裕 山崎 興輔 飯川 健勝 吉越 正勝
- 出版者
- 地学団体研究会
- 雑誌
- 地球科學 (ISSN:03666611)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.6, pp.455-464, 2006-11-25
2004年10月23日の新潟県中越地震において,長岡市悠久山地域の被害要因に関する疑問を解明するため,補充調査を行った.その結果,以下のことが判明した.(1)一般に地盤が良いとされる段丘地でなぜ被害の集中域がみられたのか:住宅が集中する段丘面上にふたつの谷状凹地を確認したが,被害はこの谷状凹地の谷底や斜面の盛土地に集中した.とくに谷頭など,傾斜地の盛土部で顕著な被害がでた.被害要因として,この谷状凹地を埋積した沖積泥質堆積物や盛土が低い方へ変位したことが考えられる.(2)沖積盛土の大規模住宅地でなぜ被害が偏在したのか:損壊家屋は隣地との境界に設けられた水路(かつての水田の用排水路)脇に多かった.宅地地盤は北西側に0.7/100程度傾斜しており,被害は盛土が厚く深い水路(約1m)がある下流部に集中した.このような水路には一様にフタがない凹地空間となっている.被害要因として,傾斜した地盤に地震時の過剰な土圧が発生したため,盛土が水路・側溝の凹地空間へ押し出し,家屋とともに変位したことが考えられる.大規模な新興住宅地の開発は,今後ますます沖積低地へ向かうと思われる.沖積低地でも微傾斜地や,深い水路や側溝がある宅地地盤には,地震動による過剰な土圧の発生に耐えられる盛土の土留め擁壁や水路・側溝の側壁の耐力強化,グレーチングやコンクリート製のフタの設置といった,地盤の変位を抑える対策が不可欠である.
- 著者
- 木戸 秀明 久保 佳史 井上 理 林 一孝 成田 祐士 内田 武 渡辺 正弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.2, pp.79-91, 1993
イヌ急性心筋梗塞モデルを用いて,血栓溶解薬ナサルプラーゼ(plasminogen pro-activator)を静脈内に持続投与し,血栓溶解作用ならびに血栓溶解後急性期および慢性期の心機能の変化を検討した.冠動脈の閉塞により,循環動態においては心拍出量の減少,体血管抵抗および左心室拡張終期圧(LVEDP)の上昇が認められ,また左心室造影による解析の結果,左心室駆出率および左心室局所壁運動の低下等の心機能の低下がみられた.このモデルに,冠動脈閉塞30分後よりナサルプラーゼを8単位/kg/分の用量で静脈内投与した結果,78.6%(11/14)に再開通を認め,投与開始から再開通までの時間は平均37.4分であった.再開通時における血漿中フィブリノゲン量は薬物投与前と比較してほとんど変化しなかった.なお,再開通5~10分後より徐々に不整脈が出現した.再開通直後は左心室収縮機能がやや改善する傾向を示したものの,心機能全体としては改善をみなかった.しかしながら,1週間後にはナサルプラーゼによる再開通群で心機能,とりわけ収縮機能の回復がみられ,心臓に対する負荷が軽減されたのに対し,対照群(薬物非投与群)では回復を認めなかった.対照群では冠動脈の持続的な閉塞によって心臓が肥大し,左心室前壁から心尖部にかけて広範な心筋壊死が観察されたが,再開通群では梗塞サイズが対照群に比して有意に小さく,心肥大の進展が抑制された.以上のことから,イヌを用いた急性心筋梗塞モデルにおいて,ナサルプラーゼの静脈内投与による再潅流療法は有用であると示唆された.
1 0 0 0 IR 和歌山県田辺湾におけるタガヤサンミナシ(イモガイ科)の異例の数の漂着
- 著者
- 平澤 康太 久保田 信
- 出版者
- 漂着物学会
- 雑誌
- 漂着物学会誌 (ISSN:13491555)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.17-21, 2011-12
和歌山県田辺湾に異例の数のタガヤサンミナシの貝殻が漂着した.それらの貝殻模様の新鮮さを基準に3段階に分類し,漂着の原因を考察した.新鮮な貝殻を多く含む異例の数のタガヤサンミナシの漂着は, 2010年12月-2011年2月の厳寒と,採取した時期に接近した台風の影響が大きいことが示唆された.また,極めて稀に漂着した生きたタガヤサンミナシ1個体を飼育し,摂食行動を確認した.
1 0 0 0 517 動圧浮上遠心式血液ポンプの血液適合性の検討
- 著者
- 山根 隆志 加藤 孝久 丸山 修 西田 正浩 大久保 剛 佐野 岳志 宮本 祐介
- 出版者
- 一般社団法人日本機械学会
- 雑誌
- 年次大会講演論文集 : JSME annual meeting
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, no.7, pp.79-80, 2003-08-05
A hydrodynamic levitation centrifugal pump is being developed for a long-term implantable artificial heart. The hemocompatibility was investigated with numerical analysis and has been verified with animal blood tests. The hemolytic property was improved by expanding the bearing gap and by adjusting the pressure balance and the antithrombogenicity has been improved by adding deep grooves to the hydrodynamic bearings to increase the flow rate through the bearings.
1 0 0 0 日本における連続殺人事件の類型と単一殺人事件との比較
1 0 0 0 水戸光圀と卍元師蛮
- 著者
- 久保田 収
- 出版者
- Association of Esoteric Buddhist Studies
- 雑誌
- 密教文化 (ISSN:02869837)
- 巻号頁・発行日
- vol.1957, no.39, pp.34-41, 1957
1 0 0 0 一人暮らし高齢者の食生活に対する地域食事サービスの役割
- 著者
- 角田 久美子 大久保 みたみ 山本 学
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.10, pp.959-968, 1995
Nutritional survey was carried out for aged individuals who lived singly in Akishima City and received community meal service twice a week, and the results were compared with those of the individuals, who did not receive the meal service. Their food habits were correlated with their daily activities. Thus, the more active life they spent, the better food habits they had.<BR>Individuals, who received meal service, spent rather passive life and their food habits were poor and monotonous. On their nutrients intake, the estimated mean intake of protein was 41g/day and that of iron was 5.5 mg/day. These were significantly lower than those in the individuals who did not receivethe meal service (<I>p</I>< 0.01).<BR>With respect to service meals offered, these meals contained rich nutrients compared with the requirements of them. However, the evaluation of present meal service program revealed that twice service a week did not serve to improve their food habits, or to correct their nutrients intake.
1 0 0 0 OA 東京多摩西部地区の高齢者の生活に関する研究(第4報) : 衣生活
- 著者
- 林 隆子 川端 博子 石川 尚子 大久保 みたみ 大関 政康 大竹 美登利 唐沢 恵子 斉藤 浩子 高崎 禎子 武田 紀久子 山形 昭衛
- 出版者
- 社団法人日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.5, pp.361-369, 1992-05-15
- 被引用文献数
- 6
The survey of the daily clothes of 708 people, from ages 70 to 95,living in Ome City,Tokyo,was conducted from May though August, 1989. We investigated the sorts of daily clothes worn on the day surveyed and the details of each garment. The results were as follows:(1) The most typical ensemble of men's upper garments consisted of an undershirt, shirt and blazer or jacket while the lower one consisted of briefs or undershirt and a blouse and sweater with three-quarter sleeves that were button closing in front. The lower garments were mainly briefs, short or long underwear and trousers or a skirt. Trousers were preferred by elder women, compared to younger women.(3) Man-made fibers were often used for the outer wear of those surveyed.(4) An estimation of the thermal insulation and weight if the garments indicated that the elderly people surveyed wore more clothing than younger people.
1 0 0 0 競走馬のスポーツ科学(第3回)トレーニング理論(基礎編)
- 著者
- 久保 勝義
- 出版者
- 日本中央競馬会競走馬総合研究所
- 雑誌
- 馬の科学 (ISSN:03884376)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.4, pp.205-209, 2007
1 0 0 0 OA トレハロース合成酵素の精密化結晶構造と触媒機構
- 著者
- 小林 正則 久保田 倫夫 松浦 良樹
- 出版者
- 日本応用糖質科学会
- 雑誌
- Journal of Applied Glycoscience (ISSN:13447882)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.1-8, 2003-01-20 (Released:2011-02-23)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 4 18
マルトオリゴシルトレハロース合成酵素(MTSase)はトレハロース生合成経路の第一段階で働く酵素であり,マルトオリゴ糖の還元末端のα-1,4結合を主として分子内転移によりα,α-1,1結合に変化させる反応を効率よく触媒する.筆者らは本酵素の立体構造を精密に(1.9A分解能)X線結晶解析し,反応機構について知見を得た.MTSaseはα-アミラーゼファミリーの酵素であり,触媒活性残基(Asp228,Glu255,Asp443)はファミリーに共通に保存されたものであり,α-1,4結合の解裂に続いてグルコースの転位が起こると考えられる.全体的な構造はファミリーに共通にみられる(β/α)8-バレルが存在し(ドメインA),活性部位はその中心β-バレルのc末端側とドメインBとの間に形成されたクレフトの底に位置している.通常のα-アミラーゼに比して挿入されたポリペプチド部分が多く,全体の分子量を大きくしている(720残基).活性部位はクレフトの一端の奥に存在し,三つの活性残基を底部に有したポケットを形成している.ポケット形成には上記挿入ポリペプチド部が大きく関与している.またポケット上部には触媒活性に必須なGlu393,側面にHis229が存在し,それぞれ末端グルコース基との水素結合に関与している.基質のα-1,4結合末端が挿入された際にポケット内部で形成される酵素・基質問の水素結合の数は,α,α-1,1結合を形成することにより増加し,その結果トレハロース残基の生成が促されると考えられる.