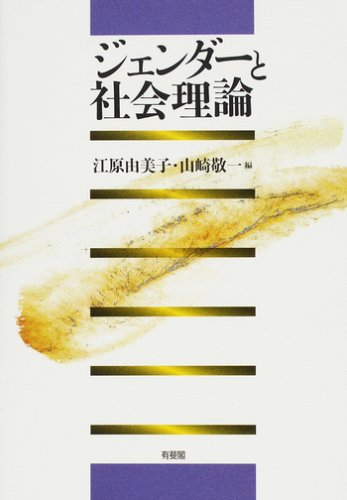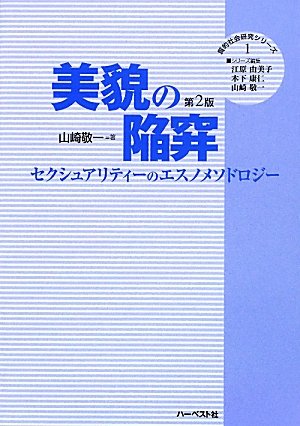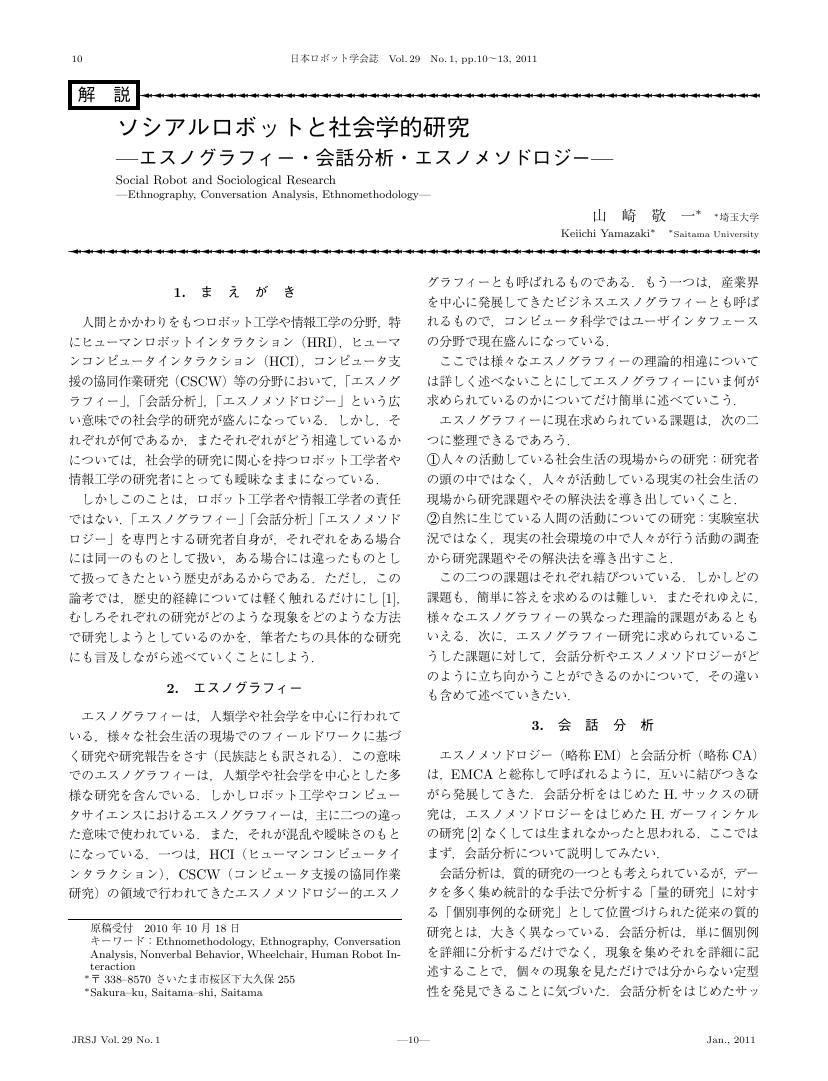7 0 0 0 ジェンダーと社会理論
- 著者
- 江原由美子 山崎敬一編
- 出版者
- 有斐閣
- 巻号頁・発行日
- 2006
4 0 0 0 エスノメソドロジー的視点に基づく購買支援システムの開発
3 0 0 0 OA Affinity Live:演者と観客の一体感を増強する双方向ライブ支援システム
- 著者
- 大津 耕陽 福島 史康 高橋 秀和 平原 実留 福田 悠人 小林 貴訓 久野 義徳 山崎 敬一
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.11, pp.2019-2029, 2018-11-15
近年さかんに行われているアイドルのライブにおいては,演者の演技に対し観客が「応援」という形で参加することにより,会場をともに盛り上げていこうとする様子が見られる.本稿では,アイドルのライブにおける演者の演技・それに対する観客の応援を振動・光に変換し,双方向に伝達しあうことで,演者・観客間の双方向インタラクションを拡張するライブ支援システムを提案する.提案手法を実現するために,応援したいメンバの演技をリアルタイムに観客の持つデバイスに振動・光として提示する機能,観客が自身の持つデバイスを振ることで光として応援を可視化して演者側に伝達する機能の2つを持つシステムを開発した.実際のライブ環境下において実験を行い,演者の動きの情報を観客に伝達することで応援したいメンバと観客の間の一体感が高まることを確認した.また,デバイスの振りの情報に基づいて観客の応援の大きさを演者の衣装に提示することによって,応援したい特定のメンバと観客間の一体感に加えて,特定のメンバを応援する観客同士の一体感が高まることを確認した.
3 0 0 0 美貌の陥穽 : セクシュアリティーのエスノメソドロジー
3 0 0 0 OA ケア場面における参与地位の配分― 話し手になることと受け手になること ―
- 著者
- 秋谷 直矩 川島 理恵 山崎 敬一
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.78-90, 2009 (Released:2010-06-11)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 4
This paper considers how people gain particular participant's orientation in multiparty settings, and explicates its structural features. For that purpose, we did videotape and examine naturally occurring interactions between elderly visitors and care workers within nursing care home for elderly. We analyze how interaction is initiated between elderly visitors and care workers, and how interaction is coordinated between them. In relation to this, Schegloff (2002=2003) and Heath (1984) discussed actions as a pre-initiating activity. Heath (1984) made a definition of it: ‘...whereas a display of availability serves as a pre-initiating activity providing an environment for the occurrence of a range of actions...’(Heath, 1984: 250). In particular, we focus on cases in which a care worker is not displaying availability to an elderly visitor who want to talk to this care worker. In such a situation, an elderly visitor does extra work in order to gain the care worker's availability. Then, When do an elderly visitor gain the care worker's availability? As a result, a care worker's utterance and behavior that suggests possibility of disengagement from participant framework by then are very useful resource for an elderly visitor who want to gain the care worker's availability.
2 0 0 0 OA 大学生のアイドルファンにおける音楽受容の調査
- 著者
- 古川 光流 袁 景竜 陳 怡禎 山崎 敬一
- 出版者
- 埼玉大学教養学部
- 雑誌
- 埼玉大学紀要. 教養学部 = Saitama University Review. Faculty of Liberal Arts (ISSN:1349824X)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.237-258, 2020
本研究は、アイドルファンであることの経験を中心に、現代の大学生の音楽受容の実態を量的研究と質的研究を組み合わせた多段階調査を行い、分析したものである。本研究では、第1段階として、S 大学の学生を中心に音楽受容の実態を調査した。その結果、音楽受容に男女差は見られず、また、現代の音楽産業の中心となっている音楽ライブの参加経験者も少数にとどまっていた。しかし、S 大学の学生のうち、アイドルの音楽ライブ参加経験がある学生を対象にした第2 段階の調査においては、どのようなアイドルを応援するかについて、男女差がみられた。また、年間4 回以上音楽ライブに参加する熱心な参加者や、複数のアイドルを応援するファンが多く見られた。さらに、第3 段階の調査として、アイドルの音楽ライブ参加経験者に対して、グループインタビューとグループディスカッションを行い、日常生活におけるアイドルファンの応援活動やコミュニケーション、複数のアイドルを応援する傾向について考察した。This paper examines the music experiences practiced by Saitama University students through quantitative and qualitative research. Data analyzed in this paper were from the questionnaire survey for the quantitative analysis and group interviews for the qualitative analysis. The first questionnaire survey revealed that there was no gender difference in respondents’ music experiences and only a small number of students who had participated in music live. However, the second survey established that there was the gender difference in attending concerts between the respondents. The second survey also showed that the respondents who participate in music live at least four times a year have tendencies to support more than one idol. The third survey as a qualitative research was to demonstrate the fan activities and communications in the idol-fan communities. This is conducted through sources from group interviews and group discussions with fan club members and idol music live participants.
2 0 0 0 OA 越境する文化・還流する文化‐ライトカルチャーの同時性と歴史性の情報論的分析
本研究では、これまで日本の若者という限定された受け手を主な対象として生まれてきた日本のポップカルチャーが、現在どうして、世代を越えた、また文化を越えた人気を持つようになったのかを、(i)エスノメソドロジーから生まれた会話分析的な物語論や、(ii)情報メディア論や、(iii)観衆論の視点から明らかにした。この研究では、経験や歴史を伝える物語がどのように語られるかについて研究した。またフランスのジャパンエクスポに出演中の日本のアイドルと日本にいるファンとの交流を、ロボットによって支援する研究を行った。また最終年度には、宝塚や歌舞伎の舞台と、アイドルグループのコンサートを観衆論の観点から比較した。
2 0 0 0 OA 言語的身体的相互行為の多文化エスノグラフィーに基づく身体テクノロジーのデザイン
- 著者
- 山崎 敬一 山崎 晶子 久野 義徳 池田 佳子 今井 倫太 小野 哲雄 五十嵐 素子 樫村 志郎 小林 亜子 関 由起子 森本 郁代 バーデルスキー マシュー 川島 理恵 中西 英之 小林 貴訓
- 出版者
- 埼玉大学
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2011-04-01
本研究は、人間の言語的・身体的相互行為とそれを支援する身体化されたテクノロジーのデザインに関心を持つ社会学者とロボット工学者の共同研究である。本研究では多文化に対応する身体化されたテクノロジーを開発するために、海外のミュージアム等で研究を行い、そこでの人間同士の言語的・身体的行為をヴィデオエスノグラフィーの手法で分析した。また、日本語話者と英語話者に対する比較ロボット実験と、日本とハワイを結ぶ遠隔ロボット実験を行った。
2 0 0 0 インタラクティブな展示装置を中心とする鑑賞者の相互行為
- 著者
- 菅 靖子 山崎 晶子 山崎 敬一
- 出版者
- 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.5, pp.1-10, 2003
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
本稿は,ミュージアム研究の展示空間における観客の相互行為に焦点を当てた鑑賞の「質」的分析を行うことにより,観客同士がつくりだす共有空間の形成の重要性および鑑賞行為における観客の相互関係を明らかにしたものである。特に,本研究では,これまで着目されていなかった共有空間に参与する「傍観者(bystander)」の役割に注目して,鑑賞行為を分析した。傍観者(bystander)と実践者との基本的な関係について,個別的なケースからより基本的な構造を分析し解明した結果,ミュージアムの展示において,傍観者(bystander)の動きは,共有空間の形成に参与するだけではなく,鑑賞行為全般を導くものである。なぜなら,傍観者(bystander)は実践者に対して,発話と共に指さしなどの非言語的なコミュニケーションを行い,情報・知識の伝達を行いやすい身体配置を取る,ということが明らかになった。
- 著者
- 山崎 敬一
- 出版者
- The Robotics Society of Japan
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.10-13, 2011-01-15
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 3209 ロボット介した遠隔作業指示システムの開発
- 著者
- 葛岡 英明 小山 慎哉 山崎 敬一 光石 衛 鈴木 健二
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 設計工学・システム部門講演会講演論文集 2001.10 (ISSN:24243078)
- 巻号頁・発行日
- pp.329-330, 2001-01-16 (Released:2017-06-19)
When designing systems that support remote instruction on physical tasks, one must consider requirements : 1) participants should be able to use non-verbal expressions, 2) they must be able to take an appropriate body arrangement to see and show gestures, 3) the instructor should be able to monitor operators and objects, 4) they must be able to organize the arrangement of bodies and tools and gestural expression sequentially and interactively. GestureMan was developed to satisfy these four requirements by using a mobile robot that embodies a remote instructor's actions. The mobile robot mounts a camera and a remote control laser pointer on it. Based on the experiments with the system we discuss the advantage and disadvantage of the current implementation.
1 0 0 0 OA リモートコラボレーション空間における時間と身体的空間の組織化
- 著者
- 山崎 敬一 葛岡 英明 山崎 晶子 池谷 のぞみ
- 出版者
- 特定非営利活動法人 組織学会
- 雑誌
- 組織科学 (ISSN:02869713)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.32-45, 2003-03-20 (Released:2022-08-03)
- 参考文献数
- 15
この論文では,リモートコラボレーション空間において,遠隔地にいる作業者がどのようにして時間と身体的空間を組織化しているかを,エスノメソドロジー的相互行為分析の手法で明らかにする.さらにそうしたリモートコラボレーション空間での共同作業に対するエスノメソドロジー的・社会学的分析に基づき,社会学者と工学者からなる筆者らの共同研究グループがデザインした,いくつかのリモートコラボレーションシステムについて紹介したい.
1 0 0 0 IR 大学生のアイドルファンにおける音楽受容の調査
- 著者
- 古川 光流 袁 景竜 陳 怡禎 山崎 敬一
- 出版者
- 埼玉大学教養学部
- 雑誌
- 埼玉大学紀要. 教養学部 (ISSN:1349824X)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.237-258, 2020
本研究は、アイドルファンであることの経験を中心に、現代の大学生の音楽受容の実態を量的研究と質的研究を組み合わせた多段階調査を行い、分析したものである。本研究では、第1段階として、S 大学の学生を中心に音楽受容の実態を調査した。その結果、音楽受容に男女差は見られず、また、現代の音楽産業の中心となっている音楽ライブの参加経験者も少数にとどまっていた。しかし、S 大学の学生のうち、アイドルの音楽ライブ参加経験がある学生を対象にした第2 段階の調査においては、どのようなアイドルを応援するかについて、男女差がみられた。また、年間4 回以上音楽ライブに参加する熱心な参加者や、複数のアイドルを応援するファンが多く見られた。さらに、第3 段階の調査として、アイドルの音楽ライブ参加経験者に対して、グループインタビューとグループディスカッションを行い、日常生活におけるアイドルファンの応援活動やコミュニケーション、複数のアイドルを応援する傾向について考察した。This paper examines the music experiences practiced by Saitama University students through quantitative and qualitative research. Data analyzed in this paper were from the questionnaire survey for the quantitative analysis and group interviews for the qualitative analysis. The first questionnaire survey revealed that there was no gender difference in respondents' music experiences and only a small number of students who had participated in music live. However, the second survey established that there was the gender difference in attending concerts between the respondents. The second survey also showed that the respondents who participate in music live at least four times a year have tendencies to support more than one idol. The third survey as a qualitative research was to demonstrate the fan activities and communications in the idol-fan communities. This is conducted through sources from group interviews and group discussions with fan club members and idol music live participants.
1 0 0 0 IR コミュニケーションにおけるフィードバックを支援した実画像通信システムの開発
- 著者
- 山下 淳 葛岡 英明 井上 直人 山崎 敬一
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.300-310, 2004-01-15
- 被引用文献数
- 17
人間同士のコミュニケーションはフィードバックによって支援されている.たとえば,問いかけに対する応答がそうである.遠隔地間コミュニケーションを実画像通信を用いて支援する場合でも,このフィードバックを適切に支援することが重要となる.また,適切なフィードバックを得るためには,応答だけではなく,問いかけといった行為も,その意図どおりに伝えることができるよう,システムが支援することも重要である.本論文では,身振りなどに表現される作業者の注目方向,すなわち志向の伝達支援と,遠隔地と共有した作業領域における直接的な指示支援の2点に着目し,指示を行う作業者の意図や,指示を受けた作業者の身体表現を,実画像通信メディアを通したあとでもその意図どおりに再現することを試みた.Interpersonal communication is comprised by feedback such as reply to the speaker. To support this kind of feedback is the system requirements for developing remote collaboration system based on video channel. In this paper, the authors focus on these two points; 1) to support communication of conducts such as gestures, and 2) to support communication of intuitive pointing between remote and local work spaces. Remote collaboration system called AgoraG is the system which complies with two points of the requirements. The authors demonstrate how the system complies with those two requirements through some experiments.
1 0 0 0 OA コミュニケーションのためのロボットの目:外見と機能の総合的デザイン
目はものを見るためにあるが、アイコンタクト等の非言語コミュニケーションのためには他者に見せる機能も重要である。また、人間と共存するロボットとの目としては、人間に親しみやすい感じを与えるものが望まれる。そこで、この2点について、レーザプロジェクタにより種々の目の像を投影表示できるロボット頭部を試作し、どのような目の形状がよいかを被験者を用いた実験により調べた。その結果、人間の目の形状程度から、さらに目を丸く、また瞳も大きい形状が、親しみやすく、また視線がどちらを向いているかが読みとりやすいことが分かった。また、目や頭部の動かし方についても調査し、人間に自然に感じられる動かし方を明らかにした。
1 0 0 0 OA ソシアルロボットと社会学的研究
- 著者
- 山崎 敬一
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.10-13, 2011 (Released:2011-02-25)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 微視的権力状況における会話分析
初年度においては文献研究と研究計画の決定のための研究活動をおこない、第二年度においてはその研究計画に基き調査を実施した。最終年度においては、それらをもとに、研究成果を論文化することを主要な課題とし、研究報告書の作成に着手した。本研究の性格上、収集したデータの分析は、今後も継続して行われると思われるが、報告書作成段階において得られた知見を以下に挙げる。第一に、対面的相互行存状況においては、状況内にある参与者の身体(視線、顔、身体の向き、参与者相互の身体配置等)が相互行存進行の上で非常に重要な意味をもっていること。第二に、特定の制度的文脈においては、特定の相互行存的特徴がみられること.第三に、特定の制度的文脈において発生する会話トピックには、一定の範域があり、その範域をコントロールしようとする参与者の実践がみられること。第四に、それらの特定の制度的な文脈における相互行存の特徴は、相互行存参与者の、「協働的達成」として成立していること。これらの知見は、社会秩序それじたいが、行存者の「協働的達成」として成立していることを明らかにしている。社会秩序の「協働的達成」のための身体技術に関しては、その一部を報告書において明らかにしたが、今後さらに詳細な研究が必要である。
1 0 0 0 OA 高齢者介護施設におけるコミュニケーションチャンネル確立過程の分析と支援システムの提案
- 著者
- 秋谷 直矩 丹羽 仁史 岡田 真依 山崎 敬一 小林 貴訓 久野 義徳 山崎 晶子
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.302-313, 2009-01-15
高齢者介護施設において,高齢者とスムーズにコミュニケーションができるロボットを開発するためには,まず,「いかにしてロボットと高齢者がコミュニケーションチャンネルを確立するのか」ということを考えなければならない.そこで,高齢者介護施設における複数人環境でのケアワーカーと高齢者のコミュニケーションチャンネルの作り方を観察した.分析方法として,社会学の一領域であるエスノメソドロジーを用いた.そこでは,行為を始めることを可能にする「対応可能性」,指向の重なりを示す「受け手性」,そして指向の重なりを参与者相互が理解したことを示す「理解の表示」という一連の手続きの制度的特徴が見られた.この調査結果をリソースとして,ロボット開発を行った.その印象評価実験を行ったところ,開発したロボットがユーザに親近感や安心感を与えることが分かった.この実験の結果は,本稿の取り組みが一定の有効性を持つということと,人びとの日常的実践の場面において社会学の手法を用いて調査し,その結果を開発に生かすということの方法論的意義を示した.
1 0 0 0 家事調停および民事調停過程のコミュニケーション分析
紛争処理は広く合意型と裁定型に分けることができる.合意型の紛争処理においては,紛争処理過程の開始,進行とその結果が紛争当事者による承認ないし規範受容に結合されている(ただし,裁定型の紛争処理でも,紛争解決の最終結果の規範的妥当性が,制度的規範により構築されるにとどまり,その過程や結果の解釈等は,かなり紛争当事者の規範受容によって構築されたり影響されたりする).本研究では,合意型の処理において当事者の間のどのようなコミュニケーションがなりたっているのかを知ることを主眼として,エスノメソドロジーの知見を参考にしながら,複数の研究を行った.(1)まず,法社会学の研究と理論における,非公式紛争紛争研究のレビューを行った.(2)その上で,理論的分析としては,法的コミュニケーションを単なる相互了解としてではなく,法的場面を存立させるための根源的かつ基盤的作用をもつものとしてとらえる社会学的視角の総合と洗練を行った.(3)以上の理論的分析の上にたつ,経験的分析としては,まず,紛争当事者と法的専門家が公式・非公式の紛争処理の準備のために事件の分析を行う法律相談場面.紛争当事者と紛争解決者が合意にもとづく紛争解決を達成するために事件の分析を行う調停場面(シミュレーション)をとりあげて,詳しい分析を行った.(4)この経験的知見を確かめるために,人が日常的場面を理解しようとする際に規範へと言及する場面を半実験的に構成し,法制度的場面と比較した.これらの結果として,本研究は,理論的ならびに経験的分析を組み合わせて,合意型の紛争処理過程が,独特の制度的規範構造のもとで起こるコミュニケーションとして,日常的なコミュニケーションと区別されることを示すことに成功した.
1 0 0 0 コンピュータ科学におけるエスノメソドロジー研究の意義
- 著者
- 秋谷 直矩 山崎 敬一 久野 義徳
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理 (ISSN:04478053)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.7, 2010-07-15