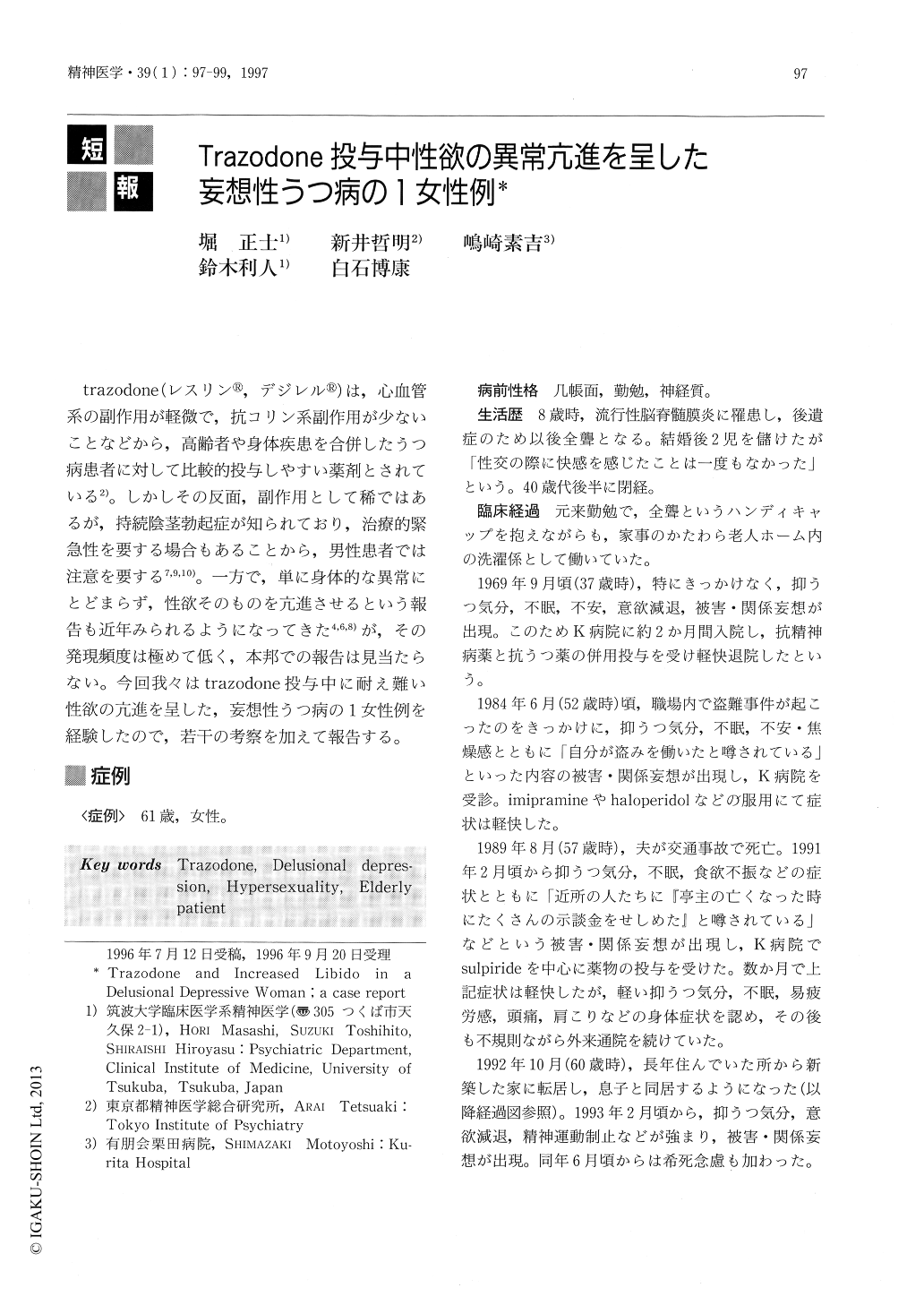1 0 0 0 皇太子さまお生れなった
1 0 0 0 李光洙の長篇<愛>について
- 著者
- 白川 春子
- 出版者
- 熊本学園大学
- 雑誌
- 熊本商大論集 (ISSN:04510585)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.p483-502, 1990-05
- 著者
- 白石 貢一郎 喜多岡 健二 石戸谷 武 菅原 幸弥
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.17 Suppl. (第25回日本理学療法士学会誌 第17巻学会特別号)
- 巻号頁・発行日
- pp.261, 1990-03-31 (Released:2017-07-07)
- 著者
- 白地 孝
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.12, pp.1479-1494, 1976 (Released:2007-12-26)
- 参考文献数
- 34
閉塞性黄疸時のビリルビンの腎よりの排泄機序, 閉塞性黄疸時の腎障害, 尿排泄障害時における血中ビリルビン値の変化, ビリルビンによる腎障害などについて, 臨床的, 実験的に検討し, つぎの様な結果を得た.1) 尿中へのビリルビンの排泄量は, 血清総ビリルビン値および直接型ビリルビン値と正の相関々係を示し, また血清アルブミン予備結合能と負の相関々係を示すことから, ビリルビンの尿中への排泄には, アルブミンと結合していない遊離の直接型ビリルビンが尿中に排泄される可能性が強いことが示された.2) 片側尿管の結紮その他によつて尿排泄障害をおこし, あるいは腎障害を有する例では, 尿中排泄ビリルビン量が減少し, 血清ビリルビン値がより高値を示すことから, 血清ビリルビンの値は, 腎機能と密に関係していることも明らかになつた.3) 黄疸発現よりの期間が長くなるにつれ, 腎障害が増強し, 尿中へのビリルビンの排泄量が減少した.
1 0 0 0 OA 無精子症に対する新規薬物療法確立のためのヒト精巣の網羅的遺伝子解析
ヒト精巣組織から次世代シーケンサー(NGS)によるトランスクリプトーム解析を行った。23,616の遺伝子のmRNAについて解析を行ったところ、cell cycle, nucleic acid bindingなどの遺伝子群が高発現の上位を占めた。非閉塞性無精子症症例との比較においてその発現は特にヒストンH3.5などのエピジェネティック関連遺伝子に認められた。また精索静脈瘤症例においてcell cycle関連遺伝子の発現が低下し、精索静脈結紮術の効果と関連することが判明した。NGSによるトランスクリプトーム解析は造精機能障害の病態解明において有用な方法であることが示された。
1 0 0 0 OA スラブクーリングボイラの開発(<特集>鉄鋼業における省エネルギー)
- 著者
- 篠原 虔章 高橋 明人 白石 典久
- 出版者
- 社団法人日本鉄鋼協会
- 雑誌
- 鐵と鋼 : 日本鐡鋼協會々誌 (ISSN:00211575)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.13, pp.1959-1967, 1978-11-01
Hot slabs after the slabbing mill are at a mean temperature of 1000℃ and have the sensible heat of 160×10^3 kcal/t-slab. The main features of a Slab Cooling Boiler (SCB) are the recovery of the sensible heat to steam (16kg/cm^2G) by mean of heat radiation from the surface of hot slabs, and continuation of cooling process of almost every kind of slab. The first installation of an SCB was completed at Slabbing Mill No.2 in Mizushima Works of Kawasaki Steel Corporation and it has been operating successfully since March, 1976. The capacity of the heat recovery in this SCB is 72000kcal/t-slab. It is equal to or greater than the heat consumption of rimmed and semikilled steel in the soaking pit. This paper discusses the basic heat transfer experiments performed under this development, the basic planning of the installation, the outlines of the system, and some results of the operations.
- 著者
- 白根澤 正士
- 出版者
- 中央大学人文科学研究所
- 雑誌
- 人文研紀要 (ISSN:02873877)
- 巻号頁・発行日
- no.49, pp.51-75, 2003
- 著者
- 白木 彩子
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.85-96, 2012-05-30 (Released:2018-01-01)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 4
2004年2月、北海道苫前町においてオジロワシの風車衝突事故による死亡個体が日本で初めて確認された。それ以降、本種の衝突事故の発生は続いているが、事故の対策はとられていない。オジロワシのような法的な保護指定種が多数死亡しているにも関わらず、実質的に放置されている現状には問題がある。そこで本報告は、これまでに発生したオジロワシの風車衝突事故の事例から事故の特徴や傾向について分析することと、事故の発生要因についてオジロワシの生活史や生態学的な特性から考察することを主な目的とした。また、これまでの保全の経緯も踏まえつつ、今後の保全対策のあり方について考えを述べた。2003年から2011年5月までに、北海道内の風力発電施設で確認された鳥類の風車衝突事故は20種を含む82件だった。このうちもっとも多いのはオジロワシの27件で、齢別にみると幼鳥を含む若鳥がほとんどを占め、主として越冬期にあたる12月から5月に事故が多い傾向がみられた。風車衝突事故による死亡個体のうち半数程度は北海道で繁殖する集団由来の留鳥であると推測されたが、個体群へのインパクトを正しく評価するためにも、今後、衝突個体が留鳥か渡り鳥なのかを明らかにすることは重要である。オジロワシの風車への衝突事故は風車が3基の施設で11件と最も多く、小規模の施設でも多数の事故が発生し得ることが示された。事故の発生した風車は海岸部の段丘崖上や斜面上にあるものが半数以上を占め、これらの地形はオジロワシにとって衝突するリスクの高い条件のひとつと考えられた。死骸の多くは衝突事故の発生から数日以内に発見されており、このことから、確認された死骸は実際に衝突死したオジロワシのうちの一部であることが推測された。現在のところ、風力発電施設によるオジロワシ個体群に対するインパクトを評価するために必要なデータは不十分な状況であるが、とくに地域集団に対する悪影響が懸念されることから、衝突事故の防止は急務と考えられる。具体的には、施設建設前の適切な立地選定と、稼働後に発生した事故対策措置である。衝突事故が発生している既存の風車については、今後の衝突の可能性を査定した上で、オジロワシの利用頻度の低い場所への移設や日中の稼働停止も含めた有効な事故防止措置の実施が望まれる。
1 0 0 0 日本蘚苔類学会第23回大会(新潟,湯沢)報告
- 著者
- 白崎 仁
- 出版者
- 日本蘚苔類学会
- 雑誌
- 日本蘚苔類学会会報 (ISSN:02850869)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.6, 1994
- 著者
- 白石 晴美
- 出版者
- 埼玉女子短期大学
- 雑誌
- 埼玉女子短期大学研究紀要 = Bulletin of Saitama Women's Junior College (ISSN:09157484)
- 巻号頁・発行日
- no.42, pp.91-101, 2020-09
trazodone(レスリン®,デジレル®)は,心血管系の副作用が軽微で,抗コリン系副作用が少ないことなどから,高齢者や身体疾患を合併したうつ病患者に対して比較的投与しやすい薬剤とされている2)。しかしその反面,副作用として稀ではあるが,持続陰茎勃起症が知られており,治療的緊急性を要する場合もあることから,男性患者では注意を要する7,9,10)。一方で,単に身体的な異常にとどまらず,性欲そのものを亢進させるという報告も近年みられるようになってきた4,6,8)が,その発現頻度は極めて低く,本邦での報告は見当たらない。今回我々はtrazodone投与中に耐え難い性欲の亢進を呈した,妄想性うつ病の1女性例を経験したので,若干の考察を加えて報告する。
- 著者
- 白井 啓 川本 芳 森光 由樹
- 出版者
- 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.15, 2018
<p>日時:2018年7月13日(金) 14:40-17:50<br>場所:8号館6階8603教室<br><br>日本で特定外来生物に指定されているタイワンザル,アカゲザルが野生化し,ニホンザルへの交雑等が問題になっている。<br>2004年に青森県下北半島のタイワンザルの全頭捕獲が達成されたのに続いて,2017年12月,和歌山県北部で野生化していたタイワンザルの群れの根絶達成が,5年間の残存個体有無のモニタリングを経て,和歌山県知事によって公表された。366頭目である最後の交雑個体が捕獲,除去された2012年4月30日に根絶が達成されていたことになる。自由集会では群れ根絶の報告とともに,経過をふりかえり学んだことを整理する。<br>一方,千葉アカゲザル問題は対策が進められているものの,さらなる課題がある。房総半島南部に野生化しているアカゲザル個体群では,2000頭を超える捕獲,除去が進んでいるものの,半島中央部の房総半島ニホンザル地域個体群に交雑が波及し,ニホンザルのメスが交雑個体を出産しているという緊急事態になっている。そこには国の天然記念物「高宕山サル生息地」もあり,ニホンザル,ひいては房総半島の生物多様性保全のための今後の課題を整理する。<br>以上,行政を含む和歌山タイワンザル関係者,千葉アカゲザル関係者から報告し,会員のみなさまと議論する予定である。<br><br>責任者:白井啓,川本芳,森光由樹(保全福祉委員会)<br>連絡先:shirai@wmo.co.jp</p>
1 0 0 0 OA ブルネルの大気圧鉄道に関する研究 第3報, 模型製作
- 著者
- 佐藤 建吉 白井 靖幸 赤坂 拓郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 C編 (ISSN:03875024)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.746, pp.2429-2434, 2008-10-25 (Released:2011-03-04)
- 参考文献数
- 8
The working model of Brunel's atmospheric railway (BAR) was made and demonstrated at a museum event and a university festival event. The original system of BAR was run commercially in England for a year during 1847-1848. The driving system of BAR is very simple but there were many difficult problems in working service. In this paper, the authors made the working model of BAR to realize and show the Brunel's challenge : the driving mechanism, the design know-how, the dream and passion, etc. The all person played with and watched at the model enjoyed very much due to the running by a vacuum cleaner. The present paper describes the summary the detail of the model, such as materials, sizes and shapes, performance, problems, and further applications.
1 0 0 0 OA 人格認知の次元性に関する研究 Norman仮説の検討
- 著者
- 中里 浩明 Michael H. Bond 白石 大介
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.3, pp.139-148, 1976-09-20 (Released:2010-07-16)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 8 7
2 experiments were performed using Norman's procedure to examine his hypothesis on the 5 major dimensions of personality perception (Norman, 1963; Passini & Norman, 1966). (a) A factor analysis was run on peer nomination rating data for male and female college students using Norman's original scales. 5 factors were extracted generally similar to those of Norman (1963): Extroversion (sociability), agreeableness, conscientiousness (responsibility), emotional stability (toughness), and culture (cultural sophistication). (b) From the data of peer nomination ratings using behavior descriptions derived from scales of Nagashima et al. (1967) only 3 factors, toughness (volition), likableness, and extroversion were found. Thus, there was a discrepancy among 2 results in the number and structure of the factors. Further discussion was made with reference to the dimensions of meaning of Osgood et al. (1957).
- 著者
- 阿部 洋太 武井 健児 高橋 和宏 山本 敦史 長谷川 信 田澤 昌之 白倉 賢二
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, 2014
【はじめに,目的】胸郭出口症候群(TOS)は,胸郭出口において腕神経叢または鎖骨下/腋窩動静脈が圧迫あるいは牽引されて生じる病態の総称である。TOSのリハビリテーションに際しては圧迫型・牽引型・混合型といった病態の把握とともに,斜角筋間三角・肋鎖間隙・小胸筋深部といった症状誘発部位の鑑別が必要とされる。鑑別方法としてAdson test,Eden test,Wright testといった脈管圧迫テスト(テスト)があり,これらは本邦におけるTOS診断に際して用いられている。現在のTOS病態の理解では,神経原性の牽引型が9割を占めるとされており,圧迫型においても血管原性は希であるとされているため,上記のテストは血管と同時に圧迫を被る腕神経叢の圧迫症状を推測するものとして使用される。しかし,テスト時の症状としては痺れなどの神経性の症状に伴い,脈拍減弱や色調変化といったいわゆる血管性の症状も出現しており,どの部位で何が圧迫を受けているのかという点とそのときの症状の関連性には不明な点が多い。我々はテスト実施時の血管の状況をリアルタイムで確認出来る超音波診断装置に着目し,その有用性を検討してきた。そこで本研究では,超音波診断装置より得られる各テスト時の血管面積の変化と,その際の症状との関連性を検討し,TOSにおける脈管圧迫テストの在り方を再考することを目的とした。【方法】被験者は日常生活においてTOS症状を有さない健常成人9名とした。測定には超音波診断装置(MyLab 25,日立メディコ社製)を用いた。測定部位は斜角筋間三角,肋鎖間隙,小胸筋深部の3箇所とし,1)上肢下垂時,2)Adson test時(頸部最大後屈+検査側回旋位,最大吸気位),3)Eden test時(両肩関節軽度伸展,両肩甲骨最大下制+内転+後傾位),4)Wright test時(肩関節90°及び130°外転位)のそれぞれにおいて,各箇所の血管面積を計測した。また,各測定時に出現したTOS症状の部位及び性質を聴取するとともに,脈拍及び指尖の色調を確認した。統計学的解析にはWilcoxonの符号付順位検定を用い,上肢下垂位と各テスト時の血管面積を部位ごとに比較した。【倫理的配慮,説明と同意】本研究はヘルシンキ宣言に沿った研究であり,群馬大学臨床研究倫理委員会の承認を得て実施した。また,対象者全員に本研究について文書と口頭にて十分な説明を行い,同意を得た後に測定を行った。【結果】上肢下垂位と比較し,Adson test時では全ての部位において有意に血管面積が減少していた。Eden test時では,肋鎖間隙において有意に血管面積が減少していた。Wright test時では,全ての部位において有意に血管面積が減少していた。各測定時のTOS症状出現状況は,Adson test時が1名,Eden test時が3名,Wright test時が6名であり,その部位は上腕内側及び外側が1名ずつ,手掌全体が1名,残り7名が第2指尖から第5指尖のいずれか複数部位であり,症状の性質は全員が痺れやだるさであった。なお,症状出現者全てにおいて,脈拍減弱が確認された。【考察】Adson testでは全ての部位において有意な血管狭窄が生じていたものの,症状出現者は1名であった。このテストは,深呼吸に起因する全身の循環動態と神経反射により生ずる一過性の血流低下が大きく関与するため,血管圧迫の意味合いは少なく,診断に際する特異度も高いことが明らかとされている。本研究においても同様のメカニズムが血管面積に関与し,同様の症状出現状況であったと考えられる。Wright testでは全ての部位において有意な血管狭窄が生じ,症状出現者も6名と最も多く,多彩な部位に痺れが誘発されていた。先行研究ではWright testによる肋鎖間隙での有意な血管狭窄がすでに報告されており,本研究結果とは異なる傾向となった。そのため圧迫部位は定かでないが,症状としては,第4及び第5指尖を筆頭に,上腕内側及び外側や手掌全体など様々な部位に出現しており,対象者によって異なる高位の腕神経叢神経幹部が血管と同時に圧迫を被ったと考えられる。Eden testに関して,本研究では肋鎖間隙においてのみ有意な血管狭窄が生じていた。肋鎖間隙では鎖骨下動静脈が腕神経叢よりも後下方を走行しているという解剖学的特徴があるため,血管よりも神経の圧迫が先行すると報告されているが,本研究では痺れやだるさといった症状に加え,指尖の色調が暗赤色に変化するといった静脈圧迫性の症状が出現しており,神経性及び血管性の所見が複合する結果であった。【理学療法学研究としての意義】本研究のようなデータの蓄積は各テストの特徴を明らかにし,TOSの病態解明の一助となるとともに,超音波診断装置のTOS評価としての有用性など,様々な点でリハビリテーションへの応用が可能である。
1 0 0 0 OA 高齢者でのインフルエンザワクチン連続接種時の接種回数とワクチン効果についての検討
- 著者
- 池松 秀之 鍋島 篤子 山路 浩三郎 角田 恭治 李 文 林 純 後藤 修郎 岡 徹也 白井 洸 山家 滋 柏木 征三郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本感染症学会
- 雑誌
- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.9, pp.905-911, 1998-09-20 (Released:2011-09-07)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1 1
高齢者における不活化インフルエンザワクチンの連続接種の際の, ワクチン接種回数とワクチン効果との関連について, 血清HI抗体価より検討した.60歳以上の長期入院患者146名 (男性28名, 女性118名, 平均年齢82.4歳) に不活化インフルエンザワクチンを接種した.69名は前年度インフルエンザワクチンの接種を受けており, 77名は前年度未接種者であった.2年連続ワクチン接種者中, 35名が今回1回のみ, 34名が今回2回, ワクチン接種を受けた.接種前, 1回接種後, 2回接種後, 流行後のInfluenza A/H1N1, A/H3N2, 及びBに対する血清HI抗体価を測定した.各インフルエンザウイルスに対するワクチン接種前のHI抗体価は, 2年連続接種者が前年度未接種者より有意に高かった.ワクチン接種後のHI抗体価は, 2年連続接種者で今回2回接種を受けた群が最も高かったが, 3群間に統計学的な有意差は検出されなかった.ワクチン接種後に, HI抗体価の4倍以上の上昇が見られる率は, 2年連続接種者で低かったが, これはワクチン接種前のHI抗体価が高いためと考えられた.ワクチン接種後のHI抗体価128倍以上の割合は, 2年連続接種者で今回2回接種を受けた群が他の群より高かったが, 3群間に統計学的な有意差は認められなかった.2年連続接種者では, 2回目接種により, HI抗体価が128倍未満から128倍以上に上昇した者は認められなかった.以上の成績より, 高齢者では, 不活化インフルエンザワクチンに対する抗体反応は, 前年度接種の有無に係らず良好で, 連続接種の際には, 接種回数1回でも2回接種と同等の予防効果が期待できると考えられた.
- 著者
- 若菜 真実 山﨑 裕子 岩佐 太一朗 部谷 祐紀 白井 智美 本間 和宏 福山 直人 田中 越郎 若菜 宣明
- 出版者
- 日本健康医学会
- 雑誌
- 日本健康医学会雑誌 (ISSN:13430025)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.68-73, 2019
<p>近年,便秘や下痢などの腸のトラブルに対する腸内環境が注目されている。腸内環境を改善するために,日本ではプロバイオティクスとして様々な発酵食品およびプロバイオティクス飲料が日常的に販売されている。特に,「こうじ菌(<i>Aspergillus oryzae</i>)」は,日本で1千年以上前から,酒,味噌,醤油を発酵させるために使用されてきた。「こうじ菌」については食品の抗酸化活性や抗菌性の増強またうま味向上に関する多くの研究があるが,ヒトの腸の改善に関する研究は報告されていない。そこで,こうじ含有食品の摂取がヒトの排便状況と糞便中の細菌数に及ぼす影響について評価をした。被験者は30代から50代3人(男性2名,女性1名)の健康成人とした。被験者には甘酒(1日1本125mL)または生塩こうじ(1日7.5g)を14日間摂取させた。0日目,7日目,14日目,35日目に採便を行い,便中の総菌数,さらに有用菌の代表として<i>Bifidobacterium</i>, 日和見菌の代表として<i>Enterobacteriaceae</i>, 有害菌の代表として<i>Clostridium perfringens</i>のそれぞれの菌数を測定した。また,排便に関するアンケート調査も行った。被験者には排便頻度と主観を記録してもらった。全期間を通して糞便中の総菌数および3種類の菌の細菌数に変動は認められなかった。しかし,こうじ含有食品摂取によって排便回数の増加や便の形状が良くなることが明らかとなった。したがって,こうじ含有食品摂取を日常的に摂取していくことは,安定した腸内環境と便通を保つのに有用である可能性が示唆された。</p>
- 著者
- 白峰 旬
- 出版者
- 十六世紀史論叢刊行会
- 雑誌
- 十六世紀史論叢 (ISSN:21878609)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.36-47, 2018-03