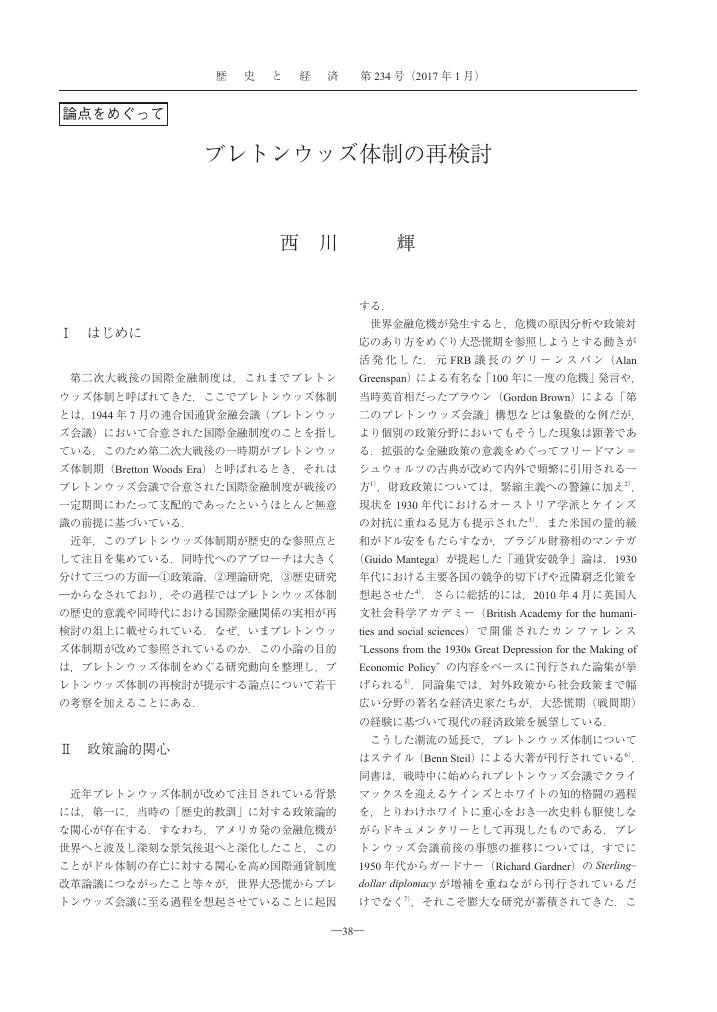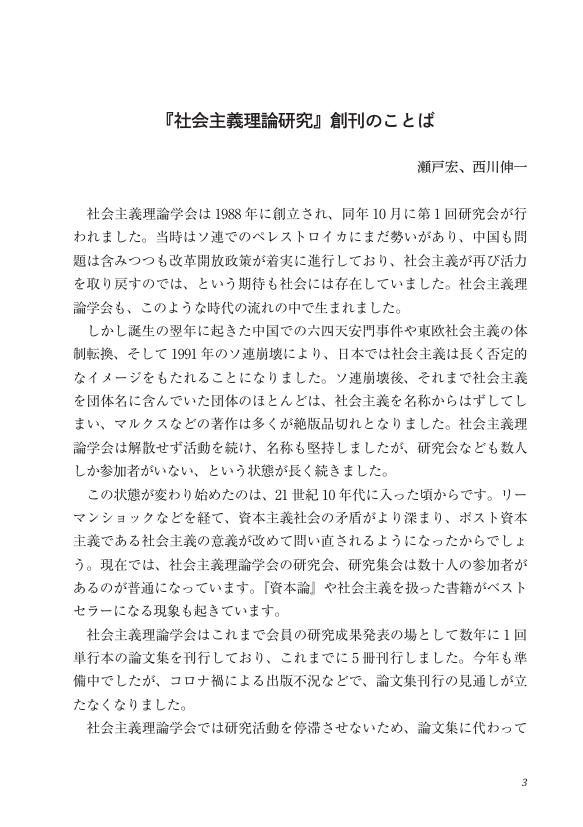1 0 0 0 OA 田中芳男とホヤ―1882年執筆の稿本『保夜考ヲ讀ム』から
- 著者
- 西川 輝昭
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- タクサ:日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.19-28, 2021-08-31 (Released:2021-08-31)
- 参考文献数
- 48
Baron Yoshio Tanaka (1838–1916), a famous historical researcher of natural history based in the “honzo-gaku” (traditional natural history) developed in the Edo Period in Japan, established himself as a talented and energetic higher governmental official in early modern Japan, establishing the National Museum. He also contributed much to the development of modern biological education by the compilation of wallcharts and translations of European and American textbooks into Japanese, and improved understanding of agricultural and fisheries products. He is therefore regarded to have bridged the gap between pre-modern and modern approaches in biology (especially botany), although his influence in the understanding of ascidians has been overlooked. However, a hand-written and previously unknown manuscript on this animal group by Tanaka (dated 1882), translated here into modern Japanese with detailed explanatory notes, included references to dissected museum specimens, evidence of Tanaka’s modern approach, since dissection and museum-deposition of specimens had not been practiced in “honzo-gaku”. The only cited western article in the manuscript, entitled “Cuvier’s molluscs”, was identified as Deshayes’ molluscan volume [completed in 1845 and including good figures of ascidian anatomy] included in the third edition of Cuvier’s “Le Règne Animal”, issued between 1836 and 1849. However, Tanaka made no reference to Lankester’s “urochordate” concept, published in 1877, and left no detailed figures of ascidian anatomy, necessary for modern taxonomy. In fact, the modern taxonomy of Japanese ascidians was begun in 1882 by foreign taxonomists, to be followed soon after by a Japanese researcher, Dr. Asajiro Oka. However, these endeavors did not avail themselves of Tanaka’s museum specimens, which were possibly unavailable even then, due to irregular museum deposition practice. It is clear that the gap between pre-modern and modern practices, was very significant in the case of ascidians.
- 著者
- 隈部 俊宏 柳澤 隆昭 西川 亮 原 純一 岡田 恵子 瀧本 哲也 JCCG(日本小児がん研究グループ)脳腫瘍委員会
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児神経外科学会
- 雑誌
- 小児の脳神経 (ISSN:03878023)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.3, pp.279-296, 2022 (Released:2022-09-23)
- 参考文献数
- 18
JCCG/AMED原班により2009~2013年に治療された99症例の15歳未満DIPGを対象とした後方視的検討を行った.その結果,1)約20%に対して組織診断が行われた,2)照射はほぼ全例で行われた,3)3/4の症例に対してテモゾロミドが使用された,4)再発に対してさまざまな化学療法追加・部分摘出等が行われた,5)生存中央値は11か月であり,照射方法・化学療法併用・化学療法内容による生存期間延長効果は認められなかった.本邦における最多症例のDIPGの治療実態と成績結果が得られた.
1 0 0 0 IR 個人特性としての好奇心の領域とタイプについて : 知的好奇心と対人的好奇心
1 0 0 0 OA アウトバウンド型オープン・イノベーションの促進要因
- 著者
- 金間 大介 西川 浩平
- 出版者
- 特定非営利活動法人 組織学会
- 雑誌
- 組織科学 (ISSN:02869713)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.74-89, 2017-12-20 (Released:2018-03-30)
- 参考文献数
- 68
本稿は,どのような環境にある企業が自社以外の組織に技術を提供しているかを,第2回全国イノベーション調査の結果を用いて計量的に検証した.その結果,イノベーションの収益化のための専有可能性として法的保護の有効性が高い企業ほど,また自社の補完的資産を把握している企業ほど,多様な外部組織へ技術提供していることがわかった.さらに,市場環境の変化が企業の技術提供に影響を及ぼしていることも明らかとなった.
1 0 0 0 OA 全国書房ネットワークの総合的研究─戦時下~占領期における文学と出版メディア─
1940年代に大阪で創業し、戦後の占領期にメジャー出版社に比肩する業務を担った出版社「全国書房」の出版事業における作家と編集者、出版人を中心としたネットワークの全容を解明することを目指し、創業から1970年前後に至るまでの出版書籍の調査、1944~1949年に刊行された文芸雑誌『新文学』の分析、および、創業者である田中秀吉(故人)宅の所蔵資料調査などを行い、終戦前後の過渡的な時代における文学と出版メディアの関係について検討、研究期間終了後に取り組む成果出版のための基礎を構築した。
1 0 0 0 OA 松果体胚細胞腫瘍患者の高次機能
1 0 0 0 OA 5024 今井町民家についての若干の問題点(意匠・歴史)
- 著者
- 関野 克 太田 博太郎 伊藤 鄭爾 稲垣 栄三 大河 直躬 西川 幸治
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会論文報告集 (ISSN:03871185)
- 巻号頁・発行日
- vol.60.2, pp.617-620, 1958-10-05 (Released:2017-08-30)
1 0 0 0 OA 5023 今井町民家の編年(意匠・歴史)
- 著者
- 関野 克 太田 博太郎 伊藤 鄭爾 稲垣 栄三 大河 直躬 西川 幸治
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会論文報告集 (ISSN:03871185)
- 巻号頁・発行日
- vol.60.2, pp.613-616, 1958-10-05 (Released:2017-08-30)
1 0 0 0 OA スコア化による聖隷式嚥下質問紙評価法の検討
- 著者
- 中野 雅徳 藤島 一郎 大熊 るり 吉岡 昌美 中江 弘美 西川 啓介 十川 悠香 富岡 重正 藤澤 健司
- 出版者
- 一般社団法人 日本摂食嚥下リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本摂食嚥下リハビリテーション学会雑誌 (ISSN:13438441)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.3, pp.240-246, 2020-12-31 (Released:2021-04-30)
- 参考文献数
- 17
【目的】聖隷式嚥下質問紙は,摂食嚥下障害のスクリーニング質問紙であり,15 の質問項目に対して重い症状:A,軽い症状:B,症状なし:C の3 つの選択肢がある.「一つでも重い症状A の回答があれば摂食嚥下障害の存在を疑う」という従来の評価法は,高い感度と特異度を有している.本研究では,回答の選択肢をスコア化し評価する方法を新たに考案し,従来の評価法と比較する.また,本法を健常者に適用し,嚥下機能が低下した状態のスクリーニングツール開発のための基礎資料を得ることをあわせて行う.【方法】聖隷式嚥下質問紙開発時に用いた,嚥下障害があるが経口摂取可能な脳血管障害患者50 名,嚥下障害のない脳血管障害患者145 名,健常者170 名を対象に行った調査データを使用した.選択肢を,A:2 点,B:1 点,C:0 点,およびA の選択肢に重みをつけ,A:4 点,B:1 点,C:0 点としてスコア化した場合の合計点数に対して,カットオフ値を段階的に変えそれぞれについて感度,特異度を算出した.ROC 分析により最適カットオフ値を求め,このカットオフ値に対する感度,特異度を従来の方法と比較した.また,健常者170 名のデータについて,年齢階層ごとの合計点数に解析を加えた.【結果】ROC 分析の結果,A:4 点としてスコア化し,8 点をカットオフ値とする評価法が最適であることが示された.本評価法は,感度90.0%,特異度89.8% であり,従来法の感度92.0%,特異度90.1% に匹敵するものであった.健常者における年齢階層別の比較では,75 歳未満と75 歳以上で明確なスコアの差が認められた.【結論】スコア化による聖隷式嚥下質問紙の評価法は,A の回答が一つでもあれば嚥下障害の存在が疑われるという従来の評価法とほぼ同程度の感度,特異度を有していた.一般高齢者では,75 歳以上になるとスコアが有意に高くなることが確認され,嚥下機能が低下した状態を評価するためのスクリーニングツール開発の基礎資料が得られた.
1 0 0 0 OA 人間の上肢力学特性に基づく自動車のシフト特性の設計
- 著者
- 西川 一男 古川 浩二 河手 功 農沢 隆秀 辻 敏夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.816, pp.BMS0247, 2014 (Released:2014-08-25)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
In the study reported here, the operational characteristics of a human-gearshift lever system were experimentally analyzed in consideration of the mechanical properties of the human arm and related effects on muscle activity. The results highlighted three points in particular: (1) It is possible to determine positioning that facilitates operation as well as the operational direction of the gearshift lever based on force manipulability in consideration of human joint-torque characteristics; (2) subjects feel that handling is easier when arm muscle activities in push and pull operations are almost equal during translational lever movement; and (3) the gearshift lever operation speed and the force-stroke characteristics have a very significant effect on whether operation is favorable or poor. Comprehensive consideration of these results is expected to be useful in the design of a human-vehicle gearshift lever system.
1 0 0 0 OA ブレトンウッズ体制の再検討
- 著者
- 西川 輝
- 出版者
- 政治経済学・経済史学会
- 雑誌
- 歴史と経済 (ISSN:13479660)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.38-44, 2017-01-30 (Released:2019-01-30)
- 参考文献数
- 30
1 0 0 0 OA 胃癌両側副腎転移により発症したAddison病の1例
- 著者
- 出口 幸一 西川 和宏 岩瀬 和裕 川田 純司 吉田 洋 野村 昌哉 玉川 浩司 松田 宙 出口 貴司 田中 康博
- 出版者
- 日本外科系連合学会
- 雑誌
- 日本外科系連合学会誌 (ISSN:03857883)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.6, pp.1186-1190, 2013 (Released:2014-12-25)
- 参考文献数
- 18
症例は85歳,男性.2006年に胃癌に対し幽門側胃切除術を施行された.術後補助療法としてUFTを1年間施行した.2009年7月に左副腎転移,傍大動脈リンパ節転移が判明し,化学療法を開始し一旦は腫瘍縮小を認めた.しかし徐々に腫瘍が進行し2011年7月には右副腎転移が出現した.2012年1月に誤嚥性肺炎を発症し入院した.入院後倦怠感悪化,食欲不振,難治性低Na血症,高K血症,好酸球増多症を認めた.当初癌性悪液質による症状を疑ったが,副腎不全も疑われたため,迅速ACTH負荷試験を施行し,Addison病と診断した.hydrocortisonの投与を開始したところ,症状の著明な改善を認めた.癌末期に副腎不全が発症した場合,症状が癌性悪液質によるものと酷似するため鑑別が困難である.両側副腎転移を有する担癌症例では,副腎不全を念頭におき,積極的に内分泌的検索を行うことが重要である.
1 0 0 0 OA 懸賞論文(卒業論文)ふしぎ発見!銭湯の魅力
- 著者
- 西川 遥夏
1 0 0 0 OA 科学的特性マップのデジタル化
- 著者
- 西川 雅史 髙橋 朋一 斎藤 英明
- 出版者
- 日本経済政策学会
- 雑誌
- 経済政策ジャーナル (ISSN:13489232)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.13-22, 2021-04-30 (Released:2021-04-30)
- 参考文献数
- 16
経済産業省は、高レベル放射性廃棄物の処分施設の立地先を選定するために「科学的特性マップ」を公表したが、人口密度などの社会的条件を考慮していない。また、画像データであるため第三者による活用が進みがたい。こうした科学的特性マップの欠落を補完するために、私たちはこれをデジタルデータ(シェープファイル)の形で再現したものを公開し、第三者が科学的特性マップ上で社会的特性を考慮できるようにした。
1 0 0 0 OA ホムンクルス、クローン、そして人工生命 ―生物学が目指すもの―
- 著者
- 西川 伸一
- 出版者
- ゲーテ自然科学の集い
- 雑誌
- モルフォロギア: ゲーテと自然科学 (ISSN:0286133X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.28, pp.2-8, 2006-10-31 (Released:2010-02-26)
1 0 0 0 OA 法・権利の創造と主体化 フーコーとドゥルーズにおける
- 著者
- 西川 耕平
- 出版者
- 日本倫理学会
- 雑誌
- 倫理学年報 (ISSN:24344699)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, pp.205-217, 2020 (Released:2021-05-24)
Dans cet article, nous examinerons la pensée de Foucault sur la loi et le droit et celle de Deleuze, faisant constamment référence au diagramme que celui-ci présente dans son oeuvre sur Foucault. On est encline à souligner, dans les études sur la philosophie française contemporaine, des différences entre ces deux philosophes. Mais, il y a des points communs remarquables dans leurs pensées juridiques, même s’il semble qu’on les ait négligés. Cet article a donc pour but d’éclaircir leur orientation commune dans ce domaine. À cette fin, nous commencerons par mettre en évidence l’interprétation que Deleuze donne de Foucault, et constaterons qu’il est possible de retrouver deux types de loi dans la pensée de celui-ci: une loi stable et une loi instable. Celle-ci, caractérisée comme une réponse à « l’autre », joue un rôle important au moment de la genèse d’une loi ou d’un droit. Puis, nous montrerons que cet aspect de la loi peut se rapporter au thème de « rapport à soi » dont s’occupe Foucault dans ses dernières années. Enfin, nous traiterons de la pensée juridique de Deleuze développée par le terme « jurisprudence », et montrerons qu’elle aussi répond à « l’autre » et s’accompagne du devenir. Nous pourrons extraire de ce qui précède deux points communs entre Deleuze et Foucault: d’abord, tous les deux donnent de l’importance aux processus de fabrication de nouveaux lois et droits à travers la réponse donnée aux cas singuliers, plutôt qu’à travers de simples applications des lois stables; ensuite, ils supposent l’un et l’autre que le sujet n’est pas un sujet tout fait et universel, mais un étant qui se change sans cesse, affecté par le singulier. En bref, le processus de création des lois et droits implique l’éthique de la subjectivation en tant que devenir autre.
1 0 0 0 OA “ある石の記憶”パルスレーザーによるホログラム
- 著者
- 西川 智子 佐藤 甲癸
- 出版者
- 芸術科学会
- 雑誌
- 芸術科学会論文誌 (ISSN:13472267)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.18-22, 2006-03-20 (Released:2008-04-11)
- 参考文献数
- 11
ホログラムの立体像は大変リアルであるために虚像の三次元空間に様々なイメージをふくらませることができる。本論文の主題は私たちの存在の意味をホログラムを用いて表現することです。なぜなら現実の存在をホログラムの虚像を用いて表現できると考えたからです。私たちは、パルスレーザを用いて作製した一連のホログラム作品 “石の思い出” を用いて幸福、輝き、平穏など人の一生を表現することができ、その有効性を明らかにできました。そこで “砂漠の薔薇” と呼ばれる石は我々の存在そのものを意味していています。
1 0 0 0 OA 『社会主義理論研究』創刊のことば
- 著者
- 瀬戸 宏 西川 伸一
- 出版者
- 社会主義理論学会
- 雑誌
- 社会主義理論研究 (ISSN:24367354)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.3-4, 2021 (Released:2021-11-25)
1 0 0 0 OA 研究展望 建築と文学の交錯 文学テクストにおける建築表象をめぐって
- 著者
- 西川 貴子
- 出版者
- 昭和文学会
- 雑誌
- 昭和文学研究 (ISSN:03883884)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, pp.219-221, 2020 (Released:2021-07-01)
- 著者
- 林元 みづき 庭田 祐一郎 伊藤 哲史 植木 進 内田 雄吾 関 洋平 西川 智章 岸本 早江子 神山 和彦 高杉 和弘 近藤 充弘
- 出版者
- 科学技術社会論学会
- 雑誌
- 科学技術社会論研究 (ISSN:13475843)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.119-127, 2020-04-30 (Released:2021-04-30)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1
Patient Centricityとは「患者中心」を意味する概念であり,患者・市民参画(Patient and Public Involvement:PPI),Patient Involvement,Patient Engagementといった言葉と同義語である.近年,製薬企業が患者の意見や要望を直接入手し,患者の実体験を医薬品開発に活かすことの重要性が認識されつつあり,製薬企業での医薬品開発におけるPatient Centricityに基づく活動(本活動)が開始されている.本活動により,患者には「より参加しやすい治験が計画される」,「自分の意見が活かされた医薬品が開発される可能性がある」といったことが期待される.また,製薬企業には医薬品開発に新たな視点と価値が加わり,「より価値の高い医薬品の開発につながること」が期待される.本稿では,日本の製薬企業で実施されている本活動の事例の一部を紹介する.今後,日本の各製薬企業が本活動を推進することに期待したい.