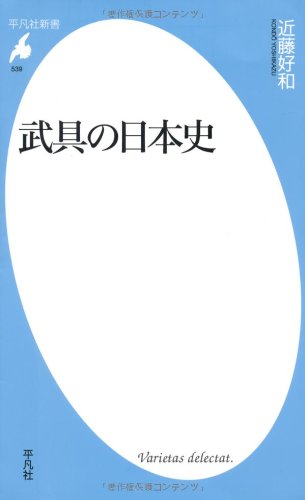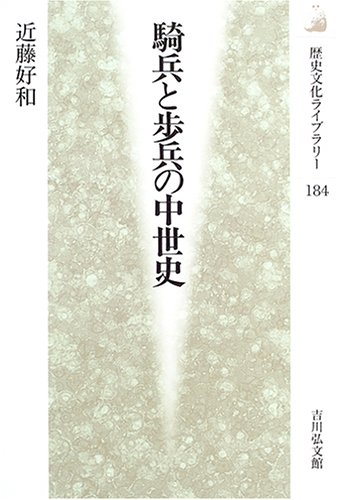1 0 0 0 気管支喘息 3
1 0 0 0 OA 5-O-アシル化キナ酸類の効率的合成によるアジサイの 青色金属錯体色素の化学構造研究
- 著者
- 尾山 公一 山田 智美 伊藤 大輔 渡邉 紀之 関口 由紀子 鈴木 昌子 近藤 忠雄 吉田 久美
- 出版者
- 天然有機化合物討論会実行委員会
- 雑誌
- 天然有機化合物討論会講演要旨集 57 (ISSN:24331856)
- 巻号頁・発行日
- pp.PosterP61, 2015 (Released:2018-10-01)
【緒言】我々は、アジサイの花色変異の現象に興味を持ち研究を行っている。一細胞分析により、アントシアニンのdelphinidin 3-O-glucoside (1)が、助色素(5-O-caffeoylquinic acid (neochlorogenic acid (2))、5-O-p-coumaroylquinic acid (3)、3-O-caffeoylquinic acid (chlorogenic acid (4))の組成比、液胞pH、及びAl3+量の違いによって多彩に赤から紫、青に発色をすることを明らかにした (Figure 1) 1-3。アジサイの青色は、pH 4の条件下、1、2または3及びAl3+を混合すると再現できることがわかった4,5。この青色色素は、水溶液中だけで安定に形成される金属錯体で、ツユクサなどに見いだされた自己組織化超分子金属錯体色素(メタロアントシアニン)とは全く異なる性質を持つ非化学量論量の分子会合錯体である。これまで、結晶化の成功例はなく、1H NMRスペクトルもブロードで複雑なため、構造は今も不明である。本研究では、5-O-アシル化キナ酸類の効率的合成方法を新たに開発した。次に、合成した助色素を用いて青色色素を再構築し、解析可能なNMRスペクトルを得ることに成功した。【5-O-アシル化キナ酸類の効率的合成法の開拓】従来の2と3の合成4-6では、1位のカルボン酸の保護基にメチル基を用い、アシル基のフェノールの保護基にアセチル基を使用しているために、最終ステップの脱保護反応で競争的脱アシル化反応とアシル転移が起こり、収率が著しく低かった。また、5位へのエステル化は酸クロリドを用いていた。そこで、合成経路を見直し、1位のカルボン酸の保護基としてPMB基を持つキナ酸誘導体5を新たに分子設計して、Scheme 1に示すように(–)-キナ酸 (4) から5段階79%で合成した。5の5位アキシアルヒドロキシ基へのアシル化反応は、遊離カルボン酸にTsClとN-メチルイミダゾール (NMI)を加えてアシルアンモニウム中間体を生成させて、そこへアルコールを反応させる田辺法7を検討した。i-Pr2NEtの添加によりアルコールとカルボン酸の求核性が上がり収率が向上した(Scheme 2)。また、アンモニウム中間体の生成と同時にアルコール5が本中間体をトラップすることを目指してNMIを最後に加えた。その結果、収率はさらに向上した(Scheme 2)。この改良法を用いてp-クマル酸やコーヒー酸などの種々の遊離カルボン酸のエステル化反応を行い、72–94%の高収率で6-12を得た (Scheme 3)。得られたアシル体6-11の脱保護反応を検討した(Table 1)。芳香環部分に酸素原子のない6-9では、いずれも高収率(79-87%)で目的のアシル化キナ酸を得た。しかし、フェノール性ヒドロキシ基をMOM保護した10と11では、収率は40%以下と低かった。種々検討した結果、BCl3/C6HMe5を作用させると高収率(69,73%)で脱保護体が得られた 8。これらにより、市販のキナ酸(4)から7段階、通算収率45–60%で種々の5-O-アシル化キナ酸類の合成を達成した9,10。【アジサイ青色金属錯体色素の化学構造】合成した助色素類を用いて、アジサイ萼片の青色再現実験と得られた溶液の可視吸収スペクトル、円二色性、およびNMR分析を行った。これまでの知見により1-5、(View PDFfor the rest of the abstract.)
1 0 0 0 OA 補綴歯科治療病名システムの信頼性と妥当性の検討
- 著者
- 松香 芳三 萩原 芳幸 玉置 勝司 竹内 久裕 藤澤 政紀 小野 高裕 築山 能大 永尾 寛 津賀 一弘 會田 英紀 近藤 尚知 笛木 賢治 塚崎 弘明 石橋 寛二 藤井 重壽 平井 敏博 佐々木 啓一 矢谷 博文 五十嵐 順正 佐藤 裕二 市川 哲雄 松村 英雄 山森 徹雄 窪木 拓男 馬場 一美 古谷野 潔
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.3, pp.281-290, 2013 (Released:2013-11-06)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 2 1
目的:(社)日本補綴歯科学会は病態とその発現機序の把握に基づく適切な補綴歯科治療を国民に提供するために,補綴歯科治療における新たな病名システムを提案した.これは患者に生じている「障害」を病名の基本とし,この障害を引き起こしている「要因」を併記して病名システムとするものであり,「A(要因)によるB(障害)」を病名システムの基本的な表現法としている.本研究の目的は考案した方法に従って決定した補綴歯科治療における病名の信頼性と妥当性を検討することである.方法:模擬患者カルテを作成し,(社)日本補綴歯科学会診療ガイドライン委員会で模範解答としての病名(以下,模範病名)を決定した.その後,合計50 名の評価者(日本補綴歯科学会専門医(以下,補綴歯科専門医)ならびに大学病院研修歯科医(以下,研修医))に診断をしてもらい,評価者間における病名の一致度(信頼性)ならびに(社)日本補綴歯科学会診療ガイドライン委員会による模範病名との一致度(妥当性)を検討した.結果:評価者間の一致度を検討するための算出したKrippendorff’s αは全体では0.378,補綴歯科専門医では0.370,研修医では0.401 であった.Krippendorff’s αは模範病名との一致度の高い上位10 名の評価者(補綴歯科専門医:3 名,研修医:7 名)では0.524,上位2 名の評価者(補綴歯科専門医:1 名,研修医:1 名)では0.648 と上昇した.日常的に頻繁に遭遇する病名に関しては模範病名との一致度が高かったが,日常的に遭遇しない病名は模範病名との一致度は低い状況であった.さらに,模範病名との一致度とアンケート回答時間や診療経験年数の関連性を検討したところ,相関関係はみられなかった.結論:全評価者間の一致度を指標とした本病名システムの信頼性は高くはなかったが,模範病名との一致度の高い評価者間では一致度が高かった.日常的に遭遇する補綴関連病名については模範病名との一致度が高かった.以上から(公社)日本補綴歯科学会の新しい病名システムは臨床上十分な信頼性と妥当性を有することが示唆された.
1 0 0 0 OA レストランサービスの原価企画
- 著者
- 近藤 大輔
- 出版者
- 公益財団法人 メルコ学術振興財団
- 雑誌
- メルコ管理会計研究 (ISSN:18827225)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.35-44, 2017-07-10 (Released:2018-02-22)
- 参考文献数
- 14
近年,原価企画がサービス業でも利用されていることが指摘されている。製造業で生成・発展してきた原価企画が,本当に,サービス業で機能するのであろうか。そこで,本研究ではサービス業としての性質を持つ株式会社ぶどうの木のレストラン事業部を考察した。その結果,レストランサービスにおいても源流管理,職能横断的チーム活動,原価削減方法としてのVE,原価企画のフォローアップが効果的に機能していることが分かった。さらに,製造業と比較して,サービス業では原価企画のフォローアップとコンセプト一貫性のある原価企画活動がより重要になる可能性があることが明らかになった。
1 0 0 0 OA vAS:インターネット環境におけるスケーラブルで柔軟なトラフィック・エンジニアリング機構
- 著者
- 近藤 賢郎 寺岡 文男
- 雑誌
- 研究報告高度交通システムとスマートコミュニティ(ITS) (ISSN:21888965)
- 巻号頁・発行日
- vol.2018-ITS-73, no.39, pp.1-6, 2018-05-17
近年OpenFlow, segment routing,network service header に代表される要素技術をもとに最短経路に基づかない end-to-end の通信路をプログラマブルに構成するトラフィック ・ エンジニアリング (TE) 手法の開発が盛んである.しかし,これらの TE 手法では network service provider (core entity) と application service provider (end entity) 間でのセマンティクスの共有がなされず,core entity は endentity のセマンティクスに基づかない通信路しか形成できない.また end entity による通信路構築が適切かを core entity で検証する機構も存在しない.本稿では,インターネットに代表される Open Network 環境を対象とする,core entity と end entity との間でのセマンティクス共有を前提としたTE手法を提案する.共通のセマンティクス理解する entity 群は closed な overlay network (vAS: virtualized autonomoussystem) に属する.vAS では end entity と core entity の双方のセマンティクスを考慮した end-to-end の通信路が構成され,その通信路に従ってパケットは転送される.vAS 上でのパケット転送は既存の OpenNetwork 環境のパケット転送に failover 可能なので,end-to-end に渡った柔軟な通信路形成とその到達可能性が両立する.
1 0 0 0 OA 上皮バリアの生物学に立脚した吸収促進技術のイノベーション・レギュレーション
- 著者
- 橘 敬祐 近藤 昌夫
- 出版者
- 日本DDS学会
- 雑誌
- Drug Delivery System (ISSN:09135006)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.20-26, 2020-01-25 (Released:2020-04-25)
- 参考文献数
- 63
イツの哲学者ヘーゲルは、事物の螺旋的発展の法則を提唱している。これは、事物の発展はあたかも螺旋階段を昇るように進むという法則であり、技術の進歩に伴い、古く懐かしいものが新たな価値等を伴って再び現れてくることを意味している。さて、単細胞生物から多細胞生物への進化の過程において、生物は生体内外を隔てるバリアとして上皮を獲得してきた。上皮は化学物質、細菌、ウイルス等の生体外異物の生体内侵入を防ぐこと等で恒常性維持に深く関わっている。当然のことながら、上皮は薬の吸収障壁となるため、古くから上皮バリア制御は薬物吸収促進の基本戦略となっている。実際、すでに半世紀以上前には、キレート剤によるヘパリンの粘膜吸収促進の報告がなされ、上皮バリア制御による吸収促進のコンセプトは提起されていた。1982年になると上皮バリアの脂質ミセル説が提唱され、中鎖脂肪酸等を用いた吸収促進技術の開発につながっている。その後、1993年のオクルディンの発見に端を発した上皮バリアの生物学の急速な進展に伴い上皮バリアの分子基盤が詳らかにされ、今まさに吸収促進技術が螺旋的発展を遂げつつある。本稿では、上皮バリアの生物学の発展に伴う吸収促進技術の螺旋的発展を概説し、バイオ医薬のDDS技術としての現状と課題を議論したい。
1 0 0 0 OA ヤブラン亜科5系統の冠水抵抗性の比較
- 著者
- 中村 幸恵 鈴木 貢次郎 近藤 三雄 Yukie Nakamura Suzuki Kojiro Kondo Mitsuo
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.98-104,
ヤブラン亜科の1栽培品種と4種,計5系統を供試植物として冠水抵抗性の違いについて比較した。冠水状態においた供試植物の生存率や葉数,根数,葉長,新芽数等の測定結果から,ジャノヒゲ,またはチャボリュウノヒゲ>ノシラン>オオバジャノヒゲ>ヤブランの順で冠水抵抗性があると判断できた。また冠水抵抗性に劣るヤブランやオオバジャノヒゲを冠水し,その水中に人為的に空気を送ると,枯死する個体が少なくなり,生育している個体の生体重や茎数,葉数の値が空気を送らない時に比べて大になった。これらの結果から冠水抵抗性の系統間差異の原因を考察した。
1 0 0 0 OA 非喫煙大学生における喫煙者やたばこに対し抱く嫌悪意識
- 著者
- 近藤 有紀 葛西 敦子
- 出版者
- 弘前大学教育学部
- 雑誌
- 弘前大学教育学部紀要 (ISSN:04391713)
- 巻号頁・発行日
- vol.123, pp.165-173, 2020-03-31
本研究は,大学生の中でも今までに一回もたばこを吸ったことがないと自己申告した非喫煙者(以下;非喫煙大学生)を対象に質問紙調査を実施し,非喫煙大学生が喫煙者やたばこに対し抱く嫌悪意識に関する要因を明らかにすることを目的とした。370名(男性112名,女性258名)から回答を得た。①370名のうち38名(10.3%)がたばこの『煙』,87名(23.5%)がたばこの『におい』が気になると回答していた。②たばこの『煙』を嫌だと「感じる」者は311名(84.1%),たばこの『におい』を嫌だと「感じる」者は301名(81.4%)であった。③非喫煙大学生が喫煙者やたばこに対し嫌悪意識を抱く要因に関する因子として,第1因子「喫煙者への負のイメージ」,第2因子「人的背景」,第3因子「周囲への影響」,第4因子「においの影響」,第5因子「マナー違反」の5因子が抽出された。本研究で,非喫煙大学生は,たばこの『煙』や『におい』に嫌悪意識を抱いている者が9割以上おり,特にたばこの『におい』に嫌悪意識を抱いていることが明らかとなった。
1 0 0 0 OA 海洋動物プランクトンとバクテリアの関係(総説)
- 著者
- 大塚 攻 平野 勝士 宮川 千裕 近藤 裕介 菅谷 恵美 中井 敏博 高田 健太郎 福島 英登 大場 裕一 三本木 至宏 浅川 学 西川 淳
- 出版者
- 日本プランクトン学会
- 雑誌
- 日本プランクトン学会報 (ISSN:03878961)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.86-100, 2019-08-25 (Released:2019-09-03)
- 参考文献数
- 94
In marine ecosystems, bacterial interactions with zooplankters are highly complex, and much attention has recently been given to these interactions. Bacteria not only play the role of food and symbionts for zooplankters, but also function as decomposers for their carcasses, exuviae and feces. Free-living bacteria are involved as major producers in microbial loops, and form the diet of nanoplanktonic flagellates, ciliates, appendicularians and thaliaceans. Epibiotic and enteric bacteria use zooplankters as refuges to avoid predation and/or as food sources. However, aggregations of epibiotic bacteria or biofilms may function as “a second skin,” sensu Wahl et al. (2012), to modulate hosts metabolism and behaviors. Because they contain rich nutrients, low pH and low oxygen, copepod guts provide a unique environment for bacteria in which anaerobes can survive. Bacterial communities on copepods vary seasonally and among species, depending on the physiology of the host. The conveyor-belt hypothesis implies that bacteria vertically, and presumably horizontally, hitchhike in different water masses in accordance with the migrations of zooplankters. Bioluminescent bacteria are likely used as biomarkers of detrital foods for some planktonic copepods belonging to the Bradfordian families and as obligate symbionts for bioluminescent ichthyoplankters. Tetrodotoxin-producing bacteria are associated with chaetognaths that may use toxins to capture prey animals. Colonial cyanobacteria provide substrata for miraciid harpacticoid copepods. Hyrdomedusae play a role as vectors of pathogenic bacteria, causing lesions in farmed fish. Modern genetic analysis is a powerful tool that will be the first step in revealing the physiological and functional interactions between bacteria and zooplankton.
1 0 0 0 OA 巨大囊胞性胃GISTの1例:本邦報告17例の検討
- 著者
- 矢野 佳子 近藤 三隆 甲村 稔 武鹿 良規 加藤 俊男
- 出版者
- 日本外科系連合学会
- 雑誌
- 日本外科系連合学会誌 (ISSN:03857883)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.5, pp.990-997, 2013 (Released:2014-10-31)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 1
症例は57歳女性.腹痛,背部痛を主訴に近医受診し,超音波検査で巨大腹部腫瘤を指摘され,当院に紹介された.腹部CTでは肝,膵,胃を圧排する23cm大の巨大な囊胞性腫瘤で,3D-CT angiographyでは左胃動脈,右胃大網動脈が腫瘍の栄養血管で,胃GISTを疑い開腹した.腫瘍は局所切除困難にて,胃全摘術を選択した.腫瘍径は23×20×12cm,重量は2,800g,内部は壊死物質と血液で満たされていた.免疫染色でc-kitとCD34が陽性で,胃GISTと診断した.術後補助化学療法を施行せず3年2カ月無再発生存中である.遺伝子解析にてエクソン11の遠位領域の挿入型変異で,比較的予後良好な稀な変異の型と考えられた.遺伝子解析は,囊胞化し巨大化した胃GISTの予後を決定する独立した危険因子になりえ,治療方針や予後の予測に重要と考えられた.本邦報告17例を集計し,文献的考察を加えて報告する.
1 0 0 0 OA 冬眠研究が拓く新たな生物医学領域
- 著者
- 近藤 宣昭
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.127, no.2, pp.97-102, 2006 (Released:2006-04-01)
- 参考文献数
- 33
哺乳類の冬眠動物が冬眠時期に数℃という極度の低体温を生き抜くことは良く知られている.さらに,細菌や発ガン物質などにも抵抗性を持ち,脳や心臓では低温や低酸素,低グルコースにも耐性を示すとの興味深い報告もなされている.このことから,冬眠現象には種々の有害要因や因子から生体を保護する機構が関与しているとの指摘がなされ,最近,生物医学分野での関心が高まりつつある.特に,冬眠発現に関わる体内因子には古くから強い関心が寄せられ探索されてきたが成功せず,近年その存在も疑問視されてきた.これには,冬眠が複雑な生体機能の統合による現象であることや,その発現が1年の長い周期性を持つこと,体温低下により生体反応が著しく抑制されることなど,実験の障害となる深刻な問題が関わっていた.その様な状況下で,我々は1980年代初期に始めた心臓研究を切っ掛けに,冬眠にカップルする新たな因子をシマリスの血中から発見した.冬眠特異的タンパク質(HP)と命名した複合体は,冬眠時期を決定する年周リズムにより制御され,血中から脳内へと輸送されて冬眠制御に深く関わることが明らかになってきた.ここでは,冬眠研究の現状や問題点を含めて,我々が見出したHP複合体が初めての冬眠ホルモンとして同定されるまでの経緯を概説し,医薬分野での新たな応用を秘めた冬眠現象について述べる.
- 著者
- 近藤 和敬
- 出版者
- 鹿児島大学
- 雑誌
- 鹿児島大学法文学部紀要人文学科論集 = Cultural science reports of Kagoshima University (ISSN:03886905)
- 巻号頁・発行日
- no.86, pp.29-38, 2019-03-13
【研究目的】発達障害児および定型発達児における, 新版K式発達検査2001(新K式)の発達指数(DQ)とWISC-Ⅳの知能指数(IQ)の関連を明らかにすることを目的とした。【研究方法】愛媛大学医学部附属病院子どものこころセンターおよび小児科, 精神科を受診した5~10歳の患者のうち, DSM-5の診断基準を用いて自閉スペクトラム症(ASD)と診断され, 本研究への参加同意が得られた9名(男児:女児=8:1, 平均月齢99.7±21.3ヶ月)をASD群とした。うち5名は注意欠如・多動症の併存があった。定型発達群は通常学級に通う児童6名(男児:女児=3:3, 平均月齢86.2±16.7ヶ月)とした。両群に新K式とWISC-Ⅳを1ヶ月以内に実施し, 各指数の比較検討を行った。比較には, 全検査領域(全領域DQと全検査FSIQ), 言語性領域(言語・社会DQと言語理解, ワーキングメモリー), 非言語性領域(認知・適応DQと知覚推理, 処理速度)の3領域を用いた。統計にはSpearmanの順位相関係数を用い, 有意水準はBonferroniの補正を行った上でp<.002とした。【研究結果】① ASD群内の新K式とWISC-Ⅳの比較ASD群内の比較では, 言語・社会DQと言語理解に強い相関を認めた。ASD群9名のうち7名が言語・社会DQ>言語理解であった。他の指標においては相関を認めなかった。② 定型発達群内の新K式とWISC-Ⅳの比較定型発達群内の比較では, いずれの指標においても相関を認めなかった。【考察】ASD児においては, 言語発達面においてのみ新K式とWISC-Ⅳに相関が認められたが, 新K式DQがWISC-ⅣIQよりも高く算出されやすいことが推測された。新K式とWISC-Ⅳは異なる背景を持つ検査であり, 縦断的な評価には慎重を期す必要があることが示唆された。今後も症例数を増やし, 更に検討する予定である。
1 0 0 0 画像認識を用いた看板広告の検出に適した状況および媒体の調査
- 著者
- 本木 悠介 中山 誠 近藤 俊輔 石川 えり 神野 さくら 中澤 仁
- 雑誌
- 研究報告ユビキタスコンピューティングシステム(UBI) (ISSN:21888698)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020-UBI-66, no.3, pp.1-8, 2020-05-18
看板やデジタルサイネージなど,公共空間に設置される看板広告の内容を理解するためには看板広告内に含まれる物体情報や文字情報を基にする必要がある.しかし,看板広告を含む一般的な街中の風景を映した画像には,広告部以外の文字や物体の情報が多く含まれており,これらの情報は広告内からの情報を抽出するにおいて必要のない情報となる.本研究は,画像内から看板広告のみを対象として物体検出する.その際により優れた物体検出モデルを作成するために状況ごとや媒体ごとに物体検出に適した看板広告を調査することを目的とする.
1 0 0 0 IR 1870-80年代のイタリア実証主義とその周辺のスピノザ
- 著者
- 近藤 和敬
- 出版者
- 鹿児島大学
- 雑誌
- 鹿児島大学法文学部紀要人文学科論集 = Cultural science reports of Kagoshima University (ISSN:03886905)
- 巻号頁・発行日
- no.86, pp.49-56, 2019-03-13
1 0 0 0 OA 「男女共同参画社会」をめぐる一考察 : 「第三次男女共同参画基本計画」策定の年にあたって
- 著者
- 近藤 弘
- 雑誌
- 大衆文化 = Popular culture
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.37-45, 2010-09-30