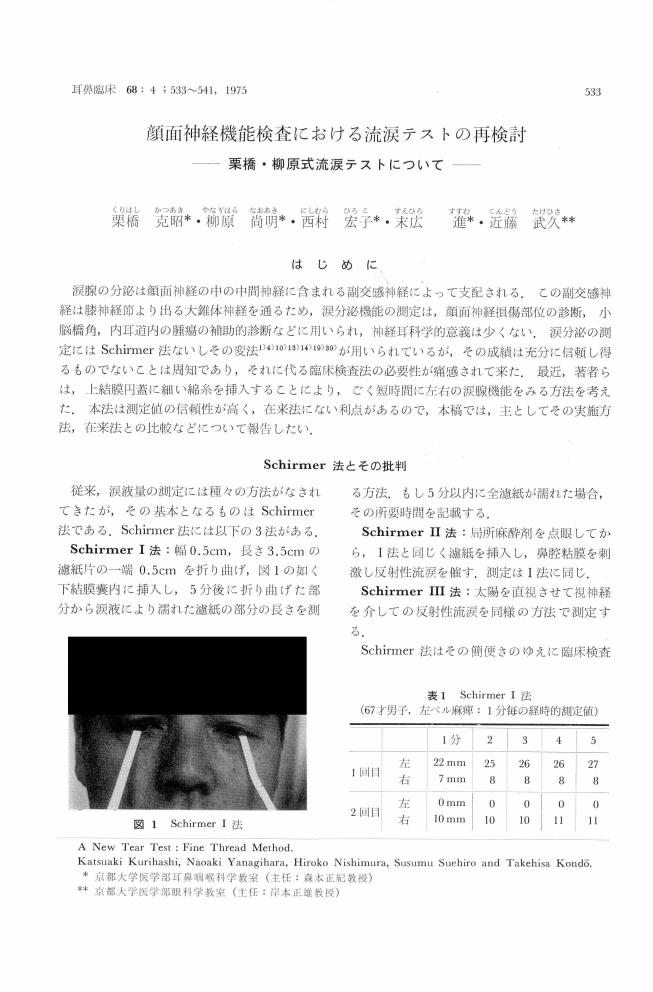1 0 0 0 OA 楊貴妃伝説で村おこし
- 著者
- 近藤 乃梨子
- 出版者
- 一般社団法人 集団力学研究所
- 雑誌
- 集団力学 (ISSN:21872872)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.196, 2014-12-28 (Released:2014-03-10)
- 参考文献数
- 11
本稿は、日本海に突き出す本州最西北端に位置する過疎の半島で始まった、ある小さなグループによる村おこしの取組みの記録である。2010-2013 年初夏の黎明期から萌芽期にあたる様子を書き記した。 山口県長門市油谷に位置する向津具半島は、過疎高齢化の進行著しい地域である。65 歳以上の高齢者が集落人口の半数を超える限界集落の存在も珍しくない。2007 年に家業である寺院経営を継承するためにU ターンした一人の青年、田立氏の呼びかけで始まった村おこしの取組みは、災いを焼き尽くすといわれる「柴燈護摩」と、かつてこの地に楊貴妃が難を逃れて漂着したと語り継がれる「楊貴妃伝説」とを掛け合わせて生み出された楊貴妃「炎の祭典」と呼ばれる祭りである。衰退していく故郷を目前に、地域活性化の定義も定まっておらず、何をすればよいのかもわからない。けれども、このままではこの地域はダメになる。そのような思いから、目標を定め、行動に移していく。いかにして、無から有が生み出され、広がっていったのかを、本稿は記している。 しかし、順調なことばかりではない。むしろ困難なことの方が多いように思われる。田立氏が帰郷した当初、荒れ果てた行政施設「楊貴妃の里」を村おこしに活用したいと役場に相談した時には、適切な対応がなされないばかりではなく、宗教的活動には使用させられないと、門前払い同様の扱いであった。資金獲得のために助成事業に申請すれば、助成元の財団からも、宗教団体ではないかと調べられたり、詳細すぎるほどの説明を求められたりした。楊貴妃つながりで中国の留学生や領事館との交流が芽生えたかと思えば、祭りに私服警官が何人も配備されるほどの厳戒態勢で臨まねばならないこともあった。取組みを「二尊院の祭り」と言われ、地域の祭りとしての協力を仰ぐことが難しい時期も続いた。 幸いにも運営ボランティアは集まったが、遊びの延長のような状態であったため、打ち合わせはバーベキュー方式や「決めない」会議になった。「欣ちゃんがやるから、てごする二尊院の祭り」を脱却して「みんながしたいからやる向津具の祭り」にいかにして変化を遂げられるのか。この問題に直面していた時、新たにボランティアに参加した、移住してきたばかりの若者、松本氏から疑問の声が上がった。なぜ会議で物事を決めないのか----。 この問題提起をきっかけに、膠着した動きに新たな風が吹いた。本稿では、村おこしの取組みの初期段階から、今後の展開に影響を与えうる重大な局面に至るまでを記録した。
1 0 0 0 OA セラミック原料解説集 ア
1 0 0 0 OA 文検修身教育法制経済問題解答
- 著者
- 稲毛金七, 近藤新一 著
- 出版者
- 内外教育評論社
- 巻号頁・発行日
- 1913
1 0 0 0 OA スギ花粉症に対するアイピーディ®の効果
- 著者
- 水田 啓介 伊藤 八次 西田 基 秋田 茂樹 加藤 雅也 小塩 勝博 海田 健宏 古田 充哉 宮田 英雄 柳田 正巳 柴田 康成 横山 壽一 松原 茂規 小泉 光 森 芳郎 大野 通敏 近藤 由香 藤宮 大 山田 匡彦 渡辺 英彦 加藤 洋治
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.12, pp.1399-1407, 1997-12-01 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 14
IPD® (supratast tosilate) was investigated for its prophylactic efficacy and therapeutic efficacy in the treatment of cedar pollinosis during the 1996 cedar pollen season. The subjects investigated were patients at the Gifu University School of Medicine and its affiliated hospitals, who had a history of cedar pollinosis. The patients were classified into two treatment groups: the prophylaxis group (70 patients), in whom IPD® administration began before the start of cedar pollen dispersion, and the treatment group (49 patients), who underwent IPD® treatment only after cedar pollen dispersion had begun and symptoms of pollinosis had manifested.Results were as follows: (1) The nasal symptoms (sneezing, runny nose, nasal congestion) were milder in the prophylaxis group than in the treatment group throughout the cedar pollen season, with the difference being significant during the season's first 2 weeks. (2) In the prophylaxis group, IPD®'s inhibitory effect was rated as excellent in 18.6% of the patients, good in 45.7% and fair in 20.0%. In the treatment group, the improvement in the symptoms was rated as disappearance in 4.2%, excellent in 20.8% and good in 43.8%. (3) When symptom inhibition in the prophylaxis group was investigated as a function of the duration of IPD® administration prior to the start of pollen dispersion, the good + excellent inhibition rate was 57.7% in the subpopulation pretreated for <2 weeks (26 cases), 64.9% with 2 to <4 weeks' pretreatment (37 cases) and 85.7% with 4 to <6 weeks' pretreatment (7 cases). Thus, IPD®'s prophylactic inhibitory rate increased with the length of the pretreatment period. (4) In the prophylaxis groups, the CAP-RAST value was significantly reduced at the time of peak pollen level and at the end of the pollen season compared with the value before IPD® administration.
1 0 0 0 動物は自然で、人間は社会か?:存在論からのアプローチ
- 著者
- 近藤 祉秋
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, pp.69, 2010
現在、文化人類学と関係領域に属する一部の研究者の間で、自然と社会という二元論が批判され始めるようになって久しい。しかし、動物と人間の関係を考える際に、このような二元論に基づかない研究をいかに進めるかについては、コンセンサスがとれていないのが現状である。本発表では、「存在論」概念を利用した先行研究をもとに、いかにして自然と社会の二元論に基づかないような動物-人間関係の研究が可能であるか、検討したい。
1 0 0 0 IR 森林浴の歴史について
- 著者
- 小林 功 近藤 照彦 武田 淳史 Teruhiko Kondou 武田 淳史 Takeda Atsushi
- 出版者
- 群馬パース大学
- 雑誌
- 群馬パース大学紀要 (ISSN:18802923)
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.57-62, 2013-03
林野庁長官、秋山氏は1982年、最初に"森林浴"を提唱し、森林療法の概念を確立した。"森林の中には殺菌力を持つ独特の方向が存在し、森の中にいることが健康な体をつくる"とする、この構想の下につくられた林野庁のオリジナルの概念であった。それは健康な体をつくるために、国有林や他の自然林を利用して、心身ともに鍛えるためにそれらを利用することから始まる。国有林と自然林での生体反応を楽しみながら。健康な身体の状態を取り戻すためには、森林浴でのハイキングにより、健全な心身の健康状態を取り戻す必要がある。ところで、我々を含む人間、日本国民が、人為的に古代からの自然環境の下で現代文明、文化を発展させてきた。人間は約500万年前の人類の誕生から、その長い歴史の中で人間と自然との関係について考えるとき、人類は現代の都市文明の中で生きていると言える。人間は、自然界に適応しながら、サルから進化した人間にとってこのことは、長い歴史から見れば、ごく最近の出来事であるが、それまでは、森林の中で、長い時間を共存してきた偉大な歴史があり、この中で、人類は進化してきた。加えて、我々日本人は欧米人とは異なる親密な自然観のもとに生活をしている。この点からも、現代人においても、私たちの周囲の自然環境が密接に温泉周辺の森林生活環境に快適性を認めている。日本は森林の土地面積が全体の75%を占め、世界有数の森林国の一つである。この数値は、アマゾン流域の無限のジャングルを持つブラジルと同一である。一方、中国、イギリスに至っては、10%前後の少ない森林の土地面積となっている。日本は、亜寒帯から亜熱帯まで、北海道から沖縄まで細長い気候分布を持つ中で人々が生活している特色を持っているのである。
1 0 0 0 OA 顔面神経機能検査における流涙テストの再検討 ―栗橋・柳原式流涙テストについて―
- 著者
- 大曽 基宣 津下 一代 近藤 尚己 田淵 貴大 相田 潤 横山 徹爾 遠又 靖丈 辻 一郎
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.15-25, 2020-01-15 (Released:2020-02-04)
- 参考文献数
- 33
目的 健康日本21(第二次)の目標を達成するため,各自治体は健康課題を適切に評価し,保健事業の改善につなげることを求められている。本研究は,健康日本21(第二次)で重視されるポピュレーションアプローチに着目して,市町村における健康増進事業の取組状況,保健事業の企画立案・実施・評価の現状および課題について明らかにし,さらなる推進に向けたあり方を検討することを目的とした。方法 市町村の健康増進担当課(衛生部門)が担当する健康増進・保健事業について書面調査を実施した。健康増進事業について類型別,分野別に実施の有無を尋ねた.重点的に取り組んでいる保健事業における企画立案・実施・評価のプロセスについて自記式調査票に回答してもらい,さらに参考資料やホームページの閲覧などにより情報を収集した。6府県(宮城県,埼玉県,静岡県,愛知県,大阪府,和歌山県)の全260市町村に調査票を配布,238市町村(回収率91.5%)から回答を得た。結果 市町村の健康増進事業は,栄養・食生活,身体活動,歯・口腔,生活習慣病予防,健診受診率向上などの事業に取り組む市町村の割合が高かった。その中で重点的に取り組んでいる保健事業として一般住民を対象とした啓発型事業を挙げた市町村は85.2%,うちインセンティブを考慮した事業は27.4%,保健指導・教室型事業は14.8%であった。全体では,事業計画時に活用した資料として「すでに実施している他市町村の資料」をあげる市町村の割合が52.1%と半数を占め,インセンティブを考慮した事業においては,89.1%であった。事業計画時に健康格差を意識したと回答した市町村の割合は約7割であったが,経済状況,生活環境,職業の種別における格差については約9割の市町村が考慮していないと回答した。事業評価として参加者数を評価指標にあげた市町村は87.3%であったのに対し,カバー率,健康状態の前後評価は約3割にとどまった。結論 市町村における健康増進・保健事業は,全自治体において活発に取り組まれているものの,PDCAサイクルの観点からは改善の余地があると考えられた。国・都道府県は,先進事例の紹介,事業の根拠や実行可能な運営プロセス,評価指標の提示など,PDCAサイクルを実践するための支援を行うことが期待される。
1 0 0 0 遺伝相談の実態
- 著者
- 藤木 典生 中井 哲郎 金沢 弘 渡辺 稔夫 柿坂 紀武 和田 泰三 岡田 喜篤 津田 克也 細川 計明 山本 学 阿部 達生 近藤 元治 斉藤 隆治 渋谷 幸雄
- 出版者
- 日本先天異常学会
- 雑誌
- 日本先天異常学会会報 (ISSN:00372285)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.101-112, 1972
最近10年間に先天異常ことに心身障害児に対する一般の関心が大いに高まってきて、染色体分析や生化学的な代謝異常のスクリーニングの改善によって、早期診断、保因者の検索、適切た治療が進められてきた。こうした染色体異常や代謝異常でたくても、一般の人々が家系の中に発生した先天異常が遺伝性のものであるか、従って結婚や出産にあたってその再発の危険率などについて、しばしば尋ねられることが多い。我カは既に過去10年間にわたって遺伝相談を行ってきたが、今回これら二機関のデーターについて集計した結果について報告する。京都では、研究室で染色体分析や生化学的なスクリーニングことにアミノ酸分析を行っているためもあって、精薄が最も多く、近親婚の可否、精神病の遺伝性、先天性聾唖の再発率、兎唇、その他遺伝性疾患の遺伝的予後だとが主なものである。実施にあたっては、予約来院した相談者は人類遺候学の専門の知識をもったその日の担当医によって家族歴、既往歴など約2時間にわたる詳細な問診と診察の後に、その遺伝的予後についての資料が説明され、パンチカードに記入ファイルされるが、夫々臨床各科の専門医の診察の必要な場合には、その科の相談医の日が指定されて、専門的な診療指示が与えられる。愛知では、昨年末までの8ケ月間の一般外来忠児約900名について集計分類してみると、精薄が31.5%を占め、次いで脳性まひ、てんかん、自閉症、タウソ症候群、先天性奇形を含む新生児疾患、小頭症、情緒障害児、水頭症、脊椎異常、フェニールケトン尿症、脳形成異常、その他となっており、また、これらの心身障害児の合併症として骨折その他の外傷、上気道感染、胃腸障害が約30%に認められた。臨床診断にあたっては、臨床各科の医師と、理療士、心理判定士、ケースワーカーなどのパラメディカルスタッフからなる綜合診断チームが新来愚老の診察にあたって、綜合的な診断と専門的な指示が与えられるように考慮されている。心身障害児の成因分析をパイロット・スタディーとして試みたが、大半の症舳こ妊娠分娩或いは新生児期に何等かの異常を認めた。このことは、このような不幸な子供を生まないようにするためには、妊娠分娩時の母子の健康管理が遺伝の問題と共にいかに大切であるかを示すものである。今后、この方面の基礎的研究が各機関で進められると同時に、患者・保因老の早期発見、結婚出産に対する適切な指導を行うために、各地にこのような心身障害児のためのセンターが作られるように切望すると同時に、人類遺缶学が基礎医学のみでなく、臨床医学の一部としても、卒後研修の中にとり入れられることを切望する。
1 0 0 0 OA 冠動脈疾患と社会経済的要因 —メカニズムと予防の視点から—
- 著者
- 坪井 宏仁 近藤 克則 金子 宏 山本 纊子
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.1-7, 2011 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 46
心疾患は、本邦では悪性新生物に次ぐ死因の第2位を占め、その多くが「冠動脈疾患(coronary heart disease, CHD)」である。CHDのリスクファクターとして、高血圧・高脂血症・糖尿病など生活習慣に基づくものが一般に知られているが、心理的・社会的・経済的因子も無視できない。多くの欧米諸国では長年にわたり心疾患が死因の第1位であるため、その原因と予防に関する研究も多く、CHDと心理的社会的因子や社会経済的因子に関する研究結果が多く得られている。わが国でもライフスタイルの変化により動脈硬化病変がさらに増加し、CHD罹患率やそれによる死亡率の上昇することが予測される。その予防において、個人の生活習慣以外にCHDの重要なリスクファクターである社会経済的要因を把握することも重要であろう。わが国は、高度成長時代を経て平等と言われる社会を築いてきたが、1990年代後半以降は個人間の社会経済的格差が広がっている。その変化の長短は視点によって異なるところであろうが、社会経済的格差が健康に影響を及ぼすのであれば、格差の変革が疾病予防にもつながるはずである。そこで本稿では、CHDと社会経済的状況(socioeconomic status, SES)の関係について、まず両者の関係を述べ、次に両者をつなぐメカニズムを主に心理社会的側面から触れ、最後にCHD予防の可能性を社会的側面から考察した。CHDは、冠動脈壁に経年的に形成される内膜の肥厚病変とその破裂により発生し、原因は酸化・炎症や交感神経系の亢進などである。一方、SESは収入・教育歴・職業(職の有無、職場での立場も含む)などから成り、さまざまな経路でCHDに影響すると考えられる。健康行動はSESによって差があり、高SES層ほど健康によい行動を取る傾向にある。その差が、健康増進資源・医療へのアクセスの違いにつながり、CHDの発症および予後に影響する。次に、心理社会的経路であるが、この経路では、心理的・社会的特性の差異が自律神経・内分泌・免疫系を介してCHDの成因に影響する。低SES層には、慢性ストレスやライフイベントが多く、抑うつ傾向・怒り・攻撃性・社会的孤立などが認められる一方、高SES層ではコントロール感や自己実現感が高い。このような差違が、視床下部-下垂体-副腎皮質(hypothalamic-pituitary-adrenal, HPA)系または交感神経-副腎髄質(sympathetic-adrenal-medullar, SAM)系を介し、炎症・酸化・血糖の上昇・交感神経系の亢進に影響し、長年の間にCHDイベントのリスクが高まる。また、両親および幼少期のSESが、HPA系およびSAM系の反応を脆弱にしたり、成人後の行動的・心理社会的リスクファクター(喫煙・運動不足・攻撃性・職場での緊張・不健康な心理状態など)に影響を与え、CHDに影響を及ぼす可能性も示唆されている。さて、CHDの予防は、生活習慣予防として特定健康診査・特定保健指導により個人および職場レベルで2008年より行われている。しかしSESとCHDの関連性を考慮すると、社会レベルでの予防策も必要であろう。WHOは、健康を決定する社会的要因として「社会経済環境」「物理環境」「個人の特性と行動」を挙げている。このうち、社会経済環境を整備することがCHD予防につがなる可能性を示した。教育による介入、社会保障制度の整備、人生の節目でのサポートなどが有効であろうことが海外の研究で示されている。SESを改善しCHDを予防する戦略には、エビデンスに基づいた社会疫学的研究が必要であろう。
1 0 0 0 OA 黄色い十字路 : 『地下室の手記』のペテルブルグ
- 著者
- 近藤 昌夫
- 出版者
- 日本スラヴ人文学会
- 雑誌
- スラヴィアーナ = Slaviana
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.112-130, 2011-03-31
1 0 0 0 OA グルコン酸カルシウム摂取による成人女性の便通および腸内菌叢に及ぼす影響
- 著者
- 浅野 敏彦 湯浅 一博 近藤 亮子 伊勢 直躬 竹縄 誠之 飯野 久和
- 出版者
- 公益財団法人 腸内細菌学会
- 雑誌
- 腸内細菌学雑誌 (ISSN:13430882)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.1-9, 1997 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 2
便秘傾向の成人女性を対象にしてグルコン酸カルシウム (GCA) の便性および菌叢に及ぼす影響について検討した.GCA摂取期間はGCAを含有するオレンジジュースを飲用し, 対照期間にはGCAを含有しない同じ組成のジュースを飲用させた.最初の試験として, GCAを1日6.0g (グルコン酸の重量として) 摂取した場合の糞便内菌叢, 有機酸および腐敗物質の分析を9名で, 排便に関するアンケート調査を107名で実施した.その結果, GCA摂取期間中のBifidobacteriumの菌数および排便回数は有意に増加したが, 水分含量, pH, 有機酸, 腐敗物質では顕著な変化は見られなかった.次に最小有効摂取量を求めるため, 糞便内菌叢については1日の摂取量を1.5g, 2.0g, 3.0gの順に設定して15名で, 排便に関するアンケート調査は1.5gおよび3.0gの順に摂取する群と, 2.0gおよび4.0gの順に摂取する群の各37名の2群に分けて実施した.その結果, 2.0g摂取以上でBifidobacteriumの菌数の有意な増加が見られ, 1.5g以上の摂取で排便回数は有意に増加し, 便の形状, 色でも一部で有意差が見られた.
- 著者
- 大高 恵莉 大高 洋平 森田 光生 横山 明正 近藤 隆春 里宇 明元
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.10, pp.673-681, 2014 (Released:2014-11-12)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 2 8
目的:動的バランス機能の評価法であるMini-Balance Evaluation Systems Test(Mini-BESTest)の日本語版を作成し,その妥当性を検証した.方法:Guilleminらのガイドラインに準じ日本語版Mini-BESTestを作成した.バランス障害群20 名(平均年齢65.4±18.7 歳)及び健常群7 名(平均年齢69±5.9 歳)に日本語版Mini-BESTest,Berg Balance Scale(BBS),国際版転倒関連自己効力感尺度(FES-I),Activities-specific Balance Confidence Scale(ABC Scale)を実施し,Spearmanの順位相関係数を求めた.結果:日本語版Mini-BESTestの平均施行時間は20.0 分で,BBS(r=0.82,p<0.01),FES-I(r=-0.72,p<0.01),ABC Scale(r=0.80,p<0.01)と有意な相関を認めた.分布の非対称性を示す指標である歪度(skewness)はそれぞれBBS -1.3,日本語版Mini-BESTest -0.47であった.結論:日本語版Mini-BESTestは既存のバランス評価法との併存的妥当性を示し,かつBBSのような天井効果を認めない点で優れていると考えられた.
1 0 0 0 OA 映画観客の読書実践: 1920年代日本における映画館プログラムと「観ること」
- 著者
- 近藤 和都
- 出版者
- 日本マス・コミュニケーション学会
- 雑誌
- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, pp.137-155, 2015-07-31 (Released:2017-10-06)
- 参考文献数
- 28
In traditional research on film reception, the cinema experience has been defined by the time period and the space in which audiences experienced the film. However, audiences also experience the cinema before and after going to the movies through the media, such as through film magazines, trailers, posters, and so on. Understanding how the film is received by audiences, researchers should consider other forms of media surrounding the film-going experience. From this perspective, this paper focuses on brochures that were published by almost all of the prewar movie theaters and analyzes the reading practices of audiences. We first compare exhibition practices by movie theaters with those by opera theaters, and argue that movie theater brochures were formed out of Western modern theater publications. The results show that prewar film exhibitors struggled to contextualize the movie into traditional theater exhibitions because cinemas were considered to be of a lower social standing than prior theater exhibitions. After exploring the origin of brochures, we focus on the contributors' column in which audiences expressed their opinions and differentiated themselves from each other to elevate their status. These contributions were regarded as a kind of literature and audiences usually read them before and after watching films. Some audiences were attracted to brochures and collected them. In particular, brochures published by movie theaters in Tokyo gained popularity. Because of the distribution system, a considerable number of films were only shown around the Kanto region. Instead of receiving original text, rural audiences experienced films vicariously through reading the brochures. Through the analyses above, we conclude that the way of watching films during 1920s in Japan was related not only to the film's text but also other practices such as writing and reading and audiences experienced something beyond the screen.
1 0 0 0 OA リハビリテーション病院の新人理学療法士に対する転倒予防教育プログラム
- 著者
- 井上 靖悟 大高 洋平 小田 ちひろ 後藤 悠人 守屋 耕平 工藤 大輔 近藤 国嗣 松浦 大輔
- 出版者
- 日本転倒予防学会
- 雑誌
- 日本転倒予防学会誌 (ISSN:21885702)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.3, pp.47-54, 2017-03-10 (Released:2017-09-25)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
【目的】本研究の目的は,新人理学療法士に対する転倒予防の新たな教育プログラムが,リハビリテーション病院の理学療法中の転倒を減少させるのかについて検討することである。【方法】2011年4月から2016年3月の5年間に理学療法中に発生した転倒事例について後方視的に調査を行った。2014年4月より新しい理学療法士の新人教育プログラムを導入し,その前後の転倒発生の変化について調査した。新しく導入したプログラムは,理学療法中の過去のインシデントを基に,各動作における環境設定や介助方法などリスク管理に必要な注意点を細分化したリストを活用した実践型プログラムである。指導者はリストの各項目について説明を加えながら実際の動作を見せることで新人の指導を行い,新人は指導者の行う場面の見学,そして模倣を繰り返した。また,指導者は随時実施内容の修正やフィードバックを与え,新人の技術向上を図った。経験段階をすべての項目についてチェックし,最終的にすべての技術を1人で実践できることを目標とした。この教育研修プログラムを,新人教育期間である4月から6月の3か月間にわたり理学療法科全体で実施した。 年間転倒件数および理学療法士1人あたりの年間転倒発生件数,転倒時動作の種類,転倒時動作の自立度について,新しい教育プログラムを導入した前後で比較した。【結果】新人理学療法士の数は,平均±標準偏差にて,教育プログラム導入前10.0±1.7名,導入後9.5±2.1名と大きな変化を認めなかった。新人理学療法士の平均転倒件数は,導入前は10.7±2.5件,導入後は5.0±1.4件と半減し,理学療法士1人あたりの平均年間転倒発生件数も,導入前1.1±0.1件,導入後0.5±0.5件と半減した。転倒時動作の種類は歩行が一番多かったが,教育プログラム導入後は,そのうち介助歩行の患者の転倒が減少する傾向を示した。【結論】新人理学療法士に対する動作ごとのリスク管理のリストを用いた現場教育は,理学療法中の転倒件数の減少に有効である。
1 0 0 0 OA 股関節の運動方向の違いによる腸腰筋筋活動の変化
- 著者
- 水上 優 建内 宏重 近藤 勇太 坪山 直生 市橋 則明
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.2 (第51回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0088, 2016 (Released:2016-04-28)
【はじめに,目的】腸腰筋は股関節屈曲の主動作筋であり,股関節疾患をもつ患者においてその機能改善は重要である。従来,腸腰筋は侵襲的な方法でしか測定できないとされ,その作用に関する報告は限られていたが,近年,表面筋電図での測定が可能であるとの報告がされた。本研究の目的は,股関節の運動方向が腸腰筋を含む股関節屈筋の筋活動に与える影響を筋電図学的に分析し,腸腰筋の筋作用と他の股関節屈筋と比べ選択的に活動する運動方向を明らかにすることである。【方法】対象者は健常男性20名(年齢22.7±2.6歳)とした。課題は背臥位での等尺性股関節屈曲運動とし,基本肢位は両膝より遠位をベッドから下垂した背臥位で,股関節以遠を10°傾斜させ股関節伸展10°とした。測定筋は利き足の腸腰筋(IL),大腿直筋(RF),大腿筋膜張筋(TFL),縫工筋(SA),長内転筋(AL)の5筋とした。ILの電極貼付部位は鼠径靭帯の遠位3cmとし,超音波画像診断装置(フクダ電子製)で筋腹の位置を確認し電極を貼付した(電極間距離12mm)。筋活動の測定は筋電図計測装置(Noraxon社製)を用いた。各筋の最大筋活動を測定した後,各課題での測定を無作為な順序で行った。課題は,股関節屈曲0°,内外転・内外旋中間位での保持(屈曲),同肢位で大腿遠位に内側または外側から負荷を加えた状態での保持(各屈曲・外転,屈曲・内転),同肢位で下腿遠位に内側または外側から負荷を加えた状態での保持(各屈曲・外旋,屈曲・内旋)の計5種類とした。負荷には伸長量を予め規定した(3kg)セラバンドを用いた。各筋とも各課題中の3秒間の筋活動を記録した。ILの3試行の平均筋活動を最大筋活動で正規化した値(%MVC)と,ILの%MVCを5筋の%MVCの総和で除した筋活動比にILの%MVCを乗じた値を選択的筋活動指数と定義し,解析に用いた。統計解析には,一元配置分散分析およびBonferroni法を用い,ILの5種類の運動時の筋活動と選択的筋活動指数を比較した(有意確率5%)。【結果】ILの筋活動は,屈曲・外転(21.6:%MVC)が他のどの運動よりも有意に大きく,屈曲(18.6)は屈曲・内転(14.9)よりも有意に大きかった。屈曲・内転,屈曲・外旋(15.9),屈曲・内旋(16.1)の間には有意差が無かった。選択的筋活動指数は,屈曲・外転(7.9)が,屈曲(6.5)を除く全ての運動で有意に高かった。屈曲は屈曲・内転(4.3),屈曲・内旋(3.8)よりも有意に高かった。屈曲・内転,屈曲・外旋(4.8),屈曲・内旋の間には有意差は無かった。【結論】本研究の結果,ILは屈曲・外転で他の運動方向よりも有意に筋活動が大きくなり,また屈曲・外転や屈曲が他の運動方向よりも選択的に筋力発揮しやすい傾向を示した。本研究結果は,腸腰筋の選択的な運動を行う際に有用な知見であると考えられる。
1 0 0 0 OA 腹腔鏡所見からみた鼠径部ヘルニアの術前CT診断能
- 著者
- 田中 穣 小松原 春菜 野口 大介 市川 健 河埜 道夫 近藤 昭信 長沼 達史 西出 喜弥
- 出版者
- 日本臨床外科学会
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.8, pp.1873-1880, 2016 (Released:2017-02-28)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 3
目的:鼠径部ヘルニア術前CTの診断能について検討した.対象と方法:平成24年1月から平成27年12月までに腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術を行った鼠径部ヘルニア198例226病変を対象に,術前のCTにおけるヘルニア検出率と日本ヘルニア学会の鼠径部ヘルニア分類での分類診断率を検討した.結果:病変の検出率は92.9%と高率であったが,1cm未満の小さいヘルニアやCT撮影時の腹圧が不十分で脱出していなかった場合には検出困難な場合があった.ヘルニアの分類診断率では96.7%であり,I・II・III・V型では100%であったのに対し,IV型では30.0%と低率であって,また対側の不顕性ヘルニアの検出率は45.0%であった.結語:鼠径部ヘルニア術前のCTは病変検出率は高率であり,ヘルニア分類診断にも役立つものと考えられた.
1 0 0 0 OA 木曽馬集団における毛色の頻度の推移
- 著者
- 江崎 孝三郎 早川 純一郎 富田 武 尾藤 惇一 野沢 謙 近藤 恭司
- 出版者
- 公益社団法人 日本畜産学会
- 雑誌
- 日本畜産学会報 (ISSN:1346907X)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.218-225, 1962 (Released:2008-03-10)
- 参考文献数
- 20
1. 長野県西筑摩郡の農家に飼育されている,いわゆる木曾馬の毛色に関して,1860年前後の古文書より,当時の状態を調査した.1943年以降は,「産駒登記原簿」および「伝染貧血症検査台帳」により,また直接に観察して,各種毛色の頻度の推移を調査した.2. 木曾馬産駒集団においては,年々鹿毛は増加,青毛は減少の傾向にあり,栗毛はほぼ一定の割合を維持している.河原毛および月毛は,合計してわずかに5%以下であつた.すなわち,遺伝子aの頻度qaは,1943年に約0.55であつたが,次第に減少して,1960年には約0.35となつた.遺伝子bの頻度qbは約0.45で,1943年以来この値を維持している.遺伝子Dの頻度qDは約0.02であつた.3. 以上の事実は,遺伝子A~aに関しては移行多型(transient polymorphism),遺伝子B~bに関しては平衡多型(balanced polymorphism)となつていることを示している.4. 木曾馬産駒集団における毛色の多型の維持と推移の機構に関して,種畜の選択に際して働く淘汰選抜の作用と,種畜から次の世代に移る間に働く淘汰に注目して,分析を行なつた.その結果,遺伝子aには,その頻度を減少させる方向に,上記二つの淘汰が相加的に作用すること,また遺伝子bに関してはは,前者がその頻度を,減少させる方向に,後者が増加させる方向に働いていることが判明した.そして,これら二つの要因によつて,鹿毛,青毛および栗毛の年次的変遷を遺伝的に説明することができた.
1 0 0 0 野生食虫目の実験動物化
- 著者
- 織田 銑一 近藤 恭司
- 出版者
- Japanese Association for Laboratory Animal Science
- 雑誌
- 実験動物 (ISSN:00075124)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.3, pp.273-280, 1977
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 オグラヌマガイの年齢構成
The age composition of 101 individuals of Oguranodonta ogurae, which were collected in a small pond at Hirakata City, Osaka Prefecture in the late autumn of 1998, was determined by examination of the annual gorwth-interruption lines. Individuals with 5 growth-interruption lines (i. e. 6 years old) were most abundant, and there were only 5 individuals younger than 5 years old. The scarcity of young individuals may be due to the heavy drought occurred in the summer of 1994. Based on the assumption of the stable age distribution, a life table was estimated. The estimated generation time was 6.3 years.