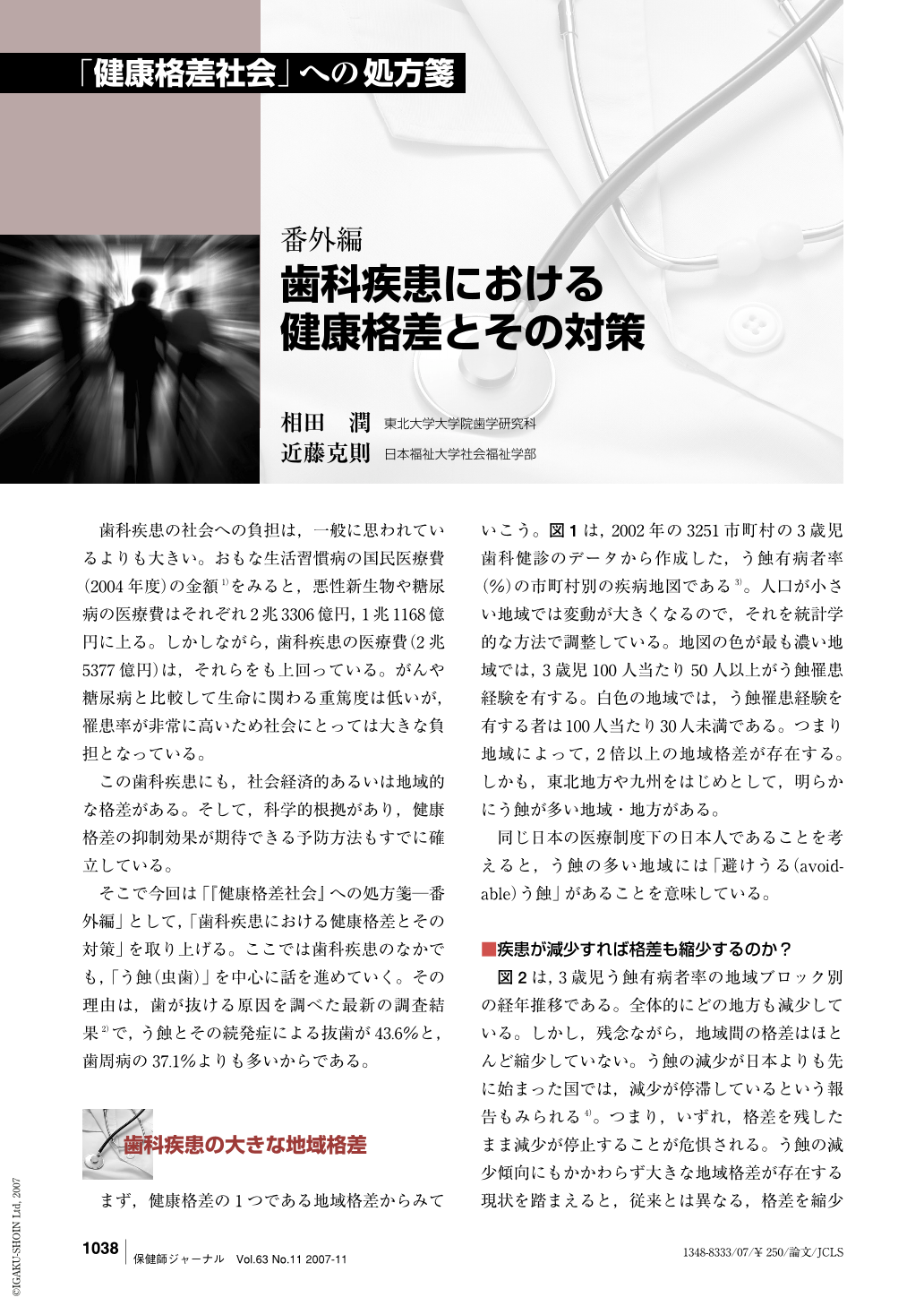2 0 0 0 IR カラスはなぜ鳴くのか?
特集 : 小嶋祥三君退職記念展望論文カラスは, 霊長類や鯨類などの社会性哺乳類と類似した. 固定的な個体群が緩やかに結びついた離合集散型と呼ばれる社会を形成している. そこでは, 個体間に競合関係や友好関係が生じ, 資源競合の解決策として機能している. 近年のカラス科の研究はその証左としての優れた社会認知戦略を明らかにしてきたが, それらに不可欠な個体認知機能のメカニズムは明らかにされていない. 個体の離合集散を伴う社会では, 音声による個体認知が有効であり, 実際に, 多くの社会性哺乳類がコンタクトコールと呼ばれる音声を用いて個体認知を行うことが知られている. 鳥類の音声個体認知については, つがい相手や親と子, なわばり隣接個体などの社会生態学的に固定的関係をもつ個体間に関するものがほとんどであり, 個体間の社会関係が時刻 と変化する複雑な社会において, どのように個の個体を認知しているのかは不明であった. 本論文では, 離合集散型の社会を形成するハシブトガラス(Corvus macrorhynchos)について, 我 が近年行ってきた研究の中から, 音声コミュニケーションについて紹介する. 彼らは音声能力に長けているとされながらも, その多くは不明のままであったが, 野外観察研究と実験室研究の両者を行うことで, コンタクトコールを特定し, それを用いたコミュニケーションが担う個体認知機能を明らかにしつつある. これらの研究は, 従来なされなかった社会性鳥類における音声個体認知のメカニズムとその機能を明らかにするだけでなく, 社会性哺乳類の知見との比較議論を可能にし, 社会生態と音声コミュニケーションの進化に関する理解を深める可能性をもつ.
2 0 0 0 スピーチの「上がり症」の実態とその対策法
- 著者
- 近藤 豊彦
- 出版者
- 東京経営短期大学
- 雑誌
- 東京経営短期大学紀要 (ISSN:09194436)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.225-232, 2002-03-15
2 0 0 0 OA 弾性表面波センサの基礎と応用
- 著者
- 近藤 淳
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.166-174, 2013-01-01 (Released:2013-01-01)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 2
圧電結晶表面を伝搬する弾性表面波(SAW)は,伝搬面と接する媒質の物理的・化学的変化によりその波の速度と減衰が変わる.信号処理用SAW素子では,この変化をいかに小さくするかが重要になる.逆にセンサ応用では,この変化を積極的に利用する.SAWセンサは,気相系,液相系センサに応用可能である.また,センサ感度は用いる圧電結晶によっても異なる.そこで,本稿では弾性波センサ一般について述べた後,SAWセンサの原理について,その考え方と摂動法により導出された摂動解を示した.次に,代表的な計測方法について説明し,実際の測定例として,ガスセンサ,液体計測,免疫反応計測などについて紹介した.
2 0 0 0 妊娠末期における習慣的身体活動の分娩所要時間に及ぼす影響
- 著者
- 近藤 有希 澤 龍一 海老名 葵 高田 昌代 藤井 ひろみ 奥山 葉子 谷川 裕子 総毛 薫 田中 幸代 白方 路子 小野 玲
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, 2015
【はじめに,目的】分娩所要時間の遷延は手術分娩や胎児の窒息,母体の感染症や合併症などのリスク上昇につながるといわれている。さらに,分娩時間の遷延は出産体験への不満感を招く一因子であり,その後の出産意欲を低下させるという報告もされている。これらのことから分娩は短縮化する必要があるといえる。分娩所要時間には有酸素能力や運動との関連が先行研究で報告されているが,骨盤底筋群トレーニングや水中エアロビクスなど特定の運動介入のものや,アスリートなど特殊な妊婦を対象としている研究が多い。しかし,多くの妊婦が子育てや仕事などの時間的制約によりこのような運動プログラムへの参加が出来ていないのが現状である。そのため,特定の運動だけでなく有酸素能力の維持・向上に効果的である日常生活での習慣的身体活動を維持することが重要と考えられる。また,初産婦と経産婦では分娩所要時間の平均時間が大きく異なる事は知られているにもかかわらず先行研究においては考慮されていない,あるいは初産婦のみを対象としているものがほとんどで経産婦についての報告は少ない。そこで本研究の目的は,初産婦,経産婦それぞれの妊娠末期における習慣的身体活動が分娩所要時間に与える影響を明らかにすることとした。【方法】対象は妊娠末期に研究参加の同意が得られ,欠損なくデータ収集が出来た121名のうち,自然分娩により出産をした初産婦48名(平均年齢28.8±4.7歳,新生児体重=3058.6±371.5g),経産婦55名(平均年齢32.7±5.5歳,新生児体重=3167.7±366.1g)の合計103名とした。妊娠末期では一般情報に加え,習慣的身体活動を質問紙により評価した。妊娠末期における習慣的身体活動はBaecke physical activity Questionnaireの日本語版を用いた。初産婦と経産婦それぞれにおいて合計点数の中央値で高活動群と低活動群に群分けした。分娩所要時間は,分娩記録より分娩第1期,分娩第2期,総分娩時間に分けて収集した。全ての解析は初産婦,経産婦それぞれに対して実施した。各分娩所要時間の群間比較は,Wilcoxonの順位和検定で比較した。多変量解析では,目的変数を分娩所要時間,説明変数を高活動群/低活動群,交絡因子を年齢,妊娠前から記入時の増加体重,出産回数,新生児体重,出産時妊娠週数,妊娠前の運動の有無として強制投入法による重回帰分析を行った。【結果】初産婦における高活動群と低活動群の間で分娩第1期時間,分娩第2期時間,総分娩時間に有意な違いはみられなかった。経産婦において,低活動群と比較して高活動群の分娩第2期の時間が有意に短かった(中央値(最小-最大):20(4-175)分,11(1-102)分,<i>p</i><.05)。交絡因子の調整後においても高活動群の分娩第2期時間が有意に短かった(β=-.36,<i>p</i>=.007,R<sup>2</sup>=.28)。しかし,分娩第1期の時間と総分娩時間では2群間に有意な違いはみられなかった。【考察】分娩所要時間に関与する因子として,陣痛と腹圧を合わせた娩出力と,産道,娩出物が分娩3要素といわれている。分娩第2期は陣痛に加えて妊婦のいきみによる腹圧が加わって胎児を娩出させる段階であり,この時期には妊婦の有酸素能力や腹筋群など骨格筋の収縮力が大きく関与しているため習慣的身体活動との関連が示唆されたと考えられる。一方で分娩第1期は分娩開始から,子宮頸管の熟化と,陣痛による胎児の下降で圧迫され子宮下部が伸展し子宮口が全開大するまでの時期であり,いきみは禁忌とされている。よって分娩第1期の時間は頸管の熟化と陣痛が主な要素であると考えられ,習慣的身体活動がこれらに影響を与えるのは困難であったと考えられる。また,総分娩時間のうち分娩1期の時間が大きな割合を占めているため,総分娩時間の短縮化に至らなかったものと考えられる。一方で初産婦に有意差がみられなかったことについては,初産婦は経産婦と比べて子宮頸部や外陰および会陰部が伸展しにくく軟産道の抵抗が強いため,娩出力以外に産道の抵抗性が分娩所要時間に大きく影響していることが考えられる。今後の研究で産道の抵抗性に影響する因子や,その他の分娩所要時間に関連する因子を解明する必要がある。【理学療法学研究としての意義】妊娠末期の習慣的身体活動は経産婦の分娩第2期の時間に影響する一要因であることが示された。胎児・母体への悪影響は主に分娩第2期の遷延において多く報告されており,妊娠末期の女性に対して適切な運動習慣の指導を行うことで分娩経過と分娩結果に良い効果をもたらす可能性が示唆された。
2 0 0 0 OA 赤外反射吸収分光法を用いたNi(110)表面上の水酸基に関する研究
- 著者
- 湯澤 哲夫 久保田 純 近藤 淳子 堂免 一成 廣瀬 千秋
- 出版者
- The Surface Science Society of Japan
- 雑誌
- 表面科学 (ISSN:03885321)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.6, pp.359-363, 1994-08-10 (Released:2009-08-07)
- 参考文献数
- 23
Coadsorption-induced recombination of surface hydroxyl species (OD(a)) on Ni (110) was verified by infrared reflection absorption spectroscopy (IRAS) and temperature programmed desorption (TPD). The O-D stretching mode of the surface hydroxyl species appeared at 2650 cm-1 at 173 K on D2O/ONi (110) surface. The hydroxyl species were thermally recombined and desorbed as D2O from the Ni (110) surface at 350 K. The recombination of the OD species to water (2731 and 2567 cm-1), was also observed at a lower temperature (117 K) when CO was coadsorbed. This OD recombination induced by CO adsorption is considered to result from a strong effect of coadsorbed CO, which lowers the reaction temperature from 350 to 117 K.
2 0 0 0 歯科疾患における健康格差とその対策
- 著者
- 相田 潤 近藤 克則
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 保健師ジャーナル (ISSN:13488333)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.11, pp.1038-1043, 2007-11-10
歯科疾患の社会への負担は,一般に思われているよりも大きい。おもな生活習慣病の国民医療費(2004年度)の金額1)をみると,悪性新生物や糖尿病の医療費はそれぞれ2兆3306億円,1兆1168億円に上る。しかしながら,歯科疾患の医療費(2兆5377億円)は,それらをも上回っている。がんや糖尿病と比較して生命に関わる重篤度は低いが,罹患率が非常に高いため社会にとっては大きな負担となっている。 この歯科疾患にも,社会経済的あるいは地域的な格差がある。そして,科学的根拠があり,健康格差の抑制効果が期待できる予防方法もすでに確立している。 そこで今回は「『健康格差社会』への処方箋―番外編」として,「歯科疾患における健康格差とその対策」を取り上げる。ここでは歯科疾患のなかでも,「う蝕(虫歯)」を中心に話を進めていく。その理由は,歯が抜ける原因を調べた最新の調査結果2)で,う蝕とその続発症による抜歯が43.6%と,歯周病の37.1%よりも多いからである。
2 0 0 0 OA 著明な腎石灰化を合併した偽Bartter症候群の1例
- 著者
- 山本 駿一 家里 憲二 長谷川 茂 塚原 常道 近藤 洋一郎 吉田 弘道 寺野 隆
- 出版者
- 社団法人 日本腎臓学会
- 雑誌
- 日本腎臓学会誌 (ISSN:03852385)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.7, pp.597-602, 2000-10-25 (Released:2010-07-05)
- 参考文献数
- 17
A 38-year-old woman was admitted to our hospital on for evaluation of thirst, bilateral backache and a feeling of abdominal fullness. She had hypokalemia, normotension, hyperreninemia, hyperaldostronism and hyperplasia of the juxtaglomerular apparatus on renal iopsy. Ultrasonography, intravenous pyelography and computed tomography showed marked bilateral renal calcification. Considering her history of persistent soft stool caused by chronic laxative abuse for 15 to 16 years and past diuretic abuse for several years since 1986, we diagnosed her as pseudo-Bartter's syndrome with nephrocarcinosis. The value of urinary Ca excretion was in the normal range, and acidification disturbance in NH4C1 loading test was revealed. In addition, she had taken analgesics for 2 to 3 years and interstitial nephritis on renal biopsy was seen. It is thus suggested that the cause of nephrocarcinosis in this case was the reduction of Ca solubility in the tubular cavity induced by incomplete renal tubular acidosis associated with analgesic nephropathy or interstitial nephritis caused by hypokalemia.
- 著者
- 白石 智子 松下 健 田中 乙菜 島津 直実 近藤 育代 越川 房子 石井 康智
- 出版者
- 宇都宮大学
- 雑誌
- 宇都宮大学教育学部紀要. 第1部 (ISSN:03871266)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, pp.13-19, 2013-03-11
2 0 0 0 IR 「移民国家」化と家族呼び寄せの権利 : グローバル時代における入管行政
- 著者
- 近藤 敦
- 出版者
- 九州産業大学
- 雑誌
- 産業経営研究所報 (ISSN:02880059)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.103-118, 2004-03-25
2 0 0 0 愛宕山勝軍地蔵信仰の形成 : 中世神仏習合像の一形態
- 著者
- 近藤 謙
- 出版者
- 日本宗教文化史学会
- 雑誌
- 日本宗教文化史研究 (ISSN:13428659)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.96-112, 2013-05
2 0 0 0 OA 心電図R-R間隔の変動を用いた自律神経機能検査の正常参考値および標準予測式
- 著者
- 藤本 順子 弘田 明成 畑 美智子 近藤 まみ子 島 健二
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.167-173, 1987-02-28 (Released:2011-08-10)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 4
歳から79歳までの各年齢層の健常人1,261例について心電図R-R間隔変動を指標とした自律神経機能検査を行い, IE常参考値および標準予測式を作成した.安静・時, 深呼吸時, バルサルバ試験, 起立試験での心電図R-R間隔をMEコマーシャル製のオートノミックR-100を使用して連続する100心拍で計測し, 平均値, 標準偏差, 変動係数, 最大値と最小値の比などを検討した.自律神経機能検査成績に性差は認められなかったが, 年齢と強い相関が認められたので年齢別の正常参考値をパラメトリック法で算出した.安静時および深呼吸時の100心拍R-R間隔の標準偏差, 変動係数および最大値と最小値の比は加齢に伴って有意に減少した (P<0.01).また多変量解析法により自律神経機能検査の標準予測式を作成し, 信頼の高い (P<0.01) 予測式を得た
2 0 0 0 OA 未刊古文書釈文作成のための協調作業環境の構築
- 著者
- 近藤 成一 海老澤 衷 稲葉 伸道 本多 博之 柳原 敏昭 高橋 敏子 遠藤 基郎 渡邉 正男 神野 潔 野村 朋弘 金子 拓 西田 友広 遠藤 珠紀 山田 太造 岡本 隆明
- 出版者
- 放送大学
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2013-04-01
未刊古文書釈文作成のための協調作業環境を構築することにより、未刊古文書の釈文を歴史学のコミュニティにおいて協同で行うことを提起し、史料編纂のあり方について新たな可能性を模索するとともに、歴史学のコミュニティの実体形成にも寄与する基礎とした。釈文作成のために外部から自由な書き込みを許す部分と、作成された成果を史料編纂所の管理のもとに公開する部分を構築し、前者から後者にデータを選択して移行するシステムを設けた。
2 0 0 0 OA 高齢者総合機能評価は健診よりも健康寿命喪失を予測する:JAGESコホート研究
- 著者
- 岡部 大地 辻 大士 近藤 克則
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.367-377, 2018-07-25 (Released:2018-08-18)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 6
目的:高齢者総合機能評価は有用とされ,その一つとして自記式質問紙の基本チェックリストがある.一方,要介護状態の最大原因は脳卒中であり,特定健康診査(特定健診)などで検出しうる糖尿病や脂質異常症などが基礎疾患と分かっている.しかし高齢者において総合機能評価と健診のどちらが健康寿命喪失リスクの予測力が大きいか比較検討した研究はない.そこで本研究では,高齢者総合機能評価と健診のどちらが健康寿命喪失の予測力が大きいか明らかにすることを目的とした.方法:要介護認定を受けていない65歳以上の高齢者を対象とした日本老年学的評価研究(JAGES)の2010年の自記式郵送調査データを用いた.同年の健診データを得られた6市町において,データ結合が可能で,その後3年間の要介護認定状況および死亡を追跡することができた9,756人を分析対象とした.基本チェックリストから判定される7つのリスク(虚弱,運動機能低下,低栄養,口腔機能低下,閉じこもり,認知機能低下,うつ),メタボリックシンドロームを含む特定健診必須15項目を説明変数とし,要介護2以上の認定または死亡を目的変数としたCox比例ハザード分析をおこなった(性,年齢,飲酒,喫煙,教育歴,等価所得を調整).結果:要介護2以上の認定または死亡の発生率は,19.4人/1,000人年であった.基本チェックリストからは口腔機能低下を除く6つのリスクにおいてhazard ratio(HR)が1.44~3.63と有意であった.特定健診からは尿蛋白異常,BMI高値,AST異常,HDL低値,空腹時血糖高値,HbA1c高値の6項目においてHRは1.37~2.07と有意であった.メタボリックシンドローム該当のHRは1.05と有意ではなかった.結論:血液検査を中心とした健診よりも問診や質問紙を用いた高齢者総合機能評価の方が健康寿命喪失を予測すると考えられた.
2 0 0 0 OA 佐馬地村地誌・三好郡史
- 著者
- 近藤辰郎, 田村左源太 編
- 出版者
- 公立佐馬地村教育研究会
- 巻号頁・発行日
- 1899
2 0 0 0 OA 岐阜県多治見市に高温をもたらす地表面加熱を伴うフェーン
- 著者
- 高根 雄也 近藤 裕昭 日下 博幸 片木 仁 永淵 修 中澤 暦 兼保 直樹 宮上 佳弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2016年度日本地理学会秋季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.100126, 2016 (Released:2016-11-09)
本研究では、地表面からの非断熱加熱を伴うハイブリッドタイプのフェーンが、風下末端地域の高温の発生に寄与しているという仮説を、3つの異なる手法・視点:独自観測・数値シミュレーションによる感度実験・過去データの統計解析から検証した。このタイプのフェーンは、1)典型的なドライフェーン(断熱加熱)と、2)地表面からの加熱(非断熱加熱)の複合効果によって生じる。フェーンを伴うメソスケールの西寄りの風に沿った地上気象要素の現地観測により、1)の典型的なフェーンの発生が確認できた。このフェーン発生地の風下側の平地における2)地表面からの非断熱加熱の効果に関しては、風下の地点ほど温位が高くなるという結果が得られた。そして、その風下と風上の温位差がフェッチの代表的土地利用・被覆からの顕熱供給(地表面からの非断熱加熱)で概ね説明可能であることが、簡易混合層モデルによるシンプルな計算にから確認できた。この非断熱加熱の存在を他の手法でより詳しく調査するため、WRFモデルによる風上地域の土壌水分量の感度実験、および過去6年分の土壌水分量と地上気温、地上風の統計解析で確認した。その結果、風上側の地表面から非断熱加熱を受けた西寄りの風の侵入に伴い、風下の多治見が昇温していることが両手法によっても確認された。この地表面加熱を伴うハイブリッドタイプのフェーンが、この風の終着点である多治見の高温に寄与していると考えられる。
2 0 0 0 OA 近赤外線イメージングによる皮下異物の検出実験
- 著者
- 早川 吉彦 山下 拓慶 大粒来 孝 妙瀬田 泰隆 佐川 盛久 近藤 篤 辻 由美子 本田 明
- 出版者
- 医用画像情報学会
- 雑誌
- 医用画像情報学会雑誌 (ISSN:09101543)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.3, pp.50-54, 2010 (Released:2010-07-28)
- 参考文献数
- 6
The wavelength range of the near infrared (NIR) light is called `water window.' The superficial vascular imaging system using near infrared light sources was developed as those using both the reflected light and transmitted light. An NIR-sensitive CCD camera was surrounded by approximately sixty light emitting diodes (LEDs) , which have alternating wavelengths of 700 (visible light) , 760, 810 and 940nm, respectively. The camera detected the reflected NIR from superficial subcutaneous tissues at the palm and back of hands, and the wrist. Differences between wavelengths were significantly observed. Images taken at 940 nm the most clearly showed the vascular vessels at insides of these regions. As an application of the NIR imaging system, we examined whether the system was the beneficial tool for finding superficial subcutaneous foreign bodies or not. Twelve light sources of 940 nm LEDs were aligned for the transmission imaging. The alien substance examined was a mechanical pencil lead with 0.5 mm diameter. Chicken and pork meats (approx. 1 to 10 mm in thickness) were used instead of human skin. The thickness and fat contents were affected on the detection. As results, the NIR imaging was thought to be the beneficial tool for finding subcutaneous alien substances detection.
2 0 0 0 IR シベリア出兵期、日本軍によるハンガリー人捕虜射殺事件の研究
- 著者
- 近藤 正憲
- 出版者
- 北海道大学スラブ研究センター
- 雑誌
- スラヴ研究 (ISSN:05626579)
- 巻号頁・発行日
- no.53, pp.333-353, 2006
- 著者
- 近藤 英男 辻本 勇 竹村 昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 体育学研究
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, 1963