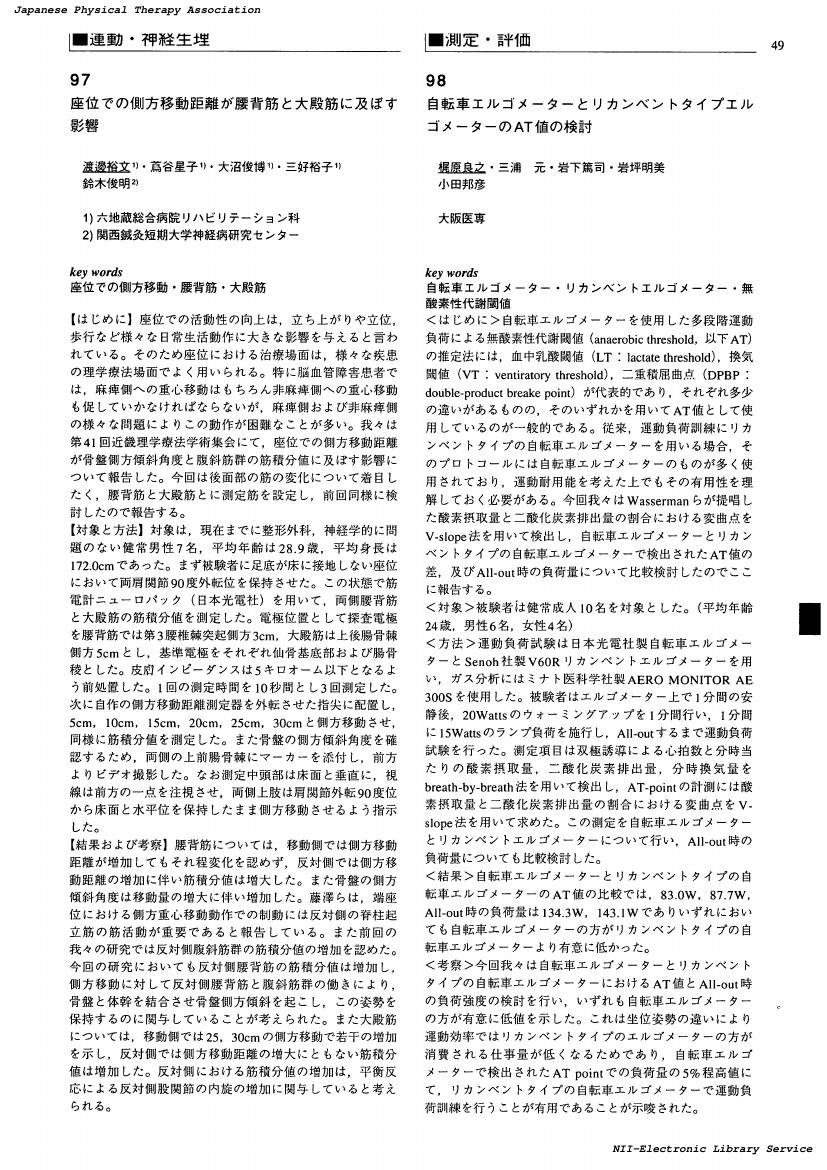1 0 0 0 OA 前脛骨筋の筋力低下が立位安定性限界に与える影響
- 著者
- 髙橋 司 榊 真智子 管 利大 佐々木 佑佳 小野 愛季 西山 徹 小林 武
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.38 Suppl. No.2 (第46回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.AdPF1007, 2011 (Released:2011-05-26)
【目的】 バランスは「質量中心を安定性限界(Limit of Stability: LOS)内に保持する能力」と定義される。また、筋力はバランスの構成要素の一つであるため、筋力低下が生じることでバランス能力が低下する。 バランスに関する先行研究は、立位バランスと姿勢調節筋について述べられているものが多い。主要姿勢筋は、主に安静立位姿勢を保持する役割を担っているが、足圧中心(Center of Pressure: COP)が絶え間なく移動している安静立位では、主要姿勢筋の活動のみでなく、当然足関節背屈筋なども関与している。しかし、足関節背屈筋と立位バランスの関係についての研究報告は主要姿勢筋に比べ数件しかなく、LOSとの関連は報告されていない。 しかしながら、臨床場面では脳卒中や腰椎椎間板ヘルニア、腓骨神経麻痺などによって前脛骨筋(Tibialis Anterior:TA)の筋力発揮が障害される疾患に多く遭遇する。TAの機能不全が立位LOSに与える影響を明確にすることは、臨床場面に有益な情報をもたらすと考える。これらの理由から、本研究はTAの筋力低下が立位LOSに与える影響を明確にすることを目的とした。【方法】 対象は健常男性21名(年齢21.1±1.0歳、身長170.5±5.9cm、体重61.4±6.4kg、BMI 21.1±1.3kg/m2)、対象筋は両側TAとした。測定項目は、徒手筋力計での足関節最大背屈筋力と重心動揺計を用いたクロステストでの足圧中心位置とし、各々TAの筋疲労前後で測定した。筋疲労はクロステスト実施中の筋力回復を考慮し、体重10%の重錘を足背部に負荷して30%以下になるまで背屈運動を行った。クロステストは、閉脚立位にて15秒間の静止立位後、前後左右ランダムにCOPを可能な限り移動させ、その位置を各々10秒間保持させた。疲労前後の平均COP位置を対応のあるt検定を用いて比較・検討した(p<0.05)。【説明と同意】 全被験者に対して実験実施前に本研究の目的・方法について、文書と口頭にて説明し実験参加の同意を得た。【結果】 疲労運動による足関節最大背屈筋力は、疲労前249.2±39.6N、疲労後63.1±27.0Nであり、疲労直後の筋力は疲労前の23.1±5.9%となった。足長と足幅のそれぞれ半分の位置を原点として、x座標は正で右方、負で左方に、そしてy座標は正で前方、負で後方に位置していることを示す。疲労前の静止立位位置は(-1.6±6.0,-12.3±8.3)%。LOSは、前方(-3.9±9.1,43.7±23.3)%、後方(-4.3±7.9,-48.3±23.9)%、右方(38.3±9.3,-10.9±7.2)%、左方(-49.1±9.3,-6.0±10.5)%であった。疲労後の静止立位位置は(-2.7±6.1,-17.2±11.8)%。LOSは、前方(-3.2±6.6,37.3±21.9)%、後方(-5.9±10.5,-38.2±23.9)%、右方(32.5±8.5,-17.9±10.7)%、左方(-38.2±10.6,-16.6±12.2)%であった。疲労前に比べ、疲労後のLOSは、足長・足幅に対して前方:6.9%、後方:10.1%、左方:10.6%、右方:5.8%それぞれ有意に減少した(p<0.05)。 また、疲労後の静止立位時と左右方向での姿勢保持時におけるCOP位置(y座標)は静止立位:4.9%、左方:10.6%、右方:7.0%それぞれ有意に後方へ変位した(p<0.05)。【考察】 TAの筋疲労前後での立位LOSは、疲労前に比べて疲労後は全方向で有意に減少した。また、静止立位時や左右方向での姿勢保持時におけるCOP位置は静止立位、左方、右方、それぞれ有意に後方へ変位した。 COPが前方移動すると母趾側荷重となり、足関節回内位となる。足関節の回内運動は内側縦アーチの降下を引き起こすことになる。後方移動では下腿は後方傾斜し、左右移動では外方傾斜する。 TAは内側縦アーチの保持を担い、閉鎖性運動連鎖では下腿の後方、外方傾斜の制動に関与する。そのため、TAの筋力低下により下腿の後方、外方傾斜の制動作用と内側縦アーチの保持作用の減弱が生じ、LOSが減少したと考える。また、静止立位位置と左右方向のCOP後方変位(y座標)については、足関節戦略での姿勢調節が関係していると考える。静止立位では、ヒラメ筋とTAの持続的な等張性活動によって姿勢を制御している。TAが疲労するとヒラメ筋とTAの筋活動比率が崩れ、TA劣位の姿勢制御となる。そのため、COPの後方変位が生じたと考えられる。【理学療法学研究としての意義】 臨床場面では脳卒中や腰椎椎間板ヘルニア、腓骨神経麻痺などによってTAの筋力発揮が障害される疾患に多く遭遇する。TAの機能不全が立位LOSに与える影響を明確にすることは、臨床場面に有益な情報をもたらすと考える。
1 0 0 0 OA 地域包括ケア病棟におけるポストアキュート・サブアキュートの傾向
- 著者
- 村田 尚寛
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.46 Suppl. No.1 (第53回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.G-88_1, 2019 (Released:2019-08-20)
【はじめに・目的】 地域包括ケア病棟における機能としてポストアキュート、サブアキュートがある。現在、ポストアキュート、サブアキュートそれぞれの身体機能や在宅復帰における傾向を述べた文献は少ない。そこで当院の地域包括ケア病棟におけるポストアキュート、サブアキュートそれぞれの身体機能、在宅復帰についての傾向を明らかにする。【方法】 対象は平成29年10月から平成30年3月に当院入院した疾患別リハビリテーションの処方があった死亡退院を除くポストアキュート群121名、サブアキュート群64名とした。処方率は85.9%であった。今回この2群それぞれの入院時と退院時のFunction Independence Measure(FIM)の比較、そしてポストアキュート群、サブアキュート群2群間の年齢、入院時退院時それぞれのFIMとFIM利得、FIM効率、在院日数を比較した。統計はT検定、X2検定を用いて有意水準を5%未満とした。【結果】 まずポストアキュート、サブアキュートのそれぞれの入院時退院時のFIMの比較ではどちらも入院時より退院時の方がFIMは高い値を示しており有意差が認められた。 次にポストアキュートとサブアキュート2群間の比較では入院時FIMがポストアキュート群67.7±30.8、サブアキュート群58.4±30.4とポストアキュート群が高い値であり有意差が認められた。一方で在院日数、在宅復帰率はポストアキュート群38.8±30.7日、63.6%、サブアキュート群29.1±15.9日、78.1%とサブアキュート群の方が在院日数は短く、在宅復帰率は高く有意差が認められた。その他の項目では有意差は認められなかった。 また在宅復帰患者に限定したFIMにおいても退院時FIMがポストアキュート87.7±32.8、サブアキュート73.6±35.7と有意差が見られた。【結論】 地域包括ケア病棟の入院患者に関しては一様にリハビリテーションの介入により身体機能の向上が図れることが示唆された。ポストアキュートの方が入院時退院時ともにFIMは高い一方で在院日数や在宅復帰率はサブアキュートより低値であり在宅復帰が困難となる事例が多い事がわかった。これは他医療機関で身体機能の向上が図れているものの全身状態とは別の要因が大きく影響していることが考えられ、家屋環境や社会的背景にて在宅復帰困難となる事例が多い。一方でサブアキュートでは元々介護保険サービスの利用といった社会的資源を活用されている事例が多くFIMが低値であっても一定の身体機能に達することにより在宅への意志が強く早期在宅復帰となる事例が多いと思われる。 ポストアキュートの患者は早期に自宅環境、社会的要因の確認を行い在宅復帰に向けた多職種、地域との連携がサブアキュートより必要である可能性が示唆された。【倫理的配慮,説明と同意】 本研究は当院倫理委員会の承認を得て実施した。
1 0 0 0 OA 間質性肺炎患者におけるステロイド治療後の理学療法効果の検討
- 著者
- 朝井 政治 俵 祐一 佐々木 綾子 岡田 芳郎 夏井 一生 中野 豊 神津 玲
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.33 Suppl. No.2 (第41回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.D0484, 2006 (Released:2006-04-29)
【はじめに】 間質性肺炎における治療はステロイド薬を中心とした薬物療法が主体で、理学療法の適応は少ないとされてきた。しかし近年、病態の安定した本疾患患者において、運動療法により運動能、QOLが改善するという報告がみられている。今回、間質性肺炎の増悪でステロイド薬投与開始となった症例の運動機能を6分間歩行距離テスト(6MD)にて評価し、理学療法の効果を検討したので報告する。【対象】 当院呼吸器センター内科にて入院治療を行った間質性肺炎患者7名(男性4例、女性3例、平均年齢69.0歳)を対象とした。全例とも間質性肺炎の増悪にて入院となった。全例でステロイド薬が投与され、うち5名で短期間大量投与による治療(パルス療法)が行われた。【方法】 入院中に実施した6MDによる歩行距離、酸素飽和度(SpO2)の変化、呼吸困難感の変化(Borg Scale)を指標とし、ステロイド薬投与前(1回目)とパルス療法後または投与開始から2週もしくは4週間後(2回目)で比較(薬物療法効果)するとともに、2回目の結果とステロイド薬減量中に並行して一定期間運動療法を実施した後を比較(理学療法効果)し、その効果の相違を検討した。理学療法は上下肢の筋力増強、歩行・自転車エルゴメータによる運動耐容能向上を目的とした運動療法を中心に実施した。運動の負荷量は、SpO2やHRをモニタリングしながら、Borg Scaleにて3-4を目安とした。運動時間は30-40分とし、1日1回、週6日の頻度で実施した。【結果】1)薬物療法効果:1例で入院直後にパルス療法が行なわれたため、6例で検討した。1回目と2回目の比較では、2回目の6MDは全例で増加を認め、平均91.7m(25-260m)増加した。SpO2は、平均で1回目7%の低下、2回目5.6%の低下、呼吸困難感は1回目0.5-6、2回目0-3であった。2)理学療法効果:理学療法の実施期間は平均50.0日(平均実施回数30回)で、実施期間中に原疾患の悪化あるいは感染等で再増悪した症例はなかった。3回目の歩行距離は、2回目の結果からさらに平均34.3mの増加を認めた。SpO2は平均7.2%低下したが、最低値は87-92%と著明な低酸素血症は認めなかった。呼吸困難感は0-4であった。【考察】 2回目の歩行距離の著しい増加は、薬物療法による呼吸機能の改善が運動能力の向上につながったと考えられた。3回目では、さらに平均で34.3mの増加を認め,理学療法を行うことにより、薬物療法による改善に加え、さらなる運動機能の向上を期待できると思われた。 今回の結果はあくまで理学療法と薬物療法との相乗効果であるが、ステロイド長期投与の副作用による運動機能の低下予防の点からも早期からの理学療法導入により、運動機能を維持・向上していくことが重要であると思われた。
1 0 0 0 OA 間質性肺炎患者における呼吸リハビリテーションの効果
- 著者
- 宮本 直美 北川 知佳 栗田 健介 岩永 桃子 力富 直人 神津 玲 千住 秀明
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.33 Suppl. No.2 (第41回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.D0483, 2006 (Released:2006-04-29)
【目的】2005年日本呼吸器学会で発表された「特発性間質性肺炎の診断・治療ガイドライン」では、呼吸リハビリテーション(以下、呼吸リハ)は運動耐容能や呼吸困難感の改善などが期待されると示されている。また、間質性肺炎は進行性で予後不良であるため、臨床上呼吸リハが遂行困難な症例も多い。今回、間質性肺炎に対する呼吸リハの効果について検討することを目的に、当院において呼吸リハを施行した間質性肺炎患者について調査検討したので報告する。【方法】平成9年8月から平成17年7月までに、当院に入院し呼吸リハを施行した間質性肺炎患者37例、65エピソード(平均年齢68±10.8歳、男性25例、女性12例)を対象とした。呼吸リハプログラムの内容は、運動療法を中心に動作コントロール指導を併せて実施した。呼吸リハ前後での呼吸困難感(MRCスケール)、身体組成、肺機能、運動耐容能(6分間歩行テスト、シャトルウォーキングテスト)、下肢筋力、ADL(千住らのスコア)を評価し、呼吸リハ実施期間、完遂状況、ステロイド投与量を調査した。【結果】呼吸リハ完遂可能であった患者(完遂群)は34エピソード(52%)、呼吸リハが遂行困難であった患者(非完遂群)は31エピソード(48%)で基礎疾患の増悪が主な理由であった。呼吸リハの実施期間は中央値で53.5日であった。完遂群では、呼吸リハ前後での呼吸困難感、肺機能(VC、MVV)、下肢筋力(n=12)で有意な改善を認めたが、身体組成に変化はなかった。また6分間歩行距離で有意な改善を認めたが、シャトルウォーキングテスト(n=10)の歩行距離に有意差はなかった。ADLでは有意な改善を認めた。ステロイド治療は10エピソードで実施されており、実施期間中の増量はなかった。【考察】今回、呼吸リハが遂行困難であった患者は全体の48%であった。これは間質性肺炎が進行性で、病状のコントロールが困難であるという本疾患群の病態の特徴を反映した結果であると思われた。しかし、完遂群における呼吸リハ前後の比較では、呼吸困難感、6分間歩行テスト(歩行距離)、下肢筋力、ADLで改善を認めており、症状安定期にある間質性肺炎患者では、薬物療法(ステロイド治療)とともに呼吸リハが有効である可能性が示唆された。
1 0 0 0 OA 健常人におけるバルサルバ効果が瞬間最大筋力に及ぼす影響 -筋力との関連性とリスク管理-
- 著者
- 天米 穂 松本 大夢 荻原 勇太 井元 淳
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.46 Suppl. No.1 (第53回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.C-49_1, 2019 (Released:2019-08-20)
【はじめに、目的】内部疾患患者におけるバルサルバ現象は、リスク管理の面から避けるべきであると、さまざまな研究で指摘されている。しかしながら、バルサルバ効果と瞬間最大筋力との関連性を示した研究は乏しい。よって本研究では、バルサルバ効果の有無がバイタルサインに及ぼす変化と瞬間最大筋力にどのような影響を与えるかを検証することを目的とした。【方法】被験者は年齢18~22歳の健常人31名(男性 16名、女性15名)とした。バルサルバ法時と呼気時の等尺性膝関節伸展筋力(以下、筋力)をそれぞれ2回ずつ測定し、バイタルサインとして血圧、脈拍および経皮的酸素飽和度(以下、SpO2)の測定を安静時、筋力測定直後、筋力測定後5分経過時の3回実施した。【結果】筋力、収縮期血圧では呼気時に比べバルサルバ法で高い値を示した。バイタルサインの変化において、筋力測定直後にバルサルバ法では収縮期血圧上昇、SpO2低下を認めた。呼気時では収縮期血圧上昇と脈拍増加を認めた。【結論】瞬間最大筋力増強の要因として、胸腔腹腔内圧上昇によって腹筋群の緊張や体幹の安定性が向上したことが考えられる。収縮期血圧は両方法とも筋力測定直後に高い値を示し、バルサルバ法では呼気時と比較して有意に上昇していた。これは圧受容器反射による影響が考えられる。脈拍は呼気時において筋力測定直後で高い値を示した。これは循環応答に加えてベインブリッジ反射による影響が考えられる。いずれの項目でも安静時‐筋力測定5分後において有意差は認められず、バイタルサインの変化は緩徐であったため、健常人ではリスクになりうる強度ではなく、バルサルバ法による瞬間最大筋力の増強は可能であることが示唆された。今後の課題として、中高年者や高齢者などに対しても検証を行い臨床応用に繋げる必要がある。【倫理的配慮,説明と同意】本研究は、ヘルシンキ宣言を遵守し個人情報の取り扱いに配慮し、被験者の同意を得て実施した。
1 0 0 0 OA 階段昇降動作における身体の生理学的反応の比較検討 下肢の昇降パターンと往復階数の違いから
- 著者
- 志貴 知彰 佐竹 將宏
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.35 Suppl. No.2 (第43回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.A0467, 2008 (Released:2008-05-13)
【目的】理学療法では階段昇降練習をよく行うが、昇降パターンや段数の違いによって、運動強度は容易に変化するといわれている。本研究の目的は、階段を連続して昇降したときの、酸素摂取量(以下V(dot)O2)、心拍数(以下HR)、自覚的運動強度が、下肢の昇降パターンと往復階数の違いからどのような変化を示すかを比較検討することである。【方法】対象は健常成人10名(男性7名、女性3名)で、平均年齢は27.0±5.8歳であった。階段は段差16cm、22段/階を使用し、ステップ数を80steps/minと一定にして、それぞれの条件で7分間の連続階段昇降を行った。その時のV(dot)O2とHRを携帯型呼気ガス代謝モニターを用いて測定し、また、昇段および降段毎の息切れ・下肢疲労を修正ボルグスケールにて記録した。階段昇降の条件は、下肢の昇降パターンを一足一段(以下A)と二足一段(以下B)とし、それぞれで一階・二階・三階の往復を行った。【結果】最高V(dot)O2(ml/min/kg)は、A-1階:14.9±1.6、A-2階:17.0±2.4、A-3階:17.9±3.2、B-1階:11.3±2.5、B-2階:13.3±1.8、B-3階:15.1±2.0を示し、各条件間で有意差がみられた。HR(bpm)は、A-1階:107.6±12.5、A-2階:121.3±12.7、A-3階:121.3±11.0、B-1階:103.0±14.0、B-2階:108.0±11.8、B-3階:107.7±13.7を示し、AとBおよび一階と二階との往復の間で有意差がみられた。息切れと下肢疲労については、A-3階:息切れ2.7(下肢疲労2.3)、B-3階:1.3(2.4)で、AとBでは有意差がみられた。経時的変化については、V(dot)O2とHRともに昇段では増加し、降段では減少する傾向がみられた。また、昇段では一定の値(ほぼ最高値)まで増加し、降段では一定の値まで減少する現象を繰り返した。この上下するサイクルはほぼ昇段および降段に要する時間で繰り返されていた。息切れ・下肢疲労ともに、昇段では増加を示し、降段では変化しないか減少した。【考察】本研究でのMets数は、最低で3.2Mets、最高で5.1Metsであった。この結果から階段昇降は中等度の運動強度であるといえる。また、下肢の昇降パターンと往復階数を変えることで運動強度を変えることができると考えられた。V(dot)O2、HR、息切れ、下肢疲労の経時的変化をみると、昇段では増加し、降段では減少する傾向がみられた。これは、階段の昇段時には求心性収縮を、降段時には遠心性収縮を繰り返す運動であり、遠心性収縮の少ない酸素摂取量で大きな張力を発揮できる特徴をよく表していると考えられた。この降段時の遠心性収縮の特徴を利用することで、運動耐容能の低下した患者などへの下肢トレーニングにも利用できる可能性が示唆された。
1 0 0 0 OA 日本理学療法士協会発展の歴史と展望
- 著者
- 松村 秩
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 臨床理学療法 (ISSN:02870827)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.48-54, 1980-08-20 (Released:2018-07-25)
1 0 0 0 OA 階段昇降様式の違いにおける大腿四頭筋活動の筋電図学的分析(運動学)
- 著者
- 徳原 尚人 北浜 伸介 宮川 孝芳 千知岩 伸匡 日高 正巳 武政 誠一 嶋田 智明
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.29 Suppl. No.2(第37回日本理学療法学術大会 第29巻大会特別号 No.2 : 演題抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.163, 2002-04-20 (Released:2018-03-06)
1 0 0 0 OA Empty can trainingが棘上筋筋活動に及ぼす影響
- 著者
- 津村 一美 渡邊 裕之 橋本 昌美 嘉治 一樹 高橋 美沙 重田 暁 千葉 一裕 月村 泰規 見目 智紀 高平 尚伸
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.41 Suppl. No.2 (第49回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0965, 2014 (Released:2014-05-09)
【はじめに,目的】棘上筋の筋活動を高める方法として,従来からEmpty can training(ECT)が実施されている。ECTは棘上筋が働きやすい肢位で実施されるため,棘上筋に対して効果的なトレーニング方法であり,他の棘上筋トレーニングと比較しても,棘上筋のより高い筋活動が得られると報告されている。しかし,これらの報告の多くは横断的研究に基づいており,ECTの介入効果を検証した縦断的研究は少ない。そのため臨床現場では,経験則に基づいた治療方法として対象者に施行しているのが現状である。従来,棘上筋の機能評価として肩甲骨面挙上筋力の測定が実施されてきたが,近年では棘上筋の正確な評価が困難であると報告されている。一方で高橋らの報告より,棘上筋筋活動と棘上筋筋厚との間に相関関係があり,筋厚測定が筋活動を反映することが明らかになっている。そこで,本研究は筋厚を測定することにより,ECTが棘上筋筋活動に及ぼす影響を検証し,介入効果を明らかにすることを目的とした。【方法】対象は肩関節疾患の既往がない成人男性15名(年齢20.8±0.9歳)の30肩とした。対象者の年齢,身長,体重,利き手,スポーツ歴を聴取した。トレーニング介入前に棘上筋筋厚,最大等尺性肩甲骨面挙上筋力を測定した。対象者は週5日,6週間にわたりECTを実施した。トレーニング介入後にトレーニング介入前と同様の項目を測定した。棘上筋筋厚測定は超音波画像診断装置(SSD-4000,ALOKA)を用いて行った。肩甲棘長を100%とし,肩甲棘基部から外側へ10%の部位を測定位置とした。測定位置において,プローブを肩甲棘に対して垂直に固定し,棘上筋の短軸画像を描出した。浅層筋膜と深層筋膜との最大距離を棘上筋筋厚として測定した。棘上筋筋厚は各2回測定し,平均値を採用した。測定肢位は座位とした。測定条件は肩関節内旋位,肩甲骨面挙上30°にて他動保持時とセラバンド負荷時の2条件とした。なお,2kg負荷はセラバンドを用いて手関節近位部に負荷した。最大等尺性肩甲骨面挙上筋力測定は肩関節内旋位,肩甲骨面挙上30°での肢位にて測定した。検者はHand-held dynamometer(μ-tas F-1,ANIMA)のセンサーを手関節近位部に固定し,対象者は3秒間の最大等尺性収縮を肩甲骨面上で2回発揮し,平均値を採用した。ECTは,手関節近位部にセラバンドを固定し,肩関節内旋位にて肩甲骨面0°~30°挙上位までの反復運動を実施した。1回の運動を2秒で完遂し,20回を1セット,インターバルを1分として,1日に3セットを実施した。検者は週2日,代償動作が生じずに適切な肢位でトレーニングを実施できているかを確認した。統計学的解析にはWilcoxonの符号付順位検定を用い,棘上筋筋厚および最大等尺性肩甲骨面挙上筋力をトレーニング介入前後で比較した。なお,すべての解析において有意水準は5%未満とした。【倫理的配慮,説明と同意】本研究は同学研究倫理審査委員会の承認を得て実施した(承認番号:2012-014)。なお,対象者には書面にて同意を得た。【結果】棘上筋筋厚は他動保持時,セラバンド負荷時の条件において,トレーニング介入前と比較し,トレーニング介入後に有意に増大した(p<0.01)。最大等尺性肩甲骨面挙上筋力はトレーニング介入前後で有意な変化を認めなかった(p>0.05)。【考察】先行研究より,筋厚は筋活動を反映すると報告されていることから,トレーニングによる棘上筋筋厚の増大は棘上筋筋活動の増加を示唆していると考えられた。しかし,最大等尺性肩甲骨面挙上筋力に変化は認められなかった。最大等尺性肩甲骨面挙上は,運動時に三角筋による張力加重が生じるため棘上筋の筋張力に対する寄与は少ないと報告されている。そのため,最大等尺性肩甲骨面挙上筋力測定は,棘上筋の機能向上を反映する指標としては不十分であり,トレーニング介入前後で変化が認められなかったと考えられた。今回の研究では,対象者を健常成人男性とし,ECTの介入効果を検証した。しかし,実際に臨床で棘上筋トレーニングを実施する対象は,腱板断裂や反復性脱臼等の疾患を有する者である。そのため,今後は,実際に棘上筋の機能を高める必要のある対象者に対しトレーニングの効果を検証していく必要がある。また,ECTと同様に,従来から実施されてきたFull can trainingとの比較を検討し,臨床現場において,それぞれのトレーニングをどのような特徴のある患者に適応させるのかを検討していく必要がある。【理学療法学研究としての意義】ECTによる治療介入に対して,棘上筋筋活動量の向上が認められ,理学療法としてのエビデンスを構築する一助となった。
1 0 0 0 OA 身体活動量評価指標の検討
- 著者
- 筒井 優 中俣 恵美 有末 伊織 酒井 菜美 糸乘 卓哉 中村 達志 峯林 由梨佳
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.46 Suppl. No.1 (第53回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.G-62_1, 2019 (Released:2019-08-20)
【目的】 超高齢社会を迎える日本では、在宅医療・介護が推進され地域包括ケアシステムの構築や健康日本21(第二次)に代表される疾病・介護予防など予防施策に力が注がれている。先行研究において、機能維持と身体活動量には密接な関係があると指摘されており、身体活動量を把握し、維持・向上を目指すことで、生活習慣病や自立度の低下など将来的な疾病の予防も可能であると考える。現在、身体活動量を評価する指標としてLife space assessment(以下LSA)や歩数計が広く用いられている。本研究では、LSAと腕時計型歩数計を用い身体活動量を評価し、両者のメリット・デメリットを検証するとともに両者を補填できる新たな評価指標の検討を目的とした。 【方法】在宅脳卒中患者12名(男性9名・女性3名、平均年齢68.1±9.9歳、発症後の経過年数15.6±7.5年)を対象に、LSAによる身体活動量の調査に加え、腕時計型測定装置ChargeHR(fitbit社製)を使用し、1週間装着(入浴時除外)を依頼、1日の歩数を調査をした。LSAと歩数の関連性は統計解析ソフトSPSSを用い、Spearmanの順位相関係数による解析を行った。さらに、アンケートを作成し、移動手段・活動内容・歩行時間を個別調査し身体活動量との関係を検討した。 【結果】LSA平均値が59点±29、歩数平均値が6367±3994歩であった。LSAと歩数に関する解析結果では相関係数r=0.618、有意確率p=0.043となり中等度の正の相関が認められた。しかし、LSAが51点と同得点の対象者間でも歩数に約5000歩の差異があるなど、LSAの得点と歩数に大きな差が生じた対象者もいた。LSAと歩数に差がみられた対象者3名をアンケートにて個別分析すると、歩行時間が長くその主な内容は近隣の散歩であった。 【考察】LSAと歩数には相関がみられるが対象者間で差異が生じていることが明らかとなった。その要因として①LSAは歩行補助具を用いると点数が低値となる②LSAが同程度であっても介助者による車での送迎より公共交通機関を利用する事で活動量が高値となるなど移動手段により歩数に差異がでる③日課として近隣を散歩しているなど移動先での活動内容や活動習慣が影響した事が考えられた。これらの事よりLSAは、生活の広がりを把握する事が可能だが、歩数には歩行時間・移動手段・活動内容が影響する為、実際の身体活動量とするには課題がある事が明らかとなった。一方腕時計型歩数計は、詳細な身体活動量の調査をする事が可能であり具体的な数値としてフィードバックが可能である為、意欲向上に繋がるメリットがあったが、アプリとの連動など管理が複雑なうえ機器が高価であり、データ収集には人的・時間的・金銭的に負担が大きく、個別調査には有用だが大規模調査を行うのは困難である。今後大規模調査を行うには、LSAで把握できない身体活動量に影響を及ぼす因子である歩行時間・移動手段・活動内容を聴取し点数化できる評価指標を検討する必要がある。 【倫理的配慮,説明と同意】本人に十分な説明のうえ、研究協力の同意を文書で得た。また、研究に参加しなくても何ら不利益を受けないこと、一旦承諾してもいつでも中断できることを保証した。関西福祉科学大学倫理審査委員会の承認を得た。承認番号【1601】
1 0 0 0 OA 自律神経活動を用いたポジショニング評価の可能性
- 著者
- 中俣 恵美 岡本 加奈子 横井 賀津志 甲斐 悟
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.2 (第51回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.1339, 2016 (Released:2016-04-28)
【はじめに,目的】高齢化や認知症患者の増加に伴い,医療・福祉現場では要介護高齢者の重度化が目立つ。経口摂取が困難な終末期を迎えると,生活の大半を静的姿勢が占めることになる。このような状況において,ポジショニングは,重要な介入方法の一つとなる。ポジショニングの目的として褥瘡予防や拘縮予防はもちろん,重度要介護高齢者では積極的な姿勢ケアによるリラクセーションは特に重要であると考える。しかし,終末期を迎えると言語機能も損なわれ,自身の要望や苦痛を訴えることができないため,そのケアは支援者の能動的なものに移行する。それゆえに,ポジショニングによる主観的満足感を確認,評価することが困難となる。そこで我々は,ポジショニングの有無による心拍数と自律神経活動を測定し,安楽の状況を評価できるか検証した。【方法】研究に同意を得られたポジショニングケアを必要とする症例3名(障害高齢者の日常生活の自立度B2:1名,C2:2名)。ポジショニングなし(背臥位)とポジショニングあり,それぞれの状況で体圧分布〈ニッタ社,BPMS〉,および5分間,自律神経活動と心拍数を測定した。ポジショニングの設定は①接地面積を広くする,②体圧をできるだけ分散する(除圧),③肩甲帯,骨盤帯,体幹での回旋(捻じれ)の改善を基本とし肢位の決定を行った。自律神経活動は,MemCalc Bonaly Light(GMS社)を用い,スペクトル解析から低周波成分(LF:Low frequency,0.04~0.15Hz)と高周波成分(HF:High frequency,0.15~0.40Hz)を計算し,HFを副交感神経活動指標に,LF/HFを交感神経活動指標にした。【結果】A氏:ポジショニングなしからありへの副交感神経活動の変化は,30.8±6.3から43.2±11.2に上昇,交感神経活動の変化は0.4±0.3から0.6±0.6に低下した。心拍数の変化は,60.9±0.8拍/分から58.1±0.3拍/分に低下した。B氏:ポジショニングなしからありへの副交感神経活動の変化は,296.2±197.2から373.4±508.4に上昇,交感神経活動の変化は8.2±14.7から0.8±0.6に低下した。心拍数の変化は,96.7±7.8拍/分から95.2±1.4拍/分に低下した。C氏:ポジショニングなしからありへの副交感神経活動の変化は,2732.4±1949.7から985.7±735.2に低下,交感神経活動の変化は,2.1±2.7から0.5±0.3に低下した。ポジショニングなしのときの副交感神経活動および交感神経活動の変動は激しく,安定しなかった。【結論】リラックス状態と副交感神経活動には,密な関係があるといわれている。今回の研究においても同様の傾向がみられ,重度要介護高齢者においてポジショニングの有無によって心拍数と自律神経活動に変化が生じた。この変化は,リラックス状態を反映していると考えられ,安楽の状況を評価できる可能性が示唆された。そして,自律神経活動として可視化することで尊厳あるケアにつなげることが可能となると考えられる。
1 0 0 0 OA 松葉杖免荷3点歩行における最大歩行速度に影響を及ぼす運動機能
- 著者
- 増田 幸泰 中野 壮一郎 小玉 陽子 北村 智之
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.40 Suppl. No.2 (第48回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.48101929, 2013 (Released:2013-06-20)
【はじめに】 松葉杖は臨床において下肢骨折などにより免荷が必要な患者に多く用いられている歩行補助具の一つである.しかし,松葉杖免荷3点歩行(以下,松葉杖歩行)は不安定な歩行形態であり,臨床においても歩行獲得のための指導に苦慮するケースがみられる.松葉杖歩行には上肢筋力が関与しているとされ,動作解析やエネルギー消費など様々な検討が過去にもなされている.しかし,実際の臨床において松葉杖歩行を可能にするために必要な筋力以外の運動機能についての詳細な検討はあまりみられていない.そこで,本研究では松葉杖歩行に関与すると思われる運動機能として筋力に加えて,バランスや柔軟性,敏捷性などを検討することで,臨床における松葉杖歩行指導の一助とすることを目的とした.【方法】 対象は健常成人女性22名(29.0±5.5歳)とし,過去に松葉杖使用の経験がない者とした. 測定項目は松葉杖歩行,身長,体重,10m快適歩行と最大歩行の他に,筋力の指標として握力,等尺性膝伸展筋力,上体起し,柔軟性の指標として長座位体前屈,敏捷性の指標として棒反応テスト,バランスの指標として閉眼片脚立位時間とした.松葉杖3点歩行は利き足を免荷した状態での最大歩行を10m歩行路にて2回測定し,速度を算出した.快適・最大歩行速度についても同様に算出した.握力は握力計にて測定し,左右の平均値を体重にて補正した.等尺性膝伸展筋力はハンドヘルドダイナモメーターにて非利き足のみの測定を2回行い,最大値を体重で除した体重比(以下,下肢筋力)として算出した.上体起しは30秒間にできるだけはやく可能な回数を1回測定した.長座位体前屈は2回測定し,最大値を採用した.棒反応テストは5回の測定を実施し,最大と最小の値を除いた3回の平均値を算出した.閉眼片脚立位時間は非利き足が支持脚となるように立たせ,120秒を最大として2回測定し最大値を分析に用いた.統計学的分析にはピアソンの相関分析を用いて各項目の関連について検討をした.有意水準は5%未満とした.【説明と同意】 本研究の実施にあたり,事前に対象者に対して書面にて研究の目的,内容を説明し,同意の署名を得てから測定を実施した.【結果】 各項目の平均値は松葉杖歩行 76.4±22.0m/min,身長157.5±5.7cm,体重 49.2±4.5kg,握力0.6±0.1kg,上体起し16.4± 4.3回,下肢筋力 0.54± 0.14kgf/kg,長座位体前屈35.1±8.9cm,閉眼片脚立位時間55.6±43.5sec,快適歩行速度 83.8± 9.6m/min,最大歩行速度118.5±17.9m/min,棒反応テスト22.8±3.7cmであった.相関分析の結果,松葉杖歩行と握力r=0.59,上体起こしr=0.51,下肢筋力r=0.55,閉眼片脚立位時間r=0.52,最大歩行速度r=0.63の間で有意な正の相関を認めた(p<0.01).年齢r=-0.31,身長r=0.17,体重r=-0.36,長座位体前屈r=0.19,棒反応テストr=-0.33の間では相関を認めなかった.また,最大歩行速度との間では下肢筋力r=0.65,握力r=0.57,上体起こしr=0.54に有意な正の相関を認めた(p<0.01)が,その他の項目においては有意な相関を認めなかった.【考察】 本研究の結果,先行研究と同様に松葉杖歩行と上肢筋力の指標とした握力において有意な正の相関を認めた.また,上体起こしと下肢筋力の間においても有意な正の相関を認め,松葉杖歩行においては歩行に影響するとされる下肢筋力のほかに,体幹筋力の影響も考慮する必要があると考えられた.さらに,バランスの指標とした閉眼片脚立位時間においても松葉杖歩行との間で有意な正の相関を認めた.閉眼片脚立位時間は最大歩行速度との間では有意な相関を認めておらず,このことから,松葉杖歩行を安定してより速く行うためには筋力の他にバランス能力の影響を考慮する必要があると考えられた.これらのことから,松葉杖歩行を指導する前に,閉眼片脚立位時間や筋力の測定を行うことが有用ではないかと考えられた.しかし,今回の結果は健常成人女性のみの検討であり,今後は対象者の拡大や実際の患者での影響を検討していく必要がある.【理学療法学研究としての意義】 松葉杖歩行における筋力以外の運動機能の関係を示唆した結果となり,臨床において松葉杖歩行獲得の指標となる可能性を見出した.
1 0 0 0 OA 前頭葉症状を呈し、易怒性と拒否がある脳血管疾患患者に対す理学療法
- 著者
- 川上 恵治
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.34 Suppl. No.2 (第42回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.E1107, 2007 (Released:2007-05-09)
【はじめに】前頭葉損傷患者では自発性や意欲の低下、行動開始の遅延、衝動コントロールの不良などを伴うことが多く、これらの付加要因があるとリハビリテーションにのりにくい。今回、既往歴に小脳出血がある前頭葉症状を呈した症例を担当し、前頭葉症状の中核となる遂行機能障害に対し問題解決療法なる段階的教示を実施したところただちに改善が見られたが、その後拒否と易怒性のために理学療法実施が困難となった。認知症の辺縁症状を考慮して理学療法を実施した結果、著名な改善が見られた症例を経験したので報告する。【症例】62歳男性。介護老人福祉施設入所中平成18年6月14日熱発、6月19日誤嚥性肺炎で当院入院し絶食と補液。6月30日肺炎軽快。7月31日理学療法開始。既往歴は32歳腹膜炎、高血圧症、52歳小脳出血手術、多発性脳梗塞、高血圧症、平成18年1月腸閉塞。【初期評価】把握反射は両手陽性。動きは拙劣。左半身低緊張。体幹の立ち直り反応なし。意識清明。HDS-R6点。発語少ない。寝具に包まれ臥床している。寝返り、移乗動作全介助。端座位は左へ傾き立ち直ろうとせず。車椅子座位は左へ傾き背あてに押し付けている。食事動作全介助、排泄オムツ。問題点;1発動性の低下、2起居動作全介助、3食事動作全介助。ゴール:車椅子の生活、食事・トイレ動作の介助量の軽減。プログラム:1起居動作訓練、2食事動作訓練。【経過】段階的教示法に基づき動作を誘導した。起座は手すりを把持し軽介助。座位は口頭指示にて右へ重心移動可となり保持可能となった。車椅子座位は傾き、背もたれへの押し付けが減った。平行棒は介助にて1往復可能となった。食事動作は自力摂取可となったが、気が向かないと自力摂取せず、スプーンを持たせると拒否し怒った。同じように起居動作訓練も拒否し怒り実施困難となった。拒否されないように接し方を変え、一方的に誘導するのでなく本人の了解を一つ一つ得ながら実施した。その結果、拒否や暴言はなくなり訓練が可能となり食事も自力摂取するようになった。【退院時評価】拒否、易怒性が見られなくなり、食事動作は自力摂取となった。自発語が増加した。姿勢の傾きは減り体幹が安定してきた。排泄動作は訴えがなく実施できなかった。問題点:1発動性の低下、2起居動作要助、3排泄オムツ。【考察】認知症の評価は機能や生活上の問題点だけを課題抽出するのではなく、本人の能力や・願望・好みといった「したいこと」や「できること」をアセスメントする事であり、拒否や暴言は認知症の辺縁症状で、接し方により改善の可能性があると言われる。症例に対し評価の視点、接し方を変えることにより、辺縁症状が改善し理学療法の実施が可能となり効果が表れたと考える。
1 0 0 0 OA 自転車エルゴメーターとリカンベントタイプエルゴメーターのAT値の検討(測定・評価)
- 著者
- 梶原 良之 三浦 元 岩下 篤司 岩坪 明美 小田 邦彦
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.29 Suppl. No.2(第37回日本理学療法学術大会 第29巻大会特別号 No.2 : 演題抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.49, 2002-04-20 (Released:2018-03-06)
1 0 0 0 OA 訪問理学療法における障害者の就労移行支援事業へ至る要因分析
- 著者
- 新井 健司 池田 雅名 大森 豊
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.46 Suppl. No.1 (第53回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.G-86_2, 2019 (Released:2019-08-20)
【はじめに・目的】平成26年度における厚生労働省の調査によると民間企業における身体障害者の雇用は43万人を超え、毎年増加傾向にある。介護保険分野で高齢者を主な対象にしている理学療法士は機能回復や日常生活活動動作の獲得、活動参加に向かったアプローチといった医学的なリハビリテーションに偏りがちであるが、リハビリテーションの概念は職業復帰・就労といった部分も含めた広範囲なものである。特に比較的年齢が若い第2号被保険者などの場合にはそのような観点が必要であると考える。また、介護保険サービスの充実に伴い、そのような対象者も増えてきている現状である一方、必ずしも成功するとは限らないのも現状である。障害者の就労支援には、対象者の身体的側面、精神的側面、知的側面、社会的側面、職業的側面の視点からのアセスメントを要する。そして、職業訓練や適正に応じた職場の開拓、職場定着のための相談などを担う就労移行支援事業の活用が推進されている。しかしながら、就労移行率が低い事業所が多く、その背景には対象者の選定に無理があるという報告が散見される。(朝日、2016)また、これらのアセスメントはリハビリテーション職種が専門職として評価すべき点が含まれている。 したがって、理学療法士が対象者のアセスメントを行い、就労移行支援事業への適切な選定されることは障害者の雇用促進に資すると考えた。今回、訪問看護ステーションにおける理学療法士として、症例を通して、職業復帰・就労を望む障害者が就労移行支援事業の活用に至る要因を分析した。【方法】 平成24年から平成29年に当事業所から訪問理学療法を受けた、職業復帰・就労を希望する身体障害がある者5名を対象とした。まず、対象者の基本属性、家族構成、経済状況、就労移行支援事業への活用の有無を調査した。就労支援に必要な身体的・精神的側面のアセスメントとしてFunctional Independence Measure(FIM)、知的側面として自己決定と判断力に関わる障害の有無、Mini Mental State Examination、社会的側面としてLawtonの尺度、職業的側面として職歴を後方視的に調査し、就労移行支援事業の活用に至る要因を分析した。【結果】 対象者は日常生活・屋外活動が自立されており、職業的側面を除くアセスメント項目に大きな差は見受けられなかった。対象者のうち、就労移行支援事業の活用に至ったものは、独居や未婚などの家族・経済状況を有している3名であった。その他2名は、主婦の専従・生活保護受給といった経済状況の変化に伴い、就労自体を断念していた。【結論】障害者の就労に関して、家族構成や経済状況等の要因が大きく関わる傾向が捉えられた。訪問理学療法士は、障害者の就労支援に関わるアセスメントを理解し、就労移行支援事業への適性を検討していくべきである。【倫理的配慮,説明と同意】ヘルシンキ宣言に基づき、本研究の目的を説明し、書面にて同意を得た。
1 0 0 0 OA 石灰沈着性腱炎に対する新しい治療法 ―体外衝撃波治療機器を用いて―
- 著者
- 木原 太史 梅崎 英城 平山 英子 西嶋 美昭 森 清 前原 洋二 吉田 健治
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.32 Suppl. No.2 (第40回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.C1006, 2005 (Released:2005-04-27)
【目的】肩関節の激痛を訴え来院する患者の中で、石灰沈着性腱炎は日常よく遭遇する疾患である。従来、保存療法として、急性期には局所安静、非ステロイド系消炎鎮痛剤の内服、局麻剤やステロイドの局注、沈着した石灰の穿刺・吸引を行った。疼痛が持続した慢性期には、関節拘縮防止のための関節可動域訓練や観血的に石灰沈着物を摘出する方法がとられていた。しかし、局注を多用することによる腱・軟部組織の変性や、穿刺、吸引による腱板の医原性の断裂などの問題が起こる危険性があった。近年、体外衝撃波治療(extracorporeal shock wave therapy)(以下ESWT)による石灰沈着性腱炎に対しての治療法がヨーロッパを中心に行われている。今回、当院でも石灰沈着性腱炎に対し、ESWTを施行し、疼痛緩和、機能向上に対し効果が得られたため、若干の知見と考察を加えてここに報告する。【方法】当院外来患者のうち、石灰沈着性腱炎と診断された7名(男性3名、女性4名)に対し、ESWTを施行した。平均年齢60±9.9歳(50-79歳)、発症から治療までの平均日数37±67.4日(1-182日)であり、患者に説明と同意を得てESWTを施行した。機器は低エネルギー体外衝撃波治療機器「Orthospec(オルソスペック)メディスペック社」を用い、X-Pにて石灰の沈着部位を確認し、その沈着上の皮膚に機器の外膜を直接当てて衝撃波を照射した。照射は約1回/Wの間隔で、平均1.7+1.1回(1-4回)行った。患者の満足が得られるか、医師の中止指示が出るまで行い、治療期間の平均は5.7±5.6日(1-15日)であった。評価は疼痛(4ポイントスケール)、機能(日本整形外科学会肩関節評価表)(以下日整会表と略す)を用いた。【結果】ESWTを1回施行後、4ポイントスケールは有意に低下した(p=0.0465)。機能面では、日整会表の合計点が有意に改善した(p=0.0291)。日整会表の中でも、肩関節可動域の屈曲、外転は有意に改善した。(屈曲:p=0.03、外転:p=0.0053)。ESWT実施後、発赤など副作用の訴えはなかった。【考察】当院では、現在までに、92例の疼痛性疾患に対しESWTを試行してきた。その中でも、今回は7名の石灰沈着性腱炎に着目し報告したが、疼痛緩和、機能改善に対し効果を得ている。疼痛緩和後のX-Pにて確認すると、沈着していた石灰像が粉砕、縮小化されており、このために疼痛緩和、機能改善が得られたと思われる。さらに治療期間の短さや、ESWT終了後1ヶ月での副作用なども見られていない事などから、ESWTは石灰沈着性腱炎に対して有効な治療法であるといえる。
1 0 0 0 OA 広背筋のトレーニング効果が呼吸機能に与える影響について
- 著者
- 田辺 康二 洲崎 俊男
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.30 Suppl. No.2 (第38回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.398, 2003 (Released:2004-03-19)
【はじめに】呼吸筋トレーニングにおいて対象となる筋は主に横隔膜であるが、これを除けば呼気筋群あるいは吸気筋群に対してアプローチすることが多く、単独の呼吸補助筋に対して行っている報告はほとんどみられない。 今回、強い運動強度において呼気に活動するという広背筋(以下LD)に着目し、健常人を対象としてLDの筋力・筋持久力の増加が換気に与える影響について検討し、若干の知見を得たので報告する。【対象と方法】計画を説明し同意を得た健常男性20名を対象とした。トレーニングはLDに対してラバーバンドを用い、初回時に測定した30%MVCの負荷で疲労困憊に至る回数を各自行わせ、8週間の筋持久力トレーニングとして行った。トレーニングの前後にはLDの筋力・筋持久力の評価および肺機能検査を実施した。また、LDと同様の呼気筋として働く腹直筋(以下RA)についても筋力・筋持久力の評価を行った。 筋力・筋持久力の評価にはトルクマシーンを用いた。LDは腹臥位で肩関節中間位から伸展方向に最大等尺性収縮を行わせ、ピークトルクとその値の50%まで減衰する時間を測定した。RAには体幹屈伸筋力測定機を用い体幹直立位から屈曲方向に最大等尺性収縮を行わせ、ピークトルクとその値の70%まで減衰する時間を測定した。呼吸機能検査はスパイロメータを用い%肺活量、1秒率、%MVVを測定した。統計学的処理はトレーニング前後の同項目についてt検定を用い、有意水準は1%とした。【結果】トレーンニング実施頻度は平均4.0回/週(遂行率57.3%)であった。LDのピークトルクはトレーニング前0.54、後0.63Nm/kg、筋持久力はそれぞれ14.8、28.1秒であり、各項目に有意な差を認めた。RAはLDのトレーニング前後でピークトルクや筋持久力に有意な差を認めなかった。肺機能検査では%肺活量、1秒率はそれぞれトレーニング前107.6、92.9%、後111.1、91.9%であり、各項目に有意な差は認めなかった。また、%MVVはトレーニング前119.7、後132.2%であり、有意な差を認めた。【考察】トレーニング後にLDの筋力に増加(17%増)がみられたが、呼気筋の瞬発性の要素を含んでいる1秒率を変化させるまでに至らなかったと思われる。 またMVVが増加した理由として、呼気時にRAとともに筋力と筋持久力が増加(90%増)したLDとの同時収縮による活動が影響したと考えられる。これにより筋疲労による経時的な腹腔内圧の減少が抑えられ、横隔膜の挙上や肋骨の引き下げを補助し、呼気量を増すよう作用したと推察される。したがってLDの筋持久力の増加は、努力性の最大換気時に呼気補助筋として有効に作用していると思われる。 呼吸器疾患の症例を対象として考えた場合、呼吸不全の原因として胸郭のポンプ機能不全があげられるが、LD単独の筋持久力の増加は低換気を改善させる可能性が示唆される。
1 0 0 0 OA 足部の筋緊張が多関節運動連鎖により下肢近位筋・体幹筋群に及ぼす影響
- 著者
- 足立 直之 坂井 健一郎 山本 絵理香 加藤 浩
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.34 Suppl. No.2 (第42回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.C0986, 2007 (Released:2007-05-09)
【緒言】本研究の目的は,足部の筋緊張を高めた歩行が,足関節より近位の膝関節,股関節,及び体幹筋群へ及ぼす影響を動的表面筋電図解析の視点から検討することである.【対象】対象者は過去に上下肢及び体幹に機能障害の既往歴を有さない健常男性19例(平均年齢:21.9±0.9歳,平均身長:168.8±4.4cm,平均体重:61.6±5.6kg)であった.また,全例には研究の目的を説明し同意を得た.【方法】表面筋電計は,TELEMYO 2400T(NORAXON社製)を使用し,被験筋は,脊柱起立筋,外腹斜筋,腹直筋,大殿筋,中殿筋,大腿筋膜張筋,大腿直筋,内側広筋,外側ハムストリングス,内側ハムストリングス,前脛骨筋,内側腓腹筋,内側ヒラメ筋とした.自由歩行及び,右側の母趾と第2趾間の付け根にパッドを挟んだ歩行(以下,パッド歩行),最大随意収縮の各筋活動を測定した.統計学的処理は,1標本t検定を用い,自由歩行とパッド歩行との%IEMGの差を検定した.【結果】パッド歩行時の筋緊張の有意な高まりは,全歩行周期において多関節筋が単関節筋に比べ多く認められた.また,遊脚相が立脚相に比べ多く認められた.筋緊張の有意な高まりは,歩行周期の0~6%で内側ヒラメ筋,前脛骨筋,内側ハムストリングス,大腿直筋,大腿筋膜張筋,外腹斜筋,脊柱起立筋,88~92%で内側ヒラメ筋,前脛骨筋,内側広筋,大腿筋膜張筋,外腹斜筋,腹直筋において下肢遠位筋群から体幹筋群までの連鎖が認められた.前脛骨筋の筋緊張の有意な高まりは,歩行周期の大部分で認められた.【考察】パッド歩行では,自由歩行時と比べ筋緊張の高まりが足部から体幹まで連鎖しており,協同して筋緊張が高まっていた筋も認められた.そこで本研究では立脚相と遊脚相に分けて,運動連鎖の特徴を検討した.立脚相は下肢遠位部が床で固定されている状態であるため,運動連鎖の視点から見るとCKCである.CKCは多関節運動,協同運動を行い,運動連鎖を引き起こすため,足部の状態によって,足関節より近位の関節筋群にも影響を及ぼすと考えられる.正常歩行では,遊脚相は下肢遠位部が固定されておらず,自由に運動ができるため,運動連鎖の視点から見るとOKCの状態である.しかし,パッド歩行では,足部の筋緊張が高まったため,下肢遠位部の自由が阻害され,CKCに近い状態になったと考えられる.つまり,足部で高まった筋緊張は,膝関節,股関節及び体幹筋群に運動連鎖を生じさせたと考えられる.臨床において,下肢遠位部の筋緊張が高い患者は,遊脚相では常にCKCの状態である可能性が考えられる.
1 0 0 0 OA 体幹回旋が上肢挙上時における肩甲骨・鎖骨の動態に及ぼす影響
- 著者
- 永井 宏達 建内 宏重 高島 慎吾 遠藤 正樹 宮坂 淳介 市橋 則明 坪山 直生
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.38 Suppl. No.2 (第46回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.AeOS3002, 2011 (Released:2011-05-26)
【目的】 肩関節に疾患を有する症例では,肩甲骨,鎖骨の動態に異常をきたしていることが多い.そのため,臨床場面では,セラピストが肩甲骨や鎖骨の動態を正確に把握し,適切な肩甲骨,鎖骨の運動を獲得することが重要である.一般に,肩関節疾患を有する患者における肩甲骨の異常運動としては,肩甲骨の内旋(外転),前傾,上肢挙上時の肩甲骨の挙上,下方回旋などが報告されており,上肢の挙上動作を行う上では障害となる.一方,肩甲骨の動態・アライメントに影響を及ぼす因子として,脊柱が後彎することで肩甲骨の前傾,内旋,下方回旋は生じやすくなるとされる.しかしながら,脊柱の回旋が肩甲骨,鎖骨の動態に及ぼす影響は明らかにはされていない.日常生活場面での上肢挙上動作には,体幹の回旋を伴っていることも多く,体幹回旋による影響を明らかにすることは臨床的に重要である.そしてこれらの情報は,より効果的な肩甲骨トレーニング開発の一助となると思われる.本研究の目的は,体幹回旋が上肢挙上時における肩甲骨・鎖骨の動態に及ぼす影響を明らかにすることである.【方法】 対象は健常若年男性19名(20.9±0.7歳)とし,測定側は利き手上肢とした.測定には6自由度電磁センサーLiberty (Polhemus社製)を用いた.5つのセンサーを肩峰,三角筋粗部,胸骨,鎖骨中央,S2に貼付し,肩甲骨,鎖骨,上腕骨の運動学的データを収集した.測定動作は,座位での両上肢挙上動作とし,矢状面において3秒で挙上し,3秒で下制する課題を実施した.測定回数は,体幹回旋中間位・体幹同側(測定側)回旋位・反対側(非測定側)回旋位でそれぞれ3回ずつとし,その平均値を解析に用いた.体幹の回旋角度は、それぞれ30°に規定した。なお、解析区間を胸郭に対する上肢挙上角度30-120°として分析を行い,解析区間内において10°毎の肩甲骨,鎖骨の運動学的データを算出した.なお,肩甲骨,鎖骨の運動角度は,胸郭セグメントに対する肩甲骨・鎖骨セグメントのオイラー角を算出することで求めた.肩甲骨は内外旋,上方・下方回旋,前後傾の3軸とし,鎖骨は鎖骨前方・後方並進,挙上・下制の2軸として解析を行った.統計処理には,各軸における肩甲骨・鎖骨の角度を従属変数とし,体幹の回旋条件(中間・同側・反対側),上肢挙上角度を要因とした反復測定二元配置分散分析を用いた.有意水準は5%とした.【説明と同意】 対象者には研究の内容を紙面上にて説明した上,同意書に署名を得た.なお,本研究は本学倫理委員会の承認を得ている.【結果】 上肢挙上時の肩甲骨の外旋は,体幹を同側に回旋することで有意に増大していた (同側回旋位>中間位>反対側回旋位,体幹回旋主効果: p<0.01) 。また、肩甲骨の上方回旋も、体幹を同側に回旋することで有意に増大していた(同側回旋位>中間位=反対側回旋位,体幹回旋主効果: p<0.01)。肩甲骨の後傾は体幹中間位よりも両回旋位の方が増大していた(同側回旋位=反対側回旋位>中間位,体幹回旋主効果: p<0.05)。一方、上肢挙上時の鎖骨の後方並進は体幹を同側に回旋することで有意に増大していた (同側回旋位>中間位>反対側回旋位,体幹回旋による主効果: p<0.01)。鎖骨の挙上は体幹を反対側に回旋をすることで有意に増大していた(反対側回旋位>中間位>同側回旋位,体幹回旋主効果: p<0.01) 。【考察】 本研究の結果,上肢挙上時に体幹を同側に回旋することで、肩甲骨は外旋,上方回旋が大きくなり,鎖骨は後方並進が大きく、挙上が小さくなることが明らかになった.体幹を反対側へ回旋させると、逆の傾向がみられた。これらの結果は,体幹の回旋状態が,肩甲骨の動態に影響を及ぼしていることを示唆している.体幹同側回旋に伴う,これら肩甲骨,鎖骨の動態は,肩関節疾患を有する患者にみられる異常運動とは逆の動態を呈していると思われる.体幹を同側に回旋することにより,肩甲骨が外旋方向に誘導され,肩甲骨周囲筋の筋力発揮が得られやすくなったことが影響している可能性がある.一方で、体幹を反対回旋した場合の上肢挙上時には、肩甲骨では上肢挙上には不利な方向へ運動が生じる傾向にあり、鎖骨では上肢挙上動作を代償する挙上運動が観察された。【理学療法学研究としての意義】 肩甲骨の内旋,下方回旋の増加,鎖骨後方並進の減少は,肩関節疾患を有する多くの患者に特徴的にみられる.また,上肢挙上時の過度な鎖骨の挙上も,僧帽筋上部線維による代償的な肩関節挙上動作として多くみられる.これらの特徴を有する症例に対しては,体幹の回旋も取り入れながらプログラムを実施することで,正常に近い肩甲骨運動を促通し,より効果的に理学療法を進められる可能性がある.
1 0 0 0 OA 医療・福祉領域の機械工学的課題
- 著者
- 縄井 清志 仙波 浩幸
- 出版者
- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.36 Suppl. No.2 (第44回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.E3P1239, 2009 (Released:2009-04-25)
【目的】本研究は、機械・工学的領域を研究する理学療法士に対して、機械・工学的支援の問題点と期待をまとめることを目的に行った.【方法】対象は、第43回日本理学療法学術大会における演者および座長である.対象者の選定は、「ロボット」「車いす」などの機械・工学的なキーワードのある研究とその座長とした.方法は、公演中に質問を行うことと、公演後に質問の了解が得られた研究者に面接調査を行った.質問内容は、「理学療法士の視点からどんな機械が望まれますか?」「工学系の人と連携するにはどうしたらいいですか?」などである.情報の処理は、聴取したコメントの内容について、機械がICFの領域のどこに影響を与えるか、で分類した.具体的には、「環境因子」に含まれる機械が、「心身機能・構造」に与える影響、「活動」に与える影響、「参加」に与える影響、「個人因子」に与える影響にコメントを分類した.また、医学と工学の連携に関するコメントは「管理・連携」としてコメントを分類した.なお、重複するコメントも加算した.【結果】研究者16名から話を伺えた.また、研究者の資料からも情報を収集した.生活機能では、活動領域への支援のコメントが最も多かった.また、素材の工夫や小型化など、機械自体への改善の要望も多かった.医療と工学の連携については、医療職はクライアントの代弁者として工学専門家に積極的にリクエストしていくことの必要性や、キーパーソンの必要性、常設の機械展示場の希望などがあった.【考察】健康は、単に病気ではないということではなく、人機能と環境等が調和された穏やかな状態(well-being)である.この人機能と環境を調和させるのに技術が貢献する.「技術」は、「人と万物との共生」と「人と万物との調和」を目指すものであることから、本研究では、健康の概念であるICFを使って医療福祉領域の機械工学的課題の整理を試みた.結果は、自立に向けた活動領域への機械工学的支援への要望が多かった.また、心身機能面や参加へのリクエストがないことから、医師や社会福祉士などとも連携して医工連携してゆく必要性が示唆された.さらに、認知機能の低下した人も安全に使用できるように、モノ自体がその使い方を強く示したデザインや機能も必要であろう.今回の調査では医工連携を推進するにはキーパーソンが重要であるとのコメントが多かった.しかし、このキーパーソンの機能はICFには認められないため「管理・連携」の領域を加えてm-ICF modelを創作した.健康を他職種と推進する上で求められる概念であると考えられる.