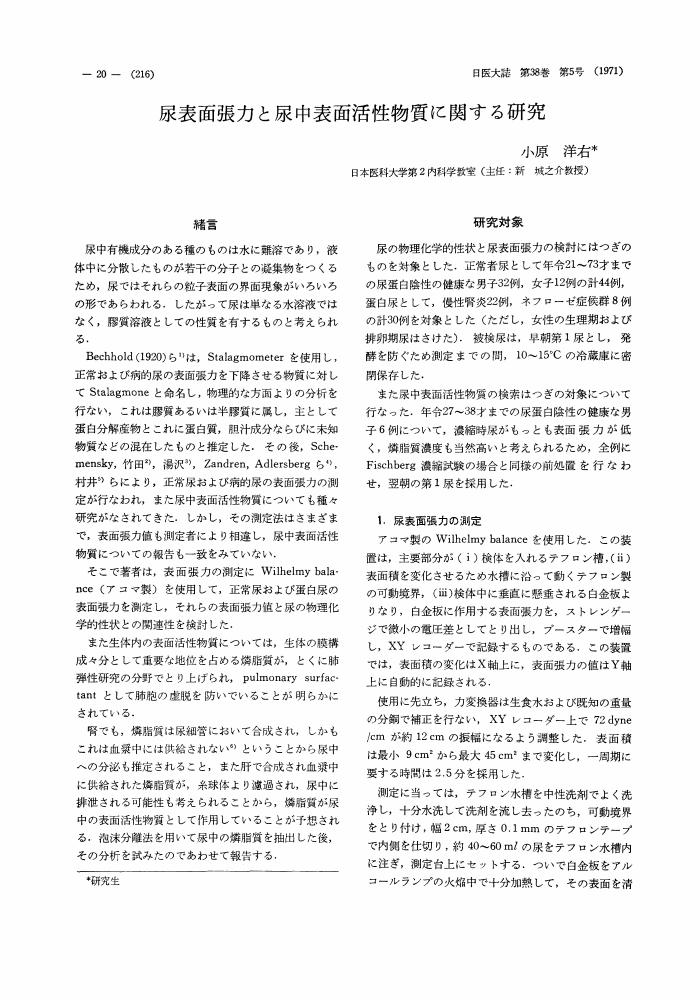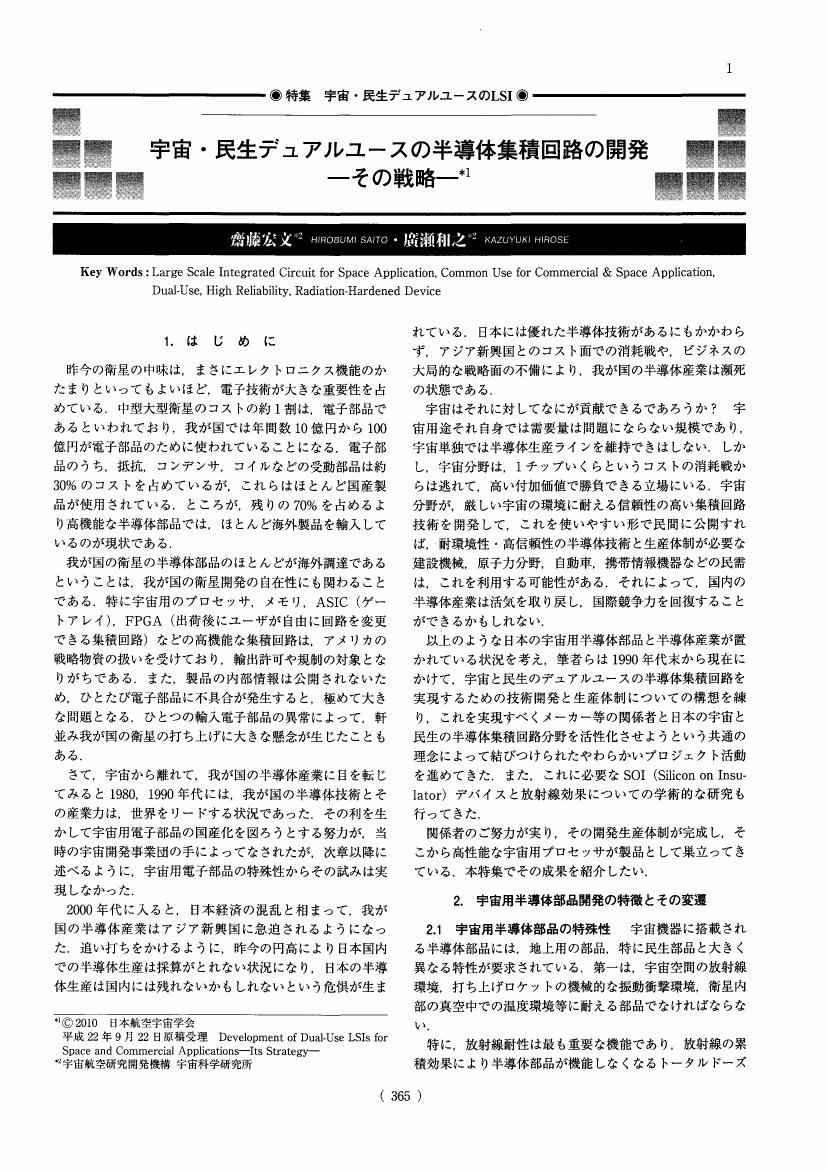抗性腺作用を有するメラトニンと思春期発来との関連が注目されているが未だ明確ではない。我々は、メラトニンのゴナドトロピン分泌抑制作用は、Gn-RHのpulse generatorに作用し、LHpulseの発現を減弱させる機序に基づくことを明らかにしてきた。また、松果体のメラトニン産生能は、初回排卵後、排卵周期の確立過程で減少すること、さらに、このメラトニンの産生能動態に対して卵巣より分泌の増量がみられるエストロゲンが強く関与していることを明らかにしてきた。思春期のメラトニン産生能に及ぼすエストロゲンの作用機序を明らかにするためにラットを用いて卵巣摘除モデル、エストロゲン負荷モデルを作製し、メラトニン産生酵素である松果体内N-acetyltransferase(NAT)とHydroxyindole-O-metyltransferase(HIOMT)に注目し、検討した。NAT活性は、腟開口期の6週には有意に増量し、排卵周期確立過程の8週では減少、以後、同一レベルで推移し、メラトニンと全く同一の変動パターンを示した。一方、HIOMT活性は、4週より6週にむけて著増し、12週まで漸増する変動パターンであった。初回排卵が認められる6週に卵巣摘除を行うと、NAT活性は8週での減少は見られず、逆に有意の増加を示した。一方、HIOMT活性は正常群との差は見られなかった。6週に卵巣摘除し、エストロゲン(E2 benzoate)を連日皮下投与した群では、NAT活性は0.1μg投与群では、卵巣摘除で認められた増量を有意に抑制し、正常群と同一のパターンを示した。一方、HIOMT活性は0.1μg投与では正常群と同一のパターンを示した。1.0μg投与群では両酵素活性ともに正常群より有意に低値であった。以上の結果より、思春期から性成熟期にかけてのメラトニン産生能は、卵巣より分泌されるエストロゲンが主にNAT活性を強く規制することで調節されていることが示唆された。また、エストロゲンのメラトニン産生抑制作用はNAT、HIOMT活性を抑制することに基づくことが示されたが、その感受性には両酵素間で明らかな差があることも示唆された。
- 著者
- 入江 信一郎
- 出版者
- 日本情報経営学会
- 雑誌
- 日本情報経営学会誌 (ISSN:18822614)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.94-104, 2011-07-15 (Released:2017-08-07)
- 参考文献数
- 18
This paper proposes the significance of institutional analysis through the observation of strategies of action. In this paper, the strategies of action, exercised by a venture firm facing the barrier that is constructed by the regulation, are analyzed. The regulation per se is not the barrier for the venture firm. Instead, the practices that are constructed according to the regulation stand up as a barrier against the venture firm, and that practices also could become the resource for the venture firm. At the methodological view, through the observation of strategies of action, we would become able to reconsider the taken for granted concepts.
- 著者
- 橘 基
- 出版者
- 素粒子論グループ 素粒子論研究 編集部
- 雑誌
- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.3, pp.C103-C114, 2000-12-20 (Released:2017-10-02)
1 0 0 0 OA 3.アメリカの神経学と日本の神経学
- 著者
- 平野 朝雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.8, pp.2249-2252, 2002-08-10 (Released:2008-06-12)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 日米貿易摩擦の国際的位相に関する実証研究
1 0 0 0 OA 50周年記念講演 日本神経学会―誕生と発展―
- 著者
- 高橋 昭
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.11, pp.724-730, 2009 (Released:2009-12-28)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1 2
日本神経学会は1960年4月15,16両日福岡市において勝木司馬之助九州大学内科学教授を会長として第1回「日本臨床神経学会」総会を開催,1963年第4回総会(大阪)において「日本神経学会」と改称,2009年仙台市において第50回総会を迎えた.学会の機関誌『臨床神経学』は1960年10月に創刊号を発行,学会名は変更になったが,会誌名の変更はなく今日に至る.今日の「日本神経学会」の誕生には,多くの紆余曲折があり多難な道程であった.1902年には「日本神經學會」が設立されたが,精神医学関係者の会員が増加し,1935年に「日本精神神經學會」と改称された.この学会では勝沼精藏が神経学関係者として久しく孤城を守っていたが,1946年から冲中重雄らが加わり,1954年に同会の「神経学部門」が独立した.1956年には「内科神経同好会」が結成,1959年11月9日第5回内科神経同好会(東京)において「日本臨床神経学会」設立が承認され,1960年4月に「日本臨床神経学会」が設立された.
1 0 0 0 金融機関としての両替商の発展に関する研究
- 著者
- 葛原 茂樹
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.1-19, 2020 (Released:2020-01-30)
- 参考文献数
- 61
日本神經學會は1902年に神経学・精神医学の合同学会として創設されたが,神経学部門の衰退により1935年に日本精神神經學會に改称された.第二次大戦後に,神経学は内科学と精神医学の狭間から復活して興隆し,困難を克服して1960年に日本臨床神経学会を設立し(1963年に日本神経学会に改称),1975年に「神経内科」が医療法の診療科名として認められた.その後の発展はめざましく,2018年に会員数は約9,000名,専門医数は5,500名以上に達した.当面する神経内科専門医基本領域化も神経学のアイデンティティ確立の一環と見做すことができる.歴史の教訓を今日の課題解決に活かすという観点から,本学会の116年を顧みる.
1 0 0 0 OA ベイズ理論から帰結する現実観の変容
- 著者
- 田口 茂
- 出版者
- JAPANESE PSYCHOLOGICAL REVIEW
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.16-24, 2019 (Released:2019-11-22)
- 参考文献数
- 24
Asai (2019) discusses a transformation of the view of reality resulting from the Bayesian theory of inference. The current paper offers philosophical interpretations concerning the significance, scope, and possible development of Asai’s discussion, which are especially based on a phenomenological point of view. Asai’s Bayesian view of reality is closely related to phenomenology. It implies a denial of determinism and naive realism. However, these traits of Asai’s view can signify a more moderate and scientific attitude. What an individual experiences as reality is the effect of certain filters that his or her experience has. Asai calls this effect “attention”; however, it is better described as “consciousness.” His interpretation of reality as mutual interference of waves is convincing and closely matches the quantum theoretical view of reality. Finally, such a transformation of the view of reality can positively affect the view of “mental disorder.” The aim of psychiatric treatment should not be to conform patients to the “only one same reality” (which is illusory), but to gear (or accommodate) different realities to each other.
1 0 0 0 OA 悪性脳腫瘍における化学療法とアポトーシス
- 著者
- 志村 俊郎 寺本 明 吉田 大蔵 足立 好司
- 出版者
- 日本医科大学医学会
- 雑誌
- Journal of Nippon Medical School (ISSN:13454676)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.74-77, 2001 (Released:2001-11-30)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 「太平記史観」の批判的検討と南北朝期政治史の再構築
1 0 0 0 OA 尿路結石の排石誘発法
- 著者
- 吉田 種臣 上田 忠和 水尾 敏之 山内 昭正 池上 茂 横川 正之
- 出版者
- The Japan Society for Oriental Medicine
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.23-28, 1982-07-20 (Released:2010-03-02)
- 参考文献数
- 11
1 0 0 0 マグネシウムの必要性とその作用
- 著者
- 糸川 嘉則 田沼 悟 小林 昭夫 森井 浩世 矢野 秀雄 五島 孜郎 KIMURA Mieko YOSHIDA Masahiko
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 総合研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 1986
マグネシウムの必要性とその作用を解明するため実態調査, 動物実験, 臨床的研究を実施した. 実態調査においては, 種々な階層を対象にして聞き取りによる食事調査を行い, マグネシウム摂取量を算出した. その結果1日のマグネシウム摂取量は155〜300mgで, 出納試験から推定されるマグネシウム必要量を下回る摂取状況であることが判明した. 小動物による実験ではリン摂取量の増加により発生する異常がマグネシウム投与により抑制される事, リン欠乏食にすると高マグネシウム尿が発生するが, 腎不全状態にしてもマグネシウムの尿細管での再吸収抑制が機能している事, 脳卒中易発症ラットにマグネシウムを負荷すると尿中マグネシウムとカルシウムの排泄量が増加し, 血圧の上昇が軽度抑制される事が解明された. めん羊を用いた研究では甲状腺, 副甲状腺摘出めん羊では尿中マグネシウム排泄量が多くなり, 低マグネシウム血症を呈し, 絶食をさせても尿中マグネシウム排泄の増加は続き血中マグネシウム濃度は急激に低下した. 又, マグネシウムの投与による血中のマグネシウムの上昇が大きく, 副甲状腺ホルモンは腎臓でのマグネシウム再吸収を調節し, カルシトニンは血中マグネシウムの上昇を押える作用がある事が示唆された. 臨床的な研究ではリンパ球内マグネシウム濃度を指標とした結果, 超未熟児はマグネシウム欠乏状態にある事が解明され, マグネシウム含有輸液により改善する事が示された. 一般人では初老期からマグネシウム欠乏傾向になる. 小児ネフローゼ症候群では低マグネシウム血症を呈し, ステロイド療法を実施する事により正常化する事が解明された. 腎不全患者では高マグネシウム血症を呈するが, この病態は副甲状腺亢進症を抑制する利点もあり, その対処には検討の要がある事が示された. 更に, 細胞内のイオン化したマグネシウムを測定する方法について検討が加えられた.
1 0 0 0 OA 光と色を使った“光防除”技術―最近の進展と可能性―
- 著者
- 霜田 政美
- 出版者
- 北日本病害虫研究会
- 雑誌
- 北日本病害虫研究会報 (ISSN:0368623X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, no.69, pp.1-9, 2018-12-21 (Released:2019-12-21)
- 参考文献数
- 23
近年,昆虫の光や色に対する応答反応(光応答反応)の研究が進み,その知見を活用した害虫防除法,即ち“光防除”の研究が進んでいる.光防除は,生産現場の光環境や農業資材の色彩などを操作して病害虫の発生や侵入を抑制することから,薬剤抵抗性を獲得した害虫の防除に利用できる.また,光を用いた技術は,化学農薬を使用せずに害虫被害を抑制できることから,減農薬栽培の助けになる技術である.本稿では,昆虫の光応答反応について説明し,それらを用いた最近の技術開発の状況について具体的事例を挙げながら解説する.光防除技術が,より環境に優しい栽培体系の確立と普及につながることを期待したい.
1 0 0 0 OA 尿表面張力と尿中表面活性物質に関する研究
- 著者
- 小原 洋右
- 出版者
- 日本医科大学医学会
- 雑誌
- 日本医科大学雑誌 (ISSN:00480444)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.5, pp.216-224, 1971 (Released:2010-10-14)
- 参考文献数
- 16
1 0 0 0 神経性やせ症の重症度と自閉症傾向との関連についての検討
【背景と目的】神経性やせ症(以下AN)は、体重や体型に対する強いこだわりを持ち、進行する低体重の重大な危険性の認識が十分でないことや、体型に人としての価値が直接影響されると感じ、他の価値観を認識したり変換したりすることができないこと等の認知的特性がしばしば観察される。一方で、これらの認知的特性は、自閉症スペクトラム障害(以下ASD)における対人関係、社会性の障害、パターン化した行動や興味といった特徴と類似しており(Zucker etal., 2007)、ANの18%がASDを併存していることが報告されている(Billstedt et al., 2000)。摂食障害(ED)は、神経性やせ症(AN)、神経性過食症(BN)、過食性障害(BED)のサブタイプに大別されているが、各々の症状は多様で重複したり、長期化により同一個体でサブタイプが相互に移行したりする(Fairburn and Harrison., 2003)。従って、上記のような認知的特性の強さが病態理解の上で重要となる。これらを踏まえ、ANにおけるASD傾向の有無およびANの重症度とASD傾向との関連を調査し、重症化に関連する要因としてANにおけるASD傾向を評価・検討することを目的とした。【方法】摂食障害と診断された15-45歳の女性43名における①自己記入式質問紙「自閉症スペクトラム指標(AQ)」と「Eating Disorder Examination Questionnaire(EDE-Q)」における相関関係を数量的に判定した。さらに、②自己誘発嘔吐の有り(n=31)と無しの2群(n=12)に分け、AQスコアの差を検定した。最後に、③それぞれの群におけるAQとEDE-Qの相関関係を判定した。【結果】①全患者におけるAQとEDE-Qスコアに相関関係は認められなかった(r=-.057 ; p=0.716)。②自己誘発嘔吐なし群は、あり群に比べて、AQスコアが有位に高かった(p=0.007)。③自己誘発嘔吐あり群となし群のEDE-Qとの相関はそれぞれ(r=-.051 ; p=0.786)と(r=.58 ; p=0.05)であった。結論として、AN制限型やBEDなどの非排出型の摂食障害は、AQスコアが高い傾向があり、重症度との正の相関があった。BEDの80%が過去AN制限型からの移行型であり、AN制限型は、時間的経過を経ても排出型に移行しづらく、ASD傾向が高いことが示唆された。
1 0 0 0 OA 固定法1.化学固定
- 著者
- 永野 俊雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本顕微鏡学会
- 雑誌
- 電子顕微鏡 (ISSN:04170326)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.105-106, 2000-07-31 (Released:2009-06-12)
- 参考文献数
- 25
1 0 0 0 OA 2.低カルシウム血症 1)特発性副甲状腺機能低下症
- 著者
- 水梨 一利
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.12, pp.1964-1967, 1993-12-10 (Released:2008-06-12)
- 参考文献数
- 5
特発性副甲状腺機能低下症は,明らかな誘因を伴わずに, PTH分泌不全を来したものであり, PTHの最大分泌能の低下およびset-pointの左への移動を特徴とする. PTH作用および血清PTH値の低下に加え,外因性PTHに対する反応性の保持によって診断される.活性型ビタミンD3によって治療されているが,血清Caの上昇に伴い,高Ca尿症を来しやすいため,血清Caを正常下界に維持することが望ましい.
1 0 0 0 OA 宇宙・民生デュアルユースの半導体集積回路の開発 その戦略
- 著者
- 齋藤 宏文 廣瀬 和之
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.683, pp.365-372, 2010-12-05 (Released:2019-04-19)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1