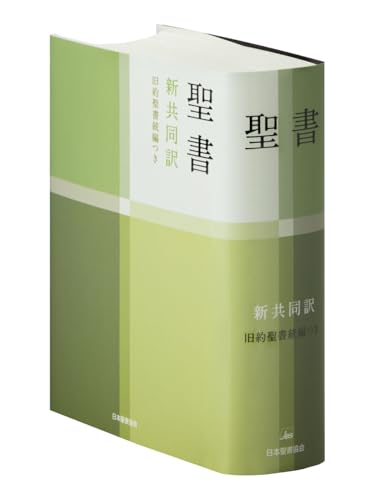2 0 0 0 IR 日本映画の新しいかたち--邦画ブームはなぜ起こったのか
- 著者
- 笹川 慶子
- 出版者
- 關西大學文學會
- 雑誌
- 關西大學文學論集 (ISSN:04214706)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.69-92, 2007-07
2 0 0 0 単旋律の進行パターンに基づく調性判別と主音推定
- 著者
- 松田 稔 秋山 好一
- 出版者
- 一般社団法人日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.4, pp.253-260, 1996-04-01
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 6
人間が音楽をどのように認知しているかを解明するために楽曲に対する統計的性質の解明が過去に盛んに行われた。その代表的なもののなかに「主音と調性の推定」がある。これらは, 音符の出現頻度などという静的な考察により行われていることが多いが, 本稿では動的な考察, つまり音符の進行確率をもとに,「主音と調性の推定」についての推定方法を提案している。それは, 個々の音高の出現確率と次の音高への進行に関する統計量に基づいた推定法で, 日本の大衆歌曲2,777曲に対して, 音高から音高への進行可能/不可能を示す可達行列により87%, 進行確率行列との相関を用いる方法により90%程度の正答率を得ることができた。
2 0 0 0 OA 糸球体上皮細胞(ポドサイト)の分子生物学(<特集>医学研究のUP-TO-DATE)
- 著者
- 淺沼 克彦
- 出版者
- 順天堂大学
- 雑誌
- 順天堂医学 (ISSN:00226769)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.11-19, 2007-03-31
- 被引用文献数
- 1
腎臓の糸球体上皮細胞glomerular visceral epithelial cellは高度に分化した細胞であり,糸球体基底膜(GBM)を外側から覆い,その外観から最近はタコ足細胞podocyteと呼ばれている.糸球体上皮細胞は血中蛋白質の最終的な濾過障壁であり,糸球体上皮細胞障害は著明な蛋白尿を引き起こす.糸球体上皮細胞障害は,多くの腎疾患や様々な実験腎炎モデルにおいて認められている.糸球体上皮細胞障害の早期には,まずスリット膜の分子構造の変化が認められ,足突起の細胞骨格の分布が変化し,足突起は消失foot process effacementして,その噛み合わせを失う.足突起消失と蛋白尿の出現に関わる糸球体上皮細胞障害の原因として主に,(1)スリット膜複合体の障害,(2)足突起内のアクチン骨格の障害,(3)GBMや糸球体上皮細胞-GBM接合部の障害,(4)糸球体上皮細胞の陰性荷電障害の4つが考えられている.近年,スリット膜の多くの構成分子が発見され,それぞれの構成蛋白間の相互作用も判明してきている.スリット膜を構成する蛋白のノックアウトマウスの多くは,蛋白尿を生じ糸球体硬化を引き起こすことから,スリット膜複合体分子は,それぞれ透過性の制御に重要な機能をもっていることが考えられている.足突起の複雑な構造は主に太いアクチン束によって支持されており,足突起消失のメカニズムの解明のためには,そのアクチン線維束に焦点をあてた研究も必要である.
2 0 0 0 ゲーム理論の歴史と現在--人間行動の解明を目指して
- 著者
- 岡田 章
- 出版者
- 経済学史学会
- 雑誌
- 経済学史研究 (ISSN:18803164)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.137-154, 2007-06
This paper considers the history of game theory since von Neumann and Morgenstern published their monumental work The Theory of Games and Economic Behavior in 1944. It points out changes in research themes and discusses what game theory has achieved up to the present. The aim of von Neumann and Morgenstern was "to find the mathematically complete principles which define rational behavior for the participants in a social economy, and to derive from them the general characteristics of that behavior." Extending the theory of von Neumann and Morgenstern, Nash classified all games as either non-cooperative games or cooperative games and defined the notion of an equilibrium point for a non-cooperative game. Nash also suggested a research program, now called the Nash program, to analyze a coop erative game by constructing a non-cooperative game model for negotiations. The main field of game theory was cooperative games in the l950s and the 1960s. Thereafter, research trends in game theory in the 1970s and the 1980s shifted from cooperative games to non-cooperative games, led by the seminal works of Harsanyi on incomplete information games and Selten on perfect equilibrium in extensive games. This so-called non-cooperative revolution greatly promoted applications of non-cooperative game theory to economics. At the same time, researchers became increasingly dissatisfied with the strong assumption of rationality in traditional game theory, and consequently research interest turned toward two new fields in the 1990s. One is evolutionary game theory, developing out of evolutionary biology, and the other is behavioral game theory, which collaborates with psychology. Evolutionary game theory investigates dynamic processes of evolution and learning in economic behavior, and it reformulates game equilibrium as a stable stationary state of those dynamic processes. Behavioral game theory studies the structures of motivation, cognition, and reasoning in human decision-making using the methodology of experiments. This paper shows how present-day research in game theory is developing in divergent fields that consider both traditional theory based on unbounded rationality and behavioral theory exploring human bounded rationality. Game theory continues to be one of the most active research fields in economics.
2 0 0 0 聖書 : 新共同訳 : 旧約聖書続編つき
- 著者
- 共同訳聖書実行委員会 [編]
- 出版者
- 日本聖書協会
- 巻号頁・発行日
- 1998
2 0 0 0 OA シュッツにおけるレリヴァンスの問題をめぐって
- 著者
- 江原 由美子
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.3, pp.54-69, 1981-12-31 (Released:2009-10-19)
- 参考文献数
- 55
シユッツのレリヴァンス概念は、彼の理論において重要な位置を与えられている。だがその理解は非常に困難である。おそらくその一因は、彼が文脈によって意味を変えて使用していることにあると思われる。この観点から本稿では第一にレリヴアンス概念の多様な文脈を整理する。次に、従来のシユッツのレリヴァンス概念についての解釈を手がかりに、レリヴァンスの意味が、 (1) 個人が選択された側面に帰属する属性、 (2) 個人の選択機能、又は選択する作用、 (3) 類型や知識の関連性という相異なる三様に解釈できることを示す。さらにレリヴァンス (体糸) の共有という論点においても、シユッツの記述に矛盾が見出せることを示す。次にレリヴァンスの問題とは何かを考察し、それが、自然的態度においてはけっして問われない、常識的思考そのものを成りたたしめている諸前提を明らかにするという問題であったことを把握する。しかしシユッツがそれを論じる視点は一様ではなく、 (1) 現象学的反省の視点、 (2) 観察者の視点という相異なる視点から考察していたのだと考えられる。ここから先に述べたレリヴァンス概念の三様の解釈の意義を明らかにする。すなわち、彼は、 (1) 日常生活者の視点、 (2) 現象学的反省の視点、 (3) 観察者の視点という三視点のそれぞれに応じてレリヴァンス概念を別の意味で使用したという仮説を呈示する。以上の考察に基づき、レリヴァンス問題の特異性を論じた上で、レリヴァンス論の継承方向を検討する。
2 0 0 0 真杉静枝と林芙美子 : 「台湾」という記号をめぐって
2 0 0 0 IR 「無条件降伏」とハーグ陸戦法規 : 日本にドイツ式「基本法」制定は可能であったか
- 著者
- 松村 昌廣 Masahiro Matsumura 桃山学院大学法学部
- 出版者
- 桃山学院大学総合研究所
- 雑誌
- 桃山法学 = St. Andrew's University Law Review (ISSN:13481312)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.87-102, 2011-03-15
2 0 0 0 OA シリーズ[3] クレーマー対処例:重症のアトピー患者
- 著者
- 三輪 亮寿
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床薬理学会
- 雑誌
- 臨床薬理 (ISSN:03881601)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.75-78, 2009 (Released:2010-04-02)
2 0 0 0 幼若ラット口蓋への外科的侵襲による影響
- 著者
- 角谷 徳芳
- 出版者
- The Showa University Society
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.5, pp.481-492, 1981
- 被引用文献数
- 1
近年口蓋裂手術は, 言語改善並びに顎発育への影響を考慮する傾向にある.現在われわれの国において主流をしめる手術法はDorrance, Wardill等の開発したpush-back法であるが, これは口蓋への手術侵襲が骨膜下層である為, 顎発育への影響が大きいとする意見があり, Perkoが開発した骨膜上層での手術法を推奨する者が現われてきた.そこでわれわれは, 実験的に正常幼若ラットを使用し, 片側口蓋粘膜を骨膜下に切除したもの50匹, 骨膜上で切除したもの50匹, 侵襲を加えないで成長させたもの50匹を1カ月ごと5カ月間各々10匹づつ断頭し, 乾燥骨としたものの, 口蓋縫合線の変化及び臼歯間横径を測定した.その結果は下記の通りである.以上口蓋裂手術時において現在主流をしめる手術法において骨膜下層での侵襲と骨膜上層での手術侵襲の二通りの方法が存在するが, 単に外科的侵襲のみについてその発育影響を比較するという意味で, ラット口蓋への実験を進めた結果, 骨膜下層までの侵襲は縫合線への影響は大きいが, 口蓋全体の発育に影響を及ぼすほどの侵襲ではないという結果を得た.
2 0 0 0 OA アメリカ的なイメージへの視線 : コラージュ作家ドナルド・バーセルミの初期短編を読む
- 著者
- 足立 伊織
- 出版者
- 現代文芸論研究室
- 雑誌
- れにくさ (ISSN:21870535)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.349-367, 2014-03-10
特集 北アメリカの文学
2 0 0 0 IR 琉球文化圏の墓制と祖霊祭
- 著者
- 下野 敏見
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.p101-119, 1995-06
トカラ列島から奄美・沖縄の琉球文化圏の墓制は、亀の甲墓や破風墓、積石墓、崖下葬、その他、いろんなタイプがある。墓制によって、また地域によって先祖祭りの仕方もちがってくる。 これらの地域の広い意味の祖霊祭はいったいどのような経過をへて現在に至っているのだろうか。 琉球における墓制の基本的な流れは遺棄的風葬墓と洗骨改葬墓の二つがある。この二つに伴う祖霊祭は当然異なる。前者は葬ったきり墓地へは二度と行かぬのだが、その代り年に一度、家でありったけのごちそうをして、歓待する。しかし、トカラ列島では家の外に近い縁側の隅でこれを行う。このことは神窓の外の庭で行うアイヌの先祖祭りのシヌラッパとよく似ている。 祖霊には、浮遊霊と遠祖(高祖)霊、近祖霊があるが、正月や盆の正祖霊は近祖霊が主対象であり、高祖霊は、正月や節替りの来訪神として現れる。浮遊霊は邪霊であり、病災をもたらしたりするので、正月や盆には門松や水棚でちょっとごちそうして退散してもらう。種子島やトカラ列島の門松での祭りがそれを証している。 琉球の夏正月とヤマト文化圏の冬正月に伴う祖霊祭の比較や夏正月の一日目から七日目までの第一週目の正月と、ヤマトの第一週目とそれに続いての十五日までの第二週目が加わった正月との比較も重要であるようだ。
- 著者
- 飯泉 達夫 矢崎 恒忠 加納 勝利 小磯 謙吉 小山 哲夫 東條 静夫
- 出版者
- 社団法人日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科學會雜誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.6, pp.878-885, 1986
ヒト腎細胞癌20症例よりえられた組織を対象としてその細胞骨格のうち,中間径フェラメソト蛋白質(サイトケラチン,ピメンチン)についてモノクローナル抗体を用いる蛍光抗体法,蛍光染色法により検討を行い以下の結果をえた.1)正常腎組織ではサイトケラチンは尿細管上皮細胞に,ビメンチンは間質細胞に認められた.2)ヒト腎細胞癌の中間径フィラメントではサイトケラチンは癌細胞に65%,ピメンチンは癌細胞に75%,間質細胞に65%証明された.3)サイトケラチンは腎癌細胞の異型度,浸潤度が進むにつれてその出現頻度が低下し統計学的に有意であった.4)以上より中間径フィラメントは腎癌細胞の分化と進展を推定する上で有力な指標であると考えられた.
2 0 0 0 OA 腎癌の骨格蛋白, 中間径フィラメントのサイトケラチン, ビメンチンの研究
- 著者
- 鈴木 明
- 出版者
- 社団法人 日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科學會雑誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.3, pp.527-533, 1988 (Released:2010-07-23)
- 参考文献数
- 25
細胞骨格蛋白の中間径フィラメントは, 細胞の癌化の過程をとらえる指標とひとつとして, 最近注目を集めている. 腎癌は近位尿細管上皮細胞から発生すると言われているため, 上皮細胞由来のサイトケラチンは, 腎細胞悪性化の適切な指標と推測される. また, ビメンチンは, 中胚葉由来細胞に特徴的に認められる. 今回, 我々は腎癌患者7例の手術によって摘出された腎の組織を用い, 二次元電気泳動法および免疫組織化学的方法を施行し, サイトケラチンおよびビメンチンの癌化に伴う変化を検討した. 塩基性型サイトケラチンの亜分画を検討したところ, 腎癌はサイトケラチンNo. 4のみの存在が同定されたが, 正常部髄質ではサイトケラチンNo. 1, 2, 3, 4, 6の5つの亜分画を検出し得た. また, 正常部皮質ではNo. 1, 4の2つの亜分画を検出した. 酸性型サイトケラチンを検討したところ, 腎癌と正常部組織のサイトケラチン表現型は非常に類似していたが, 腎癌ではサイトケラチンNo. 12が欠損していた. 一方, ビメンチンは腎癌の7例全例で認められた. 免疫組織化学的に検討しても, サイトケラチンとビメンチンの存在は, 腎癌全例で確かめられた. 以上の生化学的, 免疫組織化学的な特性から, 所謂腎癌は単なる腺癌ではなく, 肉腫のもつ性格をもあわせもっている腺癌であると考えた方が, 臨床的な特性を説明するうえにも矛盾がないように思われる.
2 0 0 0 OA アメリカ経済の金融化と企業金融 : 事業再構築との関連で
- 著者
- 小林 陽介
- 出版者
- 経済理論学会
- 雑誌
- 季刊経済理論 (ISSN:18825184)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.90-95, 2012-10-20
- 被引用文献数
- 1
Recently there has been a great deal of research generated focusing on the Financialization-Approach. However, most of the literature on financialization emphasizes the influence of the financial sector, and pays less attention to the real economy. This paper examines how to bring the dynamism of real economy into the Financialization- Approach. Firstly, I investigate the relationship between corporations and finance, focusing on the literature of corporate governance. According to the research by Lazonick and O'Sullivan, the management strategy of U.S. corporations changed from "retain and reinvest" to "downsize and distribute" after the 1980s. U.S. corporations reduced their employment, and distributed cash to stockholders, and increased dividend payments and stock repurchases to raise their stock prices. This change arose from the formation of the "market for corporate control", which is explained mainly from the following: 1) Worsening performance of corporations and agency theory, 2) Increase of the stock holding by institutional investors, and 3) Development of junk bond market. However, this change is explained only from the influence of finance. The activeness of corporations is ignored. Secondly, I investigate the situation that U.S. corporations faced in 1980s to focus on the corporate action. They faced the shift in industrial structure. Key industries, such as steel, automobile and household electronic appliances, lost competitive power, while high-technology, energy and service industries maintained competitive power. Many corporations restructured their business formations to adapt to this shift by mergers and acquisitions. While raising stock prices is a result of financial influence in the literature of financialization, raising stock prices has a positive meaning for companies which perform mergers and acquisitions. Companies can perform mergers and acquisitions advantageously when their stock prices are high. Increase of dividend payments and stock repurchases can be understood to be a result of corporate action which adapts to the shift in industrial structure by mergers and acquisitions. Finally, I discuss the corporate image which should be included in the Financialization-Approach. The corporation should be assumed the active one which pursues profits, not the passive one assumed in the former literature. This is the starting point of an attempt to bring the dynamism of real economy into the Financialization-Approach.
2 0 0 0 OA Donald Barthelme 研究における無意味さと意味付けのジレンマ
2 0 0 0 OA 荊楚歳時記の資料的研究
- 著者
- 守屋 美都雄
- 出版者
- 大阪大学
- 雑誌
- 大阪大學文學部紀要 (ISSN:04721373)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.45-113, 1954-03-25
1. Introduction. 2. Critique of the text in the Shuo-fu (説郛), edited by T'ao T'ing (陶梃) oi the Ming Dynasty (明代). 3. Critique of the text in tire Pao-yen-t'ang Pi-chi (寶顔堂秘笈)> edited by Ch'en Chi-ju (陳繼需) of the Ming Dynasty (明代). 4. Re-presentation of the original form of the Ching-ch'u Sui-shih-chi (〓楚歳時記). 5. Conclusion. The ChingcWu Sui-shih-chi (〓楚歳時記), originally complied by Tsung Lin (宗懍) in the Liang Dynasty (梁代) was a description of annual functions held around the middle basin of the Yang-tse-kiang (揚子江) at that time, and therefore ontains many traditions and records of the manners and customs of old China. Afterwards, during the Sui Dynasty (隋代), Tu Kung-shan (杜公贍) recomplied the said work, adding more descriptions, as well as his own notes, until its enriched contents looked like a sort of encyclopedia dealing with ceremonies throughout the year. However, it is a great regret for all persons concerned that this valuable piece of work by Tsung Lin was seldom looked at in the 10th century and is thought to have wholly disappeared from the world by the beginning of the 13th century. Meanwhile, Tu Kung-shan's revised annotation is widely believed to have been lost in the 13th century also, but I believe there still remain some points to be discussed in this connection. As a matter of fact, a rather good text of the Ching-ctiu Sui-shih-chi did exist in A.D. 1370, with the styles and forms proper to the original work retained to some extent. Regarding the texts of this work in our possession today, they can be divided,into two strains, and we can trace their respective sources: one is contained in a series named Pao-yen-fang Pi-chi (寶顔堂秘笈), complied by Ch'en Chi-ju (陳繼儒) of the Ming Dynasty (明代) and the other in a series named Shuo-fu (説郛)> complied by T'ao T'ing (陶〓) and completed under the same dynasty. These texts, according to prevailing opinion, are nothing but a combination of fragments of the Ching-ch'u Sui-shih-chi during the quoted in similar books of encyclopedic style written in the Tang and Sung Dynasties (唐宋時代). Yet, I have a somewhat different opinion, and should say that texts of the Pao yen-fang Pi-chi derived from th3 abovementioned text existed in A.D. 1370. Also, based upon the same text the Shuo ftc was composed, I believe. Here, it must be added that it is thought that the' Shuo-fu was supplemented by those fragments quoted in the T'ang and Sung encyclopedias. In this treatise, I have tried to re-present the original form of this text as exactly as possible, and two ways were taken to reach this end. Throughout the first part, corrections and supplements are made to the texts of the Pao-yen-V ang Pi-chi, referring to the original of the Pao yen-fang Pi-chi, and to changes, interpolations, omissions, etc., which were made while these texts were being copied one after another for generations. Next, in the second part, 54 articles of the above fragments have been shown. In fact, necessary materials, both Chinese and Japanese, were very useful, in discovering and collecting them. In so doing, I was happy to be able to detect meny omissions in the text of the Pao yen-fang Pi-chi. On the other hand, some descriptions were found mistakenly introduced in the materials as those of the Ching-ctiu-sui Shih-chi and therefore I closely examined each article as to wh3ther it was genuine or not. In the meantime, despite all my efforts, it was quite difficult to distinguish Tsung Lin's passages from Tu Kung-shan's notes, for which I am very sorry. However, if this little essay of mine can be of any help and service to the future progress of the study of Chinese folk-lore, I shall certainly be very happy.
2 0 0 0 IR 組織再編成における課税関係の継続と断絶 (小山正善教授 退職記念号)
- 著者
- 小塚 真啓
- 出版者
- 岡山大学法学会
- 雑誌
- 岡山大学法学会雑誌 (ISSN:03863050)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.1004-949, 2016-03