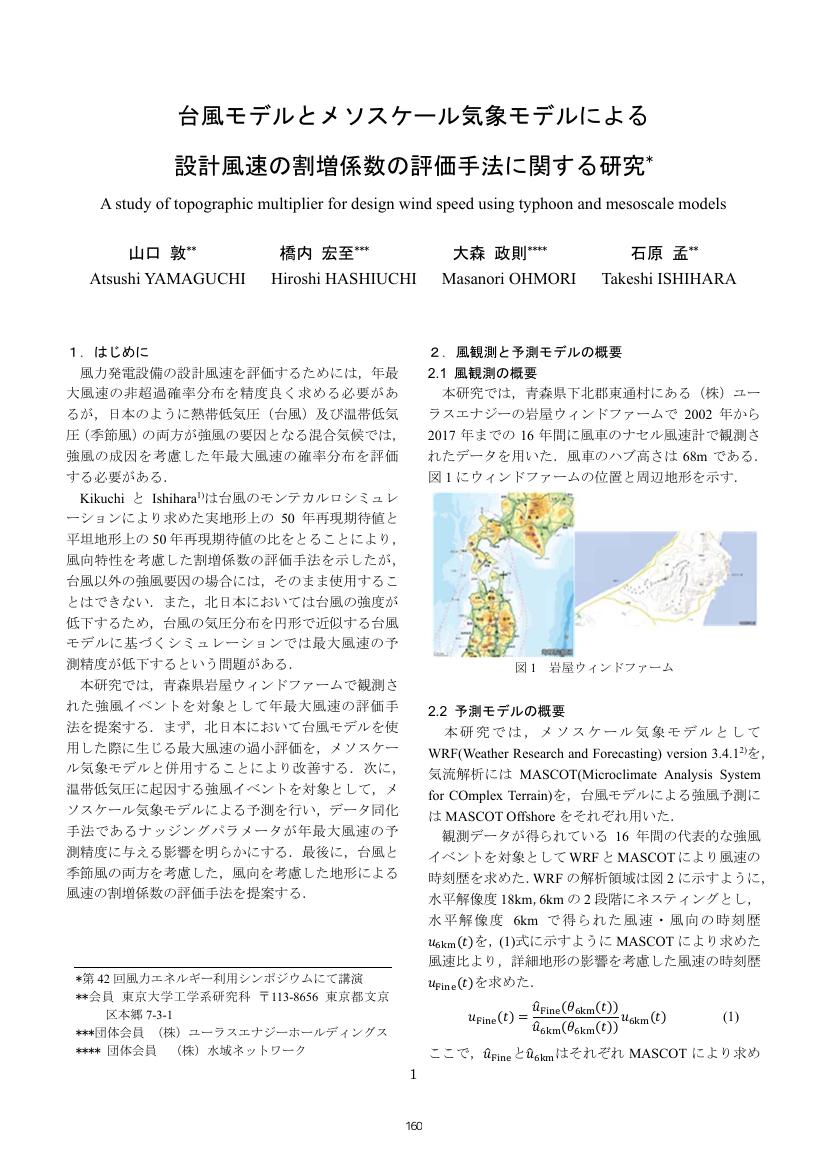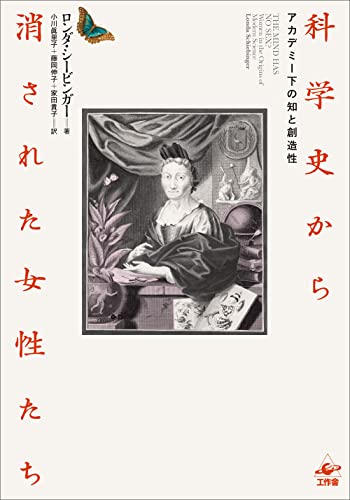1 0 0 0 OA 高気圧高酸素条件下における運動時の生体応答―ミドルパワー発揮時の場合―
- 著者
- 竹澤 稔裕 横澤 司郎 若井 勝則
- 出版者
- 学校法人 関東学園大学
- 雑誌
- 関東学園大学紀要 Liberal Arts (ISSN:21878501)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.11-24, 2018 (Released:2018-03-30)
- 参考文献数
- 6
Oxygen capsules and hyperbaric oxygen therapy, which have been used to recover physical function, are currently being examined as physical training devices. The levels of dissolved oxygen in blood are increased in hyperbaric hypoxic conditions; thus, high-intensity training is most likely possible in training at a moderate power output, which requires oxygen. The present study compared biological responses and performance during exertion of moderate power in a standard environment and under hyperbaric hypoxic conditions. The exercise task was performed in accordance with the measurement protocol function for moderate power training of the Konami Power Max upright exercise bike. Data were analyzed using the paired t test and two-way analysis of variance, with the level of statistical significance set at a p value of <0.05. Significant differences were observed in the mean moderate power values for the second and third sets, and in peak power value for the third set. In addition, interactions were observed in the changes in the mean moderate power values for each set in both environments. However, interactions were not observed for mean peak power values in any set in either environment.
1 0 0 0 OA 生物コーナー
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.10, pp.664-666, 1975-10-25 (Released:2009-05-25)
- 著者
- 久保 彰子 久野 一恵 丸山 広達 月野木 ルミ 野田 博之 江川 賢一 澁谷 いづみ 勢井 雅子 千原 三枝子 仁科 一江 八谷 寛
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.8, pp.586-594, 2022-08-15 (Released:2022-08-04)
- 参考文献数
- 15
目的 新型コロナウイルス感染症の蔓延により2020年度および2021年度の国民健康・栄養調査が中止され,都道府県の調査も中止または延期が予想されたため,日本公衆衛生学会公衆衛生モニタリング・レポート委員会生活習慣病・公衆栄養グループでは都道府県民健康・栄養調査の実施状況を調査し,公衆衛生施策立案のために必要なデータ収集の現状と課題を検討した。方法 47都道府県の調査担当者を対象に,郵送もしくは電子媒体による自記式質問紙調査を実施した。結果 47都道府県(回収率100%)から回答が得られた。健康・栄養調査を実施しているのは44自治体(93.6%)であった。新型コロナウイルス感染症の影響から2020年度調査予定の18自治体のうち「予定通りの内容で実施した」は2(11.1%)「中止した」は16(88.9%)であった。2021年度調査予定の31自治体のうち「予定通りの内容で実施した」は4(12.9%)「内容を一部変更して実施した」は5(16.1%)「中止した」は22(71.0%)であった。今後の調査方法について,身体状況調査実施の32自治体のうち「変更する予定はない」は6(18.8%)「未定」は18(56.3%)であった。栄養摂取状況調査実施の40自治体のうち「変更する予定はない」は12(30.0%)「未定」は19(47.5%)であった。2か年とも調査を中止した13自治体の各種計画評価は「各種計画期間を延長する」8(61.5%)「その他」7(53.8%)であった。2か年に調査を中止または延期した38自治体のうち,各種計画評価に関する問題点は「調査法の変更に伴う経年評価が不可能になる」「コロナ禍でのライフスタイル変化の影響が想定される」「評価に影響はないが評価期間が短縮となる」「国民健康・栄養調査中止により全国比較が不可能である」等があげられた。結論 都道府県健康増進計画等の評価のため,ほとんどの自治体が都道府県民健康・栄養調査を実施していた。また,全国比較ができるよう国民健康・栄養調査と同じ方式で実施する自治体が多かった。新型コロナウイルス感染症の影響により,国民健康・栄養調査と同様に調査を中止する都道府県が多く,今後の調査も未定と回答する自治体が多かった。
1 0 0 0 OA 小泉内閣における官僚制の動揺
- 著者
- 飯尾 潤
- 出版者
- 日本行政学会
- 雑誌
- 年報行政研究 (ISSN:05481570)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, no.42, pp.80-99, 2007-05-26 (Released:2012-09-24)
1 0 0 0 OA ブレーンストーミング集団における生産性の再検討
- 著者
- 本間 道子
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.252-272, 1996 (Released:2019-07-06)
- 被引用文献数
- 2
- 著者
- 佐野 裕基 遠藤 健司 土田 奨 六本木 さくら 荒井 芙美 高橋 亮吾 石山 昌弘 長田 卓也 上野 竜一 山本 謙吾
- 出版者
- 一般社団法人日本理学療法学会連合
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.145-154, 2022 (Released:2022-04-20)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 1
【目的】首下がり症状を呈した変形性頸椎症2 症例の前方注視障害に対して,腰椎・骨盤矢状面アライメントの改善をめざした理学療法の有効性について検討することを目的とした。【症例】変形性頸椎症を既往とし,首下がり症状が出現した2 症例であった。両症例の立位姿勢は全脊柱アライメントより,頸部屈曲位,胸椎後弯,後方重心,また症例1 は腰椎前弯代償,症例2 は骨盤後傾代償が認められた。【経過】両症例ともに頸部および,腰椎・骨盤帯に対する理学療法を実施した。いずれも介入3 ヵ月で頸胸椎アライメントが改善し,一時的に前方注視可能となり,6 ヵ月で腰椎・骨盤帯アライメントが改善し,長時間前方注視可能となった。【結論】首下がり症状による前方注視障害の改善には頸部自動伸展機能の改善に加えて,矢状面上における脊柱全体と骨盤帯のバランスが取れた立位姿勢をめざした介入が有効であると考えられた。
1 0 0 0 OA プロアクティブ・マネージメントを用いたアトピー性皮膚炎の新規治療法開発と作用解析
アトピー性皮膚炎に対する長期寛解維持療法として近年欧米で提唱されるプロアクティブ療法(ステロイド外用薬による予防的間欠塗布法)について、当大学皮膚科学講座および国立成育医療研究センターアレルギー科の研究協力のもと、ランダム化並行群間比較試験を行い安全性および有効性を検証した。1 年間の研究期間において、両群とも明らかな副腎抑制を来さず局所副作用に差を認めなかったが、症状スコアや血清 TARC 値はプロアクティブ療法群で有意に低下し維持された。さらに同群では総 IgE の上昇が抑えられ、ダニ特異的 IgE の感作を有意に予防した。 「抗炎症外用薬の予防的間欠塗布によって湿疹の無い状態を維持する」という新たなアプローチによって、アレルギーマーチの原因の1つであるダニアレルギーに対し経皮感作を予防する可能性が示唆された。
1 0 0 0 OA リフレクトアレーアンテナにおける位相誤差の周波数特性に関する幾何光学的考察とその応用
- 著者
- 牧野 滋 中嶋 宏昌 山本 伸一
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 B (ISSN:13444697)
- 巻号頁・発行日
- vol.J106-B, no.11, pp.657-668, 2023-11-01
本論文では,リフレクトアレーアンテナにおける開口上の波面と所望の平面波面との光路長差である残留収差の周波数特性を幾何光学の手法により定式化,その理論限界を明らかにする.また,球面波で近似した波面が鏡面構成,具体的には,平面反射鏡による一次放射器の像(イメージホーン)の位置で決まることを明らかにする.その結果より,リフレクトアレーアンテナの周波数特性を改善する方法として,一次放射器の位相中心の周波数特性を利用する方法を提案する.最後に,試作モデルの測定により,これらの妥当性を示す.
- 著者
- Satoshi Ohara Yosuke Hamada Yoshifumi Terajima Tetsuya Ishida Yasunori Kikuchi Yasuhiro Fukushima Akira Sugimoto
- 出版者
- Japanese Society for Food Science and Technology
- 雑誌
- Food Science and Technology Research (ISSN:13446606)
- 巻号頁・発行日
- pp.FSTR-D-23-00158, (Released:2023-11-09)
This study investigated the effect of single-boiling crystallization of high-yielding sugarcane on sugar and molasses production on a factory-plant scale compared with triple-boiling crystallization of conventional sugarcane. The sugar extraction at the roll-milling process was similar between high-yielding sugarcane KY01-2044 with high fiber and conventional sugarcane NiF8. The weight of sugar yield per sugarcane decreased by 32.6 % compared with the conventional system, whereas the yield of molasses and bagasse increased by 143.1 % and 11.5 %, respectively. The results indicated that sugar, molasses, and bagasse-derived electricity could increase simultaneously when the yields of high-yielding sugarcane were higher by a factor of 1.5 than conventional levels. Furthermore, A-molasses obtained by a single-boiling crystallization had less coloration and better fermentability and operability than conventional C-molasses. In conclusion, this study showed that combining high-yielding sugarcane and single-boiling crystallization could increase sugar production and generate high-quality molasses suitable for biofuel and bagasse-derived electricity production.
1 0 0 0 OA 河岸道を対象とした観光と日常生活における自転車利用者の評価構造の差異に関する研究
- 著者
- 扇谷 匠 一ノ瀬 彩 辻村 壮平
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会環境系論文集 (ISSN:13480685)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.813, pp.818-828, 2023-11-01 (Released:2023-11-01)
- 参考文献数
- 25
The government of Japan has developed a plan to promote cycling in response to recent increase in cyclist. The plan includes the use of a bicycle for tourism and daily transportation on riverside road; however, local governments are mainly responsible for implementing the plan and maintenance of the cycling road. The purpose of this study is to obtain knowledge to help determine a maintenance policy by understanding the impressions of cyclists. Here, we have conducted a field test using the caption evaluation method for the cyclists in tourism and daily transportation on the Kinugawa Cycling Road.
1 0 0 0 OA 茨城県における酒蔵の周辺環境からみた公開実態の分析
- 著者
- 一ノ瀬 彩 扇谷 匠
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.73, pp.1552-1557, 2023-10-20 (Released:2023-10-20)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
Over a decade, Sake breweries are attracting significant attention as tourism resources in Japan. Therefore, it is important to understand sake breweries to utilize them for tourism resources. We report a survey of the brewery’s layout and how to open to the public in Ibaraki Prefecture. We also investigate the location of the breweries and their surrounding environments. From the results of the survey, we categorize 34 Sake breweries into four broad types according to their characteristics of layouts and surroundings.
1 0 0 0 OA 陸上観測値と数値シミュレーションを用いた沖合風況の推定
- 著者
- 小長谷 瑞木 大澤 輝夫 水戸 俊成 加藤 秀樹 見﨑 豪之
- 出版者
- 一般社団法人 日本風力エネルギー学会
- 雑誌
- 風力エネルギー利用シンポジウム (ISSN:18844588)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.261-264, 2017 (Released:2018-12-21)
1 0 0 0 OA 台風モデルとメソスケール気象モデルによる設計風速の割増係数の評価手法に関する研究
- 著者
- 山口 敦 橋内 宏至 大森 政則 石原 孟
- 出版者
- 一般社団法人 日本風力エネルギー学会
- 雑誌
- 風力エネルギー利用シンポジウム (ISSN:18844588)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.160-163, 2020 (Released:2022-02-20)
- 著者
- 肥爪 周二
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.3, pp.71-66, 2007-07-01 (Released:2017-07-28)
- 著者
- 内田 孝紀 小野 謙二 飯田 明由 吉村 忍 加藤 千幸 山出 吉伸 今村 博 植田 祐子
- 出版者
- 一般社団法人 日本風力エネルギー学会
- 雑誌
- 風力エネルギー学会 論文集 (ISSN:24363952)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.71-82, 2021 (Released:2022-03-30)
In the current project, the first author and the second author play a central role in conducting high-speed tuning and wind turbine wake analysis of the supercomputer version of RIAM-COMPACT. In this report, we applied the supercomputer version RIAM-COMPACT to the wind turbine wake simulation from the wind tunnel scale to the utility-scale wind turbine wakes. As a result, we clarified unsteady wake aerodynamics of wind turbines including multiple wake interactions with high precision and high reality.
1 0 0 0 OA 西洋古典に見る色彩表現―「色」の象徴性と社会的役割に関する考察
本研究は、ホメロスの作品を中心に西洋古典に著された[色][色彩修飾語]を精査・分類・整理し、詩句の文学的効果を考察することによって、詩人の創造性および「色彩」の象徴性や社会的役割の解明を探究した。英国リヴァプール大学等訪問先の大学でも充実した調査を実施し、当初の予測をより実証的に検証することができた。多分野に関連する色彩表現の深層について一定の見解を提示し、さらに、停滞していた文献学的研究に新たな活路、つまり〈色-音-動き〉という次につながる方向性を見出だせたことは大きい収穫であった。国際的動向を見据えて研究を発展・展開させていくための今後の基盤を築くことができ、有意義な研究であった。
1 0 0 0 OA 自己は環境に適応すべきか 前期デューイ「進化と倫理」における非進化論的前提をめぐって
- 著者
- 柴田 悠
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, no.59, pp.179-193,L17, 2008-04-01 (Released:2010-07-01)
The aim of this paper is to answer the following two questions: (Q1) How valid is the widely believed proposition that each agent (i. e. an individual or a social group functioning as an agent) should adapt to its environment? and, (Q2) If this proposition needs revision, in what way should we revise it? In order to answer Q1, we trace the historical lineage of thinking about evolution-ethics from Galton through Darwin, Spencer, and Huxley to early Dewey. This survey reveals that the widely believed proposition appeared first in that lineage in the early Dewey's ‘Evolution and Ethics’ (1898), and that it depends on the following two un-evolutionary premises: first, that if X is an agent, what is desired by X is ethically good to X (P1: a familiar form of ethical naturalism), and second, that the responsibility for X's adaptation (or adjustment) to X's environment should be attributed only to X (P2: the principle of self-responsibility).Whether P1 is valid or not is too large a question to address in this paper, so we will suppose for the sake of argument that P1 is acceptable. However, it is possible to argue, both from evolution itself and from P1, that P2 is not tenable, and that a premise more appropriate than P2 is that whether the responsibility for X's adaptation to X's environment should be attributed to X alone, or to both X and X's social environment (i. e. other agents concerned with X), should depend on whether X prefers to take the whole responsibility or to share it with the social environment (P3: the principle of the agent's choice of responsibility scope).Thus we can say, in response to Q1, that the widely believed proposition is not valid (at least as we have it from the early Dewey) because it depends on P2. And we can say, in response to Q2, that a more appropriate version of it will be based on evolution, P1 (perhaps), and P3 (probably)-though within the confines of the present paper, P1 and P3 obviously remain conjectural.
1 0 0 0 ジェンダーと科学 : プラトン、ベーコンからマクリントックへ
- 著者
- エヴリン・フォックス・ケラー著 幾島幸子 川島慶子訳
- 出版者
- 工作舎
- 巻号頁・発行日
- 1993
1 0 0 0 科学史から消された女性たち : アカデミー下の知と創造性
- 著者
- ロンダ・シービンガー著 小川眞里子訳 藤岡伸子訳 家田貴子訳
- 出版者
- 工作舎
- 巻号頁・発行日
- 2022