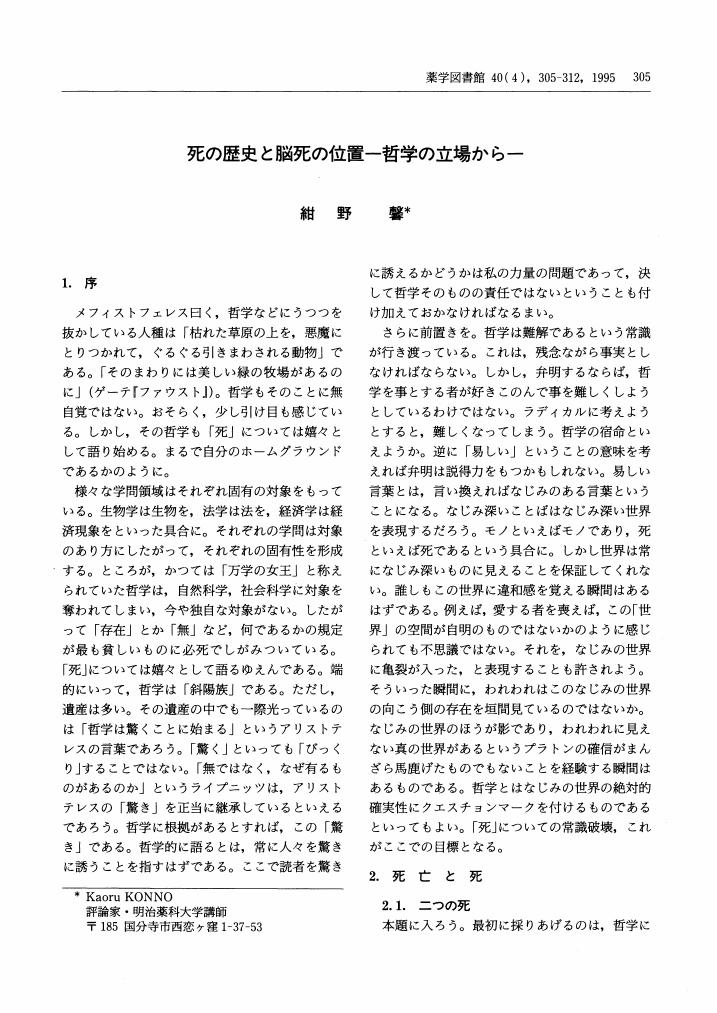1 0 0 0 原典社会主義経済計算論争
1 0 0 0 OA K-縮退グラフに含まれる誘導木の列挙
- 著者
- 和佐 州洋 有村 博紀 宇野 毅明
- 雑誌
- 研究報告アルゴリズム(AL)
- 巻号頁・発行日
- vol.2014-AL-148, no.17, pp.1-6, 2014-06-06
本稿では,k- 縮退グラフに含まれる誘導木 (連結かつ非巡回な誘導部分グラフ) を,効率よく列挙するアルゴリズムを与える.グラフ G=(V,E) が k-縮退 (k-degenerate) であるとは,G の任意の部分グラフが高々 k の次数を持つ頂点を含むときをいう.これまで,制約のある誘導部分グラフの列挙に関しては,連結な誘導グラフ (Avis,Fukuda,DAM,1996) や,コードレスパス,コードレスサイクル (宇野,第 92 回アルゴリズム研究会,2003) の列挙に関する先行研究があるが,誘導木については知られていない.最大次数が d のとき,誘導木 1 つ当たり O(d) 遅延の列挙アルゴリズムは容易に構成できるが,これをどの程度まで改善できるかは未解決の問題である.我々のアルゴリズムは,入力グラフ G が k- 縮退グラフであるとき,誘導木を 1 つ当たりならし O(k) 時間で列挙する.系として,k が定数ならば,誘導木を 1 つたり,ならし定数時間で列挙可能である.
1 0 0 0 OA 口腔内スキャナに使われる三次元光計測法の基礎知識
- 著者
- 堀田 康弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.4, pp.291-298, 2021 (Released:2021-10-30)
- 参考文献数
- 8
近年,歯科だけにとどまらず,産業界でも3Dプリンティングを中心とした新たな三次元での製造技術の普及と共に,もとになる三次元座標データ収集に対する要求が高まっている.以前は,設計形状を図面として記述するために行っていた製図やクレーモデル製作などの手作業での工程を効率化するために開発がすすめられたCAD/CAMシステムであったが,リバースエンジニアリングやCAE(computer-aided engineering)など,デジタルデータをスタートラインとする工程が増えたことで三次元計測に対する研究開発が進められるようになった.本解説では,産業界の三次元計測に用いられる代表的な手法について,その原理と特徴を解説し,歯科の口腔内スキャナで応用されている技術の解説と注意点についてまとめる.
1 0 0 0 OA 日本産木材50種のデジタル画像を用いた視覚的好ましさの評価
- 著者
- 信田 聡 前田 啓 浪岡 真太郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本木材学会
- 雑誌
- 木材学会誌 (ISSN:00214795)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.6, pp.301-310, 2016-11-25 (Released:2016-11-29)
- 参考文献数
- 14
日本産木材50種の視覚的好ましさを評価する目的で,一対比較法を用いて19歳~30歳までの被験者により視覚的好ましさの間隔尺度値を求めた。好ましさの間隔尺度値と各木材画像の色属性間の相関分析から,好ましさは「RGBの中のR値の変動係数」や「R値の最小値」と正の強い相関を示し,さらに「R値の変動係数」とは負の強い相関を示したことから,赤味が強く,暖色系の色で,木目がはっきりしない木材が,視覚的に好まれることが示唆された。
1 0 0 0 OA アイヌの酒 (10) その系譜と背景
- 著者
- 加藤 百一
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.200-205, 1970-03-15 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 23
アイヌの酒のうち樹液酒と穀物酒のつくり方をアイヌの古謡や古老の語りつたへから現代に再現することを試みられた。アイヌは古くから糸状菌の利用法を知っており穀類原料の糖化にカムダチ (麹) を使っていたことは特に興味ふかい。
- 著者
- Atsushi Asai Taketoshi Okita Aya Enzo Yasuhiro Kadooka
- 出版者
- Ritsumeikan Center for Asia Pacific Studies
- 雑誌
- Ritsumeikan Journal of Asia Pacific Studies (ISSN:13444204)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.1-8, 2018 (Released:2022-06-15)
- 参考文献数
- 25
The 1945 Kyushu Imperial University human vivisections are among the most infamous of medical atrocities involving Japanese doctors. The Japanese novelist, Shusaku Endo published The Sea and Poison, a fiction novel based on the incident in 1958. His story features young doctors, Suguro and Toda, and depicts their motivations to join the killing, as well as their regrets or the lack thereof. Endo forces us to ponder why they involved themselves in the human vivisections and what might have dissuaded them from doing so. Even today we lack clear answers to these questions. This paper will present our deliberations on the contemporary implications of Endo’s questions and positions set forth in The Sea and Poison. We suggest that Suguro failed to refuse participation in the vivisection because of his emotional exhaustion and emptiness, which could have been caused by war, the doctors’ true colors, or the dark side of medicine. It is argued that Suguro is no different from many of us, and that Toda’s claim that we are, deep down, unmoved by the suffering and death of others describes part of our minds. The meaning of strong conscience and compassion is also discussed.
1 0 0 0 OA イエスの接触 ツァラアト/レプラ、聖性と穢れ
- 著者
- 上村 静
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.2, pp.29-53, 2022-09-30 (Released:2022-12-30)
福音書のイエスはしばしば病人と接触しており、その中には当時のユダヤ社会において「穢れ」とされたツァラアト/レプラの人も含まれていた。本稿では、彼らとの接触を切り口に、イエスが「穢れ」と「聖性」についてどのような態度をとったのかを考察する。ヘブライ語聖書において、「聖性」は神の属性であり、それゆえユダヤ人は「聖なる民族」として「穢れ」を避け、「浄い」状態で生きることが求められた。ツァラアトの人は「穢れたもの」の象徴とされ、その病は神罰と解されていた。イエスは「穢れ」の問題を無視してツァラアト/レプラの人と接触した。イエスにとって神は「いのちを生かすはたらき」なのであり、律法規定が「いのちを殺すこと」になるならば、「穢れ」も「聖性」も無視すべき観念なのである。
1 0 0 0 OA 死の歴史と脳死の位置―哲学の立場から―
- 著者
- 紺野 馨
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.4, pp.305-312, 1995-10-31 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 13
- 著者
- 野田 舞 山田 真紀
- 出版者
- 一般社団法人 日本保育学会
- 雑誌
- 保育学研究 (ISSN:13409808)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.39-50, 2018 (Released:2018-10-31)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 2
本研究は,保育施設のリスクマネジメントのうち,園庭遊具に焦点をあてて,重篤な怪我のリスクを減らして,遊びの価値を最大限に発揮させる,「子どもと遊具の関わり」と「保育者の援助のあり方」を,参与観察とインタビュー調査から明らかにするものである。概念整理では,日本の遊具に関する安全基準におけるハザードとリスクの概念が,世界基準のそれと異なることを指摘し,世界基準の概念定義を用いること,すなわち,ハザードは「遊具が内在する危険性」,リスクは「ハザードから生ずるおそれのある怪我の重篤度とその発生頻度」ととらえること。そして,遊具のハザードを「遊具の本質として内在するハザード」「取り除くべきハザード」の縦軸と「子ども認知可能」「子ども認知不可能」の横軸をクロスさせた4つの象限に分けて分類することの有用性について論じた。
- 著者
- Xinxia Cao Mei Lu
- 出版者
- Resources Economics Research Board
- 雑誌
- Geographical Research Bulletin (ISSN:27581446)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.68-69, 2023-03-31 (Released:2023-03-31)
- 参考文献数
- 4
On March 9, 2023, Gole 3C well was drilled in Fuman Oilfield, Tarim Basin. This is the largest ultra-deep oil field in China: Fuman Oilfield, a key well for expanding to ultra-deep strata. The vertical depth of the well is 8,060 m and the horizontal displacement is nearly 1,561 m. This well sets a new record for the deepest horizontal well in Asia. The ultra-deep marine carbonate rocks in Tarim Basin are rich in oil and gas resources, and the largest weathering crust oil fields and the largest condensate gas fields in China have been discovered one after another. The practice and research of exploration and development in Fuman Oilfield show that Fuman Oilfield is rich in oil and gas reservoirs with good oil properties and high production per well. The completion of Gole 3C well indicates that the oilfield development in Tarim Basin has entered a new stage of 9,000 m extra-deep oil and gas exploration and development.
1 0 0 0 OA FPS ゲームの実況解説における補足情報の検討
- 著者
- 八木 聖太 梶並 知記
- 出版者
- 一般社団法人 日本デジタルゲーム学会
- 雑誌
- 日本デジタルゲーム学会 夏季研究発表大会 予稿集 2023夏季研究発表大会 (ISSN:27584801)
- 巻号頁・発行日
- pp.131-135, 2023 (Released:2023-10-28)
- 参考文献数
- 4
本稿では,First Person Shooter(FPS)の試合観戦者を対象とした,実況解説の補足情報を検討する.スピード感のある戦闘が複数場所で展開される FPS において,典型的な実況解説では,相手を倒したシーンやキャラクタの位置を主な対象としている.本稿では,実際の実況解説の映像から,実況解説者の発話を抽出し,内容に基づく分類を行うほか,観戦者に対する聞き取り調査を行い,補足情報を検討する.
1 0 0 0 OA 中国のスマホゲームにおける日本要素
- 著者
- 耿 義
- 出版者
- 一般社団法人 日本デジタルゲーム学会
- 雑誌
- 日本デジタルゲーム学会 夏季研究発表大会 予稿集 2023夏季研究発表大会 (ISSN:27584801)
- 巻号頁・発行日
- pp.60-63, 2023 (Released:2023-10-28)
- 参考文献数
- 11
近年、中国のスマホゲームは日本において影響力がますます大きくなり、多くのプレイヤーを引きつけている。しかし、これらのゲームには日本要素が取り入れられているという共通点がある。これは、中国が文化大国として自負している国にとっては驚くべきことであろう。本研究では、日本市場で最も人気のあるいくつかの中国のスマホゲーム(「陰陽師」、「原神」、「IdentityV」、「崩壞:スターレイル」など)を基に、その中に含まれる日本要素を探求し、中国のスマホゲームがなぜそうするのか、そしてその影響について分析する。
1 0 0 0 OA 人肌の透過光表現リアルタイムレンダリングに関する研究
- 著者
- 高 峰 阿部 雅樹 渡辺 大地
- 出版者
- 一般社団法人 日本デジタルゲーム学会
- 雑誌
- 日本デジタルゲーム学会 夏季研究発表大会 予稿集 2023夏季研究発表大会 (ISSN:27584801)
- 巻号頁・発行日
- pp.35-38, 2023 (Released:2023-10-28)
- 参考文献数
- 4
人肌のリアルタイムな描画は、物体内部で生じる表面下散乱現象のシミュレーションに膨大な計算が必要となるため,困難であると言える.レンダリング効率を上げるために、多くのゲームでは肌の透過光効果を無視している. Pre-Integrated Skin Shading の方法に基づいて、より正確な人肌透過光表現を実現する手法を提案する.光と法線のなす角度と皮膚の厚さをパラメータとし、深度マップに基づく事前計算による透過光効果を LUT で保存してルックアップテーブルの色値を読み取り、そのまま照明計算の透過輝度として使用できるため、計算速度を向上することができる.
1 0 0 0 OA デジタルゲーム文化におけるミソジニー課題 - 中国女性ゲーマーの語りから -
- 著者
- 張 佳
- 出版者
- 一般社団法人 日本デジタルゲーム学会
- 雑誌
- 日本デジタルゲーム学会 夏季研究発表大会 予稿集 2023夏季研究発表大会 (ISSN:27584801)
- 巻号頁・発行日
- pp.48-53, 2023 (Released:2023-10-28)
- 参考文献数
- 11
本研究では、中国の女性ゲーマーを対象にインタビュー調査を行い、デジタルゲーム文化におけるミソジニーの問題を明らかにした。結果として、ゲーム文化は、女性に対して排他的かつ男性支配的であるという実態が浮き彫りとなった。また、「女性」と「ゲーマー」という 2 つのアイデンティティの間には矛盾があることが明らかとなった。さらに、女性ゲーマーは、様々な対策を講じてゲーム文化におけるミソジニーに対抗しているものの、彼女らの対策では、この差別の構造を覆すことができないという限界がある。
- 著者
- 山本 真由美
- 出版者
- 一般財団法人 日本英文学会
- 雑誌
- 英文学研究 支部統合号 (ISSN:18837115)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.155-163, 2019 (Released:2020-12-05)
1 0 0 0 OA 東京都における精神病院の立地変遷に関する研究
- 著者
- 古山 周太郎 土肥 真人
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.379-384, 1997-10-25 (Released:2018-05-01)
- 参考文献数
- 6
This study means to show the geographecal characteristics of mental hospitals' positions and their historical change. The way of study is to analyze the city area conditions of mental hospitals and their change in Tokyo. As a conclusion, mental hospitals are likely to be built in the outerskirts. Expectionally, they had been in the city area before 1920. Secondly, the hospital has been in the city area even if we have urbanization there. Thired, in each decade of these hosipals foundation in Tokyo, They have been classified into 4 types. As the times have gone by, they have moved to the west.
1 0 0 0 OA 武道の文化性 ―薩摩藩における武道教育―
- 著者
- 村山 輝志
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.17-25, 1986-07-31 (Released:2012-11-27)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 2
There have been many discussions about whether Budo is considered to be a sport or not. Ancient Budo was a part of traditional Japanese culture, but it has developed into a competitive sport. Budo has made contributions to many aspects of our society: for example, to the arts, to the education, and so on.The Satsuma feudal clan's emphasis on education promoted it to build the first Budo gymnasium, including the Inuomono stadium and the Zoshi gym, despite of the clan's great debt.The courses of the sword was most emphasized; horseriding and archery were taught every day and the handle of a long sword and a spear were done every other day.The Satsuma teachers of Budo were the first persons who with feudal masters went to Edo to study Budo. Other feudal clans came to Satsuma to teach errantry of knights.The Budo school had its foundations before the modern times and since then, it has spread throughout Japan.
- 著者
- 江川 優子 麻原 きよみ 大森 純子 奥田 博子 嶋津 多恵子 曽根 智史 田宮 菜奈子 戸矢崎 悦子 成瀬 昂 村嶋 幸代
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.10, pp.677-689, 2023-10-15 (Released:2023-10-28)
- 参考文献数
- 22
目的 日本公衆衛生学会に設置された「平成29/30年度公衆衛生看護のあり方に関する委員会」では,公衆衛生および公衆衛生看護教育の実践と研究のための基礎資料を提供することを目的として,公衆衛生および公衆衛生看護のコンピテンシーの明確化を試みた。方法 米国の公衆衛生専門家のコアコンピテンシーおよび公衆衛生看護におけるコンピテンシーを翻訳し,共通点と相違点を検討した。次に,米国の公衆衛生看護のコンピテンシーと日本の公衆衛生看護(保健師)の能力指標の共通点と相違点を検討し,公衆衛生および公衆衛生看護のコンピテンシーの明確化に取り組んだ。結果 公衆衛生と公衆衛生看護のコンピテンシーには,集団を対象とし,集団の健康問題を見出し,健康課題を設定し働きかけるという共通点がみられた。しかし,集団の捉え方,健康問題の捉え方と健康課題設定の視点,集団における個人の位置づけに相違があった。公衆衛生では,境界が明確な地理的区域や民族・種族を構成する人口全体を対象とし,人口全体としての健康問題を見出し,健康課題を設定しトップダウンで働きかけるという特徴があった。また,個人は集団の一構成員として位置づけられていた。一方,公衆衛生看護では,対象は,個人・家族を起点にグループ・コミュニティ,社会集団へと連続的かつ重層的に広がるものであった。個人・家族の健康問題を,それらを包含するグループ・コミュニティ,社会集団の特性と関連付け,社会集団共通の健康問題として見出し,社会集団全体の変容を志向した健康課題を設定し取り組むという特徴があった。日米の公衆衛生看護のコンピテンシーは,ともに公衆衛生を基盤とし公衆衛生の目的達成を目指して構築されており,概ね共通していた。しかし,米国では,公衆衛生専門家のコアコンピテンシーと整合性を持って構築され,情報収集能力,アセスメント能力,文化的能力など,日本では独立した能力として取り上げられていない能力が示され,詳細が言語化されていた。結論 公衆衛生の目的達成に向けたより実効性のある公衆衛生・公衆衛生看護実践を担う人材育成への貢献を目指し,日本の公衆衛生従事者の共通能力が明確化される必要がある。また,公衆衛生看護では,これまで独立した能力として言語化されてこなかった能力を一つの独立した能力として示し,これらを構成する詳細な技術や行為を洗い出し,言語化していく取り組みの可能性も示された。
1 0 0 0 OA 幼児期における体力差の縦断的推移:3 年間の追跡データに基づいて
- 著者
- 春日 晃章
- 出版者
- 日本発育発達学会
- 雑誌
- 発育発達研究 (ISSN:13408682)
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, no.41, pp.41_17-41_27, 2009 (Released:2012-10-09)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1 2
The purpose of this study to examine the difference in physical fitness levels among young children from the age of three until the age of five. The study analyzed data obtained through a pursuit measurement of the same subjects conducted for a period of three years. The subjects were 206 young children(104 boys and 102 girls)with standard physiques. We administered physical tests comprising seven types of exercises to understand their physical fitness characteristics;the tests were conducted every year in November for three years. Finally, the subjects were divided into the upper-ranking group(20%)and the lower-ranking group(20%)on the basis of the results of the physical tests at three-years old that corrected the age;further, the extent to which the difference between the two groups changed after two years was examined for each type of exercise. To conduct a statistical analysis of the data, a two-way ANOVA and the multiple comparisons(Tukey's HSD test)were employed. The analysis revealed a significant difference between the two groups for all types of exercises(in the case of both boys and girls). The gap reduced with each passing year for the side-step, 25-m run, and sitting trunk flexion. The exercise types for which the gap reduced until the age of four were grip strength and standing long jump. In the case of softball throw and upright hand standing time, the gap reduced until the age of four and then increased at the age of five. However, the gap did not reverse at the age of five for any exercise type. The level of physical fitness at the age of five remains strongly influenced by that at the age of three. The results suggested that the gap in the physical fitness among Japanese pupils has already begun to be observed in young children.