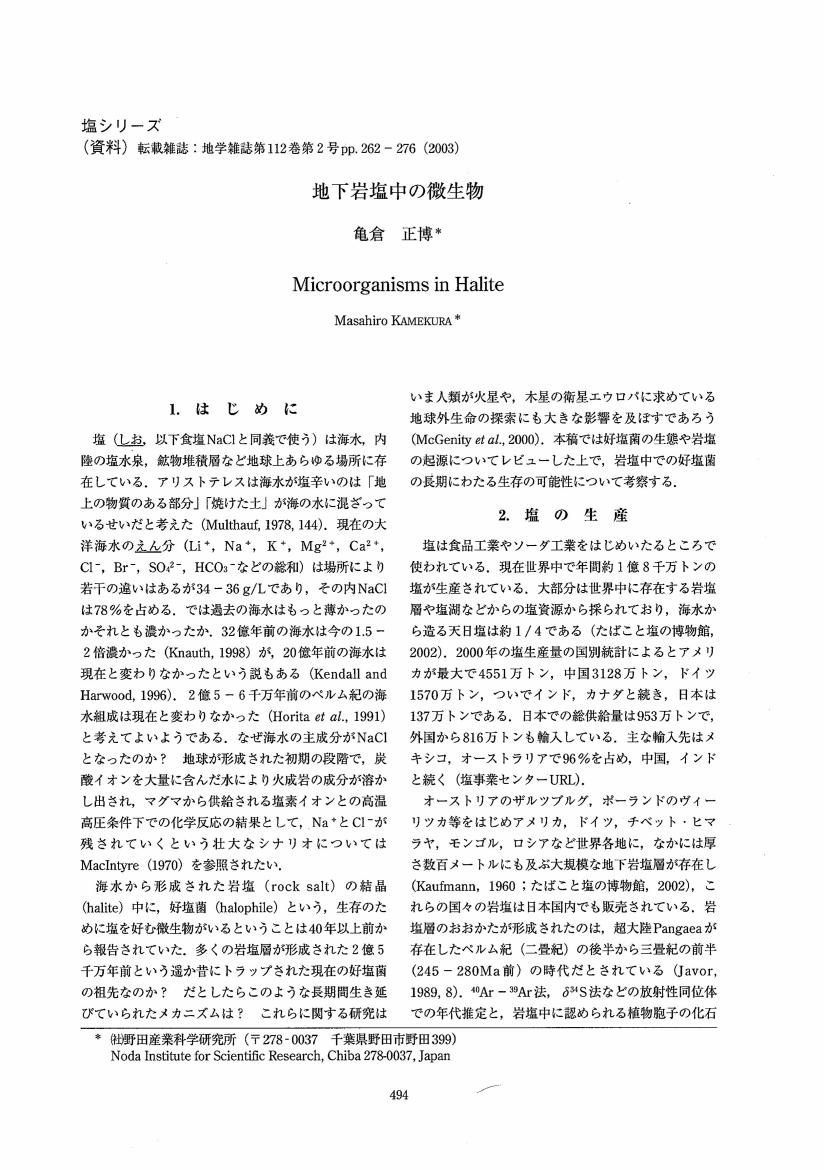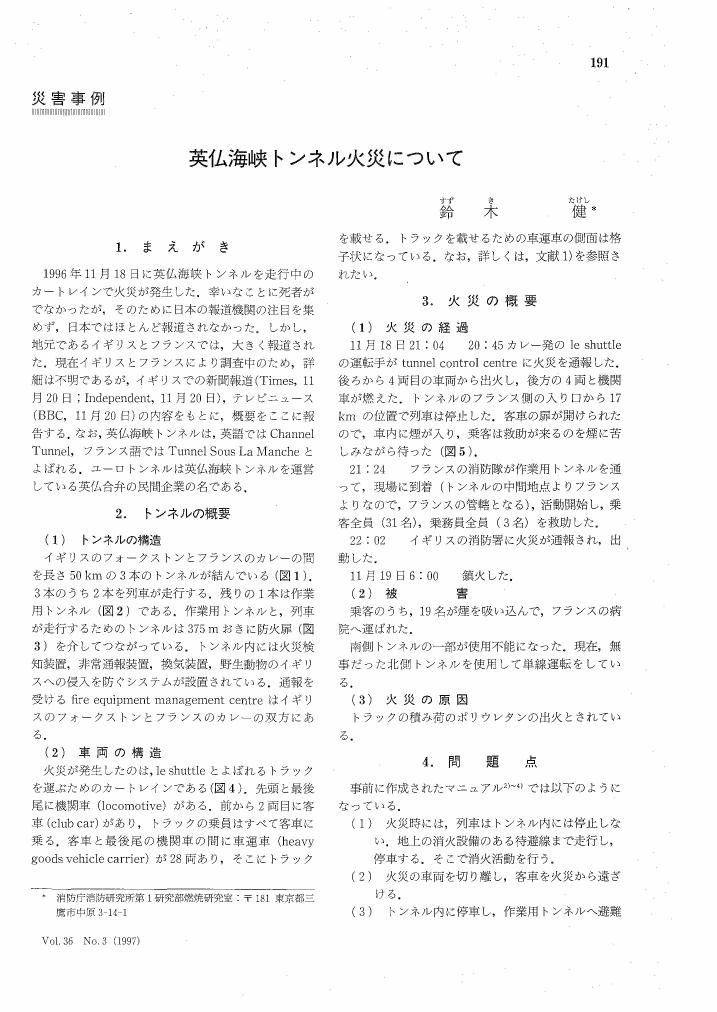1 0 0 0 OA 異なる牛肉脂肪中のMUFA割合と食味特性
- 著者
- 露木 理紗子 中島 菜恵子 松村 扶佐 鈴木 啓一 飯田 文子
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成24年度日本調理科学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.148, 2012 (Released:2012-09-24)
【目的】和牛肉のおいしさには脂肪中の脂肪酸組成が関与し、特にオレイン酸を含む一価不飽和脂肪酸(以下、MUFA)割合が高いものは食味特性が優れ、枝肉の取引価格に影響を与えている。そこで、MUFA割合が牛肉の食味特性へ与える影響について官能評価を行い、比較検討した。【方法】牛肉脂肪中の脂肪酸組成の明らかなBMS№4・7・9の仙台黒毛和牛54頭サーロインについて、8段階評価尺度での官能評価を訓練パネル10名で行った。うま味の評価では、香りの混入を避けるためノーズクリップを使用し行った。1㎝厚さにスライスした牛肉を、200℃に温めたホットプレート上で表面60秒、裏面75秒加熱した。それを線維方向を統一し、3×4㎝に切り出し、順序効果をふまえ、9項目につき評価を行った。クッキングロスは、焼成前後の重量の損失を百分率で表した。また破断測定および理化学測定を行った。【結果・考察】官能評価の「風味の強さ」「うま味」において、MUFA割合間で有意な差がみられた(p<0.05)。重回帰分析による「総合評価」に寄与する項目は、「うま味」「良い牛くささ」の風味に関する項目で寄与率82.7%であった。官能評価項目の「うま味」とうま味に関わるアミノ酸やイノシン酸分析値との関連はみられず、アミノ酸・核酸成分以外に「うま味」の評価に関わるものがあると推察された。さらに、クッキングロスが高い肉は、破断測定値においても高い値を示す傾向があり、それは特に雌に顕著であることから、MUFA割合が高く筋線維が軟らかいとクッキングロスが増加し食感が悪くなるため、高すぎるものは好ましくなく、最適MUFA割合は59 %程度と結論づけられた。
1 0 0 0 OA 『日本帝皇年代記』について : 入来院家所蔵未刊年代記の紹介(上)
- 著者
- 山口 隼正
- 雑誌
- 長崎大学教育学部社会科学論叢 (ISSN:03882780)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, pp.A1-A39, 2004-03-26
1 0 0 0 OA 経済行動分析のための数理物理モデル
- 著者
- 高橋 泰城
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理学会学術講演会講演予稿集 第80回応用物理学会秋季学術講演会 (ISSN:24367613)
- 巻号頁・発行日
- pp.249, 2019-09-04 (Released:2022-07-22)
1 0 0 0 OA 第三者行為の届出と倫理的ジレンマ:2症例報告
- 著者
- 石川 博康 糟谷 昌志
- 出版者
- 日本臨床倫理学会
- 雑誌
- 臨床倫理 (ISSN:21876134)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.38-44, 2017 (Released:2021-07-12)
- 参考文献数
- 9
本邦の健康保険制度は,第三者行為により生じた傷病に対して代替的給付を行う仕組みを有している.患者がこの給付を受けるには第三者行為の届出が必要条件となるが,この届出は後に補償問題を惹起するため,患者と医師の意見が一致せず,倫理的ジレンマが生じる可能性がある.しかし,本邦ではこれまで,第三者行為の届出やこの代替的給付の仕組みと関連して医師の倫理的問題は研究されていなかった. 我々は,第三者行為の届出と関連して倫理的ジレンマを生じた2症例を経験した.2症例とも,療養の給付事由に対する第三者行為の関与が絶対的なものではなかった.1例では医師の説得により届出が行われ,もう1例では届出が行われなかった.症例の経験を通して,この代替的給付の仕組みに関する幾つかの問題を指摘した.今後,第三者行為が部分的に関与した傷病の医療費請求のあり方について,さらなる議論を通じ,将来何らかの指針などが示されるべきであろう.
- 著者
- 中井 將人 吉川 明良 舟原 宏子 開 浩一
- 出版者
- 一般社団法人日本医療薬学会
- 雑誌
- 医療薬学 (ISSN:1346342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.6, pp.307-315, 2021-06-10 (Released:2022-06-10)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1
The criteria for palliative chemotherapy discontinuation have not been adequately systematized. We evaluated the relevance of the neutrophil-lymphocyte ratio, platelet-lymphocyte ratio, prognostic nutritional index, modified Glasgow Prognostic Score (mGPS), and clinicopathological factors as potential factors for chemotherapy discontinuation in patients with recurrent and unresectable pancreatic cancer.We retrospectively analyzed the data of 91 patients who received palliative chemotherapy for recurrent and unresectable pancreatic cancer at Hiroshima City Hospital between April 2014 and March 2018. Factors significantly related to chemotherapy discontinuation were extracted using Coxʼs proportional-hazard model, and a prognostic model was established by combining these factors.The median overall survival was 76 days. Multivariate analysis of the factors revealed that the mGPS (0/1-2) (hazard ratio [HR] = 3.053, P = 0.005), the presence of distant metastatic disease (HR = 2.605, P < 0.001), and the status of recurrent or initially unresectable disease (HR = 2.587, P = 0.013) were significantly associated with the discontinuation decision. One point was assigned to each of these three factors to create the prognostic model. A total score index of 0-3 was used to categorize three prognostic risk groups. The high-risk group (3 points) had a significantly lower overall survival than the low- (≤1 point) (P < 0.001) and intermediate-risk (2 points) groups (P < 0.001).Our study shows that mGPS and this prognostic model can help determine whether chemotherapy should be discontinued in patients with relapsed and unresectable pancreatic cancer.
1 0 0 0 OA 文明批判の存在論的再構成 H.マルクーゼ『エロスと文明』を中心に
- 著者
- 馬渡 玲欧
- 出版者
- 日本社会学理論学会
- 雑誌
- 現代社会学理論研究 (ISSN:18817467)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.68-80, 2017 (Released:2020-03-09)
本稿はH. マルクーゼ『エロスと文明』に焦点を当てながら、マルクーゼのエロス的文明論をギリシャ哲学由来の「伝統的存在論」に対する批判という観点から再構成することによって、マルクーゼがM.ハイデガーの「死へ臨む存在」論の限界を乗り越えようとしたことを示す。方法として、マルクーゼがハイデガーの弟子であり、後年まで密かにハイデガー思想が彼に影響を与えていたことを踏まえながら、両者の議論を比較する。ハイデガーとの共通点とは西欧哲学の伝統的存在論に対する批判である。ただし社会変革の主体を探求するマルクーゼはハイデガーの基礎存在論ではなく、より直接的に人間存在の本質を探求する考察に向かう。その際マルクーゼは、フロイトをプラトン哲学の延長に位置づけることで、フロイトの欲動論に人間存在の本質としてのエロスを見出す。また、ハイデガー存在論においては「時間」が考察の手がかりとなり、「通俗的時間概念」が批判された。ロゴスだけではなく、直線的時間意識も同様に人間存在の本質を規定する思考様式である。ハイデガーは「死へ臨む存在」の関心に通俗的時間概念を乗り越える視座を見出す。他方マルクーゼはこの時間意識を批判するために、「永劫回帰」の思想を取り上げる。「永劫回帰」によって、人間のエロスに対する「意志」は肯定される。人間の死を合理的に解釈する実存哲学を批判し、人間の非合理的な死ではない「生物学的な自然死」を強調するマルクーゼは、「死へ臨む存在」が人間の本質であるとみなすハイデガーを乗り越えようとした。
1 0 0 0 OA 地下岩塩中の微生物
- 著者
- 亀倉 正博
- 出版者
- 日本海水学会
- 雑誌
- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.5, pp.494-505, 2004 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 88
1 0 0 0 OA 海底地震観測によるトカラ海峡-奄美大島北部海域の地震活動
- 著者
- 八木原 寛 角田 寿喜 宮町 宏樹 後藤 和彦 平野 舟一郎 日野 亮太 金澤 敏彦 海宝 由佳 塩原 肇 渡邊 智毅 望月 将志 根本 泰雄 島村 英紀
- 出版者
- 公益社団法人 日本地震学会
- 雑誌
- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.227-239, 1996-08-23 (Released:2010-03-11)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1 1
We investigated seismic activity around Tokara Channel north off Amami Oshima, Nansei Syoto (Ryukyu) Islands of western Japan, using 12 ocean-bottom seismographs (OBS), as well as two temporal stations at Yaku Shima and Amami Oshima islands, operated from April 16 to May 10, 1992. One-dimensional velocity structure and station corrections were inverted from P and S times of 51 events provisionally well-located in the OBS network. We then relocated precisely 239 events in the studied region, using the inverted velocity structure and station corrections.Seismicity was highest in an area of about 10km×10km near the trench axis northeast off the OBS network: the largest event of MJMA 5.6 and other 40 events (probably aftershocks) were located at shallow depths. A mechanism solution of normal fault type with a T-axis of NW direction for the largest event was concordant with bending process of the Philippine sea plate. On the other hand, 18 events at depths of about 30km in a small area north of the OBS network were presumably due to interplate thrusting, because a composite mechanism solution for three events was of reverse fault type with a P-axis of ESE direction. A cluster of 17 events at depths from 10km to 25km was found in a southwest area of the network. These shallow events were probably crustal earthquakes within the Eurasian plate.We found an area of very low seismicity in the southeast of the network during the period studied. It is also identified at the nearly same location in the epicenter distribution from 1984 through 1991 obtained by Japanese Meteorological Agency (JMA) and possibly corresponds to the aftershock area of the 1911 Kikaijima Earthquake (M 8.0).Although we could not confirm any discernible alignments of shallow earthquakes along the Tokara Channel which is a notable tectonic line, the dipping angle of the intermediate-deep seismic zone changes discontinuously from about 65° on the north of the channel to about 40° on the south.
1 0 0 0 OA テッポウエビ類の巣穴構造―巣穴形成と共生者による巣穴利用―
- 著者
- 邉見 由美
- 出版者
- 日本甲殻類学会
- 雑誌
- CANCER (ISSN:09181989)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.71-75, 2019-08-01 (Released:2019-09-03)
- 参考文献数
- 16
1 0 0 0 OA 英仏海峡トンネル火災について
- 著者
- 鈴木 健
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.191-193, 1997-07-15 (Released:2017-05-31)
1 0 0 0 OA 精神科診療におけるWAIS-IVの有用性について --成人期の発達障害に関する検討--
- 著者
- 久保 りつ子
- 出版者
- 大阪経大学会
- 雑誌
- 大阪経大論集 (ISSN:04747909)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.6, pp.63-76, 2023-03-15 (Released:2023-04-06)
- 著者
- 小野寺 瑞穂 一之瀬 大雅 泉山 塁威
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画報告集 (ISSN:24364460)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.279-286, 2023-09-07 (Released:2023-09-07)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
近年、エリアマネジメントが展開するとともに、都市再生推進法人制度等により公民連携まちづくりが展開されている。本研究では、公民連携によるまちづくりの一つである「エリアプラットフォーム」に着目し、その支援事業である「官民連携まちなか再生推進事業」に採択された98団体を対象に、地域特性による分類・分析を通じて、エリアプラットフォームの組織及び活動の特徴を明らかにすることを目的とする。アンケート調査によりエリアプラットフォームの現状と実態を明らかにした上で、地域特性による分類を行い、4つのパターンに整理した。また、各パターンの組織や活動内容を複合的に分析することで、比較分析を行った。本研究により、各エリアプラットフォームが現状の立ち位置を把握した上で、類似事例を参照しやすくする点に有用性があると考える。
- 著者
- 竹中 彩 水信 夏穂 溝口 萌 山﨑 正代 泉山 塁威
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画報告集 (ISSN:24364460)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.317-324, 2023-09-07 (Released:2023-09-07)
- 参考文献数
- 20
本研究は、設置管理許可制度の導入による都心部の都市公園整備がもたらす周辺地域の変化を明らかにすることを目的とする。加えて、今後の都市公園整備を実施する自治体及び民間事業者に向けて周辺地域の変化を考慮したパークマネジメントの留意点を示す。 設置管理許可制度の導入前後における、南池袋公園及び天王寺公園の周辺地域の建物用途、路線価、都市公園と店舗の関係を分析し、インタビュー調査を行うことで、都市公園の空間整備が周辺地域の変化と関連していることが明らかになった。今後は、都市公園と周辺地域の関係をより詳細に明らかにするため、都市公園沿道の店舗以外や都市公園整備前から店舗を構える既存店舗など、周辺店舗の調査を拡大することが望まれる。
1 0 0 0 OA 曽我量深「日蓮論」における日蓮本仏思想
- 著者
- 角田 佑一
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.1, pp.51-74, 2023-06-30 (Released:2023-09-08)
本論の主題は、曽我量深(一八七五―一九七一)の「日蓮論」における日蓮本仏論の構造を解明することである。曽我は近代日本を代表する浄土真宗の教学者である。彼は二〇歳代の頃、日蓮研究を行い、同時代の日蓮主義から影響を受けて、自らの日蓮理解を深めていった。曽我の「日蓮論」(一九〇四年)において、彼の日蓮理解はさまざまに変化するが、最終的に彼は「日蓮本仏・釈尊迹仏」の見解を示す。筆者の解釈では、曽我の述べる「日蓮本仏・釈尊迹仏」の基盤には以下のような構造があると考えられる。すなわち、日蓮が自らの罪悪と無力を自覚して題目を受持するとき、久遠実成の如来を自らの主体として認識し、「本仏」としての自覚に至る。そのうえで、日蓮は久遠実成の釈尊を客体として認識し、釈尊を「迹仏」であるとみなす。曽我の日蓮本仏論の特色は、日蓮の罪悪と無力の自覚、題目受持、「本仏」としての自覚が相互に深く結びついている点である。
- 著者
- 増田 友哉
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.1, pp.27-49, 2023-06-30 (Released:2023-09-08)
本稿は平田篤胤(一七七六―一八四三・安永五―天保十四)の思想における、ウブスナ神という存在に注目し、篤胤の思想においてウブスナ神が担った役割を捉えなおす事を目的とする。その際、篤胤が近世社会におけるウブスナ神の受容から発展させた逸脱を捉える。また、篤胤のウブスナ神に関する語りを民俗や怪異の探求という視点のみで捉えるのではなく、篤胤が神話の解釈を基に創造したコスモロジーにおける、ウブスナ神の位置や役割を明らかにすることに本稿の目的がある。篤胤は世界生成の根源神であるムスビ二神の意志に基づき、オホクニヌシが人間の死後を掌り、そしてその役割をウブスナ神に委譲したと考えたのである。本稿の結論は、篤胤が近世人の日常生活に身近なウブスナ神を媒介として、自らを含む民衆一人一人の生死を、『古史伝』で創造したコスモロジーへと架橋することを可能としたということである。
1 0 0 0 OA 本居宣長「物のあはれ」説の成立と仏教の哲学的思考
- 著者
- 清田 政秋
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.1, pp.1-26, 2023-06-30 (Released:2023-09-08)
従来本居宣長は仏教批判者とされ、また宣長自身が自らの学問への仏教の影響を語らないために、宣長研究は仏教を考慮外に置いてきた。それに対し漢学との関係は、宣長が京都で医学修行の基礎として学んだ関係からよく研究された。しかし宣長の学問は仏教と深く関連し、それを追究すれば宣長について従来とは異なる新たな知見が得られる。それは宣長にとって仏教とは何であったかの追究でもある。本稿は宣長の学問の出発点である「物のあはれ」説を取り上げる。「物のあはれ」説には膨大な先行研究があるが、まだ十分明らかになっていない問題がある。宣長は、その説は藤原俊成の「恋せずは人は心もなからまし物のあはれも是よりぞ知る」の歌がきっかけになったと語る。だが研究史では俊成の歌からいかにして「物のあはれ」説が成立したかは十分解明されていない。本稿はその成立に『摩訶止観』の心の有り様と感情をめぐる仏教の哲学的思考が関わることを明らかにする。
1 0 0 0 OA 日本のCOVID-19ワクチン ──何故遅れたのか?
- 著者
- 中山 哲夫
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.10, pp.10_58-10_64, 2021-10-01 (Released:2022-02-25)
- 参考文献数
- 15
2021年2月17日からファイザー社のmRNAワクチンの接種が始まった。欧米では既に2020年12月からファイザー、モデルナ社のmRNAワクチンだけでなくアストラゼネカ社のウイルスベクターワクチンも承認され接種が始まっている。一方、国産ワクチンはDNA、mRNA、精製蛋白、全粒子不活化ワクチンが開発されPhase I/II試験が終了してPhase IIIの検討にはいっている。先行し認可されている主なワクチンはいずれも従来のタンパク製剤や不活化ワクチンと異なる遺伝子情報に基づくワクチンである。欧米では病原体発見から1年ほどで開発認可されたが、我が国の開発が立ち遅れた要因について考察する。
- 著者
- 武内 博朗 花田 信弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3, pp.206-214, 2019 (Released:2019-07-30)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
歯を喪失すると咀嚼機能が低下する.咀嚼機能が低下した状態では,糖質の摂取量が増加する.一方で低GI食品,タンパク質,抗酸化物質,食物繊維,ビタミン群,ミネラル群などの摂取量が低下する.ブドウ糖負荷の増加およびタンパク質エネルギー低栄養の状態はメタボリック症候群やフレイル,さらには非感染性疾患Non Communicable Diseases(NCDs)の発症リスクを上昇させる. 本稿は,歯科補綴治療による咀嚼機能回復と栄養指導を中心とする保健指導の集中運用が体組成や代謝指標にもたらす健康増進効果について症例を提示し紹介する. 大臼歯欠損者71名を対象に歯科補綴治療介入前後の咀嚼機能値を評価した.また,71名の症例のうち歯科補綴と同時に保健指導を実施した25名について,歯科補綴治療介入前および保健指導90日後に体組成,血圧測定,血液検査を行い,体組成・代謝について数値を比較評価した. 歯科補綴による咀嚼機能向上が71名の全症例で認められた.保健指導を実施した25名の全症例で基礎代謝基準値(骨格筋量),BMI,体脂肪率,内臓脂肪レベル,タンパク質充足率が改善した.HbA1cは保健指導群のうち測定した7例全例で改善した. 咀嚼機能低下者におけるNCDsの発症予防,重症化予防のためには,歯科補綴による咀嚼機能回復と同時に行う保健指導が有効と考えられた.
1 0 0 0 OA 高齢市中肺炎患者における入院中の身体活動量と入院関連能力低下との関連
- 著者
- 禹 炫在 青木 秀樹 片岡 英樹 山下 潤一郎 吉武 孝敏 神津 玲
- 出版者
- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.345-351, 2023-08-31 (Released:2023-08-31)
- 参考文献数
- 31
目的:高齢市中肺炎患者における身体活動量と入院関連能力低下(hospitalization-associated disability: HAD)の発生との関係,および身体活動量のカットオフ値を検討することである.方法:市中肺炎の診断にて,入院後48時間以内に呼吸リハビリテーションが開始された高齢患者を対象に,入院後の7日間に身体活動量を計測,1日当たりの身体活動量とHAD発生との関連とカットオフ値を調査した.退院時のBarthel Index合計点数が入院前より5点以上低下した場合をHADと定義した.結果:対象者95例(82[71-91]歳)のうち,33例(35%)にHADが発生した.単変量分析の結果,HAD発生には低活動と連続臥床時間の延長が説明因子であった.受信者操作特性分析の結果,1日当たりのカットオフ値は歩行時間12分,歩数1,112歩であった.結論:高齢市中肺炎患者はHAD発生率が高く,その発生に影響する身体活動量のカットオフ値は臨床現場での目標設定の指標となる可能性が示唆された.