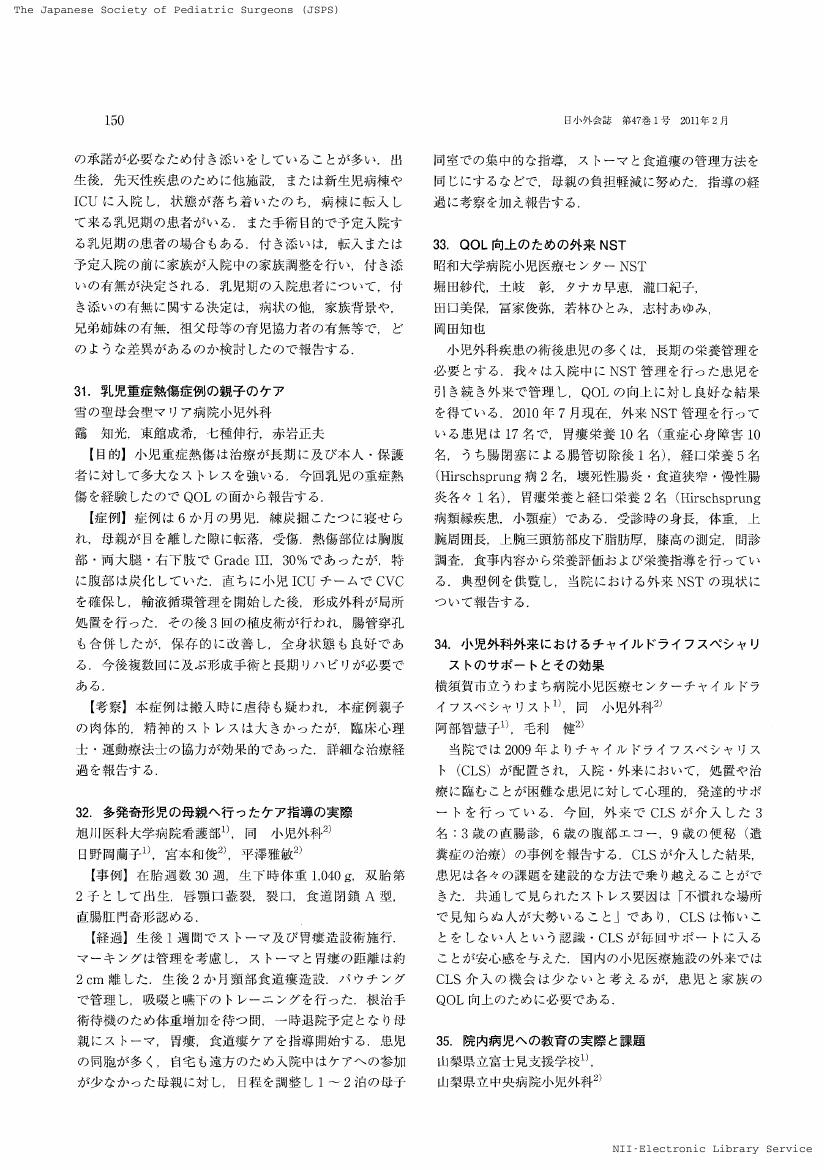1 0 0 0 OA 金属溶接部の微生物腐食
- 著者
- 菊地 靖志 松田 福久
- 出版者
- 社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- 日本金属学会会報 (ISSN:00214426)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.6, pp.393-397, 1993-06-20 (Released:2011-08-10)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 2 2
1 0 0 0 OA 抗ganglionicアセチルコリン受容体抗体が陽性を呈した全身性無汗症の1例
- 著者
- 兒玉 憲人 﨑山 佑介 小迫 拓矢 武井 藍 中村 友紀 橋口 昭大 道園 久美子 松浦 英治 中根 俊成 髙嶋 博
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.1, pp.95-102, 2018-01-10 (Released:2019-01-10)
- 参考文献数
- 10
42歳,男性.全身の発汗低下を主訴に受診した.起立性低血圧や頻尿を伴い,広汎な自律神経障害が示唆された.皮膚生検で汗腺及び血管周囲にリンパ球浸潤を認め,抗ganglionicアセチルコリン受容体抗体陽性が判明した.通常,同抗体は自己免疫性自律神経節障害(autoimmune autonomic ganglionopathy:AAG)の原因となるが,汗腺への直接作用は明らかでない.本症例には汗腺と自律神経節障害の両者の特徴が混在し,ステロイド治療が有効であった.
1 0 0 0 OA ECMO患者搬送におけるヘッドイモビライザーの有用性
- 著者
- 松村 一希 濱口 純 清水 敬樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.5, pp.429, 2023-09-01 (Released:2023-09-01)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 OA FQテストによる頸髄損傷患者の手機能評価
- 著者
- 清野 良文 橋爪 長三 赤津 昇
- 出版者
- The Japanese Association of Rehabilitation Medicine
- 雑誌
- リハビリテーション医学 (ISSN:0034351X)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.7, pp.476-483, 1996-07-18 (Released:2009-10-28)
- 参考文献数
- 18
当センターに入院した頸髄損傷完全麻痺患者35例67手に対しFQテストを施行し,麻痺レベルとFQとの関係を調べるとともに,上肢機能再建手術による改善を評価した.最低機能髄節が下がり有効な筋が増えるに従ってFQは高値を示し,さらに同じ麻痺レベルでも高齢者は低値を示す傾向を認めた.手機能再建手術によってFQは平均で約14点の改善が得られた.ADLがやっと自立可能と考えられるFQのレベル(20~30点)はZancolliの2-B:II,2-B:IIIに相当していたが,手機能再建手術によって1-Bから2-B:Iの症例もこのレベルに到達していた.総合的な手機能の評価法としてFQテストは有用であったが,評点と因子得点率を詳細に分析するにあたっては注意を要した.
- 著者
- 阿部 智慧子 毛利 健
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本小児外科学会
- 雑誌
- 日本小児外科学会雑誌 (ISSN:0288609X)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.150, 2011-02-20 (Released:2017-01-01)
1 0 0 0 OA 大量データに対するSHA-1計算のSSEによるスループット向上の検討
- 著者
- 坪内佑樹 置田真生 伊野文彦 萩原兼一
- 雑誌
- ハイパフォーマンスコンピューティングと計算科学シンポジウム論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2012, pp.77, 2012-01-17
- 著者
- Damien Simon Atsushi Mukaiyama Yoshihiko Furuike Shuji Akiyama
- 出版者
- The Biophysical Society of Japan
- 雑誌
- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.e190008, 2022 (Released:2022-04-14)
- 参考文献数
- 49
- 被引用文献数
- 1 5
KaiC is the central pacemaker of the circadian clock system in cyanobacteria and forms the core in the hetero-multimeric complexes, such as KaiB–KaiC and KaiA–KaiB–KaiC. Although the formation process and structure of the binary and ternary complexes have been studied extensively, their disassembly dynamics have remained elusive. In this study, we constructed an experimental system to directly measure the autonomous disassembly of the KaiB–KaiC complex under the condition where the dissociated KaiB cannot reassociate with KaiC. At 30°C, the dephosphorylated KaiB–KaiC complex disassembled with an apparent rate of 2.1±0.3 d–1, which was approximately twice the circadian frequency. Our present analysis using a series of KaiC mutants revealed that the apparent disassembly rate correlates with the frequency of the KaiC phosphorylation cycle in the presence of KaiA and KaiB and is robustly temperature-compensated with a Q10 value of 1.05±0.20. The autonomous cancellation of the interactions stabilizing the KaiB–KaiC interface is one of the important phenomena that provide a link between the molecular-scale and system-scale properties.
1 0 0 0 OA 「セイレーン」における「逃走」と「追跡」のモチーフ
- 著者
- 戸田 勉
- 出版者
- 山梨英和学院 山梨英和大学
- 雑誌
- 山梨英和短期大学紀要 (ISSN:02862360)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.47-57, 1992-12-10 (Released:2020-07-20)
本稿は、ジェイムズ・ジョイスの『ユリシーズ』第二挿話「セイレーン」における技法「カノン形式のフーガ」の一側面を考察したものである。これまでこの技法に関して繰り広げられてきたさまざまな議論を踏まえつつ、フーガ形式の模倣反復という特質を「逃走」と「追跡」という動きに還元し、その観点から挿話全体の構成を分析した。一では、人物の外面的な動きを中心に考察し、ブルームにとってセイレーンとは誰(何)かについて探った。二ではーブルームの内面的な動きを追い、セイレーンの本当の姿について検討を加えた。三では、「丸刈り組」という曲とフルームの関係から、別な種類のセイレーンの正体を突きとめ、この挿話のもう一つの主題について考えた。
1 0 0 0 OA 多メディア時代に於ける新聞の環境変化と存続のための諸条件
- 著者
- 森本 光彦
- 出版者
- 山梨英和学院 山梨英和大学
- 雑誌
- 山梨英和大学紀要 (ISSN:1348575X)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.A1-A15, 2010 (Released:2020-07-20)
IT化の目覚ましい進展により世界の新聞メディアは電子新聞の登場などで紙の媒体としてのあり方に大きな変革を迫られつつある。逆境の中にあるという点では共通しているものの、経営の悪化から身売りや廃刊が目立つ米欧の新聞に対し、日本の新聞はやや事情を異にする。日本の場合、広告費収入より購読費収入の方が大きい。しかも高い宅配率に支えられているため販売部数の急激な落ち込みが避けられており、米欧のような急速な経営悪化を免れている。米欧主要紙では電子媒体を通じて「ネット購読」を有料とする課金化の動きが目立つのに対し、そこまで経営が悪化していない日本の全国紙の場合、将来を見越した対応には各社間での開きが目立つ。本稿では、米欧の新聞と比較しながら日本の新聞を取り巻く環境の変化と現状を見、その上で今後生き残るための諸条件について考察する。
1 0 0 0 OA 22kVポリマー引留がいしの開発
- 著者
- 原 慎吾
- 出版者
- 一般社団法人 電気設備学会
- 雑誌
- 電気設備学会誌 (ISSN:09100350)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.11, pp.676-677, 2020 (Released:2020-11-10)
1 0 0 0 OA Mitigate: Toward Comprehensive Research and Development for Analyzing and Combating IoT Malware
- 著者
- Koji NAKAO Katsunari YOSHIOKA Takayuki SASAKI Rui TANABE Xuping HUANG Takeshi TAKAHASHI Akira FUJITA Jun'ichi TAKEUCHI Noboru MURATA Junji SHIKATA Kazuki IWAMOTO Kazuki TAKADA Yuki ISHIDA Masaru TAKEUCHI Naoto YANAI
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- IEICE Transactions on Information and Systems (ISSN:09168532)
- 巻号頁・発行日
- vol.E106.D, no.9, pp.1302-1315, 2023-09-01 (Released:2023-09-01)
- 参考文献数
- 40
In this paper, we developed the latest IoT honeypots to capture IoT malware currently on the loose, analyzed IoT malware with new features such as persistent infection, developed malware removal methods to be provided to IoT device users. Furthermore, as attack behaviors using IoT devices become more diverse and sophisticated every year, we conducted research related to various factors involved in understanding the overall picture of attack behaviors from the perspective of incident responders. As the final stage of countermeasures, we also conducted research and development of IoT malware disabling technology to stop only IoT malware activities in IoT devices and IoT system disabling technology to remotely control (including stopping) IoT devices themselves.
1 0 0 0 OA 過疎山村に出現する無居住寺院の実態とその対応
- 著者
- 中條 暁仁
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2021年度日本地理学会春季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.78, 2021 (Released:2021-03-29)
近年,過疎山村では残存人口の少子高齢化が顕著に進み,中には高齢人口すらも減少に転じる地域が現れるなど,本格的な人口減少社会に突入している。こうした中にあって,地域社会とともにあり続けた寺院が消滅していくとする指摘がなされている。村落における寺院は集落コミュニティが管理主体となる神社とは異なり,住職とその家族(寺族)が居住し相続する。そして,檀家家族の葬祭儀礼や日常生活のケアに対応することを通じて地域住民に向き合ってきた。いわば寺院は家族の結節点として機能してきたが,現代の山村家族は他出子(別居子)を輩出して空間的に分散居住し,成員相互の関係性に変化を生じさせているため,これに対応せざるを得なくなっている。こうした寺院のすがたは山村家族の変化を反映するものであり,寺院研究を通じて山村社会の特質に迫ることができると考えられる。 ところで,既存の地理学研究では,寺院にとどまらず神社も含めて村落社会に所在する宗教施設は変化しない存在として扱われてきた感が否めない。すなわち,寺社をとりまく地域社会が変化しているにも関わらず,旧態依然とした存在として認識されている。その背景には,伝統的な村落社会に対する理解を目指す研究が多かったこと,現代村落を対象とするにしても研究者が得る寺社に関する情報がかなり限定されたものであることなどから,固定的なイメージで語られる場合が多かったと思われる。 こうした問題意識をふまえると,地域社会の変貌が著しい過疎山村を対象として寺院の実態を明らかにする意義が見いだされる。本発表では,存続の岐路に位置づけられる無居住寺院に注目し,無居住化の実態とその対応の限界を報告する。 報告者は過疎地域における寺院をとらえる枠組みを,住職の存在形態に基づいて時系列に4つの段階に区分して仮説的に提起している。住職の有無が,寺檀関係や宗務行政における寺院の存続を決定づけているためである。第 Ⅰ段階は専任の住職がいながらも,檀家が実質的に減少していく段階である。第Ⅱ段階は檀家の減少が次第に進み,やがて専任住職が代務(兼務)住職となり,住職や寺族が不常住化する段階である。第Ⅲ段階は,代務住職が高齢化等により当該寺院の法務を担えなくなるなどして実質的に無住職化に陥ったり,代務住職が死去後も後任住職が補充されなくなったりして無住職となる段階である。そして,第Ⅳ段階は無住職の状態が長らく続き,境内や堂宇も荒廃して廃寺化する段階である。 このうち,本報告が対象とする山梨県早川町は,第Ⅱ段階にある寺院が多数を占める地域となっており,第Ⅲ段階を経ずして第Ⅳ段階に至るケースもみられるなど,問題は深刻化している。 本報告で対象とする山梨県早川町には日蓮宗25ヶ寺をはじめ,真言宗1ヶ寺,臨済宗1ヶ寺,曹洞宗5ヶ寺の合計32ヶ寺が所在するが,そのうち住職が実質的に在住しているのは日蓮宗の4ヶ寺にとどまる。日蓮宗寺院を調査したところ,1950年代に寺院の無居住化が始まっており,その数を増やしながら現在に至っている。いわば寺院の無居住化が常態化した地域といえる。時空間的遷移をみると北部の奥地集落から無居住化が始まっており,集落の過疎化に伴って進行していることが明らかである。近年は中心集落の寺院においても無居住化しており,住職の後継者が得られなかったことが直接的な要因となっている。 近年増加する無居住寺院をめぐっては,その管理が問題となっている。山梨県早川町では,多くの寺院で儀礼や信仰の空間としての機能を維持するために,代務住職や近隣檀家が境内を管理していた。中には,堂宇の間取りを公民館として改装し,高齢者の「たまり場」,住民による集会の場としての機能を持たせている事例があった。一方で,堂宇の老朽化によって損傷が進み,少数の檀家による復旧が困難に陥っている寺院では,檀家の同意を得て代務住職が廃寺を決断していた。ひとたび自然災害や獣害によって堂宇が損傷すると,廃寺に至るケースもある。 本発表で取り上げた無居住寺院に対しては,今後,存続か廃寺かのいずれかの方向性が想定される。前者の場合は,所属宗派の信仰空間としての機能を維持すべきか,あるいは地域社会の共有空間とすべきかという方向性も検討課題となってくる。後者については,地域社会に開放された「サード・プレイス」としての対応が想定されるし,前者については「少数社会」の構築に関する議論が参考になる。少数の現地在住の住職で,広範に分布する無居住寺院を管理するシステムの構築が求められる。
1 0 0 0 OA 教材の特性を生かした「学び」の授業開発――新美南吉『ごんぎつね』を例にして――
- 著者
- 中野 登志美
- 出版者
- 全国大学国語教育学会
- 雑誌
- 国語科教育 (ISSN:02870479)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, pp.41-49, 2022-09-30 (Released:2022-11-01)
多くの小学校では、学習者がごんに同化した読み方をしたままで『ごんぎつね』の授業を終えるところに根本的な課題がある。その根本的な課題を追究すると、『ごんぎつね』の語りの構造と最終場面における視点の転換を正しく捉えていないことに原因があることが判明した。そこで本実践では、冒頭部分の一文に着目する授業を展開し、『ごんぎつね』が伝承物語であること、『ごんぎつね』の語りの構造をわかりやすく視覚化したスライドを提示すること、『ごんぎつね』はごんだけではなく兵十も変容すること、最終場面においてごんと兵十が限定的であっても通じ合って悲劇で終わる物語ではないこと、『ごんぎつね』の特性を生かして、「その後の兵十の物語」の創作活動をするなどを構想して授業を行った。その結果、児童達は対象化して『ごんぎつね』を読めており、本実践によって『ごんぎつね』の授業の課題を解決する有用性を見いだすことができた。さらに学習者の事例を分析して、学習者が『ごんぎつね』の語りの構造を理解する際に「中山様」と「加助」が鍵を握ることを指摘した。
本プロジェクトの目的は、心の理論と呼ばれる他者の心的状態を推測する認知能力と社会行動(利他性)の関連を検討することにある。本年度は昨年度実施した自閉症スペクトラム障害を抱えた成人(ASD参加者)を対象にした実験で測定した眼球運動の解析を行った。課題は自分より多い金額を受け取る人(Xさん)と自分より少ない金額を受け取る人(Yさん)が存在するという状況の中で、Xさんの取り分をどのくらい減らすか、もしくはYさんの取り分をどのくらい増やすかを回答するという方法で行った。実験の結果、まずASD参加者は、精神疾患や発達障害を持たない健常参加者よりもYさん(自分より少ない金額受け取る人)の取り分を増やさない傾向を持つことが明らかになった。また、注視時間に関してもASD参加者はYさんの利益に注意を払わない傾向を持つことが明らかになった。これらの結果は、ASD参加者は行動レベルでも認知レベルにおいても利他性に関して健常参加者とはまた違った傾向を持つことを示している。次に第二実験としてオキシトシンをASD参加者へ投与することで利他性が促進されるかどうかを確かめる研究を実施した。オキシトシンはこれまで授乳時、分娩時に重要な役割を果たすホルモンであると考えられてきたが、近年の研究の結果、他者に対する信頼や心の理論といった社会性を促進させる働きを持つことも明らかになった。またこれらの結果を受け、近年、ASDの改善薬として注目が集まっている。実験では、20名のASD参加者に対してオキシトシンを投与し、投与前後の利他性の程度を測定した。結果に関しては現在分析中である。
- 著者
- 佐藤 忠司 山村 由華 古賀 広幸 宮崎 澄雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児腎臓病学会
- 雑誌
- 日本小児腎臓病学会雑誌 (ISSN:09152245)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.29-32, 1999-04-30 (Released:2008-11-05)
- 参考文献数
- 6
TLS (Tumor lysis syndrome) は化学療法により,またはまれに自然に悪性腫瘍が急速崩壊し,高UA (尿酸) 血症などの代謝障害に引き続きARF (急性腎不全) に至る症候群である。私たちはALL (急性リンパ性白血病) の8歳女児例に抗腫瘍剤VCR (Vincristine),DNR (Daunorubicin),MTX (Methotrexate) の投与を開始したところ翌日までに麻痺性イレウス (腸閉塞) を発症した。その後3日間で高UA血症,高りん血症などが進行し,急性腎不全となった。低Ca血症,低Na血症,肺水腫などを合併したが腹膜透析療法を含む集中治療を行い救命した。
- 著者
- TAKEO OHNISHI KEN OHNISHI AKIHISA TAKAHASHI YOSHITAKA TANIGUCHI MASARU SATO TAMOTSU NAKANO SHUNJI NAGAOKA
- 出版者
- Journal of Radiation Research Editorial Committee
- 雑誌
- Journal of Radiation Research (ISSN:04493060)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.S, pp.S133-S136, 2002 (Released:2003-05-02)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 20
Although physical monitoring of space radiation has been accomplished, we aim to measure exact DNA damage as caused by space radiation. If DNA damage is caused by space radiation, we can detect DNA damage dependent on the length of the space flight periods by using post-labeling methods. To detect DNA damage caused by space radiation, we placed fixed human cervical carcinoma (HeLa) cells in the Russian Mir space station for 40 days and in an American space shuttle for 9 days. After landing, we labeled space-radiation-induced DNA strand breaks by enzymatic incorporation of [3H]-dATP with terminal deoxyribo-nucleotidyl transferase (TdT). We detected DNA damage as many grains on fixed silver emulsion resulting from β-rays emitted from 3H-atoms in the nuclei of the cells placed in the Mir-station (J/Mir mission, STS-89), but detected hardly any in the ground control sample. In the space shuttle samples (S/MM-8), the number of cells having many grains was lower than that in the J/Mir mission samples. These results suggest that DNA damage is caused by space radiation and that it is dependent on the length of the space flight.
1 0 0 0 鼻腔・副鼻腔の音響的および構造的多様性とその音声学的寄与の探究
1 0 0 0 OA 青年期後期における自己受容と他者受容の関連 : 個人志向性・社会志向性を指標として
- 著者
- 上村 有平
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.132-138, 2007-08-10 (Released:2017-07-27)
- 被引用文献数
- 3
本研究の目的は,(1)青年期後期において,自己受容が高く他者受容が低い者と,自己受容が低く他者受容が高い者の特徴を記述すること,(2)自己受容と他者受容がバランスよく共存していることが,より適応的かつ成熟した状態にあることを明らかにすること,(3)自己受容と他者受容の関連を,発達心理学的観点から検討することであった。124名の大学生(平均年齢20.46歳)を対象に,自己・他者受容尺度と個人志向性・社会志向性PN尺度を実施した。自己受容および他者受容得点の高低によって調査対象者を4群に分類し,各群の特徴を検討した。その結果,自己受容が高く他者受容が低い者は,自己実現的特性が高い反面,社会適応的特性が弱いという特徴が見出された。自己受容が低く他者受容が高い者には,自己実現的特性が弱く,過剰適応的傾向が強いという特徴が見られた。また,自己受容と他者受容がともに高い者には,4群の中で最も適応的かつ成熟した特徴が見られ,青年期後期において,自己受容と他者受容がバランスよく共存していることが,より適応的かつ成熟した状態にあることが明らかにされた。