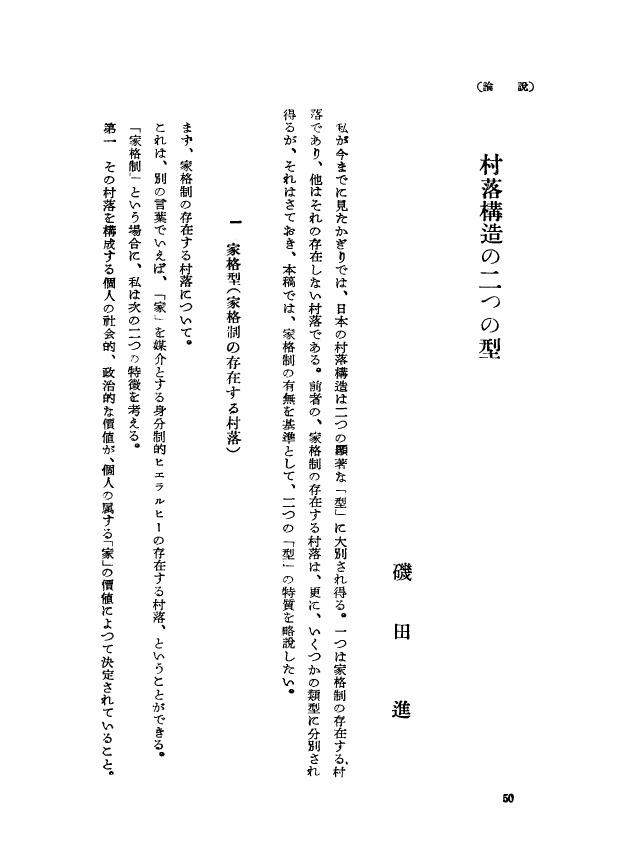1 0 0 0 OA 地下空間の心理的評価法の検討-主として東京メトロのケース-
- 著者
- 吉本 直美 和氣 典二 三田 武 和氣 洋美
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集F2(地下空間研究) (ISSN:21856583)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.1-10, 2012 (Released:2012-06-20)
- 参考文献数
- 7
この研究は地下空間のQOL,つまり快適性という心理的面から環境設計に役立たせる評価法の開発に関するものである.今回は,副都心線を含む東京メトロ8駅を選び,駅構内とそれにつながる通路を歩いてから2種の質問紙に回答を求めた.質問紙(その1)の結果では,快適感・利便性,不安感,視認性・気づきにくさ,まぶしさ・歩行のしにくさの4つの因子が抽出された.また質問紙(その2)の結果では,案内表示の視認性,地下空間の全体的雰囲気,運賃表・路線図の見えやすさの3因子が抽出された.また質問紙(その1)で抽出された快適感・利便性と不安感は,(その2)の全体的雰囲気との相関が高く,視認性・気づきにくさは,案内表示や運賃表や路線図と相関が高いことが示された.
1 0 0 0 OA 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説
- 出版者
- 国立国会図書館
- 巻号頁・発行日
- no.(月刊版. 273-2), 2017-11
1 0 0 0 OA エイズウイルスの分子進化
- 著者
- 五條堀 孝 森山 悦子 伊奈 康夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.4, pp.190-193, 1988-07-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 3
Using nucleotide sequence data of AIDS virus strains isolated from patients at various locations of the world, we examined the phylogenetic relationships among AIDS virus strains. In particular, a phylogenetic tree for AIDS virus strains was constructed using the estimated numbers of nucleotide substitutions. The phylogenetic tree constructed shows that AIDS viruses can be classified into the two major groups; "HIV-1 group" and "HIV-2 group". Evolutionary features of these virus groups were discussed from the viewpoint of molecular epidemiology.
1 0 0 0 OA 貝殻構造について
- 著者
- 岩崎 泰頴 Yasuhide Iwasaki
- 出版者
- 熊本大学
- 雑誌
- 熊本地学会誌 (ISSN:03891631)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.2-9, 1976-07-15
- 著者
- UTA KONNO KEN TAKAI SHINSUKE KAWAGUCCI
- 出版者
- GEOCHEMICAL SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- GEOCHEMICAL JOURNAL (ISSN:00167002)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.4, pp.469-473, 2013-08-20 (Released:2013-11-26)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1 2
An analytical system using continuous-flow isotope ratio mass spectrometry (CF-IRMS) was developed to determine the stable chlorine isotope ratios (δ37Cl) for CH3Cl. By using appropriate devices for sample processing prior to introduction into the spectrometer, the newly developed system successfully reduces sample requirements (>0.6 nmol-CH3Cl) to less than one hundredth of that required by the previous CF-IRMS systems while maintaining comparable precision in the δ37Cl determination (±0.1‰, 1σ). This system is also able to determine carbon isotope ratio for CH3Cl with comparable precision (±0.3‰, 1σ, >0.3 nmol-CH3Cl) to the previous study. δ37ClSMOC and δ13CVPDB values of CH3Cl in commercial tank were determined to be -6.8 ± 0.1‰ and -46.9 ± 0.3‰, respectively.
1 0 0 0 OA スウェーデン刑法における過失レイプ罪について
- 著者
- 川口 浩一
- 出版者
- 明治大学法律研究所
- 雑誌
- 法律論叢 (ISSN:03895947)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.4-5, pp.63-83, 2021-01-29
1 0 0 0 OA 米国の人種統合計画におけるカラー・コンシャスからカラー・ブラインドへの変容
- 著者
- 黒田 友紀
- 出版者
- アメリカ教育学会
- 雑誌
- アメリカ教育学会紀要 (ISSN:13406043)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.15-27, 2016-10-20 (Released:2023-01-30)
The purpose of this paper is to examine the transformation of desegregation/integration plans from "color-conscious" to "color-blind" in the United States.Current issues of equality in education are growing more and more complicated. Progress was made by Brown v. Board of Education in 1954, the Civil Rights Act in 1964, and the Elementary and Secondary Education Act(ESEA)in 1965, expanding equal opportunities in education for people of color, particularly black children. However, trends in population and racial/ethnic components continue to change, and some cities have seen increases in the Hispanic/Latino population in recent years.Furthermore, color-blind ideology has spread in the United States. Because color-blind ideology is seen by some as an ideal, seeming to indicate equal treatment of all people, both right and left use the term. However, we should be careful in our dealings with this concept, as "color- blindness" has potential to hide and exacerbate inequality.With respect to desegregation/integration, white students filed a lawsuit against the affirmative action admissions program in universities, claiming it to be "reverse discrimination" against white people. They requested equal opportunity for all, referring to the equal protection clause of the Fourteenth Amendment. Some Supreme Court decisions concerning desegregation plans have additionally affected and narrowed the scope of desegregation/integration. In elementary and secondary public education, Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No.1; Meredith and McDonald v. Jefferson County Board of Education et al., U.S. 127 S. Ct. 2738(PICS)had a huge impact on desegregation/integration plans in United States public schools, specifically outlawing any desegregation/integration plan giving priority mainly based on race. The U.S. Department of Justice and Department of Education illustrated and suggested guidelines on voluntary use of race—that is, a race-neutral strategy for achieving diversity. For instance, Cambridge’s controlled choice plan had been recognized since the 1980s as one of the better integration plans based on race and other factors; from 2002 on, factors including socio-economic status, race, and gender were used in controlled choice. However, this plan was revised in 2013, as the use of race as a criterion was forbidden.Color-blind or race-neutral educational policy has become widespread in pursuit of equality for all children. However, this strategy could in fact support rights for white people rather than people of color. We should thus examine the real situation of all children, and scrutinize whether inequality and(re)segregation has in fact grown worse than before.
- 著者
- Makoto Murata Saya Yanai Shogo Nitta Yuhei Yamashita Tatsunori Shitara Hiroko Kazama Masanori Ueda Yasuyuki Kobayashi Yoshihisa Namasu Hitoshi Adachi
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Reports (ISSN:24340790)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.6, pp.238-244, 2023-06-09 (Released:2023-06-09)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 1
Background: The incidence of heart failure (HF) is increasing, and the mortality from HF remains high in an aging society. Cardiac rehabilitation (CR) programs (CRP) increase oxygen uptake (V̇O2) and reduce HF rehospitalization and mortality. Therefore, CR is recommended for every HF patient. However, the number of outpatients undergoing CR remains low, with insufficient attendance at CRP sessions. In this study we evaluated the outcomes of 3 weeks of inpatient CRP (3w In-CRP) for HF patients.Methods and Results: This study enrolled 93 HF patients after acute-phase hospitalization between 2019 and 2022. Patients participated in 30 sessions of 3w In-CRP (30 min aerobic exercise twice daily, 5 days/week). Before and after 3w In-CRP, patients underwent a cardiopulmonary exercise test, and cardiovascular (CV) events (mortality, HF rehospitalization, myocardial infarction, and cerebrovascular disease) after discharge were evaluated. After 3w In-CPR, mean (±SD) peak V̇O2increased from 11.8±3.2 to 13.7±4.1 mL/min/kg (116.5±22.1%). During the follow-up period (357±292 days after discharge), 20 patients were rehospitalized for HF, 1 had a stroke, and 8 died for any reasons. Proportional hazard and Kaplan-Meier analyses demonstrated that CV events were reduced among patients with a 6.1% improvement in peak V̇O2than in patients without any improvement in peak V̇O2.Conclusions: 3w In-CRP for HF patients improved peak V̇O2and reduced CV events in HF patients with a 6.1% improvement in peak V̇O2.
1 0 0 0 OA ボディ・アプリシエーションの統合的支援モデルの検討
- 著者
- 生田目 光 沢宮 容子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.131-144, 2023-06-30 (Released:2023-06-14)
- 参考文献数
- 61
本研究ではポジティブボディイメージの一種であるボディ・アプリシエーションを高める心理教育的支援の開発に向けた基礎的な研究を行うこととした。具体的には,ボディ・アプリシエーションを促進すると考えられる感謝,セルフ・コンパッションおよびメディアの影響を扱い,適応的調和食行動や人生満足度への影響を含めて,統合的支援モデルを検討することを目的とした。264名の大学生を対象に構造方程式モデリングをおこなった結果,仮説モデルがおおむね支持された。感謝はセルフ・コンパッションを促進し,セルフ・コンパッションはボディ・アプリシエーションを促進した。また,感謝はボディ・アプリシエーションを直接的にも促進していた。メディアの影響は,ボディ・アプリシエーションを促進しなかったが,適応的調和食行動を促進した。さらに,ボディ・アプリシエーションは適応的調和食行動と人生満足度を促進していた。これらの結果は,ボディ・アプリシエーションの発達と介入ターゲットの理解の促進に貢献しうる。
1 0 0 0 OA 離婚後の父母コペアレンティングと子どもの適応の相互関係 ―交差遅延効果モデルによる検討―
- 著者
- 直原 康光 安藤 智子 菅原 ますみ
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.117-130, 2023-06-30 (Released:2023-06-14)
- 参考文献数
- 66
本研究の目的は,第1に,離婚後の父母コペアレンティングと子どもの適応の相互関係,第2に,子どもの適応のうち「外在化問題行動」,「内在化問題行動」,「向社会的な行動」の相互関係について,交差遅延効果モデルを用いて,経時的な相互関係について検討することであった。離婚して2年未満で2―17歳の子どもと同居する母親500名に,3か月後,6か月後に追跡調査を行った。3時点のデータを用いて,交差遅延効果モデルによる分析を行った結果,「葛藤的なコペアレンティング」は,「外在化問題行動」に正の影響を及ぼし,「外在化問題行動」は「内在化問題行動」に正の影響を及ぼし,「内在化問題行動」は「向社会的な行動」に負の影響を及ぼすことが明らかになった。また,「内在化問題行動」と「向社会的な行動」の間には,互いに負の影響関係が認められた。変数相互間の関係性については,発達カスケードを踏まえて考察を行った。本研究の結果を踏まえた介入や支援への示唆として,離婚後の「葛藤的なコペアレンティング」を抑制することの重要性および子どもの「外在化問題行動」に着目することの重要性が示された。
1 0 0 0 OA 村落構造の二つの型
- 著者
- 磯田 進
- 出版者
- 日本法社会学会
- 雑誌
- 法社会学 (ISSN:04376161)
- 巻号頁・発行日
- vol.1951, no.1, pp.50-64, 1951 (Released:2009-04-03)
- 著者
- 鈴木 正哉 前田 雅喜 犬飼 恵一
- 出版者
- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
- 雑誌
- Synthesiology (ISSN:18826229)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.154-164, 2016 (Released:2016-11-03)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 8 2
温室効果ガス削減が求められる状況の中、優れた省エネシステムに利用可能な吸着剤として、水蒸気吸着性能に優れかつ低温熱源を用いて再生が可能な無機多孔質物質ハスクレイを開発した。この論文では、粘土の研究と天然に存在するナノ物質の研究を経て、ハスクレイの合成に至った経緯、および省エネ用吸着剤として広く利用されるために必要な事項を示す。
- 著者
- 梁瀬 和男
- 出版者
- 日本広告学会
- 雑誌
- 広告科学 (ISSN:13436597)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, pp.1, 2017 (Released:2017-07-24)
平成24 年10 月25 日の知財高裁判決「テレビCM 原版事件」はCM 業界の四半世紀にわたる懸案事項「テレビCM の著作権問題」に明確な結論を出した。その結果、一般的に、広告作品の著作権者が「グラフィック制作物の場合は制作者又は制作会社」、「テレビCM の場合は広告主」となり、広告関係者はこの異常な「ねじれ現象」に直面することになった。この機会に、広告作品と著作権の関係を概観し、この知財高裁の判決を分析して、「ねじれ現象」解決への提言をしたい。
1 0 0 0 鯨類におけるウイルス検出と免疫遺伝子との相互関係
本研究では、鯨類の特に座礁集団および個体に着目し、座礁の原因究明の一つの手段として、ウィルス感染の有無とその動向のモニタリング、および検出されたウィルスの系統解析をおこない、宿主-ウィルスの共進化関係の有無と、免疫遺伝子MHCとの相互関係について探ることを目的としてきた。本年度も引き続き日本各地において座礁・混獲された鯨類より試料の収集をおこない、10鯨種・47個体の試料を得た。これは北海道ストランディングネットワーク・北海道大学・国立科学博物館・大村湾スナメリネットワーク(仮称)・宮崎くじら研究会との連携によるものであり、本プロジェクトもこれらネットワークの構築・運営の一部に携わっている。これまでに蓄積された試料について、DNA診断によるウィルス検出をおこなったところ、4鯨種・4個体よりヘルペスウィルスが検出された。本年度は特にこれらの系統解析と病理学的所見との関連性について解析を進めた。系統解析の結果、カズハゴンドウの鼻腔粘膜およびオキゴンドウの肺より検出されたウィルスは、それぞれ新たな系統のアルファヘルペスで、オウギハクジラおよびマッコウクジラのリンパ節からのものは、同じく新たな系統のガンマヘルペスと同定された。鯨類から検出されたアルファヘルペスウィルスは単一のクレードを形成し、種1分類群特異的な進化が示唆された。一方で、ガンマヘルペスウイルスの鯨類クレードは大きく2つに分かれており、これらウィルスの起源が複数あることを示した。またアルファヘルペスウィルスは主に呼吸器系統から、先行研究におけるガンマヘルペスウイルスは主に生殖器から、そして本研究によるガンマヘルペスウィルスはリンパ節から検出され、これらの系統のウィルスがそれぞれ異なる組織をターゲットとし、潜伏感染をおこなっていることが示唆された.なおこれらの結果は学術誌に投稿中である。
1 0 0 0 IR 自由と承認 : シモーヌ・ド・ボーヴォワールの倫理思想
1 0 0 0 OA 時間性と女たち
- 著者
- 棚沢 直子 タナサワ ナオコ Naoko Tanasawa
- 出版者
- 東洋大学経済研究会
- 雑誌
- 経済論集 = The economic review of Toyo University (ISSN:03850358)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.167-178, 2005-12
1 0 0 0 OA 日米独の動物園経営組織に関する研究
- 著者
- 佐渡友 陽一
- 出版者
- 帝京科学大学
- 雑誌
- 研究活動スタート支援
- 巻号頁・発行日
- 2015-08-28
日本の動物園経営は、意思決定と歳入構造に課題があるとされる。米国およびドイツ語圏の動物園経営についてヒアリング調査を実施した結果、両地域とも直営から非営利法人への切り替えが行われており、それに伴って意思決定と歳入構造の両面で改善が図られていた。この際、国外での保全研究活動に行政補助を使えないという制約が両地域に見られたことは、日本においてこの種の取り組みが進展しない一因を明らかにしたものと言える。今後の日本の動物園経営の改善のためには、本格的なファンドレイジングができる構造改革と、動物の幸せに敏感な人々を味方にする動物福祉の充実が重要と考えられる。
1 0 0 0 OA 格子型碁盤と特殊な碁盤での有効着手の相違性の解析
- 著者
- 佐藤 真史 穴田 浩一 堤 正義
- 雑誌
- 第78回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, no.1, pp.33-34, 2016-03-10
囲碁は、通常用いられる正方格子型の碁盤以外にも様々な形の碁盤で行うことができる。一方で、既存の研究のほとんどは正方格子型の碁盤上での着手の評価方法についてのものである。特に各交点の持つ隣接点の数が異なるような碁盤の場合、通常の囲碁で良いとされる着手が必ずしも有効とは言えない。B-Wグラフモデルおよび戦術写像は、碁盤の形状によらず対局を表現、解析できる囲碁の数理モデルである。本発表では、戦術写像を用いた機械学習法を幾つかの碁盤上で行い、共通する戦術、異なる戦術について解析する。
1 0 0 0 OA アクアマッサージ中の筋組織血液動態の変化
- 著者
- 須藤 明治 角田 直也 渡辺 剛
- 出版者
- 国士舘大学体育学部附属体育研究所
- 雑誌
- 国士舘大学体育研究所報 (ISSN:03892247)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, 2007