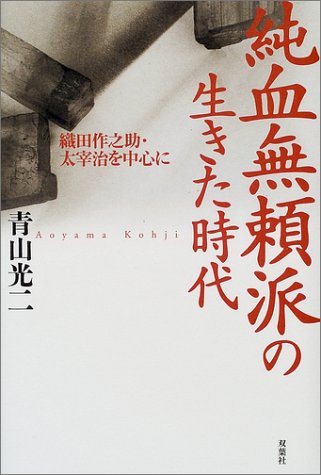1 0 0 0 OA 学級経営の意味と課題
1 0 0 0 OA 対人不安における自己呈示欲求について : 賞賛獲得欲求と拒否回避欲求との比較から
- 著者
- 佐々木 淳 菅原 健介 丹野 義彦
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- 性格心理学研究 (ISSN:13453629)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.142-143, 2001-03-30 (Released:2017-07-24)
- 被引用文献数
- 3 2
1 0 0 0 OA 軽度認知障害者を対象とした認知症と成人発達障害の認知機能検査による鑑別
認知症疾患診療は、認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)の段階で診断し、治療開始することが望まれている。しかし近年MCIの中に児童青年期までに診断されなかった発達障害者に、加齢性の認知低下が加わった状態の人が混在している可能性が指摘されている。本研究では、神経画像検査やCSF中のADバイオマーカー検査、発達障害評価を実施し、AD、DLB、ASD、ADHD等の原因疾患同定のための鑑別診断を行い、発達障害MCIと認知症MCIの割合を計算する。また認知機能や巧緻運動評価を実施し、その結果を2群間で比較した上で有意差が認められた検査項目に対し判別分析を行い、判別式を作成することで臨床に役立てる。
1 0 0 0 OA 原野商法関与者の責任
- 著者
- 松原 哲
- 出版者
- 高岡法科大学法学会
- 雑誌
- 高岡法学 (ISSN:09159339)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.43-71, 1996-12-17 (Released:2019-05-09)
1 0 0 0 OA COVID–19の神経症状と予後
- 著者
- 川本 未知
- 出版者
- 日本神経治療学会
- 雑誌
- 神経治療学 (ISSN:09168443)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.296, 2022 (Released:2022-11-22)
1 0 0 0 OA DDS技術に立脚したワクチン開発の現状
- 著者
- 河合 惇志 平井 敏郎 吉岡 靖雄
- 出版者
- 日本DDS学会
- 雑誌
- Drug Delivery System (ISSN:09135006)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.5, pp.402-411, 2022-11-25 (Released:2023-02-25)
- 参考文献数
- 72
COVID-19に対してかつてない速度でワクチンが普及した背景には、DDS技術の発展が必要不可欠であった。特に、mRNAワクチンにおける脂質ナノ粒子(LNP)の開発は、まさにDDS技術の結集といえよう。一方で、mRNAワクチンを含め、現状のさまざまなワクチンは多くの課題を有しており、より効果的かつ安全なワクチン開発に資する基盤技術の確立が世界的に待望されている。本稿では、ワクチンモダリティの1つである組換えタンパク質ワクチンに焦点を絞り、抗原改変技術からアジュバントの改良に至るまで、ワクチン開発基盤技術の最新知見について紹介する。
1 0 0 0 OA プレ・コード期のハリウッドのしたたかな女たち
- 著者
- 斎藤 英治
- 出版者
- 明治大学教養論集刊行会
- 雑誌
- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)
- 巻号頁・発行日
- vol.418, pp.39-59, 2007-03-31
1 0 0 0 OA アメリカ次世代科学スタンダードにおける幼稚園の教育内容
- 著者
- 村津 啓太
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会研究会研究報告 (ISSN:18824684)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.93-96, 2018 (Released:2018-04-07)
- 参考文献数
- 5
近年の幼児教育では,科学教育の充実が課題として取り上げられている.その基礎的な資料を得るために,本研究では,アメリカの次世代科学スタンダードにおける幼稚園の教育内容を検討した.検討の結果,幼稚園における教育内容は,物理科学における「運動と静止:力と相互作用」と「エネルギー」,生命科学における「粒子から有機体へ:構造とプロセス」,地球・宇宙科学における「地球のシステム」と「地球と人類の活動」であることが分かった.また,それぞれの教育内容は,学習者によるスタンダードの到達を意味する「期待されるパフォーマンス」と,それを構成する 3つの要素,すなわち,(1)学習者が深化・洗練させていくべき最小限のアイデアとしての「領域のコア概念」,(2)科学者が自然界に関わる理論を構築する際に行う実践としての「科学の実践」,(3)科学の領域すべてにおいて適用可能な概念としての「領域横断概念」から構成されていることが明らかになった.
1 0 0 0 OA 織田政権における「惣構」の特徴と展開 : 織田信長とその家臣に関連する事例を中心に
- 著者
- 田中 詢弥
- 出版者
- 関西大学史学・地理学会
- 雑誌
- 史泉 (ISSN:03869407)
- 巻号頁・発行日
- vol.135, pp.A1-A21, 2022-01-31
1 0 0 0 OA 聖杯への径 -ウィーン新旧楽壇抗争一八九五年-
- 著者
- 須永 恆雄
- 出版者
- 明治大学教養論集刊行会
- 雑誌
- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)
- 巻号頁・発行日
- vol.568, pp.27-72, 2022-12-31
- 著者
- 酒井 雄大 井森 恵太郎 松本 直樹 松村 恵理子 千田 二郎
- 出版者
- 公益社団法人 自動車技術会
- 雑誌
- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.6, pp.1103-1107, 2018 (Released:2018-11-26)
- 参考文献数
- 6
筒内直接噴射式ガソリンエンジンはポート噴射式と比較し高効率・低エミッションである一方,非常に緻密な混合気分布の制御が求められる.本研究においては,燃料を加熱する手法による混合気分布の制御を目的とする.本報においては,急速圧縮膨張機関を用いて加熱噴霧が燃焼特性に及ぼす影響を把握する.
1 0 0 0 OA ウィリアム・オラフ・ステープルドン著「現代の魔術師」 -翻訳と解説-
- 著者
- 浜口 稔
- 出版者
- 明治大学教養論集刊行会
- 雑誌
- 明治大学教養論集 (ISSN:03896005)
- 巻号頁・発行日
- vol.568, pp.109-125, 2022-12-31
- 著者
- 田崎 晴明
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.6, pp.466-467, 1999-06-05 (Released:2019-05-17)
- 著者
- Kotaro FUJII Masatomo YASHIMA
- 出版者
- The Ceramic Society of Japan
- 雑誌
- Journal of the Ceramic Society of Japan (ISSN:18820743)
- 巻号頁・発行日
- vol.126, no.10, pp.852-859, 2018-10-01 (Released:2018-10-01)
- 参考文献数
- 64
- 被引用文献数
- 13 33
This article provides the first critical review on the discovery and development of BaNdInO4. Exploring a new structure family of ionic conductors is an important task to develop ceramic ionic conductors. Since some A2BO4 compositions exhibit high oxide-ion conductivities, we investigated ABCO4 compositions to explore new oxide-ion conductors with A/B/C cation-ordered structures. Here A, B and C are cations [ionic radii: r(A) ≥ r(B) ≥ r(C)]. In 2014, we discovered a new material BaNdInO4 which belongs to a new structure family of perovskite-related structures. This BaNdInO4-type structure (monoclinic, P21/c) consists of alternative stacking of the A rare earth oxide unit and perovskite unit with a− b− c− tilt system. We also discovered new materials BaRInO4 (R = Sm, Y, Ho, Er, Yb) having the BaNdInO4-type structure, and report their lattice parameters and anisotropic chemical expansion. Electrical conductivity of BaNdInO4 was higher than those of BaRInO4 (R = Sm, Y, Er). Oxide-ion conduction was dominant for BaNdInO4 in the P(O2) region from 3.8 × 10−22 to 5.5 × 10−9 atm at 858°C. Oxide-ion conductivities of Ba1.1Nd0.9InO3.95, BaSr0.1Nd0.9InO3.95 and BaCa0.2Nd0.8InO3.9 were higher than that of BaNdInO4. Structure analyses of Ba1.1Nd0.9InO3.95 and BaSr0.1Nd0.9InO3.95 indicated that the excess Ba and doped Sr cations were partially substituted for Nd cation and that there existed oxygen vacancies, leading to the increase of the carrier concentration and higher oxide-ion conductivity. Following the discovery of BaNdInO4, BaRScO4 (R = Nd, Eu, Y, Yb) and SrYbInO4 were reported as new ABCO4 materials. BaYScO4 and BaYbScO4 have the BaNdInO4-type structure. BaNdScO4 and BaEuScO4 crystallize into the space group Cmcm, which has a higher symmetry than P21/c for BaNdInO4. SrYbInO4 is the first example of pure oxide-ion conductors with CaFe2O4-type structure. Further investigations of ABCO4 compositions and BaNdInO4 related materials will lead to development of materials science and solid state ionics.
- 著者
- Hisashi KATO Fumitada IGUCHI Hiroo YUGAMI
- 出版者
- The Electrochemical Society of Japan
- 雑誌
- Electrochemistry (ISSN:13443542)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.10, pp.845-850, 2014-10-05 (Released:2014-10-05)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 4 6
Sr2+, Al3+-doped LaScO3 perovskite-type oxide (La0.675Sr0.325Sc0.99Al0.01O3; LSSA), which exhibits high conductivity of both oxide-ion and proton, is expected to become an electrolyte material for high-temperature solid oxide fuel cells (SOFCs). Considering the potential of this material to serve as a solid electrolyte, its chemical compatibility with some of the typical fuel electrodes commonly used in SOFCs was investigated. Severe elemental diffusion was found at the sintering temperature of 1673 K between doped LaScO3 and the anode material, mainly due to strontium migration. To control the elemental diffusion, we lowered the sintering temperature to 1523 K. In the case of Ni-SDC, we found no elemental diffusion at the electrolyte/electrode interface. Moreover, we tried to fabricate SOFC consisting of LSSA electrolyte and some electrodes, and we performed power generation tests above 1073 K. At 1273 K, the maximum power density was 158 mW cm−2 as humidified hydrogen fuel. The electrolyte resistance was high due to the high thickness of 0.6–0.9 mm. Higher power density would seem possible if a thinner electrolyte is applied. Consequently, we found that LSSA is applicable as an electrolyte material for SOFCs.
1 0 0 0 OA 短波放送のSSB化
- 著者
- 大原 光雄
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン学会技術報告 (ISSN:03864227)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.46, pp.41-46, 1983 (Released:2017-10-02)
1 0 0 0 OA 住宅金融債券管理機構による住友銀行の提訴におけるモラルと法
- 著者
- 小阪 康治
- 出版者
- 日本経営倫理学会
- 雑誌
- 日本経営倫理学会誌 (ISSN:13436627)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.173-182, 2000-03-31 (Released:2017-07-28)
The suit filed by the Housing Loan Administration Corp. on June 30, 1998 against Sumitomo Bank in connection with Sumitomo 's alleged responsibility for the "jusen" housing loan fiasco has finally been settled by reconciliation on Feb.1, 1999. In court, Sumitomo's responsibility for huge bad loans by their inappropriate behavior was questioned. Though Sumitomo asserted that they had no legal responsibility, the Housing Loan Administration Corp. was consistently claiming that the banks which will receive public funds for survival should take the responsibility in such a case from the moral viewpoint. As a result, reconciliation that Sumitomo will pay 3,000 million yens has finally been obtained. This case appears to be one of the most important examples that pursuit of morality could become one solution even if the legal responsibility is not so clear and to be a good model showing the relation of companies and morality.
1 0 0 0 OA 熱帯マメ科早生樹植林地における亜酸化窒素排出メカニズムの解明と抑制プロセスの探索
近年、湿潤熱帯アジアでは増大するパルプ需要に答えるため大規模な植林事業が展開されており、こうした地域ではアカシア・マンギウム(以下アカシア)を代表とするマメ科早生樹が広く植栽される。しかし、アカシアは窒素固定樹種であるため成長が早い一方、土壌-植生系内を循環する窒素量が増大することで、亜酸化窒素(N2O)を通常の森林よりも多く排出することを明らかにしてきた。本課題では N2O 放出緩和オプションの提示を目的として、インドネシア南スマトラ州のる大規模産業植林地帯において、以下の研究を実施した。1)リン施用がアカシア林地からの N2O 放出に及ぼす影響、2)リン施用を導入したアカシア植林施業の温暖化緩和効果の評価。 その結果、リン施用は植物根のない状態ではN2O 排出を促進するが、アカシア根による養分吸収がある条件下では植物の窒素吸収を促進することで土壌からの亜酸化窒素排出を抑制する効果を持つことを明らかにした。またアカシア新植時からリン施用を行えば無施用区に比べ、土壌炭素の分解が促進される一方で、 N2O の発生抑制ならびに植栽木のバイオマス生産増によって、全体としては温暖化緩和効果が強化されることを明らかにした。
- 著者
- 吉田 達矢
- 出版者
- 名古屋学院大学総合研究所
- 雑誌
- 名古屋学院大学論集 言語・文化篇 = THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; LANGUAGE and CULTURE (ISSN:1344364X)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.81-99, 2023-03-31
本稿では,オスマン帝国史において「改革の時代」とされる19世紀前半における地方軍政官の人事に着目し,オスマン帝国中央政府の地方社会に対する統治方針の一端について考察した。考察対象の場所は現在のギリシア北部に存在していたヤンヤ県とし,考察対象の時期は18世紀末よりヤンヤ県を中心に中央政府から半ば自立した勢力として広大な領域を支配したアルバニア人豪族テペデレンリ・アリー・パシャの討伐が始まった1820年から,ヤンヤ県にタンズィマート改革が導入され,ヤンヤ州が新たに設立された1846年前後までとした。当該時期に就任したヤンヤ県軍政官各自の履歴,選出・離任理由などについて考察した結果,ギリシア独立戦争やアルバニア人豪族の統御などの問題に対処するため,1830年代前半まではアルバニア人豪族の任用,有力政治家の親子2代にわたる長期の統治がみられ,「第二のテペデレンリ・アリー・パシャ」が出現する可能性があったことなどを指摘した。