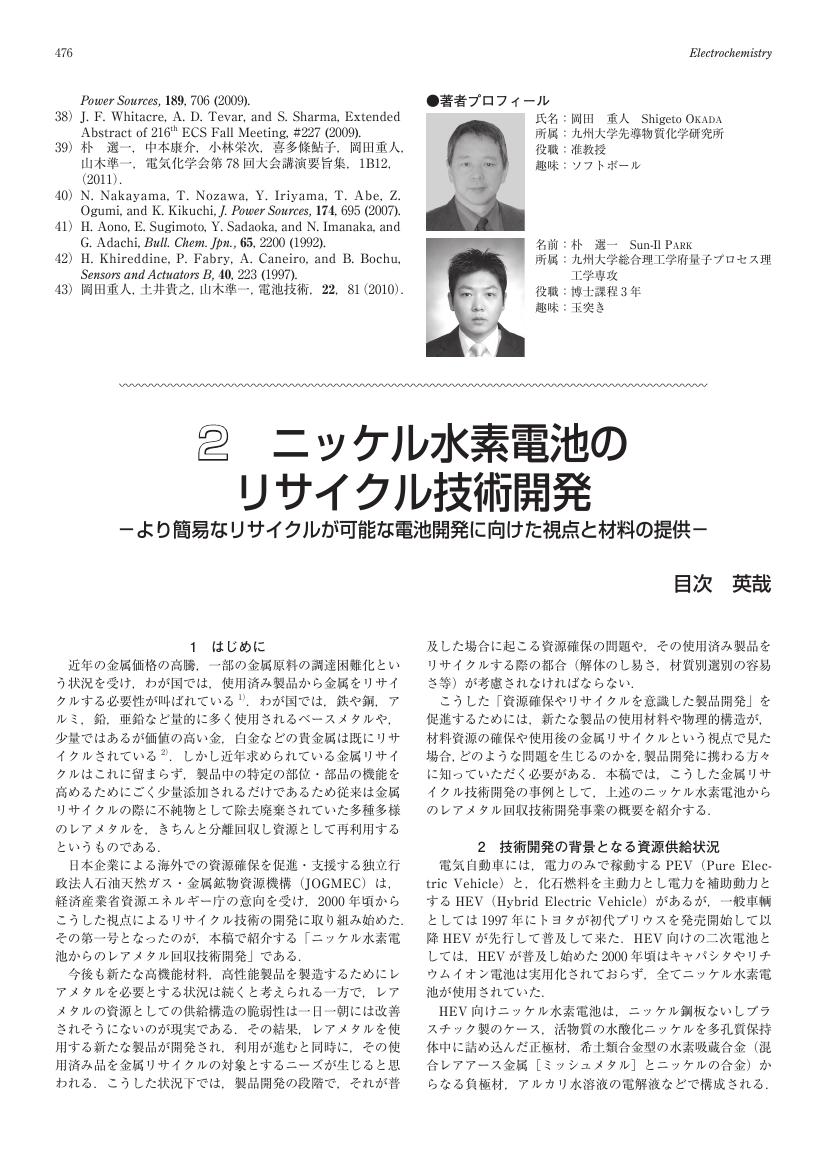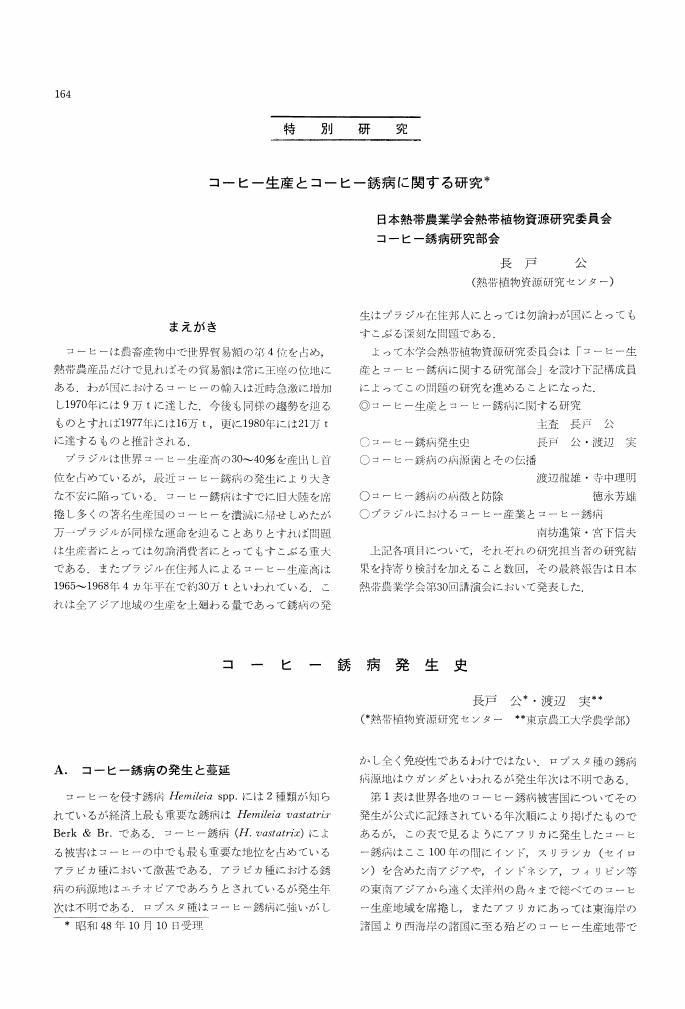- 著者
- 大倉 韻 守 如子 羽渕 一代
- 出版者
- 関西大学社会学部
- 雑誌
- 関西大学社会学部紀要 (ISSN:02876817)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.11-32, 2019-03-31
本稿は、2011年に行われた第7回青少年の性行動全国調査(JASE)のデータに基づき、日本の若者の性行動の現状を明らかにすることを目的としている。この調査は、7640人から回答を得ており、若者が性的関心をもたなくなってきたのはなぜかといった問題に焦点をあててきた。本稿は、この調査の項目のうちから、「あなたがいま、性について知りたいことは何ですか」という質問に着目して分析を行った。分析から得られた第一の結果は、性情報のニーズは、性別と学校段階によって、いくつかのタイプに分けることができるという点である。第二の結果は、性情報のニーズは、「性行為と妊娠」「性的な悩み」「性病」「恋愛」という4つのカテゴリーに収斂していくプロセスとみることができるという点である。特に、日本の若者にとって、「セックス(性交)」は、恋愛としてよりもむしろ妊娠に関わるものとして意識されているということ、その一方で性交によって生じる別種のリスクである「性感染症」や「エイズ」のリスクは性交とは独立したものとして意識されていることが明らかになった。また、第三に、性的関心が性情報ニーズと正の相関がみられたことから、性的関心が性情報ニーズに強い影響を与えていることが明らかになった。
- 著者
- 髙田 梓
- 出版者
- 日本独文学会
- 雑誌
- ドイツ文学 (ISSN:24331511)
- 巻号頁・発行日
- vol.162, pp.214-228, 2021 (Released:2022-03-25)
Christian Krachts Reisebericht über Asien Der gelbe Bleistift entstand aus seinen Reisekolumnen, die von 1999 bis 2000 in der Welt am Sonntag erschienen. In insgesamt 14 Fortsetzungen berichtete er über seine Aufenthalte in Thailand, Kambodscha, Laos, Burma [sic] , Singapur, Vietnam, Japan und auf kleinen Inseln im Südpazifik. Das Buch Der gelbe Bleistift besteht aus eben diesen Kolumnen, erweitert um seine bisherigen Reiseberichte über Aserbaidschan, Pakistan, Sri Lanka, Hong Kong und Indonesien. Auffallend ist, dass Kracht dabei viele Filmtitel in seinen Texten verwendet und damit zeigt, wie oft Filme im 20. Jahrhundert Asien thematisieren und orientalistisch darstellen. Angesichts dieses angewandten Orientalismus erzählt Krachts Reisebericht nun satirisch, wie anders das reale Asien als das in den Filmen ist, und wie diese Filme nun für den Tourismus kommerzialisiert werden. Der gelbe Bleistift zeigt einerseits das hochkapitalistisch kommerzialisierte globale Zeitalter der 1990er Jahre, aber andererseits kritisiert er auch den immer noch in Asien zu erkennenden Eurozentrismus. Wie Kracht sich früher als Journalist in seinen Auslandsreportagen oft mit sozialen Themen auseinandersetzte, fokussieren sich auch seine Reiseberichte in Der gelbe Bleistift auf soziale Probleme in Asien. Er richtet den Blick besonders auf ein mit der globalen Kommerzialisierung entstandenes wirtschaftliches Gefälle, das man mit dem ehemaligen Kolonialismus vergleichen kann. Diese ernsten und bedeutsamen Themen werden jedoch durch Krachts snobistischen Reisestil camoufliert, welcher von Luxushotels und seinem Widerwillen, sich dem asiatischen Lebensstil anzupassen, charakterisiert wird. Dass Kracht ausgerechnet „gelb“ als Farbe des Bleistiftes im Titel verwendet, kann zwar als provokativ, mit dem Rassismus assoziiert gesehen werden, noch vielmehr jedoch als Krachts ironischer Ansatz, den Rassismus gegenüber Asiaten anzuprangern. Diese ironische Methode ist auch in seinen Romanen zu sehen. In seinen beiden Romanen, Imperium und Die Toten, deren Schauplätze in Asien und zwar in einer deutschen Kolonie von Neuginea und in Japan in den 1930er Jahren liegen, ist hervorzuheben, dass der Autor Asien sehr orientalistisch darstellt. So beschreibt das erste Kapitel in Die Toten die Aufnahme einer Filmszene, in der ein Offizier Harakiri begeht, das Ritual des Selbstmordes japanischer Krieger, und Imperium betont die ehemaligen kolonialen Beziehungen zwischen Europa und Asien. Diese orientalistischen Darstellungsmuster erscheinen auch als ironische Karikatur, mit der Kracht den Orientalismus kritisiert. (View PDF for the rest of the abstract.)
- 著者
- Golusu Babu RAO Santhanakrishnan BABU Goldin QUADROS
- 出版者
- The Ornithological Society of Japan
- 雑誌
- ORNITHOLOGICAL SCIENCE (ISSN:13470558)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.199-213, 2022 (Released:2022-08-13)
- 参考文献数
- 75
- 被引用文献数
- 7
The Indian coast and its adjacent wetlands host large congregations of shorebirds, including winter and passage migrants of high conservation priority, along the Central Asian Flyway. Identifying crucial wintering and stopover sites and seasons is an important step toward conserving shorebirds and their habitats along the Indian coast. We assessed spatial and temporal patterns of shorebird composition from January 2015 to December 2016 at seven estuaries along Maharashtra's Sindhudurg district, which is located on India's west coast, a coastal zone of international importance for shorebirds. Three potential shorebird habitats –mangroves, mudflats, and sandy beaches – were selected at each of the estuaries chosen for the study. We established three vantage points, one each in the mangrove, mudflat, and sandy beach areas, to count birds during low tide. The total count method was followed to count birds, and occasional photograph-based counts were also made when flock size was big or the flocks kept changing. We recorded 31 species of migratory shorebirds, of which 68% wintered and 32% used the Sindhudurg coast as migratory stopover site. We found significantly high richness and abundance of shorebirds during winter and in the mudflats. nMDS was used to determine species composition of shorebird across habitats and months and revealed distinct patterns of composition in five unique phases: arrival, wintering, early departure, departure, and breeding. Our results revealed that the species composition of shorebirds is not homogenous across sites and months, and is largely driven by the habitat heterogeneity of estuaries, seasonality, and anthropogenic disturbances. These results provide baseline information on shorebirds along a stretch of India's west coast and highlight the importance of mudflats and non-protected coastal wetlands for shorebirds.
- 著者
- 渕野 昌
- 出版者
- 京都大学数理解析研究所
- 雑誌
- 数理解析研究所講究録 (ISSN:18802818)
- 巻号頁・発行日
- vol.1787, pp.183-189, 2012-04
- 著者
- 藤井 弘章
- 出版者
- 近畿大学大学院文芸学研究科
- 雑誌
- 渾沌:近畿大学大学院文芸学研究科紀要 = Chaos (ISSN:21877114)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.23-48, 2013-03-01
1 0 0 0 OA セルロースナノファイバーの製造概論
- 著者
- 阿部 賢太郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本接着学会
- 雑誌
- 日本接着学会誌 (ISSN:09164812)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.8, pp.296-300, 2019-08-01 (Released:2019-08-22)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1
It is well-known that nanofibers are produced in nature, for example, collagen fibrils in tendons andligaments and silk fibroin. Among the variety of natural nanofibers, cellulose microfibrils, which are the majorconstituent of plant cell walls, are the most abundant natural nanofiber on earth. The cellulose microfibrilshave great potential for use as reinforcement in nanocomposites and have attracted a great deal of interestrecently. Many researchers are now tackling the isolation of cellulose nanofibers from plant sources along withtheir efforts to utilize the nano elements. This report reviews the preparation of cellulose nanofibers fromvarious plant sources.Key words : Cellulose
- 著者
- 目次 英哉
- 出版者
- 公益社団法人 電気化学会
- 雑誌
- Electrochemistry (ISSN:13443542)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.6, pp.476-483, 2011-06-05 (Released:2012-03-30)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1 1
- 著者
- 大友 章裕 飯野 亮太
- 雑誌
- 第60回日本生物物理学会年会
- 巻号頁・発行日
- 2022-09-02
1 0 0 0 OA オリーブオイルの和食への活用 −美味しさと減塩効果を期待して−
- 著者
- 井野 睦美 大富 あき子
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 2021年度大会(一社)日本調理科学会
- 巻号頁・発行日
- pp.99, 2021 (Released:2021-09-07)
【目的】近年オリーブオイルに様々な食材を漬け込んだ商品が見られる。食材を漬けることで変化するオイルの風味を活かして、塩分量が多いと言われる和食へ利用した際の美味しさの増強や減塩効果について検討した。【方法】日本デルモンテ株式会社より提供のエキストラバージンオリーブオイルを使用し、11種の食材を1週間浸漬した。そのうち特徴のある食材3種(小エビ・かつお節・わさび)に厳選し、①常温で豆腐にかけて②加温してフランスパンに含ませて、標準オイルと比較して特徴を評価した。またこれらを和食に使用し、オイル未使用のコントロール料理と比較検討を行った。小エビオイルは味噌汁に加え、同じ塩分濃度の味噌汁と比較した。かつお節オイルは、醤油とオイルの混合液と、醤油のみをほうれん草のお浸しで比較した。わさびオイルは、醤油とオイル1:1混合液と、醤油のみを鯛の刺身で比較した。【結果・考察】小エビオイルは加温により辛みと生臭い香りが抑えられた。かつお節オイルは常温・加温両方で評価が高く、かつお節のうま味や風味が強く感じられた。わさびオイルは嗜好の個人差が大きいが、加温するとわさびの風味が減少することがわかった。小エビオイル入り味噌汁は、コントロールに比べ有意にマイルドであった。かつお節オイルのほうれん草のお浸しはコントロールに比べ有意にコクが強かった。わさびオイルを用いた刺身はコントロールに比べコク、うま味、マイルドさ、美味しさが有意に高かった。この結果から、食材を漬けたオリーブオイルを各種和食料理に使用することで美味しさが増していた。またほうれん草のお浸しと刺身は少ない醤油量で満足が高く、減塩効果も期待できると示唆された。
1 0 0 0 OA NHK「きょうの料理」にみる1990年代以降の汁物の献立の変遷について
- 著者
- 伊藤 知子 安藤 真美
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 2022年度大会(一社)日本調理科学会
- 巻号頁・発行日
- pp.136, 2022 (Released:2022-09-02)
【目的】汁物は様々な具材を使うことができ、献立の栄養バランスを取る上で便利な調整役を果たすことのできる料理である。しかし、一方で塩分の摂取量を上げる原因となりやすいことから敬遠されることもある。日本人の食事摂取基準(厚生労働省)において、1日の塩分摂取量(食塩摂取量)の基準は、改訂ごとに引き下げられ、2020年版では男性7.5g未満、女性6.5g未満とされている。本研究は、日常の食生活記録ではないものの「時代の半歩先に出る」というコンセプトで作られ食の変遷を示す資料であると考えられるNHK「きょうの料理」に掲載されたレシピから、汁物に含まれる塩分量を中心に検証を行い、献立の変遷について明らかにすることを目的とした。【方法】1990~2015年に発刊されたNHK「きょうの料理」テキストを5年ごとに調査した。汁物の献立について、だし汁の量(牛乳、トマトジュース等の液体を含む)、具材重量、塩分量を算出し、その変遷について分析を行った。【結果・考察】汁物の掲載献立数は1990年:76、1995年:75であったが、2000年は114と増加しており、以降、2005年:95、2010年:81、2015年68と減少していた。塩分量は1食で2.0gを超えるものも多かったが次第に減少しつつあった。だし汁の量は1990年では1人分200gを超えるものが多かったが、次第に減少傾向にあった。年々、減塩の必要性が重要視されるようになったこととの関連が推察された。また、1990年は「建長汁」、「国清汁」など郷土料理としての汁物の掲載がみられたが、近年になるほど具材等がわかりやすい料理名称が増加した。
1 0 0 0 OA 『それから』の百合 ― Dora Thorne、『金色夜叉』との関連において
- 著者
- 増田 裕美子
- 出版者
- 日本比較文学会
- 雑誌
- 比較文学 (ISSN:04408039)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, pp.94-107, 2014-03-31 (Released:2018-05-26)
Sorekara (And Then) by Natsume So-seki was published in the Asahi Shimbun in 1909. In this novel lilies appear as a symbol of the heroine, Michiyo. With the exception of several waka poems compiled in the 8th century Man’yōshū, however, lilies are not seen in traditional Japanese literature. In Meiji Era lilies reappeared in Ozaki Ko-yo-’s Konjiki yasha (The Golden Demon), which was written during 1897-1903. In the dream of her lover, the novel’s heroine, Miya, drowns and is transformed into a lily (yuri). Though the main original source, Weaker Than a Woman by Bertha M. Clay, does not include important descriptions of lilies, Dora Thorne, another novel by the same author, contains many meaningful scenes with lilies. In this paper, I discuss how Ko-yo- changed the meaning of lilies by drawing on an analysis of these scenes described above. While three kinds of lilies appear in Dora Thorne―lilies (yuri), lilies of the valley (suzuran), and water lilies (suiren)―Ko-yo-, who did not know the difference between them, was under the misconception that western lilies grew in the water or by the waterside. Because of this misunderstanding he made lilies symbols of rejected women like Ophelia in Hamlet, who drowns in the river. So-seki utilized this symbolism in Sorekara when the protagonist Daisuke puts lilies into the water of the vase. That act symbolizes Michiyo’s drowning, that is to say, the fact that he rejected Michiyo in the past.
1 0 0 0 街の放射線 : 歌集
1 0 0 0 音楽家・音楽学者エタ・ハーリヒ=シュナイダーの再評価に向けて
ドイツの音楽家・音楽学者エタ・ハーリヒ=シュナイダー(1894~1986)は、日本における職業的で本格的なチェンバロ演奏の祖となった古楽演奏のパイオニア、外国人による日本伝統音楽研究の先駆者、シェイクスピアの全ソネットや日本の昔話を翻訳した翻訳家、著名なスパイ、リヒャルト・ゾルゲと親密に交際し、東京裁判の傍聴記録を残した「時代の証言者」など、音楽家や音楽研究者の枠を超えたさまざまな側面を持った人物であるが、その業績の全体像はいまだに明らかになっていない。当研究は彼女の再評価を目的として、彼女の業績と経験の総体を書誌を作成してまとめ、現代における彼女の存在の重要性を社会に問うものである。
1 0 0 0 OA エピソード記憶と自己 ――自己関連付け効果をめぐる問題――
- 著者
- 堀内 孝
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.43-58, 2008 (Released:2019-04-12)
1 0 0 0 OA コーヒー銹病発生史
- 著者
- 長戸 公 渡辺 実
- 出版者
- 日本熱帯農業学会
- 雑誌
- 熱帯農業 (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.164a-168, 1974-03-10 (Released:2010-03-19)
1 0 0 0 OA 移動に対する負担感および管理者のサポートと訪問看護師の就業継続意向との関連: 横断研究
- 著者
- 永見 悠加里 藤﨑 万裕 野口 麻衣子 山本 則子
- 出版者
- 公益社団法人 日本看護科学学会
- 雑誌
- 日本看護科学会誌 (ISSN:02875330)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.122-131, 2021 (Released:2021-08-12)
- 参考文献数
- 38
目的:移動に対する負担感および管理者のサポートと訪問看護師の就業継続意向の関連を明らかにする.方法:訪問看護管理者と訪問看護師に対し自記式質問紙調査を行い,就業継続意向を従属変数とするマルチレベル二項ロジスティック回帰分析を行った.結果:管理者38名,看護師221名から有効回答を得た.就業継続意向がある者は151名(68.3%)であった.負担感は,非効率な訪問スケジュール(OR = 0.41, 95%CI: 0.22~0.78),管理者のサポートは,移動しやすい道のりの共有(OR = 2.49, 95%CI: 1.20~5.17),訪問間隔の確保(OR = 2.72, 95%CI: 1.19~6.21),移動時間の目安の提示(OR = 0.43, 95%CI: 0.21~0.92)が就業継続意向と関連した.結論:移動に関する直接的な支援が就業継続支援に有用であることが示唆された.
1 0 0 0 OA 死について考える : 死の生物学と死生観(特別講演,第6回日本健康医学会総会抄録集)
- 著者
- 豊倉 康夫
- 出版者
- 日本健康医学会
- 雑誌
- 日本健康医学会雑誌 (ISSN:13430025)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.5-7, 1996-10-31 (Released:2017-12-28)
1 0 0 0 OA WTe2薄膜デバイスにおける電極形成手法の検討
- 著者
- 細田 雅之 ディーコン ラッセル 山口 智弘 岡崎 尚太 笹川 崇男 谷口 尚 渡邊 賢司 河口 研一 土肥 義康 佐藤 信太郎 石橋 幸治
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理学会学術講演会講演予稿集 第68回応用物理学会春季学術講演会 (ISSN:24367613)
- 巻号頁・発行日
- pp.2903, 2021-02-26 (Released:2022-06-19)
1 0 0 0 OA 半導体ヘテロ構造を用いた2次元トポロジカル絶縁体の研究
- 著者
- 村木 康二
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会講演概要集 73.1 (ISSN:21890803)
- 巻号頁・発行日
- pp.1237, 2018 (Released:2019-05-13)