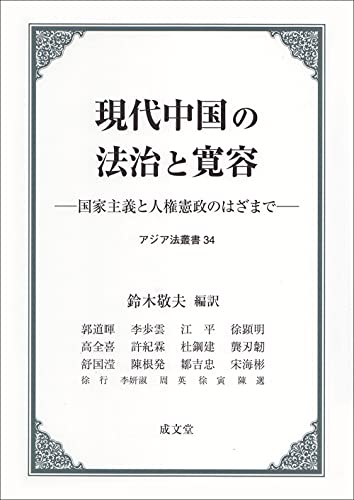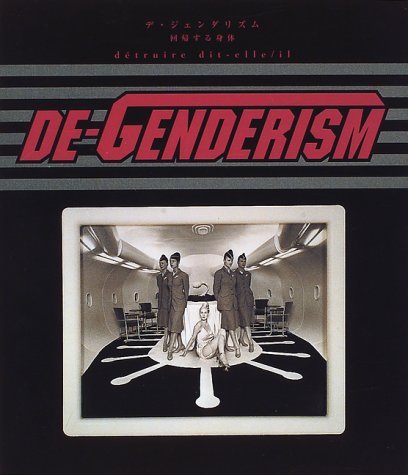1 0 0 0 月刊障害者問題情報 : 障害者運動専門情報誌
- 出版者
- 障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会
- 巻号頁・発行日
- no.27, 1985-06
1 0 0 0 OA 社会資本整備における賛否態度の形成:公正の絆理論と態度変容モデルの統合
- 著者
- 青木 俊明 鈴木 温
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.42-54, 2005 (Released:2006-04-29)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 6 5
本研究では,自己関連性と情報提示に着目し,社会資本整備に対する市民の態度形成のメカニズムを検討した。その際,ヒューリスティック・システマティック・モデルおよび精緻化見込モデルに基づいてモデル構造を検討した。インターネットを用いてシナリオ実験を行った結果,情報開示が不十分な状況では,自己関連性の高さに関わらず,プロジェクトの社会的妥当性と信頼感などの周辺情報に基づいて賛否態度が形成されることが示された。その際,どちらの場合であっても周辺情報以上に事業情報の方が賛否態度に強い影響力を持つことが示唆された。一方,十分な情報が開示されている状況では,自己関連性の高低に関わらず,プロジェクトの社会的妥当性と手続き的公正によって賛否態度が形成されることが示唆された。さらに,態度変容モデルに基づいて考察した結果,自己関連性が高い場合には手続き的公正の中身が重要であり,自己関連性が低い場合には手続き的公正が認識させる行為自体が重要であることが示唆された。これらのことから,自己関連性の高さによって手続き的公正の役割や態度形成のメカニズムが異なることが示唆された。
- 著者
- 西田 晴行
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.6, pp.539-543, 2016 (Released:2016-06-01)
- 参考文献数
- 25
酸関連疾患に対する治療薬の歴史と振り返ると、より強く、より長く胃内のpHを制御できる薬剤を求めて研究開発が行われてきた。我々は「最強の酸分泌抑制薬」と言われるプロトンポンプ阻害薬(proton pump inhibitor: PPI)の課題を克服する「究極の酸分泌抑制薬」を目指して創薬研究を続け、強い胃酸分泌抑制効果と長い作用持続を有するボノプラザンを見出した。ボノプラザンは、酸に安定で水溶性に優れ、また、PPI(ランソプラゾール)の課題とされた作用発現の遅さ、効果の個人差および食事の影響などの改善が期待できる作用特性を示した。日本発の次世代医薬品として大きな貢献が期待される。
1 0 0 0 OA 寄生虫症における遺伝子検査の意義
- 著者
- 阿部 仁一郎
- 出版者
- Osaka Urban Living and Health Association
- 雑誌
- 生活衛生 (ISSN:05824176)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.5, pp.387-394, 2006 (Released:2006-10-19)
- 参考文献数
- 43
Pathogenic analysis of clinical samples to detect the causative agent is the most reliable method of confirming infection. Morphological examination using light microscopy is a convenient tool, but the information thus obtained is limited. In Japan, while morphological examination is still the gold standard in many parasitic infections, recent molecular studies have produced a wealth of new findings helpful in the diagnosis, treatment and prophylaxis of parasitic infections. Currently, genetic examination is applied in the diagnosis of various infectious diseases to obtain rapid and accurate results and also to understand their molecular epidemiology. It is expected that molecular methodologies will be necessary for the diagnosis of various parasitic infections. In the present paper, the author summarizes the significance and prospects of genetic examination in parasitic infections.
1 0 0 0 OA PCR法によるアニサキス亜科幼線虫の同定
- 著者
- 阿部 仁一郎 八木 欣平
- 出版者
- Osaka Urban Living and Health Association
- 雑誌
- 生活衛生 (ISSN:05824176)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.168-171, 2005 (Released:2005-06-07)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 2
Anisakids are parasitic nematodes infecting fish and mammals. It is well recognized that human infection with this parasite, called anisakiasis, occurs by ingestion of raw or undercooked fish. In Japan, there are estimated to be over 1,000 cases of this infection annually. In 1999, “The Food Sanitation Law Enforcement Regulation” was partly amended, and anisakiasis was newly added to the causative agents of food poisoning. Identification of anisakid larvae has been performed by light microscopy, but it is impossible to accurately identify the worms morphologically when only small portions of the worm are available. In the present study, we showed the usefulness of PCR-based methods for identification of anisakid species using several species of anisakid larvae from Pacific cod. The larvae identified morphologically as Anisakis simplex or Contracaecum osculatum were found also to be positive for PCR amplification with only species-specific primers. In addition, the larvae of Pseudoterranova decipiens, frequently found in anisakiasis in Japan, were positive for amplification with only the P. decipiens-specific primers designed for the study. PCR using species-specific primers is thus concluded to be a useful tool for identification of anisakid larvae when morphological identification is impossible.
1 0 0 0 OA うすくちしょう油製造の留意すべき点について
- 著者
- 古田 忠夫
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.12, pp.845-847, 1977-12-15 (Released:2011-11-04)
うすくちしょう油の年間生産量はしょう油全体の約10%程度である。近年僅かではあるが.他の地方の中小メーカーでも製造されているが.そのなかには単にこいくちしょう油を脱色したような製品がある。うすくちしょう油の本来の風格を保つために.製造の留意すべき点について述べていただいた。
1 0 0 0 OA 琉歌の表現研究 : 和歌やオモロとの比較
- 著者
- ウルバノヴァー ヤナ
- 出版者
- 法政大学 (Hosei University)
- 巻号頁・発行日
- pp.1-486, 2014-03-24
1 0 0 0 OA 骨粗鬆症の予防における大豆イソフラボンの生体利用性に関する研究
- 著者
- 石見 佳子
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, no.12, pp.927-933, 2008-12-15 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1 1
大豆に含まれるイソフラボン (ダイゼイン, ゲニステイン, グリシテイン) はエストロゲンに類似した構造をもつため, イソフラボンの摂取量が多いほど骨粗懸症, 更年期障害や乳がんに対する予防効果があると言われている。更に, ダイゼインの代謝産物であるエクオールは乳がん, 前立腺がんの発症率を抑えるほか, 骨量減少抑制効果についての報告もある。最近, イソフラボンはサプリメントとして市販されているが, 必ずしも大量摂取すればよいと言うわけではない。厚生労働省はサプリメントによるイソフラボンの過剰な摂取に対して注意を呼びかけている。著者らの研究によると, 閉経後の女性に対しては大豆イソフラボン投与と適度な運動の併用が大腿骨骨密度の維持に効果があった。またエクオールを産生する腸内乳酸菌にはラクトコッカスのほか数種類が関与していることが判明したが, 今後はこれらを含む乳製品の開発が期待される。本稿では著者らのデータを含め, 大豆イソフラボンに関する最新情報を解説していただいた。
1 0 0 0 わたしの声 : 一人称単数について
- 著者
- アルフォンソ・リンギス著 水野友美子 小林耕二訳
- 出版者
- 水声社
- 巻号頁・発行日
- 2021
1 0 0 0 OA 電磁熱流体力学の基礎と応用(II)
- 著者
- 棚橋 隆彦
- 出版者
- The Iron and Steel Institute of Japan
- 雑誌
- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.4, pp.N263-N281, 1993-04-01 (Released:2009-06-30)
- 被引用文献数
- 1 2
1 0 0 0 OA 腸管出血性大腸菌O157に用いる抗生物質の検討
- 著者
- 伊藤 輝代 秋野 恵美 平松 啓一
- 出版者
- 一般社団法人 日本感染症学会
- 雑誌
- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.130-135, 1997-02-20 (Released:2011-09-07)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 25 26
腸管出血性大腸菌O157感染症患者に投与する最も適切な抗菌剤を検討するため, MIC及び抗菌剤存在下でのベロ毒素の放出を測定した. 供試薬剤として経口剤ABPC, CCL, CFDN, FOM, NFLX, NA, KM, MINO, DOXY, TCを用いた. 11株中2株が, ABPC, TC耐性であったほかは, いずれの薬剤にも感受性を示し, MIC値の上では, 殆どすべての薬剤が有効であった. 薬剤存在下でのベロ毒素の放出を測定した所, 薬剤の添加により毒素の著しい放出をもたらすグループ (ABPC, CCL, CFDN, FOM, NFLX, NA) と, 殆ど無添加の場合と変わらないグループ (KM, MINO, DOXY, TC) に大別された. 細胞壁合成阻害剤 (ABPC, CCL, CFDN, FOM) の場合は殺菌に伴ってVT1, VT2ともに菌体より放出された. キノロン系薬剤 (NFLX及びNA) の場合は, VT2のみ菌体より放出された. これに対して蛋白合成阻害剤 (KM, MINO, DOXY, TC) の場合は, VT1は薬剤無添加の場合と同様に, 測定に用いた逆受身ラテックス凝集反応の検出限界以下であり, VT2も薬剤無添加の場合と同等, あるいはそれ以下であった. この結果は, 蛋白合成阻害剤を使用すれば, 腸管出血性大腸菌O157感染症に於て, 毒素を放出させることなく, 殺菌あるいは増殖を抑制することができることを示唆している
1 0 0 0 OA 腸管出血性大腸菌O157に対する抗生物質の有効性に関する検討 無菌マウスを用いた解析
- 著者
- 澤村 貞昭 田中 和生 古賀 泰裕
- 出版者
- 一般社団法人 日本感染症学会
- 雑誌
- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.10, pp.1054-1063, 1999-10-20 (Released:2011-02-07)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 11 11
無菌マウスに腸管出血性大腸菌O157: H7 (以下0157) 1×105CFUを感染させると感染が成立し, 感染8~9日後にマウスは全例死亡した.この感染動物実験系を用いてO157感染症に対する抗生物質療法の有効性を検討した.KM, DOXY, MINO, CP, CCL, AMPC, FOMおよびMFLXの8剤についてMICを測定し, 嫌気的条件下で低いMIC値を示したFOM, NFLX (FOM, 0.78;NFLX, 0.10μg/ml) をO157感染無菌マウスに投与した.O157感染3時間後よりFOM (500mg/kg/day) 或いはNFLX (50mg/kg/day) を1日2回, 連日5日間投与したところ, 生残率はそれぞれ83.3%, 100%と著明に改善し, いずれの抗生物質を投与した群でも糞便中にはべ口毒素は検出されなかった.次にFOMの投与開始時間を感染3, 6, 12, 24時間後にしたところ生残率はそれぞれ100, 100, 0, 0%であった.即ち, FOM, NFLXは感染早期に投与を開始するとべ口毒素を放出する事なく0157を除菌する事が明らかとなった.
1 0 0 0 OA 腸管出血性大腸菌(O157病原大腸菌感染症)の流行と予防について
- 著者
- 櫻井 忠義
- 出版者
- 日本安全教育学会
- 雑誌
- 安全教育学研究 (ISSN:13465171)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.13-18, 2002-03-31 (Released:2012-11-13)
- 参考文献数
- 3
1996年に発生したO157病原大腸菌による食中毒は1県に終わらず全国に感染拡大し,年間総数も9314人という数に上り,11人の死亡者を墨した。O157病原大腸菌の特徴は赤痢薗と同じベロ毒素を有し,腸管出血を起こすだけでなく,腸管より血中へ入ったこの毒素は溶血を起こして,溶血性尿毒症症候群を発症させ,極めて重篤な腎障害を起こし,死に至ることがある。成人では下痢程度で軽快すること多いので,保菌者として他の人に感染を起こす元となるだけでなく,子供では上記のように重篤に陥りやすいので,大人は下痢をしたときの対応に気をつけて,手洗い,調理法,調理用具,食材の保管など衛生,清潔に配慮すべきである。治療はニューキノロン系の抗生物質を4~5日間投与するが,壊れた菌より毒素が放出されるので,全身状況を見ながら慎重に対応する必要がある。厚生省(現厚生労働省)ではその後,指定伝染病として法定伝染病と同じ措置をとり,鎮静化してきたようにみえるが,1997年,1998年にも多数発生し,対策が十分とはいえない状況にある。
1 0 0 0 OA 出生率と結婚の動向 : 少子化と未婚化はどこまで続くか
1 0 0 0 OA 「総合選択制高校」科目選択制の変容過程に関する実証的研究 自由な科目選択の幻想
- 著者
- 田中 葉
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, pp.143-163, 1999-05-15 (Released:2011-03-18)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 3 1
The purpose of this paper is to analyze the transformation of the process of choosing subjects in a “Sogo Sentaku-sei” High School. “Sogo Sentaku-sei” or “Sogo Gakka” senior high schools have attracted much attention in recent educational reform policies, since they are different from the conventional senior high-school system, by allowing students to make their own curriculum.However, recent studies have pointed out that these schools in fact restrict a students' capacity to choose their own subjects, thereby going against the purpose of this policy. In order to properly carry out highschool reformation policies today, the causes of this phenomenon must be analyzed.This paper will attempt to investigate how and why these schools have come to restrict the students' capacity to choose their own subjects, based on ethnographic research at “A High School”, one of the leading “Sogo Sentaku-sei” high schools in Japan.The results of the research are as follows: In the beginning, the teachers of A High School did not restrict students' choice of subjects. Eventually, however, restrictions were imposed because of the problem of time cards organization. Then a few years later, the teachers of the minor ‘gakukei’-which are loose courses-allowed students to select their own subjects because they wanted to give specialized lessons and to secure enough schooltime for them. Major ‘gakukei’ teachers who couldn't control the subjects which students would be taught because of the number of students demanded to increase the number of credits of the obligatory subjects. This demand was related to the problem of the school's overall reputation of sending students to universities.In this way, the students' ability to choose their own subjects was restricted by both of individual teachers' interests and the problem of the school as a whole. These results suggest that the problem of curriculum includes the problem of school management and that it is difficult to change the curriculum, by introducing alternative educational institutions, such as ‘Sogo Gakka’.
1 0 0 0 OA 日本海溝産の深海性後鰓類シンカイウミウシ属の1新種
- 著者
- 濱谷 巌 窪寺 恒己
- 出版者
- 日本貝類学会
- 雑誌
- Venus (Journal of the Malacological Society of Japan) (ISSN:13482955)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3-4, pp.113-120, 2010-03-31 (Released:2016-05-31)
- 参考文献数
- 11
深海性後鰓類シンカイウミウシ属Bathydorisの1種1個体が,北海道釧路沖の日本海溝の深海(3108~3265m)から採集された。本属の既知種は世界に9種あるとされ,何れも深海産で,本記録が追加され10種となる。シンカイウミウシ属は咽頭部が強大な顎板によって保護される。触角は左右が離れ,非退縮性で,触角鞘を欠く。鰓葉は個々に独立し非退縮性である。Bathydoris japonensis n. sp. ヤマトシンカイウミウシ(新種・新称)生時の背面は淡紫色を呈し,触角と鰓葉の基部は黒褐色の輪状色で囲まれる。固定標本は大形(体長125 mm)で楕円形。鰓葉は約12葉で約6群にまとめられ,円形に配列する。外形はB. ingolfianaに似るが,本種の雌性生殖門の外部の襞には切れ込みが無く平滑である。口球は大きく,歯式は49×n・1・n。中央歯は概ね台形で通常歯尖を欠くが,歯尖を有するものが稀にある。本種の側歯はすべて歯尖を有し歯尖は斜立する傾向があり,鋸歯を欠く。第1側歯は中央歯よりやや大きい。側歯列は外側歯に移るに従って,基板は次第に縦長の長方形を呈する。しかし数個の最外側歯の基板は次第に幅広く,縦方向が短くなる。歯尖は歯列の中程のもの程細長く,数個の最外側歯の歯尖は次第に短くなる。タイプ産地:北海道釧路沖の日本海溝(水深3108~3268 m)。
1 0 0 0 現代中国の法治と寛容 : 国家主義と人権憲政のはざまで
- 著者
- 鈴木敬夫編訳 郭道暉 [ほか原著] 徐行 [ほか翻訳]
- 出版者
- 成文堂
- 巻号頁・発行日
- 2017
1 0 0 0 西山美なコ展 : ピンク[ハート]ピんク[ハート]ぴんク
- 著者
- [西山美なコ作] 西宮市大谷記念美術館編集
- 出版者
- 西宮市大谷記念美術館
- 巻号頁・発行日
- 1997
1 0 0 0 デ・ジェンダリズム : 回帰する身体
- 出版者
- 淡交社
- 巻号頁・発行日
- 1997