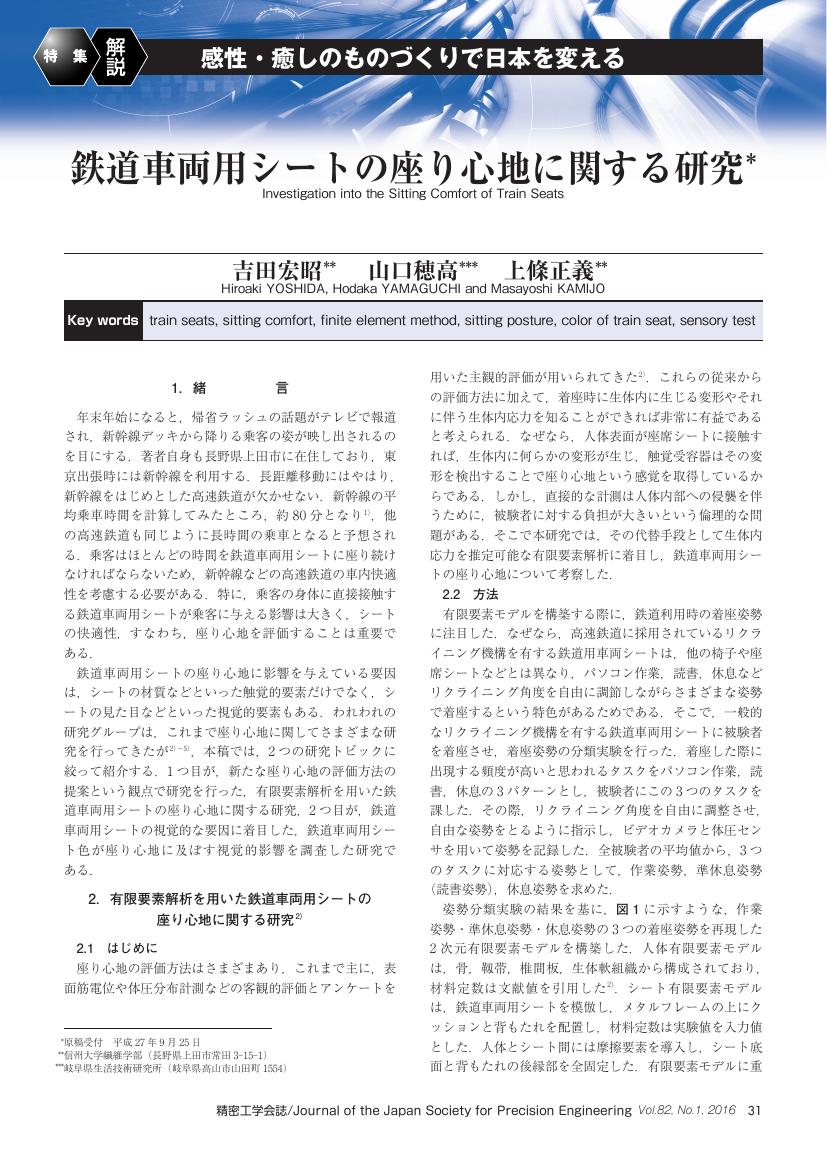1 0 0 0 OA 動体視力の定量化と科学的根拠に基づくビジョントレーニング法の確立
ビジョントレーニングの効果を定量的に評価するため、バイオマーカーの導入を検討した。指標としてBDNF(Brain-derived neurotrophic factor;脳由来神経栄養因子)を用いた。自作装置で動体視力を測定、トレーニング前後の被験者の血清、血漿BDNF濃度を測定し、動体視力との相関を調べた。結果、トレーニング前後での血清および血漿BDNF濃度は、血清では増加したが血漿では減少し、統計的に有意であった。動体視力との有意な相関は認めなかった。(第119回日本眼科学会総会発表;2015年4月)トレーニング前後で変化することから、BDNFはバイオマーカーとして利用出来る可能性がある。
1 0 0 0 OA 19世紀ドイツにおける労働者家計 - 研究課題の設定のために -
- 著者
- 川越 修 Osamu Kawagoe
- 出版者
- 同志社大学経済学会
- 雑誌
- 經濟學論叢 = Keizaigaku-Ronso (The Doshisha University economic review) (ISSN:03873021)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2-4, pp.219-253, 1984-03-15
1 0 0 0 OA コンテンツ分野における実践系博士の学位取得に関する考察
- 著者
- 高橋 光輝 戸田 千速
- 出版者
- コンテンツ教育学会
- 雑誌
- コンテンツ教育学会誌 (ISSN:24342734)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.24-33, 2017-03-08 (Released:2022-02-28)
- 参考文献数
- 26
国家政策及び産業構造の変化を勘案すれば,博士(コンテンツ)を授与する学位課程創設の重要性は論を待たない.純粋学問としての「コンテンツ学」を研究対象とする研究者養成の意義も少なくないが,それ以上に重要なことはコンテンツ業界における実務経験を有する社会人を対象とした実践系博士課程の構築である.こうした実践系博士課程においては,従来の研究者養成型博士課程とは異なり,学位取得要件として研究論文以外の実践的な活動も評価対象とすべきであろう.そこで筆者らはまず,コンテンツ分野における実践系博士課程構築の参考とするため,日本における研究者以外の人材を養成する博士課程の中でも,研究論文以外の実践的な活動も博士学位取得に際して評価対象とする,あるいは必須としている大学院―東京藝術大学大学院映像研究科,京都大学大学院総合生存学館(通称・思修館),東京理科大学大学院イノベーション研究科―について調査分析を行った.その上で,博士(コンテンツ)を授与する実践系博士課程を構築する場合の,学位要件の試案や方向性を検討する.
1 0 0 0 前衛 : 日本共産党中央委員会理論政治誌
- 出版者
- 日本共産党中央委員会
- 巻号頁・発行日
- vol.(1), no.349, 1973-01
- 著者
- 阿部 育子 習田 明裕
- 出版者
- 日本移植・再生医療看護学会
- 雑誌
- 日本移植・再生医療看護学会誌 (ISSN:18815979)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.1-15, 2022 (Released:2022-04-16)
- 参考文献数
- 24
本研究は、 臓器移植看護の倫理的場面において、レシピエント移植コーディネーター(以下、RTC)が抱く苦悩の構造とその関連要因を明らかにすることを目的とした。全国の移植施設に勤務するRTCを対象に自記式質問紙調査を実施した。その結果、84名(回収率47.5%)から回答が得られた。臓器移植看護の倫理的場面として、「臓器移植全般」、「生体移植」、「脳死移植」の3つの領域30場面の回答を基に、探索的因子分析を行った。その結果、【移植医療の不確かさ】、【RTCとしての自信のなさ】、【倫理的責務の障壁】の3つの因子構造が示された。また、各因子の下位尺度得点を目的変数とし、[個人特性]、[RTC特性]、[環境特性]、[倫理特性]を説明変数として重回帰分析を行った結果、説明率は低かったものの関連要因として『立場』、『RTC経験歴』、『担当移植件数』があった。
1 0 0 0 OA 急性扁桃炎に対するレボフロキサシン1日400mg分2投与の検討
- 著者
- 近藤 律男 平田 佳代子 谷垣 裕二 堀内 長一 佃 守
- 出版者
- 耳鼻咽喉科展望会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科展望 (ISSN:03869687)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.46-52, 2005-02-15 (Released:2011-03-18)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 2
レボフロキサシン (LVFX) はニューキノロン系抗菌薬であり, postantibiotic effect (PAE) を有し抗菌作用は濃度依存的である。この事実より肺炎や急性上気道炎に対しレボフロキサシン1日400mg分2投与法の有用性が報告されている。急性上気道炎については大部分がウイルス感染であり, 自然治癒することも多いため, 本研究では急性上気道炎の中でもより細菌感染の頻度が高いと考えられる急性扁桃炎に対し, レボフロキサシン1日400mg分2投与法による臨床効果および有効性について, 1日300mg分3投与法と封筒割付け法により分別し比較検討した。対象はレボフロキサシン1日400mg分2投与群25例.レボフロキサシン1日300mg分3投与群25例である。解析方法はデータの質に応じ, X2検定, t検定, Wilcoxon順位和検定をそれぞれ用いた。なお有意水準は5%とした。臨床効果, 治癒率, 平均治癒日数などすべての項目で有意差は認めなかったものの, 400mg分2投与法の有効性と安全性が確認された。また服薬コンプライアンスの点では400mg分2投与法は300mg分3投与法と比較し, より優れた投与法であると考えられた。
1 0 0 0 OA 第五回内国勧業博覧会審査報告
- 著者
- 第5回内国勧業博覧会事務局 編
- 出版者
- 長谷川正直
- 巻号頁・発行日
- vol.第9部, 1904
1 0 0 0 OA SP イタイイタイ病―被害発生から今日まで―
- 著者
- 鏡森 定信
- 出版者
- 一般社団法人日本粘土学会
- 雑誌
- 粘土科学討論会講演要旨集 第61回粘土科学討論会発表抄録 (ISSN:24330566)
- 巻号頁・発行日
- pp.10-13, 2017-09-25 (Released:2018-07-24)
1 0 0 0 OA 鉄道車両用シートの座り心地に関する研究
- 著者
- 吉田 宏昭 山口 穂高 上條 正義
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.1, pp.31-35, 2016-01-05 (Released:2016-01-05)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA 子どものキャンプ経験が大脳活動に与える効果 go/no -go課題による抑制機能への影響
- 著者
- 平野 吉直 篠原 菊紀 柳沢 秋孝 根本 賢一 田中 好文 寺沢 宏次
- 出版者
- 日本野外教育学会
- 雑誌
- 野外教育研究 (ISSN:13439634)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.41-48, 2002 (Released:2010-10-21)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
The purpose of this study was to examine the effects of the experience of camping upon cerebral activity.An experimental method, utilizing the go/no-go task, was used to examine the grasping response of a rubberboll to a light stimulus. The go/no-go task is a representative method of investigating the human inhibitoryfunction. The subjects were 46 children (27-boys and 19-girls) in grades 3 and 4 who participated in a 6-daycamp. This camp was designed to ensure that participants were given ample and vital opportunities for notonly physical activity but for communication with other people. We carried out the go/no-go experiment onfour occasions. (pre-1: 17days before camp, pre-2: first day of camp, post-1: final day of camp, post-2: 13days after camp)The following results were obtained.The post-1 data showed a significant decrease in the number of errors compared with pre-2 data. This resultsuggests that the children's camp which included vital opportunities for physical activity andcommunication with other people had a positive influence on cerebral activity. A similar result of asignificant decrease between pre-camp and post-camp was observed in two separate investigates. However, the change between pre-1 and pre-2, post-1 and post-2 were not significant. The results suggest that thedecrease between pre-camp and post-camp was the effect of camping experience, and its effect continued for 2 weeks after camping experience.
- 著者
- Tetsuya Konishi Kenichi Watanabe Somasundaram Arummugam Misato Sakurai Shinji Sato Seiichi Matsugoh Tetsuo Watanabe Koji Wakame
- 出版者
- Society for Glycative Stress Research
- 雑誌
- Glycative Stress Research (ISSN:21883602)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.4, pp.248-257, 2019 (Released:2020-03-03)
1 0 0 0 OA ケニア・カンバにおけるウイッチ
- 著者
- 上田 将
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:24240508)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.4, pp.324-336, 1975-03-31 (Released:2018-03-27)
The purpose of this paper is to give a brief account of Kamba witches (aoi, sing. muoi) . This paper is based on field work done in the Kyuso Division, the northern part of Kitui District, Kenya, from December 1970 to July 1973. People say they can find witches in every village. They fear witches very much. They don't want to marry the daughters of witches. Therefore, witches' daughters usually marry poor men with few cattle. The bride-wealth paid for a witch's daughter is less than normal. The characteristics of witches described include : (1) Witches are all women and their magical power (uoi or woman's uoi, uoiwa mundu muka) is inherited through the female line by doing a specific ritual in which mother and daughter join and shake their buttocks together, chanting a spell. Witches' sons do not inherit uoi at all. They are not regarded as witches. Kamba witchcraft is deeply involved with femininity. (2) Witches do not use any magical medicines (miti, ndawa) or fetishes (ithitu) . People explain that witches hide these kinds of things. Witches bewitch people by just scratching their buttocks or saying some suggestive words such as "You will see later." Witches' magical power originates from the inside of their bodies, especially their genital organs, not from medicine men or others. (3) It is believed that witches cause people many kinds of misfortunes such as disease, wounds, sterility, death, and loss of work. Witches can also cause 'disease, death, and sterility among livestock and the destruction of crops.
1 0 0 0 OA 高齢者における素早い立ち上がり後のふらつき要因の検討
- 著者
- 上條 史子 千代丸 正志 大川 孝浩 上田 泰久 西村 沙紀子
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.567-572, 2021 (Released:2021-08-20)
- 参考文献数
- 29
〔目的〕健常高齢者における素早い立ち上がり後のふらつきの要因について検討すること.〔対象と方法〕対象は男性健常高齢者15名とした.三次元動作解析システムを使用し,素早い立ち上がりとその後の立位姿勢を計測した.立ち上がり後の立位不安定の指標には,重心の進行方向位置から実効値を算出し使用した.実効値と立ち上がり動作における下肢運動学的項目と運動力学的項目の相関について検討した.〔結果〕実効値と左股関節伸展モーメント最大値の発生タイミング間には負の相関を,左膝関節モーメントの最大値とは正の相関を示した.〔結語〕立ち上がり後の立位を不安定にさせる要因には,離殿後の股関節の遠心性制御能力が考えられ,それに関連して膝関節の伸展筋力も関与すると示唆された.
1 0 0 0 アレロパシー検定法の確立と作用物質の機能
1 0 0 0 OA 視覚障害者向けゲーム開発環境の開発とそのインクルーシブゲームへの応用
- 著者
- 邉 敬花 吉澤 望 宗方 淳 古賀 誉章 平手 小太郎
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会環境系論文集 (ISSN:13480685)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.688, pp.437-444, 2013-06-30 (Released:2013-08-30)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 3 4
This study aims to ascertain the limits to which a solid angle can be used as an indicator for evaluating the senses of physical oppression and of openness in urban spaces. For that, a logistic regression analysis focusing on the street as a whole and the proportion by evaluating value was conducted by evaluating each criterion found through a logistic regression model to assess the limits of the effects of the solid angle. The allowable values for the sense of physical oppression are configured using a threshold if the sense of physical oppression is felt, but reconfiguration of the allowable values for the sense of openness is not necessary. Therefore, for those respondents who indicated that a sense of physical oppression exists, it appears that the limits of that allowable sense of physical oppression are as follows: using judgment of 75% of the evaluators, the rate of solid angles was 76%; using judgment of 50% of the evaluators, the rate of solid angles was 65%; and using judgment of 25% of the evaluators, the rate was 53%. Compared to the studies of the Japan Society of Civil Engineers, Spreiregen and Takei, those allowable values are more appropriate.
1 0 0 0 OA 摂食障害の治療・研究の最近の動向について(<特集>摂食障害の最近の動向)
- 著者
- 石川 俊男 田村 奈穂
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.122-127, 2014-02-01 (Released:2017-08-01)
- 被引用文献数
- 3
摂食障害(ED)の治療や研究の最近の動向について述べた.2013年,DSM-IVが改訂されDSM-5が公開された.そこではさまざまな変更が行われ,その例として,むちゃ食い障害が特定不能の摂食障害から独立した扱いになっている.治療面では,これまで報告されてきた精神療法の効果の有無をRCTで検討する研究が進められた結果,神経性無食欲症(AN)で治療成績の改善が得られ,認知行動療法(CBT)の神経性大食症(BN)に対する有効性の科学性が高まり,第一選択治療法との位置づけが確立した.薬物療法に関しては,BNに対してむちゃ食いなどの症状に対する治療効果が多くの抗うつ薬や向精神薬,抗てんかん薬などで確かめられた.新たな生物学的治療法として経頭蓋磁気刺激法(repetitive transcranial magnetic stimulation : rTMS)がEDにも試みられているが,その有効性については今後の課題である.一方で基礎研究面では,これまでのように遺伝子研究,神経伝達物質研究,脳画像研究,神経回路網の脆弱性などさまざまな研究結果が出されている.例えば,ニューロイメージング研究ではEDの病態生理の脳内メカニズムとして,ANで認知的柔軟性課題遂行中の腹側前頭葉-線条体回路の活動性の低下や食物に限局した恐怖・情動ネットワークの過敏性の亢進,BNでは食物刺激に対する報酬系の反応性の低下などが指摘されている.