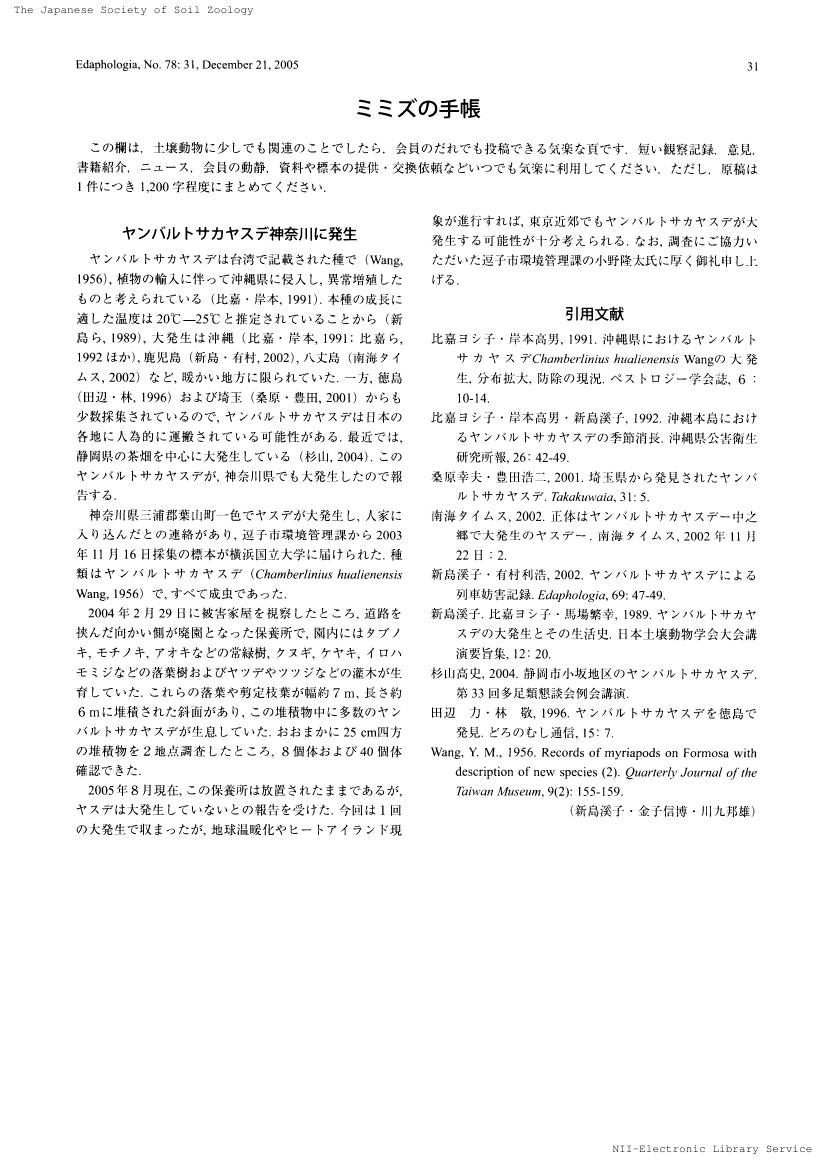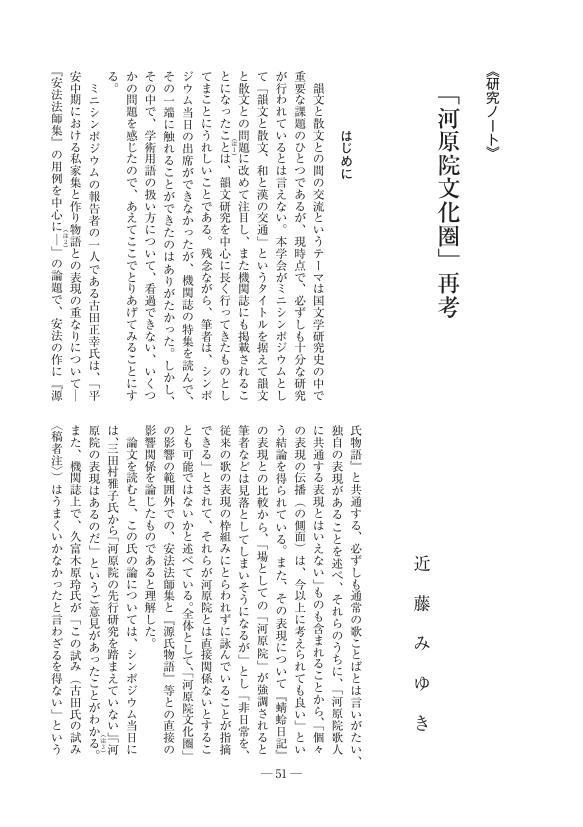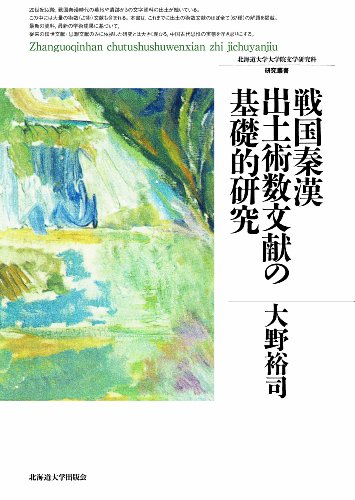9 0 0 0 OA 大阪府におけるミナミメダカの遺伝的多様性と外来個体群の侵入状況
- 著者
- 平井 規央
- 出版者
- Japanese Society of Environmental Entomology and Zoology
- 雑誌
- 環動昆 (ISSN:09154698)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.47, 2017 (Released:2018-01-06)
9 0 0 0 OA 歩兵教練ノ参考
- 著者
- 陸軍歩兵学校 編
- 出版者
- 陸軍歩兵学校将校集会所
- 巻号頁・発行日
- vol.第5巻, 1943
9 0 0 0 OA 二肢選好に基づく商品コンセプトに合致した容器輪郭形状の生成
- 著者
- 城下 慧人 小森 政嗣 横山 卓未
- 出版者
- ヒューマンインタフェース学会
- 雑誌
- ヒューマンインタフェース学会論文誌 (ISSN:13447262)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.53-62, 2022-02-25 (Released:2022-02-25)
- 参考文献数
- 14
This study aimed to estimate psychological utility functions that convert product design into impressions using preference learning methodology, and to construct product shapes that match product concepts based on the estimated functions. Using Elliptic Fourier descriptors (EFDs), we converted the contours of 26 shampoo bottle shapes into Fourier coefficients and performed a Principal Component Analysis (PCA) on the coefficients to construct shape space. Twelve persons participated in five experimental sessions corresponding to five different product concepts. For each session, participants were presented with a pair of randomly generated images of shampoo bottles from the shape space. They were asked to choose the one that matched a given product concept for 100 trials. The bottle shapes conforming to the product concepts were synthesized based on the average utility functions estimated by using Gaussian process preference learning. The synthesized bottle shapes were assessed to determine if they conveyed the intended product concepts. The results suggested that our approach is an effective way to reflect the product concept in the shape design.
- 著者
- 海津 亜希子 玉木 宗久 榎本 容子 伊藤 由美 廣島 慎一 井上 秀和
- 出版者
- 一般社団法人 日本LD学会
- 雑誌
- LD研究 (ISSN:13465716)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.58-74, 2022 (Released:2022-02-28)
- 参考文献数
- 11
発達障害を対象とした通級での自立活動において教科の内容を取り扱いながらの指導の実態を調査した。通級担当者に任意の1名について回答を求め小学校952名,中学校613名,高等学校173名の児童生徒の回答を得た。教科の内容を取り扱いながらの自立活動の指導の実施について「有り」と回答した割合は,小学校70.3%,中学校76.3%,高等学校25.4%であった。指導の内容は小・中学校のLD,ADHD,ASDいずれの障害種でも「基礎的な学習スキル」,次に「授業への参加の不安を取り除き参加意欲を促すための振り返りや先取り」が高かった。一方「特定の代替手段の使い方」「定期試験,テスト等を受ける際に必要なスキル」は40.0%に満たなかった。自立活動の区分において,50.0%を超えたのはいずれの障害種においても「心理的な安定」であった。また自由記述で求めた課題では「通常の学級との連携」に関するものが24.5%みられた。
9 0 0 0 OA 基本計画(閣議決定)の法的意義 ――住生活基本計画を素材に
- 著者
- 板垣 勝彦
- 出版者
- 公益社団法人 都市住宅学会
- 雑誌
- 都市住宅学 (ISSN:13418157)
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, no.94, pp.14-19, 2016 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 19
9 0 0 0 IR 性同一性障害をめぐる断章
- 著者
- 畑 英理
- 出版者
- 大阪大学大学院文学研究科臨床哲学研究室
- 雑誌
- 臨床哲学のメチエ
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.14-17, 2000
9 0 0 0 日本の精神医療における「病院収容化(施設化)」と「地域で暮らすこと(脱施設化)」 : 北海道浦河赤十字病院精神科病棟の減床化と廃止の取り組みを中心に (民俗儀礼の変容に関する資料論的研究)
- 著者
- 浮ヶ谷 幸代
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.205, pp.53-80, 2017-03
9 0 0 0 OA オフィクレイド教則本の比較研究
- 著者
- 橋本 晋哉 Shinya Hashimoto
- 雑誌
- 洗足論叢 = Memoirs by the members of Senzoku Gakuen College of Music, Senzoku Junior College of Childhood Education (ISSN:02877368)
- 巻号頁・発行日
- no.49, pp.27-37, 2021-02-01
9 0 0 0 OA ピエール・ルジャンドルの「解釈者革命」について
- 著者
- 田口 正樹
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 北大法学論集 (ISSN:03855953)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.189-208, 2006-07-31
- 著者
- 梅宮 新偉
- 出版者
- 放送大学
- 雑誌
- 研究報告 (ISSN:13431080)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.57-75, 2002-03
- 著者
- 山田 創平
- 出版者
- 名古屋大学国際言語文化研究科国際多元文化専攻
- 雑誌
- 多元文化 (ISSN:13463462)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.175-187, 2003-03
9 0 0 0 OA マン・ホイットニーのU検定と不等分散時における代表値の検定法
- 著者
- 名取 真人
- 出版者
- 一般社団法人 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- pp.30.006, (Released:2014-06-18)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 3 6
9 0 0 0 OA 子どもの頃の読書が成人の意識・意欲・行動に与える影響 世代間差に注目して
- 著者
- 濵田 秀行 秋田 喜代美 藤森 裕治 八木 雄一郎
- 出版者
- 日本読書学会
- 雑誌
- 読書科学 (ISSN:0387284X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.29-39, 2016-03-31 (Released:2017-01-12)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 2
This study investigates the effects of childhood reading experiences on adult consciousness, motivations and activities through structural modeling of their relations as mediated by individual annual income. Adult respondents (N=5,258, age range=20-69 years) completed a questionnaire and the results of analyses conducted for 2,589 respondents for whom annual income information was obtained suggest that childhood reading experiences have a relatively stronger influence on adult consciousness, motivations and activities than individual annual income. Moreover, the results of multiple population analysis conducted for 1,070 adults with less than ten years of work experience and 1,204 adults with more than ten years work experience indicate that (1) childhood reading experiences had strong influences on adult consciousness, motivations and activities in both populations, and (2) childhood reading experiences only had a significant effect on annual incomes for the group with more than 10 years of work experience. These results suggest that childhood reading experiences are important variables that impacts on the psychological fulfillment of adults. Thus, this study concludes that childhood reading experiences are strongly associated with adulthood consciousness, motivations and activities.
9 0 0 0 OA カイコおよび昆虫のテロメアの構造と進化
- 著者
- 藤原 晴彦
- 出版者
- 社団法人 日本蚕糸学会
- 雑誌
- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.1, pp.1_3-1_11, 2010 (Released:2016-04-20)
- 参考文献数
- 35
9 0 0 0 OA 日本人の海外観光旅行の変容 ─海外旅行自由化以降に注目して─
わが国の旅行業界では,日本人による海外渡航者数減少という課題に直面している。特に若者の海外旅行離れが叫ばれているが,これまでの我が国の海外旅行はどういった特徴があり,当時の日本人は何を目的に海外へ出かけて行ったのか。本稿では,これまでの日本人の海外旅行の経緯をまとめ,今後の日本人海外旅行市場がどうなっていくのかを考察した。 まずは,これまでの日本人の海外渡航者数を明らかにする。そして日本人の海外旅行の変遷をたどった。富裕層で,限られた人しか行くことの出来なかった海外旅行は,日本政府による海外渡航規制緩和,旅行会社による海外パッケージツアーの誕生で第一次海外旅行ブームを迎えた。その後,格安航空券や旅行代金の値下げも伴い1980年代には第二次ブームが起きた。現代は,海外旅行は日本庶民にとって特別なものではなくなり,簡単に安く海外に行き,買い物や食べ物を楽しむ旅行へと変化していったことがわかった。
9 0 0 0 OA ヤンバルトサカヤスデ神奈川に発生
- 著者
- 新島 溪子 金子 信博 川九 邦雄
- 出版者
- 日本土壌動物学会
- 雑誌
- Edaphologia (ISSN:03891445)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, pp.31, 2005-12-21 (Released:2017-07-20)
9 0 0 0 OA COVID-19をめぐるメディア・コミュニケーションとその課題
- 著者
- 田中 幹人 石橋 真帆 于 海春 林 東佑 楊 鯤昊 関谷 直也 鳥海 不二夫 吉田 光男
- 出版者
- 公益財団法人 医療科学研究所
- 雑誌
- 医療と社会 (ISSN:09169202)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.71-82, 2022-04-28 (Released:2022-05-26)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1
新興感染症であるCOVID-19に対処する中では,日々更新されるリスク知識を社会で共有し,また政策から個々人のレベルに至るまでリスクを判断していく必要があった。このリスク情報の流通と議論の場となってきたのは,もちろんメディアである。本稿では,我々の研究結果を基に,まず情報の送り手である新聞報道の傾向を振り返り,また情報の受け手である日本のメディア聴衆の相対的リスク観を把握する。そのうえで,ソーシャルメディアを含むオンラインメディア上でのコミュニケーションの成功例,失敗例を確認し,そこから教訓を得る。更にマス/オンラインメディアが複雑に絡み合う中で,COVID-19禍を通じて明らかになった感染者差別,ナショナリズム,懐疑論や隠謀論といった問題を確認したうえで,コミュニューション研究の知見を踏まえて,リスクのより良い社会共有に向けた方針を提示することを目指す。COVID-19という災害は,新興感染症として私達の医療・社会制度の刷新を求めているのみならず,コミュニケーションを通じたリスク対応のあり方についても大きな変革を求めているのである。
9 0 0 0 OA 人工炭酸泉の基礎と医学的効果・美容効果
- 出版者
- 人工炭酸泉研究会
- 雑誌
- 人工炭酸泉研究会雑誌 (ISSN:13442279)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.5-19, 2019 (Released:2019-08-01)
Ⅰ.基 礎 1.炭酸泉とは日本の温泉法によると、炭酸泉は主に遊離炭酸が250ppm(1ℓに250mg)溶けていれば炭酸泉と名前が付き、さらに炭酸泉に関しては1000ppm(1ℓに1g)溶けていれば療養泉となる。天然の炭酸泉は低温のものであれば濃い濃度の炭酸泉が日本随所にある。しかし、温度が40℃程度の温浴に適した天然の温泉は日本が火山国でもあるためか数少ない。41℃程度では大気圧下で溶存できる炭酸濃度は1000ppm 程度が上限であるため、大分県長湯温泉での大丸湯「高温ラムネ温泉」の41.2℃で遊離炭酸911ppm(2007.8.2)の源泉は珍しいものと思われる。
9 0 0 0 OA 「河原院文化圏」再考
- 著者
- 近藤 みゆき
- 出版者
- 中古文学会
- 雑誌
- 中古文学 (ISSN:02874636)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, pp.51-56, 2019-05-31 (Released:2020-06-06)