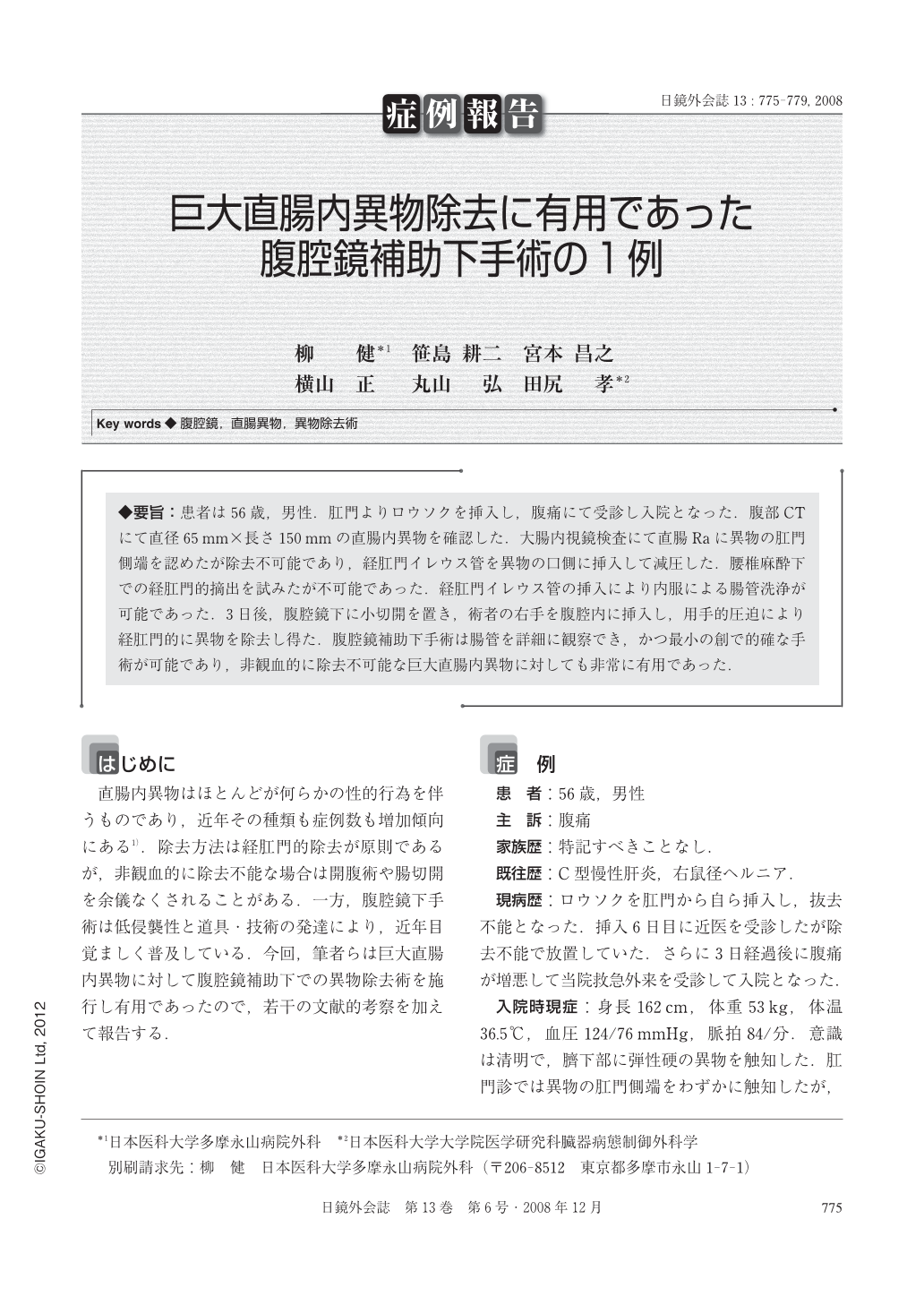1 0 0 0 巨大直腸内異物除去に有用であった腹腔鏡補助下手術の1例
◆要旨:患者は56歳,男性.肛門よりロウソクを挿入し,腹痛にて受診し入院となった.腹部CTにて直径65mm×長さ150mmの直腸内異物を確認した.大腸内視鏡検査にて直腸Raに異物の肛門側端を認めたが除去不可能であり,経肛門イレウス管を異物の口側に挿入して減圧した.腰椎麻酔下での経肛門的摘出を試みたが不可能であった.経肛門イレウス管の挿入により内服による腸管洗浄が可能であった.3日後,腹腔鏡下に小切開を置き,術者の右手を腹腔内に挿入し,用手的圧迫により経肛門的に異物を除去し得た.腹腔鏡補助下手術は腸管を詳細に観察でき,かつ最小の創で的確な手術が可能であり,非観血的に除去不可能な巨大直腸内異物に対しても非常に有用であった.
- 著者
- Misato Ogata Hironaga Satake Takatsugu Ogata Yukimasa Hatachi Shigeo Hara Seiichi Hirota Hisateru Yasui
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.22, pp.3243-3246, 2019-11-15 (Released:2019-11-15)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1 1
We herein report the first case in which an escalated dose of sunitinib was effective, even after dose reduction. A 64-year-old man with gastrointestinal stromal tumor of the small intestine discontinued adjuvant imatinib because of interstitial pneumonia. After two years, peritoneal recurrence was detected. Sunitinib was started at 50 mg/day for 4 weeks every 6 weeks, after which the dosage was reduced to 37.5 mg/day because of grade 1 gastritis, stomatitis, and a fever. Four months later, computed tomography showed progressive disease. As the adverse events were well-controlled by medication, we escalated the dose to 50 mg/day and achieved a partial response.
- 著者
- 高橋 裕介
- 出版者
- 北海道大学
- 雑誌
- 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)
- 巻号頁・発行日
- 2018
大気再突入時に高温プラズマに包まれた宇宙機が、地上局やデータ中継衛星との通信途絶現象(通信ブラックアウト)に陥ることは大きな問題である。その一方で、再突入機近傍のプラズマ諸量分布や電磁波挙動の正確な予測が難しく、通信ブラックアウト低減に繋がる知見の探索が困難な状況である。したがって、この問題を回避・緩和するために通信ブラックアウト低減化技術は必要である。いま表面触媒性を用いた宇宙機後流プラズマ密度低下を利用することによる通信ブラックアウト低減が提案されている。本研究では表面効果による通信ブラックアウト低減化メカニズムおよび低減化技術の指針を見出すことを目的とする。本年度では、ドイツ航空宇宙センター(DLR)に滞在し通信ブラックアウト低減化の研究を実施した。DLR研究者との議論の中で、これまで取り組んできた表面触媒性とは別のメカニズムを利用した新しい通信ブラックアウト低減化手法を提案した。これは冷却ガスを再突入機表面から噴出して空力加熱低減する技術(フィルムクーリング)を応用したものである。とくにここではフィルムクーリングによる低減化の実現可能性を数値解析的手法によって調べた。本課題の基課題となる研究課題 (若手研究B17K14871)では表面触媒性による通信ブラックアウト低減化の実験的実証を行った。このメカニズムを本研究課題では数値解析的手法によって次の通り明らかにした:(1)表面触媒によって生じる分子が再突入機後流に流出する。(2)後流において分子の増加が原子種の不足を招く。(3)原子種を補う方向に電子の再結合反応が促進することで、電子が低減する。(4)電子の低減によって通信電波の伝播が緩和される。
1 0 0 0 OA SBA-15 Functionalized with Naphthalene Derivative for Selective Optical Sensing of Cr2O72− in Water
- 著者
- Mehdi KARIMI Alireza BADIEI Ghodsi MOHAMMADI ZIARANI
- 出版者
- The Japan Society for Analytical Chemistry
- 雑誌
- Analytical Sciences (ISSN:09106340)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.5, pp.511-516, 2016-05-10 (Released:2016-05-10)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 4 10
A novel organic-inorganic hybrid optical sensor (NUS) was designed and prepared in two steps: the grafting of 3-(isocyanatopropyl)trimethoxysilane onto the surface of SBA-15, and then the attachment of naphthalene-1-amine. The obtained materials were characterized using low-angle XRD, N2 adsorption-desorption, TGA, FT-IR, and TEM techniques. A fluorescence study revealed that the NUS was a highly selective optical sensor for the detection of Cr2O72− among various anions, including F−, I−, Cl−, Br−, CO32−, HCO3−, NO3−, H2PO4−, CH3COO−, and NO2− with a good linearity between the fluorescence intensity and the concentration of Cr2O72− as well as a detection limit of 1.2 × 10−7 M in a 100% aqueous medium. Moreover, the applicability of real samples of the sensor is also discussed.
1 0 0 0 霞ヶ関25時 文春砲ショック!
- 出版者
- 日経BP
- 雑誌
- 日経ニューメディア = Nikkei new media (ISSN:02885026)
- 巻号頁・発行日
- no.1742, 2021-03-01
行政、通信政策、放送政策 総務省は2021年2月20日付で情報流通行政局長と官房審議官を官房付とする人事異動を発表した。週刊文春で報じられた菅義偉首相の長男から接待を受けていた問題をめぐっての事実上の更迭と見られている。さらに2月24日付で、国家公務員…
1 0 0 0 OA 資格制度の意味と限界
- 著者
- 福井 秀夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本不動産学会
- 雑誌
- 日本不動産学会誌 (ISSN:09113576)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.6-14, 2011-12-22 (Released:2016-10-19)
- 参考文献数
- 7
- 著者
- 阪本 博志 Hiroshi SAKAMOTO
- 雑誌
- 宮崎公立大学人文学部紀要 = Bulletin of Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.263-282, 2010-03-05
「マスコミの帝王」と呼ばれた評論家・大宅壮一(1900-1970)は、1965年から亡くなる直前まで『週刊文春』誌上で対談を連載し、毎回各界の第一人者との対談をくりひろげた。今日では忘れ去られているといってよいこの対談について筆者の作成した記録を示し、『週刊公論』『改造』などにおける大宅による他の連載対談の記録との比較から、その重要性をうきぼりにする。そしてこの対談の変容をさぐったうえで、考察を加える。
1 0 0 0 如来蔵思想の形成 : インド大乗仏教思想研究
1 0 0 0 如来蔵思想の形成 : インド大乗仏教思想研究
1 0 0 0 牧原出『「安倍一強」の謎』
- 著者
- 上川 龍之進
- 出版者
- 日本行政学会
- 雑誌
- 年報行政研究 (ISSN:05481570)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.114-116, 2017
1 0 0 0 IR 財産所有デモクラシーと企業規制--職場民主主義推進の是非をめぐって
- 著者
- 大澤 津
- 出版者
- 北九州市立大学法学会
- 雑誌
- 北九州市立大学法政論集 (ISSN:13472631)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.3, pp.1-26, 2020-03
本稿は、アラン・トマスの財産所有デモクラシーの構想における職場民主主義の位置づけを検討する。トマスは、市場の効率性を理由に企業規制を忌避するから、政府の介入で職場民主主義を導入することに否定的である。これに対し本稿は、職場民主主義は人々の政治的主体性の確立に重要との観点から、組織のあり方をより民主主義的なものにするため企業を規制すべきだとし、その根拠に政策レベルでの卓越主義を導入することを論じる。
1 0 0 0 OA 学校及家庭用言文一致叙事唱歌
1 0 0 0 OA 編集後記
- 出版者
- 総合危機管理学会
- 雑誌
- 総合危機管理 (ISSN:24328731)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.31-42, 2021 (Released:2021-03-15)
1 0 0 0 OA アルプァ放射体内部被曝生物影響研究 -プルトニウム発がん実験を中心に-
- 著者
- 小木曽 洋一 山田 裕司 飯田 治三 福津 久美子 福田 俊
- 出版者
- Japan Health Physics Society
- 雑誌
- 保健物理 (ISSN:03676110)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.308-313, 1998 (Released:2010-02-25)
- 参考文献数
- 15
1 0 0 0 OA 東北の地域開発の歴史と新たな地域づくり
- 著者
- 岡田 知弘
- 出版者
- 立命館大学社会システム研究所
- 雑誌
- 社会システム研究 = 社会システム研究 (ISSN:13451901)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.15-32, 2012-03
1 0 0 0 IR カナダにおける海外薬学研修
- 著者
- 大光 正男 Epp Denise A. 曲渕 直喜 湯川 栄二
- 出版者
- 第一薬科大学
- 雑誌
- 第一薬科大学研究年報 = Annual report of Daiichi University of Pharmacy (ISSN:02868016)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.59-72, 2014-03-31
The Pharmaceutical Society of Japan proposed the "Model Core Curriculum for Pharmaceutical Education" to improve pharmaceutical education and to meet the changing health care needs in Japan. One of the basic concepts in the recent six-year Pharmacy Educational System is to enhance the current system to a level where Japanese pharmacists can participate more productively in the international arena. A practical command of English is necessary for the global exchange of data/information and dialog (journals, magazines, newspapers or direct contact) and a requirement stated in the Advanced Educational Guidelines. A global perspective and attitude from an educational perspective is also reflected in the current Model Core Curriculum of the six-year Pharmacy Educational System. This rapidly evolving need for greater internationalization of Medical Pharmacy and training of medical professionals who can play an active role globally in the area of International Scientific Exchange led to the development of an Overseas Pharmacy Training Course offered to first- through fifth-year students. The Daiichi University of Pharmacy Supporter's Association created study tours first to Northern Europe and then in March of 2013 to Canada, where there are high standards in pharmacy practice and collaborative drug therapy monitoring (CDTM) and an emphasis on the Continuing Education of a pharmacist with license updating. This paper summarizes the observations of the pharmacists' role and pharmacy education in the provinces of British Columbia and Alberta, as well as student participant responses from a questionnaire and small group discussions (SGD) following the study tour.
1 0 0 0 OA WebClass類似レポート検知機能の検証
- 著者
- 倉澤 寿之 クラサワ トシユキ Toshiyuki KURASAWA
- 雑誌
- 白梅学園大学・短期大学情報教育研究
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.25-30, 2019-03-31
- 著者
- Junya Hirai Yoko Hamamoto Daiske Honda Kiyotaka Hidaka
- 出版者
- The Plankton Society of Japan, The Japanese Association of Benthology
- 雑誌
- Plankton and Benthos Research (ISSN:18808247)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.75-82, 2018-05-30 (Released:2018-05-24)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 3 12
Metagenetic diet analyses of the 18S V9 region were conducted in 40 adult female Calanus sinicus during winter in Tosa Bay (Japan). The majority of prey items were small crustaceans (of Copepoda and Cirripedia) and diatoms, taxa that are dominant in the environment and have been previously reported as important prey items of Calanus. The abundance of sequences attributable to Dinophyta and Chlorophyta was significantly lower in C. sinicus gut contents than in environmental plankton communities, suggesting that C. sinicus avoids prey from these groups. Hydrozoans were also observed, and aplanochytrids (Labyrinthulea) were detected for the first time as a major prey of C. sinicus. Additionally, high proportions of unclassified eukaryote material were observed, suggesting undetected predator–prey relationships in key copepod species in marine ecosystems. The dietary importance of aplanochytrids, heterotrophic protists that accumulate unsaturated fatty acids such as docosahexaenoic acid, has been overlooked in previous research. Calanus sinicus is a key copepod species in the subtropical coastal regions of the western North Pacific, and a major food source for the larvae of commercially important fish; therefore, further investigation into novel prey items such as aplanochytrids is recommended to understand the complex food web structures in marine ecosystems.
- 著者
- 仲秋 秀太郎 吉田 伸一 古川 壽亮 中西 雅夫 濱中 淑彦 中村 光
- 出版者
- 日本失語症学会 (現 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会)
- 雑誌
- 失語症研究 (ISSN:02859513)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.4, pp.293-303, 1998 (Released:2006-04-26)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
軽度の Alzheimer型痴呆 (DAT) 9名と中等度の DAT 9名を対象に遠隔記憶の検査成績を検討した。自伝的記憶の検査 (autobiographical incidents memory, personal semantic memory) は Kopelman ら (1989) の検査課題を一部修正して用いた。また,社会的な出来事の検査として Kapur ら (1989) の考案した Dead/Alive test を本邦でも使用可能となるように修正し用いた。その結果,自伝的記憶の検査および Dead/Alive test の検査の双方とも,近い過去に比較して遠い過去に関する記憶の検査成績が良好であるような時間的な勾配が DAT の2群に認められた。一方,自伝的な記憶の検査においては軽度と中等度の DAT の検査成績に乖離が認められたが,Dead/Alive test においては DAT の2群の成績に乖離を認めなかった。この結果には,自伝的記憶と Dead/Alive test の解答方法の相違 (再生と再認) が関与しているだけではなく,複雑な階層構造を持つ自伝的記憶が軽度のDATに比較して中等度の DAT においてより障害されやすいことも関連すると考えられた。
- 著者
- 関 直規
- 出版者
- 東洋大学大学院
- 雑誌
- 大学院紀要 = Bulletin of the Graduate School, Toyo University (ISSN:02890445)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.329-342, 2017
本稿は、未開拓分野であった、東京市の「市民音楽」事業の成立と展開について、一次資料の発掘・分析に基づき、実証的に明らかにすることを目的とする。考察の結果、以下の三点がわかった。第一に、1920年代に入り、社会全体に音楽が浸透し、音楽の営利的興行の影響が問題化する中で、東京市は、音楽の民衆化を実現する場となった。社会教育課長は、情操教育としての音楽を統合する社会教育論を持ち、また、声楽家・教育家の外山國彦は、都市住民の音楽教育活動を積極的に引き受けた。第二に、「市民音楽」事業は、①「市民合唱団」・「市民音楽研究会」、②「音楽演奏会」・「音楽講演会」、③「短期夜間音楽講習会」・「巡回夜間音楽講習会」の三つに大別できた。第三に、これらの事業は、音楽の民衆化の視点から、音楽の専門世界と都市住民の日常生活の相互作用を促進し、「市民音楽」の分野を効果的・有機的に構築していた。