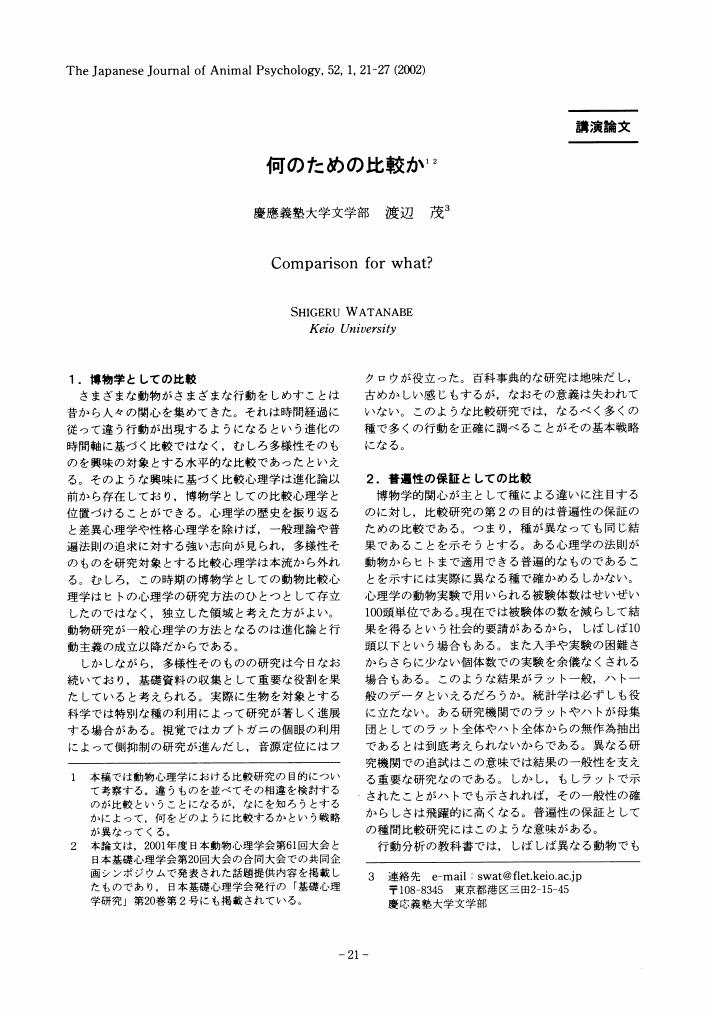1 0 0 0 近世前期における石動山の山伏支配について
- 著者
- 奥田 直文
- 出版者
- 加賀藩研究ネットワーク
- 雑誌
- 加賀藩研究 = The journal of Kaga Domain research : 加賀藩研究ネットワーク会誌 (ISSN:21861870)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.16-33, 2019-07
1 0 0 0 OA 玄々棊経
- 著者
- 晏天章, 厳徳甫 輯
- 出版者
- 囲碁雑誌社
- 巻号頁・発行日
- 1913
1 0 0 0 OA 脳血管障害の歩行分析
- 著者
- 山本 澄子
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.3-10, 2002 (Released:2002-07-24)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 16 4
3次元動作分析システムを用いて1名の片麻痺者(下肢Br.stage 4,発症後18週)の歩行を計測し,結果を正常歩行と比較しながら片麻痺歩行に共通した特徴について述べる。計測項目は,体重心の動き,麻痺側と非麻痺側の床反力,関節角度,関節モーメント,関節パワーである。正常歩行では両脚支持期に低い位置にあった体重心が単脚支持期に向けて上昇していくが,片麻痺者の麻痺側接地時にはこの動きが見られない。これは麻痺側の接地時に足関節背屈筋と股関節伸展筋の活動が正常に行われないことが原因と考えられる。これらのことから,非麻痺側から麻痺側への体重移動の重要性について考察した。
1 0 0 0 グルカゴノーマ摘出後に高度の低血糖による覚醒遅延をきたした1例
- 著者
- 岩瀬 康子 佐々木 利佳 堀川 英世 釈永 清志 山崎 光章
- 出版者
- 日本臨床麻酔学会
- 雑誌
- 日本臨床麻酔学会誌 (ISSN:02854945)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.214-217, 2012
グルカゴノーマ摘出後に高度の低血糖が原因の覚醒遅延をきたした症例を経験したので報告する.46歳女性.上腹部腫瘤と耐糖能障害を認めたため,確定診断の目的も兼ねて腫瘍摘出術が施行された.術中経過は安定しており,血糖値は103~110mg/dlであった.術後に覚醒遅延を認めたため血糖値を測定したところ,4mg/dlであった.ただちにブドウ糖を投与し,血糖値が回復すると速やかに覚醒した.術後に神経学的異常所見は認めなかった.グルカゴノーマの周術期には血糖値が大きく変動する可能性があるため,頻回に血糖値を測定する必要がある.グルカゴノーマ摘出後に覚醒遅延をきたした場合は低血糖の可能性を考慮する必要がある.
1 0 0 0 発展途上国 : ネパールにおける造形教育の目的と方法
1 0 0 0 OA クロトーによる脳の過興奮性防御機構の解明
1 0 0 0 OA 大潟村と農村計画
- 著者
- 浦 良一 木村 儀一
- 出版者
- 社団法人 農業農村工学会
- 雑誌
- 農業土木学会誌 (ISSN:03695123)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.5, pp.299-304,a1, 1976-05-01 (Released:2011-08-11)
- 被引用文献数
- 1
日本建築学会では八郎潟干拓地計画に関する特別委員会をつくって, 干拓地の全体計画, 中心地計画, 住宅計画, その他地域施設計画に関する研究を行ってきた.その成果は八郎潟干拓企画委員会建設部会を通じて八郎潟干拓地の建設に反映されていった。本稿ではその過程で検討された諸点について述べ, そこでの検討結果がその後の農村計画, 地方都市圏計画にいかに影響していったかについてもふれている。
1 0 0 0 沖縄県姓氏家系大辞典
- 著者
- 沖縄県姓氏家系大辞典編纂委員会編著
- 出版者
- 角川書店
- 巻号頁・発行日
- 1992
1 0 0 0 17世紀の東アジアにおける海賊問題と琉球
- 著者
- 真栄平 房昭
- 出版者
- 大阪経済大学日本経済史研究所
- 雑誌
- 経済史研究 (ISSN:1344803X)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.36-47, 2000
1 0 0 0 OA DPCデータを用いたMRSA感染症患者におけるTDMの臨床評価
- 著者
- 後藤 伸之 山田 成樹 藤森 研司
- 出版者
- Japanese Society of Drug Informatics
- 雑誌
- 医薬品情報学 (ISSN:13451464)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.4, pp.165-168, 2014-02-28 (Released:2014-04-02)
- 参考文献数
- 5
Objective: The purpose of this study was to clarify the importance of therapeutic drug monitoring (TDM) at acute care hospitals using Diagnosis Procedure Combination (DPC) data.Methods: We used DPC data from about 3,500,000 inpatients at about 950 acute care hospitals. The investigation period was from July 2010 to December 2010. Patients were divided into 2 groups: TDM intervention (n=22,012); and non-TDM intervention (n=26,400). We compared the clinical indicators (length of hospital stay, payment based on performance and drug costs) and use of antimicrobials.Results: TDM intervention was carried out in 45.5% patients for whom an anti-MRSA agent was prescribed. The duration of anti-MRSA agent administration was significantly longer in the TDM intervention group than in the non-TDM intervention group. The total daily cost of anti-MRSA agents was significantly lower in the TDM intervention group than in the non-TDM intervention group.Conclusion: Our results suggest that TDM intervention is often performed for seriously ill patients who require continuous treatment. TDM intervention may prevent adverse reactions as a result of adjusting the dosage of the anti-MRSA agent.
1 0 0 0 敗軍の将、兵を語る 白石真澄氏「千葉県知事選挙候補者」
- 著者
- 白石 真澄
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1485, pp.88-90, 2009-04-06
残念ながら、千葉県知事のポストに就くことはできませんでした。「敗軍の将、兵を語らず」と申しますが、兵の問題ではありません。すべての責任は私にあります。 公明党や自民党の一部の県議会議員の方やボランティアの方など、多くの人たちにご支援を頂きました。にもかかわらず、このような結果になってしまい、大変申し訳なかったと思っています。
1 0 0 0 OA 丹波と丹波西方域激び和歌山付近の地震活動の相関と兵庫県南部地震
- 著者
- 吉田 明夫
- 出版者
- Tokyo Geographical Society
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.6, pp.801-808, 1995-12-10 (Released:2009-11-12)
- 参考文献数
- 10
Correlation between seismic activities in the focal region of the Hyogo-ken Nanbu earthquake and in the surrounding regions were investigated. We found that seismic activity in the Tanba region had been well correlated with that of the Wakayama region, but the correlation has disappeared in 1990s. Activity to the west of Tanba region shows a tendency to be delayed to the activity in the Tanba region and this tendency is concordant with the f eature shown by Yoshida and Takayama (1992) that activity in the Mino region is advanced a few years against the activities in the Tanba and Wakayama regions. Such seismic correlations with time lags between surrounding areas of the Kinki triangle are considered to mean that tectonic stress in that district has a tendency to propagate or diffuse to the west at the velocity of 10 km/year. We present some evidence which decrease of the seismicity in the Tanba region in 1992-1993 period and increase in 1994 might be precursory changes for the Hyogoken Nanbu earthquake. Just after the Hyogo-ken Nanbu earthquake seismic activity in the Tanba region increased remarkably and an activity of small earthquakes was observed near the Yamasaki fault located to the west of the Hyogo-ken Nanbu earthquake. However, no unusual change of seismicity was seen in the Wakayama active region. Because a disastrous intraplate earthquake is likely to be followed by another large earthquake, and the most probable site of the succeeding large earthquake is the place where seismicity becomes active after the first earthquake (Yoshida and Ito, 1995), the Tanba region and its surrounding areas should be watched intensively in the following several to ten years.
- 著者
- 和泉 浩 IZUMI Hiroshi
- 出版者
- 秋田大学教育文化学部
- 雑誌
- 秋田大学教育文化学部研究紀要. 人文科学・社会科学自然科学 (ISSN:1348527X)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, pp.9-20, 2015-03-01
Despite the power of social capital and community resilience after disasters has been recognized, the postdisasterrecoveries and disaster mitigations after the Great East Japan Earthquake and Tsunami have still continuedto focus resources on physical infrastructures, based almost exclusively on data and knowledge of natural sciences.Against this backdrop or below the surface many sociological and ethnological studies on the Great East JapanEarthquake and Tsunami shed light on effective functioning of local communities and their social capital, or socialnetworks for the post-disaster recoveries and disaster mitigations; local community enhances individual andcommunity resilience. Some literatures point out the importance of local cultures and their traditional rituals orbuild environments and spaces of the rituals, and argue for the need for the “archive” of their memories because ofthe literally devastating effects of the Great East Japan Earthquake and Tsunami on local communities and theirmembers, but they mainly select the cultural masterpieces of local community – macro-memory or Memory ofcommunity, like museums and galleries select and collect the masterpieces of humankind. This paper theoreticallyexplores the relationships among social, collective memories, traditional rituals of local communities and socialcapital, and unveils the important functions of collective micro-memories of everyday life and social networks,which are too familiar to speak about, intentionally memorize – unspoken and pre-conscious, but one of the keyfactors for social capital and community resilience.
1 0 0 0 青いバラへの長い歩み
- 著者
- 勝元 幸久 田中 良和
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.122-126, 2005-02-01
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 明治以前日本土木史年表の試作について
- 著者
- 佐藤 馨一 五十嵐 日出夫 堂柿 栄輔 中岡 良司
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 日本土木史研究発表会論文集 (ISSN:09134107)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.191-197, 1984
年表の作成は歴史の研究において最も基本的な、しかも重要なプロセスである。土木史研究においても明治以降については、「近代欝本土木年表」としてすでに発表されている。しかし明治以前については体系的に作られた土木史年表はなく、その編成が大きな研究課題として残されている。本文はこの点に着目し、小川博三著「日本土木史概説」から明治以前の主要土木史事項を抜きだし、明治以前日本土木史年表を試作したものである。この年表では明治以前を五つに区分し、各時代ごとに30~33の項目を取り上げた。<BR>本研究の最終目的は日本土木史年表の作成にあるが、本文ではとくに年表編集のプロセスにおいて、リレーショナル・データベースを用いて簡便に土木史史料を整理し、修正し削除する方法を開発した。すなわち本研究では大型電子計算機によらず、安価でかっ日本語入出力が可能なパーソナルコンピュータを用い、さらに入力した文章データを各種ファイルに再編集した。この結果、膨大な文書史料から必要事項を任意に検索、修正、削除することが可能となり、土木史史料の作成・整理・保管・再編集作業のシステム化、迅速化が図られることになった。
1 0 0 0 OA 17-4 HEVCハイビジョンエンコーダの画質評価(第17部門画像符号化2)
- 著者
- 井口 和久 市ヶ谷 敦郎 杉藤 泰子 関口 俊一 本山 信明
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会年次大会講演予稿集 2013 (ISSN:13431846)
- 巻号頁・発行日
- pp.17-4-1-_17-4-2_, 2013-08-28 (Released:2017-05-24)
This report describes the subjective evaluation of the HEVC encoder for Hi-Vision. The encoder is developed for the purpose of communicating and reporting with limited bandwidth in case of a disaster. The subjective evaluation suggests that the image quality of developed HEVC encoder is approximately equal to the image quality coded by an AVC encoder for broadcasting, which is set to twice the level of the bitrates of HEVC.
- 著者
- 安田 彰
- 出版者
- 亜細亜大学経営学部
- 雑誌
- ホスピタリティ・マネジメント (ISSN:21850402)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.巻頭5-9, 2015
1 0 0 0 OA ある卒業生の実践記録 : 喜入の里の新田さん
- 著者
- 加納 孝代 阿部 幸子 岡田 則子 ランデス ハル
- 出版者
- 青山学院女子短期大学
- 雑誌
- 青山学院女子短期大学総合文化研究所年報 (ISSN:09195939)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.161-184, 1997-12-25
1 0 0 0 OA 何のための比較か
- 著者
- 渡辺 茂
- 出版者
- THE JAPANESE SOCIETY FOR ANIMAL PSYCHOLOGY
- 雑誌
- 動物心理学研究 (ISSN:09168419)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.21-27, 2002-06-25 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 26