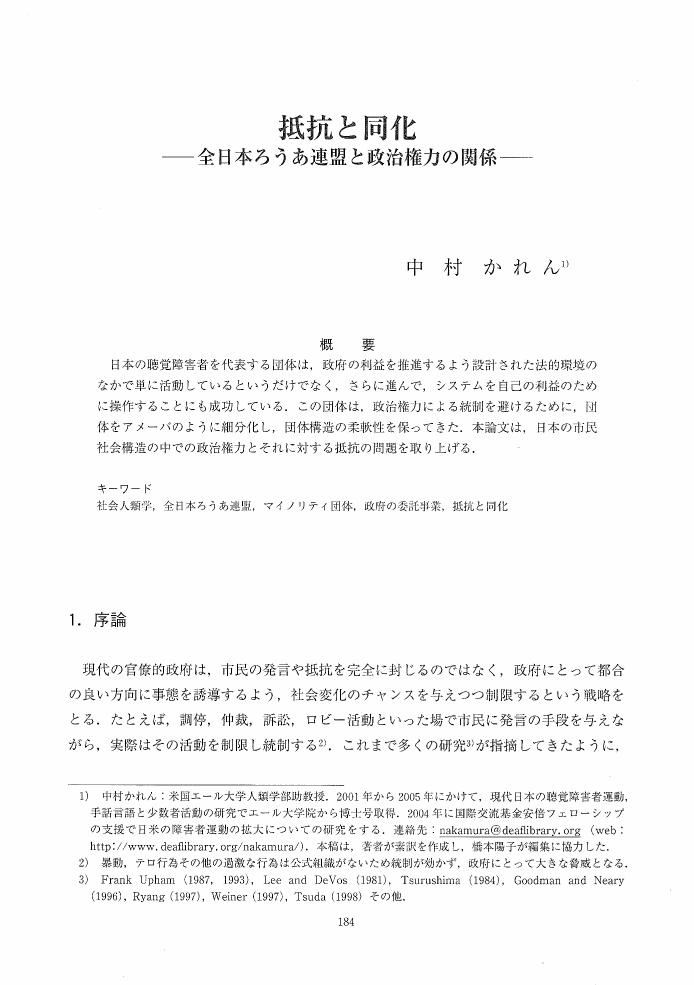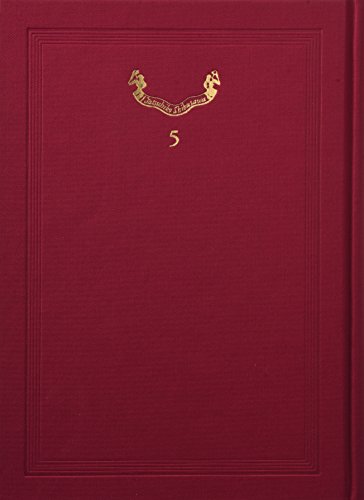1 0 0 0 OA 行政裁判所判決要旨類纂
- 出版者
- 帝国地方行政学会
- 巻号頁・発行日
- 1943
1 0 0 0 IR 韓国の憲法裁判(3・完)判例・事務中心
- 著者
- 宋 台植
- 出版者
- 白鴎大学法学部
- 雑誌
- 白鴎法学 (ISSN:13488473)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.157-221, 2003-05
1 0 0 0 王朝国家刑罰形態の体系
- 著者
- 義江 彰夫
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.3, pp.295-340,459-46, 1995
The purpose of this paper is to survey penal legal institutions particular to "dynastic" Japan of the mid-and late-Heian period, to ascertain how the penal system worked, to examine the logic behind the system, and to probe the historical background to it. Chapter 1 discusses the penal law in the preceding ritsu-ryo period. Under the strong influence of the ancient Chinese penal system, the ritsu-ryo codes specified such punishments as corporal punishment, deportation, confiscation, penal servitude, and depfivation of social standing. The code reveals the government's total control and exploitation of criminals. The author argues that the formation of the code stemmed from ritsu-ryo Japan being born under international pressures of the time and forced to develop a bureaucratic and centralized nation following Chinese precedents, while preserving Japan's indigenous tradition. Chapter 2 breaks down dyndstic Japan's penal system into three categories: (1)Kurodo-to-Hosai: Under this law, the emperors judged their vassals' minor offenses, and the Kurodo-no-To, who was in charge of the vassals, executed the judgments. (2)Dajo-kan-Hosai: Under this law, the emperors, with the help of the Dajo-kan (the Cabinet), judged both the offenses committed by court nobles of the 5th or higher rank and all serious offenses. (3)Shicho-Sai: Under this law, the Kebiishicho (Department of Investigation) judged ordinary offenses committed by people of the 6th or lower rank. By examining these three categories, the auther demonstrates that dynastic Japan's penal code was centered around "exclusion" - deportation, deprivation, and detention - and that corporal punishment and confiscation existed only as unofficial of exceptional punishments. Chapter 3 examines the historical background which led to the formation of the dynastic Japan's penal laws based on exclusion. First, the author illustrates the jurisprudential construction which formed the dynastic code out of its ritsu-ryo predecessor. Secondly, he argues that the elaboration of taboos against impurity and crime had a decisive influence over the formation of the exclusion-based punishments of dynastic Japan. The paper concludes with an explanation of how corporal punishment and confiscation, once regarded as unofficial and exceptional by aristocratic legislators, came to be incorporated into the dynastic penal code by the end of the Heian period. This transformation coincided with the emergence of the warrior class and religious powers, which did not hesitate to use such penalties as corporal punishment. When the Kamakura-Bakufu was established, it reorganized penal law strictly based on corporal punishment and confiscation.
1 0 0 0 IR 律令制下の京職の裁判権について--唐京兆府との比較を中心に
- 著者
- 長谷山 彰
- 出版者
- 三田史学会
- 雑誌
- 史学 (ISSN:03869334)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.1-31, 1996-09
はじめに一 獄令条文の解釈からみた京職の裁判権二 京職の民政と裁判三 唐獄官令の継受と京職の裁判権四 唐京兆府と京職の比較おわりに
- 著者
- Teemu Laakso Noriaki Moriyama Peter Raivio Sebastian Dahlbacka Eeva-Maija Kinnunen Tatu Juvonen Antti Valtola Annastiina Husso Maina P. Jalava Tuomas Ahvenvaara Tuomas Tauriainen Jarkko Piuhola Asta Lahtinen Matti Niemelä Timo Mäkikallio Marko Virtanen Pasi Maaranen Markku Eskola Mikko Savontaus Juhani Airaksinen Fausto Biancari Mika Laine
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Reports (ISSN:24340790)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.3, pp.182-191, 2020-03-10 (Released:2020-03-10)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 8
Background:The aim of this study was to investigate the impact of anatomical site status and major vascular complication (MVC) severity on the outcome of transfemoral transcatheter aortic valve replacement (TF-TAVR).Methods and Results:The FinnValve registry enrolled consecutive TAVR patients from 2008 to 2017. MVC was divided into 2 groups: non-access site-related MVC (i.e., MVC in aorta, aortic valve annulus or left ventricle); and access site-related MVC (i.e., MVC in iliac or femoral arteries). Severity of access site-related MVC was measured as units of red blood cell (RBC) transfusion. Of 1,842 patients who underwent TF-TAVR, 174 had MVC (9.4%; non-access site related, n=29; access site related, n=145). Patients with MVC had a significantly higher 3-year mortality than those without MVC (40.8% vs. 24.3%; HR, 2.01; 95% CI: 1.16–3.62). Adjusted 3-year mortality risk was significantly increased in the non-access site-related MVC group (mortality, 77.8%; HR, 4.30; 95% CI: 2.63–7.02), but not in the access site-related MVC group (mortality, 32.6%; HR, 1.38; 95% CI: 0.86–2.15). In the access site-related MVC group, only those with RBC transfusion ≥4 units had a significantly increased 3-year mortality risk (mortality, 51.8%; HR, 2.18; 95% CI: 1.19–3.89).Conclusions:In patients undergoing TF-TAVR, MVC was associated with an increased 3-year mortality risk, incrementally correlating with anatomical site and bleeding severity.
1 0 0 0 海外報告 抽象の森(ドイツ)コンクリートの柱が林立する斎場
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ア-キテクチュア (ISSN:03850870)
- 巻号頁・発行日
- no.647, pp.92-97, 1999-08-23
かつてBJSS(バンゲルト・ヤンセン・シュルツ・シュルテス)の4人組で活躍し,シルン・クンスト・ハレなどの作品を残したアクセル・シュルテス。グループ解散後はコンペなどで活躍し,現在はベルリンの首相官邸プロジェクトを進めている。そのシュルテスの近作,「バウムシューレンヴェク・クレマトリウム(抽象の森)」を紹介する。
1 0 0 0 OA 抵抗と同化 ―全日本ろうあ連盟と政治権力の関係―
- 著者
- 中村 かれん
- 出版者
- 国立大学法人 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社会科学研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3-4, pp.184-205, 2007-03-09 (Released:2021-02-09)
1 0 0 0 言語学バーリ・トゥード(1)「こんばんは事件」の謎に迫る
- 著者
- 川添 愛
- 出版者
- 東京大学出版会
- 雑誌
- UP (ISSN:09133291)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.4, pp.25-31, 2018-04
- 著者
- 船橋 邦子
- 出版者
- 和光大学総合文化研究所
- 雑誌
- 東西南北 = Bulletin of the Wako Institute of Social and Cultural Sciences
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, pp.18-29, 2007-03-15
1 0 0 0 OA 押出し加工性に優れた シリンダスリーブ用アルミニウム複合材料の開発
- 著者
- 乾 浩敏 佐藤 栄一 鍛冶 俊彦 重住 慎一郎
- 出版者
- 公益社団法人 自動車技術会
- 雑誌
- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.545-550, 2015 (Released:2018-01-25)
- 参考文献数
- 7
アルミ合金粉とセラミック粒子の混合材からなるシリンダスリーブは,軽量,高出力化に有効である.しかし,母相強化のために添加するCu の影響により,押出し速度向上と薄肉化に限界があった.筆者らは,Cu の添加を廃止し,Fe-Si 系化合物を分散させることで,耐磨耗性,耐焼付き性を損なうことなく上記の課題を解消した.
- 著者
- マルキ・ド・サド [著]
- 出版者
- 河出書房新社
- 巻号頁・発行日
- 1997
1 0 0 0 OA イメージマップと仮想断面実形視テストにより計られる空間認識能力間の関連
1 0 0 0 OA 小学校児童の空間構造に関する研究 (2) : 空間把握の型について
- 著者
- 足立 孝 紙野 桂人
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会論文報告集 (ISSN:03871185)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, pp.54-59,88, 1965-01-30 (Released:2017-08-30)
Frome drawings of children abowt their own home spaces, three casic types of the figurative charater are distinguished. They are follows; (1) connection type (or unit type) (2) envelopment type (or out line type) (3) division type (or pattern type) Mainly, connection type is seen among drawings of 2nd grades (of school age) children. It have a relation with attitude to apprehend spaces immediatly with his action itself. Out line type and pattern type are seen among drawings of higher school age children. Both respond to apprehension with basic constitution of the space. The outline type reveales an early stage of the tendency. At the next stage whole space is devided schematically, subject to the basic constitusion.
1 0 0 0 OA MCTの結果に及ぼす年齢の効果
- 著者
- 佐久田 博司 大吉 大輔 河原 宏俊 矢吹 太朗
- 出版者
- 日本図学会
- 雑誌
- 図学研究 (ISSN:03875512)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.Supplement1, pp.5-8, 2006 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 10
中高年齢の図形認知能力に関する調査は, 被験者の職業や環境による個体差が大きく, 統計的な考察のためには, 同一クラスに属する大学生などの群よりも多くの被験者が必要で, 個別の条件吟味が必要になると思われる.本研究は, 特に理工系の職業で同一部門に勤務している男女のエンジニアを対象に, MCTを実施し, 年齢別の考察を行った.勤務先などで実施するに当たっては, 通常の紙筆の試験が難しいため, モニタ上で行う試験を改良し, データベースを利用するなどによって, 試験環境の制約を極力除くこととした.また, 従来の紙筆によるMCT試験結果と比較するために, 大学生の男女による図学学習の前後の得点比較を行い, 本実験システムによる結果の妥当性を検証した.
1 0 0 0 日向郷土史料集
- 出版者
- 日向郷土史料集刊行会
- 巻号頁・発行日
- vol.第4巻, 1962
質の高い「チーム医療」の実現には、「多職種連携教育」が重要である。「根拠に基づいた医療」を実践するために「臨床研究リテラシー」は全ての医療者に必須の能力として求められている。「臨床研究リテラシー」の習得のためには、知識の学習だけでなく実際にデータを用いて臨床研究を実践することが非常に効果的であるが、データの入手、整備や構築が困難なことが少なくない。本研究は「多職種連携教育」の一環として情報通信技術を活用した「臨床研究リテラシー」修得のための実践研究である。「系統的レビュー」英文原著臨床研究論文出版活動を継続的に支援し、「臨床研究リテラシー」の普及と次世代の指導的人材育成を行う。
1 0 0 0 OA 日本のオペラント条件づけ研究事始め――関連年表――
- 著者
- 伊藤 正人
- 出版者
- 一般社団法人 日本行動分析学会
- 雑誌
- 行動分析学研究 (ISSN:09138013)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.156-161, 2019-02-10 (Released:2020-02-10)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
本特集は、2016年に開催された日本行動分析学会第34回年次大会(大阪市立大学)の公募企画シンポジウム「オペラント条件づけ研究事始め:スキナー研究室から送られた2組の実験装置」(企画 河嶋 孝・伊藤正人)に基づいている。このシンポジウムでは、2組の実験装置導入の経緯や実験装置をめぐる日米交流の一端を明らかにすることを目的としていた。このための基本資料として、当時の慶應義塾大学と東京大学の状況を知る関係者の方々から聞き取り調査を行い、関連年表を作成した。ここでは、関連年表(付表)の内容について紹介し、問題点を整理することにしたい。なお、年表作成にあたり、吉田俊郎、大山 正、大日向達子、故二木宏明の諸先生方から貴重な証言をいただいた。記して感謝申し上げる。年表は、慶應義塾大学と東京帝国大学および東京大学の文学部心理学研究室に関わる事項を中心に、国内外の出来事も記載してある。記載した事項は、戦前(1940年代)から現在(2010年代)までの両大学におけるオペラント条件づけ研究に関与した方々の活動や、オペラント条件づけ研究のインスツルメンテーションを総括する目的で行われた「実験的行動分析京都セミナー」(2012年~2015年)の開催などの活動にも広げてある。また、2組の実験装置の内、現存している慶應義塾大学のハト用実験装置、特に累積記録器についての考証と動作復元の試みが浅野ら(Asano & Lattal, 2012)によって行われており、実験箱についても坂上ら(Sakagami & Lattal, 2016)による論考が公刊されているので、これらについても記載してある。
1 0 0 0 OA 中国深圳市における公立幼稚園でのICT 導入の現状
- 著者
- 青木 一永
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.135-143, 2020-07-10 (Released:2020-07-10)
- 参考文献数
- 23
本稿は,直接的・具体的な体験が重視される幼児教育へのICT 導入の可能性を探るために視察した,深圳市というハイテク産業都市における公立幼稚園の状況を報告するものである.視察した幼稚園では,すべての子どもがウェアラブル端末を腕にはめ,さまざまなバイタルサインや位置情報が把握されていた.また,保育室にはスマートスピーカーや,カメラ付き大型モニター,AI 搭載の小型ロボット,プログラミング教育玩具が置かれ,子どもがそうしたICT を備えた環境に身を置き,かつ,教育として積極的に導入する実態があった.技術的課題や導入効果の検討の必要性等の課題もあるが,ICT 導入に関する先進的な取り組みは,今後の幼児教育分野へのICT導入について示唆を与えるものと言えるだろう.