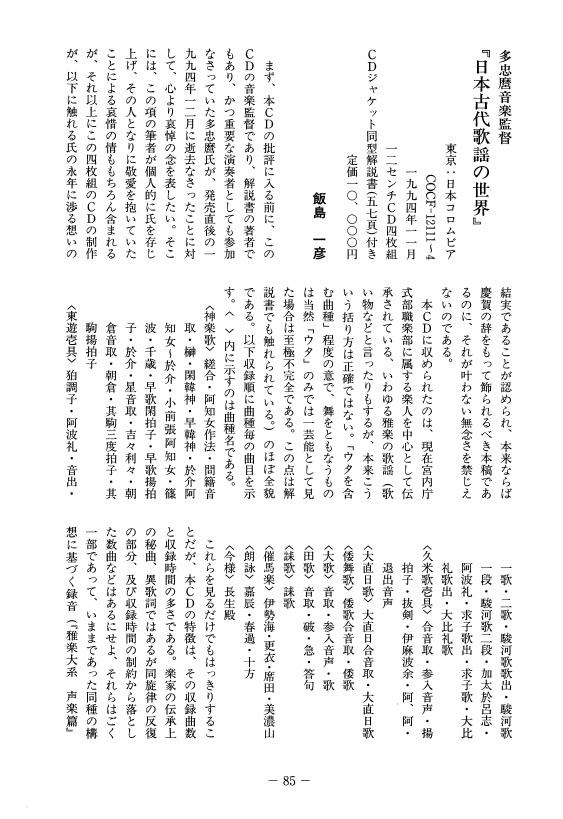1 0 0 0 OA 入院中の切迫早産妊婦からみた医療職者の言動
- 著者
- 江島 仁子
- 出版者
- 甲南女子大学
- 雑誌
- 甲南女子大学研究紀要. 看護学・リハビリテーション学編 = Studies in nursing and rehabilitation (ISSN:18825788)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.27-34, 2009-03-19
本研究の目的は、切迫早産により入院中の妊婦が、入院期間を通して変化していく自分の状況と医療職者の言動を妊婦がどのように感じとらえているのか、その時々の妊婦の思いを明らかにすることである。研究方法は切迫早産と診断され入院している妊婦3名を対象に参加観察法およびインタビューによりデータ収集を行い、内容の分析を行った。その結果①正期産近くになると妊婦の不安や不満は増加していくこと②妊婦は本音を言葉や態度に隠しているが看護者が察知してくれることを期待していること③看護者の日常のケアから喜びを得ていること、と医療職者に表出しなかった想いや医療職者への望みなどが明らかになった。以上より、異常から正常への移行期にある妊婦への関わり方、妊婦の思いを尊重した上で医療やケアを提供することの重要性が示唆された。
1 0 0 0 OA 『日本古代歌謡の世界』
- 著者
- 飯島 一彦
- 出版者
- The Society for Research in Asiatic Music (Toyo Ongaku Gakkai, TOG)
- 雑誌
- 東洋音楽研究 (ISSN:00393851)
- 巻号頁・発行日
- vol.1996, no.61, pp.85-88, 1996-08-20 (Released:2010-02-25)
1 0 0 0 OA コツの自覚に関するモルフォロギー的考察
- 著者
- 三上 肇
- 出版者
- 日本スポーツ運動学会
- 雑誌
- スポーツ運動学研究 (ISSN:24345636)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.13-26, 2003-11-18 (Released:2020-05-08)
- 参考文献数
- 31
Der Kunstgriffentsteht zugleich mit der Bewegungsurgestaltung vor der Wahrnehmung vom sich bewegenden Subjekt. Es hat in der Praxis des Sports und des Sportunterrichts sehr große Bedeutung, daß das sich bewegende Subjekt sich den Kunstgriff bewustmacht. Aber in Japan ist die exemplarische Forschung sehr wenig, wie der Kunstgriff entsteht und sich festigt. In dieserAbhandlung wurde dasBewußtmachung desKunstgriffsvom sich bewegenden Subjekt beim Bewegungslernen vom kinemorphologischen Standpunkt aus betrachtet.3 Episoden wurden dabai behandelt, in denen der Beobachter(Verfasser) die Bewegungsempfindung einer Lernenden(A) über Felge vw. Am Reck verfolgt hat. Frage und Antwort zwischen Verfasser und A wurden im Zusammenhang mit ihrer Bewegungsempfindung und iher Ausführung über Felge vw. beobachtet. Die Frage vom Lehrenden an den Lernenden ist beim Bewegungslernen unentbehrlich,um den Lernenden eine wichtige Bewegungsweise wahrnehmen zu lassen. Es wurde klar, daß diese Frage erstens über das “Idealbild” der Übung, zweitens über das “Selbsturteil über Jetzt-Versuch” der Übung, drittens über den “Bewegungsentwurf über Nächst-Versuch” der Übung gestellt werden soll. Die vom Lernenden wahrgenommene wichtige Bewegungsweise wird aber nicht sofort zu seinem Kunstgriff. Deshalb muß der Lehrende dem Lernenden diese Bewegungsweise als einen Kunstgriff bewußtmachen. Und zwar muß der Lehrende immer wieder den Lernenden nach seiner Bewegungsempfindung fragen, damit der Lernende sie in der selbst komponierenden Bewegungsmelodie feststellen kann.
1 0 0 0 技術&イノベーション 進化した自転車--快走に向けギアチェンジ
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1249, pp.88-90, 2004-07-05
最先端の自転車テクノロジーを競い合うレースの世界。価格競争が激しい市販車市場。全く違う2つのカテゴリーで、新しい「カタチ」の自転車が登場している。 MTB(マウンテンバイク)競技の業界で、最も注目されているのがホンダのダウンヒル競技車「RN01」。ホンダは昨年、このRN01で国際レース「UCIワールドカップ」への参加を表明、今年から本格参戦している。
1 0 0 0 IR ダンヌンツィオにとってのペトラルカ : 桂冠詩人モデルの模倣と超克
- 著者
- 内田 健一
- 出版者
- 京都産業大学
- 雑誌
- 京都産業大学論集. 人文科学系列 = Acta humanistica et scientifica Universitatis Sangio Kyotiensis (ISSN:02879727)
- 巻号頁・発行日
- no.52, pp.125-151, 2019-03
ダンヌンツィオにとってのペトラルカに関する唯一の本格的な先行研究として,ジベッリーニの『ダンヌンツィオとペトラルカ』(2006)が挙げられる。この網羅的な調査は,詩,小説,評論などのジャンル別で,必ずしも年代順ではない。一方,本稿は,ダンヌンツィオのペトラルカに対する態度を,若い頃から晩年に至るまで通時的に分析し,屈折した微妙な関係の推移を明らかにする。 ダンヌンツィオの最初の明確なペトラルカとの接点はセスティーナという詩形で,それを使って『結びのセスティーナ』(1886)や『深淵カラノ溜息』(1890)を作った。また『カンツォニエーレ』第22番セスティーナの一節を『ヴィッラ・キージ』(1889)で用い,恋人のバルバラ宛ての手紙にも書いた。詩人パスコリに関する評論(1892)では,セスティーナの音楽的な神秘を重視した。 その後,ペトラルカはカンツォーネという詩形と結びつけられる。ダンヌンツィオは『アテネ人への演説』(1899)でイタリア文学の代表としてペトラルカを挙げ,『沈黙の町たち』(1903)で文学の不滅性を讃える。しかし,1906年のジャコーザ追悼文では,カンツォーネなどの定型詩が時代遅れだと述べる。 1889年の『快楽』の詩論で,11音節詩行の名匠ペトラルカは,詩の創作のインスピレーションの源泉とされる。1900年の『夾竹桃』は,ペトラルカがインスピレーションを与えた最後の重要な作品である。そこでダンヌンツィオは,ダプネーを月桂樹ではなく夾竹桃に変身させ,ペトラルカにはない官能性を付け加えた。 自伝的な『快楽』に描かれた若いダンヌンツィオの桂冠詩人の栄光への夢は,約10年後の『火』の作品の虚構の中で実現されることとなる。『コーラ・ディ・リエンツォの生涯』(1905–6)で桂冠を授与されるペトラルカは,社会の平和をもたらす使者のようである。 しかし,詩形と同じように,ペトラルカは桂冠詩人モデルとしても古くなり,1913年の『コーラの生涯』の序文では,20世紀の自由で大胆な詩人に相応しい激しい人生観が表明される。第一次大戦中,平和主義的なペトラルカはほとんど言及されない。戦後に出版された『鉄槌の火花』(1924)で提示される新しい桂冠詩人は,謙虚さではなく高慢さ,人間性ではなく獣性を特色とするものだった。 ダンヌンツィオとペトラルカは,桂冠詩人という外面においては共通していたが,社会観や人間観という内面については違っていた。それゆえダンヌンツィオはペトラルカを強く意識しながらも,あまり多くを語ることをせず,屈折した微妙な関係が深まっていったのである。
- 著者
- 伊藤 智章
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.516-525, 2016 (Released:2017-03-29)
- 参考文献数
- 9
高等学校の地理教育におけるGISの普及低迷を打破するための手段として,タブレットコンピューターの活用を企図し,学校の現状に合わせた教材を開発した.沖縄への修学旅行の事前学習と現地研修において,現地の新聞記事とデジタル地図を組み合わせたアプリケーションソフトを作り,地図と記事との関連づけや,現地での研修を行うことにより,生徒に沖縄の歴史と市街地の変遷について深く理解させることができた.タブレットコンピューターによるGIS教材は,パソコンよりも操作が容易であり,かつインターネットへの常時接続を必要としないため,汎用性が高い.本教材を地理教育にGISを浸透させるための有効な手段として位置づけ,今後も普及を図っていきたい.
1 0 0 0 日本国内における児童向けセキュリティ教材の実態調査
- 著者
- 坪根 恵 長谷川 彩子 秋山 満昭 森 達哉
- 雑誌
- 研究報告セキュリティ心理学とトラスト(SPT) (ISSN:21888671)
- 巻号頁・発行日
- vol.2021-SPT-41, no.43, pp.1-8, 2021-02-22
学校教育におけるタブレット端末や PC 利用の普及に伴い,児童がパスワードを利用する機会は増加している.その一方で,国内では,パスワード教育に関する統一した指針がなく,小中学校で用いている教材や,教材内に記載されている項目やレベルは様々である.本研究は,国内で発行されている児童向けセキュリティ教材の実態調査を実施する.具体的には,教科書及び地方行政機関が独自に発行しているパスワード啓発資料を調査し,特にパスワード・プラクティスに関連する内容分析を行なった.調査の結果,(1) 教科書は出版社によって取り上げている項目は大きく異なり,パスワード・プラクティスをそもそも取り上げていない教科書もあれば,2021 年現在では既に推奨されていないプラクティスを未だ更新していない教科書も確認できた.(2) 児童向けパスワード啓発資料を作成している都道府県はわずか 7 県であり,各資料が取り上げている項目にも差がみられた.これらの結果は,教育機関が採用する教材によって内容に大きな差があること,およびその差が児童が得るセキュリティ知識の差につながることを示唆する.
1 0 0 0 OA 組み込みソフトウェア開発技術:2.組み込みソフトウェアの設計モデリング技術
組み込みソフトウェア開発では、1つの開発で複数の製品を開発するプロダクトラインの実現、ハードウェア要求を加味した効率的な実装、性能などの非機能要求の実現、高いレベルの品質確保、などが設計を進める上で課題となる。本稿では、これらの課題を解決するため過去どのような開発手法が提案されてきたか振り返るとともに、どのような問題が依然残っているのか見ていく。さらに、次世代の開発手法として、組み込みソフトウェアをモデル駆動で開発する方法をアスペクト指向や形式検証などの要素技術を取り込みながら説明する。
1 0 0 0 IR ロバート・メイプルソープ--美術教育のためのゲイ・スタディーズ
- 著者
- 福山 博光
- 出版者
- 北海道教育大学
- 雑誌
- 北海道教育大学紀要 教育科学編 (ISSN:13442554)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.109-118, 2004-02
1 0 0 0 「キラキラ駅名」はなぜ生まれるか (特集 駅の名は。)
1 0 0 0 OA 植物民俗学における植物をめぐる迷信
- 著者
- 植 朗子
- 出版者
- 京都府立大学
- 雑誌
- 京都府立大学学術報告. 人文 = The scientific reports of Kyoto Prefectural University. Humanities (ISSN:18841732)
- 巻号頁・発行日
- no.69, pp.67-75, 2017-12-25
1 0 0 0 グルコースによる細胞傷害性に対するノニジュースの効果の検討
- 著者
- 鷲崎 弘宜 萩本 順三 羽生田 栄一 関 満徳 小林 浩 丸山 久 井上 健 谷口 真也
- 雑誌
- 研究報告ソフトウェア工学(SE) (ISSN:21888825)
- 巻号頁・発行日
- vol.2021-SE-207, no.42, pp.1-7, 2021-02-22
従来のソフトウェア工学は主として開発の効率化や品質の向上に重点を置いて様々な手法やプラクティスを積み重ねてきている.しかしビジネスや社会上の価値創造が求められる Digital Transformation (DX) 時代においては,様々な人々に寄り添う考え方や,新たな社会を構想する捉え方をソフトウェアの企画や開発,運用の中心へと組み入れることの重要性を増すと考えられる.筆者らはこの問題意識のもと,従来からの工学的な知識体系やプラクティスに加えて,人々の意識や価値観,感情をソフトウェアの開発運用において扱うことの重要性を認識し,DX 時代のビジネスや持続可能な社会へ貢献するソフトウェア工学体系を考察する活動 Software Engineering for Business and Society (SE4BS) を 2019 年から進めてきている.そこでは特に,人の根源的な心的要素として捉えられる知・情・意に基づいたソフトウェア開発運用および周辺の考え方やプラクティスの整理体系化と,価値を軸として開発を進める価値駆動プロセスの例示を進めている.本稿では,価値を軸として DX 時代に必要な考え方を概観したうえで,それに応えようとする SE4B の成果の概要を説明する.さらに成果に対する評価や反応として,アンケート回答やワークショップ実施時の意見および大学教育の成果を紹介する.そのうえで,評価や反応を踏まえ,関連研究との関係も含めて将来の展望を説明する.
- 著者
- 芦原 亘
- 出版者
- 日本応用動物昆虫学会
- 雑誌
- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.207-211, 2004-08-25
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 2 7
ミカンキジラミの九州本土における越冬の可能性を明らかにするため、石垣島、沖縄本島、奄美大島のゲッキツから成虫を採集した。これらを沖縄県名護、鹿児島県枕崎、阿久根の気温変化を再現したインキュベータ内、並びに長崎県口之津の野外条件でゲッキツとウンシュウミカンを与えて飼育し、冬期の生存消長並びに越冬個体の産卵の有無を調査した。この結果、本種の成虫は九州本土、特に枕崎のような温度条件では越冬できる可能性が示された。
1 0 0 0 OA 児童虐待を受け児童養護施設に入所した子どもへのセルフケアを基盤とした生活援助
- 著者
- 井上 知美
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児看護学会
- 雑誌
- 日本小児看護学会誌 (ISSN:13449923)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.67-73, 2011-11-20 (Released:2017-03-27)
- 参考文献数
- 9
児童虐待が年々増加しており、被虐待児は日常的な生活習慣や行動が身についていないことが多く、彼らへの生活援助の必要性が指摘されている。しかし、被虐待児を対象に生活面での看護介入を行った先行研究は十分にない。そのため、本研究において児童虐待を受け児童養護施設に入所している小学校1・2年生の子ども3名にオレムのセルフケア不足看護理論のセルフケアの概念を用いた生活援助の看護介入を行い、生活習慣への影響を記述することを目的とした研究を行った。介入はThe Integrated Approach to Symptom Management(以下、IASMとする)を基に、IASMの「症状」を「生活習慣」と置き換え、本研究の介入枠組みとした。2事例に「清潔」、1事例に「活動と休息」の生活習慣に対して看護介入を行った。介入をとおして3事例が生活習慣に変化がみられたが、行動が習慣化に至るまでは介入の期間が十分ではなかった。
- 著者
- 大曽 基宣
- 出版者
- 名古屋女子大学
- 雑誌
- 名古屋女子大学紀要. 家政・自然編, 人文・社会編 = Journal of Nagoya Women's University. Home economics・natural science humanities・social science (ISSN:21857962)
- 巻号頁・発行日
- no.66, pp.43-53, 2020-03
朝食摂取や規則正しい睡眠習慣の確立は思春期の子どもにとって重要な課題である.本研究は,夕食の共食機会が少ない環境で生活する中学生の食・睡眠に関する行動変容に繋がりやすい行動目標を明らかにすることを目的とした.愛知県内M中学校全学年の生徒353人を対象に朝食内容と規則的な睡眠習慣に関する学習活動を行った.学習後に生徒が行動目標を設定し,1ヶ月後に目標達成状況を確認した.得られた結果を夕食の共食行動の有無別で分析した.その結果,目標達成者の割合は,食事量,食事バランス,野菜摂取,果物摂取の項目において,共食群の方が高かった.達成者割合が高かった目標は,共食群では果物摂取,野菜摂取,間食の量の順であったのに対し,非共食群では間食の量,睡眠習慣,乳・乳製品摂取の順であり,共食状況により達成に繋がりやすい目標に相違があった.本研究により,夕食の共食機会が少ない環境で生活する中学生の食・睡眠においては,乳・乳製品摂取,間食の量,睡眠習慣など,比較的生徒自身の心がけでコントロール可能な目標が達成されやすいことが示唆された.共食機会の少ない環境で生活する中学生の野菜・果物摂取量の増加に繋がる学習内容の検討が今後の課題である.
1 0 0 0 OA <総説>木材抽出成分と健康問題(1)
- 著者
- 佐藤 惺
- 出版者
- 京都大学木材研究所
- 雑誌
- 木材研究・資料 (ISSN:02857049)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.14-21, 1987-11-30
1 0 0 0 OA 長時間飢餓におけるオートファジー停止機構の解明
- 著者
- 鳥山 平三 Heizo TORIYAMA
- 雑誌
- 大阪樟蔭女子大学人間科学研究紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.125-142, 2009-01-31
我が国の臨床心理学界の第一人者で,長く斯界(しかい)の先頭に立って導いて来られた河合 隼雄先生が亡くなった。先生は 20 世紀最後の「老賢者」の一人と言ってもよい。筆者は,先生に特に 近い存在ではなかったが,それでも 40 年に及ぶ浅からぬ交流があった。その出会し、から,折々のエピ ソードを追想することにより,河合先生を偲ぶよすがとしたく思う。筆者の個人的な臨床心理学研鐙 の経験の織りなす,河合先生の周囲の人との交流の中に,河合先生を慕う女性と男性のさまざまな人 間模様が興味深く観察された。そこで,河合先生もよく触れておられたユング心理学の「元型」の中 でも,現代における「老賢者」の失墜(しつつしリ,そして,否定的な意味での「太母」の篭絡(ろう らく)について,見解を述べたく思う。時代は「老賢者」の英知から「太母」の呪縛へと移り行く現 代である。