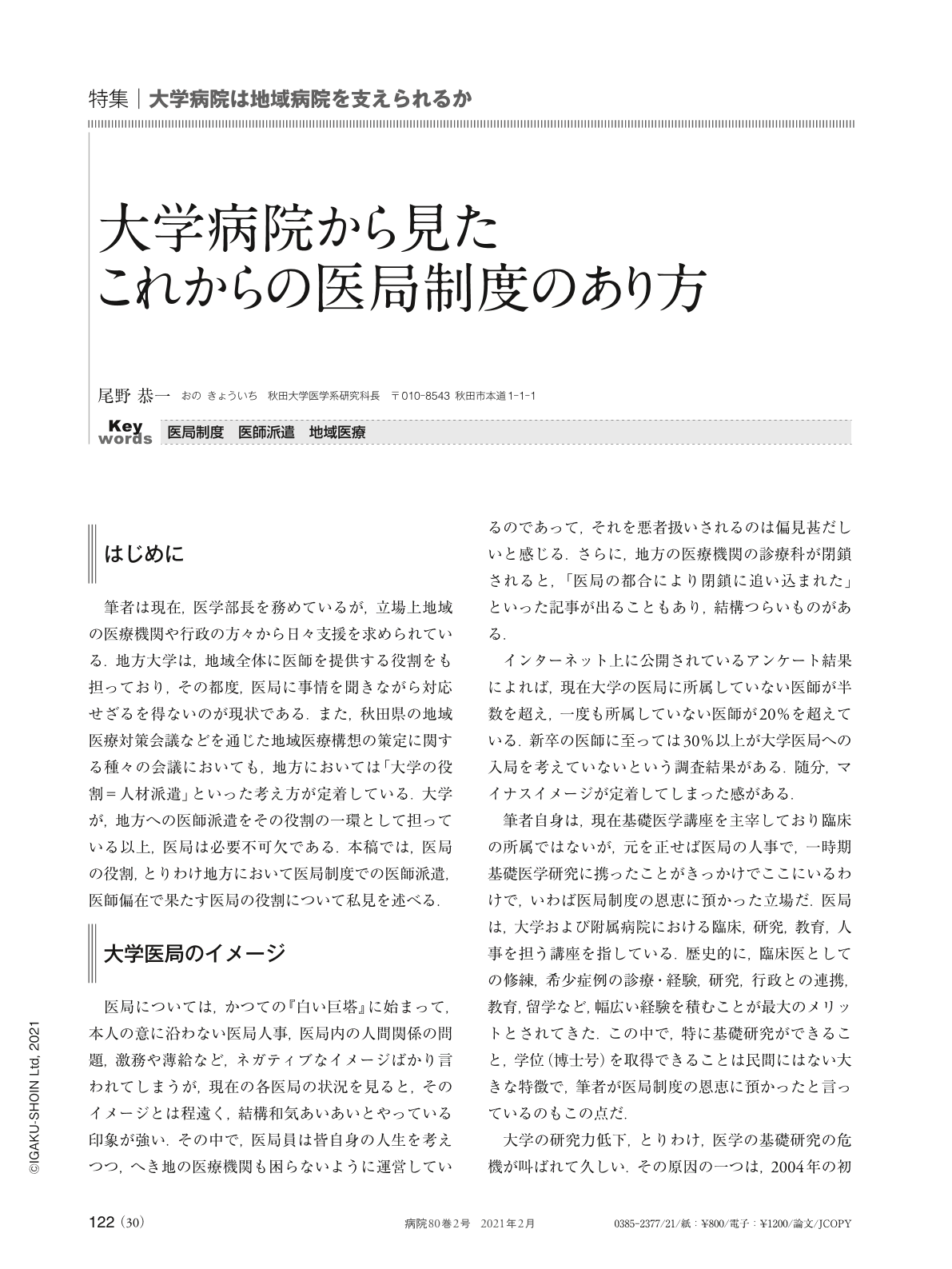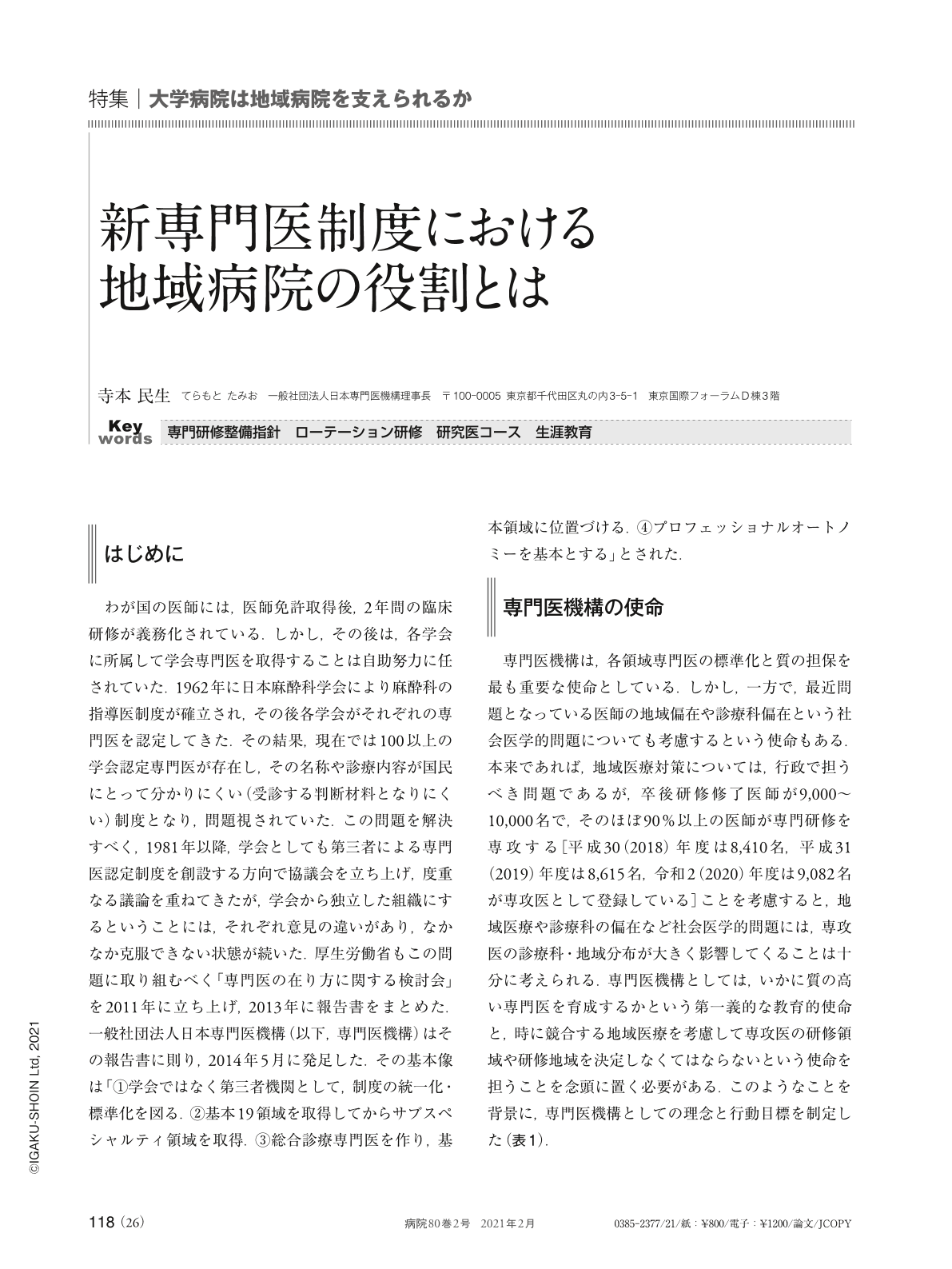1 0 0 0 OA 近世前期の大名貸証文
- 著者
- 渡邊 忠司
- 出版者
- 大阪経済大学日本経済史研究所
- 雑誌
- 経済史研究 (ISSN:1344803X)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.49-59, 1997-01-30 (Released:2019-03-01)
- 著者
- 丹後 享
- 出版者
- 大阪経済大学日本経済史研究所
- 雑誌
- 経済史研究 (ISSN:1344803X)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.60-65, 1997-01-30 (Released:2019-03-01)
1 0 0 0 PG067 やる気と負けん気と計画性(2)
- 著者
- 青木 多寿子 築田 祥子 高橋 智子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 日本教育心理学会総会発表論文集 (ISSN:21895538)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, 2009
1 0 0 0 『本城惣右衛門覚書』全文現代語訳
- 著者
- 白峰 旬
- 出版者
- 十六世紀史論叢刊行会
- 雑誌
- 十六世紀史論叢 (ISSN:21878609)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.27-50, 2020-03
1 0 0 0 スタール夫人と世論
- 著者
- 武田 千夏
- 出版者
- 大妻女子大学人間生活文化研究所
- 雑誌
- 人間生活文化研究
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, no.27, pp.316-318, 2017
<p> スイスのローザンヌ大学のビアンカマリア・フォンタナ女史は,スタール夫人は政治思想家として,父親のジャック・ネッケルの世論の考え方をそのまま踏襲したと主張した.本報告では,両者の相違を重視する.スタール夫人はフランスの近世から発達したサロンの伝統を踏襲して,女性を世論の中心に添えた点で,財務大臣の立場を反映した父親の世論とは大きく異なる.</p>
1 0 0 0 OA デイサービス利用高齢者における異なる立ち上がりテストと身体機能との関連
- 著者
- 村田 伸 合田 明生 中野 英樹 安井 実紅 高屋 真奈 玻名城 愛香 上城 憲司
- 出版者
- 日本ヘルスプロモーション理学療法学会
- 雑誌
- ヘルスプロモーション理学療法研究 (ISSN:21863741)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.67-71, 2020-07-22 (Released:2020-08-04)
- 参考文献数
- 23
本研究の目的は,デイサービスを利用している34名の女性高齢者を対象に,30秒椅子立ち上がりテスト(30-sec Chair Stand test; CS-30)と虚弱高齢者用10秒椅子立ち上がりテスト(10-sec Chair Stand test for Frail Elderly; Frail CS-10)を併せて行い,大腿四頭筋筋力とともに各種身体機能評価の測定値との相関分析から,デイサービス事業所で実施しやすい下肢機能評価法を検討することである。相関分析の結果,大腿四頭筋筋力と有意な相関が認められたのは握力のみであったが,CS-30とFrail CS-10はともに握力・最速歩行時間・Timed Up Go Test·Trail making test Part A との間に有意な相関が認められた。さらに,Frail CS-10のみ通常歩行時間とも有意な相関が認められた。これらの結果から,特別な機器を必要とせず,簡便に短時間で実施できるFrail CS-10は,デイサービス利用高齢者の歩行能力や動的バランスを反映する下肢機能評価法であることが示唆された。
- 著者
- 芳村 圭 Kei Yoshimura
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会誌 = Journal of Japanese Society for Artificial Intelligence (ISSN:09128085)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.6, pp.724-726, 2006-11-01
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 大学病院から見たこれからの医局制度のあり方
■はじめに 筆者は現在,医学部長を務めているが,立場上地域の医療機関や行政の方々から日々支援を求められている.地方大学は,地域全体に医師を提供する役割をも担っており,その都度,医局に事情を聞きながら対応せざるを得ないのが現状である.また,秋田県の地域医療対策会議などを通じた地域医療構想の策定に関する種々の会議においても,地方においては「大学の役割=人材派遣」といった考え方が定着している.大学が,地方への医師派遣をその役割の一環として担っている以上,医局は必要不可欠である.本稿では,医局の役割,とりわけ地方において医局制度での医師派遣,医師偏在で果たす医局の役割について私見を述べる.
1 0 0 0 新専門医制度における地域病院の役割とは
■はじめに わが国の医師には,医師免許取得後,2年間の臨床研修が義務化されている.しかし,その後は,各学会に所属して学会専門医を取得することは自助努力に任されていた.1962年に日本麻酔科学会により麻酔科の指導医制度が確立され,その後各学会がそれぞれの専門医を認定してきた.その結果,現在では100以上の学会認定専門医が存在し,その名称や診療内容が国民にとって分かりにくい(受診する判断材料となりにくい)制度となり,問題視されていた.この問題を解決すべく,1981年以降,学会としても第三者による専門医認定制度を創設する方向で協議会を立ち上げ,度重なる議論を重ねてきたが,学会から独立した組織にするということには,それぞれ意見の違いがあり,なかなか克服できない状態が続いた.厚生労働省もこの問題に取り組むべく「専門医の在り方に関する検討会」を2011年に立ち上げ,2013年に報告書をまとめた.一般社団法人日本専門医機構(以下,専門医機構)はその報告書に則り,2014年5月に発足した.その基本像は「①学会ではなく第三者機関として,制度の統一化・標準化を図る.②基本19領域を取得してからサブスペシャルティ領域を取得.③総合診療専門医を作り,基本領域に位置づける.④プロフェッショナルオートノミーを基本とする」とされた.
1 0 0 0 OA ナス幼植物に対する二価鉄葉面散布が葉の鉄およびカルシウムの含有率に及ぼす影響
- 著者
- 樋口 恭子 石川 哲也 庄司 崇 山本 祐司 田所 忠弘 三輪 睿太郎
- 出版者
- 日本食生活学会
- 雑誌
- 日本食生活学会誌 (ISSN:13469770)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.156-158, 2010-09-30 (Released:2010-10-27)
- 参考文献数
- 10
Recently, new types of ferrous fertilizers that release soluble Fe have been developed for use in Fe-sufficient soils. We applied ferrous chloride (FeCl2) to leaves of young eggplant (Solanum melongena) grown in Fe-sufficient soil. Foliar application of FeCl2 brought about an increase in the number of axillary shoots and fresh weight of whole shoot. Moreover, concentrations of Ca and Mn of leaves were increased though the treatment solution did not contain Ca or Mn. Foliar application of FeCl2 could increase not only Fe concentration but also Ca concentration in leaves of leaf vegetables.
1 0 0 0 OA 医療ビッグデータにおける自発報告データベースの位置づけと利用可能性
- 著者
- 酒井 隆全
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.141, no.2, pp.165-168, 2021-02-01 (Released:2021-02-01)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 3
In recent years, a variety of medical information has been digitized, and hence, various medical big data have become available. Spontaneous reporting databases are a part of the medical big data. In Japan, the Pharmaceuticals and Medical Devices Agency has developed the “Japanese Adverse Drug Event Report (JADER) database” which has been available since 2012. Thus, everyone can publish safety signal information based on the results of disproportionality analysis using the spontaneous reporting database. Since the release of JADER, many researchers and healthcare professionals are interested in it, and many reports have been prepared using JADER. Although we tend to focus on the fact that it is a publicly available database with many cases, it also has various limitations such as lack of the denominator information, under-reporting, and reporting biases. Detected signals do not necessarily imply a causal relationship between the drug and adverse event. In the “Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Module IX by European Medicines Agency”, signal detection is the first step in the signal management process. Signal detection alone does not complete pharmacovigilance activities. It is important to understand that spontaneous reporting databases are not only for researchers but also for those who are considering to apply them to clinical work by referring to research using these databases. In this symposium review, I will discuss the role and applicability of spontaneous reporting databases in medical big data.
1 0 0 0 OA 看護学実習における評価尺度に関する文献検討
- 著者
- 小松﨑 記妃子 山田 真実子 福宮 智子 佐藤 陽子 山﨑 あや 渡辺 純子 福地本 晴美
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.6, pp.499-507, 2020 (Released:2021-01-28)
- 参考文献数
- 7
看護学生による臨地実習に関する評価尺度の動向を明らかにする.本研究は,臨地実習での教授者の教育能力および学生の看護実践能力の両側面の能力を評価するための資料とする.医中誌Web Ver. 5を用いて,検索対象年は2005年1月〜2015年9月,検索式は「臨地実習」and「看護学生」and「評価」とし原著論文に限定した.その中から看護学実習に関して尺度を用いた評価を行っている文献(独自質問紙のみを使用した文献は除外)を分析対象とした.検索の結果,1,132件が抽出された.このうち本研究の条件に該当する文献は73文献あった.使用されている評価尺度は55種類あり,1文献に対し1〜11の尺度を用いるなど多岐にわたっていた.評価者は,教員,指導者,学生の3つに分類でき,評価対象は,教員,指導者,学生,実習過程(実習全般),実習環境の5種類に分類できた.人を評価対象とした文献のなかで,教員を評価した文献は4件で最も少なく全て2011年以降に確認された.指導者を評価した文献は20件,学生を評価した文献は45件あり,2005年から確認できた.教員を評価対象とした文献のうち,その評価者は,学生3件,教員(自己評価)1件であり,評価尺度は,前者は全て日本語版Effective Clinical Teaching Behaviors(以下ECTB),後者は教授活動自己評価尺度―看護学実習用―が用いられていた.指導者を評価対象とした文献における評価者は,学生14件,指導者(自己評価)6件であった.評価尺度は,前者のうち11件がECTB,3件が授業過程評価スケール―看護学実習用―であり,後者は全てECTBが用いられていた.近年の看護学実習における教育評価に関する研究では,教授者の教育実践能力を評価する尺度には,授業過程評価スケール―看護学実習用―やECTBの共通性が確認されたが,教員を評価対象とした研究は僅かであった.また,評価の時期は,基礎実習後と領域実習の前後などで2時点から3時点で実施されており,基礎看護実習から全ての実習終了後までなど一連の過程を通じた学生の評価に関する研究は見当たらなかった.看護実践能力における要素別の評価尺度を組み合わせて実習を評価していることが明らかになった.
1 0 0 0 OA ボドメル博物館所蔵プルースト新資料に見る「スワン家の方へ」推敲過程
- 著者
- 吉田 城
- 出版者
- 日本フランス語フランス文学会
- 雑誌
- フランス語フランス文学研究 (ISSN:04254929)
- 巻号頁・発行日
- vol.85.86, pp.273-291, 2005-03-01 (Released:2017-08-11)
Notre objectif, dans le present article, est de jeter quelques lumieres sur la genese de Du cote de chez Swann de Marcel Proust, en nous appuyant sur les premieres epreuves corrigees, dont l'existence n'a ete devouverte qu'en 2002. Il s'agit d'un jeu de placards etablis par l'editeur Grasset en 1913, sur lequel Proust a apporte de nombreuses corrections et additions. Chose curieuse, il n'y a guere de chercheurs proustiens qui se soient penches sur ce probleme. Une etude des procedes de correcton dans ces placards nous permettra de combler cette lacune concernant la genese de la Recherche. Voici le sort qu'a subi ce document preciex: apres la mort de Marcel, Robert Proust et sa femme Marthe l'ont conserve avec d'autres dossirs manuscrits de leur frere. Quand Robert est mort en 1935, Marthe l'aurait vendu au collectionneur Jacques Guerin, celui qui vendra a la Bibliotheque Nationale les treize Cahiers de brouillon (63 a 75). On a retrouve ces epreuves dans la collection de Guerin quand celui-ci a decede le 6 aout 2000 a l'ate de quatre-vingt-dix-huit ans. Le 6 juillet 2002, elles ont ete mises aux enchers chez Christie's a Londres. C'est le Musee Bodmer a Geneve, appele a cette epoque Bibliotheca Bodmeriana, qui les a acquises. Ces placards se composent de 52 feuilles de grand format, contenent chacune 8 colonnes imprimees et non paginees. La premiere feuille porte le timbre du ≪31 mars 1913≫, date de composition chez l'imprimeur Charles Colin a Mayenne. Sur la derniere feuille (l'avant-derniere page d'≪Un Amour de Swann≫) est appose le cachet du ≪14 mai 1913≫. Nous choisissons quatre episodes dont l'etat de correction presente un interet particulier : l'incipit de la Recherche, la lanterne magique, M. Vinteuil et sa fille et enfin l'ouverture d'≪Un Amour de Swann≫. L'examen de ces textes corriges nous devoile que Proust a continue avec acharnement et jusqu'au dernier moment le travail de suppression et d'ajout de facon a donner a ces episodes un sens profond qui puisse annoncer et preparer la suite du roman. Loin d'etre un simple remainement lexical, thematique ou stylistique, la correction proustienne nous rappelle ici comme ailleurs l'importance de la transformation textuelle, voire structurelle, qui ne cesse de s'effectuer au-dela de la premiere compositon de l'imprimeur.
1 0 0 0 IR 怒りと道徳的違反の知覚-危害の正当性と義憤および私憤に対するその影響-
- 著者
- 上原 俊介 中川 知宏 田村 達 小形 佳祐 齋藤 五大
- 出版者
- 東北大学文学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 (ISSN:03854841)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, pp.1AM-022-1AM-022, 2013
1 0 0 0 IR 国家公務員の政治的行為規制に関する人事院規則委任条項・罰則適用条項挿入の経緯と趣旨(1)
- 著者
- 岡田 正則
- 出版者
- 早稲田大学法学会
- 雑誌
- 早稲田法学 (ISSN:03890546)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.1, pp.147-163, 2008
- 著者
- 野崎 律子 掛本 知里 加藤 登紀子 有吉 浩美
- 出版者
- 公益社団法人 日本産業衛生学会
- 雑誌
- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.Special, pp.550, 2005 (Released:2017-10-05)
- 著者
- 和田 英敏 加藤 昌一 本村 浩之
- 出版者
- 国立大学法人 鹿児島大学総合研究博物館
- 雑誌
- Ichthy, Natural History of Fishes of Japan
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.1-4, 2020
1 0 0 0 デルフィニウムF1品種'アルト'の育成と特性
- 著者
- 中村 広 中村 薫 郡司 定雄
- 出版者
- 宮崎県総合農業試験場
- 雑誌
- 宮崎県総合農業試験場研究報告 (ISSN:03888339)
- 巻号頁・発行日
- no.39, pp.1-11, 2004-03
宮崎県総合農業試験場花き部育種科で育成したデルフィニウム新品種'アルト'の主な特性は下記のとおりである。1.開花型は'レグルス'より遅く,'ブルーバード'と同程度の中生である。2.草型は直立型で草丈は高である。3.花序の長さは長,幅は中。花は八重咲きで,咲き方は普通咲き,小花数の密度は中である。4.最外層がく片,最内層がく片の主要な色はともに鮮青味紫色(JHSカラーチャート8306)である。花弁の色は白である。
- 著者
- Leonard Hayflick
- 出版者
- The Keio Journal of Medicine
- 雑誌
- The Keio Journal of Medicine (ISSN:00229717)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.3, pp.174-182, 1998 (Released:2009-03-27)
- 参考文献数
- 46
- 被引用文献数
- 24 40
During the first half of this century it was believed that because cultured normal cells were immortal, aging must be caused by extracellular events. Thirty-five years ago we overthrough this dogma when we discovered that normal cells do have a limited capacity to divide and that aging occurs intracellularly. We also observed that only cancer cells are immortal. Normal cells are mortal because telomeres shorten at each division. Immortal cancer cells express the enzyme telomerase that prevents shortening. Recently, it was discovered that the telomerase gene when inserted into normal cells immortalizes them. There appears to be a relationship between these findings and aging, longevity determination and cancer. After performing the miracles that take us from conception to birth, and then to sexual maturation and adulthood, natural selection was unable to favor the development of a more elementary mechanism that would simply maintain those earlier miracles forever. This failure is called aging. Because few feral animals age, evolution could not have favored animals exhibiting age changes. Natural selection favors animals that are most likely to become reproductively successful by developing greater survival skills and reserve capacity in vital systems to better survive predation, dis-ease, accidents and environmental extremes. Natural selection diminishes after sexual maturation because the species will not benefit from members favored for greater development of physiological reserve. A species betters its chances of survival by investing its resources and energy in increasing opportunities for reproductive success rather than on post-reproductive longevity. The level of phy-siological reserve remaining after reproductive maturity determines potential longevity and evolves incidental to the selection process that acts on earlier developmental events. Physiological reserve does not renew at the same rate that it incurs losses because molecular disorder increases. These age changes increase vulnerability to predation, accidents or disease.
- 著者
- 木下 敏之
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1321, pp.137-140, 2005-12-19
改革をしっかり実行してきたのに、「抵抗勢力」たちが手を組んで組織票を固めたことで、選挙で負けてしまった。私がここで申し上げている抵抗勢力とは、全日本自治団体労働組合(自治労)を中心とした社民党や共産党の人たち、そして、小泉純一郎首相率いる今の自民党のことです。両者はここ佐賀市で手を結びました。