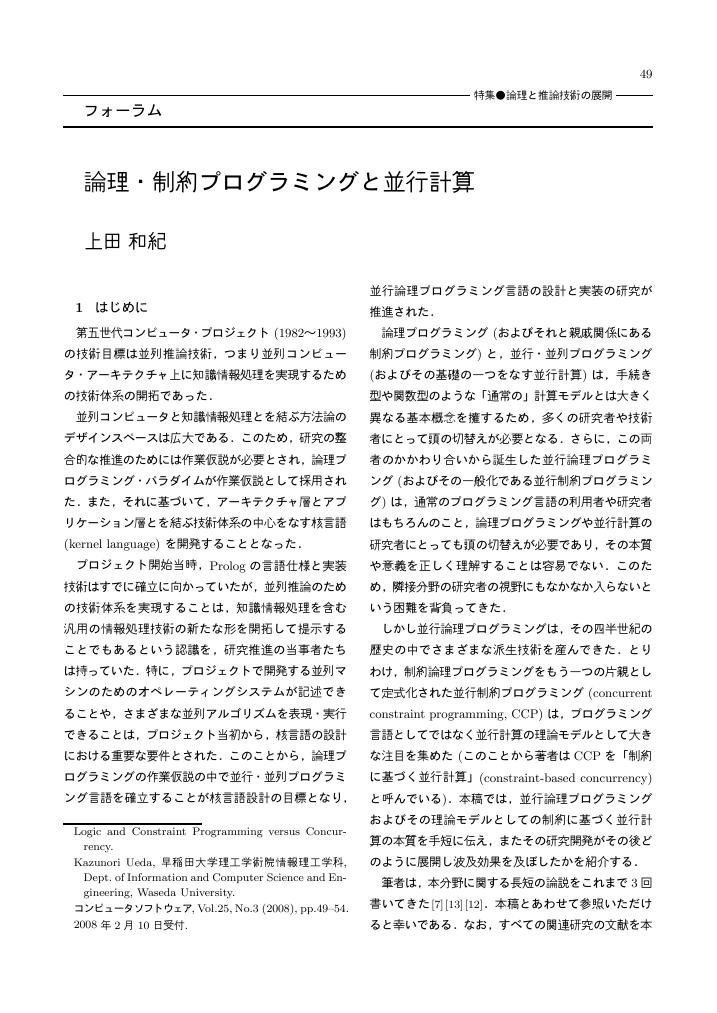- 著者
- 伊藤 淳史 冨井 眞
- 出版者
- 考古学研究会
- 雑誌
- 考古学研究 (ISSN:03869148)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.図巻頭1p,126-128, 2019
1 0 0 0 OA 論理・制約プログラミングと並行計算
- 著者
- 上田 和紀
- 出版者
- 日本ソフトウェア科学会
- 雑誌
- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.3_49-3_54, 2008-07-25 (Released:2008-09-30)
1 0 0 0 上野国における荘園形成 : 鳥羽院政期の御願寺領荘園を中心に
- 著者
- 久保田 順一
- 出版者
- 群馬歴史民俗研究会
- 雑誌
- 群馬歴史民俗 (ISSN:02854090)
- 巻号頁・発行日
- no.35, pp.44-62, 2014-05
1 0 0 0 OA 感覚と知能を備えた分子ロボットの創成
- 著者
- 萩谷 昌己
- 雑誌
- 新学術領域研究(研究領域提案型)
- 巻号頁・発行日
- 2012-06-28
1 0 0 0 中世民衆史における「癩者」と「不具」の問題--下剋上の文化・再考
- 著者
- 横井 清
- 出版者
- 花園大学文学部
- 雑誌
- 花園大学研究紀要 (ISSN:02882620)
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.79-118, 1974-03
1 0 0 0 OA 特異値計算アルゴリズムの性能評価のための条件数の大きい行列作成法
- 著者
- 髙田 雅美 木村 欣司 中村 佳正
- 雑誌
- 研究報告数理モデル化と問題解決(MPS)
- 巻号頁・発行日
- vol.2010-MPS-79, no.1, pp.1-6, 2010-07-05
本論文では,特異値分解を評価するために,条件数の大きなテスト行列の作成法を提案する.我々が対象とする条件数は,以下の 2 種類である.1 つ目は,連立 1 次方程式を解く際の困難さを 1 つの指標とする.2 つ目は,特異値の近接度を用いる.1 つ目の提案作成法では,2 重対角行列のみならず,密行列を作成することも可能である.一方,2 つ目の提案作成法では,2 重対角行列のみが作成可能である.提案する 2 種類の作成法の目的は異なるため,それぞれに意義がある.これらの作成法を用いて,LAPACK 3.2.1 に含まれているいくつかの特異値分解アルゴリズムを評価する.
- 著者
- 本田 雅規 小原 孝之 住田 吉慶
- 出版者
- メディカルレビュー社
- 雑誌
- 再生医療 (ISSN:13477919)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.85-89,7〜8, 2005-02
1 0 0 0 OA 江戸期の兵法歌に関する一考察
- 著者
- 今村 嘉雄
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.1-9, 1976-07-31 (Released:2012-11-27)
1 0 0 0 OA 手術前日までダパグリフロジンが投与され周術期の代謝循環管理に難渋した1例
- 著者
- 鴻池 利枝 大塚 将秀 出井 真史
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.3, pp.193-194, 2019-05-01 (Released:2019-05-01)
- 参考文献数
- 10
1 0 0 0 OA 手延素麺製造中の脂質ならびにタンパク質の変化と麺の性状変化について
- 著者
- 新原 立子 西田 好伸 米沢 大造 桜井 芳人
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.7, pp.423-433, 1973 (Released:2008-11-21)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 3 2
(1) 製造中における手延素麺の水分含量は,梅雨期の“厄”において上昇して, 15%以上となった. (2) エーテルおよび水飽和ブタノールで抽出される脂質の量は,ともに貯蔵中に減少した. (3) 過酸化物価,カルボニル価は製麺時に上昇し,貯蔵中は15カ月間あまり変化せず,ヨウ素価,リノール酸の比率がやや増加する傾向がみられた.このように,素麺の脂質は酸化に対して安定であった.一方厄中の変化として,酸価の上昇がみられた. (4) タンパク質の溶解性はほとんど変化せず, 2回目の厄を越えた時点でやや減少した.アンモニア,アマイド窒素もほとんど変化はみられなかったが, 1回目の厄で10% TCA可溶の窒素量の増加がみられた.そして遊離のアミノ酸も, 1回目の厄で増加した.しかし油の酸化の始まる2回目の厄には,遊離のアミノ酸の減少がみられた.総アミノ酸には貯蔵中顕著な変化はみられなかったが, 2回目の厄後すべてのアミノ酸がやや減少した.また2回目の厄後,グルテンのデンプンゲル電気泳動図に変化が認められた. (5) 素麺からとれる湿グルテンの猛状が貯蔵中に変化し,生麺およびゆで麺の吸水率が低下した. (6) テクスチュロメーターによる測定では,ゆで麺のかたさが1回目の厄を越すことによって増加した.一方,凝集性は2回目の厄を越して初めて有意差のある低下が認められた.また粉末のファリノグラムも,貯蔵期間とともに変化した. ゆで麺の顕微鏡観察では,厄を越えた素麺はデンプン粒の膨潤が抑制されていることが観察された.
- 著者
- 島村 恭則
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, pp.763-790, 2001-03
これまでの民俗学において,〈在日朝鮮人〉についての調査研究が行なわれたことは皆無であった。この要因は,民俗学(日本民俗学)が,その研究対象を,少なくとも日本列島上をフィールドとする場合には〈日本国民〉〈日本人〉であるとして,その自明性を疑わなかったところにある。そして,その背景には,日本民俗学が,国民国家イデオロギーと密接な関係を持っていたという経緯が存在していると考えられる。しかし,近代国民国家形成と関わる日本民俗学のイデオロギー性が明らかにされ,また批判されている今日,民俗学がその対象を〈日本国民〉〈日本人〉に限定し,それ以外の,〈在日朝鮮人〉をはじめとするさまざまな人々を研究対象から除外する論理的な根拠は存在しない。本稿では,このことを前提とした上で,民俗学の立場から,〈在日朝鮮人〉の生活文化について,これまで他の学問分野においても扱われることの少なかった事象を中心に,民俗誌的記述を試みた。ここで検討した生活文化は,いずれも現代日本社会におけるピジン・クレオール文化として展開されてきたものであり,また〈在日朝鮮人〉が日本社会で生活してゆくための工夫が随所に凝らされたものとなっていた。この場合,その工夫とは,マイノリティにおける「生きていく方法」「生存の技法」といいうるものである。さらにまた,ここで記述した生活文化は,マジョリティとしての国民文化との関係性を有しながらも,それに完全に同化しているわけではなく,相対的な自律性をもって展開され,かつ日本列島上に確実に根をおろしたものとなっていた。本稿は,多文化主義による民俗学研究の必要性を,こうした具体的生活文化の記述を通して主張しようとしたものである。
1 0 0 0 OA 小学生の子を持つ保護者の世帯収入別にみた食生活状況に関する研究
- 著者
- 駿藤 晶子 山本 妙子 吉岡 有紀子 硲野 佐也香 石田 裕美 村山 伸子
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.4, pp.143-151, 2020-08-01 (Released:2020-09-26)
- 参考文献数
- 17
【目的】本研究は,日本において,世帯収入と小学生の子を持つ保護者の食料品へのアクセスも含めた食生活状況との関連を明らかにすることを目的とした。【方法】東日本4県の4地域(6市村)の19小学校に在籍する小学5年生(10~11歳)の保護者のうち,同意が得られた1,231名を対象に質問紙調査を実施し,そのうち920名を解析の対象者とした。世帯収入が貧困基準以下の群(低収入群)とそれ以外の群(低収入以外群)に分け,朝食を食べる頻度,家庭での食品の使用頻度,子どもの食事に関する項目,食料品の入手や買い物に関する項目,時間的なゆとりの実感,地域での子育てに関する項目と世帯収入との関連について,χ2 検定またはFisherの正確確率検定を用いて検討し,その後,各項目を目的変数とし,説明変数は世帯収入として二項ロジスティック回帰分析を行った。【結果】多変量解析の結果,低収入群は低収入以外群に比べて,子どもの健康維持に適した食事の量とバランスがわからないといった食知識がない者,経済的な理由もしくは買い物が不便であるという理由で生鮮食品や必要とする食物の入手が困難になる者,時間的なゆとりを感じていない者が多かった。【結論】小学生の子を持つ保護者は,世帯収入が貧困基準以下であると,子どもの健康維持に関する食知識がない者,経済的な理由もしくは買い物が不便なために食料品の入手が困難である者,時間的ゆとり感がない者が多いことが明らかになった。
1 0 0 0 OA フィリピン共和国の小学校における栄養バランスをテーマとした栄養の授業実践と経過・影響評価
- 著者
- 湯面(山本) 百希奈 是兼 有葵 高木 絢加 新屋 奈美 落合 なるみ 能瀬 陽子 永井 成美
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.4, pp.152-162, 2020-08-01 (Released:2020-09-26)
- 参考文献数
- 13
【目的】フィリピン共和国では,2016年の教育改革でカリキュラムに健康(栄養の内容を含む)が追加されたが,指導案や教材に乏しく栄養の授業は十分に行われていない。そこで同国の栄養の授業推進に資することを目的として,日本の栄養教諭課程学生3名が中心となり同国内関係者と協力して現地小学校で栄養の授業を実践した。【方法】PDCAサイクルに基づき実施した。①Plan:アセスメントで文献調査とフィリピン共和国ボホール州タグビララン市現地調査を行い,栄養課題抽出後「栄養バランスの是正」を優先課題に決定し,学習指導案と教材を英語で作成した。関係者と現地で協議し修正とスタッフ研修を行った。②Do:同市立A小学校2年生1クラス(32名)で,3G FOODS(3食品群)でバランスを学ぶ栄養の授業を単回実施した。③Check(経過・影響評価):授業終了時に,児童の授業満足度と理解度を質問紙とワークシートで調べた。同時に,授業参観者(現地教師・JICA隊員等)による授業評価(現地のカリキュラムや児童への適合度)を実施した。④Act:評価結果を関係者と共有した。【結果】児童の授業満足度(楽しかった)は100%,理解度(ワークシートの問題への正答率)は91%と高かった。授業参観者による授業評価では,授業,内容ともに同国の教育カリキュラムや児童の理解度等のレベルに適していると評価され,今後活用したいとの意見も得られた。【結論】結果より,フィリピン共和国の栄養の授業推進につながる実践ができたと考えられる。
1 0 0 0 OA 中学生を対象とした給食時間等の短時間教育における牛乳飲用に対する知識理解と意識変容の検討
- 著者
- 布川 美穂 佐藤 靖子
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.4, pp.163-170, 2020-08-01 (Released:2020-09-26)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
【目的】中学生を対象に牛乳に関する短時間教育を実施し,知識理解と牛乳飲用意志向上を含む意識変容を検討した。【方法】2017年8月から9月,中学1年生561名を対象に学校給食の牛乳に関する3分間の短時間教育(以降 3分教育)を実施した。3分教育は給食の時間等に誰でも簡単にできる口頭伝授の方法を用いた。その後,自記式質問紙にて学校給食牛乳に関する知識と意識調査を行い,7項目の質問項目では男女別のデータをχ2 検定,自由記述ではKJ法を用いて検討した。【結果】3分教育を受け,男子89.3%,女子93.5%の生徒が学校給食の牛乳に対して新しい知識を得ることができ,男子90.4%,女子93.8%の生徒が今後の教育を希望すると回答した。今後も毎日飲用したいと回答した生徒は,男子85.6%,女子73.5%であった。【結論】中学1年生に実施した3分教育においては,給食の牛乳に対する新たな知識を伝えることが可能であったが,今後も毎日飲用したいという意志向上の効果は把握できなかった。しかし,3分教育の継続希望が多かった結果より,継続的な教育の実施と,牛乳飲用意志向上を含む意識変容との関係性を検討していく必要が考えられた。
1 0 0 0 OA 研究発表 『井筒』解釈の多義性 ―婚姻の形態から―
- 著者
- Marginean Ruxandra
- 出版者
- 国文学研究資料館
- 雑誌
- 国際日本文学研究集会会議録 = PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON JAPANESE LITERATURE (ISSN:03877280)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.33-52, 1999-10-01
It is usual practice in no studies to analyse no scripts as texts, from a literary point of view. In this paper I shall take Izutsu as an example and analyze its interpretations from the point of view of what is usually considered the social background to literature.To put it differently, I intend to reconsider the way interpretation is usually thought to reveal the "universal" meaning of a text―a meaning that would go beyond the interpreters' differences of gender, class and living epoch.First, I would like to have a look at interpretations of Izutsu in contemporary society. As opinion polls show, when Izutsu is performed at Nogakudo, the audience evaluates the leading character's attitude in various ways. This is related, I think, with the diversification of opinion towards the marriage system in nowadays Japan.I would like then to question the existence of multiple interpretations of Izutsu in medieval society. The story of Izutsu is based on Kamakura period commentaries on Ise Monogatari (as the well-known article "Yokyoku to Ise Monogatari no Hiden" by Ito Masayoshi has shown). Researchers do not agree whether the 24th dan of Ise Monogatari and its medieval commentaries are inserted or not in the text of Izutsu. If one takes into account medieval poetry treatises (such as Seiasho) about honkadori, one can say, I think, that the 24th dan of Ise Monogatari is not alluded to in Izutsu.I would like to consider the interpretation of the 24th dan of Ise Monogatari as seen in medieval commentaries, as well as its not being included in Izutsu from the point of view of the medieval marriage system. According to Tabata Yasuko, aristocrats (kuge) and warriors (buke) had rather different marriage systems. Would not this fact have had an influence on the way Izutsu was interpreted in the middle ages?The above analysis touches on the larger problem of the power-relationships that exist behind what is usually considered to be a unique "correct" interpretation of a text/play.
1 0 0 0 OA 謡曲『井筒』の本説考
- 著者
- 金 忠永 Kim Choong Young
- 出版者
- 筑波大学比較・理論文学会
- 雑誌
- 文学研究論集 (ISSN:09158944)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.115(46)-146(15), 1992-03-15
多くの海産養殖魚種はDHA合成に関わる脂肪酸不飽和化酵素の活性を欠損しており、健全な成長に必要なDHAを自ら合成できない。しかし、淡水に進出した一部のカレイ目魚類は特殊化した当該酵素を有しており、DHAを自ら合成できることが明らかになっている。本研究では淡水産カレイに倣い、海産カレイの当該酵素をゲノム編集により僅かに改変することで特殊化させ、個体にDHA合成能を付与することを目的とする。これにより、DHAを自ら合成できる海産養殖魚を作出する技術基盤を構築し、餌料のDHA源として魚油を必須とする従来の「魚から魚をつくる」海産魚養殖からの脱却を目指す。
植物油に含まれるα-リノレン酸(ALA)からドコサヘキサエン酸(DHA)を作るには2段階の炭素鎖数の延長と3か所に二重結合の導入(不飽和化)が必要である。一般に海産魚はこれら何れかの反応を司る酵素を欠損しているため、DHAを合成できない。申請者は、熱帯域に生息する小型シタビラメ類が、ALAからDHAを合成する際に必須な全ての不飽和化活性を持つFADSを持つことを発見した。本研究では、日本産の食用シタビラメ類と本熱帯産種を交雑することで、食用種の特徴を具備しDHAも合成可能な新品種を作出する。
1 0 0 0 OA 超音波断層撮影装置による顔面皮膚厚の測定
- 著者
- 傳田 光洋 高橋 元次
- 出版者
- The Society of Cosmetic Chemists of Japan
- 雑誌
- 日本化粧品技術者会誌 (ISSN:03875253)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.4, pp.316-319, 1990-03-20 (Released:2010-08-06)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 5 15
We studied the change in skin thickness of forehead and cheek with age for healthy male and female subjects using ultrasound method. Skin thickness decreased with ageing in forehead and cheek in both sex groups, and it was thicker at every age group in males than in females.We also measured the skin thickness from twelve different sites at face in six healthy subjects. It was shown that skin thickness of eyelid was thinner than that of jaw or cheek.