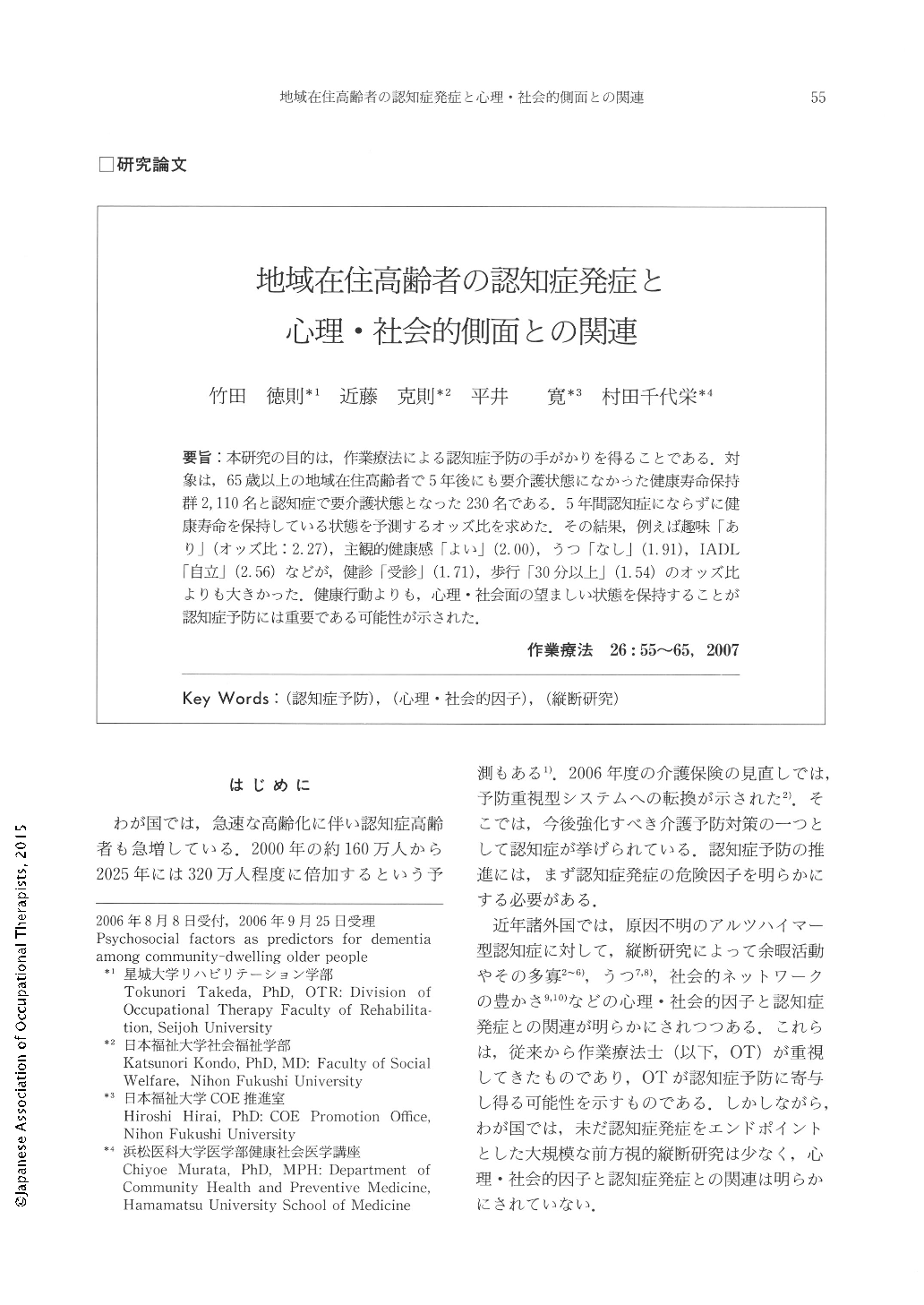1 0 0 0 4.4 ゆふ
- 著者
- 関西汽船株式会社 工務部
- 出版者
- 公益社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 関西造船協会誌 (ISSN:03899101)
- 巻号頁・発行日
- vol.142, pp.62-65, 1971
1 0 0 0 木食応其上人と連歌
- 著者
- 石川 真弘
- 出版者
- 密教研究会
- 雑誌
- 密教文化 (ISSN:02869837)
- 巻号頁・発行日
- vol.1961, no.53, pp.86-96, 1961
1 0 0 0 OA [大坪本流馬道秘書]
- 巻号頁・発行日
- vol.[2], 1800
1 0 0 0 OA 疑わしき母性性 : 比較心理学的考察(水地宗明教授退官記念論文集)
- 著者
- 関口 茂久
- 出版者
- 滋賀大学経済学会
- 雑誌
- 彦根論叢 (ISSN:03875989)
- 巻号頁・発行日
- no.第287・288号, pp.149-163, 1994-01
1 0 0 0 人力飛行機
- 著者
- 木村 秀政 内藤 晃
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.360, pp.15-22, 1984
1 0 0 0 人力飛行機STORK B
- 著者
- 木村 秀政
- 出版者
- 社団法人 日本流体力学会
- 雑誌
- nagare (ISSN:02867540)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.1-2, 1978
1 0 0 0 OA ハイエクの民主政治論における懐疑と失望
- 著者
- 山中 優
- 出版者
- JAPANESE POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.1_37-1_60, 2008 (Released:2012-12-28)
One of the thinkers whom Hayek praised very highly is Tocqueville. Hayek regarded Tocqueville as one of the best liberal thinkers of the 19th century who developed most successfully the political philosophy of the Scottish thinkers such as Mandeville, Hume and Smith. And the title of Hayek's The Road to Serfdom (1944) was named after what Tocqueville had called the “new servitude”. Evidently Hayek's argument on tyranny or despotism in the book had many similarities with that of Tocqueville in Democracy in America. However, there were, in fact, several big differences between them. Tocqueville defined individualism in a negative way: individualism “disposes each citizen to isolate himself from mass of his fellows and withdraw into the circle of family and friends”. But Hayek defined it in a positive way: the essential features of individualism were, for Hayek, “the respect for the individual man qua man”. While Tocqueville considered political freedom most important as a bulwark against the majority's tyranny or a new democratic despotism, Hayek considered economic freedom most important. Tocqueville endeavored to make the best use of democracy to make people good public citizens. But Hayek had skepticism and disappointment with democracy, which seemed to make Hayek resemble Plato rather than Tocqueville. These differences between them seem to pose a significant problem for state-society relationship in the contemporary world.
1 0 0 0 OA 2S4-2 海女と匠
- 著者
- 山下 真千代 竹内 千尋
- 出版者
- 一般社団法人 日本人間工学会
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.Supplement, pp.S88-S89, 2016-06-25 (Released:2016-10-15)
1 0 0 0 長野県の歴史的橋梁の現況について
- 著者
- 小西 純一 水口 正敬 瀬川 俊典
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木史研究 (ISSN:09167293)
- 巻号頁・発行日
- no.20, pp.349-358, 2000
- 被引用文献数
- 1
長野県における歴史的橋梁の現況調査結果を述べる.県内の道路橋, 鉄道橋, 水路橋で, 1960年代までに建造されたものを対象としたブ現地調査を行った橋は178橋である.<BR>ラチス桁, 道路鉄道併用橋, 上路曲弦プラット・トラスなど, 全国的に見て希少価値のある鋼橋が存在する一方, ここ10年の間のトラス橋, アーチ橋は急激であった.<BR>鉄筋コンクリート橋は95橋と多いが, アーチ橋がその半数を占める. 平野部では下路アーチ, 山間部では上路アーチが多い. 1930年代に建造されたアーチはよく現存している. 下路アーチの大部分はローゼ桁であり, 発祥の地にふさわしく, 1950年以降のものを含め29橋現存している.<BR>鉄道橋あるいは鉄道橋を道路橋に転用したものについては26橋であるが, 鉄道橋の発達史上重要なものが一通り揃っている. また. 森林鉄道用の立派な橋が存在する.<BR>水路橋には比較的大規模のものと, 石煉瓦アーチの小規模のものが存在する.
1 0 0 0 OA パルス波ECTの現状と導入を振り返って
- 著者
- 本橋 伸高
- 出版者
- 一般社団法人 日本総合病院精神医学会
- 雑誌
- 総合病院精神医学 (ISSN:09155872)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.106-109, 2012-04-15 (Released:2015-12-16)
- 参考文献数
- 23
1938年にイタリアで開発された電気けいれん療法(electroconvulsive therapy:ECT)は方法の修正を加えられ,現在でも治療抵抗性精神障害の治療に用いられている。わが国ではECTの研究が早くから行われていたが,方法の改良はなかなか行われず,短パルス矩形波(パルス波)の治療器は2002年になって認可された。この治療器の導入により,修正型ECTが原則化され,ECTが技術として認められるようになった。さらに,ECTのイメージが改善し,ECTの研究が世界的に評価されるようになった。しかし,わが国では非修正型のECTが未だに行われており,安全で有効な治療法としてのECTを普及させる必要がある。
1 0 0 0 IR モダリティに関する覚え書き
- 著者
- 岡部 嘉幸
- 出版者
- 千葉大学文学部日本文化学会
- 雑誌
- 語文論叢 (ISSN:21878285)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.96-75, 2013-07
1 0 0 0 地域在住高齢者の認知症発症と心理・社会的側面との関連
要旨:本研究の目的は,作業療法による認知症予防の手がかりを得ることである.対象は,65歳以上の地域在住高齢者で5年後にも要介護状態になかった健康寿命保持群2,110名と認知症で要介護状態となった230名である.5年間認知症にならずに健康寿命を保持している状態を予測するオッズ比を求めた.その結果,例えば趣味「あり」(オッズ比:2.27),主観的健康感「よい」(2.00),うつ「なし」(1.91),IADL「自立」(2.56)などが,健診「受診」(1.71),歩行「30分以上」(1.54)のオッズ比よりも大きかった.健康行動よりも,心理・社会面の望ましい状態を保持することが認知症予防には重要である可能性が示された.
- 著者
- 立花 徹美
- 出版者
- 日本図学会
- 雑誌
- 図学研究 (ISSN:03875512)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.25-32, 1987
1 0 0 0 IR ソフト多孔性錯体のフロー式精密合成と分子シミュレーションモデリング
- 著者
- 久保田 義弘
- 出版者
- 札幌学院大学総合研究所
- 雑誌
- 札幌学院大学経済論集 = Sapporo Gakuin University Review of Economics (ISSN:18848974)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.59-82, 2013-10
本稿で取りあげる北部アイルランドとスコットランド北西部で活動したダル・リアダ王国は,6世紀の初めに建国し,アイダーン王(Áedán mac Gabráin)(在位574年?-608年)の支配下のときに,その周辺国との戦いによる勝利によって,その領土を発展・拡充し,その最盛期に至した。しかし,603年頃のDegsastanの戦いにおいて,その王はノーサンブリア王国のエゼルフリス王(AEthelfrith)(在位593年-616年)に敗れ,その後,彼の勢力は衰え,同時にダル・リアダ王国の力も衰えた。さらに,彼の後継者は,周辺国との戦いに敗北するのみならず,内部抗争(ケネル・ガブラーン家とケネル・コンガル家の王家の抗争)を繰り返し,その勢力は一層衰退した。また,637年のMag Rath(ダウン州のMoira)の戦いの後,北アイルランドのダル・リアダ王国は滅ぼされ,同時に,スコットランドのダル・リアダ王国はその政情も不安定化し,ノーザンブリア王国に従属し,さらに,685年にノーザンブリア王国がピクト王国の王ブリィディ(ブルード)3世(在位671年-693年)に敗北し,730年頃にはその王国は,オエンガス1世のピクト王国の支配下に入り(従属し),その王国の上王(大君子権)がピクト王に支配に入った。最後に,ピクトとダル・リアダの融和に果たしたキリスト教の役割を調べる。第1節では,伝説のダル・リアダ王国と実在のダル・リアダ王国について,伝説のファーガス・モーによるダル・リアダ王国の建国とケネル・ガブラーンとケネル・コンガルそして,アイダーン王の全盛期その後のその勢力の陰りとその衰退,第2節では,ダル・リアダ王国の内部抗争とノーザンブリアおよびピクト王国への従属を概観し,第3節ではダル・リアダ王国とキリスト教の関係を説明する。
1 0 0 0 中国のサブプライム危機の影響と対応
- 著者
- 渡邉 真理子
- 出版者
- 比較経済体制学会
- 雑誌
- 比較経済研究 (ISSN:18805647)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.51-57, 2010
- 被引用文献数
- 1
2007年に始まったサブプライム危機は,マクロ経済の成長鈍化を通じて中国に伝播した。銀行部門の海外取引は規制され,利益追求インセンティブも弱かったため,サブプライム証券への投資がわずかであったことが幸いした。しかし,中国政府は,大規模な財政拡大,金融緩和政策を打ち出し,急速に銀行与信が拡大した。中国経済は,高度成長期を終える前に,バブル期に一気に突入してしまった感がある。
1 0 0 0 世界金融危機とドル体制の行方
- 著者
- 柴田 徳太郎
- 出版者
- 比較経済体制学会
- 雑誌
- 比較経済研究 (ISSN:18805647)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.1-14, 2011
2007年にアメリカで始まったサブプライム金融危機は,2008年秋のリーマン・ブラザーズ経営破綻を契機にドル流動性危機へと発展し,この流動性危機はエマージング・エコノミーへと波及した.アメリカで発生した金融危機がドル暴落ではなくドル流動性不足を引き起こした原因は,ヨーロッパ系銀行による「ドル・ドル」取引にあった.彼らの短期ドル資金調達困難がドル流動性危機を引き起こしたメカニズムを分析する.
1 0 0 0 OA 薬物動態学の観点から見る免疫抑制薬
- 著者
- 矢野 育子
- 出版者
- 一般社団法人 日本臓器保存生物医学会
- 雑誌
- Organ Biology (ISSN:13405152)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.131-137, 2019 (Released:2019-09-26)
- 参考文献数
- 14
A physiologically based pharmacokinetic model adapted to the clinical data was constructed in order to evaluate the contribution of liver regeneration as well as hepatic and intestine CYP3A5 genotypes on tacrolimus pharmacokinetics in adult patients after living-donor liver transplantation. As a result, the oral clearance of tacrolimus was affected by the CYP3A5 genotypes in both the liver and intestine to the same extent. Population pharmacokinetic and pharmacodynamic analysis of mycophenolate was performed in 49 patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation. Simulations based on the final parameters show that the dosage adjustment based on plasma concentrations of mycophenolate is required especially for patients with renal dysfunction and/or diarrhea. In conclusion, pharmacometrics is a useful methodology for individualized and optimized therapy of immunosuppressants.
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1909年10月14日, 1909-10-14