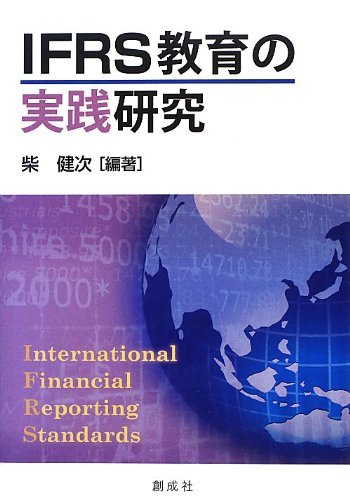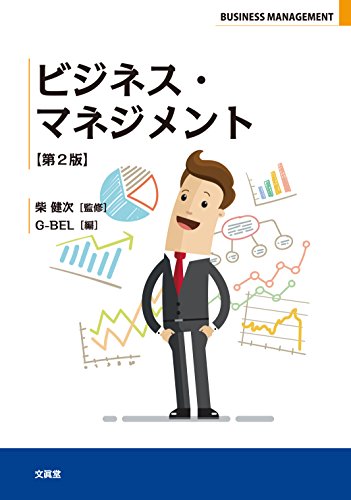1 0 0 0 IFRS教育の実践研究
1 0 0 0 ビジネス・マネジメント
1 0 0 0 OA アミノカルボニル反応
- 著者
- 早瀬 文孝
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子 (ISSN:04541138)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.10, pp.722, 2001-10-01 (Released:2011-10-14)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 OA 田邊太一について : ある幕臣のフランス体験
- 著者
- 富田 仁
- 出版者
- 立正女子大学短期大学部
- 雑誌
- 研究紀要 = The Annual Reports of Studies (ISSN:03855309)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.16-29, 1975-12-01
1 0 0 0 山梨大学教育人間科学部紀要
- 出版者
- 山梨大学教育人間科学部
- 巻号頁・発行日
- 2008
1 0 0 0 OA 研究力と学術システム・公的セクター
- 著者
- 遠藤 悟 細野 光章 王 戈 岡本 拓士 小野田 敬 桑島 修一郎
- 出版者
- 研究・イノベーション学会
- 雑誌
- 研究 技術 計画 (ISSN:09147020)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.238-257, 2019-10-25 (Released:2019-10-29)
- 参考文献数
- 21
Research performed at universities and public research institutions are crucial for the creation of new industry and for the enhancement of quality of life of the people. It contributes to improve the scientific literacy of the people and to develop human resources for research by stimulating scientific curiosity of the people. However, it is pointed out that research capability in Japan has been declined in recent years. In this paper, analyses of current situation of research activities at universities and public institutions are presented. The discussions made in this paper include the followings: (1) recognition of situation of research activities, (2) research funding, (3) governance and evaluation of universities and research institutions, (4) research performance, (5) human resources. Several recommendations for the improvement of research capacity in Japan through comparison with major overseas countries and through analyses of current research systems in Japan are presented.
1 0 0 0 在日華文学校の教育問題 : 「横浜中華学院」の事例を中心に
- 著者
- 杉村 美紀
- 出版者
- 東京学芸大学
- 雑誌
- 国際教育研究 (ISSN:03893189)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.52-54, 1991-03
1 0 0 0 OA 遺伝暗号を拡張した人工タンパク質合成系の開発と応用
- 著者
- 芳坂 貴弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.124-128, 2007 (Released:2007-03-31)
- 参考文献数
- 8
- 著者
- 永田 高志 王子野 麻代 寺谷 俊康 長谷川 学 石井 正三
- 出版者
- 杏林医学会
- 雑誌
- 杏林医学会雑誌 (ISSN:03685829)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.4, pp.275-279, 2015 (Released:2015-12-26)
- 参考文献数
- 2
インシデントコマンドシステム(ICS)は,米国で開発されたあらゆる災害対応において,組織の運用を標準化したマネジメント体型であり,本邦では緊急時総合調整システムと紹介されている。指揮統制や調整,組織運用などが標準化されていることが特徴であり,米国では災害対応のみならずマラソンやスポーツイベントなど,あらゆる危機管理事案がこのインシデントコマンドシステムに基づいて実施される。インシデントコマンドシステムは次の6つの要点でまとめられる。
1 0 0 0 HIV増殖阻害活性を有する海藻由来生理活性物質の探索
後天性免疫不全症候群(エイズ)はヒト免疫不全ウイルス(HIV)が免疫細胞に感染することにより,免疫細胞を破壊して免疫不全を起こす疾患である。本邦ではHIV感染者1.9万人,世界では2017年現在で3,690万人に昇る。現在では,逆転写酵素阻害剤の発見,その後の新薬の開発により治療が可能になった。しかしながら,エイズを根治する治療法は未だ確立されていない。本研究では,新たな治療薬の開発のため,抗HIV活性を有する海藻由来生理活性物質の探索を行った。市販のアオサ,コンブ,ヒジキ,ノリをサンプルとし,水抽出(水溶性画分)とエタノール抽出(脂溶性画分)をそれぞれ抽出した。その後,HIV-1 (R9)とTZM-bl細胞を用いて抗HIV-1活性を検討した。水溶性画分では,アオサ,コンブ,ヒジキにおいてHIV-1の初期感染を有意に抑制した。脂溶性画分において,コンブのみ初期感染を抑制した。これまでの報告により海藻由来多糖類であるフコイダンは抗HIV-1活性を有することから,海藻由来多糖類であるアスコフィラン,アルギン酸,フコイダン,ポルフィランの抗HIV-1活性を比較検討した。アスコフィラン及びフコイダンではHIV-1 (R9およびJR-FL)の初期感染を強く阻害した。一方で,アルギン酸,ポルフィランは弱い抗HIV-1活性を示した。しかしながら,HIV-1感染細胞内ウイルス量への影響が無かったことから,これら多糖類はHIV-1の初期感染を抑制すると考えられた。さらに,硫酸基を持つ化合物が血中のアルブミン(BSA)により抗HIV-1活性が阻害された報告より,10%FBSおよび50%FBS存在下でHIV-1初期感染を検討した。アスコフィラン,フコイダンの抗HIV-1活性が50%FBSにおいて低下したことから,これら海藻由来多糖類の抗ウイルス活性は非特異的であると考えられた。
1 0 0 0 OA 教室内英語多読が日本人高校生の作文力に与える効果
- 著者
- 渡邉 政寿 大場 浩正
- 出版者
- 日本教科教育学会
- 雑誌
- 日本教科教育学会誌 (ISSN:02880334)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.73-84, 2018 (Released:2020-01-26)
- 参考文献数
- 26
本研究は,日本人高校生の英語作文力が4か月間の教室内英語多読を経てどのように変化するかを調査したものである。「多読+ 英作文(ERW)」群と「多読のみ(ER)」群に分け,事前・事後に作文力と読解力テストを実施した。研究課題は,(1)教室内英語多読によって英語作文力が向上するか,(2)もし向上するなら,どの側面(内容,論理・構成,語彙,言語使用,句読点等の形式)か,及び(3)英語作文力のどの側面が英語読解力と読了語数に関連があるかであった。分析の結果,英語作文力の下位群では多読後に「句読点等の形式」以外において有意な伸長が認められた。また,ERW 群で「言語使用」,ER 群では「語彙」において英語作文力と読解力との相関がより強まり,指導法による差が認められた。更に,読了語数よりも読解力が英語作文力に影響を与えること,及び英作文評価観点の5項目にはそれぞれ「読解力」の有意な影響があることが判明した。
1 0 0 0 OA 自殺に至った口腔癌患者5例についての心身医学的研究
- 著者
- 清水 正嗣 小野 敬一郎
- 出版者
- Japanese Society of Psychosomatic Dentistry
- 雑誌
- 日本歯科心身医学会雑誌 (ISSN:09136681)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.41-47, 1991-06-25 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 12
The records of five oral cancer cases that committed suicide were studied psychosomatically. 4 were diagnosed as S. C. C. histologically and treated by oral surgeons and radiologists between 1959-1980 at the Uni. Hospital of Tokyo Medical and Dental University by Shimizu and others, and the remaining case was treated at a cancer center in Japan and the case history was examined for this study from the book written by the patient herself.The first case was a 50-year-old female with cancer of the upper left gum T4N1M0, which was treated with radiotherapy. Just one year later after the radiation, she committed suicide by jumping into a river, because of jaw pains due to tumor remains.The 2nd case was a 53-year-old male with cancer of the right cheek mucous membrane T3N2bM0, which was first treated with bleomycin, then with radiotherapy for 1. 5 years. After finishing radiotherapy successfully, the patient killed himself by hanging in the hospital due to the pain, although the tumor had clinically disappeared.The 3rd case was a 48-year-old female with cancer on the left side of the tongue T3NOMO. She was treated with interstitial radon seed radiation with success. After discharge from the hospital, she committed suicide by hanging herself at home afler complaining of pain and anxiety.The 4th case was a 55-year-old male with cancer on the right side of the tongue T3NlaMo. He was referred to the tumor conference, where the treating plan was decided to be radiotherapy. Before admission to the hospital, he killed himself by jumping into the Pacific Ocean from a ferryboat because he became pessimistic about the planned radiotherapy.The 5th case was a 59-year-old female novelist. She suffered from cancer on the right floor of the mouth and visited a cancer center, where a surgeon examined her and excised the tumor as a benign lesion. After that she was referred to the radiological department. The result of the radiotherapy was effective, but she thought her tumor would not disappear and hung herself at home due to severe mouth pain and great depression over the imagined future course of the tumor following the first failure of diagnosis and treatment.As causes of suicide by the patients with oral cancer, the side effect of pain during and after radio-therapy was pointed out at first, then the anxiety of the disease as cancer and distrust of the doctor played very important roles. For the future it should be stressed that we must not ignore these points as we examine and treat oral cancer patients.
- 著者
- Jean-Paul Ducrotoy
- 出版者
- The Plankton Society of Japan, The Japanese Association of Benthology
- 雑誌
- Plankton and Benthos Research (ISSN:18808247)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.Supplement, pp.174-184, 2010-12-25 (Released:2011-03-30)
- 参考文献数
- 67
- 被引用文献数
- 7 15
Estuaries are subject to increasing pressures due to local human activities. In addition, global change is affecting coastal habitats. Such disturbances impinge on goods and services provided by these ecosystems. The paper is devoted to efforts to restore environmental quality in some industrialised estuaries during the few past decades. It then compares strategies to recover damaged habitats and methods to restore lost ecological functionalities. Case studies are taken from the Seine in France, the Humber in England, the Scheldt in Belgium and the Netherlands and the Elbe in Germany. The article retraces briefly the morphological and ecological changes which have been inflicted on the estuaries over the last century. It puts into light actions which have been successful in improving their ecological functioning. Through comparing the various restoration schemes, policies are assessed. Details are given on efforts made lately in the Seine estuary which has lost more than 90% of its intertidal areas in about 150 years. Recently, losses due to an extension of harbour facilities in le Havre (“Port 2000”) have been compensated by the rehabilitation of a former mud flat and various constructions such as an artificial island for birds.The discussion confronts the present management of tidal estuaries to future challenges, including global changes. Such changes will not only include global warming and its consequences (sea level rise, biogeochemical cycles alteration...), but also socio-economic adjustments and a possible geo-political reorganization expected to take place in relation to increased harbour activities and the increasing need for more space dedicated to natural habitats and leisure activities (sports, tourism...).The conclusion puts together the various approaches from the considered European estuaries. Resting on a rigorous scientific approach, it proposes a synthetic approach to restoration: 1. Efficient procedures of socio-ecological evaluation, 2. A methodology to assess the ecological quality of systems considered, 3. Rigorous monitoring programs, resting on a relevant choice of indicators, and 4. Participation of local communities, in order to define strategies compatible with conservation and sustainable development at the local, regional and European levels.
1 0 0 0 OA 酸化マグネシウム大量服用による直腸内腸石の1例
- 著者
- 小澤 広太郎 金井 忠男 栗原 浩幸 山腰 英紀 石川 徹
- 出版者
- The Japan Society of Coloproctology
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.6, pp.293-296, 2002 (Released:2009-06-05)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
酸化マグネシウムは副作用が比較的少なく安全な下剤であり,治療科目にとらわれず汎用される薬剤である.今回肛門狭窄を伴う便秘患者が酸化マグネシウムを大量服用することによって生じた直腸内巨大腸石症例を経験したので報告する.症例は69歳,女性.排便困難を主訴に来院した.肛門診察にて肛門狭窄を認めたため,10月8日入院し,肛門拡張術を施行した.退院後肛門指診にて,ざらざらした砂状の凝集塊と表面不整で非常に硬い腸石を認め,腹部X線を撮影したところ骨盤内に直径6cm大の腸石像を認めた.11月15日再入院し,直腸内腸石摘出術を行った.摘出標本は茶褐色で非常に硬く表面不整であった,腸石の成分は炭酸マグネシウムとして59.9%であり,酸化マグネシウムの大量常用による直腸内巨大腸石症と診断された.酸化マグネシウムは汎用される薬剤であるが安易に増量すべきでなく,他の薬剤を併用するなどの注意が必要と考えられた.
1 0 0 0 IR 職業としての「シェルパ」をめぐる語りと実践 : ネパール・ソルクンブ郡P 村を事例に
- 著者
- 古川 不可知 Furukawa Fukachi フルカワ フカチ
- 出版者
- 大阪大学大学院人間科学研究科 社会学・人間学・人類学研究室
- 雑誌
- 年報人間科学 (ISSN:02865149)
- 巻号頁・発行日
- no.36, pp.119-137, 2015-03-31
ネパール東部のソルクンブ郡はシェルパ族の居住地である。エベレストの麓にあたるこの地域はトレッキング/登山観光の一大メッカであり、観光シーズンには多くのネパール人ガイドたちが観光客を案内して山道を行き交う。様々な民族的出自を持つガイドやポーターたちは、しばしば観光客たちから「シェルパ」として言及され、ときにはまた自らも「シェルパ」を名乗って観光産業に参与している。本稿の目的は、民族範疇とはズレを持ちつつ重なり合った「シェルパ」という職業カテゴリが、現地においてどのように語られ、実践され、また再生産されているかを、ソルクンブ郡のある村でネパール人を対象に開校される登山学校を事例として分析することである。ここでは、シェルパ族を中心にネパール各地から集まってきた生徒たちが、米国人講師の指導のもとでアイス・クライミング(氷壁登攀)の技術を中心とした登山スキルを習得する。学校では、外国人やシェルパ族、「シェルパ」として働くシェルパ族ではない人々などによって多様な「シェルパ」の理念や枠組みが提示され、生徒たちは「山で道案内するシェルパ」となるために訓練を通して自らの生活環境を対象化してゆく。生徒たちは、「シェルパ」の概念や登山用具などのモノ、環境中に道を作りだす実践などを通して職業としての「シェルパ」へと成型されてゆくのである。
1 0 0 0 発がん物質ハルマン、ノンハルマンのカテコールアミン神経系への影響
ハルマンとノルハルマンはヘテロサイクリックアミンの一つでタバコ煙中や調理した食品中、酒等のアルコール飲料にも含まれ、代謝されるとアニリンと結合して変異原物質となり、DNA損傷性を著しく増強し癌化の原因となることが知られている。また、パーキンソン症候群様の振戦や幻覚症状を引き起こすことや、それらを含むパッションフルーツのサプリメントによる鎮静作用も報告される等、神経系への影響も示唆されている。本研究では昨年度に引き続きβ-carboline化合物のカテコールアミン神経系への作用についてウシ副腎の初代培養細胞を用いて検討した。(1)Norharman≒Harman>Harmine≧Harmaline>Harmolの順でβ-carboline化合物はアセチルコリン受容体刺激によるカテコールアミン分泌を抑制した。(2)Norharmanはニコチン性アセチルコリン受容体刺激や電位依存性Naチャネルの活性化によって引き起こされるカテコールアミン分泌、Ca influxとNa influxをいずれも濃度依存的(10-100 μM)に抑制し、電位依存性Caチャネルの活性化によって引き起こされるカテコールアミン分泌とCa influxは100 μMでのみ抑制した。ニコチン性アセチルコリン受容体刺激による分泌反応抑制は非拮抗阻害であった。(3)Norharmanはカテコールアミン生合成を濃度依存的(10-100 μM)に抑制した。(4)Norharmanはアセチルコリンによるチロシン水酸化酵素の活性化を抑制した。この抑制作用はチロシン水酸化酵素ser40のリン酸化阻害によるものであった。以上のことから、ノルハルマンはニコチン性アセチルコリン受容体を介するNa^+,Ca^<2+>流入を阻害することにより、カテコールアミン分泌・生合成を抑制することが示された。
1 0 0 0 IR 日本人高校生英語学習者の従属接続詞before/afterの使用に見られる母語の影響
- 著者
- 甲斐 順
- 出版者
- 兵庫教育大学言語表現学会
- 雑誌
- 言語表現研究 = Studies in linguistic expression (ISSN:02886626)
- 巻号頁・発行日
- no.32, pp.17-31, 2016-03
1 0 0 0 OA 狂歌江都名所図会 16編
- 著者
- 天明老人内匠 編
- 巻号頁・発行日
- 1856
- 著者
- 角尾 宣信
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, pp.92-113, 2019
【要旨】<br> 敗戦後から1960年代前半にかけて、「風俗映画」と呼称される多くの作品が登場した。その特徴は、同時代のライフスタイルや風景などを記録し、そこから人々の思想や価値観を捉えるものと指摘されてきた。本論文は、総合的な「風俗映画」の研究に向けた一歩として、「風俗映画作家」と言われていた渋谷実の『自由学校』(1951年)を取り上げ、原作小説および吉村公三郎による同名翻案(1951年)と比較し、その「風俗映画」としての映画史的・社会史的意義と可能性を考察する。<br> 渋谷作品のスタイル上の特徴として、戦争および敗戦のトラウマの継続と、人物表象および心理描写両面での奥行きの無さの二点が指摘されてきた。本論文は、この二点を結ぶ線上において、本作品の特徴である男性主人公の「平面に寝ころぶ」という繰り返し現れる身ぶりを考察する。また、本作品での平面性というスタイルが、愛情や行動意欲の欠如と、ジェンダー的および物理的な平等性という二重の意味をもつことを指摘する。そして、この身ぶりの繰り返しを通じて描かれる、行動意欲を徹底して欠いた男性主人公の心理状態を、敗戦直後における日本社会全体の「虚脱」状態から歴史的に位置づける。さらに、本作品では、この「虚脱」状態を核として、「風俗映画」と見なしうる同時代の記録が構成されており、それが同時代における「虚脱」状態の逆説的かつ肯定的解釈と通じ合うことを示し、敗戦後の社会的心理状態から「風俗映画」を考察する必要性を指摘する。
1 0 0 0 OA 便および髄液検体からのインフルエンザウイルス AH1pdm の分離および抗原検出
- 著者
- 後藤 則子
- 出版者
- 一般社団法人 日本感染症学会
- 雑誌
- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.1, pp.34-37, 2012-01-20 (Released:2013-01-15)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1 1