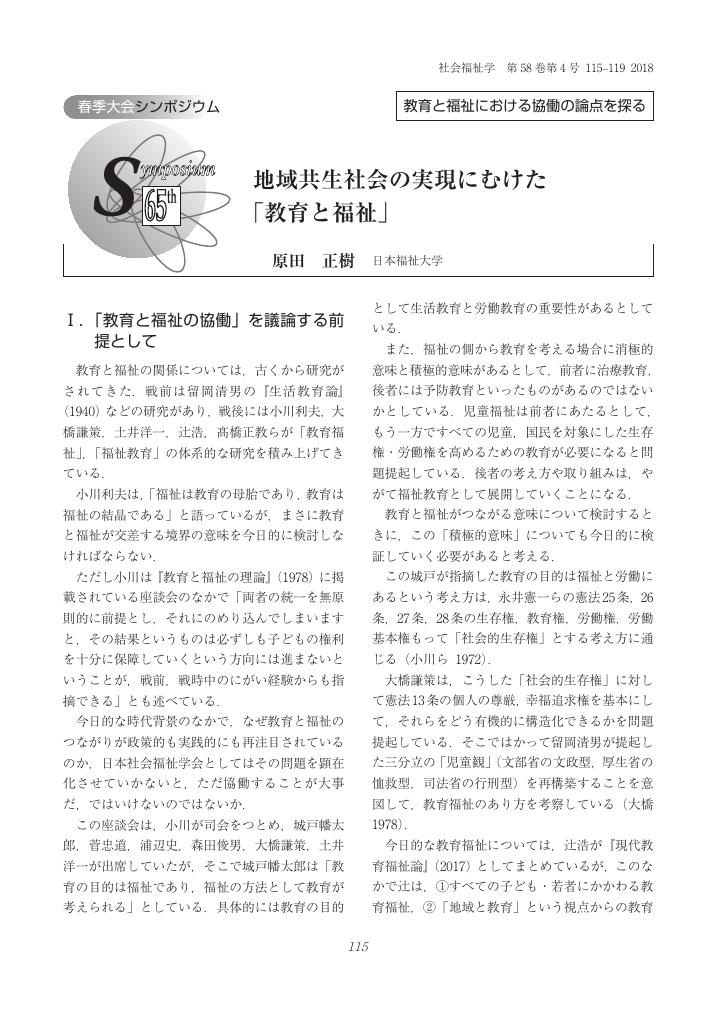3 0 0 0 OA 日本における少子化の社会経済的要因と政策
- 著者
- 飯島 佐知子 横山 和仁
- 出版者
- 一般社団法人日本衛生学会
- 雑誌
- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.3, pp.305-312, 2018 (Released:2018-09-29)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 1 6
The factors contributing to the declining birthrate in Japan include the declining marriage rate, an increase in the average age of those getting married, economic burden, childcare burden, later child-bearing, and infertility. There is a gender difference in role division, with 70% of unmarried people live with their parents and continue to work while leaving the household chores to their mothers. The loss of these housekeeping services and the increase in the number of irregular workers are factors contributing to the declining marriage rate and the increase in the average age of those getting married. The expansion of the family support policy in Japan from the male breadwinner model to the earner-career model may have been delayed, but it is expected to provide economic benefits as well as actual childcare service benefits in order to reduce the economic and physical burden of childcare for married couples. It is also necessary to provide education in reproductive health to both men and women in schools and workplaces regarding late child-bearing and infertility. Furthermore, it is necessary to evaluate the cost-effectiveness analysis of improvements in fertility and disclose the relevant information in addition to sharing information on medical technology related to pregnancy/childbirth and treatment of diseases. It is urgent to prepare society for natural and healthy pregnancies/childbirths during optimal child-bearing years.
3 0 0 0 OA 国内外のアドバンスケアプランニングに関する文献検討とそれに対する一考察
- 著者
- 大濱 悦子 福井 小紀子
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.4, pp.269-279, 2019 (Released:2019-12-17)
- 参考文献数
- 106
- 被引用文献数
- 5
【目的】国内外のアドバンスケアプランニング(ACP)を比較し,わが国で今後求められる知見について検討する.【方法】医中誌およびMEDLINEで検索可能で2019年6月までに発行された日本語または英語の論文を対象に文献検討を行った.前者ではシソーラス「アドバンスケア計画」で検索可能な原著論文,後者ではMeSH「ACP」で検索可能なレビューを対象とした.【結果】MEDILINEで849本のレビュー(約500本が米国での執筆),医中誌では186本の原著論文が検索された.日本のACP研究の数・エビデンスレベルは米国に比べ遅れを取っていること,行政および学会等で共通したACPの定義が設定されていないこと,在宅療養者を対象とした介入研究の知見はほとんどないことが明らかとなった.【結論】日本の文化的・社会的背景を考慮したACPの定義設定とともにとくに在宅療養者への効果的な介入についてのエビデンスの構築が求められる.
3 0 0 0 OA スリランカにおける菩薩王の理想とサンガ改革
- 著者
- 藪内 聡子
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.1136-1139, 2007-03-25 (Released:2010-03-09)
- 参考文献数
- 4
ポロンナルワ時代, スリランカ史上最大の英雄と称される Parakkamabahu I 世 (1153-1186 A. D.) は, それまで Mahavihara, Abhayagiri, Jetavana の三派に分かれていたスリランカのサンガに対して, Mahavihara 派の受戒のみを承認してサンガの統一を断行したが, それが可能であったのは, アヌラーダプラ時代に遡り, 政治的概念として菩薩王思想が受容されて浸透したからであることが, 史書や碑文資料により認められる.菩薩王思想は, アヌラーダプラ時代初期については Abhayagiri 派と関連して発展したが, アヌラーダプラ時代中期以降は派とは関係なく独自に進展を遂げ, 政治的イデオロギーとして, 王の存在を限りなく仏陀に近い存在にし, 王権の正当性を強化して, サンガに対する行使力増大に寄与した. ポロンナルワ時代には, 南インドからの侵略のために, ことに王は軍事的頂点の存在として英雄性が重視されるが, 菩薩王思想は英雄性と混在し, サンガ統一により Mahavihara 派のみが存在するようになった後も, イデオロギー化して Mahavihara 派と同化して存続することになる.
3 0 0 0 OA 各種口腔ケアの効果に関する検討 - 口腔常在菌数を指標として -
- 著者
- 茂木 健司 笹岡 邦典 樋口 有香子 根岸 明秀 橋本 由利子 外丸 雅晴
- 出版者
- 北関東医学会
- 雑誌
- 北関東医学 (ISSN:13432826)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.239-244, 2007-08-01 (Released:2007-09-11)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 2
【背景・目的】 口腔に存在する多数の常在菌は局所的疾患の原因となるだけでなく, 全身的障害をも引き起こす. そのため, 口腔ケアは全身疾患予防の観点から重要視されている. 今回, 各種含嗽剤による口腔常在菌数減少効果について検討した. 【対象と方法】 健常成人21名に対し, 含嗽前の唾液, および7%ポビドンヨード30倍希釈液, 薬用リステリン®(青色) 原液, 薬用クールミントリステリン®(黄色) 原液, おのおの30mlを, 15秒間口腔内に貯留後の唾液を検体とし, 一般細菌, カンジダの培養後, 含嗽剤作用前後のコロニー数を比較した. 【結 果】 一般細菌は, 含嗽前では全例から検出されたが, 含嗽後では69~93%で減少した. カンジダは, 含嗽前では27~47%に検出され, 含嗽後では25~88%で減少していた. いずれも薬用リステリン®(青色) の減少率が高かった. 【結 語】 含嗽剤を口腔に貯留することにより, 一般細菌, カンジダを減少させる効果が認められ, 特に薬用リステリン®(青色) の効果が高かった.
- 著者
- 中澤 篤史
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.315-328, 2008-12-10 (Released:2009-02-25)
- 参考文献数
- 27
The Undoukai (Athletic Association) at the Imperial University of Tokyo was a student association that consisted mainly of sports club members. The Undoukai was a departure point for Japanese sports, and led to the establishment of school sports in the Meiji period, being incorporated as a foundation in 1934. The purpose of this study is to describe the process of how the Undoukai was organized as an incorporated foundation from the late Taisho era to the early part of the Showa era, focusing on interactions among students and the university. The main documents are gathered from the Imperial University Newspaper.The results of this study are summarized as follows.1) This study describes the history after establishment of the Undoukai, which was integrated into the Gakuyukai (Athletic and Cultural Association) at the Imperial University of Tokyo in 1920. The Gakuyukai was an all-university association that included cultural activities. However, the members of the sports clubs left the Gakuyukai and organized the Undoukai again in 1928.2) This study clarifies two oppositional relationships among students during the organizational process of the Undoukai. One was between sports club members and the other students, and the other was between the left-wing students and the right-wing students. In both relationships, sports club members would win the understanding of non-athletic students and would distance themselves from the left-wing students. Both practices enabled the Undoukai to become independent from the Gakuyukai.3) This study clarifies that strong assistance from the University contributed to the reorganization of the Undoukai. There were two problems that the University needed to address: one was how to prevent students' illnesses, and the other was how to discourage students from becoming inclined to the politcal left. Therefore, the University expected general students to aspire to “healthy body” and to have “healthy idea”. While the University would recommend sports to general students in order to realize the expectation of “healthy body”, at the same time it would separate general students from left-wing students in order to realize the expectation of “healthy idea”. These expectations and practices of the University provided the impetus that nurtured the Undoukai.
3 0 0 0 OA 視的経験を社会学するために
- 著者
- 安川 一
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.57-72, 2009-06-30 (Released:2010-08-01)
- 参考文献数
- 63
- 被引用文献数
- 1
これは,視的経験を社会学するための視座設計の試作品である.わたしたちの見る営みは互いにどう違うのだろう.現代社会・文化の様々な領域で視覚の優位が言われてきた.社会学的思考も,見ることはすなわち行為であり制度である,そう述べてきた.けれども,具体的な視的経験の豊かなありかたが直視されることはあまりなかった.視的経験の実際を探ろうと思う.つまり,生理的機能としての視覚でも社会・文化・歴史的抽象としての視覚性でもない,雑多に繰り返される日々の諸経験の視覚的位相の探求である.この観点から私は,社会心理学的自己概念研究法である自叙的写真法に準じて自叙的イメージ研究を試みた.被験者に「わたしが見るわたし」をテーマにした写真撮影を求め,撮影行為と自叙的イメージとで視的経験を自己言及的に活性化して,その様子を観察しようというフィールド実験である.総じて,生成された自叙的イメージの多くは生活世界の“モノ語り”像(=モノによる自己表象)だった.ただし,イメージの自叙性のいかんは主題ではない.イメージ自体の分析が視的経験の解析に至るとも思えない.課題は分析よりむしろ,イメージ群をもって視的経験をいかに構成してみせるかにあると思う.私は,イメージ群の配列-再配列を繰り返しながら,イメージ陳列の仕方自体を視的経験の相同/相違の表象として試みつつ,この作業を通じて考察に筋道をつけていきたい,そう考えている.
3 0 0 0 OA 呼気および吸気時CT画像に基づく胸郭運動モデルの構築
- 著者
- 伊藤 広貴 越塚 誠一 芳賀 昭弘 中川 恵一
- 出版者
- 日本医用画像工学会
- 雑誌
- Medical Imaging Technology (ISSN:0288450X)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.4, pp.208-214, 2011 (Released:2011-10-12)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
胸郭の運動が一因となり呼吸による肺変形が引き起こされるため,胸郭の時系列の動きを知ることは肺内部の変形シミュレーションをする際に重要な知見となる.そこで,解剖学的知見とCT画像をともに用いる胸郭運動モデルを提案する.肋骨は肋横突関節と肋椎関節を結ぶ軸で回転運動をさせ,各肋骨の回転角度は呼気と吸気時のCT画像から求める.これにより,提案した胸郭運動モデルがポンプハンドル運動とバケットハンドル運動を定性的に再現できることを示す.さらに,呼気と吸気時のCT画像を用いて,提案した胸郭運動モデルにおける肋骨の回転角度算出手法の妥当性を検証する.
3 0 0 0 OA Twitter への投稿テキストによる炎上警告システムの構築
- 著者
- 川上 幹 彌冨 仁
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 日本知能情報ファジィ学会 ファジィ システム シンポジウム 講演論文集 第32回ファジィシステムシンポジウム
- 巻号頁・発行日
- pp.705-708, 2016 (Released:2019-03-15)
3 0 0 0 OA 銀増幅技術を用いたインフルエンザ迅速検査キットの有用性
- 著者
- 高橋 篤史 木村 泉美 樋口 貴洋 伊藤 克彦 向山 弘昭 譚 策 笹川 裕
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
- 雑誌
- 医学検査 (ISSN:09158669)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.6, pp.737-742, 2015-11-25 (Released:2016-01-10)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
イムノクロマトグラフィ法に白黒写真の銀増幅技術を応用した高感度インフルエンザ自動判定キット富士フイルム(株)「富士ドライケムIMMUNO AGカートリッジFlu AB」と他2社のインフルエンザ迅速診断キットについて比較検討を行った。対象患者131名から得られた鼻腔拭い検体を用いて,RT-PCRを基準とした各キットの陽性一致率/陰性一致率/全体一致率を算出した。インフルエンザA型に対して本キットで100% / 96.0% / 97.7%,対照キット①で83.9% / 98.7% / 92.4%,対照キット②で75.0% / 100% / 89.3%であった。またインフルエンザB型に対しては本キットで86.7% / 98.3% / 96.9%,対照キット①で73.3% / 98.3% / 95.4%,対照キット②で60.0% / 99.1% / 94.7%であった。本キットは対照キット①,②に比べA型,B型に対する陽性一致率,全体一致率が共に高かった。RT-PCR陽性,問診票で38℃以上の発熱があった症例にて発症時間と各キットの陽性率を比較した。発症から24時間以内の症例で,本キットは対照キット①,②よりも陽性率が高かった。本キットは高感度であるためウイルス量が少ない検体でも陽性判定できる可能性が高く,早期診断に有用であると考えられる。
3 0 0 0 OA 猫における乾燥スルメイカ摂食後血中クレアチニン濃度の検討
- 著者
- 丹野 翔伍 髙島 一昭 山根 剛 山根 義久
- 出版者
- 動物臨床医学会
- 雑誌
- 動物臨床医学 (ISSN:13446991)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.49-52, 2013-06-20 (Released:2014-12-06)
- 参考文献数
- 5
6カ月齢と11カ月齢の雑種猫が,人用に市販されている乾燥スルメイカを摂食した後に嘔吐したとの主訴で来院した。富士フィルムメディカル株式会社DRI-CHEM7000V(以下,DRI-CHEM)を用いた血液検査にて,2症例ともに血中クレアチニン濃度の著しい上昇が認められた。皮下輸液および制吐処置などの治療により,翌日にはクレアチニン濃度は正常に回復し,臨床症状も消失した。 後日,健常猫を用いて乾燥スルメイカの摂食試験を行った。その結果,前述の臨床例と同様に,嘔吐およびDRI-CHEMを用いた血液検査で血中クレアチニン濃度の上昇が認められた。しかし,同検体を酵素法で測定したところ血中クレアチニン濃度の上昇は認められなかった。したがって,猫が乾燥スルメイカを摂食した場合,DRI-CHEMでは偽高クレアチニン血症を生じることが判明した。
3 0 0 0 OA 健康食品による被害未然防止のための注意喚起情報の収集および解析
- 著者
- 小林 悦子 佐藤 陽子 梅垣 敬三 千葉 剛
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.93-98, 2018-04-25 (Released:2018-04-25)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 3 8
海外の健康食品をインターネットで購入できる状況において,健康被害を未然に防止するには,国内だけでなく海外の被害情報を把握することが重要である.「健康食品」の安全性・有効性情報サイトでは,国内外の行政機関から発信された健康食品の注意喚起情報を収集・掲載している.今回,2010から2016年に収集した2,124件の注意喚起情報の特徴を分析した.製品の特徴として,医薬品成分混入が85%を占め,性機能改善および痩身を標榜した製品が68%を占めた.多くは買上調査や自主回収情報であったが,健康被害事例も181件含まれ,痩身および疾病治療を目的とした利用で被害が多く見られた.日本国内では,10~30代女性,痩身目的の利用,インターネットでの購入という特徴が認められた.これらの特徴を,健康被害の未然防止のための適切な情報提供に役立てる.
3 0 0 0 OA 係り結びと不定構文
- 著者
- 衣畑 智秀
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.1-17, 2016 (Released:2017-01-24)
- 参考文献数
- 24
本稿では係り結びと不定構文の相補性について論じる。日本語の歴史においては、カによる係り結びが衰退した後に、カによる間接疑問・選言・不定などの不定構文が現れたが、このような係り結びと不定構文の相補性が、現在も係り結びが残る南琉球宮古語においても見られるか調査を行った。その結果、疑問の助詞gaによる係り結びが使われる中南部諸方言ではgaによって不定構文が形成できず、疑問のgaによる係り結びが衰退した北部の諸方言ではgaによる間接疑問や選言が見られた。このような係り結びと不定構文の相補的な分布は、係り結びの主文生起性によって説明できる。つまり、主文に生起するという係り結びの性質が、不定構文における名詞句内や従属節内でのその助詞の使用に影響しているのである。
- 著者
- 根村 直美
- 出版者
- 日本社会情報学会
- 雑誌
- 日本社会情報学会全国大会研究発表論文集 日本社会情報学会 第22回全国大会
- 巻号頁・発行日
- pp.38-43, 2007 (Released:2010-01-22)
本報告者は、平成18 年12 月-平成19 年3 月の期間、REAS(リアルタイム評価支援システム)を利用しWeb上でのアンケート調査を試験的に実施。MMORPG(マッシブリー・マルチプレイヤー・オンライン・ロールプレイング・ゲーム)のプレイヤー105 名にジェンダー・スウィチングについて尋ねた。この調査結果を手がかりに、日本のインターネットにおける自己およびジェンダーの状況について若干の考察を試みる。
3 0 0 0 OA 逸脱から教育問題へ
3 0 0 0 OA ミュオンによる地球内部観測
- 著者
- 田中 宏幸
- 出版者
- 公益社団法人 日本アイソトープ協会
- 雑誌
- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.7, pp.305-317, 2016-07-15 (Released:2016-07-15)
- 参考文献数
- 28
宇宙線に起因する高エネルギーのミュオンは透過力が非常に強いため,地球内部の観測に応用することができる。これまでに,火山や断層,洞窟などを対象に,地球浅部構造の観測が行われてきた。中でも火山を対象にした観測では,マグマの形状や位置を視覚化することにより,噴火推移の予測に使える可能性があることがわかってきた。本報文では,ミュオンによる地球内部観測の原理と手法,そして最近の成果についてレビューする。
3 0 0 0 OA 法然門流の注釈活動
- 著者
- 中村 玲太
- 出版者
- 宗教法人 真宗大谷派 親鸞仏教センター
- 雑誌
- 現代と親鸞 (ISSN:13474316)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.2-20, 2019 (Released:2019-12-24)
- 著者
- 千代田 夏夫
- 出版者
- 一般財団法人 日本英文学会
- 雑誌
- 英文学研究 (ISSN:00393649)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, pp.85, 2017 (Released:2019-05-08)
3 0 0 0 OA 地域共生社会の実現にむけた「教育と福祉」
- 著者
- 原田 正樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本社会福祉学会
- 雑誌
- 社会福祉学 (ISSN:09110232)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.4, pp.115-119, 2018-02-28 (Released:2018-06-22)
- 参考文献数
- 9
- 著者
- 井谷 惠子
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- pp.14090, (Released:2015-06-12)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1
In 2002, the Central Education Council published a report entitled “Improvement of children's physical fitness”. The report pointed out that changes in the social environment and lifestyles in recent years had influenced children's physical fitness and movement skills, and that a “comprehensive policy” addressing various aspects was essential for tackling this problem. On the basis of this report, the Ministry of Education and local boards of education are currently undertaking various projects; however, a number of gaps still remain between the findings of the report and what is actually being done to address this issue. The present paper examines the local political issues that have led to differences between the practices of local educational governments and the recommendations of the report by focusing on practices in the Tokyo Metropolitan area and Osaka Prefecture after publication of the report. This study revealed that the local governments had been strongly influenced by the results of physical fitness tests in comparison with other districts, counter to the comprehensive policy suggested by the report. This suggests that one of the reasons for the existing gap is the implicit demand for measurable results based on strong promotion of the evaluation system stipulated by the current educational policy. The results also show that most projects to improve children's physical fitness have been undertaken by schools, despite the fact that almost no budget has been allocated for this purpose, thus forcing schools to bear the burden and responsibility alone. Furthermore, it is also evident that competitive sports are frequently used to promote an active lifestyle, even in elementary and junior high schools. In view of the numerous practices aiming to improve performance through sports club activities and competitive sports events, such as long-distance relays for children and Olympic education, it appears that the government in fact has a hidden agenda to promote sports and to improve athletic performance behind the façade of children's fitness as a “social issue”.
- 著者
- 石崎 啓太 中野 冠
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)
- 巻号頁・発行日
- pp.18-00050, (Released:2018-10-02)
- 参考文献数
- 55
- 被引用文献数
- 3
This study systematically analyzed life cycle CO2 (LCCO2) emissions of a comprehensive set of mass-produced 2,000 cc class sedan-type vehicles, using a hybrid life cycle inventory approach. Gasoline and diesel internal combustion engine vehicles (ICEVs), hybrid electric vehicle (HEV) as well as battery electric vehicle (BEV) and fuel cell vehicle (FCV) were investigated, considering (i) the current BEV market trends, (ii) Japan's energy mix (the average for 2012–2014), and (iii) the use of the HVAC system. The results show that the annual average increment of CO2 emissions in use phase by HVAC system in Japan (assumed annual mean temperature of 15°C) was presumed to be evenly 9% regardless of vehicle types, although further detail analysis is required. The CO2 emissions in use phase of BEV were higher than those of HEV and FCV (applied hydrogen produced by steam reforming of LPG (on-site)) due to thermal power dominant electricity generation mix in Japan in recent years. As a consequence of high CO2 emissions from power supply and battery production, the LCCO2 emissions of BEV equipped with 75 kWh battery were higher than those of HEV, FCV (on-site), and conventional ICEV (diesel). By reducing the battery capacity to 40 kWh or less, the LCCO2 emissions of BEV become lower than those of ICEVs and FCV (on-site), making BEV a competitive alternative. However, it is difficult that BEV mitigates both LCCO2 emissions and driver's range anxiety. In conclusion, HEV shows the competitive performance in terms of LCCO2 emissions with long driving range in Japan.