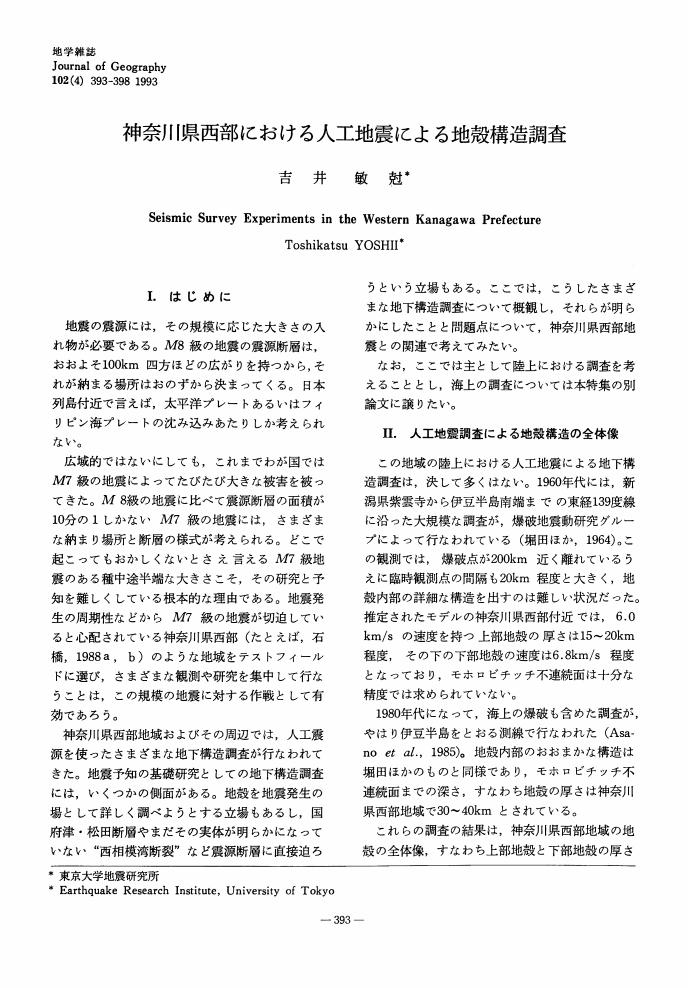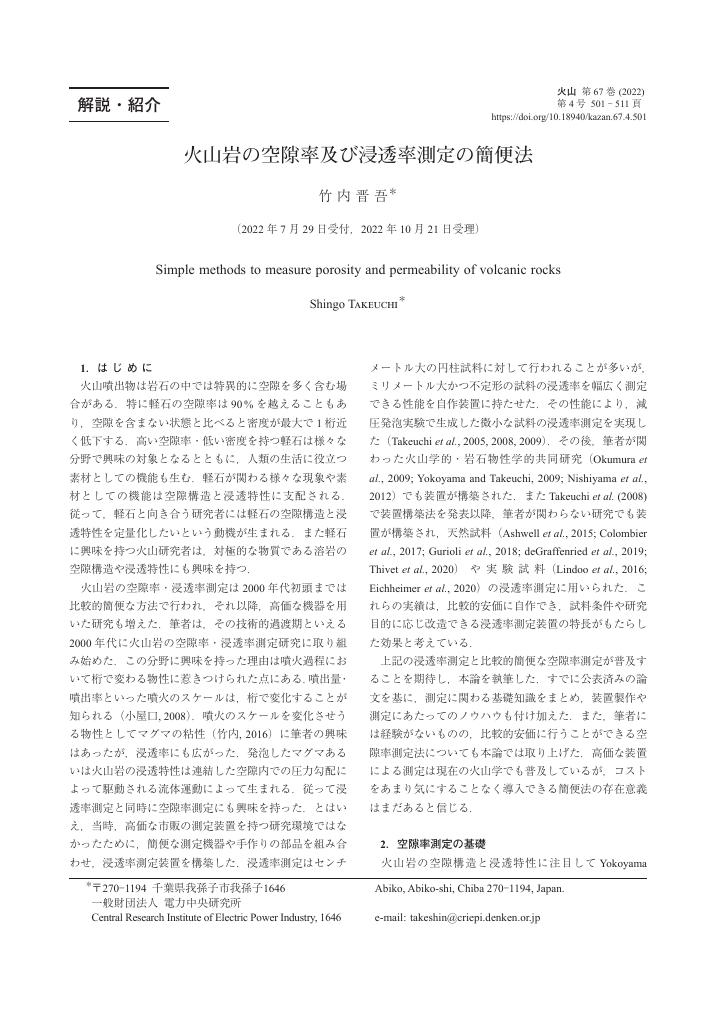6 0 0 0 OA 神奈川県西部における人工地震による地殻構造調査
- 著者
- 吉井 敏尅
- 出版者
- Tokyo Geographical Society
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, no.4, pp.393-398, 1993-08-25 (Released:2010-11-18)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1 1
6 0 0 0 IR 施設入所知的障害者の高齢化の研究--大分県内の知的障害者施設アンケート調査
- 著者
- 足立 圭司
- 出版者
- 別府大学短期大学部紀要編集委員会
- 雑誌
- 別府大学短期大学部紀要 (ISSN:02864991)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.55-64, 2011-02
大分県内の各知的障害者施設に,利用者の高齢化と老化についてアンケート調査を行った.その結果,多くの高齢知的障害者は知的障害者更生施設へ集中していることが明らかになった.知的障害者施設の介護力不足の問題と介護老人福祉施設へ容易に入所できない実態が示された.施設からは高齢知的障害者のケアと一般の認知症高齢者や身体介護を要する高齢者のケアは,基本的に異なるといった声が多く見られた.また新体系への移行に伴い高齢者生活支援プラス知的障害者固有のニーズに基づくサービスの提供,あるいは介護保険での認知症対応型共同生活介護等を高齢知的障害者に利用しやすい形態にして地域ケアの方向へシステム化するという二方向の意見に整理された.今後,高齢知的障害者固有のニーズについて,認知症対応ケアとの相違も含めて調査研究を続けていく必要がある.
- 著者
- 中村 敏秀
- 出版者
- 長崎国際大学
- 雑誌
- 長崎国際大学論叢 (ISSN:13464094)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.113-126, 2003-01-31
- 被引用文献数
- 1
本稿では知的障害者の地域移行の前提として、知的障害者更生施設の援助実態と施設援助を規定する要因について検討の必要性を提起した。それは地域移行の先駆けとなったアメリカやスウェーデンに生起した、施設の管理抑圧的な援助が地域生活援助に持ち込まれる危険性を無視しえないからである。このため全国の知的障害者更生施設の援助に関する予備調査をし、施設援助の規定要因として援助環境、利用者の自由裁量度、援助水準、職場満足度の4つの規定要因を抽出しえた。今後、この調査結果に本調査を実施する予定である。
6 0 0 0 IR 人環フォーラム No. 28
- 出版者
- 京都大学大学院人間・環境学研究科
- 雑誌
- 人環フォーラム (ISSN:13423622)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, 2011-03-20
<巻頭言>古代日本と東アジア / 上田正昭<対談>生きるための経済学 / 安冨歩, 間宮陽介, 司会 阪上雅昭<特集 : 境界を科学する>越境の試練と報償 ̶ 生物たちの上陸の歴史 / 加藤真<特集 : 境界を科学する>境界から空間へ / 間宮陽介<特集 : 境界を科学する>0と1との境界 / 立木秀樹<特集 : 境界を科学する>境界上であること - ルシン語とルシン人の場合 / 三谷惠子<特集 : 境界を科学する>地球の中の境界 / 小木曽哲<特集 : 境界を科学する>境界について / 戸田剛文<リレー連載:環境を考える>学際的ホメオスタシス研究のすすめ / 北畠能房<サイエンティストの眼>岩石の生成温度を測るための温度計 / 大井修吾<フロンティア>スポーツ健康科学の面白さ / 橋本健志<フロンティア>文学は言語を用いて何をなしうるか / 宮﨑三世<世界の街角>ロンドン、サウスバンク / 桒山智成<国際交流セミナーから>数学者から見た一五世紀イタリア絵画 - C. クリヴェッリ「聖エミディウスをともなう受胎告知」 / K. H. ホフマン、K. カイメル<フィールド便り>早起きはなぜ得なのか 時間栄養学から探求する21世紀の健康ライフ / 永井成美<書評>福家崇洋著『戦間期日本の社会思想 「超国家」ヘのフロンティア』 / 福間良明<書評>辻正博著『唐宋時代刑罰制度の研究』 / 中村正人<書評>佐野亘著『公共政策規範』 / 野田裕久<書評>舟木徹男訳・解題、O. ヘンスラー著『アジール - その歴史と諸形態』 / 上山安敏<人環図書>田中雅一、田辺明生共編『南アジア社会を学ぶ人のために』<人環図書>西山良平、鈴木久男編『恒久の都 平安京』瓦版
6 0 0 0 OA 聴覚障害児のコミュニケーション手段と家庭の言語環境 : 保護者調査から
- 著者
- 大土 恵子
- 出版者
- 大阪樟蔭女子大学
- 雑誌
- 研究紀要 = Research Bulletin of Osaka Shoin Women's University (ISSN:24322458)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.65-74, 2023-01-31
- 著者
- 藤谷 祐太
- 出版者
- 立命館大学
- 雑誌
- Core ethics : コア・エシックス (ISSN:18800467)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.319-332, 2008
6 0 0 0 OA 4.尿中NAG,尿中β2ミクログロブリン―尿細管障害・AKIとバイオマーカー―
- 著者
- 湯澤 由紀夫 伊藤 功
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.5, pp.971-978, 2008 (Released:2012-08-02)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 4 6
腎疾患,特に急性腎疾患ではより早期に障害を特定し治療を開始することが重要であるが,腎機能評価のスタンダードである血清クレアチニンの上昇は,腎不全の確立を特定するにほかならない.尿細管障害の鋭敏な指標として,尿中尿細管酵素,低分子量蛋白である尿中NAGや尿中β2ミクログロブリンが,海外ではα1ミクログロブリンが用いられている.急性腎障害をより早期に特定し治療成績を改善するべく,新たな優れたバイオマーカーの研究・開発が急がれている.
6 0 0 0 OA Ⅰ道南のアイヌの人びとの生活相―菅江真澄の民俗図絵より
- 出版者
- 神奈川大学21世紀COEプログラム研究推進会議
- 雑誌
- 『日本近世生活絵引』北海道編
- 巻号頁・発行日
- pp.02-36, 2007-12-20
6 0 0 0 OA スウェーデンにおける移民の流入と居住分化─イェーテボリを事例として─
- 著者
- 川瀬 正樹 カワセ マサキ Masaki Kawase
- 雑誌
- 修道商学
- 巻号頁・発行日
- vol.57-2, pp.95-120, 2017-02-28
6 0 0 0 IR グリム童話と『日本の昔ばなし』の比較 : 変身について
- 著者
- 太田 伸広
- 出版者
- 三重大学人文学部文化学科
- 雑誌
- 人文論叢 (ISSN:02897253)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.39-65, 2012
人間の動物への変身は『日本の昔ばなし』では神罰や罰、感情の昇華としての変身であり、人間に戻らないが、グリム童話では魔法や呪いなど異界がらみの変身であり、基本的に人間に戻る。前者は神罰などがあるにもかかわらず宗教的でないが、後者は神様が登場しないのに宗教的である。動物の人間への変身は『日本の昔ばなし』ではありふれており、本当の動物が本当の人間になり、また動物に変身したりするが、グリム童話では本当の動物が人間に変身する話は1話しかない。『日本の昔ばなし』は動物を人間として迎え入れ、子供ももうけるが、グリム童話にはそんな話は1話もない。前者は動物と人間を隔てる壁は低く、動物へのまなざしは暖かく優しいが、後者は動物への視線は蔑みである。前者は輪廻転生、後者はキリスト教の思想(動物を支配すべく人間を神が創造)の影響があろう。また『日本の昔ばなし』には人間や動物さえ神さまになる話もあるが、グリム童話にはない。ここにも一切衆生悉有仏性という仏教思想と神を頂点とする世界秩序を宗教原理とするキリスト教の違いも反映されているであろう。
6 0 0 0 OA 【研究ノート】ゴスロリが持ち得る臨床心理学的可能性
- 著者
- 徳山 朋恵 Tomoe TOKUYAMA 京都文教大学大学院臨床心理学研究科 Kyoto Bunkyo University Graduate School of Clinical Psychology
- 雑誌
- 臨床心理学部研究報告 = Reports from the Faculty of Clinical Psychology, Kyoto Bunkyo University (ISSN:18843751)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.71-84, 2015-03-31
Gothloli have been reported in many fields. However, it leads to be reported sporadically due to diversified standpoints. The purpose of this paper is to understand what kind of phenomenon is happened and how this is happened, and how one feel when one wear Gothloli from the clinical psychological standpoint. First, I classified Gothloli into 3 groups: Gothic, Lolita, and Gothic&Lolita. I summed up the study about these groups and the scheme of these things. After that, I defined the meanings of Gothic, Lolita, and Gothic & Lolita in this paper. Gothic is the deviation from society and dark view of world, and intention of transcendent material. Lolita is awareness and affirming their own dream, ideal, an unreal longing world leading to the prettiness or the girlness whatever one wear. Gothic&Lolita is combining both meanings. Second, I summed up the study of clothing psychology. Especially, the 3 points are shown in this paper: that wear relates to many kind of desire according to Maslowʼs desiring levels, that wearer decides to wear the clothes by unreal and real body scheme and self-concept, and that wear express positive or negative feelings and a sense of shame. I found that in the clinical psychological study of Gothloli, a certain paper mentioned Gothloli relates to stabbing incident in 2003, another paper said with standpoint of narcissism and phenomenology, although there are only a few studies. I interviewed 6 people and revealed that relationship between wearer and Gothloli by classifying the pattern of interview result with KJ method. In addition, I found that the difference how one think about Gothloli for wearer by the PAC analysis for 3 people. Here, I approached the mechanism model how one feel when wearing Gothloli. However, the problem of low number of subject person is still remained. Hereafter, It might be needed the additional research with more interview result, related clothing psychological research, and psychological research of cloth except for Gothloli or makeup.
6 0 0 0 OA 界面活性剤の皮膚常在菌への影響
- 出版者
- 地方独立行政法人 大阪健康安全基盤研究所
- 雑誌
- 大阪府立公衆衛生研究所 研究報告 (ISSN:21854076)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.47-52, 2009 (Released:2019-07-31)
合成界面活性剤は家庭内では多くの場面に使用されている化学物質である一方、合成洗剤、洗浄剤による皮膚障害が問題となっている。これは界面活性剤によって皮膚のバリアが破壊されることが、原因のひとつと考えられる。また界面活性剤の抗菌作用による皮膚常在菌への影響が一因ではないかと考え今回、市販の基剤も含めて検討を行った。その結果、抗菌性を有する陽イオン系以外に陰イオン系や非イオン系の一部に皮膚常在菌等に対する生育抑制が見られ、皮膚常在菌への影響が示唆された。
6 0 0 0 IR 子どもの貧困、その背景に隠れたものとは : 10 年の取材を通して
- 著者
- 西田 真季子
- 出版者
- 北海道大学大学院教育学研究院・教育福祉論研究グループ
- 雑誌
- 教育福祉研究 (ISSN:09196226)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.107-118, 2019-02-08
6 0 0 0 OA 航空機用燃料タンク清掃作業において発生した四エチル鉛中毒
- 著者
- 山村 行夫 高倉 淳 平山 二三夫 山内 博 吉田 稔
- 出版者
- 社団法人 日本産業衛生学会
- 雑誌
- 産業医学 (ISSN:00471879)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.4, pp.223-235, 1975 (Released:2011-03-04)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 2
Two cases of tetraethyl lead (TEL) poisoning are described. Both subjects had been exposed to TEL in the process of scaling using high pressure water stream during the cleaning work inside the aviation fuel tank. The aviation fuel contains TEL in a concentration of 1. 12 g lead per liter. The affected men failed to wear respirators during the cleaning work because the explosimeter indicated a negative reading for petrol. After one hour of tank cleaning work they suffered from lacrimation, running rhinorrhea and vomiting.Case 1. A 54-year-old man was admitted to a general hospital 3 days after the exposure to TEL and complained of hand tremors, amnesia and disorientation. He was restless, violent and confused in the night. On 12th day after the exposure to TEL, the condition bacame worse with marked agitation, delirium, convulsion, fever and coma. He died on 18th day after the exposure to TEL. During the admission, urinary coproporphyrin and basophilic stippling cells were normal ; no blood and urinary lead determination were done.Case 2. A 48-year-old man, on 2nd day after the exposure to TEL complained of chills, tremors, marked nausea and vomiting which persisted all night. Next morning he was admitted to another hospital. He had generalized tremors, ataxia, disorientation and at night he was suspicious, restless and violent. On 9th day after the exposure to TEL, his insomnia and restlessness gradually improved and he was discharged two months later.In this case, urinary lead determinations were done serially from 20 days to 196 days after the accident and blood lead determination was done once a week. On 20th day after the exposure, blood lead level was 52.3μg/100g, urinary lead concentration 586 μg/l and erythrocyte ALA dehydrase (ALA-D) activity was markedly reduced to 0.11μ mole PBG/ml RBC/hr. On 196th day after the exposure to TEL, his condition was both physically and mentally normal but his blood lead level was slightly elevated to 26. 1 μg/100 g and the urinary lead concentration was still at 37.0μg/l (81μg/24hr). Blood triethyl lead levels were found to be 5.8μg Pb/100g after 56 days, steadily decreasing thereafter to 1.3μg Pb/100 g up to 196 days.In this case, the reactivation of erythrocyte ALA-D and the fall of blood lead levels occurred simultanously in a manner similar to that observed in men exposed to inorganic lead. The regression line for erythrocyte logarithmic ALA-D activities and blood lead levels in this case is identical to that obtained from workers exposed to inorganic lead and the control group occupationally unexposed. These results suggest that the reduced erythrocyte ALA-D activities found in the TEL poisoning was due to inorganic lead resulting from the decomposition of TEL.Workmen handling antiknock additives were investigated regarding potential hazardous effects of tetraalkyl lead (TAL). The subjects consisted of workmen who engaged in mixing TAL into petrol, transportation of TAL by trucks or barges and storage tank cleaing. There were no abnormal values of blood lead levels, erythrocyte ALA-D activities or excreted urinary lead in those workmen.
6 0 0 0 OA 成人特発性血小板減少性紫斑病治療の参照ガイド 2019改訂版
- 著者
- 厚生労働省難治性疾患政策研究事業 血液凝固異常症等に関する研究班 「ITP治療の参照ガイド」作成委員会 柏木 浩和 桑名 正隆 羽藤 高明 高蓋 寿朗 藤村 欣吾 倉田 義之 村田 満 冨山 佳昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本血液学会
- 雑誌
- 臨床血液 (ISSN:04851439)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.8, pp.877-896, 2019 (Released:2019-09-04)
- 参考文献数
- 163
- 被引用文献数
- 11
- 著者
- 杉浦 郁子
- 出版者
- アジア女性資料センタ-
- 雑誌
- 女たちの21世紀
- 巻号頁・発行日
- no.37, pp.26-29, 2004-02
- 被引用文献数
- 1
6 0 0 0 OA 酒類中の成分がGABAレセプターに与える効果
- 著者
- 青島 均
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, no.4, pp.208-222, 2008-04-15 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 41
アルコール飲料が生体に及ぼす影響は多岐にわたるが, 最近その香気成分が注目され, 神経受容体, 特にGABAAレセプターに対する効果について著者らにより検討されてきた。本稿では中枢神経の受容体機構との関連からウイスキービール, カフェインに対するGABAAレセプターの応答に関する新しい知見を紹介していただいた。
6 0 0 0 OA 火山岩の空隙率及び浸透率測定の簡便法
- 著者
- 竹内 晋吾
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本火山学会
- 雑誌
- 火山 (ISSN:04534360)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.4, pp.501-511, 2022-12-31 (Released:2023-01-30)
- 参考文献数
- 41
6 0 0 0 近世の津軽アイヌ社会における襲名慣行
- 著者
- 上田 哲司
- 出版者
- 吉川弘文館
- 雑誌
- 日本歴史 (ISSN:03869164)
- 巻号頁・発行日
- no.835, pp.33-49, 2017-12