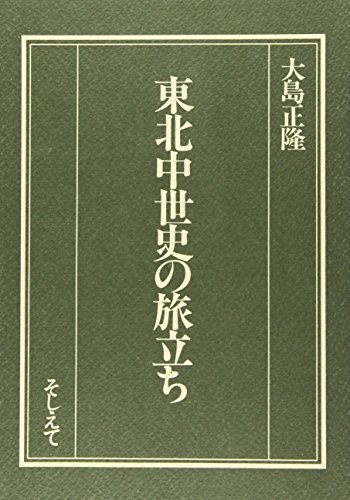6 0 0 0 OA 日本電産の M&A 戦略と限界利益管理型管理会計
- 著者
- 吉川 晃史
- 出版者
- 公益財団法人 牧誠財団
- 雑誌
- メルコ管理会計研究 (ISSN:18827225)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.65-74, 2010 (Released:2015-11-17)
- 参考文献数
- 5
6 0 0 0 OA 日本古墳の構造研究
- 著者
- Takashi Wakahara Nobuaki Wada
- 出版者
- Japanese Association for Acute Medicine
- 雑誌
- Nihon Kyukyu Igakukai Zasshi (ISSN:0915924X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.175-180, 1994-04-15 (Released:2009-03-27)
- 参考文献数
- 11
A 18-year-old man was admitted with a complaint of enormous abdominal distension and gasping respiration. The patient's colon was inflated as a result of having compressed air forced through the anus by his fellow worker. Chest and abdominal X-ray and arterial blood gas analysis revealed enormous pneumoperitoneum, hypercapnia and hypoxemia (pH 7.10, PCO2 84.9mmHg, PO2 33.5mmHg). A large amount of gas (air) was released from the abdomen by puncture on the right upper quadrant, and hypercapnia was rapidly improved. Gastrografln enema revealed rupture of the transverse colon and emergency operation was performed. There was a rupture, 3cm in diameter, in the transverse colon along the tenia coli omentalis. Multiple serosal tears (16 in total) were also found throughout the remaining colon.
6 0 0 0 IR 建仁寺の古建築 その奇構
- 著者
- 永井 規男
- 出版者
- 関西大学博物館
- 雑誌
- 関西大学博物館紀要 (ISSN:13414895)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.100-124, 2005-03-31
平成十六(二〇〇四)年度建仁寺護国院の建築及び障壁画の調査研究報告<論文・資料紹介>
6 0 0 0 OA 5年以上経過を追えた自己免疫性自律神経節障害の3例
- 著者
- 黒野 裕子 鳥飼 裕子 原 一 岡村 正哉 國本 雅也
- 出版者
- 日本神経学会
- 雑誌
- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)
- 巻号頁・発行日
- pp.cn-001793, (Released:2022-10-26)
- 参考文献数
- 14
5年以上経過を追えた抗自律神経節アセチルコリン受容体抗体陽性で自己免疫性自律神経節障害(autoimmune autonomic ganglionopathy,以下AAGと略記)と診断された3例の経過を報告する.1例目は20代女性で慢性経過の羞明・便秘・無月経を認めたが,血漿交換後,症状は緩解した.感冒を契機に一度再発したが,2度の妊娠による悪化はなかった.2例目は60代男性で急性の起立性低血圧(orthostatic hypotension,以下OHと略記)と精神症状で発症した.再燃を繰り返し治療に難渋したが,経過8年時,特に原因なく状態が安定した.3例目は80代女性で慢性経過のOHで再燃を繰り返した.経過中,OHによる転倒で大腿骨を骨折し歩行困難となった.AAGの長期観察例の報告は少なく,臨床経過を観察する上で貴重と考え報告する.
6 0 0 0 OA イタリア憲法学の歴史的素描(1)マウリツィオ・フィオラヴァンティ
- 著者
- 高橋 利安 Toshiyasu Takahashi
- 出版者
- 広島修道大学ひろしま未来協創センター
- 雑誌
- 修道法学 = Shudo Law Review (ISSN:03866467)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.163-180, 2022-09-30
6 0 0 0 OA 数学の活用力を高める指導についての研究 関係の表象を中心として
- 著者
- 眞渕 綾希 秋田 美代
- 出版者
- 一般社団法人 数学教育学会
- 雑誌
- 数学教育学会誌 (ISSN:13497332)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3-4, pp.117-126, 2013 (Released:2020-04-21)
本研究の目的は,数学の授業の中で生徒の創造的な問題解決力を育成することである。そこでは,生徒に問題解決の背景にある数量,図形の関係や構造を意識させて既習事項を高める方法を提案した。「連立方程式の解き方」を題材として,共通な関係の表象のための方略を導入し,「複数の表現の提示」,「複数の表現の比較」,「共通性の把握」という3つのステップで,既習の知識を新しい問題解決に活用を生徒に意識させた。実践の結果,生徒は関係を表象し,なぜそのような解き方をするのかについての理解を深めることで,既習の知識の活用について実感することができたことが分かった。
6 0 0 0 OA 初等中等教育における情報教育
- 著者
- 堀田 龍也
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.3, pp.131-142, 2016-12-24 (Released:2017-03-23)
- 参考文献数
- 68
- 被引用文献数
- 5
我が国の初等中等教育における情報教育について,その定義,教育内容や教育課程における制度的な位置付け,関連する調査研究等の結果を示し,日本教育工学会における初等中等教育を対象とした情報教育の研究についてレビューした.これらのレビューから浮かび上がる教育工学に対する要請について,(1) 政策立案への継続的な関与,(2) 国が実施できない精緻な調査,(3) 情報教育の実践を評価する指標の開発,(4) 実践の長期化を支えるシステムの開発,(5) 実践的な研究を査読論文にするための知見共有の仕組みの5点に整理した.
- 著者
- 金丸 麻衣 峠岡 理沙 山里 志穂 堀田 恵理 益田 浩司 加藤 則人
- 出版者
- 日本皮膚科学会大阪地方会・日本皮膚科学会京滋地方会
- 雑誌
- 皮膚の科学 (ISSN:13471813)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.38-41, 2019 (Released:2019-08-13)
- 参考文献数
- 13
20歳代,女性。両上下眼瞼の紅斑を主訴に当科を受診した。患者はマスカラを日常的に使用していた。使用していた各種化粧品,外用薬,点眼薬,およびジャパニーズスタンダードアレルゲンによるパッチテストを施行したところ,マスカラ,フラジオマイシン,ペルーバルサム,ロジン,香料ミックスが陽性となった。マスカラの成分別パッチテストを行ったところ,カルナウバロウが陽性となった。カルナウバロウは化粧品や各種ワックス製品に含まれる他,食品や医薬品の添加物として用いられるが,接触皮膚炎の報告は非常に少ない。カルナウバロウに含まれるケイ皮酸がペルーバルサムと香料ミックスとも共通することから,マスカラに含まれたカルナウバロウ中のケイ皮酸によってアレルギー性接触皮膚炎を発症した可能性を考えた。また,外用薬に含まれた硫酸フラジオマイシンに対するアレルギー性接触皮膚炎も合併していた。パッチテストでロジンにも陽性を示し,香料アレルギーの可能性が示唆された。 (皮膚の科学,18 : 38-41, 2019)
6 0 0 0 IR アンケート調査報告 「モンスターペアレント」の実相
- 著者
- 尾木 直樹
- 出版者
- 法政大学キャリアデザイン学部
- 雑誌
- 法政大学キャリアデザイン学部紀要 (ISSN:13493043)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.99-113, 2008-03
The expression "monster parent" is a Japanese-English term for parents who make unreasonable demands and requests of the school like a monster.This is similar to the notion "helicopter parent" in the United States. In this study, a nationwide survey about this widely known problem among Japanese was executed in order to understand actual situation in schools. The results showed that most teachers admit there is an increase in "monster parents." This study was able to categories five types of "monster parents." namely, "My Child-centered (overprotective)," "Negligent," "Non-Moral," "School Dependent," and "Maker of Excessive Claims."Why did such parents come to appear? The research results point out the influence of the social trend of the consumer supremacy these days, which enables parents to lodge an objection against anything with the appearance of parents, resulting in "my child centrism" and "Selfish parents."Moreover people are often isolated as parents in a local area, without friends who can hear their concerns and worries, so the complains go to directly to the school, which have difficulty fielding the complaints. In addition, this problem occurred due to loss of authority of the "school selection system" even for elementary and junior high schools and I could call these phenomina "merchandization of school." Then, how should we resolve this problem? The Ministry of Education, Culture, Science and Technology attemped to instigate "School problem solving support team," but there were only 23% in my questionnaire that supported this idea. The remaining people seem to think that a powerful team consisting of lawyers, psychiatrists, and ex-police cannot be a solution of this problem. The most popular suggestion for a solution was "mutual understanding between parents and the teachers." In a sense, it was a relief to see result, including that there is no need to establish any innovative system, but must keep making an honest effort. All we have to do is make sure that system will support advancement of "mutual understanding". Also, the school relies on neither the system nor the action treatment of the education but to value the principle. The "monster parent" phenomenon is not only a problem of schools but also a social phenomenon which should the government should make an effort to resolve by making an increase in the educational budget.
6 0 0 0 OA ヌマチチブ非在来個体群におけるミトコンドリアDNAの地理的変異
- 著者
- 向井 貴彦 西田 睦
- 出版者
- The Ichthyological Society of Japan
- 雑誌
- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.133-140, 2005-11-25 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 4
The geographical distributions of mitochondrial DNA (mtDNA) haplo-types in non-indigenous populations of a freshwater goby, Tridentiger brevispinis, were investigated. Although 26 mtDNA haplotypes were obtained from 168 individuals (including a closely-related species, T. obscurus) representing 36 indigenous populations, only two haplotypes (I-Al and III-B1) were found in 59 individuals of T.brevispinis from 12 non-indigenous populations. Many of the latter had the I-Al haplotype, thepopulations being located near indigenous populations having the same haplotype. A non-indigenous population in Lake Biwa had the III-B1 haplotype, the lake being close to the natural distribution area of that haplo-type. Thus, the non-indigenous populations of T. brevispinis may have become es-tablished following artificial transplantations from nearby populations. The III-B 1 haplotype, however, was also scattered throughout geographically-distant, non-in-digenous populations, its dispersal possibly having been a consequence of trans-plantation of Ayu (Plecoglossus altivelis), from Lake Biwa, accompanied by T. brevispinis. However, the primary cause of the expansion of non-indigenous goby populations retains unclear.
6 0 0 0 OA 憲法学からみた家族の「公」と「私」-吉田克己報告へのコメント
- 著者
- 高井 裕之
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.2000, pp.62-66, 2001-10-30 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 13
6 0 0 0 OA 指さし行動の発達的意義
- 著者
- 秦野 悦子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.255-264, 1983-09-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 55
- 被引用文献数
- 1 1
6 0 0 0 OA プライマリ・ケアの質評価─患者経験を中心として
- 著者
- 青木 拓也
- 出版者
- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会
- 雑誌
- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.40-44, 2015 (Released:2015-03-27)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1 1
プライマリ・ケアの質を評価する重要性は一層高まっており, 海外ではプライマリ・ケアの原理およびタスクに関する質指標が, 政策決定や医療提供者の質向上等に活用されている. 中でもプライマリ・ケアの原理を評価する上で, 患者中心性は重要な概念であり, 欧米では質評価尺度を用いた患者経験調査が実施されている. 残念ながら, 我が国での質評価に関する実効的な取り組みは現状では乏しいが, 先行研究によれば, 我が国で重要なプライマリ・ケアの原理は, 近接性, 包括性, 協調性, 時間的継続性, 良好な患者医師関係 (対人的継続性) , 地域志向性, 家族志向性と考えられる. 今後患者中心性を始め, 有効性や患者安全等, 複数の側面からの評価を通し, プライマリ・ケアの質的整備を推進していく必要がある.
6 0 0 0 OA イタリア合理主義建築運動における詩学と修辞 : エドアルド・ペルシコと近代の葛藤
- 著者
- 鯖江 秀樹
- 出版者
- 美学会
- 雑誌
- 美學 (ISSN:05200962)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.127-139, 2008-06-30
This paper aims at investigating the peculiar aspects of Italian architectural culture under the fascist regime. Edoardo Persico, the most important critic of architecture between the two wars, recognized well that political powers and architecture crossed on the critical discourse. From this point of view, he defined the short history of this Italian movement as a process from 'europeismo' to 'romanita', and to 'mediterraneita'. These notions do not imply the supremacy of Italian ethic and nation, but demonstrate that young architects, who had been eager to introduce European modern building styles into their own country, was subordinated to political requests of fascism. Yet it was more important for Persico to reveal the rhetorical mechanism that obstructed the European artistic taste ('gusto europeo') and also disguised the Italian one ('gusto italiano') as they were. Hence his analysis of a lot of reviews appeared on the catalogues or magazines proved the diversity of the modern culture. Persico was the only writer that could describe the whole space of critical discourse as a matrix of fascist cultures with some paradoxical characters.
6 0 0 0 OA 「狸の腹鼓の音」について
- 著者
- 横井 雅之
- 出版者
- 大阪産業大学学会
- 雑誌
- 大阪産業大学人間環境論集 = OSAKA SANGYO UNIVERSITY JOURNAL OF HUMAN ENVIRONMENTAL STUDIES (ISSN:13472135)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.79-87, 2019-03-30
狸の腹鼓といえば,童謡の「証城寺の狸囃子」にでてくる「ぽんぽこ ぽんの ぽん」というリズム感のある歌詞が懐かしく思い出される人が多いと思われる。科学者・随筆家としてよく知られている寺田寅彦も「狸の腹鼓」という随筆を書いている。それは寺田寅彦全集第9巻の「狸の腹鼓」( 原文はローマ字で書かれていて,タイトルは「Tanukino Haratudumi」)という2ページあまりの小文である。この文中で,『朧月夜に狸が腹鼓を打つと言われているが,音源を突き止めて,本当に狸が腹の太鼓を叩いているのを見たという人は滅多にいない。』ことを取り上げて,『世の中には証拠,少なくとも物質的に証拠のないことを信じている人はいくらでもある。』,『我々の目に見,耳に聞く世界のさまざまもみんな狸の腹鼓と同じで,それらの“もと”を突き止めた人はまだありそうにない。』と述べている。 「狸の腹鼓」という言葉は狂言および囲碁の世界でも使われている。狂言では,雌狸が尼に化けて猟師に殺生をいさめるが,見破られて命乞いに腹鼓を打ち,隙をみて逃げるというあらすじである。囲碁では,「狸の腹つづみ」と称する「妙手」として取り上げられることが多い。 ここでは,「狸が腹鼓を打つ時に発生する音」について,現在入手できる資料等から音の性質や発生メカニズムを突き止めようと試みた。
6 0 0 0 アニメーション「宇宙戦艦ヤマト」- : 音楽考察
- 著者
- 興津 健蔵
- 出版者
- プール学院大学
- 雑誌
- プール学院大学研究紀要 (ISSN:13426028)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.375-386, 1999-12-31
6 0 0 0 IR 現在の障がい者施設支援に関する研究 : 利用者、保護者、事業責任者の視点から
- 著者
- 佐々木 勝一 竹内 弘美
- 出版者
- 京都光華女子大学
- 雑誌
- 京都光華女子大学研究紀要 (ISSN:13465988)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.357-381, 2008-12
6 0 0 0 IR 〈論説〉アイドル150年 : アイドル・ブームと長期波動
- 著者
- 平山 朝治
- 出版者
- 筑波大学経済学専攻
- 雑誌
- 筑波大学経済学論集 = The University of Tsukuba economic review (ISSN:03858049)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, pp.1-123, 2018-03-31