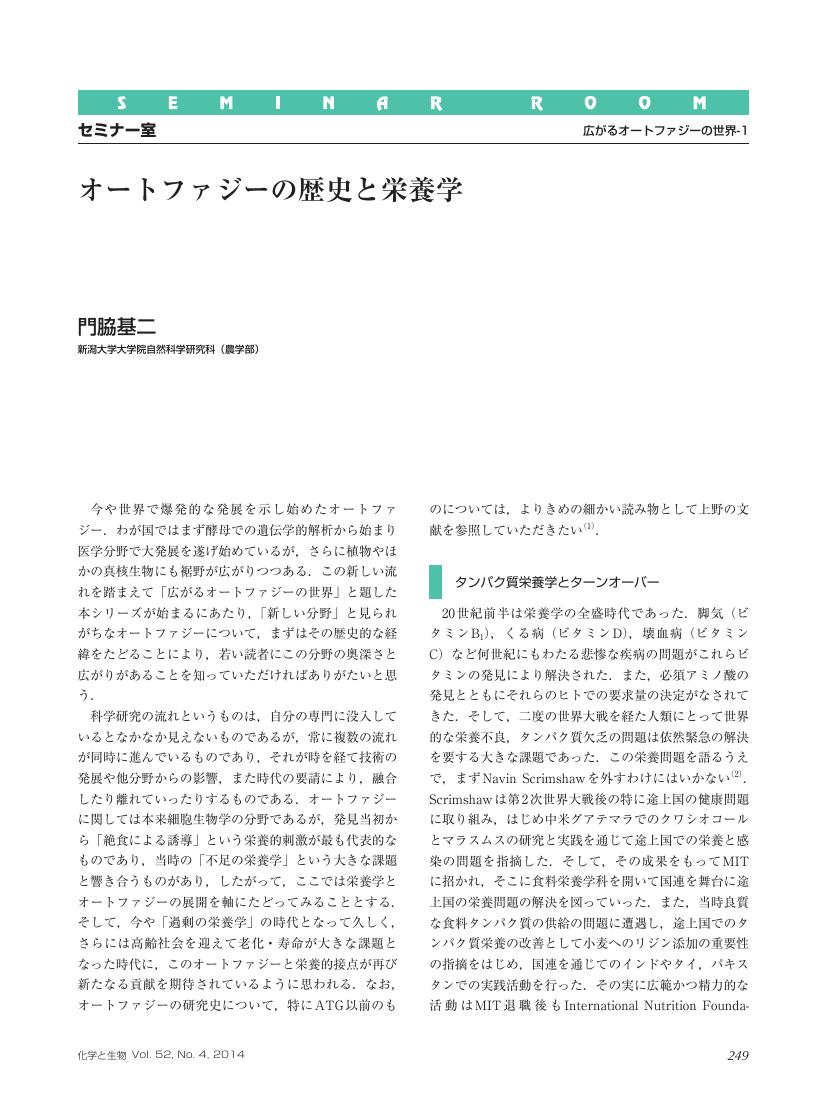3 0 0 0 OA 宗教と素朴な宗教的感情
- 著者
- 林 文
- 出版者
- 日本行動計量学会
- 雑誌
- 行動計量学 (ISSN:03855481)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.13-24, 2006 (Released:2006-04-13)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 2 6
In the contemporary world conflicts of different cultures among different nations and regions have become a serious problem. Specifically, religions exist as the basis for different cultures. In our Cross-national survey results, it was found that only 30% of the Japanese have religious faith but 70% think that religious feeling is important and that the meaning of religion is different between the Japanese and Westerners based on our cross-national surveys. The meaning of religion can be understood in the relation between religious attitudes and other social attitudes. The structure of thinking about religion and its relation to other items in our East Asia Value Survey were analyzed using multivariate analysis. The results concerning the differences among these areas were as follows. In Japan, Korea and Hong-Kong, satisfaction about daily life and religious feeling are related positively, whereas in Beijing, Shanghai and Taiwan, these are related negatively. Concerning attitudes toward science and technology, in some areas, including Japan, the medium attitude is related to religious feeling. We are continuing our on-going analysis toward seeking the meaning of religion in contemporary societies by including the results of seven Western nations' surveys.
3 0 0 0 OA 膵・胆管合流異常の診療ガイドライン(日本膵・胆管合流異常研究会・日本胆道学会編)
- 著者
- 島田 光生 神澤 輝実 安藤 久實 須山 正文 森根 裕二 森 大樹
- 出版者
- 日本胆道学会
- 雑誌
- 胆道 (ISSN:09140077)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.5, pp.678-690, 2012 (Released:2013-08-05)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 2
要旨:膵・胆管合流異常は解剖学的に膵管と胆管が十二指腸壁外で合流し,膵液と胆汁の相互逆流により,さまざまな病態を惹起するとともに胆道癌の発生母地ともなる.本疾患は不明な点が多く,また未だに治療方針も統一されていないのが現状である.今回,日本膵・胆管合流異常研究会と日本胆道学会が合同で,本疾患に対して病態から診断,治療に至るまでの膵・胆管合流異常診療ガイドラインを世界で初めて作成したのでダイジェスト版として紹介する.
3 0 0 0 OA 政党システムの分析における地方と新党
- 著者
- 砂原 庸介
- 出版者
- 日本選挙学会
- 雑誌
- 選挙研究 (ISSN:09123512)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.43-56, 2011 (Released:2017-07-03)
- 参考文献数
- 92
政党システムの分析において,これまで注目されてきたのは,基本的には社会的亀裂と政党システムの存続・変化との関係であり,地方の多様性や新党の存在は,必ずしも注目されてこなかった。しかし,近年の研究においては,地方の多様性や新党の参入を政党システムの存続・変化と結びつけた議論が進められている。本稿では,そのような議論を整理した上で,地方の多様性や新党の参入を含めて政党システムを包括的に捉える政党システムの制度化というアプローチを紹介し,今後の研究においては中央レベルと地方レベルの政党間競争を動態的に捉える観点が重要になることを指摘する。
3 0 0 0 OA ドクガ Euproctis flava とその病害に関する研究 : 第 3 編疫学的研究
- 著者
- 緒方 一喜
- 出版者
- 日本衛生動物学会
- 雑誌
- 衛生動物 (ISSN:04247086)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.4, pp.228-234, 1958-12-10 (Released:2016-09-04)
- 被引用文献数
- 1 3
ドクガEuproctis flava Bremerの疫学的性格を論じ, 東京附近の被害実態を疫学的に検討した.1.日本産Euproctis属10種について, 毒針毛保有の有無, 発生量について検討した結果, E. similis, xanthocampa, piperita, pulverea, kurosawai, pseudoccnspersa, staudingeriの8種は, flava類似の毒針毛を持つ事を確めた.E. torasan, curvataでは確認し得なかつたが, 被検標本が雄成虫だけであつたためであろうと考える.2.E. flavaを含めて, 毒針毛をもつ少くとも, 上記8種について比較してみると, 種によつて疫学相が甚だしく違う.わが国で普通に害を与える重要な種は, flavaとpseudoconspersaの2種で, 特に前種が甚だしい.これは, 異常的な大発生をして, 他の種に比べて発生量が桁はずれに大きい点に原因があるように考えた.3.わが国のドクガ大発生地は, 比較的限られているが, 共通した棲息環境として, 低い灌木叢林と, 瘠悪土壤の丘陵地帯が多い事を指摘した.4.古くから日本各地でドクガの大発生はみられていたのであるが, 最近に到つて, 大きな社会問題となつた.この理由について二・三考察したが, 大きな原因は人間の心理的, 社会的な変化に基くものであろうと推察した.5.東京都内で, 1956, 57年に起つたEuproctis属の種類による被害は, ドクガ成虫によるものが一番多く, チャドクガ幼虫, 成虫によるものも少なからずあつた.6.ドクガ成虫による被害は, 職業別に, 家庭の主婦, 勤め人, 学生に多い.罹患場所は, 殆んど屋内で, 18時から24時までの前夜半に多い.6時から10時までの朝にも少しみられた.罹患部位は, 腕, 胸部, 首に多い.また, 被害は, 1頭の成虫で1人の罹患者が出る場合が一番多かつた.7)ドクガの蛹による被害は1例もなく, 幼虫によるもの2例, 卵によるもの1例があつた.8)チャドクガ幼虫による被害は, 罹患時刻が昼間に多く, また罹患場所は全例が庭である点が, ドクガ幼虫の場合と異るが, 他の疫学相はよく類似していた.
3 0 0 0 OA ニューラルネットワークを用いた強化学習のためのネットワークパラメータ設定法
- 著者
- 山田 和明 大倉 和博
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集C編 (ISSN:18848354)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.792, pp.2950-2961, 2012 (Released:2012-08-25)
- 参考文献数
- 17
Reinforcement learning approaches attract attention as the technique to construct the mapping function between sensors-motors of an autonomous robot through trial-and-error. Traditional reinforcement learning approaches make use of look-up table to express the mapping function between the grid state space and the grid action space. However the grid size of the state space affects the learning performances significantly. To overcome this problem, many researchers have proposed algorithms using neural networks to express the mapping function between the continuous state space and actions. However, in this case, a designer needs to appropriately set the number of middle neurons and the initial value of weight parameters of neural networks to improve the approximate accuracy of neural networks. This paper proposes a new method to automatically set the number of middle neurons and the initial value of the weight parameters of neural networks, on the basis of the dimensional-number of the sensor space, in Q-learning using neural networks. The proposed method is demonstrated through a navigation problem of an autonomous mobile robot, and is evaluated by comparing Q-learning using RBF networks and Q-learning using neural networks whose parameters are set by a designer.
3 0 0 0 OA オートファジーの歴史と栄養学
- 著者
- 門脇 基二
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.4, pp.249-254, 2014-04-01 (Released:2015-04-01)
- 参考文献数
- 23
3 0 0 0 OA キビタキFicedula narcissinaの雄の齢査定法の検討
- 著者
- 岡久 雄二 小西 広視 高木 憲太郎 森本 元
- 出版者
- 日本鳥類標識協会
- 雑誌
- 日本鳥類標識協会誌 (ISSN:09144307)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.12-18, 2011 (Released:2012-11-25)
- 参考文献数
- 11
キビタキFicedula narcissinaの雄について,外部形態に基づく齢査定の方法を検討した.第1回夏羽の個体は第2回夏羽以降の個体よりも自然翼長,尾長とも短かったが計測値は重複が大きかった.また,脛羽の色は第1回夏羽,第2回夏羽,それ以降の第3回夏羽以降の3群でそれぞれ異なっており,第1回夏羽では淡褐色,第2回夏羽では灰黒色の羽が疎らに生え,それ以降の第3回夏羽以降では純黒色の羽が密に生えていた.さらに,虹彩の色は第1回夏羽では灰褐色,第2回夏羽では褐色であり,第3回夏羽以降の個体の多くは赤褐色であった.これらより,キビタキの雄の齢は脛羽と虹彩の色によって第1回夏羽,第2回夏羽,第3回夏羽以降の3群に識別することができると考えられた.
- 著者
- Eigo TOCHIMOTO Tetsuya KAWANO
- 出版者
- (公社)日本気象学会
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.4, pp.217-237, 2017 (Released:2017-07-04)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 4
In Part I of this study, the development processes of Baiu frontal depressions (BFDs) have been examined through case-study numerical experiments. The numerical simulations revealed that latent heating is dominant for the development of BFDs in the western part of the Baiu frontal zone (W-BFDs), west of approximately 140°E, while both latent heating and baroclinicity are important for the development of BFDs in the eastern part of the zone (E-BFDs), east of approximately 140°E. In this study, idealized numerical simulations with zonally homogeneous basic fields are conducted to obtain a more generalized perspective of the development processes of BFDs. The basic fields for the idealized simulations are made from the composites of the environments under which 28 W-BFDs and 43 E-BFDs developed. The idealized simulations successfully reproduce a realistic W-BFD and E-BFD. The W-BFD has a slightly westward-tilted vertical structure, modulated by latent heating at low levels of the atmosphere. In contrast, the E-BFD has a westward-tilted structure through the troposphere, similar to the well-known baroclinic wave structure. Results of available potential energy diagnosis for the effects of latent heating and baroclinicity on the BFD development are consistent with those in Part I. The W-BFD has a mechanism mainly driven by latent heating yielding strong convection, while the E-BFD develops through baroclinic instability in moist atmosphere.
3 0 0 0 特集:「特許情報と人工知能(AI)」の編集にあたって
- 著者
- パテントドキュメンテーション委員会
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.7, pp.339-339, 2017-07-01 (Released:2017-07-01)
新聞やインターネットでは,毎日のように人工知能(AI:artificial intelligence)に関する記事が掲載されており,最近ではチェス・将棋だけでなく,より複雑といわれる囲碁で対局しても,名人に勝利できるほどに進化しているようです。日本国特許庁(JPO)でも,将来,人工知能を業務システムに組み込むことを検討していることについて,「特許庁における人工知能(AI)技術の活用に向けたアクション・プラン」や,「人工知能技術を活用した特許行政事務の高度化・効率化実証的研究事業」などの資料にて公表しました。また,ここ数年の間には,人工知能を用いて特許情報を分析・解析するというシステムが,各情報提供事業者より発表され,業務の効率化やユーザの問題解決に利用する動きが始まりました。一方で,数年前に話題となったオックスフォード大学の論文で,コンピュータ(人工知能)によって「消える職業」「なくなる仕事」として,サーチャーが上位にランクされたこともあり,特許情報の検索者とその業務は,人工知能によって,少しずつ業務の範囲を狭められていくのか,それとも共存していくのかについても,興味のあるところだと思います。そこで,今号では特許情報と人工知能(AI)というテーマで,人工知能という技術を特許情報に対しどのように適合させていくのか,あるいは,特許情報を人工知能というフィルタに通した場合,どのような知見をえられるのかについて,参考となる特集を企画しました。はじめに,桐山勉氏と安藤俊幸氏の共著による総論によって,現状における特許情報と人工知能の全体動向について論じていただきました。つづいて,岩本圭介氏には人工知能を用いた情報処理システムの概念と株式会社NTTデータ数理システムにおける分析ツールへの取組みについて,鈴木祥子氏には特許文書解析へのアプローチ方法と課題について,藤田肇氏には独自開発の人工知能エンジンについて,その開発の経緯や実務への応用例など,太田貴久氏には,特許情報を人工知能に適用させる際の問題点について,田辺千夏氏には,サーチャーとシステムユーザーという複数の視点から,人工知能というツールをどのように利用するのかについて,それぞれ解説をいただきました。今回の特集が,「人工知能」というツールに興味をもたれている方の参考になるだけではなく,既に利用されている方にも新しい何かに気づくきっかけになっていただくことになれば幸いです。(パテントドキュメンテーション委員会)
3 0 0 0 OA 「手話の復権」
- 著者
- Yasuko OKADA Tetsuya TAKEMI Hirohiko ISHIKAWA Shoji KUSUNOKI Ryo MIZUTA
- 出版者
- (公社)日本気象学会
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.4, pp.239-260, 2017 (Released:2017-07-04)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 20
This study investigates future changes in atmospheric circulation during the Baiu in Japan using 20-km-mesh atmospheric general circulation model (AGCM) simulations for the present-day (1979-2003) and the future (2075-2099) climates under the Representative Concentration Pathways 8.5 scenario. The simulated future climates include the outputs obtained with one control sea surface temperature (SST) and three different SST patterns. The Baiu frontal zone, defined as the meridional gradient of equivalent potential temperature, gradually moves northward during June–July–August in the present-day climate. In the future climate simulations using the control SST, the Baiu frontal zone is projected to stay to the south of Japan in June. Thus, precipitation is projected to increase over this region, while decreasing in the western part of Japan. Future changes in precipitation and atmospheric circulations in June are consistent across all four SST patterns. However, precipitation and atmospheric circulation in July and August in the future climate simulation depends on the SST patterns as follows: in non-El Niño-like SST pattern, the Baiu terminates in late July, similar to that of the present-day climate; a result with an El Niño-like SST pattern shows that sufficient amount moisture is transported to the Japanese islands and leads in a delay of the Baiu termination until August; and in the SST pattern with strong warming in the western North Pacific (WNP), a sufficient amount of moisture is transported to the south of Japan from June until August. The difference in the SST pattern leads to a variation in sea-level pressure in the WNP and affects a variation of the Northern Pacific subtropical high around the Japanese islands in July and August.
3 0 0 0 OA この本! おすすめします 編集に役立ったMS-DOS
- 著者
- 浦山 毅
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.12, pp.872-874, 2017-03-01 (Released:2017-03-01)
3 0 0 0 OA ローラー式絞り機と遠心脱水機による布の脱水と汚れ付着量
- 著者
- 佐藤 昌子 楠 幹江 奥山 春彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会
- 雑誌
- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.4, pp.123-128, 1974-04-25 (Released:2010-09-30)
- 参考文献数
- 4
目的: 脱水後の布の含水率が, 再汚染におよぼす影響を検討するため, ローラー式絞り機と遠心脱水機を用いて, 比較実験を試みた.方法: 試料布5種, 汚れ粒子2種, 界面活性剤3種を使用した.結果: (1) ローラー絞りでは, 含水率が減少するにつれて, 汚れ付着量も減少する傾向がみられるが, 脱水機では.必ずしも, 同様な傾向はみられなかった.(2) 同一含水率における汚れ付着量は, ローラー絞りよりも脱水機の方が多い.(3) 分散液の粒子の分散状態と汚れ付着量の関係は, 汚れ粒子や界面活性剤の性質などにより異なり, 種々の汚れ付着量を示す.
3 0 0 0 OA エクセルを使ったバイオメカニズムのための統計学(3)
- 著者
- 富田 豊 内山 孝憲
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.4, pp.221-225, 2004 (Released:2006-11-17)
- 被引用文献数
- 6 5
3 0 0 0 OA 電子情報資源管理システム
- 著者
- 尾城 孝一
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.8, pp.519-527, 2004 (Released:2004-11-01)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
近年,インターネットの普及と電子出版技術の進展に伴い,図書館を取り巻く情報環境は劇的な変化を見せている。図書館が収集,管理,保存,提供する資料も紙媒体から電子情報へと急速に移行しつつある。こうした背景の下で,電子情報資源を適切に管理し,利用者のアクセス環境を整備することが,図書館にとっての喫緊(きっきん)の課題として浮上してきた。本稿では,北米の大学図書館における取り組み,とりわけ,電子図書館連合(Digital Library Federation DLF)の電子情報資源管理イニシアチブ(Electronic Resource Management Initiative ERMI)の活動を中心に報告する。
3 0 0 0 OA Quest of Soil Protists in a New Era
- 著者
- Jun Murase
- 出版者
- 日本微生物生態学会 / 日本土壌微生物学会 / Taiwan Society of Microbial Ecology / 植物微生物研究会
- 雑誌
- Microbes and Environments (ISSN:13426311)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.99-102, 2017 (Released:2017-06-24)
- 参考文献数
- 66
- 被引用文献数
- 6
3 0 0 0 OA 世界の音楽科学習指導要領を比較する (1)
- 著者
- 小川 昌文 尾見 敦子 阿波 祐子 井下 べに 永岡 都 Alison M. Reynolds
- 出版者
- 日本音楽教育学会
- 雑誌
- 音楽教育学 (ISSN:02896907)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.54-58, 2015 (Released:2017-03-22)
- 著者
- 河野 裕美 水谷 晃
- 出版者
- 公益財団法人 山階鳥類研究所
- 雑誌
- 山階鳥類学雑誌 (ISSN:13485032)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.108-118, 2015-03-20 (Released:2017-03-20)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 3
カツオドリSula leucogasterは,世界の熱帯から亜熱帯海域に4亜種が分布する.本種は島嶼間の移動が少なく,遺伝的交雑が低いと考えられてきた.しかし,東太平洋海盆を挟んで西側に生息する亜種カツオドリS. l. plotusが東方へ,東側に生息する亜種シロガシラカツオドリS. l. brewsteriが西方へそれぞれ分散して繁殖した例が報告されている.さらに,西部太平洋に位置する琉球列島南部の仲ノ神島において,2009年5月17日に頭部から頸部が白色の亜種シロガシラカツオドリの成鳥の雄1羽が飛来した.その後,2014年まで,同じ場所で同個体と思われる雄が断続的に確認され,2012年から2014年まで仲ノ神島個体群の繁殖スケジュールと同調して,亜種カツオドリと思われる雌と繁殖し,雛を巣立たせた.さらに2011年以降には,同島の別の場所で白色頭部の雄1羽が断続的に記録されるようになった.この雄は雌に対する求愛を行ったが,2014年までつがいは形成されなかった.本観察により亜種シロガシラカツオドリの日本における繁殖行動が初めて確認され,同時に別亜種の繁殖地に飛来した個体によるつがい形成から繁殖までの過程を記録できた.
- 著者
- Anil Kumar Meher Yu-Chie Chen
- 出版者
- The Mass Spectrometry Society of Japan
- 雑誌
- Mass Spectrometry (ISSN:2187137X)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.S0057-S0057, 2017-03-18 (Released:2017-03-24)
- 参考文献数
- 147
- 被引用文献数
- 4 15
Generation of analyte ions in gas phase is a primary requirement for mass spectrometric analysis. One of the ionization techniques that can be used to generate gas phase ions is electrospray ionization (ESI). ESI is a soft ionization method that can be used to analyze analytes ranging from small organics to large biomolecules. Numerous ionization techniques derived from ESI have been reported in the past two decades. These ion sources are aimed to achieve simplicity and ease of operation. Many of these ionization methods allow the flexibility for elimination or minimization of sample preparation steps prior to mass spectrometric analysis. Such ion sources have opened up new possibilities for taking scientific challenges, which might be limited by the conventional ESI technique. Thus, the number of ESI variants continues to increase. This review provides an overview of ionization techniques based on the use of electrospray reported in recent years. Also, a brief discussion on the instrumentation, underlying processes, and selected applications is also presented.
3 0 0 0 OA 自動車運転時のヒヤリ・ハット体験と報酬の遅延価値割引との関連
- 著者
- 松本 明生 平岡 恭一
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- pp.88.16323, (Released:2017-05-10)
- 参考文献数
- 26
Impulsivity has been linked to traffic safety problems in many prior studies. However, it is not clear whether impulsivity, defined by the rate of discounting delayed monetary rewards, relates to drivers’ problematic behavior. We investigated the relationship between the discounting of hypothetical monetary outcomes and near accident (i.e. hiyari-hatto) experiences during driving among occupational drivers. A total of 189 occupational drivers (160 men) completed the delay discounting questionnaire and hiyari-hatto experiences scale. In completing the delay discounting questionnaire, participants were asked to perform the two delay-discounting tasks, in which they chose between ¥100,000 or ¥5,000 available after some delay (from 1 month to 5 years) or a lesser amount of money available immediately. Subjective equivalence points were obtained from participants’ choices on delay discounting questionnaires, from which the areas under the curve (AUC; Myerson et al., 2001) were calculated. The results indicated that the rate of discounting (AUC) was negatively correlated to near accident experiences. We discuss the need for future research on impulsivity, delay discounting, and traffic safety.