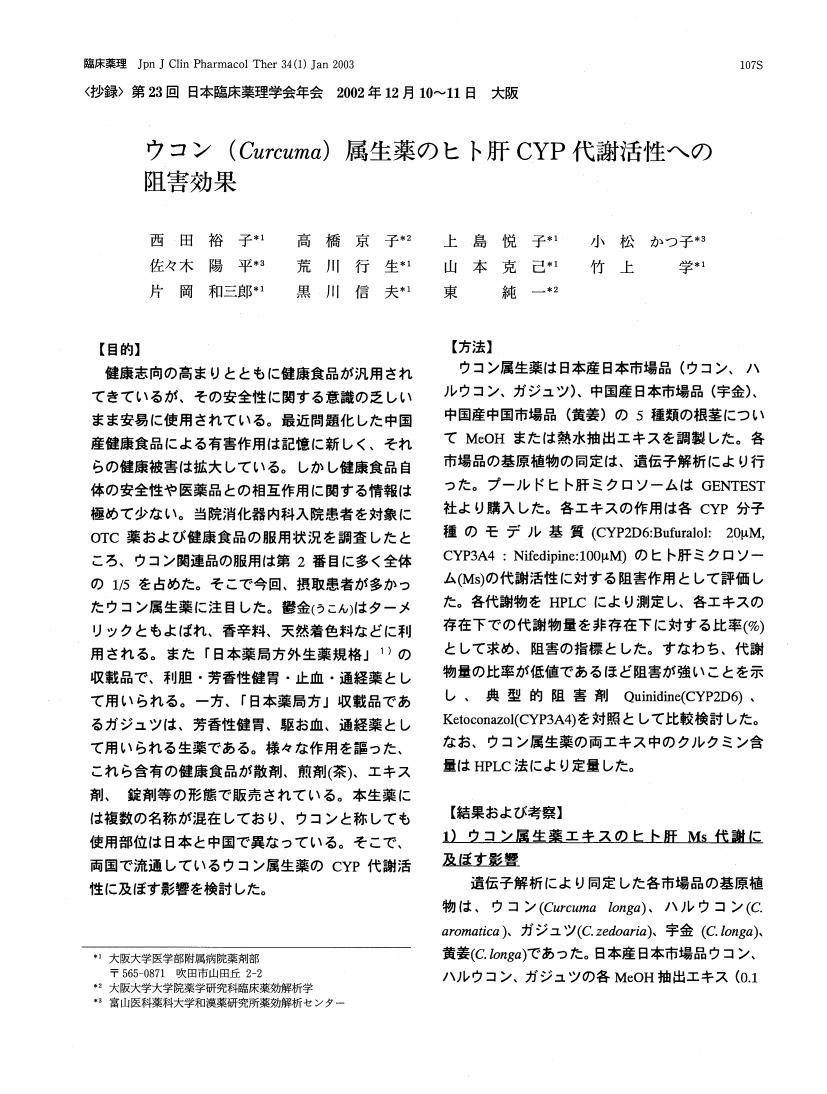- 著者
- 八尋 和郎 外井 哲志 梶田 佳孝
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.1, pp.37-42, 2011
近年、都市に人を集める産業としてプロ野球観戦が注目されており、その特性を把握することは有益であると考えられる。本研究では、福岡ソフトバンクホークス(野球チーム)の観戦者に対するアンケート調査によって、観戦者の特徴と観戦者がもたらす経済効果を分析し、以下のことが明らかになった。(1)遠方からの来場者や、1人で来た来場者は消費単価が高い。(2)試合観戦前後に、来場者は福岡ドーム(野球場)以外の場所にも立ち寄っており、都市の賑わいに貢献をしている。(3)プロ野球観戦に直接関係がない産業にも大きな需要が創出されている。(4)交通費は集客に対して大きな影響を与えている。以上より、福岡ソフトバンクホークスは都市に無視できない大きな影響を与えていることが分かった。
1 0 0 0 中高生の援助要請行動と他者配慮が適応感に及ぼす影響
- 著者
- 竹森 啓子 仲嶺 実甫子 佐藤 寛 下津 咲絵
- 出版者
- 日本認知療法学会
- 雑誌
- 認知療法研究 = Japanese journal of cognitive therapy (ISSN:18832296)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.206-216, 2018-08
1 0 0 0 OA 写真用レンズの最近の進歩
- 著者
- 脇本 善司
- 出版者
- 社団法人 日本写真学会
- 雑誌
- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.1-7, 1966-05-20 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 9
Photographic lenses have been manufactured for more than 100 years, and theoretical studies have also been continued throughout. Therefore, the progress was rather steady than striking. In recent years, however, some new types of the lenses have been developed, owing mainly to the use of new optical glasses and the introduction of an electronic computer to the lens design. Attempts have also been made to design lenses favorable for given camera mechanisms or properly corrected for newly developed emulsions. These trends will be discussed from the lens designer's viewpoint.
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1668, pp.46-49, 2012-11-26
プロ野球「福岡ソフトバンクホークス」のチケット販売やグッズの企画・販売などを手がける福岡ソフトバンクホークスマーケティングでコンシューマービジネス本部MD企画部部長を務める菊池隆昭氏は2011年8月下旬、東京・千駄ケ谷のエスプライドを目指して歩いていた。「面白い会社がある」。そう話を聞き、実際に訪問してみようと考えたからだ。
1 0 0 0 OA ウコン (Curcuma) 属生薬のヒト肝CYP代謝活性への阻害効果
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経情報ストラテジ- (ISSN:09175342)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.6, pp.54-59, 2008-07
北海道日本ハムファイターズは2006年と2007年に球団初のリーグ連覇を果たした。若手主体で勝ちまくるチームは観客を呼んだ。2007年の観客動員数はパ・リーグで福岡ソフトバンクホークスに次ぐ2位。長年リーグ下位を低迷し、人気もなかったチームに何があったのか。 なりふり構わぬ資金投入で実績のある高年俸の選手をかき集めたわけではない。
1 0 0 0 OA 医薬品の適正使用とその実践V;点眼液の服薬指導の効果と指導方法の評価
- 著者
- 大塚 亮子 青山 隆夫 高柳 理早 清野 敏一 清水 秀行 中村 幸一 小滝 一 澤田 康文 伊賀 立二
- 出版者
- 一般社団法人 日本医療薬学会
- 雑誌
- 病院薬学 (ISSN:03899098)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.269-277, 1997-06-10 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1 2
We studied the effect of advising outpatients on the rational use of ophthalmic solutions and compliance by a questionnaire (n=158), in order to establish the optimal consultation method. A total of 41.8% of the patients answered the questionnaire. In compairing the actual use of ophthalmic solutions before and after consultation, the rates of rational use increased for all items except for “applications per day”, which decreased slightly from 93.4% before the consultation to 90.2% after that. In particular, “eyelid closure” and “nasolacrimal occlusion” after instillation, and “the 5 min interval of instillation in the case of plural medication”, considerably increased from 34.8% before the consultation to 60.6% after that, from 9.5% to 50.8% and from 45.9% to 73.8%, respectively. The compliance remarkably improved in glaucoma patients after consultation regarding “the 5min interval of instillation” .Based on these results, our consultation method for the rational use on ophthalmic solutions was thus evaluated. However, since some patients who still did not appreciate the need for the rational use of such medication still presented, further improvements in the consultation method requires for the rational use.
1 0 0 0 OA 色彩環境の変化が身体運動能力に及ぼす影響
- 著者
- 張 禎 邵 建雄 潘 珍 金謙 樹 豊島 進太郎 湯 海鵬 Zhen ZHANG Jian-xiong SHAO Zhen PAN Itsuki KANAAKI Shintaro TOYOSHIMA Hai-peng TANG
- 雑誌
- 人間発達学研究 (ISSN:18848907)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.23-29, 2014-03
1 0 0 0 OA 広い反照的均衡と多元主義的基礎づけ主義
- 著者
- 伊勢田 哲治 Iseda Tetsuji
- 出版者
- 名古屋大学人間情報学研究科情報創造論講座
- 雑誌
- Nagoya Journal of Philosophy (ISSN:18821634)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.29-53, 2006
The purpose of this paper is to investigate the implication of wide reflective equilibrium (WRE) for foundationalism. On a first look Rawls and Daniels seem to propose versions of reflective equilibrium as a method of coherentism. However, the method of WRE is also compatible with modest foundationalism, and some passages of Rawls and Daniels suggest that they too allow this possibility. The version of foundationalism I endorse is a pluralist one in which not only considered judgments but also ethical principles and background theories can be included in the set of basic judgments.
1 0 0 0 OA ナノ粒子の創製と応用
- 著者
- 米澤 徹
- 出版者
- 一般社団法人 表面技術協会
- 雑誌
- 表面技術 (ISSN:09151869)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.11, pp.712, 2008 (Released:2009-05-30)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 4 3
1 0 0 0 OA 近代日英図像に見るanthropomorphic表象の変遷とエコクリティシズム
- 著者
- 千森 幹子 Scott Clive Harvey John
- 出版者
- 帝京大学
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2015-04-01
本研究は、エコクリティシズムから、1850~1930年代に至る日英文学図像におけるanthropomorphic表象、特に植物や物など人間以外の存在である自然に、人間的な感覚や感情・意味を読み取り、擬人化あるいは生命を付与する表象、を文学・美術・社会・子ども観等から考察する学際研究であり、カルチュラルスタディーズである。本研究では、植物や物が、日英の子どもの挿絵と邦訳で、どのように擬人化され、変遷したのか、そこに埋め込まれたエコロジーに対する文化的意味を、創作の過程、日英の擬人化の歴史、技法から探り、西洋的価値体系における自然観と日本の自然観の位相、人間と自然の対立融合共生の位相を、検証した。
1 0 0 0 OA 大学入試の荒廃と混乱について
- 著者
- 那波 信男
- 出版者
- 日本物理教育学会
- 雑誌
- 物理教育 (ISSN:03856992)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.1-4, 1990-02-20 (Released:2017-02-10)
共通一次試験を引きがねとする大学入試の混乱について分析を試み,問題の難易レベルと出題技術の観点から筆者の所見を述べた。あわせて教科課程の再編について言及した。
1 0 0 0 指導者の立場から
- 著者
- 永田 裕治
- 雑誌
- 日本臨床スポーツ医学会誌 = The journal of Japanese Society of Clinical Sports Medicine (ISSN:13464159)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, 2010-04-30
1 0 0 0 OA わが國金属マグネシウム工業の回顧
- 著者
- 磯部 愉一郎
- 出版者
- 一般社団法人 軽金属学会
- 雑誌
- 軽金属 (ISSN:04515994)
- 巻号頁・発行日
- vol.1953, no.9, pp.3-4, 1953-11-30 (Released:2008-10-30)
1 0 0 0 OA 仁平典宏著 『「ボランティア」の誕生と終焉――〈贈与のパラドックス〉の知識社会学ーー』
- 著者
- 豊島 慎一郎 仁平 典宏
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.97-104, 2012-10-31 (Released:2015-05-13)
1 0 0 0 IR Imaginary Companionの定義に関する考察
- 著者
- 友弘 朱音 佐野 秀樹 トモヒロ アカネ サノ ヒデキ TOMOHIRO Akane SANO Hideki 友弘 朱音(東京学芸大学教育学研究科学校心理専攻) 佐野 秀樹(東京学芸大学教育心理学講座) TOMOHIRO Akane(Graduate School of Education Tokyo Gakugei University) SANO Hideki(Tokyo Gakugei University)
- 出版者
- 東京学芸大学紀要出版委員会
- 雑誌
- 東京学芸大学紀要. 総合教育科学系 (ISSN:18804306)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.203-208, 2009