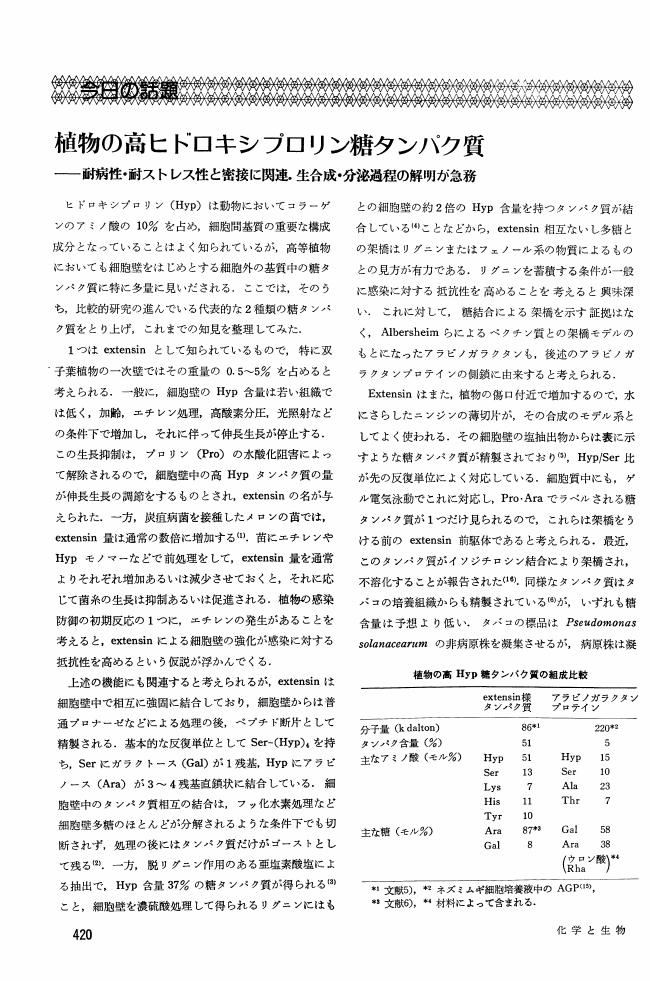1 0 0 0 OA 今日の話題
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.7, pp.420-430, 1983-07-25 (Released:2009-05-25)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 IR アクティブラーニングが要請される社会的背景の考察
- 著者
- 長光 太志
- 出版者
- 佛教大学総合研究所
- 雑誌
- 佛教大学総合研究所紀要 (ISSN:13405942)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.49-55, 2018-03-25
本研究ノートでは,日本の大学においてALが推進される経緯を,「大学の大衆化」と「能力観のポスト近代化」という大学を取り巻く 2 つの変化に注目して整理する。そこから見えて来るのは,ALという教育手法が,これらの変化への対応策であることを期待された教育手法だったという事である。ただし,ALの発祥の地であるアメリカと同様の社会現象である「大学の大衆化」と,日本独特の文脈を色濃く持つ「能力観のポスト近代化」とでは,ALへの期待が微妙に異なる。特に後者の期待には,ALに対する幾つかの仮定が差し込まれており,この仮定の真偽を巡る研究が,日本では,まだ進んでいない。本研究ノートは,こうした現状を指摘するものである。アクティブラーニング大学の大衆化能力観のポスト近代化大学生のトランジション
1 0 0 0 IR 5.1)紫斑病2例(第381回千葉医学会例会,第1回千葉皮膚科学臨床談話会)
1 0 0 0 OA 矯正臨床における児童心理への配慮
- 著者
- 管野 さゆり 小山 浩平 金野 吉晃 清野 幸男 三浦 廣行
- 出版者
- Japanese Society of Psychosomatic Dentistry
- 雑誌
- 日本歯科心身医学会雑誌 (ISSN:09136681)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.129-134, 2002-12-25 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 17
Tics are defined in the DSM-IV manual of the American Psychiatric Association as being sudden, rapid, recurrent, nonrhythmic, stereotyped motor movement or vocalization. We report on the treatment of a patient with tic symptom, a cleft lip on the left side and skeletal anterior cross bite. Clinical record: The patient, a girl with a cleft lip on the left side, was referred to us at the age of 5 months by Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Iwate Medical University School of Medicine, for the purpose of performing preoperative orthodontics.Our plastic surgery department performed the cheiloplasty at the age of 6 months. This was followed, at the age of 6 years, by work on the rhinoplasty and secondary cheiloplasty. From the age of 3 years and 6 months, due to poor upper jaw development and as a result of examination of skeletal anterior cross bite, work was commenced as the maxillary protraction, the upper dental arch expansion, and improvement of the rotated central incisors on the upper jaw.The patient continued to visit the hospital without problems until the age of 7 years and 10 months.At her next half-yearly visit, at the age of 8 years and 4 months, the patient was observed to have symptoms of blinking, facial twitching, coughing, and strange vocalizations. Her mother had considered these symptoms to be nose-related and taken her daughter to an otorhinolaryngologist, but the examination there produced no improvement and she was thinking of going to another hospital. The authors suspected Tourette's syndrome and introduced the patient to a child psychologist. Tourette's syndrome was diagnosed on the basis of the vocal tic and effectiveness of haloperidol. A year later, the multiple tics had continued with changes of place, type and frequency with no apparent regularity of pattern in either transformation or frequency. Minor incidents, increases of anxiety etc. were thought to precipitate change in and expression of the symptoms, but the patient was extremely cooperative with the orthodontic treatment.Discussion: Pediatric patients suspected of having a genetic predisposition towards tics may be liable to develop symptoms in response to triggers experienced in the home or school. In this case, the orthodontic treatment did not become a source of stress and the patient's psychological state was observed to be good. It is supposed that the condition was probably precipitated by a latent feeling of inferiority or stress experienced at school or in the children's home. Close coordination with a medical specialist is essential in the case of tics. It is important for the orthodontist to provide not only occlusion-related treatment but also psychological support.
1 0 0 0 OA 小児発育性股関節形成不全に対する広範囲展開観血的整復術の長期成績
- 著者
- 吉川 泰司 中村 正則 助崎 文雄 澤田 貴稔 宮岡 英世 稲垣 克記
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.6, pp.727-737, 2016 (Released:2017-06-08)
- 参考文献数
- 29
小児期の保存療法に抵抗した発育性股関節形成不全に対して,観血的に三宅の広範囲展開法で整復した症例の長期術後経過を検討した.1992年から,当科で広範囲展開法を施行した手術時年齢が3歳以下の症例で,14歳以降まで経過観察が可能であった22例24股を対象とした.全例が女児で,手術時平均月齢は20か月,調査時平均年齢は17歳で,経過観察期間は平均189か月であった.追跡調査率は90%であった.最終診察時に寛骨臼形成不全が軽度であったSeverin分類I,II群に該当するものは17股70%であった.最終診察時に骨頭変形が残存した重症例のうち,Kalamchi&MacEwen分類II,III,IV群で大腿骨頭壊死が術後に生じたと考えられたものは3股12.5%であった.関節症変化は3股12.5%に認められた.術後に行われた補正手術は4股であった.6歳時から最終診察までの間にSeverin分類III群からII群へ臼蓋被覆改善を認めた症例が存在し,就学前の股関節補正手術は慎重に行うべきであると考えられた.今後,乳幼児の股関節脱臼治療の成績を向上させるためには,脱臼の早期診断,術前の保存療法の改善,手術侵襲の低減と手技の改善が必要である.
1 0 0 0 OA 両国往復書謄
- 巻号頁・発行日
- vol.[90], 1000
1 0 0 0 東京音楽学校と邦楽 : 昭和11年の邦楽科開設を中心に
- 著者
- 酒井 健太郎
- 出版者
- 昭和音楽大学
- 雑誌
- 研究紀要 (ISSN:09138390)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.32-44, 2015-03-15
1 0 0 0 OA 明治中期における「辞書戦争」の書誌的検証
- 著者
- 早川 勇
- 出版者
- 日本英学史学会
- 雑誌
- 英学史研究 (ISSN:03869490)
- 巻号頁・発行日
- vol.1999, no.31, pp.85-96, 1998 (Released:2009-09-16)
This paper is an attempt to examine a 'dictionary war' between two English-Japanese dictionaries from a bibliographical point of view. They were compiled heavily dependent on Webster's dictionary and first published in the same year of 1888. One was compiled by Yutaka Shimada and published by Okura, while the other was compiled by F. Warrington Eastlake and Ichiro Tanahashi and published by Sanseido. They had many lexicographical characteristics in common. They were revised and enlarged several times in order to gain a decisive victory in the war which raged about twenty years in the Meiji period.The examination of their editions and contents reveals that they were not competing in terms of precise description of lexical items but in terms of size, total number of entry words, and repeated additions of supplements or appendixes to their main body, which cannot be regarded as substantial from a lexicographical viewpoint but very important from a historical viewpoint for a deeper understanding of the development of English-Japanese lexicography.
- 著者
- 勝野 まり子
- 出版者
- 学校法人 開智学園 開智国際大学
- 雑誌
- 日本橋学館大学紀要 (ISSN:13480154)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.3-12, 2008-03-01 (Released:2018-02-07)
「春の陰影」(1914)は、D.H.ロレンスの初期の短編小説の一つであるが、次の3つの理由から注目に値する作品である。彼自身の手によって改稿や改題が入念に6回なされた後で現在の形で出版されたこと、彼の主要な長編小説の世界と類似する世界を展開していること、そして、そこには30種類もの植物が異なる2通りの<象徴>的な形で登場することである。最後の点が、特に興味深いものである。この小論では、「植物描写における象徴の二重性」と「直感」という、密接に関係し合う2つの観点から「春の陰影」を考察する。その「植物描写における象徴の二重性」を簡潔に述べると、次のようになる。作者は、多くの種類の植物が持つ宗教上および民俗上の伝統的な<象徴>を意図的に用いて、作品の登場人物間の人間関係とプロットを暗示させ、それらを語りによって裏付けする。他方では、彼は幾つかの場面で植物を美しく生き生きと描く。そこでは、主人公サイソンは思考とは無縁に植物の美に深く感動する。それらの生き生きとした植物描写は、読者の五感にも訴えかけ、1つに結びつき、ついには1つの<象徴>を生む。そこには、それぞれの植物を個別に<象徴>として描こうとする作者の意図は見出せない。しかし、小説全体を通してみると、それらの幾つかの植物描写は一つの<象徴>となっている。それは、過ぎ行く時、春の中で土に育まれる植物と1人の女性の輝かしい生命を<象徴>している。そのような植物の二重の<象徴>は、旨く働き合い、これもまた作者の語りによって裏付けされながら、テーマを伝える。それは土に育まれるどんな生命も等しく賞賛され、それぞれがそれぞれの世界を持ち、その独自の世界は他の何ものによっても踏み込まれるべきではない、というテーマである。さらに、「植物描写における象徴の二重性」には、この作品の価値に加えて、ロレンスの作家としての豊かな才能も見出される。その<象徴>における二重性の1つは、宗教上および民俗上の伝統的なものであり、人間関係とプロットを暗示させるために意図的に用いられている。そして、それは作者が小説を書くための熟練した技と博識を有する並外れて知的な英国人作家であったことを伝える。他方では、幾箇所かでなされる生き生きとした植物描写全てが結び付き、1つの<象徴>を生み出す。それは、作者が豊かな「直感」を備えた人であったことを伝える。「直感」によって、人は誰でもどんな生命の輝きをも真に知ることができる。作者は「直感」によって、ありとあらゆる生き物の生命の輝きを認識し、「春の陰影」の主人公であるサイソンと彼のかつての恋人ヒルダも、「直感」によってそれらを認識することができる。今日、世界中で欧米化が極限的な状況にまで広まっている。それは、人間の経済的な発展をもたらしたが、同時に、あらゆる生命に大きな苦しみをもたらしている。約百年前に、英国人であるロレンスは、欧米文化を「直感」に欠くものとして批判し、「直感」が世界の望み多き将来への鍵であると信じた。我々も、知性や伝統的な知識を最善に生かしながらも、他方で、我々の「直感」を再生させることによって、そのような苦しみを軽減できるように思われる。これが「春の陰影」が我々に示唆することである。
- 著者
- 山下 純一 安本 三治 橋本 貞夫
- 出版者
- The Pharmaceutical Society of Japan
- 雑誌
- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.11, pp.3872-3877, 1983-11-25 (Released:2008-03-31)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 3 4
The mechanism of the condensation of 5-fluorouracil and 2-acetoxytetrahydrofuran (3), giving 1-(tetrahydro-2-furyl)-5-fluorouracil, was studied. An equilibrium between 2-acetoxytetrahydrofuran (3) and 2, 3-dihydrofuran (4) was observed at 120-170°C in dimethylformamide. It was found by the use of 1, 3-dideuterio-5-fluorouracil that the condensation of 5-fluorouracil with 3 occurred both by direct substitution and by the formation of 4 from 3 followed by addition of the uracil to it. The contribution of the latter path increased with increase of the reaction temperature.
1 0 0 0 OA 越州山陰高氏家譜36卷首1卷
1 0 0 0 イスラームの死生観と馬復初の来世観
- 著者
- 松本 耿郎
- 出版者
- 聖トマス大学
- 雑誌
- サピエンチア : 英知大学論叢 (ISSN:02862204)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.143-164, 2009-02
1 0 0 0 OA 新調理システムの加熱工程は,従来の調理法と比較するとビタミンCの損失が大きい
- 著者
- 岡村 吉隆 下井 亜希 藤田 和代 日沼 州司
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.2, pp.27-33, 2018 (Released:2018-05-12)
- 参考文献数
- 16
【目的】本研究は新調理システムの加熱工程において,V.Cの変化が従来の調理法と比較すると,どの程度であるかを明らかにすることを目的とした。【方法】試料はいも及び野菜類7食品とした。フードプロセッサーで粉砕後,分取し水さらし及び冷凍,加熱によるV.Cを測定し残存率を求めた。加熱方法は蒸しと水煮とした。水煮は煮汁も含めて測定した。分析は2,4—ジニトロフェニールヒドラジン誘導体化法を用い,高速液体クロマトグラフで行った。【結果】生のV.C量を100とすると水さらしの残存率は全体で平均23.7±6.0%であった。生を一週間冷凍保存すると残存率の平均は94.7±3.5%であった。蒸し加熱の工程ごとの平均残存率は,加熱69.7±17.8%,加熱後冷凍62.9±15.8%,再加熱53.7±18.0%であった。水煮の平均残存率は加熱56.7±17.7%,加熱後冷凍52.2±17.2%,再加熱45.7±20.8%であった。スライスしたさつまいもは蒸し加熱99.9±1.6%,水煮加熱は84.5±1.8%であった。【結論】フードプロセッサーを用いて粉砕すると,水さらしの残存率は加熱より低かった。生の冷凍は損失が少なかった。加熱と再加熱では再加熱の損失は少なかったものの,新調理システムの加熱工程は,従来の調理法と比較するとV.Cの損失が大きかった。また,水煮加熱は煮汁中のV.Cを含めても残存率は低いことが示唆された。
1 0 0 0 OA 静岡県における減塩推進活動
- 著者
- 赤堀 摩弥 藤浪 正子 川田 典子 佐藤 圭子 小嶋 由美 中村 美詠子 尾島 俊之
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.2, pp.34-43, 2018 (Released:2018-05-12)
- 参考文献数
- 9
【目的】静岡県は他自治体と比較して脳血管疾患死亡率が高く,食塩摂取量も多い。そこで,脳血管疾患対策の1つとして,5年で5%の減塩を目指す「減塩55プログラム」に取り組むこととし,県民の食塩摂取状況の把握ができるチェック票を開発,減塩推進活動に活用することを目指した。【方法】静岡県保健所栄養士のヒアリングによる質的データ,静岡県民102人を対象とした24時間蓄尿データより推定した食塩排泄量及び食物摂取頻度調査票(短縮版)データ等に基づいて,チェック票を開発,さらに,特に減塩をすすめたい働き盛り世代を対象としたリーフレット「ふじのくに お塩のとりかたチェック」を作成した。【結果】チェック票合計点と推定食塩排泄量の間には,有意な正の相関(Pearson相関係数0.402)がみられた。チェック票より3段階にランク付けした場合,各群の平均推定食塩排泄量はおのおの 6.8 g,8.7 g,12.2 gであった。リーフレットは70,000部以上が希望のあった県内の健康保険組合,事業所,医療機関,県栄養士会,薬局,教育機関,保育所等に配布され,県内全ての市町,健康福祉センターで活用されている。【結論】本チェック票は食塩摂取の簡易なスクリーニング・ツールとして使いやすいものとなったため,現在静岡県内の健康教室,イベント等さまざまな場面で活用されている。今後も本チェック票を活用し,静岡県における減塩対策を進めていく予定である。
1 0 0 0 オリエント考古美術誌 : 中東文化と日本
1 0 0 0 OA 名所江戸百景 水道橋駿河台
1 0 0 0 OA 教育課程改革における「主体的・対話的で深い学び」の位置づけと課題
- 著者
- 田代 高章 宮川 洋一 馬場 智子 TASHIRO Takaaki MIYAGAWA Yoichi BABA Satoko
- 出版者
- 岩手大学教育学部附属教育実践総合センター
- 雑誌
- 岩手大学教育学部附属教育実践総合センター研究紀要 = The Journal of the Clinical Research Center for Child Development and Educational Practices (ISSN:24329231)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.115-132, 2018-03-31
1 0 0 0 IR 昭和16年7月15日長野地震の家屋被害に就て
- 著者
- 金井 淸
- 出版者
- 東京帝国大学地震研究所
- 雑誌
- 東京帝國大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University (ISSN:00408972)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.4, pp.647-660, 1941-09-30
- 被引用文献数
- 2
The present paper is a report of the damage to buildings in the Nagano earthquake that occurred on July 15, 1941, with a theoretical discussion. With the kind assistance of Mr. Kodaira, the writer examined the seismic region during the period from July 17 to July 23, which had an area of about 10km in dia. consisting of nine villages, situated north-east of Nagano city, and quite close to it. The buildings in the seismic region are mostly farm houses together with granaries and sheds. The investigation in the field was made from the point of view of the dynamical theory of seismic vibration of a structure that we had developed recently.