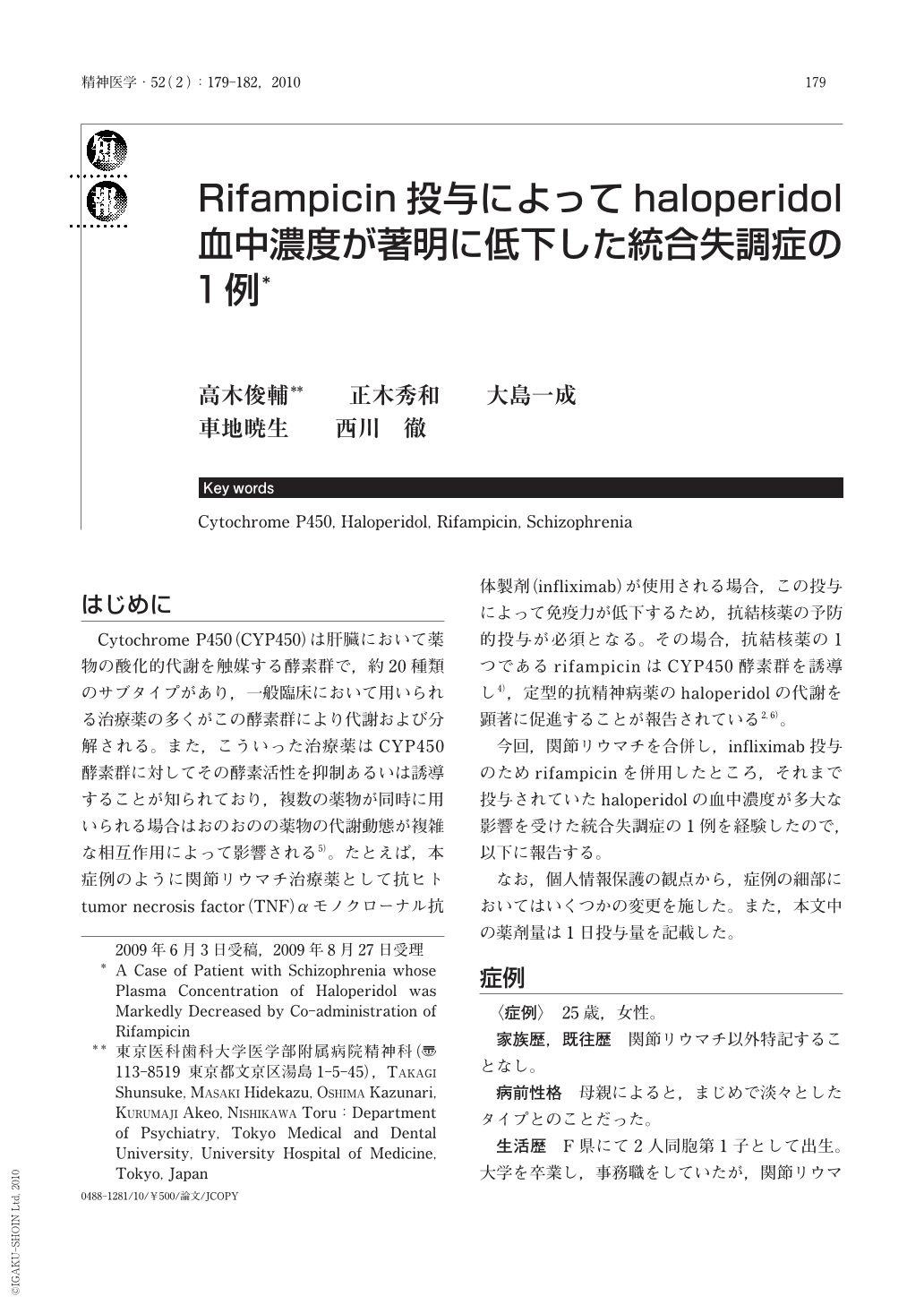1 0 0 0 OA 『明暗』をどう読むか : 漱石探求 三
- 著者
- 佐藤 泰正
- 出版者
- 梅光学院大学
- 雑誌
- 日本文学研究 (ISSN:02862948)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.12-23, 2005-01-30
1 0 0 0 OA 『道草』をどう読むか : 漱石探究 二
- 著者
- 佐藤 泰正
- 出版者
- 梅光学院大学
- 雑誌
- 日本文学研究 (ISSN:02862948)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.62-72, 2004-01-30
1 0 0 0 IR 漱石探求--『こゝろ』から何が見えて来るか
- 著者
- 佐藤 泰正
- 出版者
- 梅光学院大学日本文学会
- 雑誌
- 日本文学研究 (ISSN:02862948)
- 巻号頁・発行日
- no.38, pp.55-65, 2003-02
- 著者
- 高木 俊輔 永井 達哉 斉藤 聖 坂田 増弘 渡辺 裕貴 渡辺 雅子
- 出版者
- 一般社団法人 日本てんかん学会
- 雑誌
- てんかん研究 (ISSN:09120890)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.427-433, 2011 (Released:2011-02-01)
- 参考文献数
- 11
進行性ミオクローヌスてんかんの一型であるUnverricht-Lundborg病(ULD)は、他の進行性ミオクローヌスてんかんと比べて認知機能低下の進行が緩徐であり、他のてんかん症候群と見誤られる可能性がある。 今回我々はULDの原因遺伝子であるシスタチンB遺伝子について最も多い形式の異常は確認できなかったが、誘発電位でのgiant SEP所見や光過敏性、早朝覚醒時に目立つミオクローヌスや進行性の認知機能障害などの特徴的な症状に気付かれULDと臨床診断された症例を経験した。当症例は部分てんかんの診断のもとULDの症状、予後に悪影響のあるフェニトイン(PHT)の投与を長期間受けており、ミオクローヌスや認知機能低下が進行していた。PHTをクロナゼパム及びピラセタムに変更したところ症状に改善が得られた。 ULDはまれな疾患で診断には困難が伴うが、臨床的特徴を把握しておくことが重要と考えられた。
- 著者
- 村田 佳子 渡邊 修 谷口 豪 梁瀬 まや 高木 俊輔 中村 康子 渡辺 裕貴 渡辺 雅子
- 出版者
- 一般社団法人 日本てんかん学会
- 雑誌
- てんかん研究 (ISSN:09120890)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.43-50, 2012 (Released:2012-06-28)
- 参考文献数
- 21
高齢発症側頭葉てんかんにおいて、健忘症、気分障害、睡眠障害、排尿障害、唾液分泌過多、低ナトリウム血症を認め、抗電位依存性カリウムチャンネル複合体(voltage-gated potassium channel:VGKC-complex(leucine-rich glioma inactivated1 protein:LGI-1))抗体陽性から、抗VGKC複合体抗体関連辺縁系脳炎(VGKC-LE)と診断した。本例は数秒間こみあげ息がつまる発作が1日100回と頻発し左上肢を強直させることがあった。Iraniらは、VGKC-LEの中で抗LGI-1抗体を有するものは、3~5秒間顔面をしかめ上腕を強直させるfaciobrachial dystonic seizures(FBDS)を報告しており、本発作は診断の一助となると考えられた。本例は、本邦において抗LGI-1抗体とFBDSの関連を指摘した最初の報告である。
- 著者
- 高木 俊輔 正木 秀和 大島 一成 車地 暁生 西川 徹
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 精神医学 (ISSN:04881281)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.179-182, 2010-02-15
はじめに Cytochrome P450(CYP450)は肝臓において薬物の酸化的代謝を触媒する酵素群で,約20種類のサブタイプがあり,一般臨床において用いられる治療薬の多くがこの酵素群により代謝および分解される。また,こういった治療薬はCYP450酵素群に対してその酵素活性を抑制あるいは誘導することが知られており,複数の薬物が同時に用いられる場合はおのおのの薬物の代謝動態が複雑な相互作用によって影響される5)。たとえば,本症例のように関節リウマチ治療薬として抗ヒトtumor necrosis factor(TNF)αモノクローナル抗体製剤(infliximab)が使用される場合,この投与によって免疫力が低下するため,抗結核薬の予防的投与が必須となる。その場合,抗結核薬の1つであるrifampicinはCYP450酵素群を誘導し4),定型的抗精神病薬のhaloperidolの代謝を顕著に促進することが報告されている2,6)。 今回,関節リウマチを合併し,infliximab投与のためrifampicinを併用したところ,それまで投与されていたhaloperidolの血中濃度が多大な影響を受けた統合失調症の1例を経験したので,以下に報告する。 なお,個人情報保護の観点から,症例の細部においてはいくつかの変更を施した。また,本文中の薬剤量は1日投与量を記載した。
1 0 0 0 OA 自己表象の区分化傾向と感情体験の極端さとの関連について
- 著者
- 佐藤 徳
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- 性格心理学研究 (ISSN:13453629)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.89-100, 2000-03
本研究では, 区分化を自己の各側面から対立する感情価にある表象を"排除"する傾向と定義し, 自己表象の内容と構造の個人差がポジティブおよびネガティブ・イベント体験後の感情体験の強さ, ならびに気分変動の大きさにどのような影響をもたらすかを検討した.自己表象の内容面の指標としては自己記述に使用された項目に占めるポジティブ項目の率を, 区分化の指標としては各側面におけるポジティブ項目選択率とネガティブ項目選択率の差の絶対値の平均を用いた.その結果, ネガティブ・イベント体験後においては, ポジティブ項目率が低いほど強いネガティブな感情を体験していること, 区分化傾向が高いほど強いネガティブな感情を体験していることが見出された.他方, ポジティブな感情においては自己表象の効果は得られなかった.気分変動の大きさについては区分化の主効果のみが見出され, 区分化傾向が高いほど変動が大きかった.以上の結果は, ポジティブな感情とネガティブな感情では自己表象の効果が異なること, ポジティブ, ネガティブ双方の自己表象を統合することが極端な気分の変化に対する緩衝要因となることを示している.
1 0 0 0 OA 「この花の一よ」はなぜ折れたのか―娘子から広嗣へ―
- 著者
- 小伏 志穂
- 出版者
- 関西大学国文学会
- 雑誌
- 國文學 (ISSN:03898628)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, pp.1-11, 2003-12-17
1 0 0 0 相模湾北西部およびその周辺地域の地震活動
- 著者
- 棚田 俊收
- 出版者
- Japan Association for Quaternary Research
- 雑誌
- 第四紀研究 (ISSN:04182642)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.6, pp.461-467, 1999-12-01
神奈川県温泉地学研究所によって決定された1990年から1998年の9年間の震源データを用いて,「神奈川県西部地震」の想定震源域である相模湾北西部における地震活動と地質構造との関係について考察した.<br>地震活動の高い地域は,神奈川・山梨県境や箱根火山のカルデラ内に分布し,それぞれ丹沢山地の隆起運動や箱根火山の火山活動に関連していると見られている.箱根古期外輪山の山麓東部では,地震が深さ10~20kmに発生しており,震源の深さは箱根火山中央火口丘から山麓東部へと行くに従って徐々に深くなっている.この特徴は,火山体近くの熱的構造を反映し,地震発生層の厚み変化を表していると考えられる.<br>一方,伊豆地塊の衝突によって形成された足柄山地や,断層で囲まれた大磯丘陵,湯河原や多賀火山等の第四紀火山地帯では,地震活動は相対的に低い.また,神縄断層や国府津-松田断層などの活断層付近では,浅い地震は観測されていない.
1 0 0 0 eduroamによる大学間無線LAN連携と国内外の動向
- 著者
- 後藤 英昭 曽根 秀昭
- 出版者
- 情報教育研究集会企画・プログラム委員会
- 雑誌
- 情報教育研究集会講演論文集 (ISSN:18836003)
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, pp.109-112, 2009
- 著者
- Satoru OSUKA Hironori IMAI Eiichi ISHIKAWA Akira MATSUSHITA Tetsuya YAMAMOTO Hiroki NOZUE Tatsuyuki OHTO Kousaku SAOTOME Yoji KOMATSU Akira MATSUMURA
- 出版者
- 社団法人 日本脳神経外科学会
- 雑誌
- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.12, pp.1118-1122, 2010 (Released:2010-12-25)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 9 23
Mild encephalitis/encephalopathy with a reversible splenial lesion (MERS) is a clinico-radiological syndrome with a very particular clinical course. Three patients with MERS were evaluated by various sequences of magnetic resonance imaging with diffusion tensor imaging. Initial diffusion-weighted imaging showed reduction in the apparent diffusion coefficient values in the lesions, which completely resolved with the elimination of symptoms. However, diffusion anisotropy of the lesions showed no remarkable abnormalities in the early or delayed phases. These results may indicate that white matter architecture is preserved in both early and delayed phases in MERS.
1 0 0 0 OA 「山月記」九文考(湊吉正先生退官記念号)
- 著者
- 香西 秀信
- 出版者
- 人文科教育学会
- 雑誌
- 人文科教育研究 (ISSN:09131434)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.33-40, 1995-08-03
- 著者
- 古村 隆明 岡部 寿男 中村 素典
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. SITE, 技術と社会・倫理 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, no.437, pp.153-158, 2010-02-22
eduroamは,802.11b/g等の無線LANで,802.1x認証を利用した国際無線LANローミング基盤で,国内外の数多くの教育研究機関で導入が進んでいる.ローミング時に訪問先機関や国や地域に設置されている複数のradiusサーバにアカウント名を含む認証情報が記録されることで,ロケーションプライバシが侵害される危険性がある.そこで我々は,SAML連携を用いて発行した仮名アカウントでeduroamを利用する手法を提案する.この手法では,平常時は,個人の特定だけでなく利用者の所属組織の特定もできなくなる.また,インシデント発生時などには,radiusサーバとSAML連携組織の情報を合わせることで個人を特定することが可能である.
1 0 0 0 OA 3.胃ポリープ:内視鏡の立場から
- 著者
- 田尻 久雄 丹羽 寛文
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.5, pp.617-621, 1992-05-10 (Released:2008-06-12)
- 参考文献数
- 5
胃ポリープのなかで最も多く代表的なものは過形成性ポリープであり,内視鏡的ポリペクトミーの成績では83%を占める.そのなかで局在癌の頻度は3%であった.一方,胃腺腫の場合は発生頻度が低いものの,腺腫内の癌共存率が10%と高率にみられた.胃集検の意義は,無症状の有所見群を拾い上げることにあり,内視鏡による精密検査によってはじめて微細な変化を確診し得る.今後は,内視鏡胃集検がより普及していくことが望まれる.
1 0 0 0 OA 胃過形成性ポリープの癌化に関する検討
- 著者
- 白崎 信二 細川 治 渡辺 国重 津田 昇志 山崎 信 山道 昇 小西 二三男
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.4, pp.848-855_1, 1989-04-20 (Released:2011-05-09)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 5
当科における1963年から1985年までの早期胃癌切除例は1,038例であり,このうちI型早期癌は68例76病巣である.このI型早期癌の病理組織学的検討により,24例25病巣は胃過形成性ポリープ(以下H.P.と略記)の癌共存病変であり,I型早期癌の33%を占め,早期癌全症例の2.3%を占めていた.24例中16例17病巣は胃切除例であり,8例8病巣は内視鏡的ポリペクトミー症例であった.病変の最大径は0.7cm~5.5cmで平均2.6cmであった.最大径2cm未満の症例が8例存在し,このうち2例は1cm未満であった.また,病変に占める癌組織の割合の小さいものは,病変も小さく,病変に占める癌組織の割合が大きくなるに従い,病変も大きくなる傾向がみられた.これらより,かなり小さなH.P.にも癌が発生(H.P.の癌化)し,良性組織の増加を幾分伴いながら癌組織が増殖し病変が増大していく事が示唆された.内視鏡所見では,症例によりかなりの差異が認められ,全般的には表面の凹凸不整,白苔,びらん,出血等が観察された.また,経過観察が可能であった症例の内視鏡所見の検討より,大きさの増大,表面凹凸不整の増強が,癌発生(癌化)の可能性を示唆しうる所見と考えられた.当施設における内視鏡的ポリペクトミー開始以来10年間の生検あるいはポリペクトミーにより,H.P.と診断されたものは1,508例であり,同期間中のH.P.の癌共存例数は16例(1.0%)であった.
1 0 0 0 OA 胃ポリープの経過観察中に発生をみた胃癌症例の検討
- 著者
- 中山 健 市川 幹郎 山口 裕国 野中 洋 鈴木 俊 粉川 顕仲
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.14-25, 1989-01-20 (Released:2011-05-09)
- 参考文献数
- 28
胃ポリープ122例について5年以上平均7年10カ月間経過観察を行なった.そのうち87例(71.3%)に何らかの形態変化を認めた.ポリープの伸長33例(27.0%),膨大44例(36.1%),脱落21例(17.2%),新生20例(16.4%),胃癌の発生7例(5.7%)であった.胃癌発生例のうち1例はポリープそのものの癌の発生であったが,6例は経過観察中に胃癌が併発した. 胃ポリープ症例は胃癌の併発に注意して経過観察を行なう必要がある.
1 0 0 0 OA 自律分散ロボット群による障害物クラスタ形成の解析と制御
- 著者
- 末岡 裕一郎 北 卓人 石川 将人 杉本 靖博 大須賀 公一
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集C編 (ISSN:18848354)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.801, pp.1718-1727, 2013 (Released:2013-05-25)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 2 2
In this paper, we discuss some phenomena of obstacle clustering by distributed autonomous robots, in the light of space-discretization (or cellular automata) approach. This work was motivated by Swiss Robots which collect scattered obstacles into some clusters without any global information nor intelligent concentrated controller. Then we define fundamental event rules in this cellular world, and introduce two types of local rules for robot action: one is the Push & Turn rule, which can collect obstacles, the other is Pull & Turn rule, which can scatter obstacles. By defining several indices (ratio of immobile obstacles, ratio of moved obstacles), we investigate the dynamic equilibrium of obstacle clustering by heterogeneous agents. And, this paper also presents a control method of ratio of immobile obstacles from the estimation of each robot's local information even if all the states of obstacles cannot be measured.
- 著者
- 泉川 雅彦
- 出版者
- 関西医科大学医学会
- 雑誌
- 関西医科大学雑誌 (ISSN:00228400)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2-4, pp.171-177, 2006-12-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 13
1 0 0 0 OA 軸糸ダイニンの構造と仕組み
- 著者
- 吉川 雅英 八木 俊樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.6, pp.325-329, 2008 (Released:2008-12-02)
- 参考文献数
- 21
Eukaryotic cilia and flagella are highly specialized organelles that play important roles in generating motions and sensing flows. Here, we review recent progresses in cilia / flagella studies, focusing on their structural studies by cryo-electron microscopy.
- 著者
- 岩橋 文吉
- 出版者
- 日本比較教育学会
- 雑誌
- 日本比較教育学会紀要 (ISSN:02871106)
- 巻号頁・発行日
- vol.1980, no.6, pp.14-18, 1980-03-31 (Released:2010-08-06)
- 参考文献数
- 12