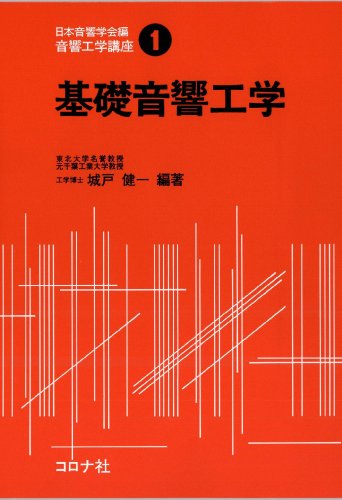1 0 0 0 東南アジア熱帯林の林冠構造と生物多様性の研究
- 著者
- 井上 民二 ABANG A.Hami LEE Hua Seng 市岡 孝朗 山岡 亮平 永益 英敏 加藤 真 湯本 貴和 HAMID Abang.A LEE HuaSeng 寺内 良平 HAMID Abang 山根 正気 市野 隆雄
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 国際学術研究
- 巻号頁・発行日
- 1994
1.植物フェノロジー調査:林冠調査区の樹木、つる、着生などの植物に個体識別コードをつけ(約600本)、花芽形成から開花、結実にいたる繁殖ステージと、展葉の生長ステージの記録を月2回、1992年から4年間継続しておこなった。その結果、展葉には多くの種でかなりの周期性がみられることが明らかになった。非一斉開花期の開花は年中を通してあまり変化がないが、3-4月ごとにやや多いこともわかった。また1996年2月から半年にわたって起こった一斉開花では、モニターしている樹木550個体のうち381個体(69.3%)、種数にして192種のうち66種(34.4%)をはじめとした189属402種の開花の開始から終了までを記録した。2.昆虫個体群トラップ調査:林冠調査区の4ヵ所(林床、中木層17.4m、高木層35m、および林冠ギャップの地上部)に誘蛾灯(UVライト)による採集を月1回、1992年から4年間継続しておこなった。4年間に採集した昆虫の総数は500万頭に及ぶ。その採集標本の同定と結果の解析を現在、行っている。3.動植物共生系調査:1996年2月から始まった一斉開花で107属160種の植物について送粉者を確認した。そのほとんどは、これまで4年間に開花の記録がない種である。その結果、マレー半島部では、アザミウマによって花粉を媒介されるとされていたShorea属は、サラワクでは甲虫、とくにハムシ類によって花粉媒介されることが明らかになった。この一斉開花以前に、Lambirで鳥媒であるとされてきたのは、228種の樹木のうちのGanua sp.(Sapotaceae)1種のみ(Momose & Inoue 1994=しかも間違い)、3種のヤドリギ(Loranthaceae)(Yumoto 1996)、7種のショウガ(Zingiberaceae)(Kato 1996,酒井 修士論文)に過ぎず、しかも送粉者はクモカリドリ2種(Nectariniidaeの1亜科)にほぼ限られていた。しかし、今回の一斉開花でDurio3種(Bombacaceae)、属未同定ヤドリギ(Loranthaceae)、Tarenna1種(Rubiaceae)、Madhuca1種、Palaquium2種(ともにSapataceae)が新たに鳥媒であることが確認され、送粉する鳥もクモカリドリ4種、タイヨウチョウ1種(Nectariniidae)、ハナドリ2種(Dicaeidae)、コノハドリ1種(Irenidae)、また盗蜜/送粉者としてサトウチョウ(Psittacidae)の関与が明らかになった。コウモリ媒は以外と少なく、Fagraea1種(Loganiaceae)が確認されたに留まった。さらにGanua sp.(Sapotaceae)では、リス/ムササビ媒というまったく新しい送粉シンドロームが見い出された。これは花弁と雄ずい群が合着し、肉厚の器官を成し、それ自体、糖度15%と甘い報酬となっている。花蜜は分泌しない。花弁/雄ずい群が花床からすぐに離脱するのにかかわらず、雌ずいは非情に苦く、落下しにくい。リスとムササビが頻繁に、かつ執拗に訪花し、花弁/雄ずい群を外して食べるうちに、前肢や口のまわりに花粉をつけるのが観察された。また、フタバガキ科などの突出木を中心に種子散布と種子捕食の過程の調査を行った。4.植物繁殖システム・遺伝構造調査:フタバガキ科Dryobalanopsis属、Shorea属植物とショウガ科植物のDNAサンプルの採取を終了し、現在分析中である。5.動植物標本管理と分類学:これまでの4年間で採集できなかった植物の花と果実の標本を今回の一斉開花で得ることができた。昆虫標本も、送粉者、種子捕食者を中心に整備が進んだ。6.研究成果の出版:調査結果は現在順調にそれぞれの学術雑誌に投稿され、出版されている。年度末に英文の報告書を出版する予定である。
1 0 0 0 洋上補給艦 (写真特集 今日のアメリカ軍艦)
1 0 0 0 OA 木曾地方ヒノキ人工林の伐期に於ける收穫量の豫想
- 著者
- 和田 武男
- 出版者
- 一般社団法人日本森林学会
- 雑誌
- 日本林學會誌 (ISSN:0021485X)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.12, pp.590-601, 1937-12-10
1 0 0 0 OA 現代社会における青少年の友人関係
- 著者
- 小澤 昌之
- 出版者
- 関東社会学会
- 雑誌
- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, no.22, pp.198-209, 2009-07-25 (Released:2013-03-28)
- 参考文献数
- 32
In this paper I have made a comparative research of the social background and trends that support Japan-South Korea student's friendship. It turns out that both national groups were generally satisfied with their friendship although there was a difference in the process of mingling with their friends. In case of associating with friends, Japanese students tended to value the feeling side, while South Korea students tended to value their attributes and their shrewdness. In the process of forming friends, analysis showed that both national groups were influenced by their degree of school adjustment and their quality of family life, while school achievement (Japanese students) and an item that asked about Internet friends (South Korean students) had a passive effect.
1 0 0 0 IR セクシュアリティ中心主義への問い : キャサリン・A・マッキノン理論の検討
- 著者
- 南茂 由利子
- 出版者
- 国立女性教育会館
- 雑誌
- 国立女性教育会館研究紀要 = Journal of the National Women's Education Center of Japan
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.71-80, 2004-08-01
アメリカ合衆国の著名な法学者キャサリン・A・マッキノンの提起するフェミニズム理論を検討する。まず、彼女の最重要課題が、セクシュアリティにおける平等であることを明らかにする。マッキノンは、現在のセクシュアリティ概念自体が男性優位社会の構築物であるとして、新たなセクシュアリティ概念の構築を主張するが、その具体的な内容は示さないままである。本稿は、それがマッキノン理論の根本的問題に由来すると捉えて、その克服方法を考察するものである。根本的問題とは、生殖の社会性という視点の欠落と、性別以外の社会的関係の無視である。それらを土台とするマッキノン理論は、「人種」、民族、階級等々の社会関係に規定されているセクシュアリティの現実を変革する具体的ヴィジョンを示すこともできない。男女平等をめざすにあたり、性別を理由とする不公正を正すうえで、セクシュアリティ追究の平等を中心に据える彼女の姿勢は、性別以外の人間の社会的諸関係を捨象したセクシュアリティ中心主義ともいうべきものである。それは、性別に限られない諸関係の中に位置づけられて生きている女性達の現実を打破する思想・運動の中心課題にはなりえない。マッキノンは、私的領域が女性抑圧の温床となることが避けられないとしてその廃止を提起する。それが誤った現状認識に立つ危険な提起であることを、本稿は論じている。ファリダ・アクターを主たる参照先としながら、公・私二領域論によっては社会の構造と人の営みを捉え得ないことと、マッキノンの提起が人の営みを国家が統括する法の監視にさらす危険を孕むことを明らかにする。近代以降広範に浸透した公・私二領域論を克服するためには、人間存在の二重性を再認識し、「個」を社会的に埋没させることのない民主的な社会関係の創造とともに、従来の公・私二領域という二元論を超える新しいイデオロギーの創造が必要とされる。
1 0 0 0 OA AST測定試薬と反応するIgM-κ型M蛋白の性状
- 著者
- 大杉 千尋 村上 信司 渡辺 嗣信
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床衛生検査技師会
- 雑誌
- 医学検査 (ISSN:09158669)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.6, pp.730-736, 2014-11-25 (Released:2015-01-10)
- 参考文献数
- 11
単一クローン性免疫グロブリン(M蛋白)は,免疫生化学検査の測定結果に様々な影響を与えることが知られている.今回われわれは,AST測定時の反応タイムコースの異常から,患者血清とAST第1試薬が反応して混濁を生じた症例を見出した.その症例における混濁の原因はIgM-κ型M蛋白であることを証明した.さらに他8社のJapan Society of Clinical Chemistry(JSCC)標準化対応試薬で患者血清を測定したところ異常反応を生じなかった.そこで,試薬成分の緩衝液に着目し,3種類の緩衝液における様々な濃度での患者血清との反応性を確認した.その結果,本症例の異常反応は現行AST試薬の低イオン強度によるものであると考えられた.
- 著者
- 三浦 壮
- 出版者
- 社会経済史学会
- 雑誌
- 社會經濟史學 (ISSN:00380113)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.4, pp.499-522, 2013-02-25
本稿は,戦間期宇部地域の工業化を検討することで,近代日本における地方工業化の特質を,主に鉱業資本家の投資活動から解明するものである。宇部地域の炭鉱および製造業の出資者はその多くが福原家の家臣団につながる家々であり,地域の共有財産である石炭鉱業で得られた利益金を再投資するよう,婚姻関係や,家同士の結びつきを利用した株式の所有を行っていた。投資動機としては,地域社会による地下資源の共有意識と地縁・血縁関係を基底とした,各鉱業資本家の製造業への投資に対する「連帯的強制」があった。新しい事業の拡大と利潤獲得は宇部社会の発展と同義の概念であり,地域社会への「貢献意欲」も重要な要因であった。鉱業資本家の所得構造を実証した結果,地元株式に集中して投資をしていたこと,地元株が中央株よりも高い利回りを維持し,特に石炭鉱業の利回りと利益総額は高いものであり,地域工業化の原資となっていたことが明確となった。
1 0 0 0 「セクシュアリティ」概念再考:精神分析の導入に向けて
- 著者
- 古川 直子
- 出版者
- SHAKAIGAKU KENKYUKAI
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.19-35,181, 2009
This article makes an effort to assess the validity and difficulty of the conceptual framework constitutive of today's gender/sexuality studies, namely the sex-gender-sexuality triad. The theoretical assumptions which underlie current research on gender/sexuality, including feminism, gay/lesbian studies, and queer theory, is characterized by a social constructionist approach. In studies regarding sexuality, beginning in the 1970s, in part because of the publication of Michael Foucault's influential work "The History of Sexuality" vol.1, social constructionists have argued that human sexuality should not be viewed as a natural fact but as something constructed in historically and culturally specific ways. This led to important theoretical developments, resulting in the analytical separation of gender and sexuality. Nevertheless, the very notion of sexuality remains ambiguous due to the obscure nature of the relationship between sex and sexuality. After reviewing the achievements and problems of current research in this field, the latter part of this article provides a brief introduction to the psychoanalytic view of sexuality, which offers a radical reconceptualization of received notions of what is sexual. Freud's psychoanalysis has been a major target of constructionist criticism, but an enlargement of the concept of sexuality in psychoanalysis can provide an alternative framework to constructionism in that it disentangles the inextricable knot between sexuality and genitality. Hitherto the fact that Freud defined the sexual without recourse to the genital, and proposed a completely new way of thinking about human sexuality, has received only scant attention. This is to say that psychoanalytic sexuality is defined in opposition to vital or organic functions such as feeding, excretion, respiration, and reproduction, and "sex" is rearticulated through this division of the sexual and non-sexual.
1 0 0 0 日本におけるカワウの生息状況の変遷
- 著者
- 福田 道雄 成末 雅恵 加藤 七枝
- 出版者
- 日本鳥学会
- 雑誌
- 日本鳥学会誌 = Japanese journal of ornithology (ISSN:0913400X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.4-11, 2002-05-31
- 被引用文献数
- 16 24
日本におけるカワウの生息状況は,非常に劇的な変化を示した.1920年以前は北海道を除く全国各地で普通に見ることができた鳥であった.ところが,明治以降から戦前までの間は,無秩序な狩猟などによって急減したとみられる.戦後は水辺汚染や開発などによって減少したと考えられ, 1971年には全国3か所のコロニーに3,000羽以下が残るのみとなった.しかしながら,その後カワウは残存したコロニーで増加し始め,それらの近隣広がった.1980年代からは愛知,岐阜,三重の各県で始まった有害鳥獣駆除の捕獲圧による移動や分散で,各地に分布を拡大していったと考えら れる.増加の主な理由は,水辺の水質浄化が進み生息環境が改善したこと,人間によるカワウへの圧迫が減少して営巣地で追い払われることが少なくなったこと,そして姿を消した場所で食料資源である魚類が回復したことなどが考えられる.2000年末現在では,50,000~60,000羽が全国各地に生息するものと推定される.
1 0 0 0 IR 発光カタツムリQuantula striataの発光系の化学的性質〔英文〕
- 著者
- 下村 脩 羽根田 弥太
- 出版者
- 横須賀市自然博物館
- 雑誌
- 横須賀市博物館研究報告 自然科学 (ISSN:05132622)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.p1-5, 1986-12
シンガポールの発光カタツムリ Quantula striata は人工的な刺激によって発光せず, また一皮凍結したあとは発光させることができない。 しかし冷凍試料の抽出液は, Fe2+, H2O2 とメルカプトエタノールを加えると発光する。抽出液中に存在する発光物質を精製して純晶を得たが, この物質はカタラーゼの一種であることが判明した。ただし, このカタラーゼがカタツムリ発光の発光物質であるという確証はまだ得られていない。
1 0 0 0 OA 根株処理機械の開発研究 (第2報)
- 著者
- 田中 勝千
- 出版者
- 農業食料工学会
- 雑誌
- 農業機械学会誌 (ISSN:02852543)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.6, pp.3-12, 1996 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 6
片刃のナイフに作用する曲げ荷重の大きさと向きを調べることによって, 片刃のナイフ形状と実作業との関わりを検討し, 両刃と比べた場合の片刃の利点を示した。また, 切断時に片刃の切刃に発生する曲げ応力について, 刃面圧力センサの測定値を用いる方法と, 抵抗線歪みゲージをナイフに直接接着し, 測定された曲げモーメントを用いる方法の二通りで求め, 切刃の形状を検討した。刃先角が小さいほど曲げ応力は大きく, 刃先角25°のナイフでは300MPaとなった。切刃先端の強度を維持しつつ切断力を低減するために, 片刃の切刃の形状を二段刃とすることを提案した。
1 0 0 0 OA 關東山地五日市地方産二疊紀(?)腕足類に就いて(摘要)
- 著者
- 野中 諄一
- 出版者
- 日本地質学会
- 雑誌
- 地質學雜誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.609, pp.188-191, 1944-06-20
- 被引用文献数
- 1
昭和17年度東京帝大理學部地質學科中期學生志水次郎, 故橋本公久兩君は五日市近傍の地質調査中同地西北方の所謂白丸古生層帶より3種の腕足瓶化石を發見したが、そめ鑑定結果は次の如くである。a) 高明山山頂神社東側, 汚褐色珪質堅硬石灰岩: Hustedia(?)sp., b) 馬頭刈山北1100米通稱小宮澤, 白色結晶質石灰岩: Squamularia cf., asiatica CHAO, Dielasma new species 同地域の層序, 構造及び古生代有孔蟲化石に關しては既に藤本博士の御研究があり, 又今囘の調査の結果は地質學雜誌, 昭和18年9月號に發表せられた通りであるが, 白丸古生層帯は有孔蟲化石に依ればモスコウ階から上部二疊系までを含み構造複雜で逆轉を示してゐる處もある。併しながら本化石産出石灰岩は略々同一層準に位し高明山に於ては二疊紀を指示する有孔蟲化石を共産する事に依り上記腕足類も亦二疊紀(嚴察なる意味のウラル世を含めて)に屬するものと考へられる。
1 0 0 0 OA 日本産ザゼンソウ属の分布
- 著者
- 大塚 孝一
- 出版者
- 長野県自然保護研究所
- 雑誌
- 長野県自然保護研究所紀要 = Bulletin of Nagano Nature Conservation Research Institute (ISSN:13440780)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.1-8, 2002-03 (Released:2011-03-05)
日本産ザゼンソウ属の3種、ザゼンソウ、ヒメザゼンソウ、ナベクラザゼンソウについて、主な植物標本庫の標本に基づいて分布図を表した。ナベクラザゼンソウは長野県産の標本に基づいて記載された新種であるが、今回の調査で、この種は東北地方から北陸地方にかけての日本海側の地域に分布することが明らかになった。
1 0 0 0 OA 中学校理科における放射線を扱う学習機会の可能性に関する検討
- 著者
- 佐々木 敏紘 渡邊 直美 木幡 大河 長島 康雄
- 出版者
- 仙台市科学館
- 雑誌
- 仙台市科学館研究報告 (ISSN:13450859)
- 巻号頁・発行日
- no.23, pp.31-37, 2014-03-31
学習指導要領が改訂され,「科学技術と人間」の内容で「放射線にもふれること」と明記された。義務教育における理科という単元で扱う場合に,中学1年から3年までの間に多くの指導場面が可能であることを指摘するとともに,それを実証する目的で,中学校第2学年の理科で放射線教育を取り上げた実践を行い,中学2年生における放射線教育に関する学習機会の可能性を論じた。
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンピュ-タ (ISSN:02854619)
- 巻号頁・発行日
- no.573, pp.44-47, 2003-05-05
引っ越しシーズンのピークを迎えた4月1日。アートコーポレーションの千葉支店では多くの社員が仕事に追われていた。 騒然とするオフィス。その一角で、ある社員が少し暗いディスプレイに向かって、黙々と伝票のデータを入力している。省スペース型パソコンのように見えるが、いかにも古そうだ。よく見るとキーボードの配列がパソコン用のものとは少し違う。
1 0 0 0 OA 聖なるものの社会学 - デュルケーム理論の再検討
1 0 0 0 基礎音響工学
- 著者
- 城戸健一編著 曽根敏夫 [ほか] 共著
- 出版者
- コロナ社
- 巻号頁・発行日
- 1990
1 0 0 0 マルス顧客操作形端末(MV-60形端末)の開発
- 著者
- 中村 翼 古田 亮 宮崎 謙太郎
- 出版者
- 日本鉄道サイバネティクス協議会
- 雑誌
- 鉄道サイバネ・シンポジウム論文集 (ISSN:18842224)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, 2014-11
1 0 0 0 OA 農薬は可愛く, けなげです
- 著者
- 武居 三郎
- 出版者
- 日本農薬学会
- 雑誌
- 日本農薬学会誌 (ISSN:03851559)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.84-85, 2000-02-20