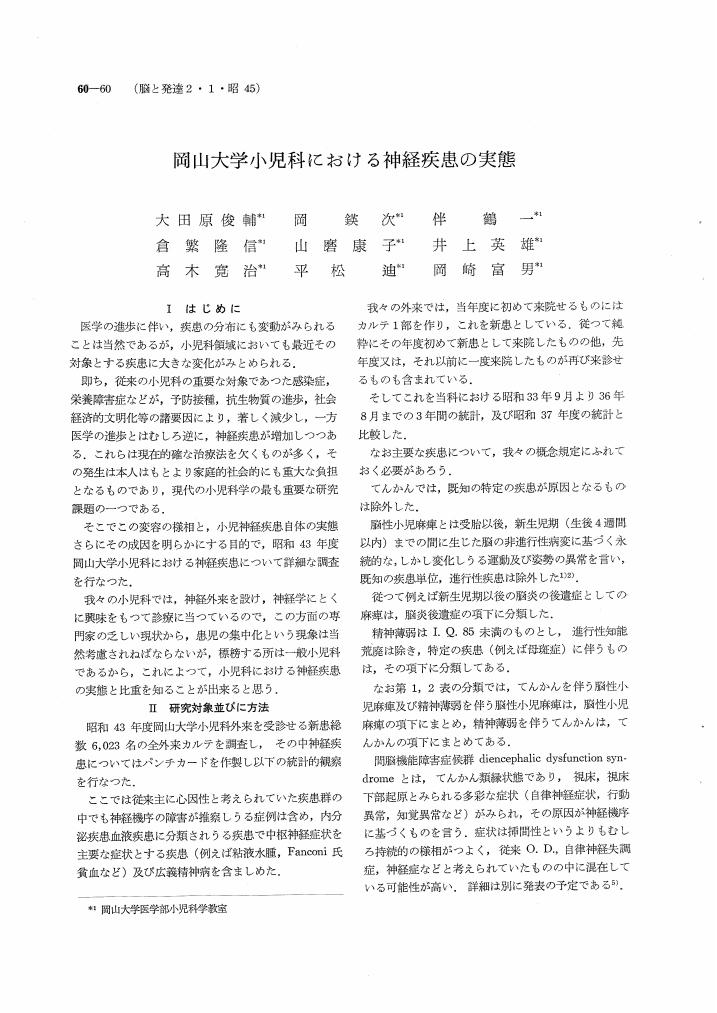1 0 0 0 OA 15.ワクチンによる肺炎の予防とその免疫学的機序
- 著者
- 川上 和義
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.9, pp.2365-2371, 2009 (Released:2012-08-02)
- 参考文献数
- 17
1 0 0 0 日露戦後の満洲経営と奉天商品展覧会
- 著者
- 長谷川 怜
- 出版者
- 一般社団法人中国研究所
- 雑誌
- 中国研究月報 (ISSN:09104348)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.7, pp.1-17, 2014-07-25
本稿では,日露戦後の満洲経営の展開について,1906年に満洲の奉天で開催された奉天商品展覧会を事例として検討する。奉天商品展覧会は,満洲における日本商品の販売拡大を目指す商業会議所が推進し,現地において様々な商品の陳列・販売が行われた。当時,日本は満洲の経済的開放を国際社会に公約していたが,日露戦争で得た権益の拡大と共に商業分野で独占的利益を得ようとしたため,英米等から猜疑を招いていた。そうした中,商品展覧会計画は,満洲における自由な経済活動を日本の政策主体が奨励する事につながると内外で判断され,計画段階では陸軍や外務省の支援が行われた。以上のように,初期の満洲経営が官・民の利害の一致により展開されていたことを明らかにする。
1 0 0 0 OA 小児難治性てんかんに対するTRH療法の短期効果
- 著者
- 皆川 公夫 田辺 千絵
- 出版者
- 一般社団法人 日本てんかん学会
- 雑誌
- てんかん研究 (ISSN:09120890)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.13-20, 1989-04-30 (Released:2011-01-25)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 2 3
未治療あるいは従来の抗てんかん薬では発作抑制が困難であったLennox症候群を中心とする難治性てんかん患児10例にTRH-tartrateを14日間連日筋注にて投与し, その短期効果を検討した。てんかん発作の抑制に関しては10例中8例に有効で, 5例には完全抑制が得られた。発作抑制効果は4~10日で発現した。脳波所見は10例中6例に改善がみられ, 4例ではてんかん放電が消失した。とくに, Lennox症候群では5例中3例に発作の完全抑制とてんかん放電の消失がみられ, 有効率が高かった。また, 全例に種々の程度の精神活動性の向上が認められたが, 重篤な副作用はみられず, 一部の乳児例に嘔吐, 発熱, irritabilityの増強が一過性に出現したのみであった。
1 0 0 0 OA 小倉金之助の数学教育における直観と論理
- 著者
- 佐藤 英二
- 出版者
- 東京大学大学院教育学研究科
- 雑誌
- 東京大学大学院教育学研究科紀要 (ISSN:13421050)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.231-239, 1997-12-12
Kinnosuke Ogura (1885-1962) was a mathematician, who introduced Perry's movement into Japan in the 1920s. His educational theory became a target for criticism in the 1960s on the grounds that it lacked logical and abstract aspect of mathematics. However this criticism holds true only at his Sugaku kyoiku no Konpon mondai (1924), but not at his later works. In Sugaku Kyoiku no Konpon mondai, he attached great importance on intuition, for it promoted students to think by self and to construct mathematical conception in their own ways, while he regarded mathematical logic as restraint of students'spontaneous thought. But in the 1930s works, he replaced 'intuition'with 'logic for children'. The intuition became no longer incompatible with mathematical logic. In addition he became to accept disciplinary value of mathematics education. What is more, getting powerfull in actual problem-solving, his theory got suitable to the need of militaristic empowerment in time of the Pacific War.
1 0 0 0 OA 岡山大学小児科における神経疾患の実態
1 0 0 0 OA 中国石窟芸術技法・材料の解明による美術史観再考‐麦積山石窟を事例として‐
- 著者
- 末森 薫
- 出版者
- 国立民族学博物館
- 雑誌
- 研究活動スタート支援
- 巻号頁・発行日
- 2014-08-29
中国甘粛省の麦積山石窟および敦煌莫高窟の壁画を対象として、1)壁画彩色材料光学情報の可視化、2)壁画制作材料・技法の非破壊分析、3)千仏図描写法の解析を進めた。1)では、狭帯域LED光源を用いた光学調査法を確立し、壁画表面の光学情報の抽出に有用であることを明らかにした。2)では、X線回折分析、蛍光X線分析、顕微鏡観察により、麦積山石窟壁画片に用いられた彩色材料や技法を同定・推定した。3)では、敦煌莫高窟の北朝期(5~6世紀)に描かれた千仏図が持つ規則的な描写表現を解析し、石窟空間における千仏図の機能を明らかにするとともに、千仏図の変遷より北朝期の石窟造営の展開について一考を提示した。
- 著者
- 伊藤 正義
- 出版者
- 鶴見大学文化財学会
- 雑誌
- 文化財学雑誌 (ISSN:13498371)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.76-63, 2013-03
1 0 0 0 IR 子宮がん患者が広汎子宮全摘出術後を安寧に生きるための強靱さの獲得を促進する看護援助
- 著者
- 秋元 典子 佐藤 禮子 Akimoto Noriko Sato Reiko アキモト ノリコ サトウ レイコ
- 出版者
- 千葉看護学会
- 雑誌
- 千葉看護学会会誌 (ISSN:13448846)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.26-33, 2003-06-30
- 被引用文献数
- 2 1
本研究の目的は,広汎子宮全摘出術を経験する子宮がん患者が,がんと共に安寧に生きるための強靱さを獲得していくことを促進する看護援助を検討することである。研究対象は,癌専門病院で広汎子宮全摘出術を経験する初発の子宮がん患者19名で,対象者の術前から術後6ヶ月間にわたり面接法および参加観察法を用いたデータ収集を行い,質的帰納的分析により,対象者の安寧に生きるための取り組みの様相と,関連する看護援助を明らかにし,以下を得た。1.広汎子宮全摘出術を経験する子宮がん患者は,【元気になりたい】という願いを原動力として,安寧に生きるためには【おしっこのコツをつかむ】【余計な消耗を避ける】【求めた情報を自分流に解釈して自らを救う】【生きるために懸命に食べる】【新しい価値観を獲得する】ことに取り組み,この取り組みの過程で【つまるところは自分次第】という意識を形成し,全ての問題解決に立ち向かう強靱な特性を培う。2.強靱さ獲得の源泉は,己の再生に欠かせない【おしっこのコツをつかむ】という必然的欠乏欲求であると言える。3.広汎子宮全摘出術を経験する子宮がん患者が,がんを抱えながら安寧に生きるための強靱さを獲得していくことを促進する看護援助は,【共有】【共感】【肯定】【支持】【強化】【尊重】を援助の基幹とし,(1)面接する(2)生活環境を快適に整える(3)食事を整える(4)身体の不快感や苦痛を緩和する,である。The purpose of this study was to identify how nursing care facilitated the efforts of cervical cancer patients who wanted to get well and to cultivate hardiness after a radical hysterectomy. Subjects were 19 patients with newly diagnosed cervical cancer who faced radical hysterectomy in a hospital specializing in cancer treatment. Data were collected by interviewing the patients and through a participant observation before and for 6 months after the operation. The following results were obtained by qualitative inductive analysis to reveal how the subjects faced the challenges of getting well and to clarify how nursing care was related to this effort. 1. Cervical cancer patients who experienced radical hysterectomy were motivated by the desire to be well and challenged the tasks of learning the technique of urination, avoiding unnecessary fatigue, acquiring and understanding information and using it to help themselves, eating well to build strength, and acquiring new values. During the process of those challenges to maintain well-being, they realized that "in the end, it is up to myself and cultivated the hardiness to face all problems. 2. The source of cultivating hardiness comes from maintaining ones' natural functions, such as learning the technique of urination. 3. Nursing care for cervical cancer patients with radical hysterectomy involved: a) interviewing patients, b) making their living environment comfortable, c) preparing meals and d) decreasing physical discomfort and pain. Such care was based on "Sharing," "Sympathy," "Affirmation," "Support," "Enhancement" and "Respect."
1 0 0 0 基本権の構造--「法的様相の理論」の見地から
- 著者
- 新 正幸
- 出版者
- 日本大学法学会
- 雑誌
- 日本法学 (ISSN:02874601)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.473-515, 2007-12
1 0 0 0 OA 高校生の生活習慣と咀嚼能力
- 著者
- 松田 秀人 橋本 和佳 高田 和夫
- 出版者
- 名古屋文理大学短期大学部
- 雑誌
- 名古屋文理短期大学紀要 (ISSN:09146474)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.25-29, 2004-04-01
目的:生活習慣とチューインガムを用いて咀嚼能力を調べた.方法:高校生を対象に生活習慣を調査した.生活習慣と咀嚼能力の関連を調べるために,歯科用キシリトールガムを用いて咀嚼能力を測定した.結果:咀嚼能力に有意差が認められた生活晋匿は,男子生徒では,「運動が大好きですか」,「朝食は毎日必ず食べていますか」であり,女子生徒では,「食べる速さはいかかですか」ゾきらいな食べ物がたくさんありますか」,「寝る前によく食べたり飲んだりしますか」であった.すなわち男子生徒では,運動が大好きな生徒,朝食を毎日必ずしも食べていない生徒のほうが咀嚼能力が強かった.また女子生徒では,食べる速さが遅い生徒,嫌いな食べ物が少ない生徒,寝る前によく食べたり飲んだりする生徒のほうが咀嚼能力が強かった.しかしながらよく噛んで食べていると自覚している生徒の咀嚼能力は,よく噛んでいないと自覚している生徒と有意差が認められなかった.よく噛んでいるという自覚と咀嚼能力は一致していなかった.
1 0 0 0 すぐに役立つPDF徹底活用術(2)PDFファイルに文字を入力する
- 著者
- 染原 睦美
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経パソコン (ISSN:02879506)
- 巻号頁・発行日
- no.482, pp.159-162, 2005-05-23
入力欄付きのPDFもある/体験版で「青い箱」を作る/文字入力の専用ソフトを使う
1 0 0 0 手根骨の動作解析
- 著者
- 山形 朋久 藤崎 紘久 長谷川 哲 浅田 莞爾
- 雑誌
- 日本臨床バイオメカニクス学会誌 = Proceedings of ... Annual Meeting of Japanese Society for Clinical Biomechanics and Related Research (ISSN:13409018)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.119-122, 2006-10-20
1 0 0 0 OA メンタルスペース理論におけるコピュラの分析はどこまで妥当か
- 著者
- 西山 佑司
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.1_135-1_140, 1994-05-20 (Released:2008-10-03)
- 参考文献数
- 11
- 著者
- 三藤 博
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.2, pp.2_86-2_89, 1994-11-30 (Released:2008-10-03)
- 参考文献数
- 14
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経Linux (ISSN:13450182)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.5, pp.40-57, 2005-05
VMware Workstationを使えば,例えば,Windows上でLinuxを同時に利用できます。両OSでファイルの共有も可能です。VMwareの設定,OSのインストール,パフォーマンス改善方法など,VMwareを使うための手順を詳しく紹介します。 自分のPCに新しいOSをインストールしてみたい,体験版のソフトを試してみたいなどと思ったことはありませんか。
- 著者
- 中嶋 信生
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. RCS, 無線通信システム (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.192, pp.33-38, 2007-08-16
- 被引用文献数
- 3
ユビキタス社会やセンサーネットワークに適合する、近距離無線やローカルネットワークの研究実用化が最近非常に賑わっている。本報告では、関連する無線規格である無線LAN、Bluetooth、IEEE802.15.4、UWB、RF-ID、微弱電波などの特徴を紹介すると共に、それらの無線規格を用いたネットワークの構成例を述べる。特に、測位応用については、GPSの補完としての屋内測位(LPS : Local Positioning System)が今後の主要研究テーマの1つと考えられるので、報告者の研究結果を含めいくつかの実例を紹介する。
1 0 0 0 OA ボリビア国中部のコロコロ堆積盆地の礫ついて : 堆積
- 著者
- 田附 治夫 前田 四郎
- 出版者
- 日本地質学会
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨
- 巻号頁・発行日
- vol.81, 1974-08-25
- 著者
- Jackson, Holbrook, 1874-1948
- 出版者
- Faber and Faber
- 巻号頁・発行日
- 1947
1 0 0 0 OA 才さかし出ではべらむよ : 『紫式部日記』の一文
- 著者
- 栗田 岳
- 出版者
- 東京大学大学院総合文化研究科言語情報科学専攻
- 雑誌
- 言語情報科学 (ISSN:13478931)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.17-31, 2010-03-01
『紫式部日記』の「才さかし出ではべらむよ」という一文(「当該箇所」と称する)について、「さかし出づ」と「むよ」の実例を調査し、以下の結論を得た。まず、当該箇所に見られる「さかす」は、「【才】を盛んな状態にする」意である。さらに、それが「出づ」と複合した結果、「【才】を【さかす】ことによって、【才】が表に【出づ】」という構造を成す。したがって、「才さかし出づ」とは、「才知を盛んな状態にすることによって、その才知が表に現れる」の如く解釈するのが適当である。一方、述語にムヨを持つ文には、言語主体の、「自身の当然とするところから外れた事態が、未来時において避けがたく生じてしまう」という判断を表す例があり、当該箇所も、その一つと見られる。以上を総合するに、当該箇所とは、「宮中で才知を働かせて、それが人の知るところになる」という事態は、謙抑を当然とする自分本来の姿からは外れているけれど、その事態がこの先に生じてしまうことは避けがたい、と嘆息する文である。そして、この解釈は、当該箇所に続く『紫式部日記』全体の文脈と調和している。