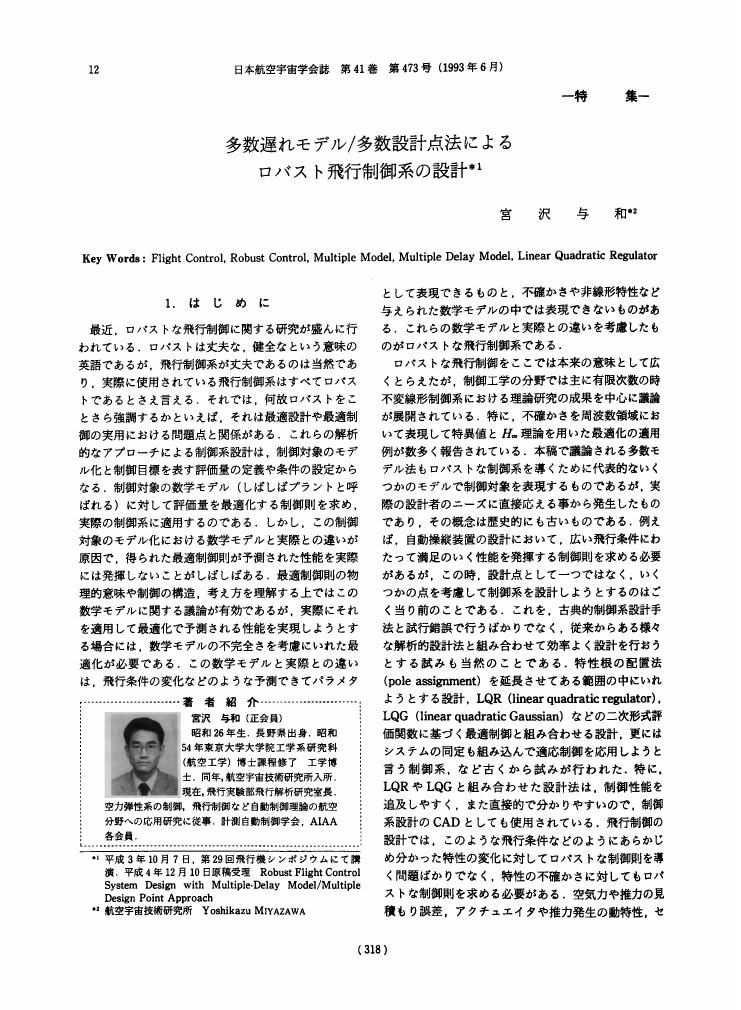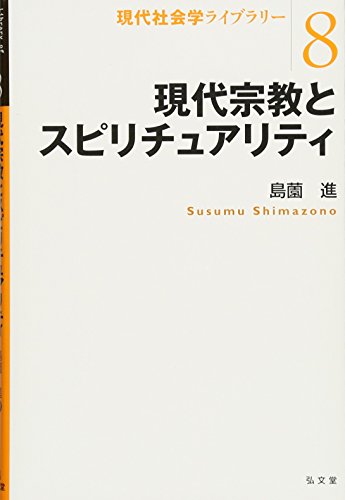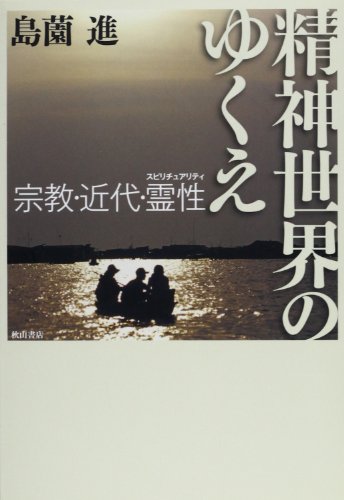- 著者
- 金子 安比古 松下 竹次
- 雑誌
- 日本小児科学会雑誌 (ISSN:00016543)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, no.2, pp.534-539, 1995-02-01
- 被引用文献数
- 16
1 0 0 0 OA 高齢化が進む離島集落の再編に資する横断的研究
日本で加速度的に高齢化が進むなか,離島はその先陣を切って進んでいるといえる。離島集落は管理能力不全が起こり始め,集落の再編期に直面するなか,コンパクト化に向けて進んでいく傾向が見られる。しかし予備調査から,離島では相当の対価を支払っても,現住地に居住継続したいという結果を得た。地域の特色と居住傾向がどう関係しているのかを見ると,結果として居住者の満足度や生きがいの差は立地や利便性と強い関連性は見いだせない。隔絶性の高い地域で,高齢者が自発的に活動に参加し,また廃校の活用においても,多くの主体によって複数の空間が複数の用途に柔軟に活用されるなど,地域や個人の自立性が高いことが推察できる。
1 0 0 0 OA 岩手県沿海四郡聯合物産共進会記念写真帖
- 出版者
- 岩手県沿海四郡連合物産共進会
- 巻号頁・発行日
- 1912
1 0 0 0 OA 自己組織化現象を利用した三次元ナノ構造作製技術
ポリスチレンとポリメチルメタクリレートのジブロック共重合体が持つ自己組織化現象によって構成される30~100nm程度のピラー,ポア,膜の各自己組織化ナノ構造を三次元ナノ構造として作製する技術を開発した。具体的には,(1)三次元ナノ構造表面に自己組織化構造を配置する方法,(2)ナノテンプレートを利用して三次元的に自己組織化構造の配列を制御する方法,(3)自己組織化構造をテンプレートにした多層膜を作製する技術,(4)三次元ナノフレームに自己組織化自由膜を作製する方法,(5)エネルギービーム照射による自己組織化構造のナノパターンニング技術,(6)集束イオンビーム照射による薄膜接合技術を提案し,実験により可能性を示した。
1 0 0 0 OA 歴史時代の蔵王火山の噴火史とその様式 -歴史記録と比較火山学に基づく復元-
- 著者
- 及川 輝樹 伴 雅雄
- 出版者
- The Geological Society of Japan
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- pp.084, 2013 (Released:2014-04-01)
- 出版者
- 日本動画協会データベースワーキンググループ
- 巻号頁・発行日
- 0000
- 出版者
- 日本動画協会データベースワーキンググループ
- 巻号頁・発行日
- 2010
- 著者
- 小野 清子
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.957, pp.127-129, 1998-09-14
今年7月の参議院議員選挙で、私は東京選挙区から自由民主党の公認候補として立候補しました。結果は、残念ながら4人の当選枠に入れず次点で落選となりました。 1986年に参議院議員に初当選してから、私は2期12年にわたり国政の場で文教、環境の問題を中心に取り組んできました。
1 0 0 0 移動計算機における情報ベース検索スクリプトの合成方式
- 著者
- 大森 匡 Wisut Sae-Tung 星 守
- 雑誌
- 全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.237-238, 1996-03-06
- 被引用文献数
- 2
最近のコンピュータネットワークではWWWなど様々な情報資源を提供するサーバ(情報ベース)が自然発生的に点在しており、ユーザか移動計算機からこうした情報資源を自由に検索・加工したい、という要求が大きい。しかし、これら情報ベースはユーザが望む利用手段や情報構造をあらかじめ用意していないことが多く、結果としてほぼ全ての情報を移動計算機側からブラウズしがちである。この問題を解決するためには一般に仲介者と呼ばれる補助機構が必要である。我々はスクリプト言語による遠隔プログラムを使ってこの機構を提案してきた。図1が提案した仲介者機構による検索手順である。すなわち、ユーザは未知な情報ベースに対し、(1)始めに、ユーザは情報ベースへそのクラス定義を問い合わせ、その仕様(i.e. 情報構造と利用手段)を教えてもらう。(2)次に、移動計算機欄で自分がやりたい検索スクリプトを合成し、(3)情報ベースに送って実行させる。この手法では、個々のユーザに依存した情報検索・加工手続き自体(「関心がある情報を探す」など)は移動計算機に載ってネットワーク内を移動し、必要な時に情報ベースへ送られる。従って情報ベース側ではそれ固有の検索手段以外はスクリプト言語の処理系だけを用意すれば良い。 我々はこの機構をPerlに永続オブジェクト操作機能をいれたスクリプト言語Persistent Perlを用いて試作している。しかし、移動計算機上にあらかじめ持っていた検索スクリプトと、情報ベース固有の情報との二つを合わせて使うようなスクリプトをユーザが直接Persistent Perlを使って記述するのは難しい。本稿ではオブジェクト指向SQLを使ってこうした検索スクリプトを合成する方式を論じる。
本研究は、難治性の皮膚角化症であるダリエー病、ヘイリー・ヘイリー病に対する外用治療薬の開発を目標とする。ダリエー病およびヘイリー・ヘイリー病は、各々SERCA2遺伝子、SPCA1遺伝子の変異による比較的頻度の高い優性遺伝性の角化皮膚疾患であり、醜形・悪臭を伴う皮疹が思春期以降の顔や胸部などの脂漏部位、あるいは腋窩などの問擦部に発症するが、現在の所、有効な治療法が存在しない。両遺伝子より転写される小胞体、ゴルジ体のカルシウムポンプであるATP2A2、ATP2C1蛋白の蛋白量が低下し、表皮角化細胞が正常な角化プロセスより逸脱することで発症する。我々は、ハプロ・インサフィシエンシーと呼ばれるこの発症メカニズより、SERCA2あるいばSPCA1遺伝子の転写を亢進し、患者皮膚でのポンプ蛋白の発現量を変異体・正常蛋白ともに増加させることで、皮膚症状を改善しうると考えた。そこで培養ヒト表皮角化細胞を用い、SERCA2・SPCA1遺伝子の発現を増強させる薬剤を、脂溶性薬剤ライブラリーをスクリーニングすることで網羅的に探索した結果、カンナビノイドとバニロイドと呼ばれる作動薬の1群が、ヒト皮膚でのATP2A2蛋白の発現を亢進することを発見し特許を申請した。ln Vitroの解析結果より発見した各作動薬群の薬剤を今後、モデル動物を用いたEx Vivoの実験を通して、より効果的で安全性の高い薬剤を検討することで探索するとともに、近い将来の臨床治験などへ向けたより効果的な薬剤の選定を進めている。さらにヘイリー・ヘイリー病の治療薬となるべき薬剤のスクリーニングも継続している。
1 0 0 0 OA 多数遅れモデル/多数設計点法によるロバスト飛行制御系の設計
- 著者
- 宮沢 与和
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.473, pp.318-323, 1993-06-05 (Released:2010-12-16)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1 2
1 0 0 0 OA パーキンソン病患者の異常姿勢に対する運動療法
- 著者
- 齋藤 透
- 出版者
- 社団法人 日本理学療法士協会関東甲信越ブロック協議会
- 雑誌
- 関東甲信越ブロック理学療法士学会 第28回関東甲信越ブロック理学療法士学会 (ISSN:09169946)
- 巻号頁・発行日
- pp.6, 2009 (Released:2009-08-11)
【目的】今回は過度な右側弯・前屈姿勢で腰痛、右下肢の痺れを呈する58歳の若年性parkinson病(以下PD)患者を担当した。入院から外来を通じて治療経過を追うと共に、在宅での生活を加味した管理とリハビリ、注意点に対して再考慮したい。 【症例紹介・方法】症例はH8年に字の書き難さで発症。徐々に前屈・非対称姿勢、右側優位の固縮・振戦を認め、H18年よりシルバーカーを使用。同時期より転倒回数の増加並びに腰痛をきたした。報告時はYhar4。今回は薬剤性の意識障害・異常行動のため入院。座位保持は右上肢優位での支持を要し、歩行は二つ折れの姿勢で前方突進はあるが可能。needは「姿勢を真っ直ぐにしたい」ということであった。治療は1回40分、計4回、外来で週1回、数回の運動療法を実施。起居動作、姿勢、歩行をビデオ撮影し、また検査項目としてTimed Up and Goテスト(以下TUG)の治療前後の比較(シルバーカー使用)。治療に繋げる視点から動作の問題点を検討、自宅での練習及び管理状態を調査した。尚、症例より掲載の承諾を頂いた。 【結果】TUGの治療前後は23秒から34秒(2/13)、32秒から40秒(2/23)と増加した。治療前後では立ち上がり方、姿勢、前方突進が改善、腰痛・下肢の痺れは減弱、また転倒回数が減少した。 【考察】結果より時間の延長を認めた要因は、本人が対象姿勢を意識し、ゆっくり動作を行っているためと思われる。非対称姿勢の主要因は右肋骨と骨盤間の伸展活動の低下、二次的要因に右股関節の屈曲内旋固定が見られた。左記に着目し姿勢改善を図ることで運動のbaseとなる全身の筋緊張が整い、体幹の抗重力活動が向上したためと考える。治療場面は背臥位で四肢の運動から体幹の支持性を高め、段階的に立位で体幹を空間で保持をするようにしたことが姿勢に関して認識しやすかったと思われる。自宅での姿勢管理では坐位時は机上に両肘を着き非対称姿勢の管理を喚起し、左殿部に支持面を持つように意識付けし対称的な姿勢に近づけたことが腰痛低下・治療効果の持続に繋がったと考える。 【まとめ】今回対称的な体幹、抗重力活動を再学習し視覚的な情報により再確認し、実際の環境を工夫することで数回のリハビリにより改善が図れた。今後の課題として、治療の期間を考慮し学習をどれだけ持続できるかを検討していきたい。
1 0 0 0 成文法と判例法を融合した法律人工知能システムの国際共同研究
- 著者
- 吉野 一 KOWALSKI Rob BRANTING Kar RUESSMANN He HERBERGER Ma ASHLEY Kevin BERMAN Donal HAFNER Carol 桜井 成一朗 北原 宗律 原口 誠 加賀山 茂 松村 良之 HELMUT Ruess ROBERT Kowal MAXIMILIAN H KEVIN D Ashe DONALD H Ber CAROLE D Haf RUESSMAN Hel
- 出版者
- 明治学院大学
- 雑誌
- 国際学術研究
- 巻号頁・発行日
- 1991
本研究は、国際統一売買法を対象領域として、成文法国である日本および西ドイツと判例法国であるアメリカ合衆国の研究者が、それぞれの法体系の特徴である「ルールに基づいた推論」と「事例に基づいた推論」の論理分析を行ない、それぞれの推論のシステム化の研究成果を交換するとともに、共同でルールの解釈と類推適用のメカニズムを解明し、それに基づいて、ルール型の推論システムと事例型推論システムとを融合させることを目的とした。平成5年度において次の点が達成された。(1)本国際共同研究によって、大陸法系の「ルールに基づいた推論」と英米法系の「事例に基づいた推論」の論理構造がそれぞれおおよそ明らにされた。(2)「ルールに基づいた推論」と「事例に基づいた推論」の相互関係、両者を融合させる道が明らかとなった。すなわち、法ルールの解釈において事例に基づく推論を利用する方法が明らにされた。(3)法的知識の表現方法として、論理流れ図の方法と複合的述語論理式(CPF)による方法とが確立された。(4)CISG(国連売買条約)の第2部契約成立の部分の論理構造が解明された。そしてそれが、開発された知識表現方法である(日本語と英語版の)論理流れ図およびCPFによって、コンピュータ上に表現された。この表現形式を共通の表現形式として用いることに日米の研究者の合意が形成された。(5)CISGの論理流れ図表現を対象に日・米の研究者が議論したが、これは異なる言語、異なる法文化を持つ日米の両国の法律家の間によいコミュニケーションを実現する方法であることが判明した。(6)CISGの法解釈学的諸論点が明らかとなった。また解釈の違いと背景となる法文化の関係が明らかになった。(7)ドイツ側の研究者は、英語、ドイツ語およびフランス語のマルチ言語のCISGのハイパーカードシステムを完成した。またCISGのドイツ語テキスト文からそれに対応する述語論理式を半自動生成する知識獲得支援実験システムを作成した。次の点で成果はあげつつも、当初計画をそのままの形で実現することはできなかった。(1)ルール型推論システムおよびルールからの類推実験システムを作成した。しかし、ルール型推論システムをアッシュレ-などの事例型推論システムと結合させるまでには至らなかった。従ってまた、ルールに基づいた推論と事例に基づいた推論を融合するシステムの実装も実現できなかった。(2)述語論理式から日本語文および英語文を生成する試験システムを作成したが、日本語と英語の法律知識ベースを融合するためのインターフェースを作成するまでには至らなかった。(3)研究のまとめ方と研究成果の執筆分担の取り決めがなされたが、年度内に本国際学術共同研究の成果報告書を作成することができなかった。これらは研究を進めるに従って問題の深さが明らかになり、安易にシステムの実装を急ぐより、研究の基礎を固めることにより努力した結果でもある。とはいえ、本国際学術共同研究によって、複数の言語で表現され、しかし条約として合意されたことによって一つの内容を持つCISG(国連売買条約)を対象にし、また大陸法系の成文法主義(ルール主義)の法的推論と英米法系の事例主義の法的推論を比較検討し、それを両者を融合させる方向で人工知能システムとして実現しようと努力したことによって、一方において、同法の諸論点が明らかになったとともに、異なる言語および法文化に属する法律家間のコミュニケーションの方法が提供された。本研究は比較法の新たなメソッドを提供した。他方において、人工知能研究にとっても、事例にもとづく推論で法ルールの解釈を支援するシステムの実現方法が確立された点で、有意義な成果を挙げたといえる。
1 0 0 0 OA 確率制御理論の応用的研究
確率制御問題の数値解法の研究を行い、数学的に厳密に収束が保証され、かつ広範囲の問題に適用でき実装も容易な新しい近似手法の開発に成功した。この手法は計算時間の短縮についてまだ研究の余地があるが、既存手法には欠けていた厳密性・汎用性を兼ね備えている。さらに、より単純で使いやすい近似法の研究を行い、確率制御問題に対応するハミルトン・ヤコビ・ベルマン方程式の2次近似により解を生成する手法の近似誤差を評価した。その結果、問題の目的関数が2次的で、状態のダイナミクスが線形に近い場合は、単純な2次近似法でも精度が高いことが分かった。
- 著者
- 片田(孫) 朝日
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 京都社会学年報 : KJS
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.73-94, 2003-12-25
This study explores the characteristic of girls' language uses in their play activities and illuminates the variety of the styles in contexts. Previous studies in Japan have found that girls and boys learn and use gender-appropriate behaviors and linguistic forms. According to these studies, girls and their groups use more polite and collaborative linguistic styles, including more mitigated verb forms, than boys. Among girls "the rule of considerateness" to others (Goffman) earns more attention than among boys. These studies, however, tend to depict children as beings who are one-sidedly socialized to be simply bound by the gender norms. This study tries to show that girls, depending on the contexts, carefully choose various linguistic styles including masculine ones, and make tactical use of the rules of considerateness and of the norms of girls' styles in their play interactions. This study are based on the data obtained through naturalistic observation and videotaped play interaction of girls and boys (of age six to nine) in a child care center in Kyoto City. In this study, the girls who like to play house, drawing and card games, were found to form more exclusive and stable play groups than those of the boys. When the girls want to get other girls to do something, they usually designed directives - speech acts in more mitigated forms. The girls in one of the two groups were willing to show their consideration for younger girls. These girls, on the other hand, reproached other girls' for their behaviors which according to them lacked consideration, using such a term as "Ijiwaru" (mean). They not only conform to the rule of considerateness, but also actively use it for themselves. In addition, the girls change their style in contexts. When boys invaded their plays, they baldly accused the boys and order to go away in imperative forms. The girls in the higher status group, also often teased and denounced a peripheral member in the group. They design directives aimed at her in aggravated forms. But the denounced girl herself challenged the denouncers insisting that an aggressive behavior is not appropriate for girls.
1 0 0 0 OA 躍進豊橋市制三十周年記念写真
- 出版者
- 東海時事社
- 巻号頁・発行日
- 1936
1 0 0 0 現代宗教とスピリチュアリティ
1 0 0 0 精神世界のゆくえ : 宗教・近代・霊性 (スピリチュアリティ)
1 0 0 0 素粒子・原子核・宇宙分野のための分野横断型線形計算手法の開発
- 著者
- 櫻井 鉄也
- 出版者
- 筑波大学
- 雑誌
- 新学術領域研究(研究領域提案型)
- 巻号頁・発行日
- 2011-04-01
本課題において、以下の研究を実施した。(1) 複数の右辺ベクトルを持つ連立一次方程式に対して開発したBlock Krylov subspace methodに対して、残差行列の直交化による安定性の改善を行い、さらにシフト行列に拡張した。開発した手法を密度汎関数法で現れるバンド図計算に適用し、従来その計算量の多さから実現できていなかった規模の原子数で結果を得ることができた。また、固有ベクトルの相関を利用することで、少ないステップでバンド曲線を描くことが可能になった。(2) 行列トレースのstochasticな推定法を利用した固有値分布の大域的推定により、指定した領域の固有値密度を推定することで、固有値計算で用いる解法の適切なパラメータ自動推定法を開発した。これにより、パラメータの最適化をユーザが行う必要がなくなり、解法の利用性が向上した。(3) 超新星爆発のシミュレーションで現れる大規模な線形方程式を対象として、そこで現れる行列の性質を解析し、前処理のための適切なスケーリング法、およびパラメータの選択をする方法を開発した。また、前処理行列に対して影響の少ない行列要素のカットオフを行い、計算時間の短縮を行った。開発した手法を実装し、超新星爆発シミュレーションで現れる問題に適用して、従来法に対して計算時間が短縮されることを確認した。実問題に対応した規模で計算を行うために、開発した手法の並列化を進めた。
- 著者
- Nagaaki Katoh Akira Matsushima Masahiro Kurozumi Masayuki Matsuda Shu-ichi Ikeda
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.17, pp.1991-1995, 2014 (Released:2014-09-01)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 3 10
A 52-year-old woman with a high serum alkaline phosphatase (ALP) level underwent a liver biopsy, which showed diffuse heavy deposition of Aκ amyloid, and was diagnosed as having immunoglobulin light chain (AL) amyloidosis. Although she received high-dose melphalan with stem cell transplantation and achieved a hematologic complete response (CR), her ALP level began to increase one year after treatment. Further examinations revealed that she was still in a CR state with dominant bone-type ALP, and re-biopsied liver specimens demonstrated marked regression of amyliod deposition, providing important evidence that the turnover of hepatic amyloid proteins can actually occur more rapidly than previously thought.