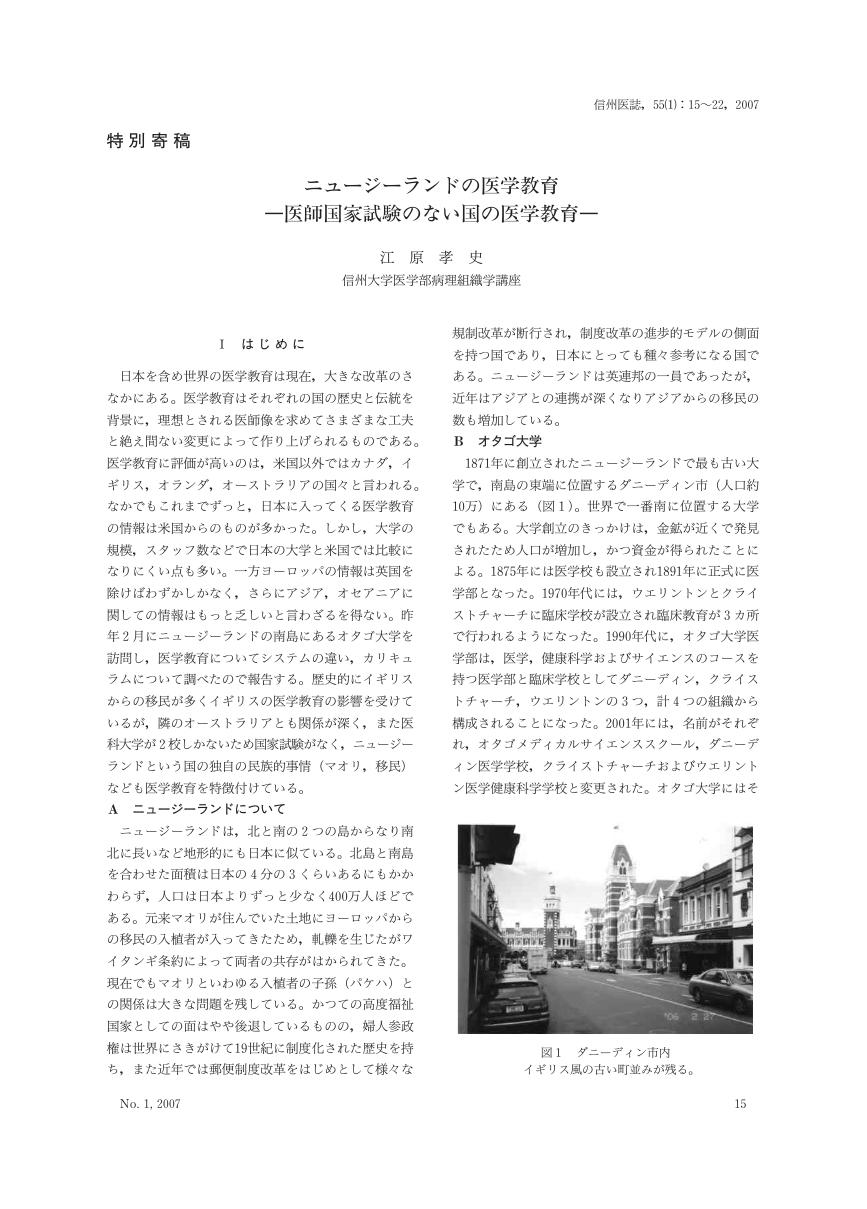2 0 0 0 OA クシシュトフ・ヴォディチコの「パブリック・プロジェクション」の変容とその意味について
- 著者
- 越前 俊也
- 出版者
- 美学会
- 雑誌
- 美学 (ISSN:05200962)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.43-56, 2006-09-30 (Released:2017-05-22)
Krzysztof Wodiczko started his Public Projection in 1980, by anatomical analysis of architectures on photographs. If we use the terms of Walter Benjamin, this new artistic presentation can be understood as a behavior to give an Exhibition-Value to architectures, which have their own Aura and Cult-Value. According to the terms of Alois Riegl, the writer of "The Modern Cult of Monuments," it also can be understood as a behavior to make known the intention of authors of architectures by projecting their symbolic images to Intentional Monuments. It changed, however, in the middle of 1980's, to a behavior to protect Monuments by projecting critical thoughts and reflections of inhabitants around them. Wodiczko seemed to regard their thoughts and reflections as Artistic-Will (Kunstwollen), one of the most important terms of Alois Riegl, but we must not overlook that there is a gap between them. Video Public Projections, which Wodiczko started in 1996, used architectures as transitional objects: a term of developmental psychology for silent speakers. Public Projection continued changing in the past quarter century in order to extract various abilities of architectures.
2 0 0 0 OA オゾン/酸素混合ガスの最小着火エネルギー
- 著者
- 水谷 高彰
- 出版者
- 独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
- 雑誌
- 労働安全衛生研究 (ISSN:18826822)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.45-48, 2009 (Released:2009-06-30)
- 参考文献数
- 5
近年,オゾナイザー(酸素をオゾンにする装置)の開発により,10vol.%を超える高濃度オゾンガスが酸素ガスから直接,得られる様になった.前報では,オゾン濃度15vol.%以下,初圧1.0MPa以下の条件下における分解爆発限界濃度や最大爆発圧力,火炎伝ぱ機構とオゾン濃度,圧力の関係を実験から明らかにした.本研究ではオゾン濃度15vol.%以下,大気圧のオゾン/酸素混合ガスの最小着火エネルギーを測定した.最小着火エネルギーはオゾン濃度の増加にともない,指数関数的に減少し,オゾン濃度15vol.%近傍では10mJ程度となった.この値は,大気圧下、化学量論組成近傍のメタン/空気混合ガスの最小着火エネルギー0.2mJより大きい値であるが,可燃性粉じんの爆発における最小着火エネルギー1~300mJ程度から比較すると決して大きい値ではない.オゾナイザーの開発がさらに進み,15vol.%を超えて高い濃度のオゾン/酸素混合ガスが製造される様になれば可燃性混合ガスと同程度,もしくはそれ以上に着火危険性が高い混合ガスになることが示唆される.最小着火エネルギーの測定条件の検討のため,放電間隙を変えて14vol.%オゾン/酸素混合ガスの最小着火エネルギーを測定した結果,放電間隙3~4mmで最小値をとった.この結果は,消炎距離が2~3mmであるという以前の研究結果と符合した.
2 0 0 0 OA 情報入手時間の差異がある市場の振る舞いに値幅制限が与える影響:人工市場によるアプローチ
- 著者
- 謝 凡 秋山 英三
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会論文誌 (ISSN:13460714)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.5, pp.AG21-A_1-8, 2021-09-01 (Released:2021-09-01)
- 参考文献数
- 22
To enhance the stability of the financial markets, price limits have been implemented in numerous financial markets. The effects to markets’ stability and traders’ profitability of price limits have been discussed by previous research. But it has not been discussed when there is difference between traders on speed of information acquisition. The asymmetry of information acquisition between traders can be observed in many situations, e.g., overseas investors and domestic investors, insiders and outsiders. Because methods, languages, etc. they use to get information are different, they obtain information about the fundamental values of financial commodities with different speeds. We used a double-auction artificial market to simulate when difference on speed of information acquisition exists, how price limits effect the stability of the financial market, and the profitability of traders who has different speeds to obtain the information about fundamental value. We found if there is difference of speed for getting information between traders, price limits do not always enhance the stability of market. When the band of price limits is loose, the volatility of market price will rise if the ratio of traders with fast speed of information acquisition is relatively large. And when the band of price limits is loose, some traders who has slower speed of information acquisition may be hurt by price limits. Our work shows it is necessary to consider the difference on speed of information acquisition when designing some market institutions like price limits.
2 0 0 0 OA 昆虫の翅を規範とした柔軟なマイクロ人工翅
- 著者
- 田中 博人
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.5, pp.405-409, 2015-05-05 (Released:2015-05-05)
- 参考文献数
- 8
- 著者
- 山下 達也
- 出版者
- 教育史学会
- 雑誌
- 日本の教育史学 (ISSN:03868982)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, pp.97-109, 2007-10-01 (Released:2017-06-01)
This paper intends to clarify diversity amongst "Mainlander" (Japanese) teachers in colonial Korea. "Mainlander" (Japanese) teachers were a central presence in elementary schools in colonial Korea that cannot be overlooked when discussing Japanese colonial education policies. Conventional literature on the subject has heretofore clarified such matters as teachers' hometown, transfers, instructional activities, and the like. Results of such studies are keys to clarifying the reality of "Mainlander" teachers. However, understanding of "Mainlanders" who became teachers in colonial Korea should not be limited to only one category, and I problematize this point. Among "Mainlander" teachers in Korea, a variety of people coexisted who can be differentiated by length of stay/career in Korea, presence or lack of experience spent in "the Mainland" (Japan) and gender. The historical reality, therefore, cannot be determined if all teachers in colonial Korea are simply labeled "Mainlander" teachers. Although it goes without saying that we should not overlook the fact that "Mainlanders" as settlers possessed specific positions and roles, at the same time, it is necessary to recognize their internal diversity. Following this outlook, this paper differentiates so-called "Mainlander" teachers by examining the characteristics and relations of "Mainlander" teachers invited from "the Mainland" versus "Mainlander" teachers trained in Korea. First, I pay attention to the teacher-training phase of each, because it is clear that these groups passed through a different process of training. Second, I examine the characteristics and relations of both through document analysis, looking specifically at the times when these individuals became teachers, understandings about educational ideas and policies of the Governor-General's office, knowledge about Korea, and grasp of "the Mainland" were different for each group of teachers. In particular, I argue that these differences originated in differences in the teacher-training process found in Japan and colonial Korea. In addition, I argue that when "Kominka Education" became strongly entrenched, a difference in the characteristics of each type of teacher becomes evident. In addition, I reexamine the implications of the existence of invited teachers from Japan, whose presence had previously been understood as necessary in order to make up for the lack of teachers in colonial Korea.
2 0 0 0 OA 膵疾患のMDCT診断
- 著者
- 入江 裕之 吉満 研吾 石神 康生 田嶋 強 浅山 良樹 平川 雅和 牛島 泰宏 本田 浩
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, no.12, pp.1333-1338, 2006 (Released:2006-12-06)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 4
膵疾患のMDCT診断を行うための必要な知識として,MDCTの特長,膵のダイナミックCT, 3次元画像の臨床的有用性について解説した.MDCTの特長は高時間分解能と高空間分解能にあり,それらを利用して得られるボリュームデータは臨床に役立つ3次元画像を提供する.膵のダイナミックCTは膵実質相,門脈相,遅延相の3相撮像が基本であり,適切な撮像開始時間を設定するためには造影剤の血行動態を理解しておくことが重要である.CTAは膵疾患の術前血管造影を不要にし,MPRは膵疾患の診断能を向上させた.さらに主膵管の全長を1画像で表示できるCPRは膵疾患のMDCT診断にはなくてはならない画像となっている.
2 0 0 0 OA 人と動物の間の社会的感情としての擬人化
- 著者
- 山田 弘司
- 出版者
- 日本動物心理学会
- 雑誌
- 動物心理学研究 (ISSN:09168419)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.41-47, 2012 (Released:2012-07-27)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
This study surveys dairy farmers' ways of raising, sense of animal welfare, and emotional impressions on their cows, and discusses their personification to livestock in contrast with that to companion animals. The farmers have professional knowledge and skills to feed and handle the cows. They get a living from keeping cows, considering the cost and benefit. This economy-based view sometimes leads to the desertion of treatment on disordered livestock. Companion animal owners usually keep their animals with no such economy-based but emotion-based view. Farmers' “employer-employee” relationship to their cows would interfere with the personification attitudes. This author compared the attitudes of 187 dairy farmers and 218 collage students, reveals the dairy farmers show more sensitivity to animal welfare and more favorable impression and stronger personification, such as “child-like” and “family-like” views. Thus emotion-based attitudes and the personification would be caused in any situations with human-animal interactions, regardless of the roles and the professional knowledge of animals. As a calming effect of handling for experimental animals and decreased escape distance on intimately reared cows show, animals interacted with human also have the emotion-based affection or emotional bond.
2 0 0 0 OA 福島の原子力事故の経験から 『牛ふんの汚染を例に基準値の課題を考える』
- 著者
- 白井 真
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.12, pp.758-759, 2015 (Released:2020-02-19)
2 0 0 0 OA 半夏厚朴湯が著効した周期性嘔吐症候群の一例
- 著者
- 越田 全彦 山崎 武俊
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, pp.134-139, 2017 (Released:2017-10-20)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 2
症例は特記すべき既往のない19歳男子大学生。16歳の時に明らかな誘因なく1日に10回以上嘔吐を繰り返し,経口摂取不能のため近医入院の上,点滴加療を受けた。発作間欠期にはほぼ無症状だが,以後年に2~3回,激しい嘔吐のために1週間程度入院するようになった。その都度精査を受けたが,脱水を認めるのみで他に明らかな異常を認めなかった。19歳を過ぎた頃より毎月入院するようになったため,精査目的に当院紹介受診となった。西洋医学的には特記すべき異常を認めず,周期性嘔吐症候群と診断した。漢方医学的には,気鬱・気逆と診断した。半夏厚朴湯を処方したところ,自覚症状は著明に改善し,内服開始から半年が経過したが嘔吐発作は出現していない。 気鬱・気逆を伴う強い嘔吐症状を半夏厚朴湯が予防する可能性があり,機能性消化管障害に対する漢方薬の有効性が示唆された。
2 0 0 0 OA 「自己の二重性の意識化」としての自我体験
- 著者
- 清水 亜紀子
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.231-249, 2009-05-01 (Released:2009-07-04)
- 参考文献数
- 20
本研究では,自我体験の「体験内容」・「体験の位置づけ方」の類型化を試みる。そこで,25名の被調査者を対象に,自我体験に関する個別面接調査を実施した。得られた語りを分析した結果,自我体験の体験内容は,時間軸・空間軸への問い,存在への感覚的違和,自・他の実在への懐疑,独一性への気付きの4つに分類された。また現時点での自我体験の位置づけ方は,個人史再編成,体験同化,意味づけ途上,体験疎外の4つに分類された。特に,個人史再編成では,新たな自己が生成される一方で,体験疎外では,旧来の自己のあり方を堅持しようする様子がみて取られた。さらに,事例的検討から,自我体験とは,「第二の私」が「今ここの私」として生きるという新たな自己の成立の契機的体験であり,その体験をいかに受けとめるかによって,「今ここの私」を根底から崩すものにも,支えてくれるものにもなりえるパラドキシカルな体験なのではないかと考えられた。
2 0 0 0 OA 胆汁酸と免疫系
- 著者
- 田中 廣壽 牧野 勲
- 出版者
- 一般財団法人 日本消化器病学会
- 雑誌
- 日本消化器病学会雑誌 (ISSN:04466586)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.10, pp.693-699, 1996-10-05 (Released:2008-02-26)
- 参考文献数
- 49
2 0 0 0 OA 冷凍フグ解凍時における筋肉の毒化
- 著者
- 塩見 一雄 田中 栄治 熊谷 純智 山中 英明 菊池 武昭 河端 俊治
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.2, pp.341-347, 1984-02-25 (Released:2008-02-29)
- 参考文献数
- 1
- 被引用文献数
- 6 7
It is said that, during the thawing of frozen puffer fish, muscle becomes toxic due to the migration of toxin (tetrodotoxin) from toxic viscera and skin. In this study, the extent of toxification of muscle after thawing at 4°C was examined using slowly or quickly frozen puffer fish Fugu niphobles. No significant difference in the extent of toxification of muscle was observed between slowly frozen specimens and quickly frozen ones. The muscle of most specimens was found to be toxic (up to 58 MU/g) even immediately after the first thawing. The migration of toxin into muscle from toxic tissues progressed gradually with the time elapsed after thawing; several specimens showed a strong toxicity of more than 100 MU/g after 24 and 48 h from the end point of thawing. The toxicity of muscle at the second thawing was failry low as compared with that at the first thawing probably because of the difference of muscle parts used for toxicity test. In the case of half-thawed specimens, the toxin did not migrate into muscle from toxic tissues.
2 0 0 0 OA 作業療法におけるピアサポートの内容と 作業療法士の役割に関する文献レビュー
- 著者
- 横山 和樹 小笠原 那奈 小笠原 啓人 矢部 滋也 森元 隆文 池田 望
- 出版者
- 公益社団法人 北海道作業療法士会
- 雑誌
- 作業療法の実践と科学 (ISSN:24345806)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.3, pp.47-55, 2021 (Released:2021-08-31)
- 参考文献数
- 23
本邦の作業療法におけるピアサポートの内容と作業療法士の役割を探索的に明らかにすることを目的に文献レビューを行った.対象文献11編を分析した結果,ピアサポートの内容は,多い順にフォーマルなピアサポート,インフォーマルなピアサポート,仕事としてのピアサポートに分類された.作業療法士の役割は,グループの立ち上げや運営,グループ参加前後の個別支援,当事者の希望や役割等の評価やそれを生かした実践,ピアサポートの活用に向けた治療構造や環境の調整等が報告された.また,ピアサポーターと連携する時の役割として,同等な立場としての関わり,当事者が安心・安全に活動するための体制づくり等が挙げられた.
2 0 0 0 OA 毛髪胃石による小腸閉塞を発症した1女児例
- 著者
- 松寺 翔太郎 渡邊 峻 谷 有希子 山口 岳史 荻野 恵 桑島 成子 土岡 丘
- 出版者
- 日本小児放射線学会
- 雑誌
- 日本小児放射線学会雑誌 (ISSN:09188487)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.116-121, 2019 (Released:2019-11-22)
- 参考文献数
- 18
毛髪胃石は経口摂取された毛髪が胃内で一塊となったもので,稀に腸閉塞を引き起こす.今回我々は毛髪胃石による腸閉塞に対し小開腹により胃石を摘出した一例を経験したので報告する.症例は11歳女児.腹痛・嘔吐を主訴に来院した.腹部造影CTでは非絞扼性の内ヘルニアが疑われた.イレウスチューブを挿入すると大量の血性排液を認めたため緊急手術を施行した.中腹部正中切開にて開腹すると,Treitz靭帯から200 cmの小腸内に長径6 cmの毛髪胃石を認めたため摘出した.術後イレウス管抜去の際に胃内の胃石残存が疑われ,内視鏡的摘出の方針とし術後9日目に一旦退院となった.再入院後,胃石の内視鏡的摘出を試みたが困難で,初回と同じ創で小開腹し長径8 cmの胃石を摘出した.開腹歴のない腸閉塞の鑑別診断として稀ではあるが胃石によるものも考慮する必要がある.また胃石の画像的特徴を認識し重複毛髪胃石の確認を行うことが重要である.
2 0 0 0 OA ニュージーランドの医学教育―医師国家試験のない国の医学教育―
- 著者
- 江原 孝史
- 出版者
- 信州医学会
- 雑誌
- 信州医学雑誌 (ISSN:00373826)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.15-22, 2007-02-10 (Released:2014-05-20)
- 参考文献数
- 6
2 0 0 0 OA 高齢者の主観的幸福感に及ぼす運動習慣の影響
- 著者
- 安永 明智 谷口 幸一 徳永 幹雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.173-183, 2002-03-10 (Released:2017-09-27)
- 被引用文献数
- 9 6
本研究では,地域の高齢者209名を対象に,QOLの重要な構成要素である主観的幸福感に運動習慣が及ぼす影響について,心理社会的変数を加えて,その関係性を明らかにしていくことが目的であった.以下のような結果が得られた.1)運動習慣は,特に後期高齢者において,社会的自立因子,健康度自己評価,家族サポート,主観的幸福感で有意に肯定的な影響を及ぼすこと.2)運動習慣はADLを維持すること,そしてADLを維持していくことは,健康度自己評価やソーシャルサポートを高め,そのことが主観的幸福感に影響すること.3)これらの結果から,運動習慣が主観的幸福感に及ぼす影響は,ADLやソーシャルサポート,健康度自己評価を通した間接的な影響であることが推察された.なお,本研究は,地方小都市である一地域を対象に実施したものである.したがって,地域的なバイアスが諸変数に及ぼす影響も考えられる.今後,都市部などを含んだ様々な地域を対象に同様な調査を繰り返し,共通性を明らかにしていく必要があるであろう.また,横断的な分析であるために,因果関係までは言及することができなかった.今後は,縦断的な調査方法を用いて,因果関係を明らかにしていくことを課題としたい.
2 0 0 0 OA 加熱調理した野菜類・いも類中のアクリルアミド含有量
- 著者
- 石原 克之 奈良 一寛 米澤 弥矢子 星野 文子 有馬 正巳 古賀 秀徳
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.32-37, 2009 (Released:2015-02-27)
- 参考文献数
- 14
炭水化物を多く含む食品を高温で加工された食品中からアクリルアミド(AAm)が検出されたと2002年4月にスウェーデンの研究者により発表された。その後,種々の加熱加工食品中に存在していることが明らかとなった。しかしながら,加工食品同様に食材に加熱加工を施す家庭での調理食品についての検討はあまりなされていない。そこで,家庭での調理食品に着目して調査を行った。種々の加熱調理食材にAAmが認められ,含有量の高かったのは,もやし,次いでにんにくであった。また,食材中のアスパラギン(Asn)含量と加熱後のAAm含量との間に強い相関(R2=0.66)が見られた。しかし,Asn含量が低くても加熱が強いとAAm含量が高くなる可能性があることが分かった。このことから,家庭での調理においても過度な加熱調理を避けることでアクリルアミド生成が抑制されることが示唆された。
2 0 0 0 OA 野草アメリカフウロを利用したジャガイモ青枯病の防除
2 0 0 0 OA 保育者の虫嫌いの状況に関する調査 ― 保育者志望の大学生や一般女性との比較から ―
- 著者
- 山野井 貴浩 伊藤 哲章
- 出版者
- 一般社団法人 日本環境教育学会
- 雑誌
- 環境教育 (ISSN:09172866)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.1_33-39, 2021 (Released:2021-08-24)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1
To understand the level of Entomophobia in nursery teachers, we undertook a questionnaire survey of nursery teachers, students taking a nursery teacher-training course, and ordinary women. Results indicated that nursery teachers tend to like arthropods and can look at photographs and illustrations of them more comfortably when compared to the students and ordinary women. An age-based analysis showed that nursery teachers in their 20s–50s were able to view photographs and illustrations of arthropods with less resistance than students and ordinary women of the same generation. There was no significant difference between participants in the 20–40 age range, but nursery teachers in their 50s showed greater preference to arthropods than university students and ordinary women. As the degree of preference for arthropods had a stronger influence on their confidence in arthropod-related childcare rather than the degree to which they could look at arthropods, it is necessary to develop training to encourage nursery teachers to like arthropods through experiences of seeing, touching, collecting and rearing such creatures.
2 0 0 0 OA ペースメーカのすべて 1
- 著者
- 岩本 眞理
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本小児循環器学会
- 雑誌
- 日本小児循環器学会雑誌 (ISSN:09111794)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.5, pp.534-542, 2014-09-01 (Released:2014-10-15)
- 参考文献数
- 10
ペースメーカは徐脈性不整脈に対する唯一の有効な治療法である.小児の適応例は成人と比べると頻度は少なく,小さい体格・成長・長期管理という小児特有の問題から植え込み法や合併症も成人とは異なる点がある.植え込みの適応は2011年日本循環器学会を中心とした研究班によりガイドラインが改訂された.ペースメーカの構成は電池とリードからなり,方法は一時的と永久的ペーシング,電極は心内膜電極と心筋電極がある.機能は3〜4文字コード表示で示される.心房心室興奮の順次性が維持されたペーシング様式を生理的ペーシングと呼び,循環動態の観点から有利である.植え込みは各症例に適した方法を選びパラメータを設定する.ペースメーカ外来では12誘導心電図・胸(腹)部X線写真・プログラマーによるパラメータ測定を行う.これによりパラメータ設定の適正化・電池交換時期の予測・トラブル回避を行ってペースメーカの適切な管理を維持する.