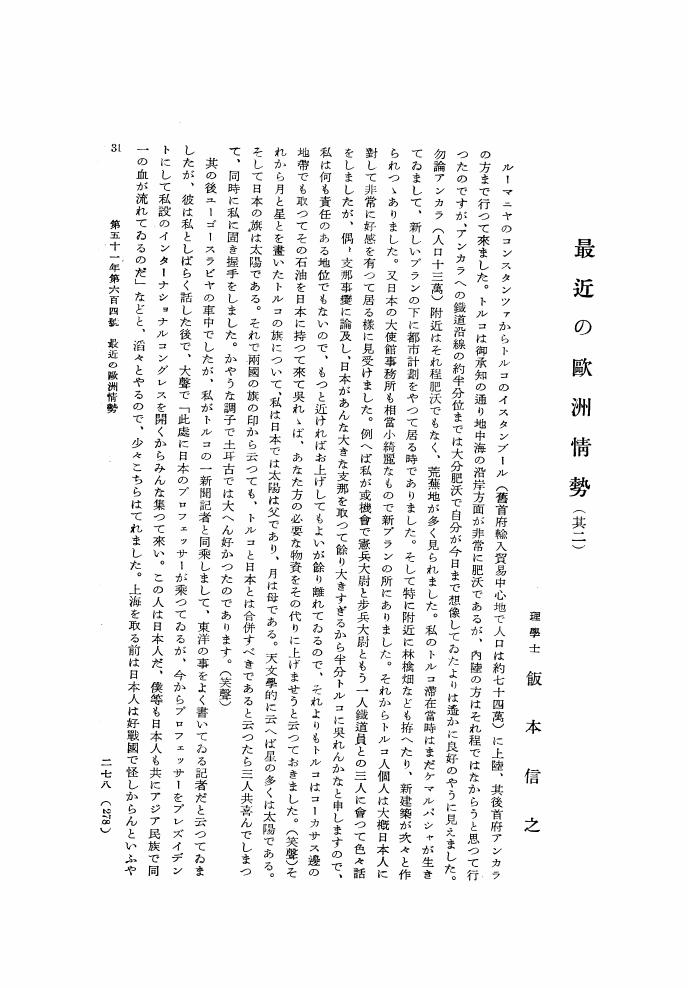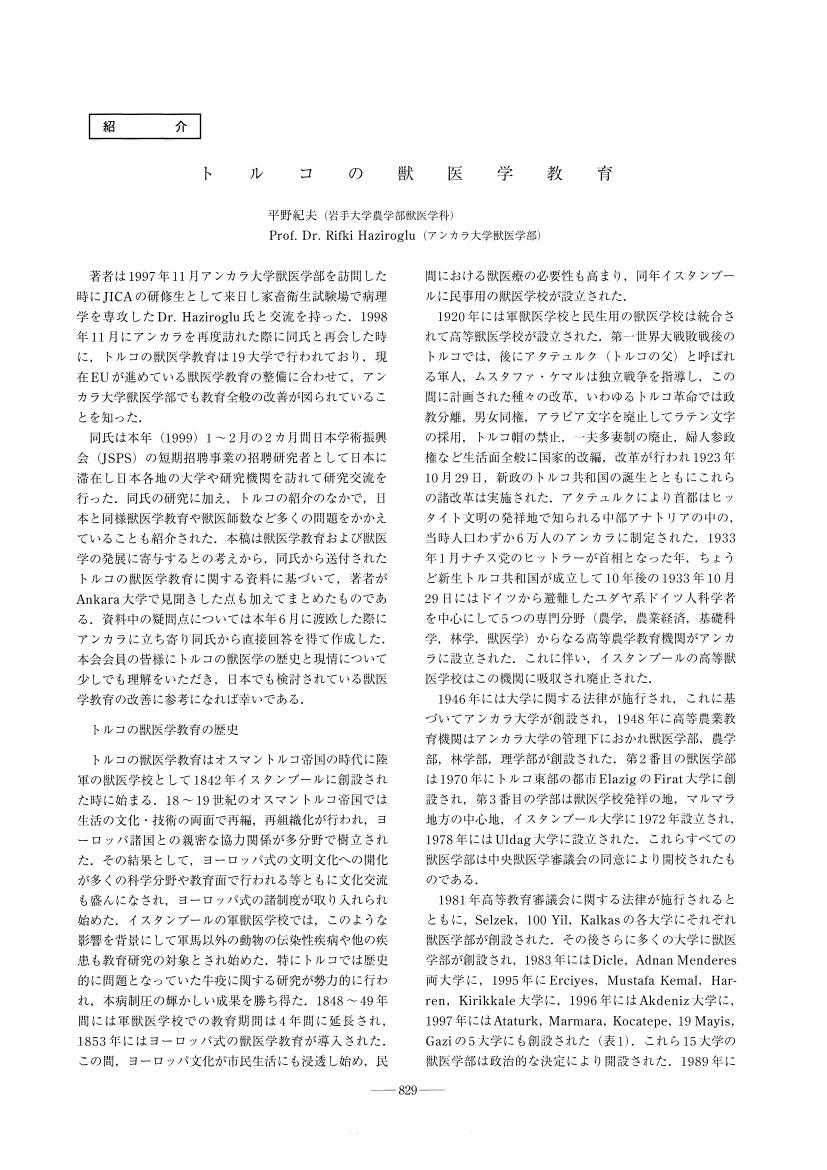1 0 0 0 OA 接続助詞の文末用法をもたらす要因--相互行為における参与者の認知の観点から
- 著者
- 横森 大輔
- 出版者
- 京都大学大学院人間・環境学研究科言語科学講座
- 雑誌
- 言語科学論集 = Papers in linguistic science
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.57-76, 2006-12
- 著者
- 小野 将之 西村 邦裕 谷川 智洋 廣瀬 通孝
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会技術報告 (ISSN:13426893)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.79-84, 2009
- 参考文献数
- 5
科学技術の高度な発達があり,様々なセンサ有したデバイスを用いて日常生活での体験をデジタル化して記録に残すことが手軽になってきており,体験を記録する分野は「ライフログ」とよばれる.ライフログの研究はこれまで様々なされてきたものの,その活用においてはまだ発展途上である.本研究では,ライフログを記憶想起支援などの実用用途への活用するための構造化を目指し,実際に多様なセンサを用いてライフログ取得を行い,ニューラルネットワークを用いてデータ取得者がどのような行動をとっていたかの推定を行った.さらに効率的な閲覧を可能とするビューアを提案・実装し,評価実験を通じてそれらの効果を検証・実証した.
1 0 0 0 速報 2005年夏モデルパソコン
- 著者
- 倉田 雅弘 中村 稔
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経パソコン (ISSN:02879506)
- 巻号頁・発行日
- no.480, pp.30-39, 2005-04-25
各社が重点を置いているのがテレビ関連機能の強化。特にテレビ映像の高画質化が一段と進んだ。色のにじみを抑える3次元Y/C分離や画像の2重映りを低減するゴーストリデューサーといった従来の機能は、大半のテレビ録画機能付きパソコンが採用している。さらに独自の映像処理ソフトや映像回路で高画質化を図る製品も多い。
1 0 0 0 OA 多形態媒体による分散図書館情報へのアクセス支援システム
- 著者
- 阪口哲男 [著]
- 巻号頁・発行日
- 1997
1 0 0 0 OA 地域に対する図書館網計画に関する研究
- 著者
- 中村恭三 [著]
- 巻号頁・発行日
- 1998
1 0 0 0 OA 利用圏域の二重構造に基づく疎住地の図書館計画に関する研究
本研究の目的は、多様化した日本語学習者の対応した読解教材を作成を支援するシステムを開発することにある。具体的には、WWW情報のキーワード検索において、各学習者に相応しい漢字難易度、語彙難易度、ジャンルに絞り込むシステムをWWW上に作成した。漢字の難易度は日本語能力試験級別漢字表を参照し、学習者が指定する級よりも上級の漢字含有率が20%未満の文章に絞り込むシステムを作った。同様に、語彙の難易度も日本語能力試験級別語彙表と照合し、任意の級よりも上級の語彙が20%未満しか含まれない文章に絞り込むようにした。ジャンルは、歴史、地名、生物、美術、文学、人物、政治、用語の中から学習者がいずれかを選択すると、さらにジャンル毎に設定してあるカテゴリ別に絞り込みを表示した。今後の課題としては、ジャンルの妥当性を検討する必要がある。また、技術面では、システムをWWWサーバから各学習者のコンピュータにダウンロードして使用する方式に改善したい。そうることにより、WWWサーバのセキュリティの強化、また各学習者によるカスタマイズが可能となり、より使いやすいシステムとなることが期待できる。
1 0 0 0 IR 大学生における「ひとりの時間」と孤独感・対人恐怖心性との関連
- 著者
- 海野 裕子 三浦 香苗 Yuko UMINO Kanae MIURA
- 出版者
- 昭和女子大学生活心理研究所
- 雑誌
- 昭和女子大学生活心理研究所紀要 (ISSN:18800548)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.51-61, 2010
- 被引用文献数
- 2
Relationship between emotions about spending time alone, how they spend their time to be alone,and the degree of loneliness and anthrophobic tendencies in university students were investigated. We administered a multiple-scale questionnaire to 347 university student participants. The main results were as follows:(1) A positive correlation was found between emotions about independence/ideals, and "awareness of individuality," an aspect of loneliness; and a weak negative correlation was found between emotions about loneliness/anxiety and "understanding and sympathy between people," also an aspect of loneliness. However, there was no relationship between emotions about fulfillment/satisfaction,and loneliness.(2) A positive correlation was observed between awareness of individuality and how participants spent their time during rest/liberation, and introspection.(3) Anthrophobic tendencies showed a significant positive correlation with loneliness/anxiety,and a significant negative correlation with fulfillment/satisfaction.(4)Anthrophobic tendencies showed a significant positive correlation with rest/liberation. These results suggest that awareness of individuality in loneliness was related to time to be alone, and that anthrophobic tendencies, a personality characteristic, were also related to time to be alone.
1 0 0 0 OA 幼児の社会的問題解決能力と「心の理論」の発達
- 著者
- 子安 増生 鈴木 亜由美
- 出版者
- 京都大学大学院教育学研究科
- 雑誌
- 京都大学大学院教育学研究科紀要 (ISSN:13452142)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, pp.63-83, 2002-03-31
1 0 0 0 OA 幼児の自己制御機能尺度の検討 : 社会的スキル・問題行動との関係を中心に
- 著者
- 大内 晶子 長尾 仁美 櫻井 櫻井
- 出版者
- 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.414-425, 2008-09
本研究の目的は,幼児の自己制御機能を,自己主張,自己抑制,注意の移行,注意の焦点化という4側面から捉え直し,新たにその尺度を作成すること,また,4つの側面のバランスと社会的スキル,問題行動との関係を検討することであった。保育園と幼稚園に通う幼児452名の保護者に対し,子どもの自己制御機能に関する項目に回答を求めた。そのうち保育園の幼児262 名の社会的スキル,問題行動について,担任保育者から回答を得た。因子分析(主因子法・プロマックス回転)の結果,4下位尺度23項目からなる自己制御機能尺度が作成され,その信頼性と妥当性が確認された。次に,4下位尺度の標準化得点を用いてクラスター分析を行った結果,6つのクラスターが見出された。各クラスターの社会的スキル,問題行動得点を比較した結果,望ましい社会的スキルの獲得には自己制御機能の4つの側面が全て高い必要があること,内在化した問題行動の出現には4つの側面が全て低いことが関係していること,外在化した問題行動の出現には自己主張の高さと自己抑制および注意の制御の低さが関係していることが明らかになった。One of the purposes of the present study was to develop a scale of young children's self-regulation that measured 4 aspects of self-regulation: self-assertiveness, self-inhibition, attention shifting, and attention focusing. A second purpose was to examine the balance of those 4 aspects in relation to social skills and problem behavior. The parents of 452 preschool and kindergarten children rated their children on the self-regulation scale; in addition, the teachers of 262 preschool children rated those children's social skills and problem behavior. Factor analysis (using the principal factor method, Promax rotation) identified 4 factors or subscales, and 23 items. The reliability and validity of the overall scale were confirmed. Cluster analysis of standardized scores on the 4 subscales identified 6 clusters. A comparison of the scores on social skills and problem behavior in each cluster indicated the following: It is necessary for the acquisition of desired social skills that all 4 aspects of self-regulation have high scores. Low scores on all 4 aspects were related to internalizing problems; high self-assertiveness scores combined with low self-inhibition and attentional control scores were related to externalizing problems.
- 著者
- 広瀬 洋子
- 出版者
- 放送大学
- 雑誌
- 放送大学研究年報 (ISSN:09114505)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.89-102, 2011
ICT活用は世界の大学のあり方を大きく変えようとしている。放送大学においても、従来の放送授業から、インターネットによるオンデマンド型配信授業で学習する学生が増加しており、印刷教材のデジタル化も検討課題になりつつある。 日本でこうしたICTによる学習の変革を一番切実に必要とし、ここ20年、パソコンを最も先鋭的に活用し学習に役立ててきたのは視覚障がい学生である。2011年現在、放送大学に学ぶ視覚障がい者は142名。全国の高等教育機関に学ぶ視覚障がい者の20%を占めている。 放送大学では第一期卒業生の杉山和子氏がボランティア組織「菜の花の会」を立ち上げ、視覚障がい者が抱えていた印刷教材を読むことの困難さに支援がなされた。放送大学がこの地道な活動を継承し、ICTを活用した活動として発展させるために、「菜の花の会」のこれまでの活動を振り返り、記録しておきたい。
1 0 0 0 OA オフィスの節電照明の変化実態把握と新しい省エネルギー光環境への展開
本研究では東日本大震災後の首都圏節電下のオフィスの光環境の実態の記録を残すとともに、そこからオフィス照明の基本要件を抽出し、省エネルギー照明手法の開発を行った。節電によって、照明のエネルギー削減はランプや器具の効率の向上の他に、必要照度を下げる、照射面積を小さくする、照射時間を短くすることによる効果が大きいことが示された。これらは「光環境の質を落とす」と考えられ触れられてこなかった方法である。照明の基本的要件の見直しから着手し、照射面積・時間、昼光利用を考え、人の視覚特性を利用した「不均一・変動照明」による照明手法の提案を行い、これらに基づいた新しい照明基準作成の準備を行った。
1 0 0 0 OA 最近の欧洲情勢
- 著者
- 飯本 信之
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.6, pp.278-286, 1939-06-15 (Released:2010-10-13)
1 0 0 0 OA ヌーリー・シャアラーンと佐原大佐
- 著者
- 前嶋 信次
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- オリエント (ISSN:00305219)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.4, pp.1-14,140, 1966 (Released:2010-03-12)
The activities of Nuri ash-Shaalaan, the grand chief of Ruala Bedouin tribe in Syrian Desert, during the 1st world war was vividly described by T. E. Lawrence in his Seven Pillars of Wisdom. Therefore the life of this old warrior became very popular among the people who are interested in the modern history of the Arab countries. However, the account of the same hero by the late Colonel Keiji Sahara, who explored the Arab lands twice during the time between the 1st and 2nd world wars, has been hitherto quite neglected, or rather forgotten even by his compatriots. I have already made public an article “Arabia and Nejd horses” in the “Saudi Arabia”, the magazine of the Saudi Arabian Society in Japan, No. 21, April 1967, and through it I tried to introduce Mr. Sahara's reports about the thoroughbred horses of Arabia.This time, I intend to introduce from the standpoint of historical evaluation the idformation of his interview with ash-Shaalaan and his eldest son. I think that, though it is not so colorful as that of T. E. Lawrence, it is still worthy of note because it is probably one of very few pictures in his later days of this friend of Lawrence of Arabia.
1 0 0 0 OA 統一と進歩委員会の系譜
- 著者
- 設楽 國廣
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- オリエント (ISSN:00305219)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.1-15, 1992-09-30 (Released:2010-03-12)
The Committee of Union and Progress (CUP) was established in 1889 by Ibrahim Temo and his classmates at the Army Medical School in Istanbul to restore the 1876 Constitution, which had been suspended by Sultan Abdul Hamid II since 1878. However, under the suppression of the Sultan, CUP leaders took exile to Europe. The founder, Ibrahim Temo, moved to Constanza, Rumania.The Osmanli Committee of Liberty, another Constitution-supporting organization established in Selanik in 1906, accepted a mission of the CUP in Paris, which was then under the leadership of Ahmet Riza, and changed its own name to CUP Selanik in the same year.In 1908 Niyazi, a member of CUP Manastir, another CUP local, which had separated from CUP Selanik, started the rising for the revival of the Constitution that marked the beginning of the Young Turks Revolution.After the 1908 uprising, the CUP Selanik leaders—Talat, Cemal, and Enver—in their attempt to gain recognized positions in the traditional regime, approached older statesmen in the Osmanli government. It was in accordance with this strategy that they decided to eliminate other CUP members, even its founder Ibrahim Temo, so to make CUP Selanik the only authoritative center of the CUP. As a result, Ibrahim Temo, who played a crucial role at the initial stage of the Young Turks Revolution, lost his power base in Ottoman Empire politics and later became a Senator in Rumania.
1 0 0 0 OA トルコの獣医学教育
- 著者
- 平野 紀夫 Rifki Haziroglu
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医師会
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.12, pp.829-832, 1999-12-20 (Released:2011-06-17)
1 0 0 0 カメラマンから見た映画技術史
- 著者
- 廣澤 文則
- 出版者
- 日本大学
- 雑誌
- 日本大学芸術学部紀要 (ISSN:03855910)
- 巻号頁・発行日
- no.47, pp.5-20, 2008
映画が発明されて約百二十年経った。映画の発明には多くの科学者や技術者達の技術開発や努力のおかげであり、一朝一夕に出来上がったものではない。映画技術史を授業で教えるためには、映画技術に関する科学史・写真史等は必要不可欠であり、時には化学史や機械開発史まで必要となってくる。しかし、それぞれの名専門分野での詳しい開発史はあるが、映画技術史に関すると思われるものを専門家ではないが、広く浅く年表にまとめ資料化を計った。
1 0 0 0 OA スギ人工林の今後の取り扱いについて : 花粉症に関するアンケート調査をもとに
- 著者
- 安村 直樹 山本 博一
- 出版者
- 林業経済学会
- 雑誌
- 林業経済研究 (ISSN:02851598)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.47-52, 2001-03-15
近年社会問題となっているスギ花粉症(以下花粉症)に関わって,市民の森林・林業に対する認識,特に人工林に対する認識を把握するためにアンケート調査を行った。アンケート調査からは,花粉症有病者を中心として,人工林を花粉少品種,特に他の樹種へ転換することを強く望んでいることがわかった。今後花粉症有病率の増加傾向が変わらないとすれば,人工林に対する花粉症由来の意見や認識はますます強くなっていくものと思われる。育成に長期を要する森林は長期的な視点からその取り扱い方を決定しなければならないが森林における花粉症対策もその例外ではない。まず早急な転換によって生じる問題点についての情報を提示し市民の理解を得ることが必要である。そして森林の取り扱いについて市民の理解を確実にするためには針葉樹人工林の効率性を市民に十分に認識してもらった上で,長期的な視点から人工林の持つ効率性と広葉樹天然林の持つ多様性との調和について改めて社会的な議論を巻き起こしていくことが必要である。
1 0 0 0 OA 虚構の現実、リアルなフィクション:英米文学と「親密さ」という現象に関する一考察
日常は「表現された秩序」だと唱えたミクロ社会学者、E. ゴッフマンの理論をH.ジェイムズの文学作品に重ね、ジェイムズ文学は現実の虚構性をリアルに描いたものだと*Performing the Everyday in Henry James’s Late Novels*(Ashgate, 2009)で主張。今度はジェイムズが高く評価したAusten、Wharton、G. Eliotの作品に同様の分析を行い、インティマシー(「親近感、近しさ」)をテーマに単著*Performing Intimacies of the Everyday*(仮) を書き上げ、英米の某学術出版社の外部審査用に準備中。