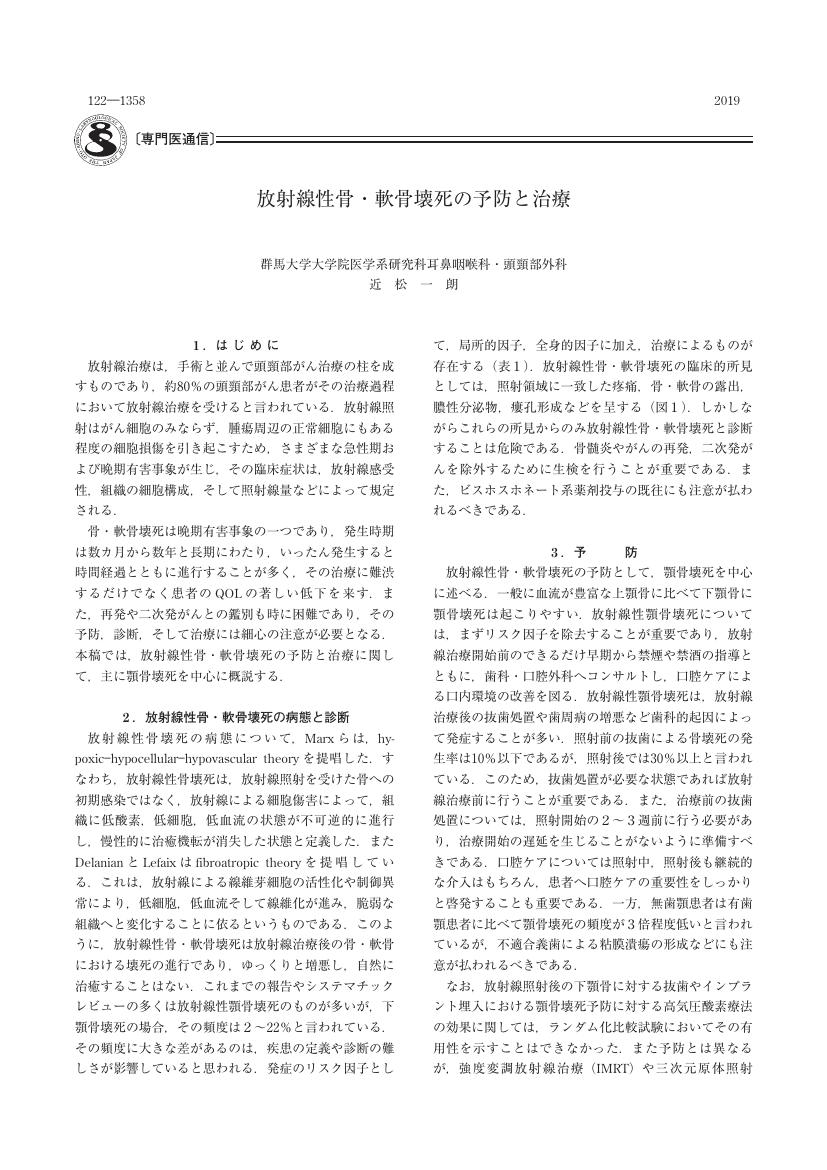2 0 0 0 OA 国立銀行設立にみるリレーションシップバンキングの原型 : 地域金融の円滑化と殖産興業
- 著者
- 南地 伸昭
- 出版者
- 生活経済学会
- 雑誌
- 生活経済学研究 (ISSN:13417347)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.43-57, 2005-03-30 (Released:2016-11-30)
In the Meiji era, the new government established small-scale banks nationwide, aiming to encourage community industries through making regional finance smooth, having adopted the small banking principle of the United States National Banks. These small-scale banks had a common feature that the local potentate, a "shizoku", a merchant, a landowner, an industrial person, and municipalities positively participated in establishing banks. Moreover, they have coexisted with community by supporting the creation and the development of regional commerce and industry through making regional finance smooth. Such historical details agree with today's situation in which regional financial institutions nationwide grapple with a variety of management problems along "Action Program concerning enhancement of Relationship Banking Functions" aiming to rebuild regional businesses and to activate communities. Because regional financial institutions share the fate with the community, their most important mission, according to the various characteristics of each regional economy, is to attempt the activation of the regional economy by the establishment and the development of the local industry.
2 0 0 0 OA 数理最適化を用いた必要最低限の食費の算出
- 著者
- 髙橋 正弥 上野 瞳 佐藤 直人 鈴木 香澄 稲葉 洋美 澁谷 顕一
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.136-141, 2018 (Released:2018-03-09)
- 参考文献数
- 16
The purpose of the present study was to estimate the minimal food cost based on the dietary reference intake for Japanese people. For this purpose, we calculated the minimal food cost using mathematical optimization. To calculate a food plan for each age-gender group, 68 mathematical optimization models for each of the food plan groups were employed. For the calculation of mathematical optimization models, we used data based on the dietary reference intake for Japanese people and a retail price survey by the Statistics Bureau of the Japanese Government. We established four categories (25%, 50%, 75% and 85% for standard food intake). From these restrictions, we calculated the minimal food cost using mathematical optimization. The normal food cost per month for adult males (18-29 years) was 41,865 Yen, and for adult females (18-29 years) was 26,037 Yen. Based on these results, we were able to estimate the minimal food cost for families in order to prevent lifestyle related diseases. In this study we used computed ingredients instead of food to calculate optimal combinations, so it has not been verified whether these combinations can be realized in practice. In order to put the results of this study into practice, it is necessary to verify the results of the calculation and the connection between cooking and menu planning.
2 0 0 0 OA 2)感染症への対応と感染対策
- 著者
- 高橋 孝
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.5, pp.498-501, 2011 (Released:2012-02-09)
- 参考文献数
- 11
災害後の経過と発生頻度の多い感染症を考慮する場合,発生直後~3日以内(急性期)においては外傷・熱傷・骨折に伴う創部感染症(特に破傷風に注意)が多く,4日目以降~復旧(亜急性期~慢性期)までの段階ではかぜ・インフルエンザ・感染性胃腸炎・結核・麻疹が多数発生する.被災高齢者がこれらの感染症に罹患しやすい環境(避難所)に置かれている点を忘れてはならず,疾患の早期発見・早期対応および感染予防の対策が医療従事者に求められている.本稿では,東日本大震災における感染症や感染対策に関する各種報告を踏まえて概説する.
2 0 0 0 OA 人間らしさを感じさせる将棋におけるミスの認知モデル
- 著者
- 杵渕 哲彦 伊藤 毅志
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第28回全国大会(2014)
- 巻号頁・発行日
- pp.1E35, 2014 (Released:2018-07-30)
コンピュータ将棋はプロ棋士に迫るレベルになっているが,アマチュアにとっては将棋を楽しむ為の対局相手でもある.既存の棋力調整方法では,人間が手に不自然さを感じるという問題点が指摘されている.この問題に対し,コンピュータに人間らしいミスを犯させるという手法が考えられる.本研究ではこれを実現する為の基礎研究として,ミスを犯した際の思考についてインタビューを行い,人間がミスを犯す際の認知モデルを提案した.
2 0 0 0 OA ヘリウム同位体比からみた2008年岩手・宮城内陸地震前後の深部流体挙動
- 著者
- 堀口 桂香 中山 貴史 松田 准一
- 出版者
- 一般社団法人日本地球化学会
- 雑誌
- 日本地球化学会年会要旨集 2010年度日本地球化学会第57回年会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- pp.10, 2010 (Released:2010-08-30)
本研究は,2008年岩手・宮城内陸地震震源域周辺にて,地震の前後におけるヘリウム同位体比の時空間変化を追跡したものである.地震発生1週間後から半年毎に計4回,温泉水と温泉ガスを採集し,溶存ガス中のヘリウム同位体比を測定した.その結果と2006年7月に同じ地点でサンプルを採集・測定した結果とを比較すると,地震直後には5カ所の温泉において10-85%の増加,2カ所において11-35%の減少が観測され,1年後には地震発生前の値に戻っていく傾向がみられた.これらの結果は,同地域の震源域の地下に地震波の低速度域が認められるという地球物理学研究と一致しており,地球化学・地球物理学双方の研究結果は整合的であり,深部から上昇してきたマントル起源の流体が地震発生に関与した可能性を示唆している.
2 0 0 0 OA 16 裁判化学
- 著者
- 星野 乙松 石倉 俊治
- 出版者
- 公益社団法人 日本分析化学会
- 雑誌
- 分析化学 (ISSN:05251931)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.13, pp.136R-142R, 1962-12-05 (Released:2010-05-25)
- 参考文献数
- 263
裁判化学は司法裁判に関係ある事件の解決に応用される分析化学の一分野であって,鑑識化学ともいわれ,分析の対象,目的はきわめて多岐にわたっているが,その中で最も重要でしばしば扱うのは,生体試料中の薬毒物の分析である.今回は1957年までを記載した前回の総説に引き続き,1958~61年の間に発表された裁判化学関係の文献のうちから薬毒物の分析法に重点をおいて最近の進歩をふりかえってみることにする.なお,薬品分析,農薬分析,機器分析などの関連項目と重複する報告は特に重要と思われるもの以外は集録しなかったので,それらの項目も参照されたい.
2 0 0 0 OA ウイルスによる胎盤の獲得と発達
- 著者
- 葉梨 輝 金野 俊洋 櫻井 敏博 今川 和彦
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF OVA RESEARCH
- 雑誌
- Journal of Mammalian Ova Research (ISSN:13417738)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.4, pp.214-220, 2009 (Released:2009-12-08)
- 参考文献数
- 28
レトロウイルスは新しい遺伝子を取り込み,その機能を獲得,発揮することが出来る.実際,レトロウイルスの一種であるラウス肉腫ウイルスは宿主に感染することによって,宿主の持つがん遺伝子srcを取り込み,それを自らのゲノムの一部にしたことは良く知られている.このようにレトロウイルス側が宿主細胞側の遺伝子を取り込み利用することが可能であれば,それとは逆に,細胞生物側がレトロウイルス由来の遺伝子を取り込んで利用することがあっても不思議ではない.脊椎動物のゲノム上にはレトロウイルス由来と思われる配列が数多く存在しており,内在性レトロウイルス(Endogenous Retrovirus, ERV)と呼ばれている.そして,それら遺伝子の発現は,哺乳類において特徴ともいえる“胎盤”で高いことが知られている.このようなレトロウイルス由来タンパクの組織特異的な発現とその機能を考えれば,レトロウイルス由来の遺伝子が胎盤の形成機構に関与している可能性は高い.本論文では,哺乳類,特にヒトにおける胎盤形成のメカニズムと内在性レトロウイルスの関係について,胎盤に発現するERV由来タンパクsyncytinを中心に,今後の展望を交え述べていく.
2 0 0 0 OA 女子の第二次性徴に関わる下着教育に関する研究
- 著者
- 庄 莉莉 村上 かおり 鈴木 明子
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集 69回大会(2017)
- 巻号頁・発行日
- pp.42, 2017 (Released:2017-07-08)
【目的】現在,ブラジャーは女性の生活必需品となっており,その装着が適切であるかどうかは女性の心身に大きな影響を与えているため,ブラジャーを着け始める思春期から,正しい知識をもってブラジャーを装着することが求められる。本研究では思春期の女子のブラジャー装着の現状や課題,またその第二次性徴に関わる下着教育の必要性や課題を明らかにすることを目的とした。 【方法】ワコール及びグンゼなどの調査資料に基づき,思春期の女子のブラジャー装着の現状や課題を追究した。また,歴史,教育,被服衛生などに関する先行研究を整理し,日本におけるブラジャーの普及や変遷の歴史的背景を踏まえ,家庭,学校や下着メーカーでの下着教育の現状や課題を分析した。 【結果】バストの発達やブラジャーの装着に悩みを抱え,その正しい知識を持たないままブラジャーを着け始める思春期の女子が多いため,早い時期にバスト発達に関する知識とブラジャー装着の指導が求められることが明らかになった。一方,下着教育の重要な場である家庭では,その教育が機能せず,学校教育でもほとんど行われていない。下着メーカーは思春期向けのブラジャーの開発や下着教育を積極的に行っているが,いずれも大都市圏だけに限定されている。また,学校での下着教育については約20年前のデーターしか見られない。以上から,思春期の女子及びその親の下着教育に関する認識の実態を明らかにする必要性が認められた。
2 0 0 0 OA 下着類・寝衣類のサイズ
- 著者
- 嶋津 亨
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会
- 雑誌
- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.11, pp.462-466, 1981-11-25 (Released:2010-09-30)
2 0 0 0 OA 「舞踊」という用語の初出と初期の使用法に関する研究
- 著者
- 窪田 奈希左
- 出版者
- Japan Society for the Philosophy of Sport and Physical Education
- 雑誌
- 体育・スポーツ哲学研究 (ISSN:09155104)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.57-66, 1995 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 48
It's been generally considered that the term “Buyo” was made by Shoyo Tsubouchi. But the term was used by Ochi Fukuchi before him. The purpose of this study is to clarify that the term used by Ochi Fukuchi is the origin of “Buyo” being used today. The method of study is as foll ows:1. To clarify where and now the term was used.2. To examine the background datum.The results out of the procedures written above are summerized as follows:1. There is a use of the term in the “Kaiojidan” and there are seven uses in the “Engekihimitsudan”2. He called the “Ejanaika-Odori” by people “Buyo” in the “Kaiojidan”.3. In the “Engekihimitsudan” he used the term to grasp and improve conditions of Japanese-Opera. He called the movement with Kyokufushi (music) “Buyo”. And emphasized that it was important to the opera. His ideal was Western-Opera but he thought the tradition of Japanese-Opera was also precious.On there grounds I have come to the conclusion we may say that the term “Buyo” used by Ochi Fukuchi is the origin of “Buyo” being used today.
2 0 0 0 OA 19 世紀末イギリスの日本趣味
- 著者
- 佐々井 啓
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.221-230, 2010-04-15 (Released:2012-12-13)
- 参考文献数
- 42
The aim of this article is to consider Japonism in Britain at the end of the 19th century through two types of dresses; tea gowns worn by women for five o'clock tea at home, and fancy dresses for boys and girls at fancy dress balls. In this period , in formation on Japan and the Japanese spread through the in troduction of Japanese customs, arts, and skills in the Japanese village in London, and through plays on Japan like ‘The Mikado' and ‘The Geisha'.At the same time, tea gowns were also popular, so Japanese styles such as the kimono, obi, Japanese-style sleeves, and Japanese patterns were adopted as a part of their design. Fancy dresses for children also had a Japanese flavour. For example, dresses imitating ‘three little maids' in ‘The Mikado' and ‘a geisha', were seen at fancy dress balls every year after 1892. A linear kimono design provided a new view of the body, and it can be suggested that these dresses had an influence on the later fashion trends.
2 0 0 0 OA ステファン問題とその解法
- 著者
- 徳田 尚之
- 出版者
- 社団法人 日本流体力学会
- 雑誌
- 日本流体力学会誌「ながれ」 (ISSN:02863154)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.4, pp.299-310, 1988-12-30 (Released:2011-03-07)
- 参考文献数
- 26
相変化を伴ういわゆるステファン問題は実に多くの重要な物理現象に現れる.この展望記事では, まずそれらの中でも特に最近注目を集めている地球科学での応用例の一, 二を紹介し, 続いて動く境界を持つステファン問題に対処するため開発されている代表的な解析法を説明する。最後に, 著者が最近開発したLagrange-Burmann展開に基づく新しい級数解を紹介し, その利点を詳述する.
2 0 0 0 OA 高齢者の聴力低下と左右差が精神活動と社会的交流に及ぼす影響
- 著者
- 田所 夕子 松田 ひとみ
- 出版者
- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会
- 雑誌
- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.175-185, 2013 (Released:2013-10-04)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 3
目的 : 本研究は, 地域在住の高齢者において聴力低下および聴力の左右差が精神活動と社会的交流に及ぼす影響を明らかにすることを目的とする. 方法 : 日常生活が自立している高齢者56人を対象に聴力測定と質問紙調査を実施し, (1) 聴力低下レベルで3群に分類, (2) 聴力の左右差の有無で2群に分類した. 各群に対し, 精神活動と社会的交流に関する項目について群間比較を行った. 結果 : (1) 聴力と精神活動との間に直接的関連は見出せなかったが, 聴力低下が中等度以上の群は他者との交流を避ける傾向があり, 閉じこもりの危険要因となる可能性が示された. (2) 聴力の左右差がある者は孤独感が強まり, うつ傾向となる危険性が見出された. 考察 : 聴力低下や聴力の左右差は, 高齢者の精神活動や社会的交流に影響を及ぼすことが明らかにされた. うつ, 閉じこもりはいずれも介護予防事業施策の対象であり, 聴力低下の実態を主観的および客観的評価の両面から把握する必要がある.
2 0 0 0 OA 放射線性骨・軟骨壊死の予防と治療
- 著者
- 近松 一朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.10, pp.1358-1359, 2019-10-20 (Released:2019-11-06)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 3
2 0 0 0 OA 薄肉彎曲管の応力と変形について
- 著者
- 鵜戸口 英善 中桐 滋 加納 巖
- 出版者
- 一般社団法人 日本高圧力技術協会
- 雑誌
- 高圧力 (ISSN:21851662)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.1328-1336, 1968-05-25 (Released:2010-08-05)
- 参考文献数
- 14
2 0 0 0 OA 机上でできるテルミット反応(実験の広場:5分間デモ実験)
- 著者
- 小松 寛
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.5, pp.242-243, 2009-05-20 (Released:2017-06-30)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 2
2 0 0 0 OA 赤面する青年
- 著者
- 小倉 敏彦
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.346-361, 1999-12-30 (Released:2010-04-23)
- 参考文献数
- 28
本稿は, 明治・大正期の小説文学に頻出する「赤面する青年」という形象を焦点に, 明治中期における「恋愛」の受容と青年意識の変容について考察する試みである。文学作品の中に描写された, 女性を前にして赤面・狼狽する男たちの姿を, ここでは, 男女間の関係性および (恋愛対象としての) 女性像の変容に対応した, 変調の表象として読解していく。従来, 近代的恋愛の成立は, 近代的個人あるいは主観性の成立と相即的に論じられてきた。しかしながら, ここで読みとられた青年たちの逸脱的な様態は, 明治期における恋愛の発見と受容が, 主観性=主体性の成立の帰結というよりは, 一次的には, 新しい生活慣習と教養を身につけた女性たちとの対峙によって解発された, コミュニケーションと自己同一性の危機であったことを物語っているのである。
2 0 0 0 OA 8個のPTP誤飲を内視鏡的に摘出した1例
- 著者
- 加納 由貴 淺井 哲 松尾 健司 竹下 宏太郎 一ノ名 巧 赤峰 瑛介 藤本 直己 山口 拓也 城田 哲哉
- 出版者
- 日本腹部救急医学会
- 雑誌
- 日本腹部救急医学会雑誌 (ISSN:13402242)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.727-731, 2018-05-31 (Released:2019-12-07)
- 参考文献数
- 18
症例は92歳の女性。Press through package(以下,PTP)を誤飲しその後呼吸苦・胸痛が出現し当院へ救急搬送された。胸腹部CTで食道・胃内に7個のPTPを認め緊急内視鏡的異物摘出術を施行した。内視鏡を挿入すると実際には食道・胃内にそれぞれ4つ合計8つPTP異物を確認し,摘出した。翌日胸腹部CT・上部消化管内視鏡検査でPTPが小腸・大腸含め消化管内に残存していないことを確認した。PTP誤飲は消化管穿孔を起こす危険があり緊急内視鏡的異物摘出術の適応となる救急疾患である。今回われわれは1つの症例で8個のPTPを誤飲した希少な症例を経験した。実際には胸腹部CTで想定された数よりも多くのPTPが摘出されており,PTP誤飲ではCTでは検出されないPTPの存在を念頭に置いて処置および経過観察をする必要があると考えられた。
2 0 0 0 OA 人物の属性表現にみられる社会的ステレオタイプの影響
- 著者
- 菅 さやか 唐沢 穣
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.180-188, 2006-11-30 (Released:2017-02-08)
Recent studies have demonstrated that stereotypical expectations result in biases not only in memories and judgments, but in language use as well. The present study examined the effects of communicative contexts on verbal expressions of stereotype-relevant information. In order to do this, we developed a new linguistic index for content analyses, involving stereotypic representations. In our experiment undergraduate students were presented with behavioral descriptions of either an ingroup, or an out-group member, and were asked to describe their impressions. The stimulus information given to the students included both stereotype-consistent, and inconsistent cases. Results showed that the out-group member was described in more stereotype-consistent, abstract terms, than the in-group member. This was interpreted as higher tendency of bias against the out-group. Ultimately, the newly developed index was found to be useful in identifying dispositional expressions that are peculiar to the Japanese language. Finally, implications for the study of stereotypes as collectively shared representations are discussed.
2 0 0 0 OA 5)腸内細菌と多発性硬化症
- 著者
- 山村 隆
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.9, pp.1717-1721, 2016-09-10 (Released:2017-09-10)
- 参考文献数
- 10