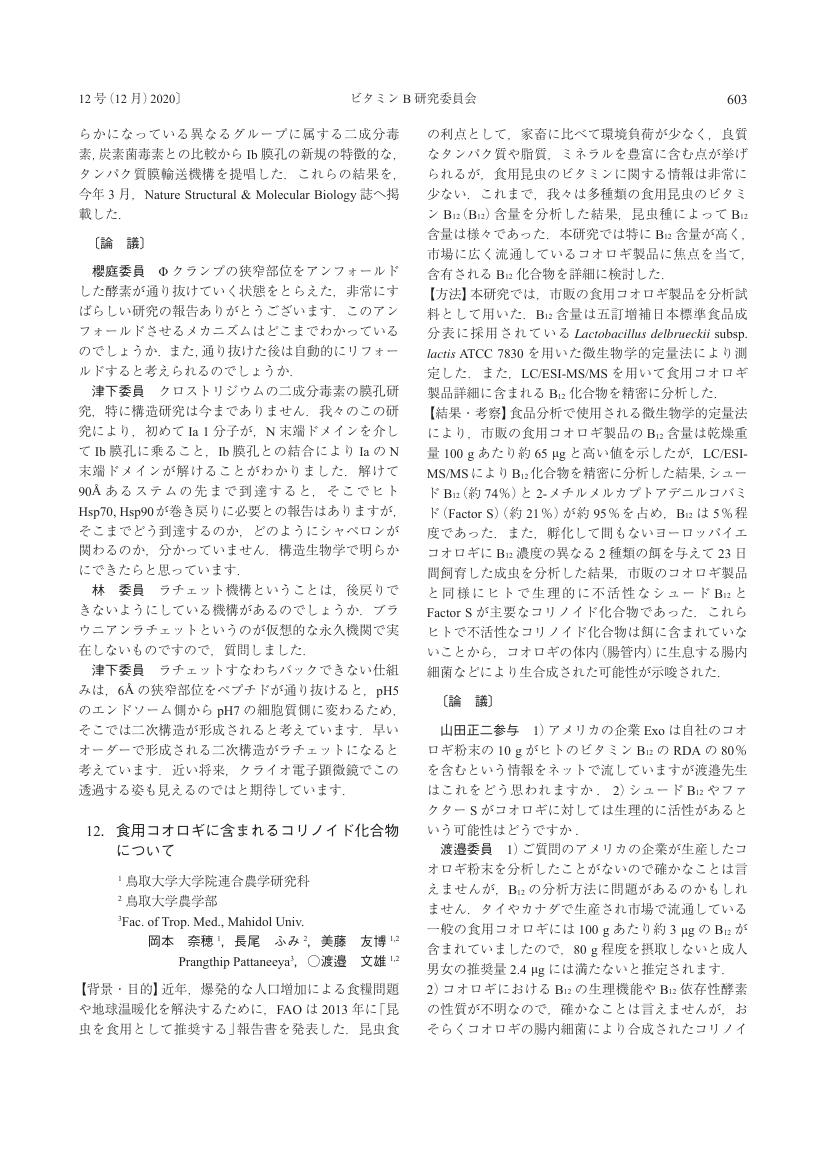4 0 0 0 OA 梶井基次郎「檸檬」にみられる人物像 : 美と倦怠のドラマ(平成三年度卒業研究佳作)
- 著者
- 丸山 香世
- 出版者
- 上田女子短期大学
- 雑誌
- 学海 (ISSN:09114254)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.56-65, 1992-03
4 0 0 0 OA ターボポンプ式液酸・液水ロケットエンジンの起動過渡特性の解析
- 著者
- 冠 昭夫 若松 義男 志村 隆 都木 恭一郎 鳥井 義弘 KANMURI Akio WAKAMATSU Yoshio SHIMURA Takashi TOKI Kyoichiro TORII Yoshihiro
- 出版者
- 航空宇宙技術研究所
- 雑誌
- 航空宇宙技術研究所報告 = Technical Report of National Aerospace Laboratory TR-868 (ISSN:03894010)
- 巻号頁・発行日
- vol.868, pp.33, 1985-07
The first Japanese LOX/LH2 rocket engine (LE-5) employs a turbopump-fed gas generator cycle system. The LE-5 engine starts up in such an unique method that the power of the turbopump system is at first built up by a coolant bleed cycle followed by a gas generator cycle. A computer program for the start transient simulation has been developed and it has been utilized for analysing start-up characteristics of the LE-5 engine. The outline of the computer program and the analytical results are discussed here. The results of the analysis have been effectively used for the setting of the firing test condition and for the determination of the engine start sequence in each phases of the development. The results of the simulation are also compared with the experimental results.
4 0 0 0 OA 12. 食用コオロギに含まれるコリノイド化合物について
- 著者
- 岡本 奈穂 長尾 ふみ 美藤 友博 Prangthip Pattaneeya 渡邉 文雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本ビタミン学会
- 雑誌
- ビタミン (ISSN:0006386X)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.12, pp.603-604, 2020-12-25 (Released:2021-12-31)
4 0 0 0 OA ラインベルガーのオルガン協奏曲における楽器法とその着想源
- 著者
- 田川 真由
- 出版者
- 日本音楽学会
- 雑誌
- 音楽学 (ISSN:00302597)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.2, pp.87-102, 2021 (Released:2023-03-15)
18世紀から作曲され始めるようになったオルガン協奏曲は、19世紀に入り一度作曲が途絶えたが、19世紀後半に再び作曲されるようになる。この復興と呼べる現象を指摘したコロバは、J. G. ラインベルガー(1839-1901)のオルガン協奏曲におけるオルガンとオーケストラの組み合わせ方が、他の作曲家と異なると述べている(Choroba 2001)。しかしコロバは、様々な作曲家の楽曲の形式分析を主眼としていたため、ラインベルガーのオルガンの用法は十分に論証されていない。そこで本研究では、ラインベルガーのオルガン協奏曲を、同時期に書かれた他の作曲家(フェティス、プラウト、ギルマン)の楽曲と比較し、彼のオルガンの用い方の独自性と、その着想の源泉を明らかにすることを目的とする。 本論ではまず、ラインベルガーのオルガン協奏曲の分析を音響設計に着目して行った。そして、彼の楽曲がオルガンとオーケストラという2つの音響体を対立させる構図ではなく、両者を同時に用いることで、音響を融合させていることを明らかにした。これが彼の楽曲の独自の特徴と言える。 次に、その着想の源泉について、作品成立背景を示すあらゆる資料から探った。そして、新たに完成した大オルガンを想定して作曲した同時代の作曲家と異なり、ラインベルガーの身近にあったオルガンは大規模なものではなく、彼の作品は特定の大オルガンのために作曲された可能性が低いことを示した。また、彼がモーツァルトの教会ソナタの校訂作業から少なからず影響を受けていたことも指摘した。 以上の考察から、ラインベルガーのオルガン協奏曲の音響設計は、同時代のフェティスやギルマンらと異なる環境にあった彼が、オルガンとオーケストラを融合した、より汎用的な作曲を指向したことによる成果であったと結論付けた。
4 0 0 0 OA 浄厳述『臨終大事影説』についての考察
- 著者
- 疋田 秀
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, pp.489-508, 2020 (Released:2021-04-06)
- 参考文献数
- 14
浄厳述『臨終大事影説』は、浄厳(一六三九~一七〇二)が霊雲寺における口述を観輪という僧侶が聞き書きしたものであり、江戸時代の真言宗の臨終行儀について詳細に説かれている文献である。現在、確認できる写本は、京都大学の図書館に所蔵されている『臨終大事影説』と、智積院に所蔵されている『臨終大事私記』との二本の存在が確認されている。本論では京都大学蔵本の『臨終大事影説』を底本として扱い、智積院所蔵の『臨終大事私記』と校訂していき、翻刻をしていく。そして、『臨終大事影説』に説かれている内容を確認していきながら、他の真言宗諸師における臨終行儀と比較して、『臨終大事影説』の特徴を見出すことが本論の目的である。
4 0 0 0 杉本鉞子 : 「武士の娘」の経験のストーリー
- 著者
- 鈴木 明美
- 出版者
- 日本オーラル・ヒストリー学会
- 雑誌
- 日本オーラル・ヒストリー研究 (ISSN:18823033)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.154-164, 2006
This paper has a purpose to analyze a collaborative work of Etsu Inagaki Sugimoto. Sugimoto wrote a book called A Daughter of the Samurai in English in 1925. The book received wide recognition both in America and Europe. Although A Daughter of the Samurai classified as an autobiography, we could clarify the book as a work of fiction. I would like to show a collaborator of this book, an American woman called Florence Mills Wilson. Sugimoto and Wilson were life long friends, worked together with their united hearts and minds. Their cross-cultural experiences led to a collaborative work of a life story of a daughter of the samurai, contained full of sympathy.
- 著者
- 樅山 定美 掛谷 和美 柳 久子
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.522-532, 2022-06-30 (Released:2022-06-30)
- 参考文献数
- 20
目的:救急看護師がとらえた代理意思決定を行う患者家族に対する看護支援の重要度の認識と実践度の実態を評価し,実践が困難な背景を明らかにすることを目的とする。方法:64施設の救命救急センターに勤務する164名の救急看護師を対象に,無記名アンケート調査を行った。結果:対象者の年齢は35.6±8.1歳であり,救命救急センター勤務年数は5.1±4.2年であった。救急看護師が認識した重要度と実践度には強い相関性を認めた(r=0.89,p<0.001)。 しかし,十分に実践できない項目も存在し,他職種からのサポートに関する項目が上位を占めた。実践が困難な理由には患者に対する救命の看護業務を優先せざるを得ない状況がもっとも多かった。結論:救急看護師の代理意思決定支援は,救急の状況のなかで家族支援に十分に時間を割くことができていない課題があり,さらに他職種との連携や調整の不足と,その体制の整備が必要であることが明らかになった。
4 0 0 0 OA ケアへの規範的アプローチ : その隘路と突破口についての覚え書
- 著者
- 川本 隆史
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 研究室紀要 (ISSN:02857766)
- 巻号頁・発行日
- no.32, pp.71-80, 2006-06-30
4 0 0 0 OA <論説>ケアの本質とジェンダー : 高齢者ケアをめぐる諸問題の視座として
- 著者
- 生野 繁子
- 出版者
- 熊本県立大学
- 雑誌
- アドミニストレーション (ISSN:1340752X)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.75-104, 2003-03-25
4 0 0 0 OA 院政期に於ける斎王選考の問題 (日本中世史特集号)
- 著者
- 長塩 智恵 ナガシオ チエ Chie Nagashio
- 雑誌
- 史苑
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.1, pp.7-32, 2015-01
4 0 0 0 OA 水のコスモロジー : 異界との接点としての水辺<1> : 天竜水系の伝承を中心として
- 著者
- 春日井 真英
- 出版者
- 東海学園大学
- 雑誌
- 紀要 (ISSN:02858428)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.165-178, 1990-07-20
4 0 0 0 OA 碩鼠漫筆 : 墨水遺稿
4 0 0 0 IR イタリア語mattina/mattinoの用法について
4 0 0 0 OA 円了と哲次郎―第二次「教育と宗教の衝突」論争を中心として
- 著者
- 長谷川 琢哉
- 出版者
- 東洋大学井上円了記念学術センター
- 雑誌
- 井上円了センター年報 = Annual report of the Inoue Enryo Center (ISSN:13427628)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.23-49, 2013-09-20
4 0 0 0 OA 同調志向尺度の作成 : 規範的影響と情報的影響
- 著者
- 横田 晋大 中西 大輔 ヨコタ クニヒロ ナカニシ ダイスケ Kunihiro Yokota Daisuke Nakanishi
- 出版者
- 広島修道大学学術交流センター
- 雑誌
- 広島修大論集
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.23-36, 2011-02-28
4 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1916年07月10日, 1916-07-10
4 0 0 0 OA 筋萎縮に対する運動・栄養介入:基礎研究の最新エビデンスと現場での応用
- 著者
- 藤田 聡
- 出版者
- 日本基礎理学療法学会
- 雑誌
- 日本基礎理学療法学雑誌 (ISSN:21860742)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.3-8, 2015-08-24 (Released:2018-09-28)
- 著者
- Ken Sawada Naoko Seino Takuya Kawabata Hiromu Seko
- 出版者
- 公益社団法人 日本気象学会
- 雑誌
- SOLA (ISSN:13496476)
- 巻号頁・発行日
- vol.19B, no.Special_Edition, pp.1-8, 2023 (Released:2023-03-10)
- 参考文献数
- 23
Considering urbanization effects on atmospheric states and subsequent precipitation is crucial to improve the accuracy of forecasting localized heavy rainfall around urban areas and to mitigate related disasters. For this purpose, it is effective to use a time development model that can accurately represent city-specific effects, such as urban heat island effect, in the assimilation process, and to assimilate high-frequency/high-density surface observation data that have not been used thus far. Therefore, this study incorporated a forecast model with an urban canopy scheme into an ensemble-based assimilation system and assimilated dense surface data from an Atmospheric Environmental Regional Observation System. Then, we performed analysis-forecast experiments for a heavy rain event in Tokyo metropolitan area on 30 August 2017, to examine the impact of urbanization. Our results showed that the urban scheme and surface observation improved near-surface temperature and moisture fields, thereby contributing to the formation of a clearer convergence line between the easterly and southerly winds where it was observed. Consequently, these improvements resulted in an earlier onset of rainfall and better reproduction of the heavy rainfall distribution.
4 0 0 0 OA エコシステム構想における精神障害者就労・生活支援ツールの意義
- 著者
- 御前 由美子
- 出版者
- 関西福祉科学大学
- 雑誌
- 総合福祉科学研究 (ISSN:18849288)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.199-212, 2010-03-31