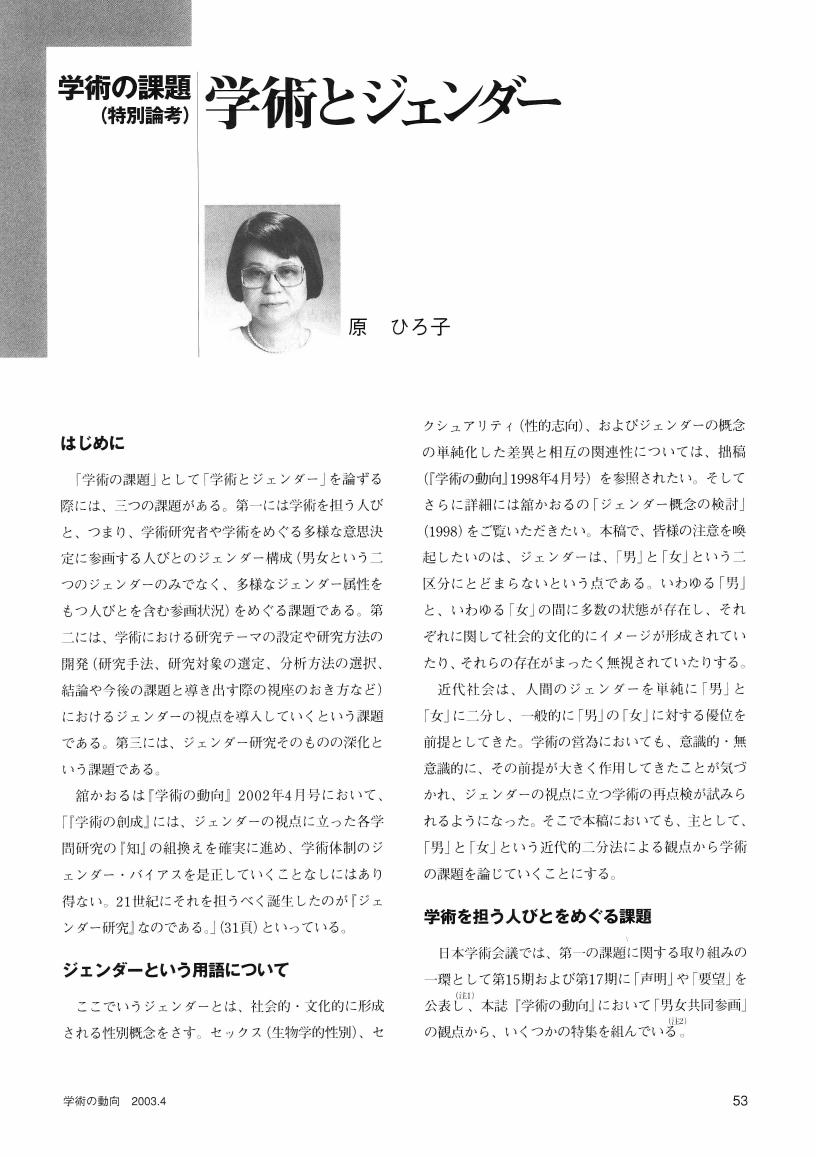4 0 0 0 OA アメリカ法研究の意義と課題─刑事手続法を中心に─(法学部開設10周年記念号)
- 著者
- 小早川 義則
- 出版者
- 桃山学院大学
- 雑誌
- 桃山法学 = St. Andrew's University law review (ISSN:13481312)
- 巻号頁・発行日
- no.20・21, pp.59-92, 2013-03-29
4 0 0 0 OA 特集2: 条約とリプロダクティブ・ライツ
- 著者
- 堀口 悦子
- 出版者
- 国際女性の地位協会
- 雑誌
- 国際女性 (ISSN:0916393X)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.11, pp.166-169, 1997-12-20 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 5
4 0 0 0 IR 合戦絵研究 : 軍記物語の絵画化
4 0 0 0 IR 人魚について
- 著者
- 菅原 克也
- 出版者
- 東京大学比較文学・文化研究会
- 雑誌
- 比較文学・文化論集 (ISSN:0911341X)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.86-95, 1991-06-10
4 0 0 0 OA 明治三〇年代における「修養」概念と将来の宗教の構想
- 著者
- 栗田 英彦
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.3, pp.471-494, 2015-12-30 (Released:2017-07-14)
本論文では、哲学者・井上哲次郎によって構想された将来の宗教-「倫理的宗教」-と、それに対する改革派宗教者らの批判から、「修養」と呼ばれる宗教性を帯びたカテゴリーが生まれてきたことを論じる。明治三〇年代における教育からの宗教の排除と倫理教育への宗教の必要性という矛盾した要求のなかで、井上も宗教者らも新しい宗教のあり方を模索していた。それゆえ、宗教者たちは倫理的宗教論の抽象性を批判しつつ、その諸聖賢などの理想の人格や内観や坐禅といった具体的な実践をそこに結びつけることで、より実践的な倫理的宗教、すなわち「修養」を生み出した。さまざまな論者によって「修養」概念は用いられ、倫理と宗教、宗教と宗教の境界を超えて展開する超宗教的なカテゴリーとして、戦前日本で幅広い影響を与えることになったのである。
4 0 0 0 OA fMRIを用いた発声障害患者における高次脳機能の研究
4 0 0 0 OA 学校法人,及び財団法人における 評議員会制度の意味
- 著者
- 岡本 仁宏 Masahiro Okamoto
- 雑誌
- 法と政治 = The journal of law & politics (ISSN:02880709)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.3, pp.1(391)-59(449), 2022-11-30
- 著者
- 鷹木 恵子 Keiko TAKAKI
- 雑誌
- 国際学研究 = International studies (ISSN:21859779)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.11-30, 2016-03-20
4 0 0 0 OA 女性差別撤廃委員会第42・43・44会期報告
- 著者
- 林 陽子
- 出版者
- 国際女性の地位協会
- 雑誌
- 国際女性 (ISSN:0916393X)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.25-29, 2009 (Released:2012-02-14)
4 0 0 0 OA 近代大阪における都市下層社会の展開と変容 : 1930年代の下層労働力供給の問題を素材に
- 著者
- 佐賀 朝
- 出版者
- 桃山学院大学
- 雑誌
- 桃山学院大学経済経営論集 = St. Andrew's University economic and business review (ISSN:02869721)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.3, pp.159-195, 2012-02-29
This article examines the historical trajectory of urban lower class society in modern Osaka. Taking into account developments from the early modern period, it analyzes the transformation, expansion, and structure of urban lower class society in the modern period, as well as the way of life of lower class city residents. Specifically, this article focuses on the example of the1930s. First, it analyzes urban lower class society, which was characterized in the early modern and modern periods by the fact that its members frequently gathered together in concentrated residential zones, while also considering the development of the city of Osaka as a whole. Centering on the transformation and dismantling of early modern Osaka's best-known slum district, Nagamachi, urban lower class society developed during the modern period in a form whereby new slums emerged during the processes of industrialization and urbanization. The slums that appeared after Nagamachi's dismantling, including Kamagasaki and those in the Nipponbashi neighborhood, each possessed a subtly different character. Entering the twentieth century, Osaka's slums became even more diverse. Not only did the city's largest outcast community, Nishihamacho, continue to expand, but also new communities inhabited by immigrants from the Korean peninsula and migrants from Okinawa appeared. Thereby, an urban lower class society possessing various unique features took shape in Osaka. Lower class city residents, who lived in the above slum districts, were neither the "negative versions" of modern urban citizens, nor passive subjects. In the rapidly industrializing and changing society of the early twentieth century, they established a world in the city's back-alley tenements into which impoverished migrants, who moved to Osaka, married, gathered together in low-income residential districts, and permanently settled, were absorbed. Influenced in part by new urban governmental policies, during the early twentieth century, lower class city residents not only continued to congregate in the same residential communities, but also began to participate in local reform movements and become increasingly aware of their rights as citizens. The eviction disputes that occurred in the Nipponbashi area over the municipal government-led Substandard Housing District Reform Project are a manifestation of the growing rights consciousness of lower class city residents. Second, this paper examines the case of urban "lower class" laborers in the1930s. In particular, it engages the theme of "lodging and employment brokering." Focusing on brokers who provided housing and employment introduction services to short-term and non-contract laborers and remain a problem in contemporary Japan, this paper analyzes range of issues concerning the supply of "lower-class" labor power during the1930s. Examining two types of laborers, dockworkers and bathhouse workers, this article considers their similarities, differences, and mutual relationship. In the bottom tiers of urban society in1930s Osaka, lower class laborers were closely linked with a specific stratum of brokers called "inns," "rooms," and "brokerages," who provided them with housing and employment introduction service. In addition to arranging housing and employment for unskilled laborers sent to work at the port and the city's baths, brokers extracted brokerage fees, board, and commissions from them. However, in the1930s, as the national unemployment crisis deepened, government officials and labor unions began to view such brokers as a problem and their reform became an important social issue. A significant number of Osaka's dockworkers and bathhouse workers were Korean laborers. During the period in question, which saw an intensification of the problems of low-wage labor and harsh labor conditions, immigrant Korean laborers were forced to accept terrible living conditions. Furthermore, small and mid-sized entrepreneurs involved in the management of bathhouses and shipping labor at the city docks passed on their financial struggles to their workers in the form of poor living and labor conditions. As I noted above, the structure of urban lower class society in Osaka, which formed in the early modern period, was transformed by an increase in the number of migrants from elsewhere in Japan and abroad. During the first half of the twentieth century, lower class city residents continued to play vital role in urban society, supporting the development of the mega-city of Osaka at its base.
4 0 0 0 統計・機械学習による異分野相関を俯瞰する方法論の確立
COVID-19、SDGsの複雑に絡み合った課題に対しては、多くの異分野に跨がる学際的研究が 不可欠であり、異分野相関を俯瞰できる方法論が必要となる。従来の統合評価モデルによるアプローチには、1) 不確かさの所在が不明瞭、2) 多様なデータの十分な活用が困難、3) COVID-19のような突発事象への対応不可等の問題がある。本研究では、統計・機械学習により、この従来モデルをデータ駆動型の確率モデルに転換させて、上記の問題1)、2)を解決する方法論Iを確立する。さらにこの方法論Iを、突発事象を含め、様々な事象を包括できるモデル統合の方法論IIへと変革させ、問題3)を解決する。
4 0 0 0 IR 親密性としての"性-愛"論の構図
- 著者
- 中村 由香
- 出版者
- 東京大学大学院教育学研究科生涯学習基盤経営コース内『生涯学習基盤経営研究』編集委員会
- 雑誌
- 生涯学習基盤経営研究 (ISSN:1342193X)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.113-122, 2009
本稿の目的は近代家族と親密圏・親密性についてのこれまでのアプローチを,近代感情現象のシンボルである"愛"の側面から整理することにある。親密圏に関する理論研究において,親密圏は近代家族と同一視されてきた。そして,近代家族間での親密性の靱帯となったのは,異性間の"性"的な関係を含意した"愛情(=恋愛)"であった。近代家族研究,ジェンダー研究などの歴史社会学研究においても,"愛"の存在は自明視され,それに対して政治的視点から評価し,変革しようという研究が蓄積されてきた。"愛"は,まさに家族社会学者やフェミニズムからの糾弾を受ける原因となってきたものの,それ自体が家族ひいては親密圏という存在の否定につながるものではない。"愛"は,"家族関係の維持"という点でもある種の安定性を持っていたと同時に,"性"という衝動的な感情を含みこむことから生じる不安定性・衝動性と共存する役割を果たしてきた。本稿では,このような"性"と"愛"の関係から,親密圏を親密たらしめる持続性の構造的内実の一端を明らかにすることで,その否定・肯定のどちらかに終始するのではない親密性概念を抽出する為のアプローチを見出そうとする。研究ノート/Notes
4 0 0 0 OA 学術とジェンダー
- 著者
- 原 ひろ子
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.4, pp.53-56, 2003-04-01 (Released:2009-12-21)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
4 0 0 0 OA 特別修学支援室と連携して行う,障害のある学生へのサービス : 北海道大学附属図書館の事例
- 著者
- 小林 泰名 栗田 とも子 河野 由香里
- 出版者
- 大学図書館研究編集委員会
- 雑誌
- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, pp.1714-1-1714-9, 2018-03
障害学生支援は大学全体として取り組むべき課題であり,その中に「大学図書館の障害者へのサービス」が位置付けられる。北海道大学附属図書館では2012年3月から,障害学生支援担当部署と連携して「プリント・ディスアビリティのある利用者のための資料電子化サービス」等の障害学生へのサービスに取り組んでいる。2017年9月までの5年半の取り組みについて報告する。
- 著者
- 椿 広計
- 出版者
- 日本統計協会
- 雑誌
- 統計 (ISSN:02857677)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.4, pp.2-5, 2019-04
4 0 0 0 OA 気候を改変する技術と地球温暖化問題 気候工学(ジオエンジニアリング)研究の最新動向
- 著者
- 杉山 昌広
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.12, pp.767-771, 2014 (Released:2020-02-19)
- 参考文献数
- 5
気候工学(ジオエンジニアリング)とは,人工的に気候システムに介入し気温を低下させたり,二酸化炭素を大気から回収したりして地球温暖化を抑制する手法である。国際的に地球温暖化対策の進展が芳しくない中,一部の科学者が焦りを感じ,研究の重要性を訴えている。しかしながら,実施のみならず研究についてもこの技術は多くの社会的問題を引き起こす可能性がある。そのため,自然科学・社会科学の両面から研究が活発に進められている。仮に実施されれば,その影響は世界中に広がるため,日本も傍観者でいることはできない。市民,ステークホルダー,専門家で議論を始めることが必要であろう。
4 0 0 0 IR 「社会モデル」の思想と宗教 : 共生する社会の構築に向けて
- 著者
- 頼尊 恒信 Yoritaka Tsunenobu ヨリタカ ツネノブ
- 出版者
- 「宗教と社会貢献」研究会
- 雑誌
- 宗教と社会貢献 (ISSN:21856869)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.75-99, 2018-04
論文特集 : 宗教・障害・共同体―障害と共に生きることの宗教性本稿では、2016 年7 月に神奈川県相模原市で起きた障害者殺傷事件を受けて、事件とその背後にある優生思想について論点を整理する。そして、国連の障害者権利条約ならびに同権利委員会による一般的意見を参照しつつ、国際的な脱施設化への流れを確認する。その上で、仏教福祉思想が抱える課題点を明確化する。障害者権利条約をはじめとする社会モデルの思想を基軸として、相模原事件後の日本の共生社会の形成と宗教思想との関係について考える。Focusing on the murder of disabled people in Sagamihara City, Kanagawa Prefecture in July 2016 (Sagamihara Knife Attack), I describe the eugenic thoughts that forms the background of the case. Furthermore, I describe the stream for international deinstitutionalization, referencing the "Convention on the Rights of Persons with Disabilities" and general comments by the "Committee on the Rights of Persons with Disabilities". Moreover, I show problems of Buddhism welfare thought. Finally, I discuss attitudes towards the formation of Japanese living-together-society after the Sagamihara Knife Attack and religious thoughts, based on thoughts of social models such as the "Convention of the Rights on Persons with Disabilities.
4 0 0 0 OA 濃尾平野における水田タイプ別のカエル類の種組成
- 著者
- 天白 牧夫 大澤 啓志 勝野 武彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.5, pp.415-418, 2012 (Released:2013-08-09)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1 4
We elected an area where uniform paddy cultivation is done by the overall community, and divided roughly into five rice field types; I (Rice field and lotus field mixture area), II (Pond adjoining area), III (Rotation of crops area of rice, wheat and soybean), IV (Fabricated field / Mixture of the waterway of the ground and concrete) and V(Not-fabricated field / Mixture of the waterway of the ground and concrete) in Noubi plains. We conducted a line census investigation on a ridge in order to investigate the species composition of frogs according to the rice field type. The results of our survey, there were large numbers of frogs in the areas which have a moist cultivating environment (Type I , V). In contrast, in the well-drained rice fields (Type II , III and IV) where rice seedlings were transplanted in June, there were small numbers of frogs irrespective of the environmental structure. The number of frogs in Type I where different crops (rice and lotus) were cultivated in parallel was larger than that in Type V because the waterside has always existed there.