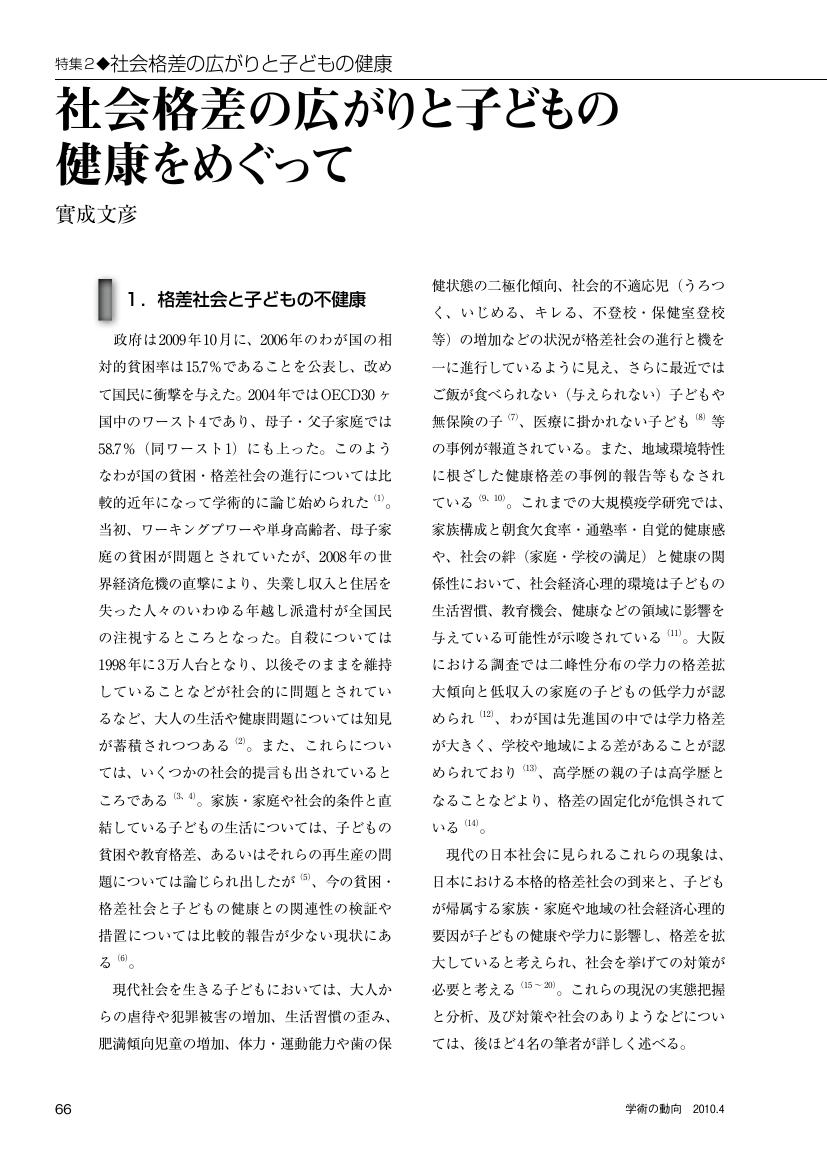4 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1921年05月27日, 1921-05-27
4 0 0 0 IR 二代目市川団十郎と劇場経営 : 享保十九年の江戸歌舞伎 (加藤定彦教授 定年退職記念号)
- 著者
- ビュールク トーヴェ Tove Bjoerk
- 出版者
- 立教大学日本文学会
- 雑誌
- 立教大学日本文学 (ISSN:0546031X)
- 巻号頁・発行日
- no.109, pp.104-117, 2013-01
4 0 0 0 IR 『三体詩幻雲抄』を通してみる室町時代における漢籍流布の状況
- 著者
- 劉 玲
- 出版者
- 筑波大学国語国文学会
- 雑誌
- 日本語と日本文学 (ISSN:02856352)
- 巻号頁・発行日
- no.55, pp.38-54, 2013-02
4 0 0 0 OA 社会格差の広がりと子どもの健康をめぐって
- 著者
- 實成 文彦
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.4, pp.4_66-4_74, 2010-04-01 (Released:2010-10-18)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1
4 0 0 0 「SPOKEN BASIC 1」の認識システム
- 著者
- 新美 康永 小林 豊 浅見 俊幸 三木 豊
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理 (ISSN:04478053)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.5, pp.p453-459, 1977-05-15
- 被引用文献数
- 2
This paper describes a highly predictive speech recognition system, developed as a voiceinput ptogramming system, in which a modified version of 'BASIC', named 'SPOKEN BASIC 1', is used. The system consists of four major components; acoustic processor, lexical matching procedure, syntactic processor and semantic processor. The acoustic processor transforms incoming speech signals into a sequence of labeled segments. The syntactic processor makes grammatical predictions using a left-to-right parsing scheme and a depth-first or a breadth-first tree search. The semantic processor refines those grammatical predictions and sends predicted words to the lexical matching procedure, which correlates them with the sequence of labeled segments. 142 sentences uttered by four male speakers were processed through the present system. It responded as follows: 116 sentences (81.7%) were correctly recognized, 19 (13.4%) incorrectly recognized and the others rejected.
- 著者
- 小宮 勲 白坂 崇 梅津 芳幸 橘 昌幸 泉 隆
- 出版者
- 公益社団法人 日本放射線技術学会
- 雑誌
- 日本放射線技術学会雑誌 (ISSN:03694305)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.270-277, 2004
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 12 14
In this study, we investigated the usefulness of the fluorescent glass dosimeter for measuring patient dose. The fluorescent glass dosimeter is constructed of a glass element and its holder. One type has a tin (Sn) filter and the other does not. The characteristics of these two types of fluorescent glass dosimeters were studied in the range of diagnostic X-ray energy. The result was excellent for each characteristic. Directional dependency, however, was recognized in the fluorescent glass dosimeter with tin (Sn) filter. Based on these evaluations, patient skin dose was measured for abdominal interventional radiology and diagnostic digital subtraction angiography using the holder without filter, which is less direction-dependent and eliminates obstructive shadows in radiography and fluoroscopy. The average skin dose of 30 patients for abdominal IVR was 1.17±0.44 Gy (0.51-1.94 Gy), while those for diagnostic DSA examination was 0.54±0.21 Gy (0.15-1.02 Gy). The fluorescent glass dosimeter provides high capability for skin dose measurement. The fluorescent glass dosimeter is also useful for controlling patient dose during IVR procedures.
4 0 0 0 イスズ箱考 : 個人携帯用祭具セットの比較研究
- 著者
- 宮内 〓
- 出版者
- 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.2, pp.59-68, 1996-07-31
- 参考文献数
- 20
島根県の美保神社において,氏子が戸外での儀式に酒,つまみ,盃,箸などを運ぶために使用する「イスズ箱」と沖縄地方で御嶽信仰において,お供えを運ぶための「ビンシー」と呼ばれる箱とを比較して,デザインの特質を述べた。1.意味不明のイスズ箱とは,「神に酒を供えるための錫の瓶を収めた箱」であることを明らかにした。2.イスズ箱は,針葉樹の白木製で,隅打付接ないし組手接の箱である。わが国古来のアイデアである中蓋によってつまみ,盃,箸と徳利とをへだて,徳利が壊れないために箱の内部を巧妙に仕切っている。中蓋はお盆としても使用される。3.ビンシーは広葉樹で朱漆塗り,蟻組接である。箱の作り方として中国の影響が指摘される。また,箱自体が神に供物を捧げる台となる。4.二つの箱の機能は類似しているが,デザインが非常に異なるのは,文化,伝統の反映であると考えられる。
4 0 0 0 OA 沖縄のエイサー芸能の生成過程の解明-「手踊りエイサー」の様式性に着目して
4 0 0 0 OA 犬における電気鍼刺激の自律神経リズムに対する効果(外科学)
- 著者
- 木村 祐哉 原 茂雄
- 出版者
- 社団法人日本獣医学会
- 雑誌
- The journal of veterinary medical science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.4, pp.349-352, 2008-04-25
- 被引用文献数
- 10
鍼治療のもつ長期的効果の検討のため,犬の自律神経の概日リズムに対して電気鍼刺激がもつ影響について,コサイナー法を用いて評価した.自律神経機能の指標としては心拍変動の周波数解析を用いた.温度,日照時間をコントロールした環境制御室において馴化させたビーグル犬を用い,保定のみの場合,あるいは保定した上で電気鍼刺激を加えた場合の24時間心電図データを求めた.保定のみの場合では15分間保定台にくくりつけるのみとし,電気鍼刺激はその間,脊椎上に存在する2箇所の経穴(GV-5, GV-20)に刺入した鍼を電極として5V, 250μsecの電流を2Hzの頻度で加えた.心電図データからは心拍数および心拍変動の変動係数(CVRR),高周波数成分(HF),低周波数成分/高周波数成分比(LF/HF)を求めた.得られた5頭分のデータによると,心拍数は刺激後に最大となり,その後減少する傾向が見られた.その他の心拍変動の指標では明期に減少し,暗期には次第に増加する傾向が見られた.コサイナー法によると刺激の有無に関わらずいずれの指標も有意な24時間周期を示し,それぞれの周期性を比較すると,交感神経活動の指標とされるLF/HFで水準の上昇(P=0.006)と頂点位相の前進(P=0.012)がみられた.結論として,電気鍼刺激は犬における交感神経の概日リズムを前進させ,またその水準を上げる効果をもつことがわかった.
4 0 0 0 OA A-6. 生体試料の超微弱発光各種疾患患者血液の超微弱発光を中心として
- 著者
- 依田 敏行 後藤 由夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床化学会
- 雑誌
- 臨床化学シンポジウム (ISSN:03863417)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.20-22, 1982-07-15 (Released:2012-11-27)
- 参考文献数
- 7
The detecting ability of the photon counting system of single photoelectron counting method has been greatly improved and an equipment of this method, designed for biochemical and biomedical applications, was developed. The photomultiplier used in the instrument was of bialkali photocathode of 5cm diameter with the spectral responce nearly from 300nm to 660nm and of specifically low noise selected from hundreds of the same photomultipliers. The photomultiplier was cooled down to -20° in the equipment in the actual photon counting for the further reduction of the noise. All other possible electrical noises from the inside and the outside of the counting machine were eliminated or minimized. The sensitivity of the photon counting equipment reached the level high enough to permit the determination of extremely weak light emission like those of human blood and tissue samples. Thus, the first quantitative measurement, to our knowledge, of ultra weak chemiluminescence of human blood samples was performed with this instrument. The whole blood and plasma samples of normal subjects gave relatively low levels of light emission. On the contrary, the blood samples of patients with diabetes mellitus and with liver diseases showed significantly higher light emission levels. Of particular interest was of the blood of patients with obstructive jaundice and of severe hepatitis. The light emission of the blood samples of these disease was generally very high and in the levels allowing the spectral analysis of the emitted light.The analysis and the scavenger experiments indicated the contribution of singlet oxygen as the photon emitting entity in these blood samples.
- 著者
- 金馬 国晴
- 出版者
- 東京大学大学院教育学研究科 教育学研究室
- 雑誌
- 研究室紀要 (ISSN:02857766)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.25-34, 2001-06-29
- 著者
- 三沢 伸生 大澤 広嗣
- 出版者
- 日本中東学会
- 雑誌
- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
- 巻号頁・発行日
- no.28, pp.107-126, 2013-01-05
近年になって、「回教政策」をはじめとして、長らく学界で取り上げることがなかった戦前・戦中期における日本とイスラーム世界との関係についての研究が進んできている。第1に「回教政策」やイスラーム研究の中心人物にかかわる研究、第2に第1と同じく関係団体や研究機関にかかわる研究、第3に日本社会における反響、第4に在日タタール人など在日イスラーム教徒や日本とイスラーム世界との関係にかかわる研究である。このなかで第3の日本社会における反響の研究が遅れている。社会科学一般で用いられているようにメディア研究を進めていくことが必要である。代表的日刊新聞に比べて仏教系日刊新聞『中外日報』にはイスラーム関係の記事が多く所収される。現在、1937年から1945年の同紙に所収されるイスラーム関係記事のデータベース化を進めており、本稿ではその一部を紹介しながら、当時の日本社会におけるイスラーム認識の振幅の一例を示す。
4 0 0 0 OA 北風と太陽-最終講義第一部-
- 著者
- 山田 耕作
- 出版者
- 物性研究刊行会
- 雑誌
- 物性研究 (ISSN:05252997)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.5, pp.703-710, 2005-08-20
この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。
- 著者
- 古畑 淳
- 出版者
- 山梨学院大学
- 雑誌
- 山梨学院大学法学論集 (ISSN:03876160)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, pp.63-85, 2013-02-15
4 0 0 0 OA イブン・スィーナー著『治癒』形而上学訳註 (第一巻第三章)
- 著者
- 小林 春夫 仁子 寿晴 加藤 瑞絵 倉澤 理
- 出版者
- 早稲田大学イスラーム地域研究機構
- 雑誌
- イスラーム地域研究ジャーナル (ISSN:1883597X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.103-136, 2013-03-31
4 0 0 0 OA <原著>「死の受容」についての一考察 : わが国における死の受容
- 著者
- 菊井 和子 竹田 恵子
- 出版者
- 川崎医療福祉大学
- 雑誌
- 川崎医療福祉学会誌 (ISSN:09174605)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.63-70, 2000-06-26
エリザベス・キュブラー・ロスの名著「死ぬ瞬間」(1969年)がわが国に導入されて以後, 死にゆく患者の心理過程はターミナルケアにあたる医療職者にとっても社会全体にとっても重要な課題となった.なかでもその最終段階である"死の受容"についての関心が高まった.キュブラー・ロスは"死の受容"を"長かった人生の最終段階"で, 痛みも去り, 闘争も終り, 感情も殆ど喪失し, 患者はある種の安らぎをもってほとんど眠っている状態と説明しているが, わが国でいう"死の受容"はもっと力強く肯定的な意味をもっている.患者の闘病記・遺稿集およびターミナルケアに関わる健康専門職者の記録からわが国の死の受容に強い影響を及ぼしたと考えられる数編を選び, その記述を検討した結果, 4つの死の受容に関する構成要素が確認された.つまり, 1)自己の死が近いという自覚, 2)自己実現のための意欲的な行動, 3)死との和解, および4)残される者への別離と感謝の言葉, である.わが国における"死の受容"とは, 人生の発達の最終段階における人間の成熟した肯定的で力強い生活行動を言い, 達成感, 満足感, 幸福感を伴い, 死にゆく者と看取るものの協働作業で達成する.
<p>環境問題に対する認識が深まるにつれて、自然との共存という概念が注目されてきている。だが、共存の対象となる自然についての認識は必ずしも深まってはいない。自然保護に関する意識を見ると、観念的な自然保護に規定されている傾向が認められ、人間の介入を規制することによって自然が保護されると理解されている。しかし、実際に自然と接触のある地域においては状況が異なり、より具体的なレベルで自然保護を理解している。ここで、注目されるのが生活と環境という領域における諸研究であるが、人間-自然関係のうち親和的ではない関係の持つ意味について、十分検討する必要がある。</p><p>青森県脇野沢村では、天然記念物である北限のサルによる食害問題が深刻化しており、サルの保護と地域社会の両立が大きな問題となっている。このことが問題化した原因としては、明治以降の狩猟、森林伐採、拡大造林、サルの観光資源化、不良作物の投棄などの事実が複合的に作用したことが指摘できる。自然との共存とは、これらを総合的に扱いながら問題の解決へ向けて対策をとることであると思われる。</p><p>ここでは、サルの保護と被害という状況の中で、総合的な解決に向けた試みが行われている。その1つの理由として、サルが存在感に満ちたものとして認識されていることがあげられる。このような認識を得るに当たってサルの否定的な要素も組み入れた上での総合的な接近が重要な意味を持っていると考えられる。</p>
- 著者
- Masaki Ishihara Yuka Takagi Gefei Li Masato Noguchi Shin-ichiro Shoda
- 出版者
- (社)日本化学会
- 雑誌
- Chemistry Letters (ISSN:03667022)
- 巻号頁・発行日
- pp.130646, (Released:2013-08-02)
- 被引用文献数
- 10
A convenient protection-free synthetic route toward alkyl glycosides has been developed. The alcoholysis of one-step preparable glycosyl donors, 4,6-dibenzyloxy-1,3,5-triazin-2-yl (DBT) glycosides, under hydrogenolytic conditions gave the corresponding glycosides in good yields without adding any acid promoters. The method could be successfully applied to the glycosylation of an acid-labile oligosaccharide.
4 0 0 0 OA JBIG, JBIG2の標準化動向
- 著者
- 小野 文孝
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.5, pp.616-621, 2001-05-20 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
ISOとITU-Tに共通の新たな2値画像符号化標準JBIG2が誕生した.新標準は, パターンマッチング技術の利用により, テキスト画像のビジュアリロスレス圧縮で従来標準の数倍の圧縮性能を有し, ロスレス圧縮やハーフトーン画像圧縮でも従来標準を大きく凌駕する.本稿では2値画像符号化の歴史にもふれつつ, JBIG, JBIG2の最新動向を紹介する.