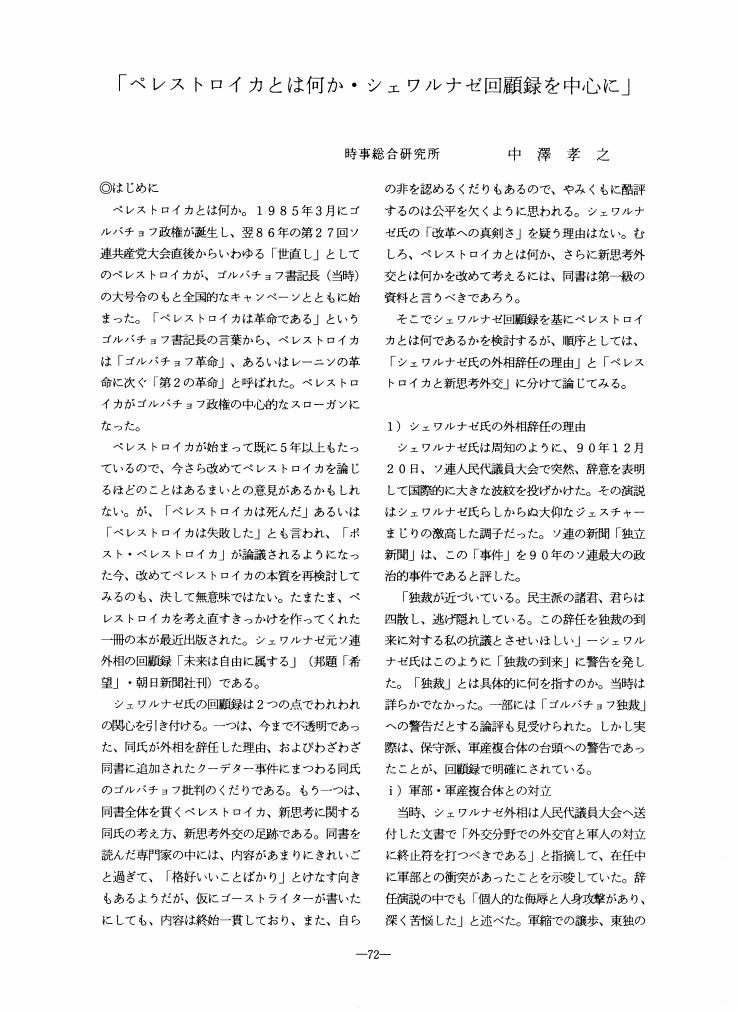3 0 0 0 OA スティーヴン・ヴァン・エヴァラ著『政治学方法論入門』
- 著者
- 石田 淳
- 出版者
- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2000, no.125, pp.224-227, 2000-10-13 (Released:2010-09-01)
3 0 0 0 OA <あめつち>から<いろは>へ : 日本語音韻史の観点から(<特集>日本語音韻史の新展開)
- 著者
- 小倉 肇
- 出版者
- 日本音声学会
- 雑誌
- 音声研究 (ISSN:13428675)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.14-25, 2004-08-31 (Released:2017-08-31)
In this paper, I propose that the phonotactic restriction that 衣 ([e]) should be used at the word-initial position and 江 ([je]) should be used otherwise was formed in the early part of the 10th century. The phrase "e-no-je (えのえ) ", which is included in Ametsuchi-no-uta written by Minamoto-no-Shitago, also follows this phonotactics. Around the middle of the 10th century, the phonotactics began to lose force gradually, and the change from [e-] to [je-] occurred at the initial position of the second (and subsequent) word in the combination of words. Consequently, the delimitative function of [e] weakened, and [je] came to be used at both the initial and non-initial positions. By the end of the 10th century, [e] had completely merged into [je].
3 0 0 0 OA 満洲の歓楽街-エロスと規律権力:近代日本のカフェ文化(5)
- 著者
- 山路 勝彦 Katsuhiko Yamaji
- 雑誌
- 関西学院大学社会学部紀要 (ISSN:04529456)
- 巻号頁・発行日
- no.139, pp.43-73, 2022-10-31
3 0 0 0 OA ドイツ語圏人文地理学における現代社会の認識と地域概念
- 著者
- 森川 洋
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:13479555)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.6, pp.421-442, 2002-05-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 107
- 被引用文献数
- 4
今日の急激な社会変化に対応して,欧米諸国では地理学者の多くが地域概念に注目している.その場合に,社会科学としての人文地理学には今日の社会存在論に適合した地域概念を構築し,研究に利用することが要求される.本稿ではドイツ語圏における地域に対する考え方とその変化をたどり,今日論議されている問題点を紹介する.WerlenはGiddensに倣って現代社会をポストモダン社会ではなく近代末期として解釈し,近代社会の特徴を脱定着化,時空間を超えた社会システムの広がり,グローバル化としている.しかしその解釈は,伝統的社会と近代的社会の差異を中心に考えたもので,情報技術や交通の発達とグローバル化に基づく現代社会=近代末期社会の特徴を明確に示したものとはいえない.人文地理学で考えられた地域概念の発達史をたどってみると,「実在する全体的地域」から研究者の分析的構築物または思考モデルとみられるようになり,さらに,人間行為によってつくられた社会的構築物と考えられるようになった.ドイツ語圏では地域概念は今日なお玉虫色をなしていて種々の見方があるが,地域はグローバル化と平行して発展する傾向にあると考える人が多い.地域の特徴や形態は変化するとしても,それは将来もなお重要な研究対象として存続するであろう.地域的アイデンティティを加えた地域の重合関係や他地域との結合関係を中心とした地域構造の研究が今後重要であろう.地域の計画面における実用的価値も低下することはない.
3 0 0 0 OA 野菜の食味と加熱
3 0 0 0 OA 日本語教育で扱うべき語の選定のための医学用語と一般語のはざまの語彙の分析
- 著者
- 山元 一晃 稲田 朋晃 品川 なぎさ
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.175, pp.80-87, 2020-04-25 (Released:2022-04-26)
- 参考文献数
- 9
日本語教育で扱うべき語を選定することを目的として,医学用語と一般語のはざまにあたる語彙を医師国家試験を対象として分析した。まず,『現代書き言葉均衡コーパス』と対照し,対数尤度比に基づく特徴度により,特徴的な語を抽出した。その後,『日本医学会医学用語辞典Web版』に,見出し語またはその一部として含まれている語以外の語 (ただし,『日本語教育語彙表 Ver. 1.0』に含まれている語を除く) を,医学用語と一般語のはざまの語彙とした。はざまの語彙は,異なりで全体の12.5% (272語) あり一定数あることが確認された。これらの語のうち頻度が5以上ある語について用例にあたった。その結果,「体の部位や位置を表す語」,「患者の状態を表す語」「医療・福祉分野以外では使わないような語」などに分類できた。また,このような語の中には医療分野以外では用いられず,かつ,推測の難しいと考えられる語があった。
3 0 0 0 OA 日本における化学肥料消費の動向と問題点
- 著者
- 西尾 道徳
- 出版者
- 一般社団法人 日本土壌肥料学会
- 雑誌
- 日本土壌肥料学雑誌 (ISSN:00290610)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.219-225, 2002-04-05 (Released:2017-06-28)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 8
3 0 0 0 OA 新しい戦争からの出口の条件 ―二層ゲーム論の発展による撤退決定過程の解明
- 著者
- 中村 長史
- 出版者
- 日本政治学会
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.2, pp.2_234-2_256, 2021 (Released:2022-12-15)
- 参考文献数
- 42
領域国内の平和定着を領域国外からの派兵によって実現しようとする「武力を用いた平和活動」 からの撤退決定が可能となるのは、いつか。活動の一参加国に着目する先行研究は、派遣部隊の犠牲者数増加を有権者から批判されそうなときだと論じてきた。しかし、活動の主導国については、このような 「目前の非難」 回避のための撤退決定は、論理的にも経験的にも考えにくい。そこで、本稿では、主導国は 「将来の非難」 回避をも図ると捉える。また、介入時には対内正当化が最重要であるが撤退時には対外正当化が最重要になる 「重要度の逆転」 が起こるという形で、二層ゲーム論を発展させる。この 「将来の非難」 回避と 「重要度の逆転」 を踏まえれば、以下のような仮説が得られる。すなわち、撤退後に治安が悪化した場合に生じる不満を他の主体に逸らすことができるとき、撤退決定が可能になる。その責任転嫁の対象については、国内主体として前政権、国外主体として国際機関や被介入国などが考えられるが、撤退を正当化する際には対外正当化が最重要となるため、国外主体への責任転嫁こそが必要になるのではないか。この点につき、米国主導のソマリア、イラクへの介入を事例として分析を加える。
- 著者
- 瀧本 家康 川村 教一 田口 瑞穂 吉本 直弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本理科教育学会
- 雑誌
- 理科教育学研究 (ISSN:13452614)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.3, pp.573-587, 2023-03-31 (Released:2023-03-31)
- 参考文献数
- 18
日本の梅雨季から夏季にかけて大雨をもたらす水蒸気が地球規模の大気の運動によって日本付近へ輸送されていることに着目して,WEB気象マップを活用した探究教材を開発し,実践を行った。本実践では3種類のWEB気象マップを活用し,個々の生徒がマップから読み取れる雲,雨,風の情報を複合的に整理し,水蒸気の起源を探究することを授業の軸とした。中学校3年生を対象として,2021年8月の大雨を事例とした実践を行った結果,水蒸気の起源について,複数の異なる情報源を総合的に考察して71%の生徒が少なくとも太平洋やインド洋の遠方から水蒸気が輸送されていた可能性を見いだして表現することができた。本教材の有用性を検討した結果,77%の生徒は複数の情報を複合的に捉えて考察を行うことができたとともに,それを通して日本の気象と地球規模で生じている大気大循環のつながりを考えるきっかけとなった。さらに,37%の生徒はWEB気象マップの利用を通じて気象への興味関心が喚起され,20%の生徒は今後も活用したいと感じており,本稿が開発したWEB気象マップを利用した探究教材の有用性は一定程度示されたと考えられる。
3 0 0 0 OA 「ペレストロイカとは何か・シェワルナゼ回顧録を中心に」
- 著者
- 中澤 孝之
- 出版者
- ロシア・東欧学会
- 雑誌
- ソ連・東欧学会年報 (ISSN:03867226)
- 巻号頁・発行日
- vol.1991, no.20, pp.72-79, 1991 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 16
3 0 0 0 社会科学における生活史研究,再考
- 著者
- 辻本 昌弘
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学研究 (ISSN:24357065)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.63-81, 2021 (Released:2021-04-12)
本稿は社会科学における生活史研究の意義と方法を明らかにするものである。生活史とは,インタビューや文書 史料などをもとに,ひとりの人物の来歴をくわしく記録したものである。本稿では,生活史研究におけるインタ ビューと解釈の特徴について検討したうえで,以下の 2 点を指摘した。①生活史研究の意義は,既成の通念を揺 さぶり新たな解釈を生みだす手がかりを提供することにある。②生活史研究の意義を実現するためには,イン タビューにおいて出来事を具体的に描写する口述─出来事の写生─を語り手から引きだすことが必要となる。 以上を踏まえて,生活史研究における聞き手のインタビュー技術をめぐる諸問題,さらにインタビューで口述さ れた内容を編集して生活史を執筆するうえでの諸問題を論じた。最後に,生活史研究は,語り手・聞き手・読み 手の言語コミュニケーションをつうじて新たな解釈を豊かに生みだすものであることを指摘した。
- 著者
- 孫 瑾
- 出版者
- 日本道敎學會
- 雑誌
- 東方宗教 = The Journal of eastern religions (ISSN:04957180)
- 巻号頁・発行日
- no.136, pp.22-38, 2021-08
- 著者
- ERI GONDA KAZUMICHI KATAYAMA
- 出版者
- The Anthropological Society of Nippon
- 雑誌
- Anthropological Science (ISSN:09187960)
- 巻号頁・発行日
- vol.114, no.2, pp.127-131, 2006 (Released:2006-08-10)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 4 4
Somatometric research was conducted in Tonga, Polynesia, with a focus on foot and hand size and proportions. Data were taken on 140 adults (90 females and 50 males) and compared with those of other population groups. In addition to their heavy body-build, Tongans were found to have significantly longer and wider feet and hands than the Japanese, French, Australian Aborigines, or Bamanann-Fulbe West Africans. The significance of these physical characteristics of Polynesians is discussed from a micro-evolutionary viewpoint.
3 0 0 0 OA 海外の日本語学習者のキャリア形成 ―世界市民の育成のために―
- 著者
- 福島 青史
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.175, pp.65-79, 2020-04-25 (Released:2022-04-26)
- 参考文献数
- 31
「海外の日本語学習者」は,「日本語教育機関において,外国語としての日本語を学ぶ外国人成人」だけではない。移動の時代において,移住や国際結婚などにより,「日本 / 海外」「日本人 / 外国人」という枠を超えた,世界で生きる人を対象としている。そのような世界市民の育成のためには,日本語教育は人の生を日本と海外で分断することなく,一つの連続した生としてみなし,それぞれの生の意味を見出す支援をしていくことになる。このためには,日本と海外の日本語教育,外国語教育,国語教育,教科教育の関係者が連携を取り,社会を形成する人の複言語教育とその体制を開発しなければならない。
3 0 0 0 OA 認知運動療法の紹介
- 著者
- 糸数 昌史
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.297-300, 2007 (Released:2007-07-11)
- 参考文献数
- 5
認知運動療法は,運動機能回復を一つの学習過程と捉え,脳の認知過程に注目した認知理論を基礎として成り立っているアプローチ方法である。今回,その背景と概要を紹介する。
3 0 0 0 OA 冷戦期アメリカの対日外交政策と日本のテレビジョン放送導入
- 著者
- 奥田 謙造
- 出版者
- 日本科学史学会
- 雑誌
- 科学史研究 (ISSN:21887535)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.241, pp.1-13, 2007 (Released:2021-08-11)
The plans for TV broadcasting emerged in Japan when Japan and the US began to negotiate a peace. There were two institutions in Japan that promoted TV broadcasting : NHK, a public radio broadcasting station, and Yomiuri Shinbun, a private daily owned by Shoriki Matsutato. At that time the US was looking for new allies and new ways to block the spread of communism. Then American politicians such as Senator Karl Mundt came to understand that television was a useful tool of psychological warfare against communism. When Hidetoshi Shibata, one of Shoriki's best confidants, found a news report of Mundt's "Vision of America " proposal in the US Senate Congress, he thought that it was a good opportunity for giving a push to a scheme for a new Japanese TV broadcasting. Shibata visited the US in April 1951, met Mundt and others, and asked for their support to Yomiuri's plan. Soon after that Shoriki established Nippon Television Network Corporation (NTV), and invited American TV consultants to Japan. They argued that the Japanese TV system should adopt the American TV standards. In September the Sun Francisco Conference was held for the Treaty of Peace with Japan that led to the termination of the occupation. A report of the US State Department one month after the conference said that Japanese supported the American standards for implementation of the peace treaty and defensive alliance, and by television the Japanese nation would be welded into a democratic ally of the US. With the American standards NHK began its TV broadcasting service in February 1953, and NTV, in August.
3 0 0 0 OA 生物記号論から見た重力医学生物学
- 著者
- 高沖 宗夫
- 出版者
- 日本宇宙生物科学会
- 雑誌
- Biological Sciences in Space (ISSN:09149201)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.4, pp.193-199, 2008 (Released:2010-08-06)
- 参考文献数
- 21
医学生物学の分野において環境因子としての重力は余り重視されていない。重力が一定不変であるためその役割が気づかれ難い事の他に、その作用が他の因子とは異なるため実験的に扱い難い点が大きな障害になっていると考えられる。重力と生物の関わりを研究するためには、主体である生物が重力に関係する現象をどのように捉え処理しているかという観点から、重力を記号(sign)として扱う生物記号論(biosemiotics)を適用することの必要性を論じる。
3 0 0 0 OA 小児の口呼吸に関する実態調査 保育園年長児の保護者に対するアンケート調査
- 著者
- 小久江 由佳子 猪狩 和子 小松 偉二 真柳 秀昭
- 出版者
- 一般財団法人 日本小児歯科学会
- 雑誌
- 小児歯科学雑誌 (ISSN:05831199)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.140-147, 2003-03-25 (Released:2013-01-18)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 4
近年,口呼吸をする小児が増加しているといわれているが,実際に口呼吸をしている小児の割合や口呼吸が引き起こす問題点に関しては未だ明らかにされていないことが多い.そこで,今回小児における口呼吸の実態を調査する目的で仙台市内の保育園11か所における年長児クラス(4~6歳)275名の保護者を対象にアンケート調査を行い,206名から回答を得た(回収率74.9%).アンケートにより,口呼吸吸群群,鼻呼,中間群と群分けし比較したところ,以下の結果を得た.1.保育園児の22.8%が口呼吸をしている可能性が高い.2.口呼吸群は鼻呼吸群と比較して以下のような傾向があった.1)鼻咽頭疾患の既往率が高い.2)口唇,口に乾燥がみられる.3)唇が弛緩し,上唇がめくれている.4)風邪をひきやすい.5)よく聞き返す.6)前歯部の咬合は正常の割合が低い.7)咀嚼嚥下が上手にできない.8)猫背である.3.口呼吸は離乳時期,おしゃぶりの使用の既往との間に関連は認められなかった.以上より口呼吸は様々な問題点を引き起こしていることが示唆され,外来患者における呼吸様式を把握することの重要性ならびに耳鼻咽喉科との連携強化の必要性を再確認した.