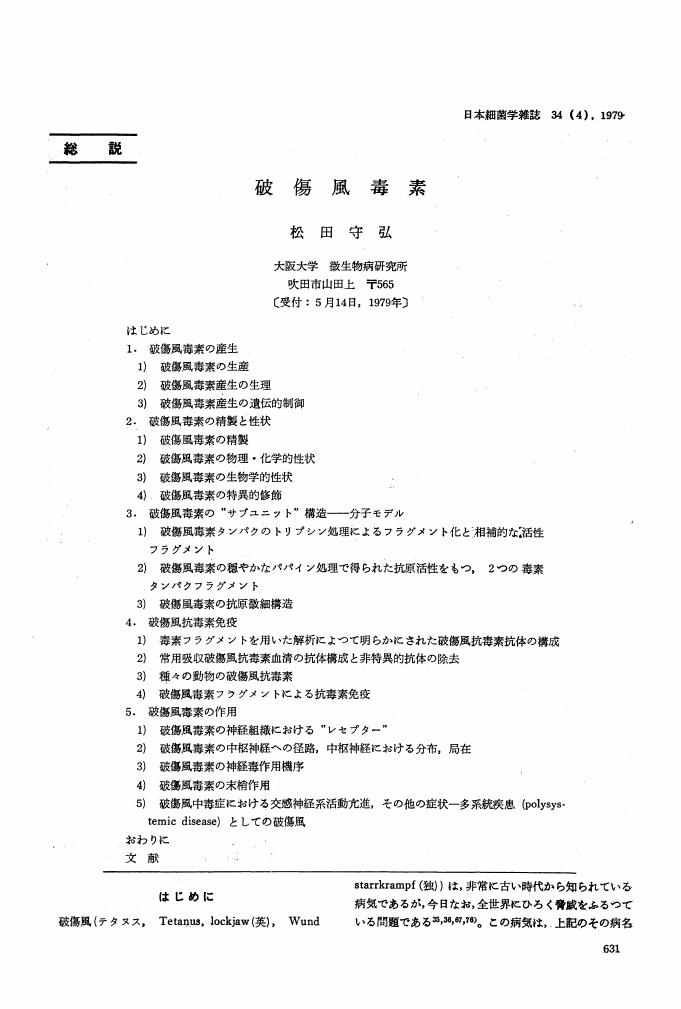3 0 0 0 OA 「朝日新聞」記事取消し事件を考える
- 著者
- 瀬戸 純一 セト ジュンイチ Junichi Seto
- 雑誌
- メディアと情報資源 : 駿河台大学メディア情報学部紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.49-65, 2016-03
3 0 0 0 OA 公開空地はコモンズとなりうるか?
- 著者
- 藤井 さやか
- 出版者
- 公益社団法人 都市住宅学会
- 雑誌
- 都市住宅学 (ISSN:13418157)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, no.90, pp.76-78, 2015 (Released:2017-06-29)
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 新宿における野宿者の生きぬき戦略:野宿者間の社会関係を中心に
- 著者
- 山口 恵子
- 出版者
- Japan Association for Urban Sociology
- 雑誌
- 日本都市社会学会年報 (ISSN:13414585)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.16, pp.119-134, 1998
3 0 0 0 オタスの森―われらのなかのギリアーク人―
3 0 0 0 奥羽大名と越前朝倉氏の通好
- 著者
- 佐藤 圭
- 出版者
- 秋田大学史学会
- 雑誌
- 秋大史学 (ISSN:0386894X)
- 巻号頁・発行日
- no.61, pp.12-30, 2015-03
3 0 0 0 OA 関東の大木式・東北の加曽利E式土器
- 著者
- 谷井 彪 細田 勝
- 出版者
- 一般社団法人 日本考古学協会
- 雑誌
- 日本考古学 (ISSN:13408488)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.37-67, 1995-11-01 (Released:2009-02-16)
- 参考文献数
- 102
東日本の縄文時代中期終末から後期にかけては,関東での急激な集落規模の縮小,柄鏡型住居(敷石住居を含む),東北での複式炉をもつ住居の出現,住居数の増加など,縄文時代でも最も栄えたとされる中期的社会から後期的社会へと大きく変貌を遂げる。土器群も隆帯が文様描出の基本であった中期的な土器から,磨消縄文が卓越する後期的土器へと変っていく。しかし,関東と東北では大木式,加曽利E式などのように共通的文様要素がありながら,その構成で異なった土器が分布する。これは住居跡形態でみられたような差と同じような差ともいえる。後期への土器の変化もそれぞれ独自な展開をしているため,両地域土器群の平行関係は関東,東北の研究者間にずれがあり,共通した認識が得られていない。この原因は,編年的研究の方法及び型式理解の混乱に起因している。我々の編年的研究の目的はまず型式学的細分があるのではなく,住居跡出土土器を基本単位として,それぞれ重ね合わせ,さらに型式学的検討を加えて有意な時間差を見出そうとするものである。本稿では関東,東北で異系統とされる土器を鍵として,両地域の土器群の平行関係を検討した。その結果,従来関東の中期末の確固とした位置にあるとされた加曽利EIV式が段階として存在せず,加曽利EIII式後半と称名寺式段階へと振り分けて考えた方が,合理的に解釈できることを明らかにした。また,東北で加曽利EIII式後半に平行する土器群として関東の吉井城山類の影響を受けた,いわゆるびわ首沢(高松他1980)類の出現段階が挙げられ,多くの研究者が大木10式とする横展開のアルファベット文の段階は,後期称名寺式出現期に平行するとした。また,本稿で取り上げた類が決して固定的でないことを明らかにするため,吉井城山類,岩坪類について,各種の変形を受けて生成された土器群を紹介し,相互の関係,時間的展開を通して土器群の実態を検討した。関東と東北の関係でみれば,全く異なるようにみえる土器でも,相互に共通した要素がうかがえ,交流の激しさ,それぞれの地域の独自性を知ることができる。また,関東地域での地域性についても同様なことがあり,このような地域間の差異こそ縄文人の独自性と創造性,人々の交流の結果であり,そこにこそ縄文人の生き生きとした姿を垣間みることができる。
3 0 0 0 IR 芥川龍之介における"語り得ぬもの" : 「羅生門」と「或阿呆の一生」を架橋するもの
- 著者
- 天満 尚仁 テンマ ナオヒト
- 出版者
- 立教大学日本文学会
- 雑誌
- 立教大学日本文学 (ISSN:0546031X)
- 巻号頁・発行日
- no.110, pp.87-99, 2013-07
3 0 0 0 OA 破傷風毒素
3 0 0 0 IR <原著論文>『新羅之記録』と新羅明神史料
- 著者
- 新藤 透
- 出版者
- 「図書館情報メディア研究」編集委員会
- 雑誌
- 図書館情報メディア研究 (ISSN:13487884)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.19-28, 2005-09-30
『新羅之記録』は正保3 年(1646)に成立した,松前藩の歴史書である。同書の冒頭部には近江国園城寺内にある新羅明神の縁起に関する記述がある。『新羅之記録』の著者,松前景広は園城寺を訪れた際,寺僧から新羅明神の縁起を聞いたとされている。従来,『新羅之記録』と新羅明神に関する史料との関係を検討した研究は見あたらない。 そこで,拙論では『新羅之記録』と新羅明神に関する史料とを比較し,両者にどのような関係があるのか検討をした。その結果,『新羅之記録』は新羅明神の史料を参考にして書かれたことが明らかになった。 'SHINRA- NO- KIROKU ' is a historical record of the MATSUMAE HAN which was formed in 1646. This book contains a description about the origin of SHINRAMYOUJIN which is in the Onjyoji in Oumi-no-kini in the beginning part. It is supposed that the author, MATSUMAE Kagehiro of 'SHINRANO- KIROKU' has heard the story of the origin of SHINRAMYOUJIN from the temple monk when he visited Onjyoji. In this paper, it was reviewed the relation between the description in 'SHINRA-NOKIROKU ' and the historical records about SHINRAMYOJIN. As a result, it is found that 'SHINRA- NO-KIROKU' consulted the historical records of SHINRAMYOUJIN.
3 0 0 0 『新羅之記録』にみられるアイヌ民族関係記述について
- 著者
- 新藤 透
- 出版者
- 苫小牧駒澤大学環太平洋・アイヌ文化研究所
- 雑誌
- 環太平洋・アイヌ文化研究
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.1-14, 2008
3 0 0 0 『新羅之記録』の編纂とその歴史認識
- 著者
- 関口 明
- 出版者
- 吉川弘文館
- 雑誌
- 日本歴史 (ISSN:03869164)
- 巻号頁・発行日
- no.842, pp.17-32, 2018-07
3 0 0 0 『新羅之記録』における「夷」「狄」表記について
- 著者
- 工藤 大輔
- 出版者
- 中央大学
- 雑誌
- 中央史学 (ISSN:03889440)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.38-71, 1996-03
- 著者
- 小池 亜子 古川 敦子
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.172, pp.88-101, 2019 (Released:2021-04-26)
- 参考文献数
- 16
学校教員の現職研修では教員の主体的な計画による研修の推進が求められている。日本語指導に関する教員研修については,学習項目の提示や教育実践を基盤とする研修方法の提言があるが,事例研究は少ない。本研究では,教員の自主的・主体的研修活動である「自主研究班活動」と市教育委員会主催の「市教委研修」とを関連づけて研修を行っている群馬県伊勢崎市の約5年間の取り組みを対象として,市教委研修の内容や方法の変化とその要因を考察した。その結果,自主研究班活動に参加した教員が指導主事とともに市教委研修を企画し運営することにより,地域の教育課題や教員自身の実践上の課題に基づくワークショップを中心とした課題解決型の研修へと変化する道筋が示された。自らの実践に即して教員自身が研修の内容を企画し運営する「ボトムアップ型」の研修の促進要因として,活動を推進する教員の思考と管理職からの助言が影響を与えていることが示唆された。
3 0 0 0 OA 慢性腎臓病における代謝性アシドーシスの治療介入がもたらす腎保護機序の解明
本研究における主な発見を以下に記す。1.アルカリ性化剤介入前後における血漿および尿のLC-MS/MSによる尿毒症物質の定量的メタボローム解析の結果、クエン酸Na・K投与群でインドキシル硫酸・パラクレジル硫酸・アルギニノコハク酸の尿中排泄が増加し、インドキシル硫酸の血中濃度が低下した。2.クエン塩Na・K投与によって酸性尿の改善が認められたが、特に早朝尿に比べ随時尿のpH改善が大きいほど腎機能は良い傾向が認められた。クエン酸Na・Kは重曹とは異なりアルカリ性化以外の腎保護効果が期待できる可能性が示唆された。今後の慢性腎臓病の新規治療戦略の骨幹となる可能性が考えられた。
3 0 0 0 OA 対処方略の柔軟性が外傷性ストレス反応に及ぼす影響(原著)
- 著者
- 木村 諭史 市井 雅哉 坂井 誠
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.133-142, 2011-09-30 (Released:2019-04-06)
本研究では、質問紙調査法により、外傷体験を有する大学生191名を対象に、外傷体験想起時の対処方略の柔軟性が外傷性ストレス反応に及ぼす影響について検討した。対処方略の柔軟性の定義は加藤(2001b)に従い、"失敗した対処方略の使用を断念すること"(基準G)、"新たな対処方略を使用すること"(基準N)の二つを基準とした。分析対象者を二つの基準に従って分類した結果、G-N群は41名、G-noN群は36名、noG-N群は49名、noG-noN群は65名であった。基準G(2)×基準N(2)の2要因共分散分析を行った結果、基準G×基準Nの交互作用がみられた。単純主効果を検討した結果、新たな対処方略を使用した場合、それまで用いていた対処方略を放棄した者は放棄しなかった者に比べて回避症状得点が有意に高い一方で、新たな対処方略を使用しなかった場合、それまで用いていた対処方略を放棄した者は放棄しなかった者に比べて回避症状得点が有意に低かった。以上のことから、本研究では、対処方略の柔軟i生に富むことが外傷性ストレス反応の悪化につながる可能性が示唆された。
3 0 0 0 IR 宮崎駿の『紅の豚』 : 登場人物たちはどのようにつくりあげられたか(1)
- 著者
- 青木 研二 AOKI Kenji
- 出版者
- 茨城大学人文学部
- 雑誌
- 人文コミュニケーション学科論集 (ISSN:1881087X)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.97-115, 2014-09
3 0 0 0 OA 世界の潮流から外れる日本の自転車政策 —ドグマ化した車道通行原則と非科学的な政策形成—
- 著者
- 早川 洋平
- 出版者
- 交通権学会
- 雑誌
- 交通権 (ISSN:09125744)
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, no.36, pp.43-59, 2019 (Released:2021-04-11)
3 0 0 0 芥川龍之介「歯車」論 : 投企としての逸脱 (<特集>国文学)
- 著者
- 副田 賢二
- 出版者
- 山口大学
- 雑誌
- 山口国文 (ISSN:03867447)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.32-41, 1993
3 0 0 0 OA エゾオオカミ研究史の検討
- 著者
- 梅木 佳代
- 出版者
- 北海道大学文学研究科
- 雑誌
- 研究論集 (ISSN:13470132)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.35-67, 2016-01-15
本稿は,エゾオオカミ(Canis lupus hattai)に関する従来の研究動向を概観し,個々の論点における現状の到達点と問題点を整理することを目的とする。日本国内にかつて生息していたエゾオオカミおよびニホンオオカミ(Canis lupus hodophilaxあるいはCanis hodophilax)は,どちらも明治時代に絶滅した。これら在来のオオカミに対する関心は高く,明治時代以来さまざまな形で情報の発信と蓄積が行われてきた。しかし,その内容や成果の全体が整理されまとめられたことはない。本稿では明治時代から現在までに刊行された日本のオオカミについて記述がある文献を収集し,そのうちエゾオオカミに言及する213件の文献を分析対象としてその研究史を検討した。これらの文献の内容から,従来の知見の多くが限られた事例に基づいて提唱されたものであること,その妥当性の評価が行われていないことが示された。エゾオオカミに関する研究・議論においては,北海道内にオオカミが生息していた期間の記録や情報,そして確実な標本資料の双方が非常に少ないことが常に議論の前提とされてきた。しかし,専門的・学術的な議論の中ではそうした前提をふまえた「仮説」として提示された記述が,繰り返し参照されるうちに定説と化している。また,限られた情報に基づいて提唱された知見が一般化される一方で,エゾオオカミに関する情報や資料を体系的に収集し,情報を質・量ともに拡充しようとする試みはごく一部にとどまっている。今後のエゾオオカミに関する研究では,既存の知見の妥当性の評価が求められると同時に,検討対象とするべき情報や事例の数を増やすことが優先的に目指されるべきである。
3 0 0 0 OA 数理議論学の発展 : 動向と今後の展望(<特集>論理に基づく推論研究の動向)
- 著者
- 沢村 一
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.408-418, 2010-05-01 (Released:2020-09-29)