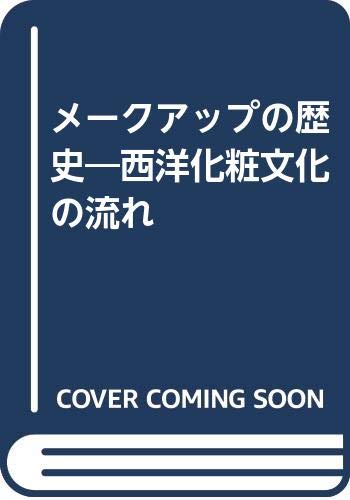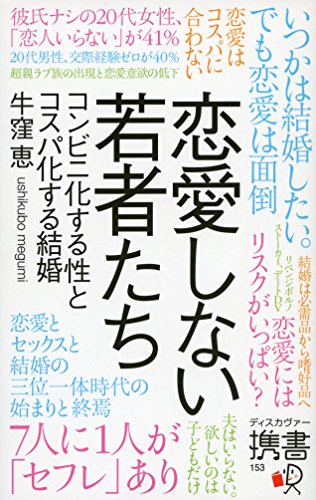2 0 0 0 OA 樺太庁の史料館(公文書館)の歴史から(1945年-1947年)
- 著者
- コスタノフ A.I コジェブニコワ ダリア
- 出版者
- 北海道大学大学院文学研究院北方研究教育センター
- 雑誌
- 北方人文研究 (ISSN:1882773X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.99-108, 2023-03-25
- 著者
- 木村 麻衣子
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.5, pp.184-186, 2023-05-01 (Released:2023-05-01)
2 0 0 0 OA 坂口安吾の一人称についての計量文体分析
- 著者
- 渡邉 幸佑
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.5, pp.192-194, 2023-05-01 (Released:2023-05-01)
坂口安吾の作品について,先行研究によると1945年ごろを境に一人称が「僕」から「私」に転じ,ふたたび「僕」に戻ることも混用もなかったという。しかし,この先行研究は「僕」と「私」の頻度を数えたものではなく,直感による論考に留まる。そこで,本稿では,坂口安吾のエッセイを対象に,KH coder(計量テキスト分析のためのフリーソフトウェア)を用いて,「僕」と「私」の頻度を数え,一人称の変化について検証した。その結果,1945年以前に「私」のみを使用した作品があり,1945年以後に「僕」と「私」の混用があるとみられるものがあった。先行研究の指摘は必ずしも妥当するものではなく,「僕」と「私」の使い分けについてさらなる検討が必要である。
2 0 0 0 日本の書籍目録に占める漢籍の位置―江戸時代以前の書目に注目して―
- 著者
- 永田 知之
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.5, pp.178-183, 2023-05-01 (Released:2023-05-01)
古代以来,日本では漢籍が多く収蔵されていたが,伝統的な四部分類に基づく書目は中世ではごく稀であった。これは,当時の書目の多くが仏典を対象とする聖教目録だったことを主因とする。19世紀に入ると,漢籍(非仏典)に四部分類を用いる書目の編纂が顕著となる。漢籍の増加,寺院の外での漢学の隆盛,『四庫全書総目』等による中国からの分類法の流入がその原因だろう。大正期以降は漢籍に特化し,四部分類を施す目録が珍しくなくなる。これは日本文化からの漢学など中国文化の析出が漢籍を他の書籍から独立させたことを一因とする。総じて言えば,書目での漢籍の扱いは中国文化が日本で占める位置の反映であり続けたと思しい。
2 0 0 0 OA 大内氏領国の総合的研究-その文化性の継承の視点から-
2 0 0 0 OA 上海における京劇の現在 ―乾坤一劇場 劇中更有劇―
- 著者
- 禾 一暸
- 出版者
- 愛知大学現代中国学会
- 雑誌
- 中国21 = China 21 (ISSN:13428241)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.123-140, 2017-03-31
2 0 0 0 OA ヴェブレンにおける制度進化の理論
- 著者
- 高 哲男
- 出版者
- The Japanese Society for the History of Economic Thought
- 雑誌
- 経済学史学会年報 (ISSN:04534786)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.34, pp.28-39, 1996 (Released:2010-08-05)
- 参考文献数
- 32
The most important Characteristics of Veblen's evolutionary economics lay in presenting the unfolding system of an accumulative process of institutions. According to Veblen, institutions are the habits of thought, in other words, the spiritual attitudes or the norms of conduct in a particular community. Although each community has its own institutional and cultural complex, “the instinct of workmanship”, that is, the abiding trait of human nature shaped in an ancient period, remains at the bottom of the complex, and secures the preservation of the species. Within limits set by workmanship, the emulative norms of conduct such as predatory exploit, conspicuous leisure and consumption can prevail. Since the instinct of workmanship coalesced with pecuniary success in the age of handicraft, automatic economic growth has been built in to continue forever. Those who cannot adapt themselves to machine technology are inclined to retrogress into more familiar and older norms of conduct. Veblen's theory of social evolution cannot be fully understood without appreciating the role of retrogression in it. We cannot find any idea of such retrogression in either New or Neo-Institutional Economics.
2 0 0 0 OA <資料紹介>大妻女子大学蔵 : 『平治物語絵巻 信西巻』
- 著者
- 小井土 守敏
- 雑誌
- 大妻国文 (ISSN:02870819)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.87-95, 2020-03-16
2 0 0 0 OA 「動機の語彙」論再考 -動機付与をめぐるミクロポリティクスの記述・分析を可能にするために
- 著者
- 藤原 信行
- 出版者
- 立命館大学大学院先端総合学術研究科
- 雑誌
- Core Ethics : コア・エシックス = Core Ethics : コア・エシックス (ISSN:18800467)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.333-344, 2008
2 0 0 0 OA 食物文化考 古事記神話と稲作文化
- 著者
- 池添 博彦
- 出版者
- 帯広大谷短期大学
- 雑誌
- 帯広大谷短期大学紀要 (ISSN:02867354)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.A27-A37, 1988-03-25 (Released:2017-06-13)
- 被引用文献数
- 20
2 0 0 0 OA 心不全患者における栄養状態の評価と介入
- 著者
- 白石 裕一 三上 靖夫 的場 聖明
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.12, pp.1143-1149, 2020-12-18 (Released:2021-03-13)
- 参考文献数
- 18
心不全患者における栄養状態は予後予測因子であり,その評価は重要である.栄養障害の要因は多岐にわたるが心機能の面からは左心機能より右心機能の関与が注目されている.栄養状態の評価は問診,採血項目,身体計測,バイオインピーダンス法などの生理機能検査などが行われているが決定的な方法は確立されていない.当院では簡便な指標としてエコーを用いた大腿直筋厚の有用性を報告してきた.また,退院前の食事摂取エネルギー量の評価をすることで必要な食事摂取ができているか評価をし,どのような要因がその阻害因子になっているかを検討して介入している.当院での取り組みを紹介しながら心不全患者における栄養について概説する
2 0 0 0 メークアップの歴史 : 西洋化粧文化の流れ
- 著者
- リチャード・コーソン著 ポーラ文化研究所訳
- 出版者
- ポーラ文化研究所
- 巻号頁・発行日
- 1993
2 0 0 0 OA 飲酒時の食事摂取は何故重要なのか? ~アルコール代謝動態への影響からみた考察~
- 著者
- 大嶋 俊二
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, no.3, pp.167-178, 2017 (Released:2022-06-22)
- 参考文献数
- 50
アルコールは酵母のもたらす最大の贈り物である。その甘美な贈り物も,飲み方によっては醜悪な贈り物と化してしまうため,アルコール代謝動態の研究は重要であるが,飲酒時の様々な条件が及ぼす影響については,エビデンスが少ない。そこで,飲酒時の種々の条件の中でも特に重要な飲酒時の食事摂取が,アルコール代謝動態に及ぼす影響,ならびにその役割について主にヒトでのデータを基に今回解説いただいた。
2 0 0 0 OA 動力源としての牛馬(さまざまな動力源,<メカライフ特集>チカラのみなもと)
- 著者
- 緒方 正則
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会誌 (ISSN:24242675)
- 巻号頁・発行日
- vol.111, no.1072, pp.170-171, 2008-03-05 (Released:2017-06-21)
- 参考文献数
- 12
2 0 0 0 OA 肺癌とKRAS―その分子生物学と治療戦略―
- 著者
- 古賀 教将 光冨 徹哉
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本肺癌学会
- 雑誌
- 肺癌 (ISSN:03869628)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.188-199, 2022-06-20 (Released:2022-06-29)
- 参考文献数
- 30
KRAS遺伝子変異は非小細胞肺癌を含むヒトの癌で頻度の高いがん遺伝子変異の一つである.発見から30年以上のKRAS変異陽性癌の治療法開発にもかかわらず,臨床的有用性を示す薬物は得られず,創薬不能な標的とされてきた.理由として,KRASとGTPの親和性は高く結合阻害は困難,KRASの下流シグナルや膜結合に必要な翻訳後修飾はいくつも平行しており,単一の経路や修飾反応の阻害では他の活性化が起こる,KRAS変異陽性癌は必ずしもKRASに生死が依存していないことなどが考えられる.2013年にGDP結合KRASに低分子化合物がはまるポケットが見出され,G12C変異KRASに限定的ながら,KRASを不活性なGDP結合型に非可逆的に固定する化合物が報告された.この発見に基づき,ソトラシブやアダグラシブなどのG12C特異的阻害剤が開発され,前者は2021年に米国で,2次治療以降のKRASG12C変異陽性非小細胞肺癌に対し迅速承認された.今後,G12C以外の直接阻害剤,G12C阻害剤との併用療法,耐性獲得後の対策,有効な患者選択のためのバイオマーカーなどについて,さらなる研究開発が待たれる.
- 著者
- 北川 修平 倉本 晃司 上泉 康樹
- 出版者
- 身体運動文化学会
- 雑誌
- 身体運動文化研究 (ISSN:13404393)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.1-15, 2022-03-15 (Released:2022-04-12)
- 参考文献数
- 89
The purpose of this study is to build the new organizational theory in ball games of team sports. For this aim, the authors focused on the training principle of ecological training and its philosophical foundation.The philosophical foundation of ecological training is ecological dynamics, and this is being integrated ecological psychology and dynamical system. We revealed theoretical principles (A, the attunement to affordances; B, the exploration of adaptive movement variability in meta-stability; C, the exploitation of neurobiological degeneracy), methodological principles (A’, individual constraints; B’, environmental constraints; C’, task constraints) and general principles (A”, education of attention; B”, education of calibration; C”, education of intention) from this philosophical foundation. The structure of these (theoretical, methodological and general) principles is fractal (theoretical ⇒ methodological ⇒ general) and they are interacting, as the superstructure is including the understructure.A training is needed to be designed as aggregation of competitive environment, so environments of sports are unpredictable and have noise. Players are capable to perform the creative and dynamic play that emerge generation and decay (i.e., self-organization and dissipation), thorough interaction between them and environments. We defined its play as frail emergence.The issue in the future is to propose the concrete training of ecological training and consider the organizational theory based on ecological dynamics.
2 0 0 0 日本古典音楽大系
- 著者
- 吉川英史 [ほか] 監修
- 出版者
- 講談社
2 0 0 0 OA 入出金情報を用いたデフォルト予測モデルの検証—機械学習による実証分析—
- 著者
- 三浦 翔 井實 康幸 竹川 正浩
- 出版者
- 一般社団法人 日本統計学会
- 雑誌
- 日本統計学会誌 (ISSN:03895602)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.187-216, 2020-03-30 (Released:2020-12-02)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
金融機関における信用リスク管理業務では,法人債務者のデフォルトに対する予兆管理が行われている.この点,債務者が大企業を中心とした上場企業であれば,企業の信用状態をタイムリーに反映しやすい株価などをデフォルトの予兆管理指標として活用できるが,中堅中小企業を中心とした非上場企業には,信用状態を即時に反映する指標が存在しない.また,信用リスク管理業務では,財務情報を用いた信用リスク評価が一般的に行われているが,財務計数には,信頼性及び即時性の面で一定の制約がある.そこで,本稿では,中堅中小企業を中心とした非上場企業にも適用可能で,かつタイムリーなモニタリングを実現するためのデフォルト予測モデルを構築する.具体的には,金融機関の預金口座における入出金情報を用いて,機械学習モデルや統計モデルを用いたデフォルト予測モデルを構築し,モデル精度の検証を行い,そのうえで予兆管理実務への適用可能性について検討する.モデル精度検証の結果,入出金情報を用いた場合において,機械学習モデルの精度は十分に実用可能な水準であることが確認された.また,機械学習モデル対比ではやや精度が落ちるものの,解釈性に優れたロジットモデルについても,実務で十分に活用可能な精度を有することが確認された.
2 0 0 0 恋愛しない若者たち : コンビニ化する性とコスパ化する結婚
- 著者
- 牛窪恵 [著]
- 出版者
- ディスカヴァー・トゥエンティワン
- 巻号頁・発行日
- 2015